
Island ORBCD1
524013-2
Pomme Fritz/Orb
テクノの人、アレックス・パターソン(Alex Paterson)が主宰する、アンビエント・ハウス・ユニット、ジ・オーブの三作目にあたるミニアルバム(EP)。計40分、最長9分ほどの全6曲。テクノと評されるにしては乗れるリズムとも華麗で心地良いメロディとも程遠く、純粋に音響的なアプローチが際立っている。スピーカーから聞こえてくる著しく無機的でギミックに溢れた音は一応人間の可聴域に合っているが、どこか別の星で、別の重力と大気のもとで聴くが相応しいように思う。タイトルはベルギーあたりで“フライド・ポテト”を表す言葉のようだが意図は不明。
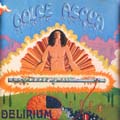
Fonit Cetra
CDM 2025
Dolce acqua/Delirium
今振り返れば、プログ・イタリアーノの第一世代とでも云うべきデリリウムの初作アルバム。初期においてカンタウトーレを中心にした構成は多いが、このデリリウムもその一つ。そのカンタウトーレを担うのが後に伸し上る、本作限りの中心人物であったイヴァーノ・フォサッティ(Ivano Fossati)。まぁ、踏み台にしたというところだろう。構成はフォサッティの男気に溢れた歌とアコギ+フルートに重量級ジャズ・ロック楽団を配したというコンプレクス。美しく哀切たっぷりのメロディと剛毅な朗唱が、ジャズやクラシックなどいろいろな要素を織り込んだ達者なテクニックに支えられているが、バンド・アンサンブルの一体感と完成度という意味では、2作目以降に比べ遥かに稚拙でカンタウトーレ部分が浮き上っている。プログと称するのはちょっと無理があるだろう。
ちなみにLPとCDを所有しているが、大昔に購入したLPは再発廉価版だったらしくスリーブも違うし曲順も違うしで、最近聞き比べてようやく同じものだと気がついた(笑)。ヒット・シングル「Jesahel」がボーナスで追加。
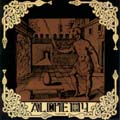
東芝EMI
TOC-6796
Alchemy/Third Ear Band
イギリスのアコースティック・ユニット、第三耳団の栄えある初作アルバム。当時、国内盤LPも発売されていたように記憶している。首領であるインド系のグレン・スウィーニィ(Glen Sweeney:故人)のパーカッションを基盤に、ミンズ(Paul Minns)の管楽器、コフ(Richard Coff)の弦楽器にチェロのデイヴィズ(Mel Davis)が加わったカルテット。
使用楽器から音は想像できるが、その想像は概ね外れる。ツントトツントトテテテントン~。無窮と無謬の法悦。斬新というよりは500年前のものですといわれても納得しちゃいそうな暗黒と蒙昧。タイトル通り中世錬金術とエルメス哲学あたりが勘どころで、古代フェニキア人の踊りだと言われれば率直に信じよう。アコースティック楽器のつづら織りのような、神経症的なまでに反復を繰り返す単調なリズムの上を、無調(あるいはワンコード)にして相互連関を無視する即興オーボエと即興ヴァイオリンが走る。演奏は大雑把で粗雑な部分も散見されるが、スウィーニィ曰く、宇宙の摂理の反射としての独特の楽曲スタイルは概ね病的にして類を見ないだろう。国内盤CDだが廉価仕様で中スリーブは献辞が切れていたりと粗悪にして手抜きがみえみえ。
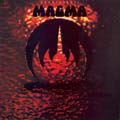
Köhntarkösz/Magma
4作目(正確には5作目)。4作目は『Wurdar Itah』というのですが、当時、そのデモ・テイクが映画「トリスタンとイゾルデ」のサウンドトラックとして勝手にリリースされたおかげで、マグマ名義で出せなくなったのが真相だそうで。今ではそのあたりの状況は改善されたみたいです。さて、これもお決まりの重低音の強迫そのもの。重苦しくたたみかけるような音がこれでもかこれでもかと迫ってきます。音の種類が増えて(楽器が増えたな)アンサンブルは一層重厚になった。そんな中で、アフリカ人のような(後注;マルセイユ生まれのフランス人)ジャニック・トップ(Jannick Top)の地べたをのたうつようなベースがぞっとして気色悪い。この人の曲も“凄い”です。熱帯雨林の闇のなかで毒蛇に狙われて竦みあがるような絶体絶命。話せばわかるみたいな人間性が欠如してないか! 中期マグマの脂が乗りきった高密度が恐い。

Aerie Faerie Nonsense/Enid
イーニドの二作目。微妙にビート・ロック色を含んでいた1枚目の中途半端な部分が一掃されて、古典風現代音楽として付け入る隙のない非常に完成度の高い構成になった。音もとてもきれいだし、長い曲のバランスもよく一気に聞かせます。シンフォ系にありがちな猪口才な仰々しさは不思議なことにまったく感じられなくて、エレガントな可愛らしさと気品が見事です。ユニゾンするギターのソロには脳殺ですね。スコアを書いているゴドフリィ(R.J.Godfrey)がタクトを振ればたぶんそれはそれで誰一人疑うこともなくクラシックになるんでしょう。もちろんEnidの音そのものはクラシックではない現代音楽ですが。ちなみにジャケは一見すると綺麗なのだが、ヒトデや巻貝と一緒に磯に浸かって潮に洗われる死化粧を施した水死体なのだろうか。
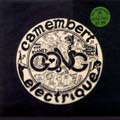
Camembert electrique/Gong
おふざけな内容はとても高度だしテクもアイディアも曲も、まぁ、申し分ないです。でもデヴィッド・アレンは自分のやっていることを茶化さずにはいれないのだな。コミック楽団すれすれのイカレた冗談を散りばめたへろへろ爆笑コントにせずにはおれないらしい。恥ずかしがりなんだな、きっと。だから、「And you tried so hard」というとても似つかわしくないまともな曲にはびっくりです。最初で最後だよなぁ。曲名の綴りもまるで英語のようにあってるしさ。ギターを取りあげてベースを弾かすとまともな曲になるみたいだな。ま、他の曲は既に充分これでもかこれでもかと“妙”で“へん”ですが。一応“これはGongのFirst Album”なんて書いてあるけどこれの前に出ていたのは何なのだろう。裏ジャケのヒッピィの真ん中の子供はワイアット(Robert Wyatt)の息子ですが、この頃はドラムのピップ・パイル(Pip Pyle)の息子になっていたそう。
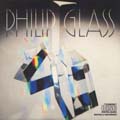
Glassworks/Philip Glass
ユダヤ系アメリカ人、フィリップ・グラスの円熟期のアルバム。ミニマル現代音楽の人ですが、難しいことは抜きにしてとても聴きやすいです。真冬の大気の中にきらきらとガラスが降り注ぐようなピアノの音。音楽理論についてはさっぱり素人なもんで、どこがどのように現代音楽かと問われてもお手上げですが…。ぶち切れそうなときに最適なもんで最近よく仕事のBGMになってます。

The kick inside/Kate Bush
デビューアルバムだっけなぁ。「Wethering Heights(嵐ヶ丘)」は結構衝撃的でした。姿形が女っぽい人はたくさんいるけれど、ここまで女であることを前面に押し出してきた人は実はかなり珍しいと思う。いろんな意味で最初から特異、かつエキセントリック。「嵐が丘」を書いたのはエミリ・ブロンテだけどこれはまた暗い復讐物語だし、どこのムーア(moor;荒地 確かヨークシャーだっけか)が舞台だったか覚えてないけれど、ムーアはほんとに荒れて、土がなくて、石がごろごろ転がって、泥炭に水が溜まって、沼になって、ヒースが赤紫の花を咲かせて、ただそれだけ。犬でも連れていないと迷子になりそうだ。
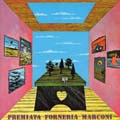
RCA ND 71784
Per un amico/Premiata Forneria Marconi
プログ・イタリアーノの代名詞とでも云うべきPFMのイタリアにおける2作目。後にピート・シンフィールドの目に留まり、英語化されたものが『Photo of ghosts(邦題:幻の映像)』として世界デヴュー盤になる。冒頭「Appena un po'(ほんのちょっと)」は英語盤の「River of Life」。低く静かにうねるメロトロンの響きに導かれガット・ギターが被り、イタリア語歌詞のせいもあってかなりアレンジが違って聞こえる。繊細さと雄大さが入り組んだ緻密な構成と複雑な展開、卓越したテクニック、多彩な管楽器群とバンド・アンサンブル、そして何よりも美しくこなれたメロディと変幻自在のリズムと正に衝撃的な内容だった。音楽的な基盤や背景がブルーズやジャズ、クラシックやオペラ、地中海民族音楽まで含めて、極めて自然かつ身近に感じられるあたりに、得も云われぬ深い感銘を受けた。聴取者のレベルに迎合した商業音楽とは根底から異なる芸術といってよいパワー漲る創出・発露の典型というべきか。これを聞いちゃうと、英語盤は(それなりの良さはわかるのだが)やっぱりちょっと違うんだよなぁ。タイトルは『とある友人のために』。
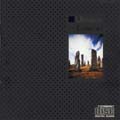
東芝EMI
CP35-3139
Lament/Ultravox
ウルトラヴォクス、ユール(Midge Ure)期の3作目、通算6作目。実は好きだったんですね。フォックス(John Foxx)の頃も良かったけれどユールもいいですよ。LD(おぉ、Laser Diskのことね)も持ってたりして。エレクトロニクスと民族色が絶妙にマッチして類い稀なメロディ・センスで表現されるマイナー調の美学。あるいは演歌。コンピュータ・パンクからトラッドまで幅はあるが、一本通った骨太な力強さが見えるようになってきました。ジャケットはスコットランド・ルイス島、コラニッシュ(Callanish)の環状列石、スタンディング・ストーンと思われる。同所で行われた「One small day」のPVがあまりに寒そうで印象に残っている。
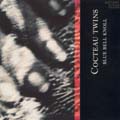
Blue bell knoll/Cocteau Twins
私が思う最盛期はこの辺か。ゆるゆると音が流れていくような。比較的地味な気はするけれど、瞬間的に見せる表情は艶やかでちょっと色っぽい完成された音ですね。複雑で凝ったボーカル・パートをこなすエリザベス・フレイザの声もそんなに前に出てこなくて夢見心地。まぁ、言葉でどうこう言うのはこういう音楽の場合かなり空しいんでちょっと書きようがないですね。余計なお世話だろうけど、飯食う金があるなら買って損はないと思う。

Gregorian Chant/Choir of the Carmelite Priory,London・John McCarthy
中世キリスト教会で修道僧達が歌った賛美歌の原型。って中学のとき習った気がするぞ。宗教歌ではありますがその後の西洋音楽の基礎を築いたとされているわけです。音階とかちょっと今とは違うのかもしれないですが、野太い力強さが耳に残ります。ってこの頃は女人禁制だから歌うのはすべて男です。

In a foreign town/Peter Hammill
VDGG以来ずいぶんとたくさんのレコードを出していますが、この人はとても形容が難しい。他の何に惑わされることもなく、我が道を行くってタイプだからはまると抜けられなくなります。もともと出版社が出してくれるほどの詩人なわけで、言葉がわからないと結構辛い。曲の方も変拍子ビシバシで重くて格好良いのからピアノだけまでいろいろ。
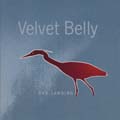
The landing/Velvet Belly
個人的には最近のものより好みかも。垢抜けないどよ~んとした感じがかわいらしい。アンヌ・マリー・アルメダルの渋めで細い声がネオサイケ風のギターに乗ってうろうろと漂う。いかにも北欧風な淡々とした硬めのドラムと地味で重いベースが印象的です。サンプリング・ループには「Lark's tongues in aspic」が使われてると書いてありますねぇ。
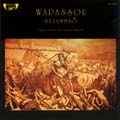
Salammbo/Wapassou
フローベールの歴史小説「サランボー」をモチーフにしたトータルアルバム。テーマは文学的というか暗いです。エレクトロニックなキーボードとチェロ、ギターが絡み合って地味ながらも緩い緊張感溢れる音づくり。文藝路線の耽美派というとわかりやすい。パーカッションが無いんでズルズルしちゃうとこもあるんだけど、フランスらしい華麗な構成と流れるような美しさで聞かせます。音感が類例に染まらず新鮮なのね。

Gold mine trash/Felt
フェルトのベスト盤かシングル集か未発表テイク集と思われる。曲ごとにプロデューサが違うし。ローレンスの穏やかで少し虚無的なボーカルとモーリス・ディーバンクの透明感のあるギターが売りですね。結構テクニカルなんだけれどピュアな生っぽさを活かし切っている。80年代を代表するとてもイギリスっぽい音だろう。1曲「Primitive painters」だけエリザベス・フレイザ(Elizabeth Fraser)がデュエットで歌っていてコクトー・ツインズみたいになっちゃってるのがあるけれど、この曲はいいなぁ。いわゆるネオサイケなギターポップ、線の細いとても柔かな音と空気の中をふわふわ漂うようなギターがとても印象的で美しい。