
Shouting at the ground/Zoviet-France
およそ大量生産には向かない何ともけったいなパッケージで一世を風靡した(嘘だって)ソビエト-フランス(Zoviet-France)ですが、これはCDです。もちろんジュエルケースと云われる普通のプラケースです。いわゆるノイズ乃至は音響系と称するのだろうが、情報が殆どない不詳さが相変らずです。今でも忘れた頃にポツポツと新作が出ているようですが入手性は良くない。タイトルと中身の関連はこれまたよくわからないのだが、寝静まった明け方に地の底から響いてくるような音とも振動ともつかぬもの、遠い海鳴りや遠い記憶を揺さぶるような微妙に感覚を刺激する環境音で構成されたアンビエント。耳を澄ますとどこからか聞こえているのだけれど、正体のつかめないあれです。白昼の草原だったり、夕闇の山峡だったり、明け方の街中だったり。はまると結構虜になるかもしれない。
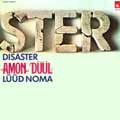
Disaster/Amon Düül
初期の数枚のアルバムの音源集です。だから内容的には69年の1st以前の音で数日のセッションの生録音にして、正規盤に使われた曲の加工元。ビートルズのカバーみたいなフレーズもあって笑えますが、基本は原始的なリズムとほとんどワンコードのフレーズを延々と繰り返していく催眠ノイズ。相変らずの太鼓ですが、考えてみれば(いや、みなくても)ドラムセットのペーター・レオポルト(Peter Leopold)以外全員パーカッションだし、叩くという行為は人間にとってなかなか根源的だし、祭太鼓のミニマル・アバンギャルドみたいなもの。スコーンと抜ける格好良さとはほとほと無縁に、繰り広げられる虚無的な狂宴。

Banco del Mutuo Soccorso/Banco del Mutuo Soccorso
クラシカルな要素とカンツォーネの土臭さが実に絶妙に溶け合って、重量級だがとても新鮮なたたずまい。まぁ、何といってもジャコモおじさんの絶唱を受入れられるか否かで決ってしまうところはあるでしょう。「R.I.P(Requiescat in pace:安らかに眠れ:墓碑銘の常套句)」なんか重いけれど中間部の全宇宙を聾するような独唱は惚れ惚れするほど美しい。チェンバロ独奏と鼻歌の実況録音みたいな小品がさらっと涼風といった趣で、それほど暑苦しい印象はない。SF風の効果音と伝統的な古典楽器の組み合わせも面白いが、ふとしたはずみに、忘れた頃に始まるピアノのメロディとそれを追っかける歌ものカンツォーネが刹那的な印象を刻み付ける1st。
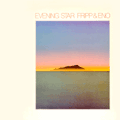
Evening star/Fripp & Eno
いわゆるアンビエントのはしりとでも云うのでしょうか。コラボ二作目。渋谷の表通りの輸入レコード店で買った憶えがありますが、もう遥かな昔。この組合わせだから出てくる音は想像通り。あとはフリップかイーノかどちらに傾いてるかぐらいが印象の分かれ目だろう。前作がイーノ寄りの躁狂感で跳ね回っていたのに対し、こちらはフリッパトロニクスの静謐感がより強く感じられるかもしれない。一定の周期で繰返されるギターのフレーズが妙に覚醒的で、ループが静かにうねっている割には、どうも黄色っぽいイメージが頭から離れない。

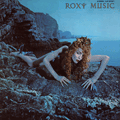
Siren/Roxy Music
やっとのことでようやく世間に認知された5作目。非常にコンパクトで良質でこなれたポップさ加減はかなり売れ線を意識してます。『For your pleasure』や『Stranded』の頃の、斜に構えた頽廃感はファンキィなリズムに覆い隠されてしまったようだ。全体的には職人風のプロ意識とブライアン・フェリィの野心と上昇指向がうまく噛み合った質の高いものに成っているのではないでせうか。黄昏た雰囲気が無くなってしまって(「Just another high」くらいかな)個人的には残念ですが、いずれ『Avalon』に結実するわけだから、まぁ、良しとしよう。
ところで今気がついたのだが、左のジャケ絵、上がCDで下がLP。“Siren”はシレーヌとかセイレーンと称し、船乗りを惑わす妖魔を意味するのだが、上の絵じゃまるで死体みたい。

Act one/Beggar's Opera
ヴァーティゴからリリースされたベガーズ・オペラのデビュー作。クラシック趣味が昂じて名曲をアレンジしまくりで、なんだか訳のわからないものになってます。それもテクニックと力づくでコラージュしちゃいましたという感触で、ほとんどやけくそで早弾きしています。非常にしっかりとした全体構成で、ボーカルが入るとゆったりした品の良い英国滋味が漂いますが、一作目からこんなことをやっていて良いのだろうかと、一応、心配した記憶はあります。マーティン・グリフィス(Martin Griffiths)の声はとても暖かみがある上に、伸びやかで声量があり気持ち良いほど正統的に聞こえます。その歌謡曲風の柔らかみを消すために、ちょっと機械的にイコライズ処理されたような人工的な雰囲気がありますが、まぁ、狙いはそれっぽくて良いのでないでしょうか。
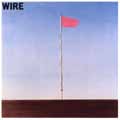
Pink flag/Wire
当時既にパンクに傾倒できる年齢でもなかったので、入れ込んでいたわけではまったくないのですが、一応、ワイアの1stアルバム。長くても3分、1分あるかないかの短い曲がてんこ盛り。元々ちっとも若くないし、テクニックはゼロに等しいが、若気の至りみたいな部分がこれっぽっちも感じられない音で、スパスパと削ぎ落すようなソリッド感が気持良い。アンチ○○なパンク全盛の時代の中で「おれたちゃパンクじゃないよ」みたいなシニカルな自己認識が、覚醒したリズムと突き離した外観に表れていて甚だよろしいのではないでせうか。
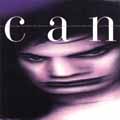
Rite time/Can
初代ボーカリスト、マルコム・ムーニーがめでたく復活していて、びっくりした再結成ものにして最終作。ホルガー・チュカイ(Holger Czukay)も復帰しているようだし、微妙におちゃらけている曲もあって、音楽的にもチュカイのソロの延長線的な雰囲気が濃厚に感じられる。一方、ムーニー氏は相変らず舌足らずな5歳の餓鬼のような優れた歌唱力を発揮しております。86年頃に録音されてお蔵入りになっていたものが日の目を見たようですが、この後はリミックスに各自ソロのみと実質的なカン名義最終作になった模様。まぁ、音楽的にはいわゆるカン以外の何物でもない皮相的かつギミックに溢れた抽出コアのようでいて、理性的にすっきり整理されたポスト・ポップのようなもの。わざと外したような変拍子でノリかけるとずっこけるような不思議な諧謔が愉しい。

Alphataurus/Alphataurus
スピネッタと怒濤のストリング・シンセ、暗めでハードにドライブしちゃう曲調が印象的なアルファタウルスの正規唯一作である1stです。静と動が目まぐるしく入れ代わる、少しくぐもった遠い音となかなかロマンチックなメロディが気に入っています。単純だけど「Croma」みたいな曲が好みなのだ。ボーカルはイタリア歌もの系専任にありがちな、こってりした民族色を強調したもの。エコー掛けて位相ずらして未来派風っぽい、ほの暗い雰囲気を醸し出しているように思う。当時のイタリアものに顕著なドラムのバタバタした録音が足を引っ張る部分はあるものの、意外にリズムがスコーンと抜けて暗い透明感が際立っている。

Resurgence
RES143CD
Choices under pressure/Peter Blegvad
スラップ・ハピィ(Slapp Happy)を構成したトリオの一人、アメリカ人、ピーター・ブレグヴァドのソロ・アルバム。かつてのトリオの諧謔味と少しコミカルな部分、ギターを中心にした演奏部分を担っていたと思われます。今作は、かつてのソロやヘンリィ・カウのグリーブスとのコラボ・アルバムなど、以前にリリースされた曲のアコースティック・バージョンです。恐ろしく賢明でシニカルで、いたずらっ子の初老のおじさんという雰囲気丸出しですが、良い味が出ています。アコースティックの柔らかさもあるけれど、飄々と、淡々と、実に良い形で年輪の刻まれた音です。本業以外でも「リバイアサンの本」というマンガを描いて出版しているとか、新聞の日曜版にマンガを描いていたりするそうですが、タイトルはその辺から取っているようです。まぁ、多芸な殿方ですこと。

Low-life/New Order
ダンスビートに傾倒を始めたのはこの頃か。三作目。デジタルな手法の導入は始まっているものの、まだ音が生っぽくてかわいい。あるいは、生硬で素朴でぎこちないぎごちない。おまけにバーナード・サムナーのボーカルもお世辞にも上手いとは云えないどころか、“音痴”としか表現出来ない。それが味といえるレベルにはまだ達していないとみるべきだろう。楽曲の良さ、メロディの美しさは前作に比して遥かに向上している。漸くジョイ・ディヴィジョン(Joy division)の影を払拭できたということでしょうか、少し明るくて、少し楽しそうな雰囲気が漂う。「Perfect kiss」のバージョンは「Substance」に入ってる長い方(12吋シングル)がアレンジ共、個人的には好みです。

Third Ear Band/Third Ear Band
「気」、「水」、「火」、「土」、4曲入りの1stのようなタイトルのセカンド。執拗に延々と繰り返されるアコースティックなリズムと、メロディを弾かない弦楽器は、何かを我慢してる人を発狂させるのに最適のように思える。チェンバー・ミュージックのように前に出てくる近代合理主義的な音楽ではなくて、むしろアンビエントに近く、呪術的で悪魔的、この執拗なループと単調な無調はかなり狂気に近い。前作『錬金術』を受けているのだろうが、テーマが辛気臭い『万物の四元素』であるし、その表象としての表現力と描かれた事物は賞賛に値する出来映えだ。前作に比べると奏でられる楽器音も部厚くなって、いろんな意味でシュールなまでの凄味が加わった。全曲インスト。年代物にしてはとても分解能の高い音で、それがまたうすら寒くて、そしてとても美しい。
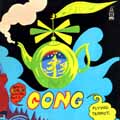
Flying teapot/Gong
不可視電波妖精3部作の第1作。「ぼくも あんたも おれたちゃ みんなきちがい」という実に端的でわかり易いコンセプト。空飛ぶ急須の物語。メンバーのクレジットも全部いんちき臭い変名の使用が義務付けられて、相変らずのぶっ飛んだ不真面目さとお笑いを露呈したエンターテインな芸人根性が見事である。もっとも役は決ってるが演者はその時の都合で変えれば良いわけで、なかなか先見の明に富んだ優れた人材起用法でもあります。中身に関してはどうこうというより(I am your pussyだそうで)、近代合理主義に対するアンチテーゼとしての快楽主義的猥褻さで宗教的解脱を目指すのであろう。うんうん、明解です。アマチュアリズムは希薄になって、Hi T Moonweed(演者はTim Brakeか?)による水晶機械(VCS3)の効果だろうか、スペイシーな浮遊感が加わってきました。

The fat of the land/Prodigy
これはテクノ扱い、巷ではデジ・ロックと称するそうです。稀な日本盤なのだがなかなか豪勢な作りで、ライナーにはいろいろなことが書かれているのだが、一応ざっと読んでみても、中身がなさ過ぎて最後まで読めないし、途中まで読んだところもさっぱり意味がわからんにょ。私のトレンドに対する適応性の欠如を露呈してるわけですが、「爺の出る幕じゃねぇだろ」といったところでしょう、はい。一般的にはおおむね最初の1分で拒絶反応を食らいそうな先の尖った音ですが、ディジタルな気分にはぴったりで、気持良いのではないでしょうか。耳にずけずけ馴染むというか、脳を通り越して心臓あたりにストレートに打撃音が伝わって来る物理的な運動量の大きさにはただ呆れる。前作に比しても部厚く粘っこく油っぽくなりました。

Red/King Crimson
あれよあれよと死に急ぐようなかたちで出たと思ったら、やっぱり出る前に終わっていた第2期最終作。この時点で既にトリオになっていましたが、再びイアン・マクドナルドがサックスで起用されて同窓会かと思った記憶があります。モノクロの(古臭い)ジャケの中で“Red”の文字と裏ジャケの何かの機器のメーターのレッドゾーンだけが赤くて、メーターの針はもちろんレッドゾーンに突っ込んでるわけです。まぁ、他にもいろいろ意味付けされているようですが、考えても意味はない。購入したのは74年の秋、当時はすぐにカセットテープに録ってレコード本体は友人間を巡り巡る。
「赤」「墜落天使」「再び赤い悪夢」「神の導き(本当はただの地名)」「暗黒」と全5曲、暗い曲が並びます。ちょっと宗教色のあるタイトルですが、フリップ御大、彼女が正真正銘の魔女(黒魔術師だか占星術師だか)だそうだから、どちらかというとタブーな方の宗教です。かなりハードに押してくる重い音(ヘビメタ)で破綻しかかっているものもあるし、相変わらずのライブ・テイクも含まれてるし、全体を通した静と動の配置は見事ですが曲の出来は今一つ。それでもまぁ、多分な超絶と絶望が凝縮されて、ラストの「Starless(暗黒)」になだれ込む。終焉にふさわしい情緒と解答だろう。
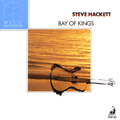
Bay of kings/Steve Hackett
最盛期(人によって大きく認識は異なりそうだが)ジェネシスの看板を背負っていた、2枚目途中から『Wind and wuthering』までのギタリストでした。楽曲のなかでの位置付けは純粋にリード楽器ですが、しゃしゃり出てくるタイプではないせいか、あまり目立ちませんが優れたセンスが光る演奏でした。ジェネシス自体、音楽的にはアントニィ・バンクス(Anthony Banks)の主導権の下にあったと聞きますが、この人がリタイアした後の低汰落とショウビジネス路線をみると、あながちそういうわけでもないのでしょうか。これはソロになって7作目ですが、穏やかで安定した実に英国的な英国趣味でいっぱい。全体としてはアコースティック小品集という位置付けですが、'84バージョンの「Horizons」が目を惹きました。