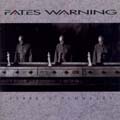
Metal Blade
PCCY-00007
Perfect symmetry/Fates Warning
アメリカのプログ・メタルの重鎮、フェイツ・ヲーニング(以下FW)の5作目。最初に聴いたFWでもある。ドラムのゾンダー(Mark Zonder)加入により、いわゆる黄金期の布陣が整い、変拍子を多用したテクニカルな演奏が楽しめる。アルダー(Ray Alder)のハイトーン・ヴォーカルがやや一本調子なものの、それは主に曲調に拠るもので、構築美を追求する方向性と共に、次作以降、より堅固で複雑なものに成っていく。
一方で、70年代の成果を鑑みれば、内容にはこれといって目新しさはなく、あくまでもロックというジャンルの中での技術的発展と類型化による聴き易さの創出は歯痒さでもあるが、そのあたりは80年代から90年代にかけての一段と商業化の道を進む音楽全体の課題だろう。それなりに観念的な歌詞は意外に内容が面白くて面食らった。全8曲の重量感溢れる鋼のリフが鈍くクールに輝く。突然、挿入されるアコギの音色も繊細で新鮮だ。
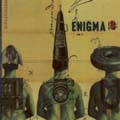 Virgin
Virgin7243 8 42066 2 8
Le roi est mort,Vive le roi!/Enigma
すっかりメジャーになって、あちらこちらからよく聞こえていた憶えがあるドイツのエレクトロ・アンビエント・ダンス・ユニットのアルバム3作目。ヒーリングブームだったかな? エニグマは元々、(1枚目や2枚目は特に)キリスト教的な宗教観をスパイスに今風の信心深くない(アンチ)讃美歌を作っているのだろうが、中身には縁が無いし、別に知るつもりもない私達には可もなく不可もないちょっとオシャレな聴き心地の良さだけが感じられる辺りが丁度よい。誰でも知っているグレゴリオ聖歌や、ちょっとエキセントリックでありながら郷愁を呼び起こすモンゴルの羊追い歌などを巧く西欧風にアレンジして安直かつ効率的にポップに仕上げるあたりはプロの為せる業。妙な懐かしさと気持良い音に浸っていると、ミヒャエル・クルトゥのそれなりの敏腕プロデューサとしての過去を鑑みれば、なんだか予定調和風に乗せられているだけという感もありあり。だが、それもまた一興。
区分に必ずしも意味はないが全12曲。タイトルは『王は死んだ。(新)王、万歳!』を意味する劇中などで多用される古典イディオム。原典は絶対王制時といわれるが詳しくは知らない。黄褐色のエンボス・ヴィニルに両面印刷された類稀なアートワークとエニグマ暗号機を模した緻密で異形のイラストレイションもあまねく賞賛されるべきだろう。
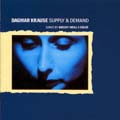
Hannibal Records
MDC6-1140
Supply & demand/Dagmar Krause
ブレヒト作詞、クルト・ヴァイル、ハンス・アイスラー作曲の1920~1940年代の主として劇中歌の歌曲集。歌うのは今の人、スラップ・ハピィ(Slapp Happy)⇒ヘンリィ・カウ(Henry Cow)でレコメンの女神と崇め奉られたダグマー・クラウゼ。もちろん歌詞はすべてドイツ語。ブレヒト(Bertolt Brecht:1898-1956)はナチに追われアメリカに逃れるも、戦後、コミュニストゆえ逃亡を余儀なくされ、思想的な安住の地DDRにおいて演劇界に大きな影響力を及ぼしたドイツの劇作家、ヴァイル(Kurt Julian Weill:1900-1950)はブレヒトの協働者であったが袂を分かちアメリカに定住したユダヤ人作曲家。アイスラー(Hanns Eisler:1898-1962)はブレヒトと同じコースを辿った作曲家。
全26曲。独語18曲+一部の英語ヴァージョン8曲。ローザ・ルクセンブルク(虐殺されたドイツ共産党女性党首)に捧げた「ベルリン・レクイエム」や著名作「三文オペラ」の劇中歌など、1930年代のヒット曲をかなり正統的に歌っている模様。本や映画からでっちあげたイメージにあるヴァイマル(ワイマール)からナチスへの端境期のベルリンそのもの情景が浮かび上がるようだ。

Magnum Music Group
CDTL 011
Fööl Moon/Amon Düül
整理しよう(笑)。さまざまな情報から推測するに、1960年代後半、当時流行のヒッピーごっこから派生したドイツのアングラ・サイケ団アモン・デュール(Amon Düül)はセクト集団であるAmon Düülと、ノンポリ集団であるAmon Düül IIに分裂した。両方に在席した太鼓奏者の例もあるので区別はよくわからないが、双方単独でアルバムをリリースし始めることになる。しかし、時代の流れは速く、無印Amon Düülは70年代早々、IIも80年代を待たずに消息を絶つ。IIは90年代後半のリヴァイヴァル・ブームに乗って復活を成し遂げるわけだが、公式Webには記載されていない活動停止期に、IIの創設時構成員デイヴ・アンダーソン(Dave Anderson:70年代後期のHawkwindのベース奏者)と現役でもある本家の主ギター奏者ヨハネ・ヴァインツィエール(John Weinzierl)が、81年にイギリスで昔の名前を使ってそのままデヴューしたのがこのAmon Düülというわけ。そして、その分家Amon Düülの5作目最終作にあたるアルバムがこの『Fööl Moon』ということらしい。無印、IIとの区別はAmon Düül(UK)と表記するのが慣例のようだ。
中身は全5曲の原始的ドロドロ・サイケだが、オリジナルのドイツDüül色は薄く、Hawkwindのスペース・サイケ路線に近い。上記二人に加え、ヴォーカルはHawkのカルヴァート(Robert Calvert)、ドラムはVdGGのガイ・エヴァンズ(Guy Evans)というのが正式な構成員の模様。ちなみに所有盤のスリーブに印刷されている曲名、クレジット等は曲数が異なる上、契約上の問題なのか明らかにぼかして書かれている。

Virgin
7243 8 49377 2 0
QE2/Mike Oldfield
4作目『Incantations』以降はまったく聴いておらず、90年代に入ってから思い出したように『Crises』、『Platinum』と、後追いで再び聴きだした中期のオールドフィールド小品の一枚。『Platinum』の次作にあたるスタジオ盤6作目のアルバム。時代に合わせた新しい試みとして、ポリリズムやデジタル・ビートなど意欲的に取り組んではいるがお世辞にも成功しているとは言い難い。長曲は展開がこなれておらず、唐突なツギハギが目立ち、ハードなアレンジの違和感がことさらに耳に障る。短曲に無理矢理ど派手なオーケストレイションを施したり、パーカッシブなリズムを前面に押し出してみたり等、まぁ、以前の型からの脱皮を暗中模索といったところか。民俗系のファーファイサ・オルガンやギターのメロディは相変わらずきれいなのに……と複雑な意識にさせられる。路線転換が整理され、コンセプトや割り切り、アレンジの上達やアンサンブルの効率化がなされ、狙い通りの音が耳に届くには今ひとつ時間が必要だと思われる。

A&M/PONY CANYON
PCCY-10178
Last tango/Esperanto
冷湿で隠微な曲が多い前作に比べ、ぱっと最後の仇花が咲いたとでもいうべきエスペラントのラスト・アルバム。凝りに凝りまくったビートルズの「エリナー・リグビィ」のカバーを含め、豪奢でスリリング、コンパクトでかつセンス良くまとめている。ベルギーの田舎から出て来て一瞬、花開いたかに見えたが? やはり売れなかったと。この後、首領兼第1ヴァイオリンのライモン・ヴァンサン(Raymond Vincent)のソロが1作出ていた記憶があるが、これにて終了。最後の曲はやはりタンゴで、びちっと暗くきめている。
「Last Tango」
“平和通り”を流していると
歌が聞こえてきて、引き返してみる
それだけ、そうやって無駄な一日を過ごしている
“平和通り”をただ流して
公園に寄り道をして
楽譜を弾いて
また車に戻る
退屈と云うんだ
退屈と
苦労した年月にもかかわらず
人はおまえが正しくないという
その晩、皆に見捨てられた
苦しい戦いに勝とうとしてきたことも
誰も知らなかったことを悟った
ショウを見る人などいなかったのだ
その最後の苦悩のなかで
最後のタンゴを書き上げた
部屋の奥で
別の旋律が鳴って
ショウが始まる
もっとも、誰かが勝ち名乗りをあげるわけじゃないし
誰かが優勢になるというわけでもない
そうそう、とんでもなく長きに渡って
その部屋の奥で
その旋律は書かれてきたのだ
ライトが灯る
隠れる間もなく
通りをかっ飛ばして
脇をぶち当てる
かっこうよくないか?
最悪だな
苦労した年月にもかかわらず
人はおまえが正しくないという
その晩、皆に見捨てられた
苦しい戦いに勝とうとしてきたことも
誰も知らなかったことを悟った
ショウを見る人などいなかったのだ
その最後の苦悩のなかで
最後のタンゴを書き上げた
努力を重ねてきた年月だけど
人はおまえが間違っているという
その晩、皆に見捨てられた
苦しい戦いに勝とうとしてきたことも
誰も理解してくれなかったことを悟った
ショウを見てくれる人などいなかったのだ
その最後の苦悶のなかで
最後の曲を書き上げた
この当時、『ラスト タンゴ イン パリ(Last tango in Paris)』などという、今思えばかわいい映画も流行っていたが、何か関係があったのだろうか。ジャケを含め、醸し出されるイメージとなんとも云えない悲哀は似ているような気がしないでもない。残念ながら、ジャケで頽廃しているお姉さんは映画の人(マリア・シュナイダー:Maria Schneider)ほど若くもないし美人じゃない。

Polydor
POCL-1647
1959
Deutsche Sinfonie/Hanns Eisler//Gewandhausorchester Leipzig
ハンス・アイスラー(1898-1962)は退廃芸術家としてナチスに睨まれてアメリカに渡るものの、戦後、コミュニストとして赤狩りに追われ国外追放となり、結局DDR・ベルリンに安住の地を定めた人で、最終的には東独音楽界の重鎮に登りつめた作曲家兼社会思想家。今は無き東独国歌の作曲者としても名高い。そのアイスラーが1935~1957にかけて作曲した交響曲が、副題「反ファシスト・カンカータ」と名付けられた本作『ドイツ交響曲』である。ブレヒト作詞の部分を含めて原曲のスコアができたのは1937年、初演は1959年の東ベルリン、初めて録音されたのは1995年ライプチヒ(すなわち本作)だそうで、人も不遇だったけど曲もびっくりするぐらい不遇だった。
全11楽章65分ほどの独唱および合唱付き交響曲。歌詞はかなり辛辣で面白い。というか取りようによっては拙いんじゃないの? と云いたくなるような二面性が込められているような気がしてならない。テーマは、基本はナチズムの弾劾と抑圧された人民の解放なのだが、それはそのままDDR末期の圧政(あるいはスターリニズムそのもの)に対する革命と壁崩壊に伴う市民の解放であり、更に数十年の時を経て、新自由主義的資本主義への糾弾と自らの愚かな選択(信望した正義の裏切り)を未だに甘受できない最低の民へのレクイエムに他ならない。
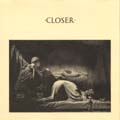
Factory FACD XXV
Closer/Joy Division
『お終い』などというタイトルをつけるからホントにお終いになってしまったジョイ・ディヴィジョンとしては正規2作目にして最終作で最高のアルバム。イアン・カーティスの死後に発売された当時、なんだかあまりにも“そのもの”という感触のスリーブデザインと中身の音にぞっとした憶えが甦る。残った人はニュー・オーダー(New Order)として復活するわけだが、おかげ? で80年代を風靡する良い楽団になったように思う。
全9曲、車用の紙製スリーヴ付。前作に微かに残されていたポスト・パンクの屋台骨はもはや乾き切った残骸と化して、出口のない暗渠には虚ろな空気が澱んでいるだけ。冷徹に刻み続ける単調なビートにモノトーン一色に塗り潰されながらも青白い生気を漂わせるヴォーカルが人魂のように燐光を放つ。どん底に沈んでいくような崩壊感と押し潰された孤独を淡々と演じきるフック(Peter Hook)のリード・ベースが印象的。しかし、全編を覆うこのキリキリと引き攣るような神経症的切迫感と心が壊れてしまったような絶望、あるいはすべてを放棄したような諦観、蒐気迫る悲愴さは堪えがたくも、救いがない。病みに病んでいる。
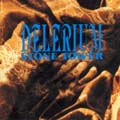
Dossier
DCD 9024
Stone tower/Delerium
デレリアムというのか。プログ・イタリアーノのデリリウム(Delirium)がこんなアルバムを出していたのか? と半信半疑で買ってみたら、中身は180度正反対だが、思いもかけず良かったという杜撰さ。スリーブ・デザインの傾向が似ても似つかぬというのに。こちらのデレリアムはBill LeebとRhys Fullberなるカナダ人デュオの模様。本作『石塔』は一応4作目に当たるアルバムのようだ。
解説の類が一切ないので類推する他はないが、大理石に彫りこまれた中世の人物やマリア像、吸血ミイラなどがお好みらしい。予期される宗教色は皆無でどちらかというと怪奇趣味に近い。音の方もそんな彫刻に耳をあてると聴こえてきそうな暗黒ゴシックが全6曲+3曲。全曲インスト。蛇紋系大理石の血管のような模様にどくどくと白い血が流れているような、なんともいえないエグ味が類例なく素晴らしい。リズム・マシンがチープに聞こえたり、アンサンブル構成に瑕疵がないともいえないが、それが逆に、この手のシンセモノにありがちな類型化を免れていて、非常に斬新感に溢れた内容に驚いた憶えがある。すなわち、プログから派生したというよりはインダストリアル・ノイズの系列で捉えるべきなのだろう。残念なことに、次作くらいから趣が変わって段々とテクノ・ダンスに擦り寄っていくが、この時点ではまだアンビエント色が強くイメージをくすぐられる陰鬱な出来映えだ。
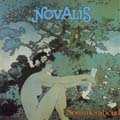
Brain
841 354-2
Sommerabend/Novalis
『夏の夕べ』という原題がとても似合う抒情的佳作にして世評も高いノヴァリス3作目。プロデュースは電子音楽系のアッヒム・ライヒェル(Achim Reichel)。このジャケは世紀末アール・ヌーボーの頃のポスターか本の装丁(作:Maxfield Parrish;1870-1966 アメリカの画家)だったと記憶している。
全3曲、うちインスト1曲。当時、まったくわからないなりに、凛々しさと柔和なまろやかさが同居するドイツ語の歌も美しくて良いじゃないかと思ったことを憶えている。ドイツ表現主義(よりはかなり前)の文人ノヴァーリス(Novalis, Georg Philipp;1772-1801)の歌詞を使った「不思議な宝物(Wunderschätze)」が秀逸。リズムがもったりして巧くはないし、うっかりするとアマチュア臭さが拭えないが最後まで引っ張る的確なアレンジと展開に加え、何よりもリリカルでロマンチックな演歌がツボに嵌る。タイトル曲は20分弱の長曲だが、これまた映像が思い浮かぶほど親密かつ鮮烈であった。アコギとストリング・シンセの背後に湧き上がる蛙の声を聴いていると、蛍や田圃の水面に映る月、そよぐ夜風など、どうにも日本の正しい夏の濃密な雰囲気を享受することができる。青く稚拙だった14歳の夏は本当にこれに尽きた。

Virgin
7243 8 42577 2 9
Cantata Mundi/Adiemus2・Karl Jenkins
カール・ジェンキンズ(Karl Jenkins)主宰のアディエマス・プロジェクト2作目。内スリーブの写真を見る限り、ジェンキンズはやはり母屋を乗っ取ったあの伝説の人で、庇を貸したやはり伝説の人ラトリッジの名は今回(前作では共作クレジットが入っていた)はない。通算4作を数えるアディエマス・プロジェクトは、主としてアフリカ言語を駆使する多言語歌手ミリアム・ストックリィ(Miriam Stockley)を看板に立て、オーケストラを使った声楽入りの現代音楽で、作曲・編曲・指揮を司る中心人物がかつてソフト・マシンで一世を風靡したジェンキンズ。ちなみにジェンキンズはウェールズ人で、首都カーディフの王立音楽院出というエリート。ストックリィを見出した才は、やはりイングランドにおけるウェールズ人としての矜持に他ならないという気もする。
初聴はTVかビデオ・ドキュメンタリィのBGMだろう。1作目のインパクトはないが、テーマの印象深さは勝るとも劣らず、極めて汎欧州的な様式美とストックリィの原始的なまでの真美を湛えた“声”によるパフォーマンスはより完成の度合いを高めている。一つの音楽作品としてみるならば4作中でも焦眉であろう。演奏はロンドン・フィル。
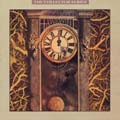
Catsle
CCSCD 321
Live Chronicles/Hawkwind
SF作家のマイケル・ムアコックが詩の朗読をしたり、専属ダンサーである巨女ステイシアがストリップをするステージで名高かったサイケデリック・スペース・コズミック楽団の85年のライブ。78分超え全24曲のボリュームでお腹いっぱい。含まれている朗読は残念ながらムアコックではないようだ。音質も良くかっちりとしたアレンジでまとまって、スペース・ファンタジィ期の雰囲気がよく伝わる選曲+編集になっている。初期の「宇宙は夢も希望もなくただ冷たい、絶対零度、“無”こそ宇宙」といったとてつもない無常感に基づいた薬物エログロ・ハードSF路線も愉しかったが、70年代中期以降は微妙に爽やかで物語性を重視したスペース・ファンタジック・オペラ路線に転向している。また、この時点では、原初構成員はギターのブロック(Dave Brock)のみとなっている。
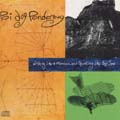
Columbia CK45403
Wishing like a mountain and thinking like the sea/Poi Dog Pondering
90年代中期のシカゴ時代の作品を聞いて、タイトルに惹かれ少し遡ってみたら柳の下にドジョウは二匹はいなかった。近作とはエライ違いですが無国籍ぶりが著しいタロイモ思考の恐らく2作目と思われる。ハワイ人オラル(Frank Orral)を中心人物として、アルバム毎に人員構成が変わっているようだ。ということで、北部ポリネシアのハワイアンを基盤にカントリー、ラテン、ウェストコースト、ディキシーランド・ジャズまで、なんでもありの大道芸フォーク・ロックという路線で、曲ごとに印象は微妙に異なっている。
ヴァイオリン、バンジョー、マンドリンにアコーディオン、アコギというアンサンブルで、歌は民俗色と西海岸風の軽さを併せ持った不思議な味わい。長閑で暢気で軽妙さを漂わせながらも、旧ハワイ王国系民俗ポップ的な、田舎から出てきたんだけど夢にまでみた都会は思ったより世知辛くて疲れちゃうさっといった趣が濃厚。休みの日ぐらいは故郷の南の島を思い出して歌でも歌おうよと、楽しさの陰に微妙な哀感が漂う。
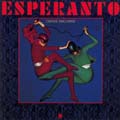
A&M Records
PCCY-10177
Dance Macabre/Esperanto
8+ゲスト3と構成人員が整理され、あまりエスペラントではなくなった2作目。中身はクリムゾンのピーター・シンフィールド(Peter Sinfield)のプロデュースに引っ張られたというべきか。前作の焦点ボケしたどさ回りの旅芸人風ビッグバンドからは随分と進歩した典型的な70年代プログと云えよう。三作目は逆に耽美退廃に傾斜して豪奢な趣すら漂わせるので、隠微を崇拝する者からはこの2作目が好まれるかもしれない。湿ったほの暗さは迫り来る「赤き死(の仮面):小説」や「ノスフェラトゥ:映画」でぺストに怯えて踊りまくるシーンを思い起こさせる。ちなみに、ジャケは仮面をつけた女性が鞭と短剣でプロレスしてるところ。タイトルは『死の舞踏』で、サン=サーンスの同名曲のカヴァー。ついでにクレジットの最後には、「20cm以下のスピーカで聴いたり、空港のラウンジやエレベータの中、ディナー・パーティやセックスのすぐ後に聴いてはいけんよ」と自信満々の記載がある。ははぁ、よござんす。正座して聴かせて戴きます、はい。

Elektra 1098-2
Marquee moon/Television
トム・ヴァーレイン(Tom Verlaine;左から二人目)はフランスのヴェルレーヌ(象徴主義の詩人 Paul Verlaine;1844-1896)に心酔してその名前を使ったと聞いたことがあるが、いわゆるニューヨーク・パンクのカリスマであった。詳しくは知らないが、ヲーホール、ベルベッツ、パティ・スミスと連なる系譜、すなわちニューヨーク・アンダーグラウンドの正統な嫡子として期待され、短いながらも峻烈に輝いて、そしてあっという間に散った。削りたての生木のような軋むギターと神経症的なヴォーカルがやたら印象に残っている。初めてラジオから流れた「Marquee moon」や「Elevation」を聴いたときの衝撃は今でも忘れがたい。パンクとして売られたとは云え、中身は酒と薔薇と薬の古典的美学であり、構築美に溢れた退廃とヘロヘロの憂鬱に侵されきった剥き出しのセンスが痛々しくも切なく響く。
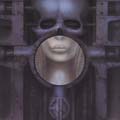
Victory
383 480 020-2
Brain salad surgery/Emerson,Lake& Palmer
当時、友人に借りて録ったアナログ・カセット・テープがブチ切れて買い直したCD。LPは観音開きの変形ジャケだった憶えがあるが既に手元にはない。5作目にしてこれが実質的に、そして本質的にELPの到達した完成形にしてラストアルバムだと考えている。以降は焼き直しと自己劣化コピーに過ぎないという点が、なし崩しにして考えなしのELPのELPたる所以でもある。
冒頭の佳曲「Jerusalem」はイギリス近代の作曲家パリー(Charles Hubert Parry:1848-1918)の同名曲のカバー。原曲は合唱曲というより聖歌にして国民愛唱歌。あるいは戦後の労働党の党歌として知られる。歌詞は象徴主義画家・詩人ウィリアム・ブレイク(1757-1827)。2曲目「Toccata」はアルヘンティーナの作曲家、ヒナステラ(Alberto Ginastera:1916-1983)のピアノ・コンチェルト1番、第4楽章のリアレンジ。以上はエマーソンのクラシック趣味。レイクの抒情フォークを挿んだ後半は大曲「Karn evil #9」。元々はLP-A、B面に跨った30分弱の三部構成組曲。ありとあらゆる要素のごった煮にして、ロックの恰好良さを余すところなく演じ切ったアルバムの焦眉。歌詞はクリムゾンのシンフィールド(Peter Sinfield)。当時はクリムゾンやらフロイドに比べ、かなり陽性で派手(というか体育会系別ジャンルか)だった気がするが、気持ち悪い汗と腹毛の肉体派映像とアホさ丸出しの哺乳類曲芸を見なければ実はシンプルで結構良い音でないか? と再評価すべきものかもしれない。