
m-note RECORDS
8 84385 79558 0
Whitescape/Otoemon-ayahiro SUMI
Webの情報によれば、名は“鷲見 音右衛門文広”と綴る中年のオジサン。正規の音楽教育を受けた後、作曲を生業としながらピアノ演奏もする方のようです。youtubeにアップされていた夜行ユリカモメのBGMに使われていたのが初めて聴くきっかけだったと記憶している。音源はCDとmp3で提供されているようだが、CDは品切ればかりで入手性は良くないが、そのうち改善されるのだろう。mp3じゃなくてFLACなり無圧縮にしてくれれば即座に乗り換えるんだがね。webに作者自身による各曲の解説あり。
本来は器楽曲として作られたものを純化したピアノ・アルバム。楽器の数が少ないと一般的には単調になりがちで全部同じに聞こえてくるもんだが、転調やリズムに工夫が凝らされていて予定調和的でありながらも新鮮、あるいは鮮烈なエッジの効いた切断面を垣間見せてくれる。清冽で叙情的、明快で率直な抒情一直線でありながら、それなりに変化に飛んだ曲調で最後まで楽しめる。静粛性の高いクルマを高速で滑らせながら夜景を眺めつつ聞くには最高ですな。他のアルバムはエレクトロニカ風の構成を取っているようなので、そちらも聽いてみたい。

7 51937 43482 5
Sometimes/Goldmund
薄暮の湿地に草を掻き分け入っていく黒衣の女二人……という意味深なスリーブがゾクリとするほど印象的で邪な想像力を掻き立てるアメリカ人キース・ケニッフ(Keith Kenniff)によるゴールドムンド名義の近作。同一人によるエレクトロニカ+アンビエント路線のHeliosに対し、ゴルトムント(ヘルマン・ヘッセの『ナルチスとゴルトムント』?)を称するこちらは郷愁に満ちたアンティーク・ピアノを主体としたポスト・クラシック+アンビエント路線なのか。なのか?
敢えて奥に篭ったような、淡々と心象風景を奏でるピアノと空疎な背景を連続的に、或いは断続的に埋める電子楽器音が織りなす耽美と親密性に溢れた構成は生真面目で単調でありながらも飽きさせることなく、仄かにエロティックで心を惹き付けて止まない。一方で、アレンジ凝りまくり、かなり作り込んだ音響で、淡々と単調に聞かせながらも奥はとても深い。う~ん、拡散し続けるイメージは、具象でありながらも見事に凝縮された心象を描写するワイエス(Andrew Wyeth:1917-2009)の世界に近い。「絵」が見るものでなく読むものであるように、「音」もまた聴くものでなく読むものなのだろう。
ちなみに、若い頃、ワイエスはあざとい感じが拭えずに好きではなかった。ところが1985年に『ヘルガ・シリーズ』と称される240点にも及ぶ未発表の作品群が存在することが公になって、個人的な評価は180度転回した。
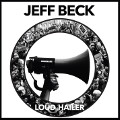
ATCO R@ 555546
Loud Hailer/Beck, Jeff
60年代イングランドで産声を上げたヤードバーズの2代目ギター奏者(初代はエリック・クラプトン、3代目はジミー・ペイジ)だったと記憶している。もう70は優に超えていると思うのだが、相変わらず元気なことで。元はブルーズ・ギターだった気がするが、70年代中期のフュージョン・ブームに乗ってクロス・オーヴァー方面に思いっきり転向して、以降はジャズ、最近はエレクトロニカに接近している模様。改めて聴き直してみると、ジャンルはどうでもいいのだろう。テクニックに関しては申し分ないというか神技の領域。80年代中期以降はフィンガー・ピッキングになったのね。最近の映像を見てビックリした。ちなみに随分昔、クロス・オーヴァー時代に一度生で見た記憶があるのだが、いつどこで、隣りにいたのは誰なのか、完璧に記憶が欠落している。
CDは普通に入手した輸入盤だが、音圧高過ぎないか? いや、だから『Loud hailer』なんだろうが。タイトルは「メガホン」の意。冒頭、異常に音圧が高くてスピーカー壊れるかと思ったわ。今作は若い女性歌手と女性ギターを従えて、というか前面に押し出して、リズムは外注だがよくまとまっている。真正面から声を上げる的に真摯にして充実、密度も濃過ぎて、久々に“重い”。

CST126
"Luciferian Towers"/Godspeed You! Black Emperor
カナダのポスト・ロック、アンビエント・エレクトロニカ。Mt.Zionから室内楽風クラシック趣味と政治色・宗教色が乗った歌詞を省捨した轟音アンビエント。Mt.Zionの主催者:Efrin Menuckが主催するもう一つの顔でもある。楽団名は70年代中期の日本映画から取られた。ブラック・エンペラーは当時土曜の夜に出没していた暴走族の名前だな。アルバムとしては6作目。ジャンル区分が不能な包接体としては日本のWorld End Girlfriendとよく似ている。
全曲歌なし。ルシファーは明けの明星を意味する悪魔にして堕天使。サタンの別名。悪魔の塔はアメリカ・ワイオミング州に実在する岩山だが、おそらく宗教的な意味合いは無いし、タイトルになっている塔は別のもの。2017年に炎上したロンドン郊外のタワー・マンション「Grenfell Tower」を指していると思われる。このエフリム・メヌックという人物はなかなか急進的に政治的な方のようで、シニカルで相当キツイ意思が垣間見えるのだが、音として表現される圧倒的な絶望感と諦めに近い無常感はひたすら重く、悲しく、美しい。




sound cd ss012
Slope/Jansen, Steve
ステーブ・ジャンセンの2007年初ソロアルバム。元は1976年デヴューのJapanのドラマー。実兄がデイヴッド・シルヴィアン。Japanは粉飾プンプンの強烈なカモフラージュを被りながら、当時の状況の中で如何に逆しまに進むかを志向・体現してきた、意識高い系の権化みたいなバンドであった。もっとも国内メディアを通した外観はミーハー的な扱い一辺倒で、完全に目を眩まされ関心の外に置いてしまっていたわけで、今思えば残念この上ない……というのは個人的な懺悔。改めて今聴くと、そのヘンテコリンな楽曲をヘンテコリンに演奏するジャンセンのドラムも十二分にヘンテコリンで、エモーショナルな情感を排した無機的で理知的な、現代音楽的パーカッションとでもいうべきか。
淡々と多種多様なコラージュのようなインスト曲中心ですべてジャンセン作だが、本人の歌は無し。後から知るには実兄とは相当の確執があった(今でもある)模様だが、本作でも「Playgraound Martyrs」、「Ballad Of A Deadman」の2曲でデヴィシルが歌っている(歌詞もデヴィシル)。まぁ、しかし、この人の声が入るとモノクロの映像に色が着いていくように、ホント一瞬で空気の色が変わるというか、華やぐんだよなぁ。

KSCOPE375
Insurgentes/Wilson, Steven
基本的に殆どの既成メディアからは引き篭もった生活をしているので、この人の名を初めて意識したのはイエス(Yes)のリマスターを手掛けるエンジニアとして、次にバルビエリ・ジャンセン・カーンの元Japan組でギターを弾いている映像を見て、この人は何をする人ぞ? と思ったのがきっかけ。結果的には名前しか知らなかったポスト・プログレのポーキュパイン・トゥリー(Porcupine Tree)を率いる鬼才であったという流れ。更にその後、No-Manの片割れであったことにも気付く(笑)。自分だけで探し、自分だけで選び、自分だけで聴く以上のことを何もしないから灯台下暗しは多発する。そういえば、クリムゾンの最新リマスターも手掛けていたな。まぁ、その筋の玄人、音響界の才人でもあるせいか、Blueray-albumにはFLACとmp3の無料downloadコード付き。
と、前置きが長くなったスティーブン・ウィルソンの薹が立った初ソロ作「反乱者」。精緻にして構成と展開の妙を尽くしたような陰鬱なアンサンブルとアレンジにリリカルで不穏なメロディと歌詞が乗る。尖り過ぎることもなく、そこはかとない洗練と耳に馴染む予定調和が基調なんだがちょっとクール過ぎで気に入っている。前衛やらアヴァン・ガルドといった古臭いシガラミとは別次元でのプログレスなのだろう。

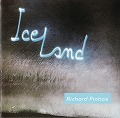
CTCD563
Iceland/Pinhas, Richard
70年代中期にフランスでHeldon(エルドン)を主宰していたリシャール・ピナスのソロ3作目。クリムゾンのロバート・フリップを想起させるディストーション・ギターをシンセサイズドさせた純粋器楽的なアプローチと一世を風靡した ドゥルーズ+ガタリの構造主義やポストモダン哲学を基盤にした情報の伝達とそのインターフェイスにこだわった取組みというのか? 当時にしては意識高い系の権化であり、一方で妙に情動的で感性が突っ走っちゃう変態性を併せ持つ二面性が不思議。
初期ピナスの代表作でもあり、当時全盛プログレの陰で勃興したアンビエント・テクノからトランス・ミュージックへの橋渡し的な存在にして、フリップ&イーノに代表されるデジタル以前のアナログ・アンビエントの萌芽。タイトル通り、凍てつく極北のブリザードと変幻するオーロラの揺らぎを模した無機的で無常観が溢れる。ギターはかなり控え目でシンセ主体だがアナログ・シーケンサの不可思議な反復リズムも効果的に使われて飽きさせない。かなり長尺の組曲8曲に25分のボーナス付き。


TYPE062
Something that has form and something that dose not/On(Reworked by Fennesz)
思わせ振りなイラスト(最近多いな、こういうの)に目が留まる浮遊型ノイズ・アンビエント。シカゴ・ノイズ? 二人組ONのオリジナルを元に、オーストリア人フェネス(Christian Fennesz)が再構成、アレンジしたもの。非常に異質というか、音楽の異端とでもいうべき取り付く島のない絶壁フラット、お手上げの痛快なのか爽快なのか、こういうのって世の中的にヤバくね? あまりの素っ気なさと剥ぎ取られて感情の残滓すら残っていないような無機さ加減に、凡そ人間に聴かそうというよりは細胞の固有振動と位相が同期するようなヤバさがある。
「形あるものと無きもの」という思わせぶりなタイトルは多分「色即是空」みたいなものなのだろうと勝手に解釈している。このジャケットのたいそう叙情的な情景と無機音の反復ループが段々と正体を晒してくるような曲(というよりは音)の股裂きのようなソグワナサの深奥に朧気に垣間見えるスッカスカの無常はなかなか心地良い。音像は構築的でそこはかとなく刺激的で作者のセンス? は全く推し量れないが、おもしろい。ちょっと、目を開かされた。
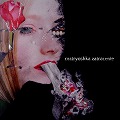
UNS-014
Zatracenie/Matryoshka
退廃お耽美抒情陰鬱エレクトロニカ。日本人男女二人組、マトリョーシュカの1st。人造人間作家ベルメールのような淫靡なキモさと奇形的人体改造趣味に湿り気の多い美を見るのはわからんでもないが、うへぇと一瞬ギョッとする。それなりに壮大で哀愁を押しまくるメロディと、少女趣味風の儚さと拙さを綯い交ぜにした詠嘆調女性ボーカルは英語風だが聴き取れるか否かのギリ線狙いで残滓なのか斬新なのか。ひたすら内密でマイナー調の染み入るノンジャンル・ポストロック。
タイトルはポーランド語でザトラツェニエ:壊滅、破滅、取り潰し。World End Girlfriend(以下WEG)からノイズとアグレッシブな疾走感を捨象し、アンビエント・エレクトロニカと室内楽を足して3で割ったような薄ら寒い隙間感が醸し出すしっとりと湿った寂しさは、あまり類例の無い感触でそれはそれで素晴らしい。Remixを含め4枚ほどアルバムが出ているようだが、売れてるとは思えないし入手性は良くないというほどでもないか。マトリョーシュカはロシアが誇るあの入れ子人形だ。


Dead Oceans DOC132
Slowdive/Slowdive
1990年代初頭に頭角を現し、その筋では一世を風靡したスローダイヴの復活2017年作。エレクトロニカやシューゲイザというよりは遥かにギターポップに近い湿った温もりと世間受けする安定した儚い歌メロが特徴だが、そういった古臭さを補って余りある典型的なイングランドの職人センスには脱帽する。
いやぁ、各人すっかりオジサン・オバサンになってますが、機材のせいもあるが昔より良いよな。4曲目「Sugar for the pill」、6曲目「No longer making time」あたりの圧倒的に拡散していくサビメロやらタメというか無音の間のとり方なんて上手いよな。オレも年をとったなと率直に思う。意図はわからんがライブのラストはシド・バレットの「Golden Hair」。歌詞はジェイムズ・ジョイス(James Joyce:1882-1941)。原曲は陰の中に一瞬垣間見えた陽を儚く喜ぶ“もののあはれ”を体現したような曲だが、こちらは壮大なシューゲイズと化している。