
Virgin
7243 8 394432 3
(1994)
Encore/Tangerine Dream
ようやく手に入れた77年3月のアメリカ・ツアーにおけるライブ。94年のリマスター。分量はLPなら2枚組相当だがCDで増補されたのかは不詳。計70分超え、各16~20分弱程度の全4曲。布陣はフローぜ+フランケ+バウマンという最盛期黄金トリオ。おそらくオリジナル構成員最後のトリオ形態。76年の『Stratosfear』以降のメロディアスBGM路線とそれ以前の前衛プログ・アンビエント路線の両方を味わうことができる端境期ライブで、前衛時代の面影が残っているあたりが評価の基軸か。アメリカ仕様ということで若干軟派イージーリスニング・トリップ路線寄り。心地良いシーケンサを基軸にしたウルウル・ヒタヒタな明快メロ+グルーブ・リズム。ピアノやメロトロンの使用頻度が高いあたりは古の時代を感じさせる全曲インスト。トリオ編成でのライブとしては極めて緻密に構成され、当時の音響芸術としては一級にして秀逸だろう。
Virginが発掘したウェールズの超絶マイナー:マイク・オールドフィールドという前例の成功の下で成立し得た、辺境ドイツの勃興期電子音楽風ロックであることには違いないが、ドイツ系の中では比較的マネージメントが上手く、時代の波を読んで世界に羽ばたいて成功した部類ではあるだろう。リアルタイム聴取という意味で、'74~'78の冷涼シーケンス・パターンにやられた世代なので、このあたりは遥かな記憶と悔恨や愉悦がない混ぜになって情動を掻き乱す。
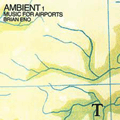
EMI 50999
6 84523 2 2
Ambient #1:Music for Airports/Eno, Brian
イーノのアンビエント・シリーズ第1段。空港の出発ロビーに相応しい音楽というコンセプトの下に作られたミニマル音楽の発展型にして極めてイギリス的な到達点でもある。意味性や伝達性といった音楽に内包されていた観念を極力排除した環境音楽という概念が成立した記念すべき名作ともいえようか。曲名は「1/1 16:30」「2/1 8:20」「1/2 11:30」「2/2 6:00」なわけだが、78年のLP時点でどういう配置だったのかは不詳。「1/1」の共同作曲・ピアノにワイアット(Robert Wyatt)、エンジニアリングにコニー・プランク(Conny Plank)の名前が見える。
“薄日、ときおり小雨”みたいな淡々としたリリカルな清涼感は極めてイングランド的な滋味を彷彿とさせる。ボイスもソリーナではなく実際の生人声である辺りは、古き良き時代のしっとりとした湿り気を感じさせて心地良い。極度に制限された音数と最小のアンサンブルが奏でる余韻にひっそりと埋没するのも、乾いた音を立てて落ち葉が舞う、秋たけなわという趣か。

EMI
0946 3 63946 2 6
(2006)
Decay Music/Nyman, Michael
75年にグリーナウェイの映画用に作曲された(が、映画で使われなかった)「1-100」に「Bell Set No.1」をB面に配し、76年にイーノによるプロデュースで、イーノ設立のオブスキュア・レーベルより発表されたナイマンのデビュー作。リマスターされ、ボーナス・トラック「1-100(Faster Decay)」が追加された再発が2006年の本作になる。ミニマル(Minimal)という言葉を世に出した現代音楽の評論家でありながら、以後は作曲家として理知と前衛に邁進するのは周知の通り。
「1-100」はナイマン演奏による超絶シンプルなミニマル・ピアノ曲。不協和音を巧みに織りまぜながらも、無音の静謐に間歇的に響く研ぎ澄まされた音の羅列が浸れるほどに心地良く、反宗教的でありながら、聞くものを至高の天界、或いは幽玄の涅槃へと導く。「Bell Set No.1」は73年初演。ベルとトライアングル、ゴング、シンバル、タムタムによる5人編成の合奏曲。共にタイトル通り、発音のアタックから減衰していく音、すなわち余韻を主役にしたアンビエントの始祖的な作品。手法的な小難しさは置いておいても、十分に心地良く、聞いていることを忘れるほど聞き流せる。

DGM0550
The Equatorial Stars/Fripp & Eno
“Fripp & Eno”名義の共同作業としては75年の『Evening Star』以来約30年ぶり。タイトルは「赤道の星々」。赤道とは地球を中心に南北の天頂軸に直角な円の仮想的な円周、天球上の赤道を指すのだろう。電気ギターにアナログ・テープ・ループの再生音を重ねていくフリッパートロニクスの現代的な援用とイーノの鍵盤再生音のコラボ全7曲。曲名は恒星の名から取られているのか? total:47分。もちろん全曲インスト。リズムはあったりなかったり。
30年という時間経過を鑑みれば、内容に音楽的な意義を見出そうなどとは今更思うこともあるまい。一方で、先鋭やら斬新さ以外にも価値がないというわけではないことぐらい理解できるのも時間の為せる技にして効能。クールでバリバリ、テクノロジーを誇示する硬質ガラスのようなアンビエントが巷に溢れる中で、そこはかとなくアンニュイでクタァ~とした色っぽい香気を感ずる本作はアンビエントを基調としながらもその範疇から逸脱してみせる珍しい部類。心地良くも流麗な持続音の洪水ながらも、哀惜に満ちた生の情念が迸るような有機っぽさを感ずる。現代のテクノロジーを以ってすれば、アナログ・フリッパートロニクスも色褪せた感があるが、そこはそれ、極めてイギリス的でプラグマティックな展開で聴取者を煙に巻く。予定調和的なお約束の情感溢れるメロディとアンサンブルに関しては天下一品の部類にして巧者。

King Record
KICP 2828
(1996)
East west/Pinhas, Richard
70年代後期から80年代にかけてエルドン(Heldon)を主宰したフランスの、あまりフランス的ではない前衛電子音楽系のギター奏者、リシャール・ピナスのソロ4作目。アメリカのSF作家ノーマン・スピンラッド(Norman Spinrad)にインスパイアされた、SF風世界都市風景小品集といった趣で、スピンラッド自身も冒頭とラストの「Houston 69」でヴォイスで参加を果たしている。ロケット打上げ基地のあるヒューストンに始まり、ロンドン、京都、XXXXX(名前のない街)、ルュイトール(フランスアルプスのリゾート:生地?)、ニューヨーク、パリ、ケフラヴィク(アイスランド西部の港湾都市)を巡ってヒューストンに還る旅の印象か。一曲を除きインスト。
ピナスのギター+鍵盤はE-Mu コンピュータ・システムで電子的に変調され、フリッパートロニクス的展開を漂わせつつ、高速かつクールに疾走する。鍵盤システムにズール人脈のパトリーク・ゴティエ(Patrick Gauthier)の名が見える。時代の趨勢としてエレポップ風のアプローチも感じないわけではないが、概ねよく熟れて、フリップ&イーノの後追いと言われようとも、あくまでピナスらしい心地良いグルーブ感と冷涼で硬質なアレンジが全体を律している。
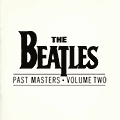
Parlophone
CDP 7 990044 2
Past Masters Vol.2/Beatles
後期ビートルズの1988年編集のシングル・コンピレーション。リマスター全15曲。棺桶に片足を突っ込みかけた身として唐突に「Hey Jude」が聞きたくなって入手したが、すべてアルバム未収録のシングル・ヴァージョンおよびボツ曲で、期待していなかった割には、なかなかお買い得にして面妖。ビートルズの盤権はデズニーと並ぶ著作権亡者の餌食になって沸々と腐敗臭が漂うからなぁ。リマスターも効いて印象も新た。「Rain」やビリー・プレストン(Billy Preston:アメリカ人・黒人鍵盤奏者)入りの「Get Back」や「Don't let me down」あたりは、それなりに価値はあるのだろうし、名曲「Across the Universe」の冒頭には鳥の鳴き声のSEが入っているモノ。特に「Don't let me down」はアルバム曲よりイキイキとダイナミックで改めて目を開かれる思い。うぬぬ。
あらゆる意味で彼等の66年~70年は、後世の礎というか、範になった新しい概念と要素、手法がてんこ盛りであることは今更言及することでもないが、そういうレベルを超えた歌曲の出来の良さにはもはや平伏するしかないだろう。40年以上経っているのに、どれもみんな憶えていて、いやはや、なんとも語る言葉がないな。

LSD 2.000-2
(b)Engel des Herrn, Die/Engel des Herrn, Die
92年リリースの“主の天使(或いは主の棍棒・愚息)”初作。当初はメイル・オーダーのみの自主制作で貴重だったらしい。Neu!⇒La Düsseldorfの故クラウス・ディンガー(Klaus Dinger)が主宰したテクノと云うよりは、エレクトロニック・ヒッピー・パンク。収録タイトルは88年から91年にかけての全9曲。4人編成の促成ユニットと思われるが、ディンガー以外は不詳。この後、ライブを1作残して頓挫。
極めてポップで、あくまでも心地良い音符のつづら織り。前半はスコーンと抜ける透明感とクラウトにあるまじきポップで儚くも美しいメロディが際立つ。ソリーナをバックにしたテクノと云うよりは普通のビート・ロック。後半は10分超えヴァージョンの焼き直し「Cha cha 2000」に更に焼き直しの「Cha cha 3000」。ラストは20分越え。CDのみのボーナスでタイトルの愚弄「主の棍棒:20'47」。いつものお巫山戯ノイズ・ヒッピー風パンクで、深刻味のなさとズンドコでパワフルなライブ版「Cha cha」のような長曲で締めくくり。意外に評価の高い世評は希少価値への評価であって、郷愁或いは懐古の側面でのみ、語られるべきと思う。

MT 194-1
Ацнза/Линда(Linda)
84年ロシアでデヴューのカザフスタン人女性ボーカル兼コンポーザ:リンダの4作目のアルバム? コンピかベスト盤的な扱いなのかもしれない。情報少なすぎ+(キリルじゃ)字が読めん二重苦でさっぱりわからん。極めてリリカルである意味東洋的、民俗的(要は演歌的情動)とも云えるメロディを、打ち込みの洗練されたテクノ・リズムと高度なエレクトロニクス処理で聞かせるネオ・民俗プログ・ポップでいいかな? 一部の曲の歌詞が明らかに日本語(水の中の踊り?)だったり、詩の朗読が日本語だったりと面食らうというか仰け反るのだが、出来の良さは手放しで褒めてもいい素晴らしい部類。歌もテクニックも文句の付け所がない。
非絶叫型の透明感溢れる可愛らしい声質だが、明らかにそれなりのアカデミーで声楽の専門教育を受けているプロフェッショナル。100回歌っても100回とも全く同じに歌えるタイプだわ。歌詞はロシア語。あちらの歌手はプロっぽすぎて興冷めしちゃうことが多いんだが、この人はツボを心得ている。中央アジア風のイスラムと東洋が入り混じったような曲調を非常に上手く生かした構成とアレンジが決まっている。決まり過ぎかな?

Noir Records
DFD-21124
Illuminate/Qntal
90年代初期から現在に続く、ドイツの電化トラッド、クンタルのEPと思われる。初期のヒット曲?「Entre moi」のビデオ付CD-ROM。正規版未収録のシングル・ヴァージョンやクラブ・ヴァージョン、リミックス等、非常にポップでグルーブに富んだ聴きやすい展開を狙っている楽曲が集中的に収録されている模様。元々、中世ゲルマン系+初期ラテン系+ガリシア・ポルトガル系楽曲のエレクトロニック+テクノな大胆アレンジと主唱シラー(Syrah:aka Sigrid Hausen)の透明感溢れる達者な歌唱が売りだが、正規アルバムではかなりアカデミックなアプローチが主体になっており、お世辞にも聴きやすいとは云えない内容で、BGMやポップ領域とは完全に一線を隔てている。鍵盤担当がプログラミングを兼ねているため、テクノ風の音の扱いが非常に巧みで、古楽との差異感をいっそう際立せる辺りが斬新か。歌詞は中世ドイツ語、中世フランス語、ラテン語等で原則原曲の通り。
映像はnet上に山ほど転がっており、公開には非常に積極的な模様。歌手としてのハウゼン以外は、フィドル系+鍵盤系の2名からなるトリオ編成。それなりの年齢のようで若くはない。ライブではゲストとしてバグパイプやハーディ・ガーディ、パーカッションが加わった映像を見ることができる。

East World
EW0025CD
Díe Lösunǵ/Amon Düül
アルバム4作とコンピ1作を残した80年代Amon Düül UKの実質最終4作目。84年に録音、89年に3作目『Fool Moon』と逆順でリリースされたもの。88年死去の元ホークウィンド(Hawkwind)のロバート・カルバート(Robert Calvert)が共同作曲・全作詞、朗読風ヴォーカルでほとんど主役状態。テクニカル・サイケ・フュージョン、或いは疾走Gongと云われたOzric Tentaclesから2名が参加とけっこう豪華。ペンギン+鷹+etc.という主要な構成員は前作と基本的に同じ。可愛い声の女性ヴォーカル(Julie Wareing)も出番は少ないが歌っている。ADUKの4作中、ADというよりはほとんどHWか? と思われる節もあり、最もこなれてグルーブ感に富んだ聴きやすいポップなノリ。アレンジもADというよりはウェールズのポップ・ミュージックの領域。しゃがれた声で歌われる虚無的な歌詞とHW調のマイナーな節回しが心地良いほど決まっている。
タイトルはSolution(解)の意だが、解散・大団円といった意味が込められているのかもしれない。CDは2008年の再発リマスター。オリジナルは全7曲と比較的コンパクトな曲が並ぶ。ボーナスとして、けっこう名曲「Drawn to the flame」の別ヴァージョンがPart.2として追加収録されている。

WARNER MUSIC JAPAN
WPCL-735
 CCCDシングル
CCCDシングルぼくたちの失敗~ベスト・コレクション/森田童子
この節操のカケラもない落差(笑)。バブル崩壊直後の絶世欝TVドラマ『高校教師』で発掘採用され、末世を体現するかのように、一世を風靡した70年代覆面シンガー・ソング・ライター、森田童子のコンピ盤。80年代漫画界の内田善美と同様、ある日突然もう辞めたとリタイアしてそれっきり。おまけに、作者による再版拒否で再発不可? なのか、レコード会社の都合なのかは知らないが、あまりにも希少な中身を過去として追想するしかないことで、否応にも存在価値は至高の領域に達してしまうという稀有な例。金に目が眩んだ遺族が出現するわけでもなく、当人が過去の栄光にすがることもない状況を鑑みれば、多分、お二人とも結婚を機にそれまでの全てを捨てて、それまで以上の充足の中で生きているのでしょう。羨ましい限り。
純音楽的な嗜好としては苦手な部類に属する内省的・私小説叙情フォークというジャンルで、すこぶる儚げな女声と、ピアノと弦楽主体のダイナミズムに乏しい器楽アンサンブルがいっそう薄幸感を煽る。その少し前の、いわゆる反体制・全共闘フォークの挫折と瓦解の上に成立し得たある種の退嬰的「思い入れ」を前提とした世界観を共認できるかどうかが分かれ目か。ウマヘタなのかヘタウマなのか、リヴァーヴ掛けまくりの歌唱と語り、典型的JPOP風イコライジングとあからさまで直截的なSEは好みを分かつところだろう。ジャケ絵は風間完。きっかけは下段、10年ほど前、知人に借りたCCCD版シングルによる。
青海川(新潟県柏崎の西、米山付近)は昔よく、無目的にフラフラと海岸や川岸を徘徊していたところ。同じ地名が出て驚いた。80kmほど西、糸魚川の富山県境付近にも青海という地名があって、同じく青海川という川が日本海に注ぐ。ちなみに翡翠で有名(河床にゴロゴロ)なのは後者。80年代終わりごろ、「いつまでもこんなことが続くわけねー」と頭の片隅で思いつつも、踊らにゃ損、損と踊り狂っていたバブル末期の記憶がラップして、殊更印象深いものがある。

Repertoire
IMS 7029
Waters of change/Beggar's Opera
70年代初期のB級ブリット・ロック、ベガーズ・オペラの2作目。初作がクラッシクのフレーズを多用した高速チンドンだったのに比して、専任メロトロン奏者(Virginia Scott:女性)を加え、全曲オリジナル、英国滋味に溢れた前期プログレ的な完成度が一気に高まった佳作(あるいは隠れ名盤:個人的には最も好み)になっている。このメロトロン奏者、後半全曲を作曲しており、アレンジの才や演奏も主鍵盤奏者に引けをとらない。有能過ぎてポップ・ロック的展開の次作では名前が消えている。深くしっとりとした情感を湛えたストリングズ音主体のメロトロンをバックにグリフィス(Martin Griffiths)の上手い歌が殊更映える。よく練られた曲の展開と転調を生かした抑揚あるアレンジが非常に心地良く、チグハグになりがちな歌と器楽のアンサンブルもバランスよく決まっている。
B級の宝庫Virtigoレーベル故、オリジナルの録音が時代物であることを鑑みても救い難い質で、再発リマスターとはいえ限界がある。ジャケは岩場を流れ落ちる水。タイトルは『移りゆく流れ』とでもいうべきか。

Rama-Lama Music
RO 50672
-1983
Todas sus grabaciones en Discos EPIC/Alameda
エスパーニャ南部、アンダルシアの民族プログ・ポップ、アラメーダの1stから4thアルバムを2CDにまとめた再発リマスターCD。タイトルは『彼らのEPIC/Sony時代の盤のすべて』という素っ気ないが明快なもの。全32曲。1~7が1st『Alameda(ポプラ並木)』、8~15が2nd『Misterioso manantial(神秘の泉)』、16~24が3rd『Aire cálido de Abril(4月の暖気)』、25~32が4th『Noche Andaluza(アンダルシアの夜)』。ロック・アンダルシアでも比較的後発の部類のせいか、同郷先達のトリアナの湿度とマイナー調とは異なった洗練された節回しと明快ながらも抑制されたアンサンブルが特徴か。作を追うごとにゴージャスさと緻密なアレンジが冴え渡る。鍵盤x2、ギター、ベース、打楽器の5人編成でギターが器用に歌謡を兼ねる。4作で頓挫後、90年代中頃に復活している。
おそらく当時もシングル・カットされたと思われるポップス演歌からプログ・ジャズ・高速フラメンコ・フュージョンまで玉石混淆だが、どれも格調高い曲調で、アレンジも派手さはないが極めて達者な職人的テクニック。マシンのように正確なドラムズ、スラップ奏法もこなすベース、的確で抑えに抑えた鍵盤、フラメンコ・ギターもそつなく鮮烈なフレーズをこなし、尚且つ、切々と謳いあげる節回しが特徴のカンテも見事に決まる。それでいて、自らのアイデンティティを極めて的確に表現し切った完成度は唸らせるものがある。

RCA ND 71838
Live in U.S.A. /Premiata Forneria Marconi
海外進出に成功し、発売当時のLPでは『Cook』と称された絶頂期のライブ。海外進出とはもちろん、メディア産業を牛耳る英米資本からレコードをリリースし、英米、特にセールス規模の桁が違うアメリカでの成功を意味する。もっとも、そこで求められたものはアメリカン・ポップスとは毛色が違う、面白可笑しい異邦の“ロック・ちんどん”であり、観客が求めているものが所詮猿回しの極地「Celebration」でしかないことに気付いたパガーニの脱退を誘う結果となる。結果的には、時代状況の閉塞と進取的気運の失墜という外的要因も相まって、海外からの撤退と民族路線への回帰の契機になってしまった。
主に英語版『甦る世界』からの曲目が、超絶な演奏技術と絶妙且つ自由自在なアレンジで、即興とロッシーニ作ウィリアム・テル序曲などを織り交ぜながら展開されていく様はまさに圧巻。各楽器パートはめまぐるしく入れ替わるが、音の組み立て自体が堅実で、アンサンブルの妙を生かし切ったアレンジと躍動感には舌を巻く。パガーニの叙情的なフルートもスタジオ盤より冴えている。西洋音楽の始祖イタリアの豊かな素養と、バックボーンの重みは通り一遍のポップスと侮ってはいけないのだろうが、堅苦しさを感じさせない華麗なエンターテインに目眩ましされてしまう。

Spalax 14923
Picture Music/Klaus Schulze
制作録音は2作目『Cyborg』と3作目『Black Dance』の間だが、当時の本国ドイツでは未発表で、フランスでのみ発表された。ドイツでは評価を確立した『Timewind』以後の76年リリース。ドイツ経由で情報が入っていた当時の日本では存在すら知られていなかった。A面・B面共23分越えの各1曲。様々なジャケ違いが存在するが、これがオリジナルLPと同じと云われるSpalaxの再発デジパック盤。ジャケ絵はダリ風のスュルレアル市松空間に穿たれたドア、天井にぶら下がるベルメール風関節人體。
A面「Totem」では、当人(シュルツェは本来ドラムズ奏者)による生ドラムとシンセの掛け合い、B面「Mental Door」のアナログ・シーケンサをバックにしたリリカルで調性に則ったメロディの絡み等、ミニマム音楽の手法導入と後のテクノ・トランス的なグルーブ感を併せ持つ抑揚のある展開が特徴。曲調は概ね美麗で流麗。音圧と執拗なループでグイグイ押してくるようなシーンはない。変調オケや声楽といった古典的ギミックへの拘りが薄く、異様・或いは破滅的なまでの冷涼さに拘った前後作の硬質でクールな精神世界のイメージと大きく異なる辺りがお蔵入りだった理由と思われる。次作『Timewind』にて、両者の統合が計られて、シリアスで辛気臭いテーマを固定音を持たない電子楽器群のみが奏でるという、黎明期の画期的なスタイルが完成することになる。

EG Records
VJCP-2308
Discipline/King Crimson
青、黄と続く三部作という形式を踏襲し、80年代冒頭、唐突に再編された第二期クリムゾンは『訓練』で幕を開ける。ベース他にレヴィン(Tony Revin)、イフェクト・ギターとヴォーカルにトーキング・ヘッズ(Talking Heads)のエイドリアン・ブリュー(Adrian Belew)という布陣。パーカッションは第一期のブルフォード(Bill Bruford)がそのまま採用されている。81年にリアルタイムで聴いた段階では物議を醸した世評と同じくピンと来なかったが、聴く耳がすっかり枯れてようやく追いついた今となっては全く平気。道化としての役割を担うブリューの脳天気な声や派手なイフェクトも、むしろ心地良いレベル。30年以上前に、ここまで出来てしまったことには改めて恐れ入る次第。
総体的な質の高さは構成員の資質からして文句のつけようがない出来栄えだが、むろん、驚嘆かつ平伏すべきは統率者にして尊師フリップ(Robert Fripp)の、完璧な理性と抑制の下で、有り得ないフレーズを弾きまくる、(弾きたいかどうかは別にして)誰にも弾けないギターであろう。表題曲「Discipline」における間奏部のツイン・ギター一拍ずらしなんて神業に近いアンサンブルで、ブリューは相当辛かっただろう。全7曲、最長でも8分ちょっとというコンパクトに切り詰められた楽曲は、ポップ・ロックの範疇にあって先鋭と円熟、或いはサービス精神のバランスの良さが際立つ。