
Constellation
CST009
He has left us alone but shafts of light sometimes grace the corners of our rooms.../A Silver Mt. Zion
未だに詳細は皆目知らず予備知識ゼロで、数年前知人から借りて聞いて以来、病み付きになっているSilver Mt. Zion(以下SMZ)。基本的にはカナダのGodspeed You! Black Emperor(略してGY!BE)なる、まるで前世紀の滑稽モノ、珍走団を思わせる名前の企画型大楽団の内の3人(Efrim Menuck, Thierry Amar, Sophie Trudeau)が主宰するトリオで製作されたSMZの1stアルバム。本作は頭にA、2nd以降はTheeが付いて、構成員が拡充されるにつれ付加される名前も長くなるが、中身は基本的に同一の模様。Zionは“シオンの丘”を指すのか、カナダに実在する同名の山を指すのか不明。タイトルは直訳すれば『彼は私たちを残し一人逝ってしまったが、一筋の光がときおり部屋の片隅を照らし出す……』(厳密には複数の光条が複数の隅をであるが)と、長い。
ピアノ、ヴァイオリン、コントラバスといった室内楽編成に、サンプリング、テープ・コラージュ、ループを加味しフォークとアンビエントが入り混じった微妙な地平に構築されたあまりにも静謐な諦めと沈痛なレクイエム。アンサンブルというには程遠い音の薄さが殊更に空疎と虚無を描き出す。完成度は2作目以降に譲るが、剥き出しのエッセンスはあくまでも美しく儚い。純粋耽美とは若干趣が異なり、ヒリヒリするような乾きが痛々しいまでの残夢を奏でる。昨今では出色の出来だろう。若干の呟きのような歌入り。主宰者Efrimの恐らく死んでしまった飼い犬のWandaに奉げられている。

Rhino R2 72226
Trilogy/Emerson Lake & Palmer
ライブ『展覧会の絵』を含めれば4作目。ダイナミックではあるが荒っぽい2作目『Tarkus』の欠点がほぼすべて修正されたE.L&Pといえばよいか。体育会的で破天荒な劇場ダイナミズムや無理矢理アクロバットに内包される趣味の悪さに眉をひそめてしまう人間にとっては『1st』の次に好みである。総体としての完成度は次作に譲るが、緻密なアレンジと比較的抑制が利いた全9曲。レイクのアコギと歌の出番が多く、エマーソンも硬質で音符が尖った結晶のようなスタンウェイ・ピアノの演奏を多く聞かせてくれる。前半は小組曲を筆頭に歌入りの小品がメイン。きちっと締まった緊張感とレイクの演歌で抑揚を付けて、段々ズブズブに成っていくのはいつものパターン。後半はエマーソンのクラシック趣味を髣髴とさせる2組曲+繋ぎ小品という構成で緻密なアレンジにのったメロディが印象的である。よくセルフ・コントロールされた鍵盤トリオとしての典型的な曲作りであるが、テクをひけらかせばひけらかすほど、サーカスの珍獣ショーになってしまうあたりは宿命なのだろうか。
ライブでも頻繁に演奏された「Hoedown」はコープランド(Aaron Copland:1900-1990)のバレエ音楽「Rodeo」のカヴァー・アレンジ曲。エンジニアは6人目のイエスとも言われたオフォード(Eddie Offord)。所有盤は2000年ごろのライノ・リマスター再発盤。

Elkarlanean
KD-58
Musikaz blai/Itoiz
前作『Alkolea』で既にその萌芽は感じられたが、カルロス・ペレスと鍵盤以外の構成員が入れ替わってリズムが弾けだしたバスク・イトイスの4作目。プログ趣味の粋人からは呆気に取られた全9曲であるが、タイトにこなれたリズムと電子鍵盤を多用したよく練られたアレンジに、甘々ななかにも微妙な渋さを湛えたカルロス・ペレスの歌が映える。彼の歌のそこはかとない湿り気と淡々としながらも熱っぽい絶妙なトーンが特有のバスク臭を醸し出すが、アンサンブルはカラッと晴れた突き抜けた感触を呈し、以前とは若干趣の違う独特の抒情を余すところなく表現している。フォーク調の民俗色は薄れたものの、曲はこなれメロディはコンパクトで以前にも増して親密性を増した。アップテンポでベースがぐいぐい前に出てくる曲が多く、一聴して意識的な転換を感じさせるが、フォーク色、ジャズ色、ポップロック色を取り混ぜて、バスク・ポップとでも言うべき方向への転機となったように思える。
これまた以前とは大きく趣の異なるジャケは、締めた鶏をぶら下げたペレスと日光浴の水着女性二人。光と影の強いコントラストと乾いた空気感が伝わる。タイトルは『音楽浸り』というような意味だと思うが、相変わらずよくわからん。歌詞はすべてスペイン語訳とフランス語訳付きでとても親切。

E.G.Records
0777 7 87189 2 5
Music for films/Eno
『映画音楽』と題されてはいるが、各種映像作品のサウンドトラック用に作られたものや、他の目的で作られたがサウンドトラック用に使えそうなもの、あるいは(ほとんどは)蔵で埃をかぶっていた過去数年に渡る未発表作を寄せ集めたコンピレーション小品集であるとイーノ自身の解説が載っている。つまり、具体的に何らかの映像作品に採用されたというわけではないらしい。1分から4分ほどの全18曲、すべてインスト。儚げなメロディが秀逸な曲が大半で、視覚を喚起する音であると同時に極めて抒情的である。クラスター風のリズムや叙景的な曲題など、方向性はアンビエントを向いているのだろうが先鋭感を感じさせない作りで、個人的には折衷的で、極めて耳あたり良く気持の良い音像のように思う。豪華なゲスト陣も出しゃばることなく、薄暮のような一定の透明感と色彩感で綴られた均質な音のスケッチ。アンプの電源を入れるといつの間にか聞こえてきて、何かしているうちに聞いていること自体を忘れ、気がつくといつの間にか終わっている。
70年代後期以降のイーノに関しては、意識的に聴くことはなく、断片的に、そこにあるモノをそこにあるときに聞こえてくるものを聞いているだけである。凡そ主体性を持った行為として聴いてはいないので、『空港用音楽』や本作の続編も、そのうちどこかから聞こえてくるまで、意識的に聴くことはないだろう。ということで、いいんですよね?

ECM
1000 1779926
(2008)
Rypdal, Terje+Miroslav Vitous+Jack Dejohnette/same
ひんやりとした暗い夏の情景、全インスト6曲。叙景的でクールな極超耽美アンビエント・前衛ジャス。ロック的な要素も皆無ではないが、グルーヴ感とは隔絶された艶やかさと軽やかさは現代音楽の一範疇と捉えたほうがしっくりくる。ECMだから領域的にはジャズなのだろうが、ギター・ベース・ドラムによる即興の応酬と適度に使われている電子鍵盤やギター・シンセ類が青白い空間を押し広げ、不可逆的に拡散していく。ノルウェイ人ギター奏者、テリイェ・リプダル(Terje Rypdal)のリーダー・アルバムという体裁になるのだろうが、その道の第一人者たちによるトリオ1作目ということで極めて聴き応えのある内容になっている。リプダルのサステインが掛かったヴァイオリンのようなギターに絡むのは、元ウェザーリポート(Weather Report)のチェコ人ベース奏者、ミロスラフ・ヴィトウス(Miroslav Vitous)と、高速で精緻でいながら、あくまでもしなやかなドラム奏者、ジャック・ディジョネット(Jack Dejohnette)。
78年録音、79年リリース、2008年のECM音源。廉価再発仕様と思われるデジパックと同じ大きさの紙ジャケ。CDは極めて無造作にペーパースリーブのポケットに剥き出しで突っ込んであるというのがあちら製のお約束。もちろん聴くことには何ら支障がない。

Fünf und vierzig 02
In the night/Dunkelziffer
70年代中期、CAN絶頂期に突如失踪したダモ鈴木が10年の沈黙を破り、これまた唐突に復活して方向性が変化したドゥンケルツィッファーの2ndアルバム。冒頭とラストに13分と10分超えの長尺サイケ・ガレージ・トランスを配置するものの、中間は2~5分の日本語ポップ歌謡といった趣で非常にこなれて聞き易い。CANダモ期の前衛呪術風味というよりは後期CANのエスニック・ポップ色全開で、目新しさは感じられないものの明るく健康的ですらあるかもしれない。やっていることは70年代の延長線上だが、ノイエ・ドイッチェ・ヴェレの興隆と共にようやく時代が追いついたといった風情だろう。
エレクトロニクスもこなれ、特徴であるリズムも整理されてコンパクトに心地良く決まっている。ダモの御声は相変わらずのヘロヘロだが、ずいぶんと上手くなった。ちゃんちきおけさのような腑抜けた音頭で「きみのことなど~、どうでもいい。Sunday Morning~」と、和製英語の発音でどうでもよさげに歌う姿は誇らしげですらある。全7曲。所有CDは97年の再発。
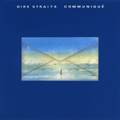
Vertigo
800 052-2
Communiqué/Dire Straits
1stのインパクトがあまりにも強すぎて、ほとんど話題にすらならなかったように思う二作目。個人的にも狭視野で目的以外のすべてを捨象した生活を余儀なくされていた時季で、2ndが出たことすら知らずに再びダイア・ストレイツに興味が回帰したのは85年のAVブームでプロモ・ヴィデオ花盛りの5作目『Brothers in arms』であったと記憶している。
基本はノップラー(Mark Knopfler)兄のワンマン。ストラトキャスターのお手本のような透明感が際立つシングルトーン、だみ声のオッサン歌を支える弟ノップラー他のシンプルでかっちりとしたアンサンブルという基本線は1stから変化はない。16ビートのハイテンポな格好良さを全面に出した1stに比べ、くったりとメローなスローテンポのブルーズ・ロック基調で、微妙な哀感と社会ネタを謳いあげる大人のロックといった風情か。地味ではあるがキレのある心地良さは初夏を思わせる空気感を髣髴とさせて極めて気持良い。表立って評価されることは稀だが、陳腐化しないとても良いバンドの一つ。1stに比べると録音も良い(金を掛けられた)のだろうが、96年の再発リマスターは極めて透明度のよい音質で、音が前に出て臨場感溢れる。

Warner Bros.
8122-73883-2
Tusk/Fleetwood Mac
盛者必衰のマック、一躍メジャーに伸し上がった70年代後期三部作のラスト。大輪の花として開花したニックス(Stevie Nicks)に袖にされた盛期マックの音楽面での立役者にしてギター奏者、バッキンガム(Lindsay Buckingham)が9曲を書き、5曲を成長したニックスが書く。残りはベースの旦那を見限って離婚した女マックヴィーが6曲を書くという、みんなヤリタイことがあるし、LP2枚組みにしちゃえば? と、もうグズグズ状態ではあるが、才女マックヴィーは少なくともバッキンガムの才能に惚れているし、ニックスはただの可愛い子ちゃん歌手にあらず、どうしてなかなか優れた作曲者としての片鱗も窺える。
アルバム・タイトルは『牙』の意で、前作『噂』から2年半ぶりのリリースだが、牙を抜かれた虎のように、持ち寄った20曲をちゃちゃっと仕上げたような極めて素っ気なくプロフェッショナルな味わいが全編を覆う集大成のようなもの。もっとも、手を抜いているという馬鹿売れ後のよくある方向性ではなくて、プロデュースに加えエンジニアにも名前を連ねているバッキンガムによって、単なるポップアルバムの領域を超えた極めて凝った、慎重で繊細なまでの音作りが為されている。クールなブルーズ・ポップの女マックヴィー、小悪魔的でかったるそうな倦怠感を漂わせたバラードが真骨頂のニックスの楽曲は質高くまとまっている一方、 洗練されたポップロックの範疇に留まらないカントリー色やエスニックへの傾倒をもって、新たな方向性を切り開こうとアクの強さを発揮するバッキンガムの貢献も目を見張る。
所有盤は21曲77分というデモとアウトテイク満載で2CDになった2004年のライノ・リマスター再発の2版目。「Sara」は時間的制約があった以前のCDとは異なって、6:26版のフル・ヴァージョンが収録されている。左右のセパレイション、音の分解能ともに良好。音圧も丁寧に抑えられてレンジいっぱいでクリアとオリジナルの意図をきっちり反映した素晴らしいリマスター。輪郭が妖しく色付いてすらいるヴォーカル、鮮明で新鮮なアコギ、弾けるリズムと言うことなし。

Columbia
COL 466421 2
Suddance/Osanna
70年代中期、チッタ・フロンターレ(Citta Frontale)とウーノ(Uno)に分裂、ウーノはイギリスに渡りノヴァ(Nova)と改名して、ジャズ・ロック・フュージョンするが、啼かず飛ばずで飯すら満足に食えずに嫌気が差したルスティーチ兄(Danilo Rustici)はさっさと退却。ナポリに戻ってオザンナを再編したものの、時代の趨勢は既にここにあらずで、本作が実質的なラストアルバムとなった。オザンナの象徴ともいえる管楽器奏者エリオ・ダンナ(Elio d'Anna)と、元チェルヴェロ(Cervello)のルスティーチ弟はイギリスに置き去りということで不在。
曲調は高速ジャズ・ロックを基調に、チッタ・フロンターレ組の民俗色がそこはかとなく薫るといった按配のものが目立つ。ほの暗く猥雑でシュールな土俗色は面影もなく払拭されたが、イギリス仕込みの洗練と民族歌曲のバランスが非常に巧みで、テクニカルで質高くまとまったナポリ賛歌になっている。時代に合致したコンパクトな歌曲と簡潔な構成は賞賛されるべきであって、混沌と構築が危ういバランスで拮抗し両立したかつての悪夢型抒情プログの趣を求めてはいけないのだろう。一本調子になりがちだが、のびのびと歌うヴァイレッティ(Lino Vairetti)の歌も気持ち良い。タイトルは仏語・伊語のSud=“南”を接頭した合成語だろう。
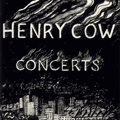
ESD 80822/832
1995
Concerts/Henry Cow
ヘンリィ・カウ(以下HC)の頂点とも云える76年の2枚組ライブ。アナログLPリリース時は1枚目が作曲もので2枚目が即興でまとめられていたが、95年、ようやくCD化されたものは大幅に拡充されて、追加音源が限界まで収録されている。収録時期は『靴下三部作』の73~75年ということで、ベースのグリーブズ(John Greaves:以下JG)とダグマーが重なっている時期。JGはHCでは政治的に浮いたのかもしれないが、非常に理知的でかつ上手い人であり、後にナショナル・ヘルス(National Health)に加わるが、洒脱なインプロに走り過ぎて、アレンジ中心のヘルスとは袂を分かつことになる。 総体として極めて緻密、かつ緊張感に溢れた演奏で、曲自体が非常に良く考えられて作られているだけではなく、それを従来の手法とは隔絶された独自性を持って実践したという意味で、現代音楽の新しい一歩を踏み出していると云えるだろう。
旧LP-A面は約23分のメドレー。「Beautiful as the Moon;Terrible as an Army with the Banners(月のように美しく;旗を掲げた軍隊のように恐ろしく)」を冒頭と締めに配し、中間に「鼠のための涅槃」「オタワの歌」、ダグマーがマッチング・モール(Matching Mole)の「Gloria Gloom(翳りゆく光輪、あるいはミサ曲の“栄光の賛歌”を皮肉ったもの)」を歌うという、75年のBBCライブ。録音も良く、ダグマーの歌には凄みすら感ずる素晴らしい出来。後半はスラップ・ハピー(Slapp Happy)とのジョイント・アルバム『Desperate Straights』に含まれる「Bad Alchemy(偽錬金術)」、ロバート・ワイアット(Robert Wyatt)が加わって、「赤ロビンフッド」をダグマーとデュエットするというレア・アイテムに研ぎ澄まされた現代楽曲「Ruins(破壊)」、最後の2曲はLP-D面の即興インスト曲で、LPとは収録の割り振りが変わっている。
2枚目はLP-C面とD面の一部曲に、CD化に際して追加された73年頃、ダグマー以前のインプロのライブ集の音源で構成されている。即興といってもジャズやロック、クラシックの要素はほぼ完膚なまでに破壊され尽くし、極めて現代音楽的な手法で再構築された音の九十九織り。真面目に聴くとけっこう面白いと思うのだが、一般性は皆無だな。決して日和見に堕ちない、息苦しいまでの強固で明晰な意志を心底から賞賛しよう。
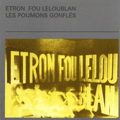
GAZUL
GA 8661.AR
Les Poumons Gonflés/Etron Fou Leloublan
フランス南東部、スイス・イタリア国境に近いグルノーブルのレコメン大道ちんどん、エトロン・フー・ルルーブラン(以下EFL)の3作目。エトロン(étron)は“糞”、フー(fou)は“狂った”、ルルーブランは“Le Loup Blanc”の短縮形だそうで“白狼”を意味する。概ね“いかれポンチ白狼”とでも取ればよいのだろうが、これといった情報もなく詳しいことはわからない。EFLは70年代中期からマグマ周辺のズール(Zeuhl)派生としてアヴァン・ガルド領域で活動していた模様だが、管楽器+バス+太鼓という当初のちんどんトリオに本作から女性鍵盤が加わって、奇矯でキッチュなスカスカの高速アンサンブルに奥ゆかしい広がりと緻密な華やかさが加味された。けったいなリズム、饒舌で演劇的な歌、ボードレールの引用、唐突に挿入される親密で懐かしいジンタ、全体を覆うダダイスム(Dadaïsme)等々、非常にテクニカルだが、敢えて崩した洒脱と崩壊感の妙を愉しむ極めて大陸的でクールな諧謔の至福。切れ味のよいセンスがお見事な全10曲。レコメンの親分、カウのフレッド・フリス(Fred Frith)が2曲に参加の上、後見役として控える。タイトルは『膨張した肺』、あるいは転じて『胸いっぱい』という意図と思われる。

ADD
CD LLL 117
La Petite Bouteille de Linge/Greaves, John
ヘンリィ・カウ(Henry Cow)からヘルス(National Health)へと渡り歩き、同じくCowをお払い箱になったブレグヴァド(Peter Blegvad)等とつるんだ後の、ポップからジャズ、現代音楽の領域までをひっくるめたグリーブズの膨大な音楽作品のほんの一面であり一部としてのアルバム。本作はドラムの元同僚ピップ・パイル(Pip Pyle)以外はフランス人脈を駆使した大陸風のネオ・クラシック、ジャズ色が濃厚で、劇曲からジプシー、スウィング、ビッグバンド、シャンソン、カンタベリ・ジャズ・ロック、大道ブラスバンド等々、非常にヴァラエティに富んだ楽曲によって構成される。製作はパリという大都市の伝統音楽ともいえる、猥雑で決して上品とはいえない下町の大衆音楽、パリ・ミュゼット(Paris Musette)を率いるパトリック・タンダン(Patrick Tandin)。グリーブズの陽気で惚けたキャラクターは年相応に相変わらずだが、、無頼な偽悪趣味は若干アクが薄れたか。それでいて、緻密で繊細、軽妙で洒脱。ふわりと紛れ込む密やかなメロディはジョゼフ・ラカイユのソロに似た感触も感ずる。テクは元々定評があるが、歌もこなれて上手い。さすがエリート。一部の歌詞はフランス語だがシャンソンの発音も付け焼刃でなく、それなりにちゃんと聞ける。
ベースだけでなく一通り何でもこなせる人だから、5曲目「Rose c'est la vie」などというピアノの弾き語りとゲストのヴァイオリンによるバラードなんぞも枯れた中年のいい味わいを醸し出している。タイトルは『洗濯の小瓶』の意だが、意味はわかりそうでわからん。

Brilliant Classics
99748
Lyrische Stücke/Grieg, Edvard Hagerup//Håkon Austbø
エドヴァルド・グリーグ(1843-1907)の抒情小曲集、全10巻、計66曲をまとめた3CD廉価全集。1867年から1903年に至る37年間に渡り書き続けられた、決して大仰ではなく、北欧らしい明るさと清潔感、清涼感に溢れた数分単位の小体さの連なり。半分弱はどこかで耳にしたことがあるような親密さが心地良い。グリーグはノルウェイの民俗音楽を普遍化した近代音楽の作曲家。ピアノ奏者としても卓越した才能を発揮した。義務教育上有名なのはイプセンの戯曲『ペール・ギュント(Opus23)』の劇音楽とピアノ協奏曲(Opus16)といわれる。
第1集の最初の曲「アリエッタ」は37年後のラスト第10集の最後の曲「思い出」で再び同じテーマが奏でられ、ウロボロスの如くきれいに輪が閉じる。個人的には後期の作品ほど、華麗にして繊細な美しさに満ちて好みに適う。現代の北欧ものに通ずる呆気カランとした衒いの無さや、近代的な辛気臭い思想性を卓越したある種の諦観とイノセンスは時代を越える純粋性を持ち合わせているのだろう。奏者は近代ものでは定評があるデンマーク人、ホーコン・アウストボ(Håkon Austbø)。2001年の録音。

Virgin/EG
EEGCD 38
Broadcasting from home/Penguin Cafe Orchestra
アンビエント勃興期、国内的には浮かれたバブルな世相にするりと浸透して、ポスト・モダンな商業主義的文化啓蒙を隠れ蓑に一世を風靡したペンギン・カフェ合奏団(以下PCO)のアルバム3作目。イーノによるアンビエント・レーベル、オブスキュア(Obsqure)の出身。PCOは既に故人であるマルチ奏者サイモン・ジェフス(Simon Jeffes)を創始者とした不定な構成で、80年代初頭はテクノの被り物を脱いだ坂本龍一近辺とのコラボでも大いに名前を売っていた。
全12曲の小品集。全曲インスト。古典音楽としての室内楽を基礎に、ミニマルとフォークロアの結合を計り、純粋アンビエントというよりは、何らかの主題を仄めかし微妙な郷愁を誘う手法は、斬新でありながら決して行き過ぎることはない英国的プラグマティズムと中産階級的な教養を規範として、丁寧かつ慎重に折衷されたもの。穏やかで親密なメロディと緩いリズムは英国滋味を湛えながらもイーノ的手法、あるいは南イングランドの優雅な刹那と田園的な心象風景の下で新しい時代の夜明けを演出する。ゲストのジェフリィ・リチャードソン(Geoffrey Richardson of Caravan)のピチカート・ヴィオラ、ステーヴ・ナイ(Steve Nye)のピアノあたりは鮮烈さを増して印象的。11曲目のドラムはマイケル・ジャイルズ(Mike Gilesと表記)なのだろうな。

ReR LC-02677
2003
Winter Songs/Art Bears
79年初聴。寄る辺の無さと無窮の崩壊感に例えようのない親密さを感じた。凍てついた金属に素手で触れてしまったような、ひりひりするような痛みが未だに癒えない研ぎ澄まされた極北。鋼のように強靭で、あらゆる妥協と予定調和を排した音楽の果て。創造行為の行きつくところ。あまりにも素っ気無く、無駄を削ぎ落とされたコアだけが剥き出しで投げ出されている。“恐れ(畏怖)”に近い。
隠者(The Hermit)
隠者は座る
火を前にして
魚を焼く
フォークに刺して
その手が持ち上げられて
みぞれを受け、陽を浴びる
その靴は脱げ落ちて
忘却
時は過ぎ
粉雪が
夏空に
ヘンリー・カウにおけるダグマー歌モノの発展系アート・ベアーズの全3作中2作目。フリス+カトラー+ダグマーのトリオ編成。ぎりぎりと軋みながら廻る車輪の如く、常に壊れていることを宿命付けられた重いリズムと不協和音に彩られた現代音楽の傑作の一つ。カトラーの歌詞が極左思想的終末論を基底にアミアンの大聖堂の彫刻をモチーフにして想起したもので、暗黒中世的に瘴気迫るダグマーのヴォーカルに身の毛がざわざわと総毛立つ。現在の所有盤は『Art Box』といわれる再発リマスター6CDセット。残りもおいおい。
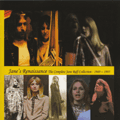
Renaissance Records
RMED-384
Jane's Renaissance 1969-1995/Relf, Jane
第1期ルネサンスの歌手としてその筋では著名なジェイン・レルフの完全集。18曲+14曲+ボーナス1曲の2CD。ジェイン・レルフが歌う、69-70年の第1期ルネサンス、76-79年のIllusion、86-95年のStairway時代のすべての音源が収められている。ジェイン・レルフは60年代のブルーズ・ロックの立役者ヤードバーズの歌手にして夭折したキース・レルフ(Keith Relf)の実妹。ヤードバーズがジミー・ペイジ(後のZep)に乗っ取られて以後、脱退した兄レルフとドラムのマカーティ(James McCarty)の人脈の中でそれなりのキャリアを積み、2009年現在、既に引退したと思われる。素人臭いが包容力のあるしっとりとした声質が後々、卓越したソプラノで一世を風靡したルネサンス第2期の歌手アニー・ハスラム(Annie Haslam)との対比で語られていくことになる。ポップス歌手というよりはイングランド・トラッド+クラシカルなバラードあるいは時代がかった演歌ポップスを得意とし、英国の滋味を体現するようなそこはかとなく、くぐもった声質と、彼女の歌に合わせた後見人マカーティ他の類稀な曲作りセンスが鈍く光る。ハスラムとは比較にならないほど地味な存在だが、ある意味ここまで根強い隠れ人気があるのは、もちろん彼女が美人だったからに他ならない。
衆目を集めるに相応しいのはやはり名曲「Face of Yesterday」だろう。蕩けそうなアルトが押し付けがましさの微塵もなくしっとりと響く。71年と77年の両ヴァージョンが収められている。ボーナスはジェインが歌う2期ルネサンスの「Carpet of the Sun」というわけで、これもなかなか興味深い。集大成ということで、一応リマスターされているが、正規版からデモテイクまで音質はバラバラ。2001年のマカーティ主導の再結成アルバム『Renaissance Illusion』は含まれていない。