
Swan Song
20P2-2028
Presence/Led Zeppelin
鳴り物入りで登場した7作目。ずっこけ気味の世相のなかで、タイトル通り極めて確固たる力強さと明晰なまでの論理性に貫かれたアルバムでもあった。2LPだった前作『Physical Graffiti』の2枚目は従前のアウトテイク集だったので、実質前作1枚目ラストの「Kashmir(カシミール:インド・パキスタン国境の紛争地帯。実際にはモロッコの情景に触発されて書かれた模様)」に続くのが、10分に及ぶ「Achilles Last Stand(アキレスはもちろんギリシャ神話の男神アキレウス)」ということになる。全7曲。ラストの長尺ブルーズを除いて、硬質でマッシブなエッセンスだけが抽出されたような乾燥気味の音作りが、スパスパと躊躇いなく夾雑物を削ぎ落としていく様は痛快ですらある。個人的にはJPJの鍵盤が聞けないのはちょっと残念。
Zepの偉大さは(どれも水準を遥かに越えてはいるが)テクニックでもなく、美メロがあるわけでもなく、外面が良いわけでもなく、ただ、モード(旋法)的な『構築』と全体構成のバランスの妙にある。それらはそのまま、ペイジのギター奏者としての才覚とJPJのアレンジャーとしての才能に端的に起因しているわけで、70年代中期の数枚のアルバムをもって、西洋古典音楽の地平の上でディープ・パープルやブラック・サバスが到達できなかった一つの頂点に立ったことは間違いないだろう。

Columbia
47359 2
Ian Hunter/Hunter, Ian
モット・ザ・フープルの首領兼ピアノ奏者兼歌手であったイアン・ハンターのモット解散後初ソロ・アルバム。もう60過ぎだと思うが、現在に至るまでそれなりにコンスタントにアルバム・リリースは為されている模様で、最近はもっぱらプロデューサ業に勤しんでいる様子。内容的にはMOTT末期の歌物R&Rバラード路線の延長であり、微妙な哀歓を感じさせる独特の歌唱や歌詞、ちょっとインテリっぽい詩の朗読なんぞもMOTT時代の発展系で、MOTTだといわれてもほとんど違和感は無い。ワイルドぶった破天荒な偽悪趣味も相変わらずだが、歳相応の円熟味が見え隠れするのも事実。性質はまったく異なるが、上述のZEPのロバート・プラントと同様に、伴奏に乗せてその和音から期待されるメロディを歌う歌手ではないがために国内ではあまり好まれないようだが、はまると病み付きになる独特の叙情的趣が気に入っている。
共同プロデュース、アレンジ、作曲、ギター、メロトロンをこなすミック・ロンソン(Mick Ronson:故人)は初期デヴィッド・ボウイ楽団の番頭だった才人。

CBS 460246 2
Romance in the new age/Lundsten, Ralph
スウェーデンの電子音楽家、ラルフ・ランゼン50代の作。何作目かは既に不詳。76年から86年にかけて録音された作品の自選コンピレイションのようなものか。1936年生まれということで旬は60年代から70年代、70年代中期以降は安定期というか、初期のぶっ飛んだエグ味はきれいサッパリ拭われて、タイトル通りロマンティックでメロディアスにニューエイジしております。ゆったりしたリズムとぽよよんとした夢見がちの全インスト12曲。本人が「目を瞑って聴け。良い夢を見よう」というくらい確かにBGMスレスレ、あるいはそのもの。もちろんジャケ買い。
元来は、舞台やバレエ音楽の出身だと思われますが、アンドロメダ・スタジオなる自前のスタジオを構え、電子楽器のみに留まらず、民俗音楽から現代音楽、前衛実験からクリスマス曲集まで、ありとあらゆるジャンルの音楽、あるいは相互ハイブリッドに携わってきた重鎮にして宇宙の伝道師さながらの実践者。北部ゲルマン人特有のロマン主義と、スウェーデンというある種の孤高と恵まれた明るさを髣髴とさせる楽観主義は行き過ぎた諦観の帰結なのかもしれない。

Black Widow
BWRCD 015-2
Curses and Invocations/Standarte
ギターが聞こえなくなって鍵盤トリオになったスタンダルテ2作目。当然のことながら鍵盤の比重が高まって、ピアノ、オルガン、シンセ、メロトロン(サンプリングではなく本物)の唸り方は尋常ではない。組曲もお目見えし、歌物も穏やかに一歩引っ込んだ雰囲気で、耳には優しい70年代プログの90年代的解釈といえよう。心置きなく堪能できるフルート音、ストリングズ音、コーラス音のメロトロン重奏も広漠とした寂寥と慰藉を見事に具現しているし、はっとするような新鮮で切ないフレーズの耽美も抗し難い魅力を秘めている。曲構成や展開も前作に比して遥かにこなれ、無理なくきれいにまとまった。70年代Virtigoのグレイシャスのカバーが一曲含まれる。
純然たるイタリア人トリオはフィレンツェの出。タイトルは『呪いと祈り』。歌詞は全て英語。前作のけっこう気に入っていたアートワークはピヴェッティ(Franco Pivetti)の黙示録シリーズから「読書の天使」なるドローイングに変わっている。これはこれでまた、かなり気に入っている。

1979
3 Violin Concertos, 5 Violin Sonatas, Cello Concerto/Tartini, Giuseppe //I Solistti Veneti
このところ毎日聴いている愛聴盤。ジュゼッペ・タルティーニ(1692-1770)はバロックから古典への端境期のイタリア(生地ピランは現スロヴェニア)の作曲家兼ヴァイオリン奏者。オペラと教会音楽をまったく作らなかった当時としては十分変人であろう。作品の大半はヴァイオリン協奏曲とヴァイオリン・ソナタという具合に徹底している。アルビノーニ、ヴィヴァルディの正統なる嫡子である、たおやかで華麗なメロディと流れるような気持ち良さが同居した弦楽曲は只ひたすら美麗である。ソナタ形式にみられる初期古典様式への取っ掛かりや、奏者の第一人者であることを生かした奏法の開発にも貢献した模様。奏法に関しては門外漢であるが恐ろしく難度の高いテクニックが要求されているようで、非常に情感に満ちた演奏が繰り広げられている。著名なのはソナタであるが、初めて聴いた(いや、どっかで聞いたことのある曲なのだが)協奏曲(特に冒頭D-Moll、D45)の滴るような美しさには正に圧倒された。
テンコ盛りの2CD、76年と79年の録音。2004年のリマスター。演奏はイタリアものでは定番、麗らかで明晰でありながら音のしなり具合が真似のできないのシモーネ(Scimone)指揮のソリスティ・ヴェネティ。ヴァイオリンはAmoyal、ないしはToso。ヴァイオリン協奏曲3曲とチェロ協奏曲、ソナタが5曲で、もっとも著名な「悪魔のトリル」を含む。

Mys CD 114
Shepherd's Symphony/Popol Vuh
ポポル・ヴフの近作。一応スタジオ盤としては最終作に当たるもので、首領であるフロリアン・フリッケ(Florian Fricke)の2001年死去により以後新作は出ないはず。それほどの歳ではないはずだが、その全盛期にリアルタイムで聴き、それなりに感銘を受けてきたものにとっては、なんとも感慨深くも残念なことだ。
アルバム毎に変遷を重ねた音楽性も前作『City Raga』あたりからはワールド・ミュージック色が濃いトランス・テクノといった趣で、かつての崇高なる神秘主義的民俗音楽といった趣向からは想像もつかないものになっている。それを安直な堕落とみるか、斬新な発展とみるかで評価は変わろうが、内容的には概ね良くできていると考えている。コニー・ファイト脱退後はほとんど主導権を握ってきたフリッケに代わって、エンジニアを兼ねるギド・ヒエロニムス(Guido Hieronymus:ギリシャ人?)のクレジット曲があるなど、内部の変遷が音楽性の変化に繋がっていると見ることが妥当だろう。
タイトルは『羊飼いの交響曲』であるが、特に組曲というわけでもなく、全7曲。女声が入る曲もあるがサンプリングと思われる。

HAGAKURE
ISCP-1132
Dance/四人囃子
最近またカルテットで復活? しているようですが、73年? デビューの四人囃子のずいぶん間が空いた、現在のところスタジオ盤6作目にしてラスト・アルバム。前作に引き続き四人囃子というのは名前ばかりのトリオ編成で、ベースの佐久間正英がギターも兼任するという形。まぁ、元が三人官女と五人囃子の中間をいく変則だったわけだからこれで良いのか? 森園以後は内容的にも大きな変遷を遂げ、今作ではデビュー時のプログというよりはテクノ・ファンク色が全開で、そのあたりは佐久間の趣向なのだろう。プロデュースに加え曲も佐久間がほとんど書いている。一般性には欠けたが、いろいろな意味で先進的な役割を果たしてきただけのことはあって、中身は詰まらない迎合や媚がなくてきちんと聴ける高質なものに仕上がっている。ラストの「眠い月」あたりなどのインスト曲も叙景的で気持ちよい。
ちなみに森園期にライブを二度ほど見に行った記憶がある――走馬燈回転中――お値段は国内レベルで中身は外タレ・グレードという歌謡曲やニューミュージック全盛の当時としては、なかなかコスト・パフォーマンスの良いライブでありました。う~ん、あの頃は貪欲によく見に行っていたなぁ。2002年の再発リマスター、紙ジャケ仕様。

DHM
05472 77854 2
Prophetiae Sibyllaum/Lasso, Orlando di //Cantus Cölln+Konrad Junghänel
突然脈絡もなく時代は遡る。表記はイタリア語でオルランド・ディ・ラッソ(1532-1594)、ラテン語でオルランドゥス・ラッスス(Orlandus Lassus)であるが、今風に言えば生まれはベルギー人~死んだときはドイツ人である。ローマのパレストリーナ(Giovanni Pierluigi da Palestrina)と並ぶ後期ルネサンス・フランドル楽派の巨匠であり、ヨーロッパ中で絶大な人気を誇った言葉通り一世を風靡した流行音楽家。世俗歌曲に特に秀で、イタリア滞在中に作曲されたイタリア語世俗歌曲であるマドリガーレは175曲、フランス語世俗歌曲であるシャンソンはコメディから酒場の酒呑み歌まで約150曲が遺されている。上記にミュンヘン定住後のドイツ語リートやラテン語歌曲、宗教声楽曲を加えると作品は2000曲を越える。
12のモテットからなる宗教曲集「シビラの預言(Prophetiae Sibyllarum)21:04」にマドリガーレとシャンソン15曲で全69分越えのテンコ盛り。リュート伴奏が僅かに聞こえる「シビラの預言」を除けば全て四声ポリフォニー、ア・カペラ曲。ソプラノ、アルト、テノール、バスの四声部がそれぞれ独立した旋律とリズムを同時に歌う(歌詞は声部によって言語が違ったり、中身が違う)という典型的なルネサンス音楽であるが、バロックに繋がるダイナミックで感覚的な高揚や情感に訴える要素がそこはかとなく加味されているあたり(平たく云えば奔放なソプラノ、歌詞優先)が一般受けした理由でもあるのだろう。静謐な均衡と調和からマニエリスム指向の奔放と奇矯へ向かう世紀末において、程よく抑制された頽廃とエロスが必然の和声進行、跳ねるようなリズムのもとで艶やかな蕾を開き始めたという情態か。最近の音楽に聞きなれた耳で聞くと予定調和で先が見える古典派音楽(の発展系)とは違った、四つの物語が独自進行しながら一つのクライマックスに突入していくような斬新感が味わえる。
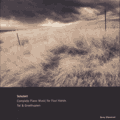
Sony Classical
5 099708 788421
Complete Piano Music for Four Hands/Schubert, Franz //Yaara Tal & Andreas Groethuysen
オーストリアの古典派~ロマン派楽人、フランツ・シューベルト(1797-1828)の四手ピアノ曲全集。7CDボックスセット。シューベルトといえばドイツ歌曲の作曲家として特に著名であるが、これは名前の通り一台のピアノを二人で弾く連弾曲を集めたもの。当時としては最もお手軽な室内楽かつレッスン曲としてそれなりの需要があったらしい。コンサート等では2台のピアノを用いる場合もあるようだが、基本は1台のピアノの高音部と低音部を二人の奏者が弾くもの。動画(適切な例ではないがサン=サーンスのダンス・マカブル)を見る限り、ペダルや、手の重なり、作曲者によっては肩越しなど、スリリングでアクロバットな動きがなかなか面白い。プロの場合は演者が男女デュオの場合が多いようだが、当然視覚的な効果も考えていて微妙に愉しそうだな。シューベルトも音楽教師をしていたどこかの伯爵の娘カロリーネと一緒に弾くために「連弾のための「幻想曲ヘ短調」(通称「カロリーネ幻想曲」)」を作曲献呈しているぐらいだ。
31歳で夭折する楽聖の音楽に関しては、おこがましくてとてもじゃないが語れる言葉を持たない。演者のタール & グレートホイゼンはイスラエル人とドイツ人の男女デュオ。ちょいともったいぶった格調の高さ、冷徹で崇高なまでの透明感、それでいて花のある豊かな情感を併せ持つ楽曲を適切な解釈で弾きこなす。情感の演出がクールで現代的、かなりベタな著名曲も清冽で硬質な透明感を湛えた演奏で印象を新たにするものがある。93~95年の20bitディジタル録音。

Mellow Records
MMP 118
Anno Demoni/Jacula
ヤクラのアウトテイク集。70年代イタリアのユニット、ヤクラは唯一のアルバム『魔法典における末期男色』を75年にリリース後、首領であるバルトチェッティ(Antonio Bartoccetti)の個人プロジェクトであるアントニウス・レクス(Antonius Rex)に移行して現在まで異端宗教風俗物メタルの活動が続いている模様。音源は74年~78年に録音されたもの。基本は微妙に俗物っぽさを拭いきれない1stと同路線。3曲目のみ首領の妻にしてシンセ奏者、ドリス・ノートン(Doris Norton:イギリス人?)による美麗なスキャットをピアノが彩る目から鱗が落ちそうな美曲。ドラム入りはラスト1曲のみで、シンセや教会オルガンのリズムパターンによるどちらかというとアンビエントなアレンジが中心でグルーブ感はほぼ皆無である。
ほぼ全編に渡って鳴り響く、鈴のような金属音と悪魔の舌舐め摺りのようなシンセ音はCD化の際に編集によって挿入されたものだろうが、マス受け狙いのチープさが否めない。タイトルは『魔の年』あるいは『悪霊の年』といった意味か。

Ltmcd 2331
Sound Tracks + Urban Leisure/Tuxedomoon
80年代衒学室内楽タクシードムーンの12作目にあたるコンピ盤。主として映画や舞台用に主要作の合間に録音されたインストEPを集めたもの。オランダの怪奇映画「The Field Of Honour(1983)」、SF映画「Plan Delta(1986)」(共にBob Visser監督)のサウンドトラックに加え、80年アメリカ時代の初音源化「Urban Leisure Project part1-4」、歌詞のないオペラとして作られたオケ入りの「The Ghost Sonata(1982)」にライブが1曲加えられた全12曲、2002年のリマスター。
元来、なかなか捉えどころの難しい(既製の言葉で極めて表現しにくい)TMであるが、本作はボーカル曲が皆無ということで尚更先鋭かつ境界領域的な音作りが為されている。ゆったりとシーケンスするリズムと弦楽器、管楽器、エレクトロニクスのアンサンブルは純粋に室内楽の様相を呈しているし、黄昏たメロディと仄暗く冷湿な触感は耽美と頽廃にどっぷりと漬かりきった甘い腐臭を放っている。叙景的な陰影の深さとその押し付けがましくない、一歩引いた心地良さは天下一品。主に80年代のベルギー移住後の音源ということでパンク色は皆無、というかロック色すら皆無の現代音楽というべきだろう。

Elkar
KD-4008
Itoiz/Itoiz
ベタベタ、ダサダサ、アマアマという三拍子が揃ってしまった、バスク音楽では恐らくもっとも有名なイトイスのもっとも有名な1stアルバム。しかしながら、その甘ったるい声、危なっかしいテクニック、意味不明五里霧中の歌詞という三重苦を乗り越えても尚、例えば、所有音源から10枚アルバムを選べといわれたら確実に選ぶであろう、音楽が本来持っていた瑞々しい“感動”を余すところなく表現しきった、圧倒的なまでの情感に満ち満ちた豊穣な熱さがぎっしりと詰まった正真正銘の「名盤」と呼んでよいだろう。
時間軸でみればバスク音楽の中でも後発にあたるが、そのせいか他のバスク楽団とは異なる特質を備えている。凝った展開とアンサンブルの妙で聞かせる大曲とアコギバックの引き語りの素朴なメロディと叙情的なフルートの絡み合い、上手くはないが魅力に溢れたフアン・カルロス・ペレスのヴォーカルの甘さあたりでも十分な内容だが、それに加え、ちょっとドタバタしているが達者で、小刻みで小回りの利いた意欲的なリズム隊も評価に値する。突き抜けたダイナミックなアンサンブルと泣きまくるメロディの艶やかさも、理性的でクールなバスク音楽の中では殊更異質な部類のように思える。
残念ながらバスク語表記のみの輸入盤が手元にあるだけで、音以外に関してはほぼ皆目見当も付かないのが実情である。イトイスの音楽がその風土と歴史に深い関わりを持っているだろうことは推察されるが、概観的な知識だけで理解が及ぶものではない……。“バスク(Basque)”はフランス語の呼称で、スペイン語では“バスコ (Vasco)”、バスク語では“エウスカディ (Euskadi)”。現スペインに4県、フランスに3県。スペインの西部3県はバスク自治州を構成するが、フランス国境のナファロア県はカスティーリャの影響下にあるらしい。“Itoiz”とは人名にも使われるらしいが、ナファロア(ナヴァラ)県の県都イルーニャ(パンプローナ)東郊の山岳地にあった小さな町の名前かもしれない。検索を掛けるとわかるが、かなりのトラブルの末、現在はダムにより水没(地図⇔航空写真)した模様。
バスクというと縁遠い感があるかもしれないが、実は意外に身近な存在である。例えば、ピカソの絵で著名なゲルニカはビルバオ近郊の都市。また、日本でもっとも有名なバスク人は歴史に名を残したイエズス会のフランシスコ・ザビエル(Francisco de XavierまたはFrancisvo de Gassu y Javier, 1506-1552)だったりする。

Elkar
KD-10105
Hontz gaua/Haizea
77年1stアルバムでデビューしたアイセア(ハイセア)の2作目にしてラスト。現在も活躍する女性歌手アマイア・スビリア(Amaia Zubiria)を擁し、バスクの中では比較的プログ色の濃い前衛サイケ・フォーク。それなりに達者なリズム隊付きの6人編成であり、グレゴリオ聖歌風のア・カペラや、フルート等管楽器の多用はよくあるパターンだが、水音風のシンセSEやパーカッションに代表される凝った音響効果などは他のバスク楽団には殆ど聞かれない珍しいアプローチだろう。味わい深いバスク調のメロディを歌うアマイアの美声の合間、あるいは背景にゆるりと流れる、しっとりと濡れた夜の如きアンサンブルとアンビエント処理は叙景と叙情に優れた描写をみせている。
後半は二部構成14分越えの大曲「Hontz gaua(梟の夜)」。こちらも夢幻と静謐の狭間のようなひっそりと佇む夜の情景。冒頭の聖歌から連綿と展開されるSE、フルートにタブラを重ね……この濃密で湿った感触はクリムゾンの『アイランズ』のチェロの低音弦の感触を髣髴とさせる。裏ジャケの絵が正にイメージ通りなわけだが、孤独な梟は修道者を意味するのだろうか。“Haizea”は「風」の意。
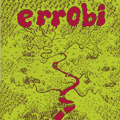
Elkar
KD-15
Errobi/Errobi
イトイス出のフアン・カルロス・ペレスと共に、後に歌手としてバスク音楽のスターダムにのし上がったアンイェ・デュアルデ(Anje Duharde)とフランス・バスク人のミシェル・ドゥカウ(Mixel Ducau)のフォーク・デュオの1stアルバム。デュオではあるが現代詩人ダニエル・ランダルト(Daniel Landart)を作詞者に加えたトリオ編成で、ほぼ全曲、電気ギター、ドラム入り。一部で聞こえるピアノの音色やシンセ? のアレンジも繊細でクール。アンサンブルは荒削りの歌ものフォークとフォーク・ロックの中間で、宗教風男声アカペラなんぞも加えた新機軸も打ち出している。録音は時代なりの音質だが、ジャズ(ファンク)調の饒舌な電気ベースがかなりボコボコ鳴っていて、そこに載る純バスク調の歌や語りとのバランスが醸し出す空気感が非常に新鮮かつ斬新。
ジャズ・ロック色が強まって、花開くのは79年の3作目くらい(ようするにバスク音楽の旬は78~79年ということか?)だが、75年というのはフランコ帝政の終焉とともに王制が復古しバスク語の使用が解禁された年であり、本作がバスクのポップ・ロックとしては最初の記念すべきレコードとなったようだ。クレジット、歌詞は全てバスク語だがブックレットにはフランス語、スペイン語訳付きと親切。“Errobi”とは恐らく「Roots」ないし「Origin」という意味合いを示しているのだろう。

Elkar
KD-10.117
Enbor/Enbor
バスクのエンボルのデビュー・アルバム。ときにはジャズロック風の展開をみせるきっちりとしたアンサンブルとゆったりとたゆとう男女ボーカル、鍵盤、管楽器入りの7人編成のフォーク・ロック。リズム隊がタイトで締まっているので、叙情一辺倒に流れないあたりは同時期のイトイスよりもずっと上手いだろう。安易な比較で語ることは好まないが、うっかりするとイングランド・フォークやカンタベリィ音楽(ハットフィールズやスパイロジャイラを思わせる)と聞き間違えそうな枯れた滋味とセンスは極上の味わい。全7曲、歌詞はバスク語。出自が不明な孤立言語であるバスク語の独特な語感とともに、冷涼でしっとりとした曲調、展開は病み付きになる親密さを兼ね備えている。“Enbor”とは「(木の)幹」の意。
ジャケットは石油精製工場の煙突の間に沈む夕陽。ビスケー湾沿いのバスク地方はスペイン有数の鉄鉱石の産地であると同時に重化学工業地帯で、本来はスペイン国内でも経済的に最も恵まれた地域にあたるが、極度に中央集権的な歴代カスティーリャ政府の統制下にあって少数民族であるが故の辛酸と悲哀を舐め尽してきたという歴史背景がバスクのアイデンティティという形で集約される結果に繋がったのだろう。

Elkar
KD-10.111
Itziar/Itziar
ちょうど同時期のイトイス(Itoiz)の2nd『Ezekiel』にも客演していたバスクの民謡歌手イツィアール・エギレオール(Itziar Egileor)の唯一作と思われる佳作。一応エルカール(Elkar:バスクの民族系レーベル)のWebではポップ・ロックに分類されている。6~7人のリズム隊付フォーク・バンド編成によるものだが、イツィアールが歌う天上の美声だけでなく、男歌手の歌もあり、効果的に使われているひんやりとしたストリング・シンセや臨場感溢れる港風景のSEをバックに、しんみりとしたトラッド・フォーク調からアップ・テンポのジャズ・ロック調まで、叙情的ながらも異種多様な展開が内包されているという点で単なる民謡と捉えるべきではないのだろう。場所柄、スペインではあるもののスペイン色はまったく感じられず、ビスケー湾岸文化圏とでもいうべきか、フランス・バスク、ブルターニュ、果てはウェールズ、アイルランドに跨って残存する、ラテンやゲルマンに駆逐された古の香りが濃厚に漂う。歌詞、クレジット他はすべてバスク語。
個々の曲の出来もよく、この手のものには珍しくテクニックも上々で素人臭さは感じられない。一方で、プロデュースが甘くアルバムとしては散漫な印象も否めない点で大きく損をしているが、それもまた素朴な田舎風味の発現というべきなのだろう。しっとりとした夜の手触り感が妖しくも心地良い。ドラムは同じバスクの楽団エンボルの人(Enbor:Javi Robador)。