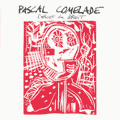
Les Disques du Soleil et de l'Ancier
7243 8459692 7
L'argot du bruit/Comelade, Pascal
玩具の楽器を使って楽曲を演奏する、トイ・ポップの元祖パスカル・コムラードの中期の作と思われるが資料が少なくて全容がはっきりしない。かなり多作でリリース量も半端ではないが、当然の如くほとんど入手できない。内容はミニマル領域にあってアヴァン・ガルドの範疇にあることは間違いないが、表出される伝統的で素朴な、あまりにも可愛らしい音楽はラテン大道芸と減算の美学の合の子のようにノスタルジックで物悲しい。玩具楽器を使いながらもチープでもキッチュでもなく、あくまで極上のセンスを感じさせる曲作り、惚けたアレンジが素晴らしい。
70年代中期から音楽活動を始め、80年代中期から頭角を現したようだが、当初はエレクトロニクス寄りの実験室内楽であったという噂。ZNRみたいなもんかね? 根底に近しい雰囲気を感ずる。極めて多芸かつ有能なフランス在住のカタロニア人。タイトルは『噂の言葉(今評判の言い回し)』の意。男女ゲストによる歌入りが3曲あるが原則はインスト曲。冒頭から3曲目は耳を疑うファウストの「The Sad Skinhead」。歌とギターは正真正銘のペロン(Jean-Hervé Peron)。タマゲタ。

Rhino
R2 73349
Seventeen Seconds/Cure
鍵盤が加わりカルテットになったセカンド・アルバム。初期キュアの原型ともいえる研ぎ澄まされた空気感が横溢する次作『Faith』に劣らぬ良作。ジャケ通りの薄ら寒い冷涼感と切り込むような刹那感が秀逸。気持ちよい。カリカリするような繊細な感性と斜に構えた視線が80年代初頭の閉塞一辺倒の時代性を象徴する。ちょっと意外な気がするが、10曲中2曲がインスト、他曲もあまり歌詞の比重が重くない。ミニマルなリズムパターンなども時代を反映したものではあるが、けっこう先見性はあったように思う。ヴィジュアル・イメージを伴ってそれなりにブレイクするのは80年代後半に入ってからだが、「A Forest」などその後の20年通しでキュアを代表する曲を含む。個人的にロバート・スミスが前に出すぎたキッチュかつ豪奢なものは苦手で、キュアはクールなアンサンブルが真骨頂と考える。

Virgin
7243 8 41650 2 4
The Miller's tale/Verlaine, Tom
全然パンクじゃなかった(笑)ニューヨーク・パンクの雄、というか伝説あるいは偶像だったテレヴィジョン。その首領は現代のヴェルレーヌを名乗っていたが、結局のところ、トーマス・ミラー(Thomas Miller)というのが本名なのでしょう。長らく新作も出ないし、たまにライブに出ているような話は風の便りに聞くが、恐らく集大成的アンソロジーとなったライブ+スタジオ・コンピ別テイク集の2CD。と思ったら去年(2006年)個人名義では16年ぶりに新作が出ている模様。
前半10曲は1982年ロンドンでのライブ。きっちりと構築された極めて緻密な演奏が、10分越えの長曲も飄々としていながらも息をつかせぬ緊張感で聞かせる。観客ノイズもリアルに録られているが、ライブ・アルバム『Blow Up』とはまた違った、クールに洗練された一面を聴かせてくれる。後半は18曲中6曲が未発表。
さて、このイギリスかぶれ(評価もイギリスで圧倒的)の男のことだから、タイトルが単なる自分の名前とは思えないのである。中世英詩人チョーサー(Geoffrey Chaucer:1343?-1400)の大作『カンタベリ物語』の教訓挿話「Miller's Tale」を引っ掛けているに違いない。ちなみに“Miller”は一般名詞だと製粉屋(風車を動力とし臼を廻して麦を粉にした)で、英語としては巧みに分量を誤魔化すインチキ野郎というイメージがあるらしいが、どちらかというとこの業界には珍しい筋を通す潔さと、クールな賢さばかりが目立っているように思う。

Concerto Royale
206201-360
Brandenburgisches Konzerte/J.S.Bach
いわゆる『ブランデンブルク協奏曲(BWV1046-1051)』に『管弦楽組曲(BWV1066-1069)』を組み合わせた爆安廉価3CD。彗星のように登場したレーベルは、脱兎のごとく売り逃げを図り現在既に入手が難しい。演奏者は聞いたこともない室内オケだが、現代楽器による演奏は悪くはない…というかなかなか良い。どこかの音源をパクったか、ゴーストかもしれない(笑)。最近の録音ではないだろうが、比較的音質も良い。
全6曲からなる『ブランデンブルク協奏曲』は1721年、ブランデンブルク辺境伯クリスティアン・ルートヴィヒに(就職活動の口添えのため)献呈されたことからこの名がついている。ブランデンブルクは略称BRB: ブランデンブルク・アン・デア・ハーフェル (Brandenburg an der Havel)でブランデンブルク大聖堂のあるベルリン西郊の都市。バッハの協奏曲のなかでももっとも著名だと思われる計2時間弱のボリューム。バロック期の合奏協奏曲仕様が基本だが、3番の弦楽、5番のチェンバロの扱いは後の古典派時代の特定の楽器をフィーチュアする協奏曲の原型になった。特に5番ではフルート、ヴァイオリン、チェンバロを独奏楽器として用い、通常は通奏低音楽器のチェンバロを独奏楽器群に加えること自体が独創的だが、更に長大なカデンツァ(演奏者の任意独奏)が与えられており、最初のチェンバロ協奏曲(当時ピアノはない)といわれる。
『管弦楽組曲』は四つの組曲からなる合奏組曲。荘重なフランス風序曲を頭に、ガヴォット、メヌエットなど、いくつかの舞曲で構成される。弦楽器だけで演奏される3番の第2曲「Air(Aria)」は後のアウグスト・ヴィルヘルミの編曲による「G線上のアリア」として極めて有名。色彩感に富んだ華やかさと品の良い流麗なメロディは一定のレストランのBGMの定番。…ではあるが、きちんと音圧をかけて真面目に聴くと、その圧倒的な“凄み”にはもはや平伏する以外に為すすべもない。

SPV
085-304002 CD
2005
Almost alive.../Amon Düül II
77年、ドイツ、スカンジナビアのみでリリースされた11作目くらい。『恍惚万歳』あたりを最初の転機とするなら、非ドイツ語圏でのリリースが放棄された本作は第二の転機か。以後の2作をもって自然消滅することになる。6面デジパック再発リマスター。時勢なりにかつての混沌状態はすっかり解消されて、妙にタイトなリズムと健全な明るさが台頭してきて面食らう。生弦楽の使用や豪奢なロマン派風アレンジは70年代後半のノリだが、いろいろな意味で素人臭さが抜けて、曲構成やメロディまですっかり洗練されて違和感ありまくり(笑)。レナーテが1曲のみの参加で相対的に歌ものの比重が落ちたことも大きく印象を変えている。それでも「Ain't today tommorow's yesterdays」や「Hallelujah」あたりの縦横無尽な展開転調と重厚な色ノリは健在でかつての栄華を髣髴とさせる。
後半はライブが2曲入っていたり、以前のアウトテイクみたいな微妙に製作時期が異なる曲があったりと、途中で資金と気力が枯渇した模様。タイトルは「...and looking fine」と続くわけで、反語的に『概ね生きてて…まっとうに見える(けど瀕死ですぅ)』という意味なのだろうなぁ。

metamatic
meta7cd
Cathedral Ocean III/Foxx, John
売れているとは間違っても思わないが、一気に飛躍を遂げた『聖堂大海』シリーズの三作目。冷涼感溢れるアンビエント風エレクトロから、人声パートが大幅に拡充されて、もはや現代のモテットといってもよいレベルに昇華された。染み入るような冷たさと光に満ちた水没した聖堂で永遠を夢見る聖歌はただ美しい。ということで基本的に書くことがない。最大の欠点は生きているのが嫌になることだろう。ああ、もういいや、お迎えが来たのか、手を取られてそのまますぅっと魂が抜かれるような圧倒的な喪失感、生気を抜かれた乾いた屍がコロンと転がっているような無常で明るい透明感でいっぱいだ。
あまり上手いと思わなかった曲作りや構成も、気負いが消えて一歩抜け出たような、諦めの向こう側の清々しさが感じられる。DVD版(プレヴューがようつべに二つ上がっているようです)も出るようなので早まったなぁ。

Columbia
477849 2
A Rainbow in Curved Air/Reiley, Terry
いや、まぁ、しかし、購買意欲を削ぐデザインだこと。シュトックハウゼン(Karlheinz Stockhausen)やヤング(La Monte Young)の影響の下に、60年代に頭角を現した第二世代のアメリカ人現音作家テリィ・ライリィの二番目くらいに著名な作。ミニマルの創始者ともいわれ、後のライヒ(Steve Reich)やグラス(Philip Glass)の師匠筋に当たるがミニマル・ミュージックの御三家として扱われることも多い。20世紀中葉、形式主義に陥っていたクラシックから完全な脱却を図り、民族音楽への憧憬を深めつつも独自のスタイルを醸成した功績は計り知れないものがあるだろう。
70年代の本作は音の最小要素を連ねたミニマルに即興的な要素を加え、全体構成(序破急)を破壊する方向に向かった意欲作。その割には短いが。音色はなかなか刺激的で、電子オルガンと電気ハープのループだけでなく、かなり聴き易い対処(飽きないための仕掛けと変化)とシーケンス・パターンのように聞こえるリズミカルな処理が為されているあたりは大衆化への適切な方法論が感じられる。どのような処理が為されているのかは不詳だが、一応全ての楽器を当人が演奏しているようだ。タイトル曲(18:40)に加え、「Poppy Nogood and the Phantom Band」(21:40)が収録されている。タイトル曲は即興変奏で延々と拡張され、有名な「徹夜コンサート」で演じられたはず。リマスターが為されているのかどうか特に記述はないが、(クラシック・レベルの録音だから)音質はぞくぞくするほど鮮鋭である。

Polydor
557 974-2

3rd

5th
3 Originals/Earth & Fire
1973年の3rd:『Atlantis』、75年の4th『To the world of the future』、77年の5th『Gate to infinity』の3作にシングルB面7曲+シングル2曲をボーナス追加して2CDにしたお買い得再発廉価オランダ盤。4thは既に所有しているが、4th、5thのほとんどとシングルB面集は既存初期のCDとは別ヴァージョンとの注記がある。きちんとしたリマスターが施されているようで音の輪郭がディテールまで明確に聞こえる。
3rdは前作の発展系。タイトル通りアトランティスの栄枯必衰を描いた前衛的な意欲作。A面が全1曲の大曲「Atlantis」で後半に5小曲。ではあるが、シングル向きのポップス曲に混じって、いわゆるシンフォしているものは後半の小曲だったりするところが奇異というか面白い。そのあたりがオランダの特異性なのか、只の天邪鬼なのかは知らないが“考えている”ことはよくわかる。4thにおいても、泣きの轟音メロトロンが特質であるのに、エレピなんぞも使ってちょっとファンキィな“ノリ”を組み合わせるあたり一筋縄ではいかない。今聞くと敢えて典型たることを拒絶するような異物感が顕著に感じられる。この手の類例は多くをクラシックからの引用で賄うが、E&Fの場合は長曲ですら、曲構成やアレンジを含めてクラシックというよりはソウル・ファンク的なアプローチが色濃く感じられるあたりが非常に稀というか興味深い。逆に5thになると時節柄全10曲と小品集の雰囲気だが、今度は微妙なクラシック基調の構成、抑揚と生オケ・アレンジ、あるいは王道歌もの的ポップが5,6分の曲にテンコ盛りに充填されている。もっとも、カーフマンの歌はソウル・ジャズだなぁ。更に、おいおいと仰け反るのがシングルB面集で、アルバム収録ヴァージョンよりも典型的なプログなあたりが唸らせるというかシニカル。なんだか頭を垂れて再評価した次第でありまする。

Harmonia Mundi
HMA 1901455
Musique de chambre/Lekeu, Guillaume //Ensemble Musique Oblique
フランク(César Franck)の弟子の一人である夭折のベルギー人、ギヨーム・ルクー(1870-1894)の室内楽作品集。未完の絶筆になった「ピアノ四重奏曲」を中心に、「モルト・アダージョ」「ラルゲット」「アダージョ」の弦楽作品、作詞も自前の「三つの詩」歌曲による計74分04秒の法悦。作品のほとんどは二十そこそこの若書きだが、しなやかにして繊細、研ぎ澄まされたメロディが冴え渡る。師匠であるフランクのドイツ・ロマン派風の構築と世紀末を風靡したフランス印象主義の狭間に生れ落ちた至高の耽美はあくまでも内省的で密やかな熱情を奏でる。
どれも優れて美しいが、白眉である「ピアノ四重奏曲」の第二楽章の抑制された儚さを具現するEMOの極めて繊細な弦楽とアリス・アデル(Alice Ader)のピアノのアンサンブルは聴きどころ。ひたすらしなやかな弦楽に対し、輪郭が明瞭でクール、大胆な抑揚を誇るアデルのピアノがするりと背景から浮かび上がる様はえもいわれぬ抒情を醸し出す。回りくどく創りあげた美しさではなく、只そこにあるもの。ルクーに辿り着いたのは只の偶然だが、この手の決して派手にも劇的にもならない小体な真美こそが、あくまで求めて止まないものに近いのではないかと考えている。

Mercury
983 778-1
Keepsakes/All About Eve
ゴシック・トラッドで売り出し、インディでそれなりの評価を得、夢を紡いだAAEの形見。ジュリアン(ヌ)・リーガン(Julianne Regan)の美貌と懐古趣味、清楚を装いつつも微妙に色気を強調した官能的なボーカル、ギターのブリッチェノ(Tim Bricheno)の繊細かつメロディアスな曲作りが閉塞した時代の片隅に咲いた一服の清涼剤としての艶やかな花だったことは否定できないだろう。うんうん、(下手だったけど)好みだったぞ。お定まりの(わかっちゃいるが抑えられない破滅的衝動の結果としての)破局を経て、主要な作曲者であったブリッチェノを失ったことで三作目の路線転換に失敗し、バンド自体は魅力を失い、90年初頭には実質的に終わっていたと考える。現存するし、まだやる気もある? みたいだから、あまり梗概的完了形で述べてしまうのも気が引けるが、ブリッチェノ抜きの2000年代の復活モノは最早完全なる別モノと評価すべきだろう。
コンピ2CD+DVDセット。コンピには2曲の新曲を含み、全19+17曲のうち16曲が未発表、ないしはリミックス、ライブ・ヴァージョン等となっていて良心的な内容、かつ価格になっている。DVDはプロモーション・ビデオ15曲にTV用口パクあて振り演奏が6曲でおそらく新味はないものと推察されるが、ま、可愛いから許す(おまけ1,2,3,4)。PAL、リージョン2。

WB
20P2-2608
Burn/Deep Purple
歌手がイアン・ギランからデヴィッド・カヴァーデイルに変わった通算10作目。DP=イアン・ギランというほどのアイデンティティを持っていた看板歌手の交代は当時としても大きな憂慮を含んでいたが、一聴して《ま、いいんでないの?》というのが当時の結論だった気がする。シャウト気味のギランよりも女性的ないわゆる巧いボーカルではあるか。セカンド・ボイスのグレン・ヒューズもおっさんの魅力全開で良い。痺れるわ。円熟期から若干下降気味ではあるが、熟練した味のある佳曲のオン・パレード。アップテンポのギターリフが“かっちょええ”タイトル曲の「Burn」をはじめとして、あまりケチをつけるところがない。ジャケがダサいのは4th『In Rock』以降の慣例だから気にしても仕方がないだろう。初期の文学クラシック基調から、ハード・ロックを経て、ブルーズ色が濃厚に香る遷移期にあたる筈だが、次作『Storm Bringer』がパッとしない出来だったせいか、それ以降は聴いたことがない。

Seventh records
EX03
Le cœur allant vers/Vander, Stella
マグマの総帥の妻にして歌唱隊の一員、ステラ・ヴァンデールの稼業40周年記念通俗歌曲集。マグマ以前の60年代はキワモノ・アイドル歌手としてアンチ・ポップ・アルバムをリリースしていたらしいが残念ながら未聴。全13曲。ピアノや弦楽四重奏をバックに歌う全曲カバー、ビートルズからバカラックまで、往年のスタンダード曲で固めた尋常さが売り。なんと! ガブリエル・フォーレ(Fauré)の歌曲、「La Fée aux chanson(Op.27 No.2:歌の妖精)」「Après un rêve(Op.7 No.1:夢のあと)」まで歌っているあたり、なんだかちょっと感慨深い。
ちょっと線が細い、よく通るきれいな声のシャンソン歌手としては十二分に上手く、音だけ聴いたら誰だかわからん(笑)。80年代以降の低迷期を経た昨今の尋常でないマグマ熱には正直近寄りがたい違和感を感じますが、こちらは素直に歳を重ねたちょっとシニカルでちょっと可愛らしい大人の味わい。夜更けのしっとりと重いヴァン・ルージュのように、積み重なってしまった年月を嫌がおうにも飲み干す苦さと、ゆっくりと発酵した渋みを存分に味わうことができる。タイトルは4曲目でもあるピエール=ミシェル・シヴァディエ(Pierre=Michel Sivadier:俳優兼歌手?)の「Le cœur à l'envers(心乱れて)」の同音異義語による言葉遊びで「…に向かう心」といった意味だろう。

sickroom
skk 220
Cheval de frise/Cheval de Frise
ギター(クラシック・ギター)のThomas Bonvalet+ドラムのVincent Beysselanceなる変則デュオのデビュー作。現在のところ本作を含むアルバム2作とEPがリリースされている模様。ボルドー出身のようだが、資料が少なくてほとんどなにもわからない。部分的に電気も使っているものの、全曲インスト、無調と変拍子によるラウドでノイズ、緩急自在の変則音楽。透明と混濁、収束と発散、秩序と混沌が怒涛の奔流となってに目の前を駆け抜けていく様には、もう只、唖然とするのみ。あまり適切な比喩ではないが、ギター・ロックの味わいとバルトーク仕込み現代室内楽の変則リズム強化版を大西洋岸的湿度とトータルセリーの土壌に植え付けたようなものとでも云うか。
スリーブに使われている数枚のノスタルジックな写真は「マルネ(フランス北東部マルネ県)の戦場」というらしいが意図不明。ちなみにシェヴァル・ドゥ・フリーズとは成句で“防柵(軍事用バリケードの類)”を示す。

1987
1992
Waltz for Debby/Bill Evans Trio
いわゆるリバーサイド四部作と称される初期トリオの4作目、あるいはモダン・ジャスの名作ないしは名盤の一つ。1961年ニューヨークのクラブ、ヴィレッジ・ヴァンガードに出演した際のライブ録音。同日の録音の一部がトリオとしての3rdである『Sunday at the Village Vangard』として、本作以前にリリースされている。サパー・クラブ? でのライブで、飲み食いの食器の音、客のざわめき、疎らで気のない拍手など、おいおい誰も聴いていないのか? といった感触の極めて臨場感に溢れた録音になっている。87年のリマスター、92年の再発盤でタイトル曲などのボーナス4曲(別テイク3曲)入り。
演奏はもちろん素晴らしい。リマスターとはいえ録音も当時の技術の粋を凝らしたものだろう。クールで内向的な白人ジャズとして繊細な洗練と斬新で攻撃的なアドリブに支えられた出色の出来。ピアノ、ベース、ドラムの三位一体の為す至高のアンサンブルに関しては、語られ過ぎてこれ以上書くのは門外漢には恥ずかしいが、観客は上質で豊かなサパータイムを過ごせたことだろう。音楽の善し悪しは食いものの旨い拙いによく合う。
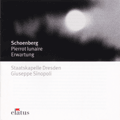
elatus
0927-49017-2
Pierrot Lunaire(Op.21), Erwartung/Schönberg, Arnold //SKD, Dir. Sinopoli, Giuseppe
青紫の夕景に貼り付いた今宵の月はまるでにんまりと笑ったかのような、薄く糸のように細い下弦の月だった。ベルギー・スュル・レアリスムの詩人アルベール・ジロー(Albert Giraud:1860-1929)の詩『ピエロ・リュネール(月に憑かれたピエロ)』から21篇を選び、朗唱と室内楽で奏でられる30分ほどの歌曲集。とはいっても、アルノルト・シェーンベルク(1874-1951:ユダヤ・オーストリア→アメリカ人)ということで、表現主義+無調である。歌というよりは音程をつけたソプラノ朗読。歌詞はドイツ語。演奏は静と動が精緻に組み合わされた効果的にしてダイナミック、飽きさせない狂的な演出がクールでするりと染み込んでくる。1912年の発表当時はそれなりに悪評だったそうだが、無調が市民権を持ち始めた非保守的な時代の気分に恵まれ、現代音楽の代表的な音源に成り得たと思われる。音楽楽理の専門的なことはとんとわからないが、構成的でもメロディアスでもないが(笑)けっこう聴きやすい叙景的な歌曲のように感じる。世紀末的耽美に彩られた歌詩も素晴らしい。
97年の新しい録音で歌手はアレサンドラ・マルク、演奏はSKD+ジョゼッペ・シノポリ。不気味なほど非常にクリアな音質で、月夜の青白い、ひんやりとした気持ちよさと気が狂いそうなまでの透明感が絶品。歌劇『Erwartung(期待)Op.17』付で70分越えの再発廉価盤。

EMI Classics
7243 5 85180 2 3
Mélodies/Ravel //Berganza, etc
モーリス・ラヴェル(Maurice Ravel:1875-1937)の歌曲集。生まれはフランス南西部、バスクのシブール、父はスイス人、母はバスク人。精緻で技巧的な印象派ではあるが、レトリックと修辞に満ちた捻くれ加減と明晰な論理性が叙情性に秀た同時代のドビュッシーとは一線を画す。バレエ音楽である「ボレロ(Bolero)」や「ダフニスとクロエ(Daphnis et Chloe)」に代表される、ちょいとエキゾティックで華麗な色彩感に富んだオーケストレイションと、現代音楽すれすれの斬新なピアノ曲が代表的である。
有名どころで「シェエラザード(Shéhérazade)」、「博物誌(Histories naturelles)」あたり。「草の上で(Sur l'herbe)」はヴェルレーヌ詩。マラルメ詩に曲をつけた「ステファヌ・マラルメの3つの詩(3 Poèmes de Stéphane Mallarmé)」はパリでシェーンベルクの『ピエロ・リュネール』を聞いて触発されたものとされる。「2つのヘブライの歌(2 Mélodies hébraïques)」に「マダガスカル土人の歌(Chansons madécases)」あたりのエキゾティズム、映画の劇中歌として作られた「ドゥルシネア姫に心を寄せるドン・キホーテ(Don Quichotte à Dulcinée)」まで、ほんの数分の単発ものから30分以上に渡る組歌曲まで千差満別てんこ盛り。
女声のジェシー・ノーマン(Jessye Norman)にテレーザ・ベルガンサ(Teresa Berganza)、男声のジョゼ・ヴァン・ダム(José van Dam)と豪華メジャーどころを揃えた歌手は7:3くらいで女声が多い。けっこう耳憶えのある曲も多く、「おおお。これはラヴェルだったのか」と自らの浅はかさに目を開かせられる思い。昨今はこういったものも酒のお供に鼻歌が歌えるくらいたいそう面白く興味深い。歌が上手なのは当たり前として、はっとするほど技巧的なアンサンブル、迸る才気に裏打ちされたゆるりとした空気がくったりと心地良いまでに堪能できる。全曲歌詞付、EMIの赤と黒シリーズ廉価盤。1984年のデジタル録音で2CD、61分+74分越え。どういう関係なのかは不詳であるが、ジャケ絵はデトロイト美術館蔵、ベンソン(Frank Wseton Benson:1862-1951)の「我が娘エリザベス」。