
Brilliant Classics
92177
Tafelmusik/Telemann, George Philipp //Musica Amphion
英語で書けば『Table Music』ということで文字通りの食卓の音楽=食事のBGMです。ドイツ・バロックの楽人、ゲオルク・フィリップ・テレマン(1681-1767)の代表作である室内楽全集。ハンザ自由都市ハンブルクを拠点に同時代人であるバッハを凌ぐ人気と類稀な商才で膨大な楽曲を残している。ハンブルク市の音楽監督(公務員)として週二曲のカンタータ(オケ付声楽曲)の作曲を義務付けられていたため、教会カンタータだけでも1000曲にのぼる作曲をこなしているが、他にオペラから管弦楽曲、宗教曲にいたるまで全部聞けるのかどうかは知らないが、昔の人はとにかくよく働いたようだ。1773年、自身が発行する音楽雑誌に発表した楽譜は飛ぶように売れ、英仏はもとよりロシアからも予約注文が殺到したとか。
テレマンはリコーダー(縦笛)の大家としても著名で、多くのリコーダー曲を作曲すると共に、超絶技巧な演奏までをこなしたようだ。本作は三部に分かれた全18曲のうちリコーダーが含まれる曲は一曲に過ぎないが、多種多様な木管、弦楽器による典雅にして優美な楽曲群は主張し過ぎることもなく、背景に埋没し過ぎることもなく適度な中庸さをもって食事の愉しさを倍加させたことだろう。残念ながら、それなりの質を有した生演奏を聞きながらまっとうな食事をする機会はまずないし、逆に美味しい食事を味わいながら聞こえてくる音楽は概ね悪趣味で雰囲気にそぐわないものだ。まぁ、食事という行為を徹底的に軽視するか、形骸ファッション化することで今の社会は成り立っているのだろう。くわばら、くわばら。演奏はオランダのムジカ・アンフィオン(Musica Amphion)という古楽団体。2003年の鮮明なDDD録音。ブリリアントの4枚組廉価版。

Virgin
CDVIP 170
Dazzle ships/O.M.D.
タイトルは『迷彩艦』の意。主としてWW2時代の光学的迷彩(ex.1,2:あまり良い例がない)を指すのだろうが意図は不明。アルバムとしては4作目にあたる。前作を踏襲したロシア構成主義風のデザイン(by ピーター・サヴィル:Peter Saville)から見て取れるように、中身も10年ほど前のクラフトヴェルクの『放射能』を思わせる前衛色が強い。チェコのラディオ・プラハの放送開始オープニング・テーマがそのままアルバム冒頭に使われている。同時期にDAFあたりも東に目を向けていたことからも、その時代、何らかの共通する意識や認識があったのだろう。非常に硬質で突き放した、概ねダークで叙情的なエレポップ。透き通るような気持ち良さと技術的に初期のサンプリング、SEとチープな電子音、深いリヴァーブが掛かったヴォーカルが特質であるが、次作以降はよりメロディアスでポップな方向に趣を変える。
「Time Zone」では複数の時報、お馴染みどころではNTTの117、時報をカウントする無機質な女声が延々と繰り返される。

ARTIS
ARCD011
Strata/Opus Avantra
70年代の二作の後、沈黙を続けていたオプス・アヴァントラの三作目。奏でられるピアノ・フォルテ、弦楽とドネラ・デル・モナコの歌による豊饒でありながら冷涼なクールさを漂わせた現代室内楽。タイトルは「Grande Notteruno」と注釈があるように「素晴らしき夜想曲」の意。夜想曲はそれまでの形式にとらわれない、主として一楽章三部形式のピアノ曲で、創始したのはアイルランド人の作曲家ジョン・フィールド(John Field:1782-1837)とされているが、名実ともに著名なのはショパンだろう。
「Strata」
夜の母の棺の中で
私はそこで生まれ
その喜びは自らの探求を惑わせる
沼地の小道は迷宮に至り
ときめきの眩暈は霞んだ道に目を凝らし
苦悩する
起こりうるひとつの希望
確固とした……
「Strata」はデル・モナコによる献辞のようなもの。「Canto incompiuto(未完成の歌)」の純粋美学的なしなやかさと相まって、幽玄と見紛うばかりの独特な世界が垣間見える。そういえば主唱であるドネラ・デル・モナコが関連ソロアルバムを出していたように、彼等はヴェネツィア出身のヴェネツィア色の色濃いグルッポなのだろう。おそらくビゾットが描いたと思われるジャケ画の鉛色の海や特異で風土的な三角屋根(アルド・ロッシまんまだねぇ)と旗、微妙に頽廃的な仮面をモチーフにしたエロティックな刹那感はかつて栄華を誇った海の都の落日を想起させる。時代が時代ということもあり、70年代初期の精緻かつ極め尽くした高揚感はないものの、夜想曲らしいゆるりとした叙情性と爛熟した果実のような濃厚な腐臭(死臭か?)がそこはかとなく漂うさまは濁った溜まり水を湛え沈みゆくヴェネツィアにこそ相応しい。

Threshold
820 211-2
Question of balance/Moody Blues
『ひ孫へ』と『童夢』に挟まれて若干影の薄い中期の作にして五作目のレトロな冒険活劇絵巻。アインシュタインにファントマにキングコングにサンダーバードかなぁ? 海を眺めるイタリアのリゾート風景が時代を感じさせる表ジャケに劣らず、サイケなレインボー・カラーに加工された内ジャケも古き良き時代。ムーヴメントには若干早すぎた才覚と、非ロック的な大人の余裕が徒になって近縁では極めてマイナーな扱いが残念である。ちなみに写真・デザインは後のマンダラバンドのデヴィッド・ロール(David Rohl)とクレジットされている。
コンセプチュアルな前後作に比べ、冒頭が「Questions」、ラストが「Balance」という体裁は取っているものの、どちらかというと淡白な流れが顕著ではあるか。LP-B面後半のピンダー作「Melancholy Man」から「Balance」に至る文明批評的な高揚感はなかなか聞かせるものを持っている。『釣り合いの問題』というタイトルはクリムゾンの『ポセイドン』を髣髴とさせる展開でもあるわけで、当時、彼等が何を憂いていたのか(言わんとするところはわかるが)は敢えて今追っかけても意味はないが、まぁ、いつの世も憂うべきことには事欠かないのは自明の理だろう。当時の彼等のヒューマニスティックな良心も、今や古き良き時代の回顧的な思想になってしまった。

ビクターエンタテイメント(株)
VICP-60051
A pleasant shade of gray/Fates Warning
運命の歯車がギリギリと廻るような重厚な変拍子とリフ、重さと脂の抜けた枯れが両立するボーカル、狭間で花やぐ生ピアノとアコギの考え抜かれた構成の妙と安定したアンサンブルが冷たく美しい60分全一曲(一応Part IからPart XIIにindexは振られている)のトータル・アルバム。中期FWの到達点といってよい出来だろう。しとしとと降り募る灰色の雨に微かな色気まで感じられるほの暗さ。ゆるゆると灰白色の闇から湧き上がり、再び曖昧な闇と光の狭間へと消えていく陰に対する偏愛と鋼のように冷徹な情念の表出。絶品です。
この灰色の陰
このある種の悲しみ
この冷たい朝の光
この沈黙の狂気
中空に貼りついて
記憶のようにさまよい
雲のように漂い
必死にしがみついている
過去の現在の狭間に
若さと老いの狭間に
あなたとわたしの間に
あなたとわたしの間に
……
さぁ、どこから始めよう
他に何と言えようか
歳月すべてが刻まれてしまった今
何ができるというのか
朝の影が踊る間に
しばらく目を閉じて
長い夜を洗い流す
雨の音を聞く
また別の一日に
直面することに覚醒し
また、心に希望を持って
この灰色の陰を抱きしめる
この心地良い灰色の陰を
異様なまでに音圧が高い日本盤ボーナス・トラック? はPart IIのリミックスで、終曲の後、若干間を取っているが純粋に蛇足だ。

Arte Nova
74321 49697 2
Stabat Mater/Boccherini, Luigi Vivaldi, Antonio //"Musica Viva" Chamber Orchestra
スタバト・マーテル二題。共に、一節目、「悲しみに暮れた聖母マリアは立ちぬ」と歌われる“スタバト・マーテル・ドロローザ(dolorosa)”にしてカトリック教会の聖歌。詩作は13世紀のヤーコポーネ・ダ・トーディ(Jacopone da Todi)といわれる。マリアが磔になった息子の前で嘆き悲しむという内容であるが、若干のヴァリエーションが存在し、ルネサンス、バロックのパレストリーナ、スカルラッティ、ベルゴレージから現代のペルト、ペンデレツキに至るまで、曲をつけている多くの作曲家たちの採用した歌詞にもバラツキがあるようだ。
ルイジ・ボッケリーニ(1743-1805)のスタバト・マーテルは(43:32)の長尺。滑らかで素朴、聡明な感触の優しい情感がこもったソプラノ独唱パートを中心にした宗教声楽曲。抑揚の大きさや後半の盛り上がり方はオペラを思わせる華やかさを感ずる部分もあるか。一方、アントニオ・ヴィヴァルディ(1678-1741)の同曲は(18:53)に凝縮された簡潔で悲痛、一際美しいメロディが際立つ。ヴァイオリン協奏曲並みの音圧で歌と交互に奏でられる弦楽の鮮烈さはさすがに唸らせる。1750年を境にする年代的にヴィヴァルディのものはバロック、ボッケリーニは古典の時代の楽曲で、それぞれ相応しい典雅と敬虔をふくよかに包含している。共にイタリア人らしい明るい花やかさも特徴的である。主唱歌手が二人ともロシア人のせいかモスクワで96年のDDD録音。

SONY
SOPM 65
VI/Chicago
前作の延長線上だが更にソフト路線に傾斜がかかった6作目。全10曲と曲もコンパクトかつ洗練された良質なポップとなっている。デビューして5年ほど。自分達がやりたいことを必ずしも人が求めていないことに気付き、客観的に時代を読み、売れ線を分析して路線転換ができるだけの技量と器量も付いてきた。当時と今ではまるで別の国だが、まぁ、アメリカほど革命が似合わない国もないということにようやく気付いたのだろう。したがって、次作で若干の揺り戻しはあるにせよ、内容は徹底している。ジャズ、ロック、ファンク、ブルースとあらゆる要素を自家薬篭中のものとしながらも、オリジナリティに富んだ当時としては鮮度溢れる清々しさが気持ち良いほど感じ取れる。ロバート・ラム、テリー・キャスにピーター・セテラという三人のボーカル+作曲も青臭さが抜けた円熟と、それぞれの特質を生かした旨味が滲み出てきたように思う。
確か最初はロバート・ラムが好きだった同級生の女の子に借りて聴いたもの。密かに慕っていた彼女には代わりに当時出たばかりの『VII』を貸したような記憶がある。久々に聴き返していたら、懐かしいけれど手の届かないもどかしさみたいなものがぽっかりと湧き上がってしまった。ということで、本来的には本Webの当初からのコンセプトに極めて合致した“懐かしのレコード”である。実際に自分でLPを入手したのはかなり後(数年後)だったと記憶している。もっとも、こういう話はとても書き易いし、聴いているだけで細かいエピソードなんぞもうっかり思い出したりしてこそばゆいのだが、わざわざ公衆に開陳して読んで頂くほどのものではないか。当時のLPは、まるで本物の紙幣のように孔雀織りの光沢加工がされた手触りが柔らかい質感のある凝ったジャケットで、汚れそうだから腫れ物に触るように丁寧に扱ったものだ。

Atlantic 82676-2
Live/Genesis
『Selling England by the pounds』の製作が遅れ、急遽つなぎでリリースされた絶頂期のライブ盤。視覚的な情報が皆無だった当時、典型的なライブ場面(クラークの『幼年期の終わり』のオーバーロードに扮した「Watcher of the skies」だろう)を写したジャケ写真には痺れたものだ。左からハケット(ギター)、ラザフォード(12弦ギター、ベース、ベースペダル)、扮装して立っているゲイブリエル、コリンズ(ドラム)、バンクス(鍵盤)という黄金期の布陣で、ゲイブリエル以外は全員着席というのが面白い。稀にラザフォードが立って弾くこともある(主にダブルネックを使うとき)ようだが、75年以前は概ねこのスタイルが踏襲されている。
楽曲は2nd~4thアルバムから選ばれたどれも代表曲といえるもの。音質もまぁまぁで、ほぼスタジオ盤通りのアレンジを完璧にこなすアンサンブルは賞賛に値する。このぎこちないまでの人工味とグルーブを廃絶した複雑怪奇な構成展開がジェネシスの持ち味。スティーヴ・ハケット(Steve Hackett)は後に「当時は作曲した楽曲を意図通りに表現するだけのテクニックがバンドになかった」と語っているが、なんのなんの。自ら開発したタッピング奏法を取り入れたフレージングは極めて斬新にして繊細で類例を聞かない。当時、20代前半の若造がこれだけの曲を書き、演じていたというのは心底驚異的ですらある。
ジェネシスの特異性はジャズやブルーズに寄り掛からない頭でっかちで頑固なまでの人工臭さとシニカルで辛辣な現代性にあったわけで、フォーク、トラッド、古典のエッセンスや構成を借りながらも強引なまでの自己消化の上に何ものでもない一つの流儀を創りあげたことにある。そのあたりはバンド・アンサンブルにも顕著である。ギターのハケットは印象的なフレーズ弾きとアンビエントな効果音を担い、コードを弾かない。本来のギタリストの役割を担うのは、ベース奏者のラザフォードであって、彼の12弦ギターによるコードストロークとアルペジオがジェネシスのアンサンブルの根幹を成している。バンクスの鍵盤も音圧的に背景を支えるというよりは煌びやかな色彩感に溢れたリード楽器である。コリンズは優れたドラマーでありながら重要な歌手であり、もちろんゲイブリエルは歌手でありながら曲に合わせた役作りとコスチュームで演劇する演者なわけで、各々が本来の役割とは違った位置に存在価値を見出すような楽曲そのものがジェネシスのジェネシスたる由縁だろう。

BMG
74321 752582
The very best of/Rondò Veneziano
70年代ニュー・トロルスやオルメのプロデューサー(オルメではメンバー・クレジット)でもあったピアノ奏者ジャン・ピエーロ・レヴェルベリ(Gian Piero Reverberi)が主宰するロンド・ヴェネツィアーノの廉価秀逸抜粋。テンコ盛りの全21曲。80年のスタートで現在も継続中。おそらくどこかの音大教授の職にあり、メンバーはその音大の学生9名で構成されているようだ。ドラムとバス以外は全員女性(弦楽4+管楽器3くらい?)でバロック風の白いかつらと絢爛豪華な衣装で新古典主義風のライブを行っているようです。途方もない枚数のアルバムが出ているようで、どれがどうなのかさっぱりわからんわ。いかにもヴェネツィア風味なカラフルで頽廃的なまでに豪奢な色彩と、バロック最大の楽都ヴェネツィアの象徴であるサンマルコ寺院や観光ゴンドラ風景などを多用したイメージ作りが端的で目を引く。
ロンドは輪舞曲というバロック期の楽曲の形式を表す。適度にクラシカルなモチーフが取り入れられた楽曲はイージー・リスニングすれすれではあるが、リズムもアレンジも非常に工夫されて心地良さと新鮮味に満ちているあたりが不思議なくらい。艶やかで悩ましい旋律とのりのりのビートで現代アレンジされた楽曲はすべて歌なしインスト曲で、かつプロフェッショナルな出来映え。

MASO
CD 90016
1998
Magic Music/Third Ear Band
突如復活した「第三の耳団」の5作目にあたるフル・アルバム。わけのわからんイタリアのレーベルからのリリースだったため、しばらくは過去のアルバムの焼き直しか、同姓同名の大方紛い物だろうと相手にしていなかったもの。公に発表された前作『マクベス』からは26年が経っている。首領であるスウィーニィ(Glen Sweeney)以外は過去との関わりはない再編プロジェクトのようなものだったと思われる。全6曲、ラスト「Third Ear Raga」のみ89年のライブ音源のようなので、おそらく細々と何らかの形で存続はしていたのでしょう。
内容は未発表4th『The Magus』とは異なる先祖回帰で、電気は使っているものの、1,2作目の非電化瞑想室内楽の路線に近い。電気ヴァイオリン、ギターには電気的なエフェクトが多用され、うねるような心地良い浮遊感と輪廻する刹那が即興的に体現される。一方、管楽器、打楽器は生楽器で、朴訥で単調なリズムが瞑想的な黄昏を醸成する。スウィーニィ曰く「色彩・純粋な振動・第三の耳で聞くことができる惑星の鼓動」というわけで、病的なまでの強迫神経症的末世を感じさせた以前に比して、遥かに悦楽的で滑らかに美しいメロディが奏でられる神秘主義的宗教に近いものを感ずる。

帝蓄/Avispa
TECW-25075
Árabe/Medina Azahara
いやぁ~、凄い凄い。生きていてよかった。民族楽器の前奏が静かに終わり、ん? と耳をそばだてると突然音量が変わったリフが響き始め、ズンガズンガどっひゃらガーと思わず息が止まって、次の瞬間、腹を抱えて笑い出してしまう。すると、そこはもうスペイン南部、アンダルシアの灼熱の光の中。乾燥した大気と濃緑のオリーブの林、目くるめく色彩と光量のコントラストに瞳孔が悶絶する。アンダルシア“ド”演歌をメタルなロック節に乗せて猪突猛進、ベタベタの節回しで熱唱するコルドバのベテラン・プログ・メタル・アラビック・フュージョン、メディナ・アサアラの9作目。タイトル『アラベ』はそのままアラビア人を指すわけで、雰囲気も曲調も見事な先祖返りであらせられるところは衆知異存のないところでせう。しかし、まぁ、背景のメディナ・アサアラ(アブドル・ラーマン三世建立の宮殿)に比して、暑苦しくもだっさい面々だこと。元はアラビア語でMadinat Al-Zahra(マディーナトルザハラ)と書いて「花の都」という意味らしい。今残るのは平原に発掘され一部復元された遺跡だけのようですが、シリアから嫁いだ妃のために建てられた宮殿は故郷の雪山を望郷する妃のためにアーモンドと桜が一面に植えられて、春になると真っ白な花が雪原のように周囲を埋め尽くしたとか。
後半は二枚組みのご当地盤では別CDになっていたカバー集。どこの誰の曲だろうが問答無用! 全部スペイン語で歌ってしまうあたりはもちろん、曲名までスペイン語にしてしまうあたりが痺れますな。

PHILIPS
PHCP-10160
Gymnopédies/Satie, Erik //Leeuw, Reinbert de
当時は調性放棄と教会旋法の導入を平然とやってのけた突き抜けちゃった革新者で、間違いなく異端であるが、ドビュッシーやラベルがべた褒めし、後に晩年に書いた『家具の音楽』あたりがポスト・モダニストたちに再評価されたことで、今や環境音楽の元祖として崇め奉られるエリック・サティ(1866-1925)のピアノ曲集。薔薇十字団に所属し、どこまで本気だったのか後に「主イエスに導かれる芸術のメトロポリタン教会」を設立(ちなみに信者はサティ本人のみ)しながら、フランス共産党員であったという極めて変人(寓意はわからんが「トロワの高校の物理学教師」といわれた不変の黒尽くめ山高帽スタイルも怪異である)だったようです。
曲目は典型的かつ人気の高い「三つのジムノペディ」「冷たい小品(1:逃げ出したくなる三つの歌、2:斜めに踊る三つの踊り)」「六つのグノシェンヌ」組曲に「天国の英雄的な門への前奏曲」「舞踏のための小序曲」を加えた比較的リリカルなベスト盤のようなもの。テンポは聞いたことがあるものの中では最も遅め。過剰なまでの装飾と加算の美学の申し子である西洋芸術のなかで、音の隙間、無音の美学を突き詰めるに至った稀有な存在であることは間違いないだろうが、初期の神秘主義的な音の連なりから、ユーモアと諧謔の時代を経て、家具の音楽(アンビエント・ミュージック)やシュールレアリズムの幕開けともいえるバレエ音楽(というかメディア・ミクス)に辿り着く変遷は非常に興味深い。演奏はオランダ人、ラインベルト・デ・レーウによる70年代の録音。
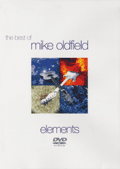
Virgin
7243 5 99990 9 8
Elements/Oldfield, Mike
76年のBBCでの『Tubular Bells part1』のライブに19曲のヴァージン時代のPV集、『Wind Chimes』集他、インタビューでテンコ盛りのDVD。TV放送用に撮られたと思われる『TB1』はマイク・ラトリッジが弾くイントロ・ピアノで厳かに幕を開ける。およよ? という疑問はラストの字幕で解決されるが、カール・ジェンキンズにヘンリー・カウ、Gongからヒレッジ、モワルラン、ストーンズのミック・テイラー、カーブド・エアのフランシス・モンクマン(?:字幕が出ないところを見ると契約上の問題か)と開いた口が塞がらない豪華オールスター総出演である。オールドフィールドはベースとアコギ担当というあたりは73年のリリース直後のライブ・フィルムと同じであるが、風体は随分と生意気そうに逞しくなった。右手でarp、左手でエレピを弾くカウのバス奏者ジョン・グリーブズにオルガン、ムーグをいじるホジキンソン、やっぱり糞真面目にギター、ベースと大活躍のフレッド・フリスと才人カウの貢献度は高い。ミキサー2名がボリューム・スライダーいじりながらハミング入れているのには笑った。総勢15人+8名くらいの女声合唱隊(ノーセッツが見える)付のほぼ原曲に忠実なアレンジの『TB1』です。
販促ビデオのほうは、ありきたりの内容で映像と音は別テイクであるが、ジョン・レノンの射殺事件を追悼した「Moonlight Shadow」、薔薇戦争のころフランスに援軍を求め嵐の英仏海峡を渡ろうとして辿り着けない苦悩を歌った「To France」あたりの、脂が乗り切った時期の歌曲におけるマギー・ライリィのボーカルとモワルランのドラムは極めて感慨深く染み入るものがある。後半は若干毛色が変わって、ケルト風味のワールド・ミュージックやポップな領域の歌手を起用した良く言えば意欲作、悪く言えば迎合作だが、オールドフィールドの味は出ているでしょう。見なくても聴けばわかるが、テクニックは相変わらず驚異的である。
NTSC、リージョン0。
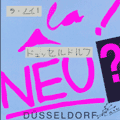
CTCD-051
Düsseldorf/La! Neu?
元祖デュッセルドルフは80年を待たずに崩壊し、表舞台から姿を消したクラウス・ディンガーが突如リリースしたラ! ノイ? の初作。微妙に日本語がちりばめられたスリーブ等を見ても、再起にあたってノイ後の未発表作を発掘リリースに漕ぎ着けた某インディ系レコード会社が何らかの形で絡んでいることは想像に難くない。一曲目「Hero'96」はノイ!の三作目『Neu! 75』の「Hero」の改作。副題は“告訴”だものな。ミヒャエル・ローターの了解なしにノイの未発表『Neu4』をリリースしたことと何らかの関係があるのだろうが、業界裏話もバブルに踊った徒花の功罪にも興味はない。
音像は予算不足のせいか荒っぽく、一発録りに近いスタジオセッション風で曲名も極めて等閑というか何も考えていないというか。Hero'96(22:37)、Mayday'95(4:24)、Düsseldorf-22.12.95(33:39)、Mayday'96(8:36)の計4曲。偶数短曲が歌(というべきか?)入り曲で、陽だまりの痴呆老人のようなヘロヘロのワンコードをヘロヘロ繰り返すというもの。奇数長曲はそこはかとない乾いた寂寥と90年代重低音アパッチ・パンクの応酬だが、延々と繰り広げられるノイズとビートはそれなりに快感を持って疾走する。剥き出しで洗練とは程遠いが、まぁ、これはこれでよいのかな……と思わせるコアなエッセンスは凝縮されている。リリースは日本盤のみ。これは数年前、一時大量に出回っていた日本盤未開封新古品。

Warner
2292-44121-2
La Düsseldorf/Düsseldorf, La
70年代の本家デュッセルドルフの1stアルバムのデジタル・リマスター。プロデュースはユニット+名匠コンラート・プランク(Konrad Plank)。構成はクラウス+トーマスのディンガー兄弟にハンス・ランペ。ノイ(Neu)の功績を引き継いだ人力テクノの進化系。
一曲目「デュッセルドルフ(13:17)」、二曲目「ラ・デュッセルドルフ(4:28)」とLP旧A面はひたすら出身地をよいよいよいと連呼。表ジャケはデュッセルドルフ空港の夜景だろう。3、4は「Silver Clouds(8:01)」に「Time(9:24)」とな。「銀雲」はほのぼのとしたアープ・オデッセイの単純で単調なメロディ、8ビートの極めて簡略化されたリズムが単調かつアンビエントに響く元祖テクノの原型。思い入れも主張も何一つない至上快楽的音場生成。蕩けそうな悦楽と前向きで楽天的な浮遊。「時間」は毎度お馴染み独英仏伊語ちゃんぽんによる16ビート・テクノ。青春時代、少女時代、幼児期、ローラースケートをしてるとき、クリスマスの時期、最高の時……時は淡々と過ぎていくと。
ツインドラムでありながら不気味なほど同じ手数で同じフレーズを叩くユニゾン・ドラムがもうドイツ人丸出し。クールな素っ気無さと未来憧憬のエレクトロニクスを触媒にした化学反応のような定常的で定量的な再現性の発露にして標準化。裏ジャケの銀雲のような、陽極酸化皮膜処理したアルミコルゲートパネルか溶融亜鉛メッキの波板鋼板の壁面の下でポーズをつけるトリオの微妙に未来的なスタイルが、当時としては開いた口が塞がらないぶっ飛びかげんでもあった。

Repertoire
REP 4688 WY
The Return of Onkel Boskopp/Reichel, Hans+Eroc
ハンス・ライヒェル(公式Webは非常に軽くよく出来ている)はダクソフォンといわれる擬似人声がのたくったような奇妙な発音をする楽器を作り出した改造ギター奏者、エロックは長年に渡ってどさ回りのサーカス、グロープシュニットの親方を務めてきた退役ドラム奏者。GS以後もスタジオ・エンジニア業の傍ら積極的に自作をリリースしていますが、これは特異でけったいなご両人のコラボ作。曰くありげなご両人(左:Eroc、右:ライヒェル)の姿を見ればわかる通り、不審きわまる不良中年によるコミカルですっとぼけた奇矯さが売り。さすがにその道の第一人者同士、すれすれまで工夫され、凝りに凝った前衛現音ポップとしか形容しようのない全インスト曲。ダクソフォンの微妙に郷愁を感じさせる味わいがしっとりとポップなワルツにのると、煌びやかな色彩と抑制された溢れる情感が優しい空気に漂い始める。
だいたい『ボスコップ叔父さんの帰還』といわれても意図不明だが、内スリーブによれば“ボスコップ叔父さん”には丸いのと四角いのがあって、恋人同士を“Good tune”に導く強い薬と解説されているわけで、余計わかんねぇって。83年から97年にかけて製作され、録音の質はもちろん、マスタリング、リマスタリングを含めた音質は自然でかつ冴えている。