
VICG-40057,58
春の海・六段/宮城道雄、八橋検校、他 //宮城喜代子、他
たまには日本のものもよいでしょ。邦楽というとWW2後に開発された西洋音楽を基盤にした演歌や歌謡曲をルーツとする、過去とは一線を画した音楽を指すようだから、この手のものは和楽とでも言うべきでしょうか。もちろん「和楽」などというと人を撲殺できそうな紙塊重量月刊雑誌を思い浮かべてしまうほど、老若問わず、コンテンポラリィでブリリアントなジャパニーズのメイン・ストリームからは、まるで恥部のように黙殺される過去の遺物。まぁ、世襲と資本主義に身を委ね、滅亡の道を辿る当世の芸道に比べればましではあると思うのだがなぁ。
元々、日本古来の音楽(といわれているもの)には雅楽に代表される渡来音楽と、記譜法が存在しなかった(開発しなかった)ために再現できない古代宗教祝詞に代表される土俗宗教音楽があったようです。筝曲は基本的に前者の流れを継承するもので、ここで用いられる琴は「筝」といわれる紀元前3世紀ごろ中国で開発された13弦(正確には“絃”)の楽器(中国ではツェン、フィンランドではカンテレ)を指す。琴という6弦楽器はまったく別の形態である。筝は江戸時代に八橋検校(やつはし・けんぎょう:1614-1685)によって楽器として完成され、同時に筝曲というジャンルが一般化した。“段もの”といわれる変奏曲の代表的なものが「六段」。ちなみに“検校”とは当時の盲人音楽家組合の最高位を指し、江戸時代においては障害者の職業保護のため筝は盲人にしか弾くことが許されなかった。後継者に生田検校や山田検校など現代の流派の始祖がいる。ついでに“八橋”は検校発案の京菓子の名前として現代に伝えられている。
宮城道雄(1894-1956)は大正から昭和初期に活躍した神戸の音楽家。8歳で失明、当時日本領だった朝鮮で14歳にして伊藤博文に激賞される。西洋音楽の構造を筝曲に導入した「春の海」は1929年作、フランスの女性ヴァイオリン弾き、ルネ・シュメーと競演、1932年に日米仏でレコード化される。後に芸大教授にまで登りつめるが走行中の列車から転落死(?)という数奇な運命を辿る。
中身の話を書く前にこれだけの予備知識が必要という意味でも、既に忘れ去られた遺物(異物か)であることは紛れもない。2CDの前半は宮城道雄の作品。「春の海」は瀬戸内海を渡ったときの感触を表現したものといわれる。潮の動き、流れ、波の音、魯を漕ぐ水音、海鳥の鳴き声といったうららかな春の海の情景動態を盲人の極めて鋭敏な聴覚、嗅覚で捉え、繊細かつ構造的に描きだしたもの。伴奏はヴァイオリンではなくて尺八ヴァージョン。人間国宝である直系の子孫による演奏が収録されている。
二枚目は検校もののオムニバス。八橋以外にも光崎、吉沢検校らの作品が収録されている。「六段」は筝の器楽曲としては古典にあたるもの。典型的な日本情緒(いやいや、今となってはもう別の国、異国情緒というべき)を掻き立てる7分ほどの変奏曲。六部立ての変奏曲としての形式と、筝のあらゆる技巧が盛り込まれた練習曲としての性格も併せ持つ。基本的にはソロのリード楽器として使われているが、尺八、胡弓とのアンサンブルとして作られた器楽曲も多い。
と、まぁ、わかった風なことを書いてはいるが、今回改めて聴きなおして日本の筝曲というのは単音の冴えが肝なのではないか? などと考えた。いまどき筝を弾いている現場やら音源を探すのは一苦労だから類例の検証はできていないのであるが、中国の筝曲などは明らかにアンサンブル指向で同時に多絃をはじくことで、ハープのようなアンビエント風の効果を狙っているように思える。

Naxos 8.555779
Music for Ondes Martenot/Bloch, Thomas
オンド・マルテノは20世紀初頭、電気技師兼チェロ奏者モーリス・マルテノ(Maurice Martenot:1898-1980)によって開発され、テルミンに遅れること8年、1928年に初演された鍵盤タイプの電気楽器。オンド(Onde)は波、電波の意。電磁波楽器であるテルミンが(その構造上)ほとんど宗教風のパフォーマンスに見えるのに対し、こちらは不可思議な(いや、共鳴を利用して巧妙に設計されたというべきか)形態のスピーカーに囲まれて弾く小さなオルガンといった概観で見た目はそれほど奇異な感じはしない。音色のほうも今となっては不思議というほどではないが、アナログシンセが登場するまでの西洋楽器としては、鍵盤楽器とは思えない不可思議で奥ゆかしい音色をもたらしたのは事実だろう。ちなみに決して際もの扱いされているわけではなくて、コンセルヴァトワールにはオンド・マルテノ科が実際にあるようだし、メシアンの「トゥランガリラ」が代表的だが、ジョリヴェ、ミヨー、オネゲルあたりも頻繁に自作に取り入れている。
トマ・ブロッシュ(1962-)はオンド・マルテノの奏者兼普及家といったところか。近作ではレディオヘッドの「Kids A」ライブでその微妙な音色を聞くことができるなど、なかなか活動的な人のようだ。本作でもメシアンやマルティヌーに加え、自作曲を披露している。更にピアノ奏者ウィッソン(Bernard Wisson)やイギリス人管楽器奏者リンゼイ・クーパーとのコラボレイト作が含まれる。20世紀現代音楽の始祖からほとんどプログレしちゃっているクーパーまで千差万別雨霰。その忘れ去れゆく悠久の音色を心ゆくまで堪能できる。
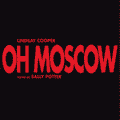
VICTO cd015
Oh Moscow/Lindsay Cooper
上記にも参加しているクーパーはヘンリィ・カウの二作目以降に構成員となったコンポーザ兼管楽器奏者にして政治的女権拡張論者というよりも行動者。専門はバスーン、オーボエ。王立音楽院出のエリートととしてケンブリッジ-初期カンタベリィ人脈の中に登場し、カウ以後の動態を鑑みるには現音畑の音楽家で、見目麗しい女性です。80年代から90年代に数枚のソロ・アルバムをリリースしていますが、91年に多発性硬化症なる難病を発症し、カウの同僚カトラーが募金を呼びかけておりましたが、既に音楽界からは完全にリタイアした模様です。
作詞を映画監督兼歌手のサリー・ポッター(Sally Potter)、全作曲、管楽器演奏をクーパーが担当したプロジェクトのようだ。7人のバンド編成で、サックスに23 ハース(Alfred 23 Harth)、バスにヒュー・ホッパー、トランペットにフィル・ミントン(Phil Minton)と男性演奏者はそうそうたるメンバーを擁している。録音はカナダ、ケベックでの89年のライブで、同じ編成でヨーロッパ各地とモスクワでライブが行われた。全10曲の組曲風トータル・アルバム。構成から見ればジャズ+室内楽を想起させる編成だが、非常にポップ・ロック寄りで歌詞も平易かつ明解であるあたりは、それなりの浸透性と大衆プロパガンダを狙ったということだろう。
本作は冷戦終結を背景に、87年に着手されたヨーロッパの再興を基本的なテーマとしたポリティカルな作品。平たく言ってしまえば、ウラル山脈までがヨーロッパであり、そこに住む我らは○○人である前にヨーロッパ人なのだということだろう。ほんの十数年でその統合の理念は、再び楔を打ち込もうとする果敢で陰湿な策謀を排除しつつ、確実に加速し充実しつつあるのは現実に見る通り。100年、あるいは500年先を見据えた理念こそが、何かを為す原動力と足りうる最低限の資質であることを証明した良い例だろう。

ESD81412
Unrest/Henry Cow
おぉ、世間様は黄金週間。防音壁の向こう側では朝っぱらから微速前進と停止を繰り返し、新装開店の大規模小売店舗には昔懐かしいアドバルーンまでが上がっている。天気は上々、清々しい(くもないか)空気と穏やかな日差し。北東の風もおさまって気温も上がり始めた。ふ~む、と木の芽芳しき外気に誘われ財布を懐に入れたはよいが、おお、有り金が437円しかないのであった。そんなときには清貧の憂鬱、すべてをぶち壊しにする凍てついた『不安』。
本家家元カウ二作目のリマスターCD。木管奏者リンゼイ・クーパー(Lindsay Cooper)が要員となった円熟期カウの傑作。場合によっては最高作との評価が一般的か。前半曲がアレンジメント、後半はスタジオ即興をもとにテープワーク、ループ処理、オーバーダビング等の粋を凝らしたもの。4曲目「Solemn Music(荘重な音楽)」のみチャドウィック(Jonathan Chadwick)のシェイクスピア劇「テンペスト」の引用。脈絡のない一部のクーパーのおふざけヴォイス、ラストのグリーヴスのどうでもヨサゲな一節を除けば、若きエリートたちによる全曲インスト、クールで緻密、諧謔と文明批評的反体制色の色濃い室内楽の完成である。肝心のクーパーによるオーボエとバスーンが惚けた味わいで陰滅気味のアンサンブルに彩りを添えている。前半四曲は恐らくスコアを起こして緻密に作曲された技巧的なポリリズム。多調とでもいえばよいのか? 一つの曲でバスラインとメロディの調が違ったり、無調転調を繰り返したり、もう何拍子だかさっぱりわからん変則拍子、ひりひりするような乾いた冴えと根底に流れる意外にリリカルな風情が鮮烈にして才気煥発。
カトラーには怒られそうだが、気持ちの良いお洒落な、そして何よりも格好良いアヴァン・ガルド。根底に見え隠れする極左思想とともに猪口才な子供にゃ極めて衝撃的な世界でした。クーパーちゃん(左からフリス、カトラー、クーパー)もかわいいしな。アルバムはワイアットとグルグルのウリ・トレプテ(Uli Trepte)に献呈されております。

Materiali Sonori
MASO CD 90120
Cool August Moon/Stàlteri, Arturo
ピアノものを二つ。最初はイタリアのアルトゥーロ・スタルテリ。スタルテリは70年代ピエロ・ルネーレ(ピエロ・リュネール)の鍵盤奏者。見切りをつけた後に現音系ピアノに転向というか、元々はクラシック系のピアニストだったのだろう。PLにおいても現音色は濃厚だったが若気の至りというやつか。その後しばらくは本業で大人しくしていたようですが、やはり血は争えないのか色気というか洒落っ気が出てしまうのだな。本作はブライアン・イーノの楽曲を生楽器で再現したカバー・アルバムという体裁。もちろんスタルテリのピアノ、あるいは弦楽四重奏など室内楽編成を生かしたリアレンジ。ピアノ以外の編成はヴァイオリン、チェロx2、バスーン、電気ベース、打楽器でピアノ・ソロから合奏アンサンブルまでいろいろ。
躁な曲(ex.「暖かい奔流」など)のアレンジも面白いが、やはり白眉はスタルテリの表情豊かなピアノを生かした沈み込むように鎮静していく曲だろう。『8月の冷たい月』というタイトルが示す通り、深いインディゴ・ブルーの濃密な空気感と冴えた月の光がこの世のものとは思えない耽美を照らし出す。『Appolo』のテーマ「Ascent」、「St. Elmo's Fire」等々、原曲がピアノ曲じゃないから上手いんだか、下手なんだか。持てる才能が発揮されているのはもっぱらアレンジなのだろうが、そつなく楽しげで、淡々とした儚げな良い味は出ているでしょう。

Deutsche Grammophon
471 769-2
Credo/Beethoven,Pärt,Corigliano //Grimaud, Hélène, etc
続くはエレーヌ・グリモー自身による企画・選曲・演奏というフィーチュア・アルバム。ついでに曲の並べ方、アレンジも含めてトータル・コンセプト・アルバムという体裁で、こういう作り方をしたクラシック系のアルバムはあまりないのではないだろうか。
曲目は、
「オスティナート」12:04 ジョン・コリッリャーノ
「テンペスト」21:58 ベートーヴェン
「コーラル・ファンタジィ」19:03 ベートーヴェン
「クレド」15:16 アルヴォ・ペルト
頭二つがピアノ・ソロ、後半二つはオケ+合唱付。
グリモーは15歳でCDデビューして当然の如くちやほやされて、そんな業界にウンザリこいて引き篭もり+狼少女になってしまった人ですが、その麗しき見目からは想像もつかないビート感と強拳、迸る感性が特徴です。打鍵が強く区切りが明瞭なのですね。特に近年はその傾向が顕著で、拍子を誤魔化したり音を省略したりしない突き抜けちゃった生硬さが真骨頂、もちろんプロだから上手いです。指異様に長いし。さらに演奏だけでなく文才も溢れており、天は二物を与えぬどころか少なくとも三物くらいは与えたようだ。選曲もフランス人らしからぬ硬質さと冷やっこさが特徴。最近もブラームスにシューマン? 最初はラフマニノフとショパンだし、ラヴェルは弾いていたが一度ドビュッシーとかフォーレを是非聴いてみたい気がするな。タイトル『クレド』は通常文ミサの第3曲目「信仰宣言」にあたる。内容に関しては語る言葉をもたない。グリモー自身による解説、インタビュー付。
いつまで見れるか知らないけれど、おまけにどうぞ。バッハのシャコンヌですね。

Musea FGBG 4283.AR
1999
Saga de Ragnar Lodbrock/Saga de Ragnar Lodbrock
マリコルヌあたりと似た土壌から生まれた電化民謡歌劇。グループというよりはプロジェクトとして組織された? サガ・ドゥ・ラニャール(ラナール)・ロドブロクの唯一作。前半は恐らく唯一のアルバムで、後半ボーナスは主要人物であるプルースト(François Proust)による自作自演、劇場用の歌曲のようだ。詠み人知らず、オルレアン民謡、中世の詩人ヴィヨン(François Villon:1431?-1463?)の詩に曲をつけた電化民謡である。ロック色はほぼなく、深い響きの語り風フランス語シャントと完全に中世世俗歌的民謡の世界。効果的に使われたソリーナやシンセの音が暗く湿った不思議な感触を醸し出している。
“Ragnar Lodbrock”は“毛むくじゃらの半ズボン”の意でデンマーク王(774-854 or 796-865)であったらしい。イングランドのヨークでイングランド王アエラの急襲で殺害される。その模様が臨場感溢れるアルバム中のオラトリオ大曲「ラナール・ロドブロクの追悼歌」なのだろう。サガは中世北欧神話のこと。

Arte Nova
74321 59227 2
Fioretti del Frescobaldi/Frescobaldi, Girolamo //Krumbach, Wilhelm
たまにはイタリアものなど。フレスコバルディはそれなりのヴィノと特級オリーブオイルで著名な現在も存続するフィレンツェの侯爵家の一つ。共和制だからそういう階級が制度的に残っているわけではないのだろうが、まぁ、どこも同じだな。その何代目かは知らないが、ジロラモ・フレスコバルディ(1583-1643)は、ローマ・カトリックの総本山、サン・ピエトロの終身オルガン奏者としてそれなりの地位にあったらしい初期バロックの作曲家兼奏者。大バッハより100年ほど早い。いわゆるフーガとしての対位法の基礎等、バロックのオルガン曲としての原型はこの時期にほぼ完成していたように思われる。どちらかというと暖かめのシンプルな曲調で、劇的なのはラストのトッカータぐらいかな。すべてオルガン曲ですが変化に富んだ旋律と敬虔な上品さが心地良い。たぶん天井高さが30mくらいある伽藍で聴くとまったく別ものに聞こえるのだろう。タイトルは『精華集』、『業績』の意で世界初録音になる模様。98年のデジタル録音で、奏者はヴィルヘルム・クルムバッハなるドイツ人のようです。

apex 2564 60522-2
2003
Missa ad Usum Cappellae Pontificiae, 6 Motets/Scarlatti, Alessandro //Ensemble Vocal de Lausanne, Michel Corboz
アレッサンドロ・スカルラッティ(1660-1725)はバロック初期の作曲家。爛熟期に主としてチェンバロ曲で膨大な業績を残した息子のドメニコ(Domenico)のほうがはるかに有名で、スカルラッティといえば一般に息子のドメニコを指す。シチリアのパレルモ生まれ、主にナポリ楽派オペラの第一人者としての功績が評価されているようだがオペラはよくわからん(笑)。膨大な数のオペラ、歌曲を残したとされるが再評価が始まったのは20世紀後半で、今のところ音源はあまり存在しない。
本作は晩年、ローマに移った時期に作曲されたミサ曲と宗教歌6曲を集めたもの。パレストリーナの伝統と格式を意識した“Stilo antico(古様式)”といわれるルネサンス・ポリフォニーを多用した厳かで気品に溢れた四声のための宗教曲です。「Missa ad Usum Cappellae Pontificiae(教皇の通常ミサ)」は典型的な通常文ミサで、歌唱はコルボらしい情感と清明さに溢れたもの。25名による合唱はモテットもすべてア・カペラで器楽演奏はなし。
1965年の古いライブ録音ですが、音場は狭いながらもデジタル・リマスタリング済みで音像は透き通るようにクリアです。

SKY
CD 3042
Beautiful Lady/Jane
80年初頭に崩壊し、86年にドラム+歌のペーター・パンカによって再編された、所謂ペーター・パンカズ・ジェインの第一作。70年代のプログ風味の上に構築されたポップで、後に隆盛するB級プログ・メタルの原型といってよいだろう。こなれたリリカルなメロディとシンプルなリズム、ノリノリのグルーブと売れていた記憶は皆無であるが、売れてもおかしくはない要素は包含されている。歌詞はすべて英詩、クラウト色は徹底的に隠蔽されている。ラスト「Imagination」に至ってはオリジナル曲の中間にレノンの「Imagine」を挟む有様で、節操がないというべきか、純粋なオマージュというべきか、呆気にとられること請け合い。
ボーナスはタイトル曲「Beautiful Lady」のマキシ・シングル長尺ヴァージョン。長短長という転調が決まった小気味良さが気持ちよい佳曲。

Cherry red record
ACMEM 24CD
Me and a monkey on the moon/Felt
80年代リリカル・ネオ・サイケ、フェルトの10作目にあたるラストアルバムの再発リマスター紙ジャケ仕様。中期以降は現プライマル・スクリームのダフィー(Martin Duffy)のキーボード主体の音作りにローレンス(Lawrence)の儚げな歌(死にそうな声)、ギターが乗るというかたち。全曲コンパクトな歌ものになって若干投げた? 的な刹那感が漂うが、曲はそれなりにシンプルでストレート、一段と聴き易くなった。歌詞も最終作を意識したような総括的内容で意味深でシニカル、思索的な前作までとは趣が違う。結果的に個性が埋没したあたりが最終作となった由縁なのか、10年の達観の成果なのかは不詳である。繊細な柔らかさは踏襲されているものの、黄昏た薄暮感が薄れたのか、ところどころ今までにない明るさが感じられる。非常にメロディアス、かつ構成展開がきちんと確立された音楽なので安心して聴けますが、しっとりと息づいた耽美と叙情性の表現は相変わらず見事です。
しかし、人気がないな。これだけの質と継続性を持ちながらほとんど知られていないというのはやはりインディだから? プロモーションそのものと無縁だったのかもしれないが。
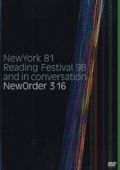
Rhino
R2 970194
316/New Order
81年のニューヨークでのライブと98年のレディング・フェスでの映像。前半ではデビュー直後(というかイアン・カーティスの自殺でキャンセルになったJoy Divisionのアメリカ公演のやり直し版かな?)の鋭利な若々しさを、後半では20年弱の歳月を経てすっかり変形した形状を露呈しておりまする。一瞬、同一人物とは思えなかったが……人のことは言えんわな。(笑)
ライノの音源ということで画像、音質的には問題なし。質量ともに非常に明瞭で良質な出来ばえです。問題は中身。正直、手品の種明かしを見ているようで困ったな。
前半はおそろしく素っ気ない、ついでに観客も困り果てているような不思議なライブ。MCも一切無しで淡々と間違えながら曲を演奏しています。人間シーケンサ的役割を果たすリズム隊の精度とクールなグルーブはなかなかのもの。神経質でピリピリ、暗鬱でシャープなイメージ通りの演奏ですが、サムナーと鍵盤は下手。楽器も歌も辛いものがある。
後半レディングの方は半分カラオケ大会のようなもの。人間には弾けない基本的なリズムのシーケンス・パターンはよいとしても、誰も弾いていないフレーズが満載でその場で踊っていればわからないのかもしれないが、DVDで見ていると正直しらける。リズム隊(特にエレドラ叩いているときのモリス)のパフォーマンスは体型を含め概ね及第点だろうが、ベースラインは機械だし、フックの手元は高音弦をスルスル、モリスも機械に音を重ねているといった趣。鍵盤のギルバートおばさんに至っては機材に貼り付けた紙を見ながらプリセット音片手一本指奏法、JDの曲はまったく弾けず指すら動いていない。サムナーの歌は格段に上手くなっているとはいえ、変な奇声を上げるわ、横目でちらちらモニターの歌詞見ながら歌っているし、歌を歌いながらギターは弾けないアマチュアレベルのテクニックが寒すぎる。ピアニカ吹いているのは可愛いけどねぇ。それでも一見きちんと曲になっているあたりが最近のライブっちゅうことなのでしょうか? ということで、コンピュータ時代のライブそのものに意義がどれだけあるのか、疑問が残る内容であった。「True Faith」「Bizarre Love Triangle」に「Temptation」、あるいはJD時代の「Isolation」や「Atmosphere」などなど、スタジオワークとしての曲の出来が衝撃的だっただけに、あえてライブに打って出る必然性がよくわからないというか、困惑させるものがある。否、既に他人には出来ない芸を見せる演奏会ではなくて、皆で一緒に踊りにいく団体体験パフォーマンスみたいなものに転換していると考えるのが適切なのだろう。
132分。タイトル『316』はJDの曲が3曲、NOの曲が16曲という意味。NTSC、リージョン1。海外で購入したCDよりも安い米盤(一般的にDVDのほうがCDより安い)ですが、普通に日本語字幕あり。日本で出ている日本盤というのは歌も吹き替えで日本語で歌っているのかな?(笑) ということで次回『511』に続くかも。
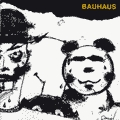
BBL 29 CD
Mask/Bauhaus
災厄の80年代初頭を象徴する頂点ともいえる二作目。かつてはオルタナ、後にポジティヴ・パンク、今はゴスという括りがなされるが、どれも馴染めるものではないというか、どれでもよいさ。何のための差別化かよくわからん。投げ出したようなリズムと暗鬱神経症的ヴォーカル、神経を逆なでするようなギターワーク。お世辞にも上手いとはいい難いが、それを補って余りある鈍い暗灰色のくすみ、あるいは呪い。タイトル『MASK』は現代詩人ローグ(Brilburn Logue)の1981年の作と何らかの関係があるのだろうが、わしゃ知らん。
これはラジオが壊れ、ウラニウムの蘭がぱちぱちいうときのためにある。
これはフェーン風が吹いて一握りの骨のような電信線をガタガタ揺らすときのためにある
これは夢の救急車が深夜に通りをすれすれに走り去るときのためにある
これはおまえが眠れる暴動に巻き込まれ、天が崩壊するときのためにある
これはおまえのセックスがヴードゥーに満ちるときのためにある
これはおまえの服が想像的であるときのためにある
これはおまえの肉体が縮こまり、二度と戻らなくなるときのためにある
恐らく、LP発売時にもこの文言が内スリーブに記載されていたはず。フェーン風というのはいわゆるフェーン現象が起きるときに吹く乾燥した熱風のことで、ヴードゥー(Voodoo)はハイチの土俗宗教というか神秘主義的呪術を指すのだろう。
「Mask」
影の男は粘土の中で考える
息詰まる日常の罠にはまった思想を夢見て
鉄の仮面を着けて見出したもの
のみで彫った眼のためのスリットからプラスティックの汗を流しながら
物言わぬ口の下で広がっていくもの
聞く耳を持つならば、おまえにはわかるはずだ
酔いつぶれたキュビストの母音字体
模造された頭部の芸術から
模造された頭部の表現から
変身が施され
神秘的で屈辱的な方法で
自分であるところのものが、何か他のものに置き換わるまで
分割された性格、分断された感覚
その影こそが実体だ
これもまた、わかったような、わからないような、意味があるんだかないんだか、自己韜晦的で象徴的な、するりと入れ替わる気持ちの悪さと、内スリーブにも掲載されているデレク・ジャーマン風の容貌が気色悪くも目を惹く。シングル曲がボーナス・トラックとして5曲追加。

CTCD-047
Live in Tokio/Amon Düül II
ありぃ? 間違えたかな? と思わずスリーブを見直すブレイクビーツ・テクノにぶっ飛ぶ96年、東京での還暦(ぐらいだろ)ライブ。いやぁ、元気な爺婆だこと。選曲も主に近作『虚無月照番号』に過去の名作を加えたもので、プロモーターと結託した出稼ぎ老人にありがちな、ヤル気ないけど過去の思い出・昔の名前で出ています状態を回避しているあたりは老いても枯れぬ意欲と心意気が感じられる。もっとも、70年代における捉え方(というか国内での販売戦略)があまりにもアングラ・サイケ的不良芸術集団を強調しすぎたもので、『倫敦実況』でも聴かれるように本来はずっとストレートでババリア・ローカル色も薄く、偏屈ではなかったと捉えるべきだろう。
おのぼりさん的集合記念写真は昭和33年築の懐古的国威発揚塔の大展望台でのショットだろう。微妙に斜めに傾いだスチールマリオンとスチールサッシ、どんくさい棕櫚の植木鉢にカタカナで“ハイソフト”(キャラメルだっけ?)などという看板が素性をいみじくも露呈しているといえよう。この塔、今までに二度登ったことがある。もちろん往復ともにエレベーターだが、最初はまだ年齢が一桁だった頃、母親に連れられて。主眼は蝋人形館だったような気がするが、浜松町から延々歩いていく途中、増上寺の緑を基壇に威容を誇る当時としてはその未来的なフォルムに圧倒されたものだ。
二度目はすっかり枯れはじめた頃、外苑西通りを南下し青山墓地の中で外苑東通りに抜けるつもりが六本木のトンネルを潜ってしまい、道を間違えたが適当に転がしていたら夕闇が夜に呑みこまれる頃、煌々とオレンジ色にライトアップされた元は増上寺の墓地である塔の足元に乗り入れた。ノスタルジー、老朽化、晩夏の東京は濃い藍色のイメージに埋没していった。しかし、形状はともかく、あのアナクロな色彩にはどうも馴染めないな。
ちなみに基壇部にある蝋人形館を含む観光ビルはバブル期くらいから日本マクドナルドの社長一族の所有物らしく、趣味のクラウト音楽関連でコアかつ思いっきり場違いな商売をしているそうです(行ったことがないので伝聞です。本作やライブの招聘にも何らかの関わりがありそうです)。

EfA 4122/23
Magma live/Magma
六作目に当たるライブ二枚組。全盛期マグマによる最高の、あるいは奇跡的なパフォーマンス。75年6月パリでの録音。当時のライブ録音としては音質もそれなりで、ぶいぶい歪み唸るパガノッティのバスもロックウッドのヴィオロンもヴィドゥマンの鍵盤も人間業とは思えない凄まじいまでの演奏を繰り広げるが、ヴァンデールのドラムは基本的にジャズドラムで、前のりでかつチューニングも固めだから重くもたつくことはないあたりがマグマのマグマたる由縁かもしれない。重量級でありながらの強迫変拍子突撃感は他には真似の出来ない超絶テクニックによってもたらされたものであることがよくわかる。基本はアレンジされた楽曲の再現で、全体構成は破綻なくかつ最良の緊張感を保って進行する。ただし演者がライブ向きだったせいかスタジオ版よりも遥かに迫力に富んでいる。
まぁ、当時はそれなりに斬新に感じたりもしたものだが、今となってはグロテスクな非尋常さだけが誇張されるきらいはあるか。却ってヴァグナーあたりのドイツ・ロココ風時代モノ歌劇の古臭さと、援用してみたものの消化しきれていない感覚的稚拙さが滑稽に思えるかもしれない。ジャケ写真はBraved Zumizionというマグマ専属のライトショウ・チームによるイメージの投影。このご尊顔はツタンカーメンですか?
最近のCDではタイトルに副題がついていたり、追加曲があるようですが、音源はLPのみなので詳細は知りません。

Apache
4509-90069-2
Double jeu/Berger+Gall
ミシェル・ベルジェ(Michel Berger:1947-1992)とフランス・ガル。夫妻による92年の、結果的にはベルジェの遺作となった最初で最後のデュオ・アルバム。研ぎ澄まされたセンスと洗練、針の穴を通すような緊張感と切なさがない交ぜになったような乾いた抒情が全編に漂う。奇を衒わず劇的な要素を排除し、淡々としていながらも印象的な曲と、意味深で非常に重い歌詞を書くベルジェの溢れる才能が遺漏なく発揮されている。かつてのフランス近代音楽の系譜に連なる非常に独特な構造と構成、諧謔的なメロディと先鋭なリズムが織り成す極上の空気感は筆舌に尽くしがたい。凄いな、このベルジュという人。
「市場の通路(Les couloirs des Halles)」
その部屋の天に
鋲で留められたありとあらゆる写真
夢の中のドアのように
風に飛び散るかもしれない
でもそれは、彼女の一部でしかない
宛名の変更が偶然だとしても
それは彼女の一部でしかない
見せ掛けの優しさを見たとしても……
それでもやはり、それが愛なのだ
彼女が夢見たことではないにせよ、いや違う、むしろ、いいことじゃないか
それでもやはり、それは愛なのだろう
彼女が望んだことではないにせよ、いや違う、むしろ、いいことじゃないか
中央市場の通廊で
迷った視線がすれ違う
誰かが悪いのではなくて
誰かが忘れたのでもなく、誰かがケチったわけでもなく
数時間の間
彼女は思い起こした説教を繰り返す
彼女はそらで暗じている
恐れを遠ざけるすべての言葉を
それでもやはり、それが愛なのだ
彼女が夢見たことではないにせよ、いや違う、むしろ、いいことじゃないか
それでもやはり、それは愛なのだろう
彼女が望んだことではないにせよ、いや違う、むしろ、いいことじゃないか
行間省略し過ぎ。指示代名詞多過ぎ。韻の踏みかたとデュエットのパート分けは決まり過ぎ。
尋常でない露出度を誇るバスはもちろん盟友ジャニク・トップ(Jannick Top)、ギターはクロード・アンジュといういつもの布陣。おかげでそれなり(に凝っている)の太鼓+プログラミングが浮き気味ながらも、プロフェッショナルで鮮烈なアレンジが堪能できます。いわゆるポップ領域の音楽でありながら、こういった特異なベースラインを採用し、生かせるコンポーザの才能も賞賛されるべきだろう。地鳴りベースの神とまで崇め奉られたトップがマグマを捨てて何故ベルジェと組んだのか、答えはここにある。