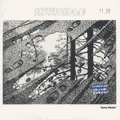
Columbia
2-493866
Invisible/Invisible
あちこちで名前を見ることができるスピネッタ(Luis Alberto Spinetta)なる人物が主宰するアルヘンティーナ(Argentina)のユニットの1st。緊張感に富んだハード・サイケ風の感触ながらも土地柄ラテン臭が漂うコンプレクス。後の透明感溢れる繊細さの萌芽も十二分に感じとれるが、インパクトの強い変拍子やテクニカルな転調、複雑でシャープなリズムチェンジが冴えるロック色の強さが特徴。歌詞は南米スペイン語。ジャケを見ればなんとなく感じとれるように、とてもナイーブで感受性豊かな自然観が伝わってくる。
おそらくリマスターされているのでしょう。音像は鮮明で細かいニュアンスの表現力も失わない優れた仕上がり。再発品はすべて紙ジャケ。ただし普通の紙ジャケと違い大きさがジュエルケースと同じ高さで並べるのに大変都合がよい。
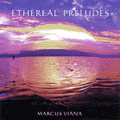
Sonhos e sons
SSCD068
Ethereal preludes/Viana, Marcus
タイトル通りの『天上の序曲集』。全曲ピアノ・ソナタ。ピアノに関して学術的なバックグラウンドはない(正規のピアノ教育を受けていない)と自ら述べているように、本業たるヴァイオリンとは勝手も違うだろう。上手くはないし技巧的に優れているとも思わないが、がしかし、やはりそこはそこ。魂を揺り動かすヴィアナの音楽としての質は保たれているといえるだろう。ミナス特有の滴り落ちそうなリリカルさがしっとりと濡れた豊饒な耽美と恍惚を目の前に現出させる。
この前奏曲集は彼が進める『地球の音楽』シリーズの主要な道程の一つであるらしいが、うねる川面が押し寄せるような感情の高ぶりに触発された“即興”によるもの、と説明されている。3分から11分ほどの全11曲。録音も奥行きのあるアンビエントな立体感を強調したもの。所謂ピアノ弾きのソナタ集とはほぼ対極にある音像であろう。
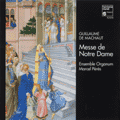
Harmonia Mundi
HMC 901590
Messe de Notre Dame/Machaut, Guillaume de //Ensemble Organum, dir. Marcel Pérès
単独の作曲者によるものでは現存する最古の通常文ミサといわれるノートルダム・ミサ曲。12部に分かれた計56分36秒。ギヨーム・ドゥ・マショー(1300頃-1377:マショーはシャンパーニュ地方の地名。“川向こうの権右衛門”という表現とあまり変わらない)は、アルス・ノーヴァ(Ars Nova=新しい技法)の最も著名な作曲家。新しい記譜法とリズムの導入により複雑な音楽を表現できるようになった。ちなみに、これ以前のゴシック期の音楽をアルス・アンティクア(Ars Antiqua=古い技法)というが、今云う“ゴス(ゴシック)”というのは、雰囲気のみ聖堂宗教歌の残響とほの暗さを模しているのであって、音楽理論的にはバロック以降の古典~現代音楽の範疇である。
演ずるはアンサンブル・オルガヌム、指揮を含め計8名の男声合唱ないしは男声ソロで、中世中期の簡潔で素朴な(そしてある意味異様な)多声化されたモノフォニック・メロディ(=オルガヌム)が堪能できる。間延びした野太さと優美な敬虔さが同居するあたりは、現代曲にはあり得ない茫洋とした冷暗さを感ずるくらいだ。
もっともこの時代のものは、現存する楽譜が現代とはまったく異なり、その解読や解釈をめぐり、演者によって音程や音階を含めかなり違ったものになるのが普通であって、曲の長さなどもけっこう異なったものが多い。本来は器楽との合奏であったと考えられているが、この版は合唱のみで器楽なし、ただし合唱部はキリエの繰り返しの回数などでは楽譜を忠実に再現した版らしい。95年のデジタル録音で薄ら寒くなるほどの触感は見事。
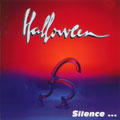
Musea
FGBG 4257.AR
Silence......au dernier rang!/Halloween
同じくフランスのこちらは現代もの。呪術的で少し妖しいアルトとヴァイオリン入りの6人編成、ジャズ・ロック基調の四作目にあたるライブ盤。初期は英詩でタイトルも英語ながら暗鬱なネオ・プログ。三作目あたりから専任女性歌手を得て基本線は変わらないものの、しなやかなセンスと洒落た華やかさがそこはかとなく匂う。それほど長曲はないが、よく練られた複雑な展開と独特のクールな変拍子に乗るほの暗いメロディが新鮮だ。女声によるVDGGのカバー曲「House with no door」入り。名称はアロウィン(ハロウィン)だが宗教色は薄い。ハロウィンの起源はキリスト教化される以前のケルトのサウィン祭に求められるが、ブルターニュの突端ブレスト出身ということでルーツといえばルーツなのだろう。もっとも、田舎臭さはほぼ完璧に払拭されて、ブルターニュの冷湿なケルト風土色はほとんど感じられない。
密やかで少しドスの訊いたジェラルディン・ル・コック(Géraldine Le Cocq)なるお姉さんが主唱ですが、ルコックといえば雄鶏(Le Coq)にして探偵だな。
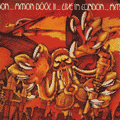
Repertoire
REP 5005
2003
Live in London/Amon Düül II
おそらくその特徴を最もよく表して、世間的にもその真価が認められた絶頂期72年12月の実況録音盤。ツインドラムズの7人編成+敏腕プロデューサと構成的にも黄金期。このころの映像は残っていないのだろうか? つくづくもったいない話だ。リマスターとはいえ元の録音が今一つで低音がこもり気味なのだが、元祖太鼓集団の発展型としてのドコドコ乱れ打ちすっとこどっこい連打の迫力は十分感じられる。公演にあたって急遽ペータ・レオポルトが呼び寄せられたらしいが、このあたりはプロデューサ、オラフ・キュプラー(Olaf Kübler)の才覚によるものだったらしい。美麗ながらも呪術的に直立して謳い上げるレナーテ・クナウプのヴォーカルも含め、その視覚的要素は極めて奇異かつ新鮮なものだっただろう。二、三作目あたりの曲が中心で、「ジンテルマン」の咽び泣く中近東メロディや中間部のシンセと雄叫び(雌叫びか)即興に興奮したものだ。
ちなみにジャケ・デザインは他と異なり鍵盤のログナー(Folk U Rogner)ではなくておそらくイギリス人によるセンスの欠片も感じられない醜悪なもの。さそりのような侵略者がドイツ軍のヘルメットを被っているあたりが如何にもといった感覚。あまり感心しないリミックスのボーナス2曲入り。2003年のリマスターはエロック(Eroc)によるもの。

Garden of Delight
CD 028
1998
At the cliffs of river Rhine/Agitation Free
こちらもほぼ最盛期、というかオリジナルの末期に近い構成員による74年2月のケルンでの発掘ライブ盤。40分弱と短いが『Fragments』に比べてもライブのわりに音質は非常に良好。「Through the moods」や「Laila」など代表的な曲を含む、延々とうねりのたうつ歌なしジャズ・ロック・ブルーズ。職人的な技巧安定度もさることながら、切れ味鋭い音像は年代ものの古さをまったく感じさせない。映像残っていないのかな。
ギターレ二本にバス、鍵盤、太鼓という簡素編成ながら、静から動、寂から激に移り変わる変幻自在の即興アンサンブル、強力なリズム隊とアンビエントで鮮鋭な鍵盤の織り成す万華鏡的多面展開には唸らされる。特にヘーニッヒのシンセの扱いは今聴いても群を抜いている。ついでに極めてドイツ的にリリカルでロマンティック、決めるところはビシッと決まるので、芋臭いのが相場のクラウトととしては破格に格好良い。

Scribendum
SC 027
Symphony No.7 in C op.60/Shostakovich, Dmitri //Svetlanov, Evgeny USSR State Symphony Orchestra
冬となればやはり凍てつく厳寒の鋼、スヴェトラーノフ(Evgeny Svetlanov:1928-2002 公式Webがあるのだなぁ)でしょう。ドミトリ・ショスタコーヴィチ(1906-1975)による通称『Leningrad(レニングラード=現サンクト・ペテルブルグ)』、4楽章76分におよぶ長尺曲ですが、映像的でパワフルなWW2をテーマにした標題音楽です。初演は1942年、ドイツ軍に包囲されたレニングラードで。まぁ、一般的には国威発揚ものととられた時期もあったようですが、ペテルブルグ人にとっては田舎もんのスターリンに散々痛めつけられた記憶もあるので、微妙に複雑、かつ表裏が巧妙に錯綜した仕掛になっているというのが最近の評価らしい。
演ずるはクラシック界のへヴィ・メタル、ソ連の怪人、エフゲニィ・スヴェトラーノフ+ソ連国立。78年の発掘ライブ盤です。(少なくとも第一楽章は)鋼のような弦と咆哮する金管、炸裂するパーカッション。品とか繊細とかそういった概念とは無縁のパワー。暴虐と絨緞、殲滅と蹂躙(読めるけど書けない漢字ばっかり)などという言葉に表象される、平原を埋め尽くす精鋭機甲師団と自動車化狙撃師団の怒涛の進撃のようだ。山は削られ谷は埋められ、街は瓦礫と化し森は荒地と化す。通り過ぎた後には何も残らない。……などと評されることが多いようだが、まぁ、それは殊更差異を強調して購買意欲を煽るという戦略と、ロシア(あるいはソ連)にたいする、長年に渡って植え付けらて来た陳腐なイメージの恣意的展開に過ぎない部分が多いように思える。振幅の大きさはロシアの大地の豊かさであろうし、耳を澄ませば母性的なまでの繊細な美にたいする共感と憧憬が滔々と流れているのではないか……と思っている。
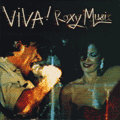
Virgin EG
7243 8 47436 2 8
Viva! - Limited/Roxy Music
『Siren』後、1976年、6作目にあたるライブ。常連以外としては鍵盤と電気ヴァイオリンにジョブソン(Edwin Jobson)、ベースにウェットン(John Wetton)乃至はガスタフソン(John Gustafson)がクレジットされている。個人的に好みの範疇に入る前半期のロクシーではあるが、やはりロクシーはスタジオ・バンドであるのだろう。はっとするような音の鮮烈さ、新鮮味はライブではタダのロック音楽に堕してしまう。名曲揃いで、テクニックも初期に比べれば雲泥の差であるが、視覚的要素があればより愉しめたのだろう。
この手のものは何も考えずに適正価格であることだけを判断基準に買っているのだが、タイトルの“Limited”は出し入れが面倒で使い勝手が悪い紙ジャケのことを表しているようだ。
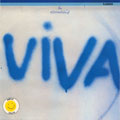
Teldec
244 113-2
Viva/Düsseldorf, La
同じく『万歳』タイトルのラ・デュッセルドルフの二作目。ノイの片割れ、クラウス・ディンガー(Klaus Dinger)に弟のトーマス(Thomas D.)、同じくノイのハンス・ランペ(Hans Lampe)が基本構成になるトリオ。20分越えの大曲「Cha Cha 2000」にピアノで追加二名がクレジットされている。人力テクノの一つの完成形。クラウトでありながら、クラウトの枷から解き放たれ、英米音楽が作り出す産業ピラミッドをも乗り越え、時代を超えた普遍性を獲得した稀有な例だろう。
敢えて訳すほどのことはないのかもしれないが、英語とドイツ語とフランス語とイタリア語がゴタ混ぜになった脳天気な歌詞は生の肯定に満ち満ちている。
頭の「Viva」
万歳 惑星、地球
地球
人生、愛、子供たち
そして、今日。今を愛する
愛は我々の世界にある
愛と生
愛は我々の世界に生きる
我等の地球
万歳
万歳 万歳
地球の我等
万歳 万歳
我等の地球
万歳 万歳
我等のすべての愛に
我等のすべての生に
万歳
閉めの「Cha Cha 2000」
チャチャ二千年
未来が呼んでいる
未来が呼んでいる
チャチャ二千年
チャチャ二千年
未来で踊れ
私と共に
チャチャ二千年
チャチャ二千年
未来へ踊れ
私と共に
チャチャ二千年
チャチャ二千年
用心せよ
誰も我々の夢を壊すことはできない
チャチャ二千年
チャチャ二千年
用心せよ
ブルーレーザーの眼は
楽園を見るが
恐怖は成長し
世界は破裂し
新しい秩序の元に再編される
我々誰もが必要とする
チャチャ チャチャ チャチャ
それは変革
我々の誰もが変革を望んでいる
弱者を気遣い
貧困を分かち合い
我々が導かれる世界
それは劇的な展開に満ちたもの
チャチャ 美しい都市
チャチャ 美しい都市
だから
車から降りて
自らの足で歩き
自らの身体を動かして
食べるだけの生よりも
豊かに
泥酔せず
煙草も吸わず、薬もやらない
考えることから始めよう
そして、働くことを始めよう
自らの内に深く
これこそが
楽園への第一歩
心を開き
目を開けば
さぁ
それが楽園を作り出す
川は青く
大気は澄み渡り
草地は緑に覆われた楽園を
よりいっそうの労働と
我等を愛し、騙すことのない
より良い指導者が必要とされる
我等の必然
それは努力 努力
二千年 を得るために
二千年 を得るために
チャチャ二千年
技術の共鳴
経済の共鳴
空想の幻想
我々はそのすべてを手に入れたが
いまだそれを理解できず
見ることもできない
問題は膨れ上がり
我等を押しつぶす
深い夢にまどろんで
やがて目を覚まし
感覚を取り戻す
その手法を
その可能性を
やがて
太陽に向けて
最初のステップを登り
それを感ずる
二千年を
如何にすべきか
さぁ、実行のときだ
未来で踊れ
チャチャ二千年
未来に向けて踊れ
チャチャ二千年
レーザーブルーの眼は
楽園を見る
すべての戦争が終り
愛の未来が到来する
弱者をいたわり
貧困を分かち合う
二千年
そのドアの前に立っている
う~ん。弥勒信仰のようだな。こちらは22年後、弥勒は56億7千万年後だけどなぁ。もちろん、彼らが(あるいは我々が)望み夢見、足掻いたはずの来世は来なかった。
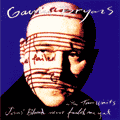
Point Music
438-823-2
1993
Jesus' Blood never failed me yet/Bryars, Gavin
ギャヴィン・ブライヤーズは元ジャズマンの現代音楽作曲家。75年ごろにA面「タイタニック」、B面本曲というLPでリリースされていたものの拡張再録音盤。『イエスの血は決して私を見捨てたことはない』というタイトルは、ロンドンのとある駅頭で老人が即興でメロディをつけて歌っていたものをワンフレーズ録音したもの。そのワンフレーズ
Jesus' Blood never failed me yet
Never failed me yet
Jesus' Blood never failed me yet
There's one thing I know
For he loves me so...
を延々とループさせながら微妙に抑揚のついた弦楽室内楽が儚げにメロディを奏でるといった構成だった。当時のLPはその物理的限界ゆえに25分程度の曲であったが、この新録音盤はCDの限界74分に拡張され、若干エモーショナルで大仰なアレンジとボイスを後半に加えたものになっている。バックも50人編成くらいのオーケストラになって、16人編成の合唱団付とえらく裕福になって個人的には違和感ありまくり。オケの指揮者がグラス子飼いのリーズマン(Michael Riesman)だったりして、あぁ、なるほど。
おかげで飲んだくれて痩せこけて蹲って死にかけている老人浮浪者の絶望的な諦観はきれいさっぱり消し飛んでしまった。当時はどちらかというと「タイタニック」よりも、こちらの染み渡るようなやるせなさに感銘を受けた。元のLPをそのままリマスターしたCDもあるようなので買い直そう。
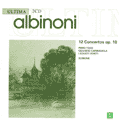
ERATO
0630-18943-2
1997
12 Concertos op.10/Albinoni //Scimone
凡そゲージュツに邁進し、偉大な業績を成し遂げた過去の偉人たちは、昨今の売れっ子アーティストとは異なって貧困に喘ぎ、病に苦しみ、果ては狂死したり、ボロ屑のように社会の底辺でのたうちまわり頓死していったものだが、トマゾ・アルビノーニ(Tomaso Albinoni:1671-1751)は異例中の異例、ベネツィアの紙問屋の若旦那として悠々自適、嫌々教会に就職なんぞせず、現実のよしなしごとはすべて番頭にうっちゃって優雅に趣味の音楽に勤しんだと。
全部で12のヴァイオリン協奏曲で構成された協奏曲集第10集。10集というからにゃ、1から9まではあるのだろうが、5,7,9集しか見たことはない。楽譜が散逸して、現存しているものも部分だったりとその作品の大半は消失しているようだ。バロック期の宿命のようであるが、同時代人であるバッハはほとんど残っているところをみると宮廷や教会といったバックの差なのだろうなぁ。
この作品10は弦楽と極一部ハープシコードを使った室内楽。多彩でカラフル。明るくしなやかで上品、春うらら、きらめく陽光、そしてその背景としての冷たく湿ったベネツィアの冬を思わせる艶やかな旋律があまりにも見事なバロッコ・イタリアーノ。1979年のアナログ録音をリマスター済み。シモーネ(Claudio Scimone)指揮、モダン楽器による演奏はI Solisti Veneti。極上です。
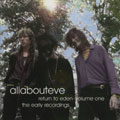
aaevp5
Return to eden - volume one - the early recordings/All About Eve
1stアルバム以前、自主制作時代の音源、シングル、同B面、デモ、拡張リミックスをまとめた初期補填集。多くはシェイプアップされて1stないし2ndに収められている。時代のせいかもしれないが、正規盤に比べ歌もアレンジも生々しく元気がよい。歌詞も初期ドラフト・ヴァージョンだったり、中世伽藍風残響たっぷりのしゃかりきアップテンポなアレンジが多くそれはそれで面白いか。冒頭は85年の初シングル「D for desire」で、裏声にならない初期コクトー・ツインズのダーク・サイケそのもの。ときにはけだるく、ときには切なく謳い上げるリーガンの御声も張りがあって良いねぇ。ちなみにタイトルの“Eden”は、メジャーからアルバムデビューする前にシングルをリリースしていた自主レーベルの名でもある。
一応、第一巻とあるから続編が出るのかもしれないが公式Web(http://www.julianneregan.net/)? にも音沙汰はないな。
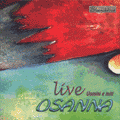
Afraka
SS-002 A-B
Live -Uomini e miti/Osanna
2003年に行われたオザンナを中心にした70年代プログ・イタリアーノ懐メロ歌謡ショーの実況実演版。オザンナ以外の、ニュー・トロルスのご老体ヴィットリオ・デ・スカルツィ、アレアのファリゼリ、バンコの元達磨(見違えるほど痩せた)、ソレンティの妹、バレット・ディ・ブロンゾを乗っ取っちゃったお化粧あんちゃんあたりは、老けてはいるが中身の伴った内実をさらけ出せているという点で見応えがある。
オザンナは原初構成員のカンテ、リノ・ヴァイレッティ(Lino Vairetti)を中心にした編成で、70年当時の首領、ダニーロ・ルスティチの姿も見えるには見えるが、無理やり連れ出されたような、もはや立つことすら出来ない廃人ぶりを晒すだけでなんとも無残なものだ。基本は『Takaboom』アレンジの再現で、かつてのおどろおどろしい土俗祭礼隠滅因習暗黒邪宗仮面舞踏的な切れ味も真美も感じとることは難しい。ステージ・バックに『ゲルニカ』を飾るあたり何らかの意図はあるのだろうが陳腐な底の浅さを覆すには至らない。
最後におまけで入っているインタビュー・シーンにはターリャピエトラ+ミキ・デイ・ロッシのオルメやプログ・イタリアーノに関わりの深かったピーター・ハミルも登場する。そのライブシーンが収められていないのは随分だな。DVDとCDのカップリング。CD前半はDVDと同じライブ音源、後半はスタジオ音源。新曲なし。DVDはPAL、リージョン2。

Mute
ALCB-285
Madra/Miranda Sex Garden
微妙に刺激的な名前だが、これがまたジャケ通りの女性トリオ・コーラスグループの初作。前回のお色気ぷんぷん匂ってきそうなバナナラマとは正反対、清廉潔白なる古楽風ア・カペラという、およそ現代においては呆気に取られて唖然と開けた間抜けな口が塞がらないような奇天烈ぶりを上品に呈示する古謡なのである。イングランドの所謂トラッド・フォーク/ジャズ・ロックといわれる音楽が純粋な自国の伝統に根ざしたものでなく、実際にはアメリカン・フォーク/ジャズ・カントリーの影響下にあるような恣意的な錯誤は感じられず、ダンスタンブル(John Dunstable:1390頃-1453)からタリス(Thomas Tallis:1505頃~1585)に繋がるルネサンス音楽の系譜の上に花開いた、16世紀イングリッシュ・マドリガルの作曲家であるモーリー(Thomas Morley:1557-1602)あたりを中心にした英語世俗歌の現代版といった趣である。全25曲、すべてア・カペラ。一曲、重鎮パレストリーナ(Palestrina)なんぞも混じっているが、英詩に置き換えられている。
残念ながら二作目以降は更に女性が二人加わるものの、若干の楽器を導入したアンビエント・サイケ・コーラスのような作風に変化してしまう。根本にレーベル側のゴシック・ブームにあやかろうという販売戦略が透けて見えてしまうのが玉に傷であることは否めないのだが、ご当人たちは純粋に古楽方面の出身らしいし呈示されているものは努めて真摯なものであることを評価しておこう。リリースはイギリスのインディ、ミュートから。
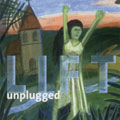
OHR
140011-2
Unplugged/Lift
70年代D.D.R.時代の生き残り、リフトの2000年近作。もっとも生き残りは鍵盤+主唱のローゼ(Werther Lohse)一人で、ヴァイオリンの女性が歌も歌って、アコギ(兼ギターシンセ)を加えたトリオ編成での非電化(じゃないじゃん)実況録音盤。録音はかなり小さな会場のようですが、おそろしく鮮明な音像と雰囲気が伝わってくる秀逸なもの。基本は歌物ですが、かつての名曲のオンパレードにイントロが始まっただけで観客が大騒ぎ。
一曲の中でDUR⇔MOLLところころ移り変わる変幻自在な独特の転調が、ヴァイオリンの儚い旋律に乗るときの圧倒的なまでの哀感はドイツ人好みのドイツ歌謡なのだなぁ。おそらく演者も聴者も89年以降は手に入れたはずの夢が結局のところ別の欺瞞でオブラートされていただけであることに少しづつ気付き、否応なしにそのより強大な力に翻弄されてきた人たちでしょう。ローゼのMCや聴衆の反応に何ともいえない痛切な一体感が感じられます。今風の音楽とは無縁な彼岸の境地ですが、心に染み渡るたおやかさと悲しいまでの凛々しさには圧倒されてしまう。歌詞も自前のMCもすべてドイツ語。ジャケ画はローゼ作「魔法の森の前で」。
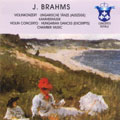
Concerto Royale
206216-360
Violin Concerto, Hungarian Dances/Brahms, Johannes //etc
3CDで600円台(購入時。円安で今は800円台。あぁ、もっと買っときゃよかった)などというドイツ、ハンブルクの過激な廉価盤メーカー、よくある原盤ライセンスを買い取ってリリースするディストリビュータだと思ったら、妙なマイナー曲ばかりを組み合わせたその奇妙な品揃えがいとをかし。おまけにCDの円盤三枚をトリッキィな手法で強引に2CD用のシングルケースに収めてしまうというけったいな手法には目が点になった。余計コストアップになる気がするのだが……。
中身はブラームス(Johannes Brahms:1833-1897;ドイツ・ロマン派)の寄せ集め室内楽選集といったところ。録音日時は不明で曲によりばらつきがあるが、ステレオで音質も良い方だろう。そして肝心の演奏はど素人の私が聴いてもはっきり凄いとわかるだけの内容を持っている。
収録曲は次の通り。
1;ヴァイオリン協奏曲 D-DUR op.77
2;ハンガリー舞曲より10曲抜粋
2はハンガリー、ロマ族のジプシー民俗音楽に感銘を受けた、著名にしてよく耳にするリズミカルな舞曲。
3;弦楽六重奏曲 NR.1 B-DUR op.18
3は一般的な弦楽四重奏(1st、2ndヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ)に更にヴィオラ、チェロを一本づつ加えた編成。4楽章40分弱 1860年、ブラームス27歳の若書きであるが、若書きであるが故の情熱と苦悩に満ち満ちた悩ましくも美しいメロディが堪えられない。
4;ホルン三重奏曲 ES-DUR op.40
5;クラリネット五重奏曲 in B minor op.115
6;弦楽六重奏曲 NR.2 G-DUR op.36(抜粋)
演者は今一つ明確な書き方がなされていないのだが、1,3,6あたりのヴァイオリンがズザンネ・ラウテンバッハー(Susanne Lautenbacher)なのだろう。不詳のせいもあって、あまり聞いたことのない団体ばかりですが、とても端正でいながら惚れ惚れするようなしなやかさ、憂いの表現が絶品です。