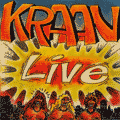
EMI Electora
7243 8 22671 2 6
Live/Kraan
さすがに毎日暑いな。右脳と左脳が乖離して独立モードで作動するものだから効率は良いがフィードバックに欠陥が生じるというか、致命的なチョンボが起きそうで恐い。
ワウの掛かった電気サックスに加え、軽妙洒脱と悪乗り、妙な掛け声、奇態な声芸、怒涛の電気ベース、コード弾きワンマンショーに至るまで、北西ユーラシアの凍てついた芸道を突っ走る四人組、初期の集大成的ライブにしてリマスター廉価盤。当初はLP二枚組み、曲間で切れていたものがCDではつながって聴くことが出来ます。
とにかく凄い。圧巻とはこれをいう。ジャズロック・ベースの妙な中近東インスト曲を連発するクラーンの真骨頂。的確で圧倒的なテクニックはこけおどしをまったく必要としない。ここまで出来ればさぞ気持ち良いだろう。すっとぼけた味わいもイカレたクラウトの際限のなさが小さくまとまらずに絶品であろう。ほとんどないが歌入り曲のテンション落ちまくりのヘロヘロ脱力ボーカルとタイトで疾走する演奏のギャップが凄い。爆笑である。

Brain
833 612-2
Live at Home/Jane
こちらも76年、ハノーファーにおける脂が乗り切った時期のライブ。英語で歌う北ドイツ製短調叙情演歌という基本線は一貫しており、初期各アルバムの秀曲揃いで当初はLP2枚組、ボリュームたっぷりの80分。録音、ミックスは名匠コニー・プランク。おかげで当時のライブとしては低音がきちんと拾えてかつ潰れていないという音質が確保されている。 聴く限りではメロトロンは既に使用しておらず、当時最新のポリフォニック・シンセの音が聞こえる。派手な個人プレイはまったくないアレンジ主体の淡々としたアンサンブルが特徴ですが、音が薄くなったときのゆったりと透き通るようなシンセの儚さが気持ち良い。二言目にはB級扱いされるのが一般的ですが、よく練られた起承転結のある曲展開と安定した無理のない演奏、暗く沈みこむような曲調、独特の突き放したような哀感は虜になるものを持っている。
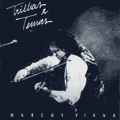
Sonhos e sons
SSCD006
Trilhas e temas Vol.1/Viana, Marcus
サグラドの総帥、マルクス・ヴィアナのソロ一作目。『軌跡と主題』というシリーズで現在6作ほどがリリースされているようです。主に映画音楽やTV用として作られた曲のようですが、サグラドの収録曲のバイオリン・コンチェルト風アレンジ(というかこっちが原曲か)等も含まれています。この第一集は悩ましくも美しい電気バイオリンを前面に出したもので、インスト曲が大半なので伸び伸びとした演奏がふんだんに楽しめます。
ロック色はほとんどありませんが元々そういう方面の人なのでしょう。楽曲の質は非常に高く優れた作曲家に多いように、バイオリン、鍵盤演奏家としても並外れた技量の持ち主です。ラストは子供の歌う「アヴェ・マリア」で締めくくり。
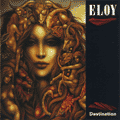
SPV
084-48082
Destination/Eloy
とうとうボルネマン+ゲルラッハのデュオになってしまった90年代エロイ。ゲストをかき集めてこなしているようだ。フルートのソロがちょっと面白い。曲はそれほど長くはないが展開の凝った6~7分の力の入った曲がほとんどで20年選手のわりに意欲を失わない馬鹿正直謹厳実直品行方正さが好感。工夫されたリズム、子供の合唱から女声コーラルまでアレンジも緻密でダイナミック、独特のリリカルなメロディが映える。
「人類の失墜(Eclipse of mankind)」
悲嘆に暮れた無意味な涙が刺々しい大地に滴る
期待される未来は既になく
見渡す限りの自己破壊の残骸
危険に無頓着で、あらゆる警告は無視された
戻るには遅すぎる
運命は閉ざされた
飛べない鳥のように
希望もなく、未来もない
あらゆる真実の価値は抹殺された
無意味な言葉が恐怖を追い払っても
空虚な約束は苦痛に溺れる
真っ当な感覚は鎖に繋がれ
偽りだけを信じてきた
今、その代償を払いながら
統制の上を絶望が流れゆく
戦争と犯罪に支配された
狂気に侵された世界で
そのどこかで、暴力が叫びをあげる
より多くの犠牲を求めて
家庭すらも性倒錯の余韻に浸りつつ
救いのための祈り
それすら虚しい
変革の明日は既になく
残された時間すらないように
未来は今現実そのものと化した
虚栄と名誉は盲目の闘争をもたらし
真実の価値は隠蔽されたまま
今もなお、内側から焼き尽くされる
恐怖の鉤爪に捉えられて
我等人類は失墜に至る
うぬぬ。なんだか救いがないな。捻りもないけど。
頭目のボルネマンは昨今メタルのプロデューサ稼業で当たったらしい。
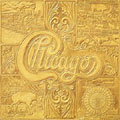
CBS/SONY
SOPW1~2
VII/Chicago
『V』、『VI』とシングル・アルバムだったものが再びダブルLPになった7作目。日本での発売は74年5月。リアルタイムで最初に購入したシカゴとして、たいへん思い出深い。ここから『VI』『V』『III』『Chicago』『Chicago Transit Authority』と購入していくには数年を要したが、私個人のシカゴ体験はそこで収束してしまった。この『VII』はLPが現存しておりまして、それを自分なりにマスタリングして聴いております。当時は寄せ集め的で散漫な印象が否めなかったけれど、今は伸び伸びしてコンパクトにまとめていないところが自然でよいなぁと思う次第。個人的に7作(ライブのIVはないから6作か)の中でも最高作だと思っている。当初は一枚になる予定だったらしいが、構成員内部ですら上手くまとまらず、ならばいっそのこと有体のままを晒そうという意識が、ロック音楽全体が難しい時期に差し掛かるなかで陳腐化を避ける良い結果を導いたと云えなくもない。
前半はほとんどインスト曲が続き、前作の洗練されたポップを期待すると驚天動地。初期を思わせるジャズロックの緊張感が気持ち良い。後半に入るとようやく前作の発展形が現れる。メロディが甘すぎる気もするが、キーボードに巾が出来て一回り音像が奥行きを増した。
少し後に出たラム(Robert Lamm)のソロ『Skinny Boy』を探しているのだがないなぁ。

T-Two
03822
資本主義の風景/スコープ
タイミングがズレ気味だが、ま、季節柄。Scopeでスコープと読むのだろう日本人五人組、2ndアルバムらしい。1stはマイナー・レーベルから出ていたようだが、今作はほとんど自主制作といった趣。幼稚園児の歌う「君が代」ではじまるノイズ風味アンビエント70年代風プログであるが、トータルアルバムを作るだけの構成力には今一つ欠けているようだ。
専任歌手を抱えているわりに歌の比重は軽く、歌詞は曲名ほど刺激的でもなく、文字を見ないと日本語なのに何を歌っているのかさっぱりわからない。それほど若くはないと思うのだが、ちょっとだけ刺激的なタイトル等を含めコンセプトは情緒的でかなり恥ずかしい。この国でこの種の試みを続けていくことは甚だ困難を伴うであろうことはよくわかっているつもりだが、ピアノ・ソロをバックに歌うリリカルパートを中心にコンパクトにまとめた方が特質が出て良いのではなかろうか。
ジャケ写真は広島県産業奨励館の廃墟。最初に見たのはちょうど17、8年程前の初夏か。最終便で帰る時間潰しに川面で夕涼み。当時は廃墟オタクだったので、それなりの興味を持って寄り道したのだが、周囲は頑丈な鉄柵に囲まれて中に入ることすらできないというていたらく。真下から見上げた夕景のドームはさぞかし美しいだろうに、と残念に思いつつも、冴えないデザインで弄くりまわされた周囲の広場や愚劣なモニュメントに比べれば遥かに静謐な存在感を誇っていたことが残された唯一の記憶だ。
周囲20kmをそのままの姿で、都市の廃墟として焼?死体レプリカ付きで完全保存、鼠園にでも運営させれば、今ごろ世界で最大、最高に壮絶な観光地になっていたであろうに惜しいことをしたものだ。ことごとく事象を矮小化せずにはおれないのか。当初の予定通り京都に落とせば、それはそれでより想像力をかき立てられる展開になっただろうが、相手は先読みのできる大人だったようで至極つまらない。
ときおり、誤解を受けるようですが、広島型反戦主義者にも、アンチ原子力関係にも興味はありません。個人的には夕暮れの裏道で「旦那、旦那、いいウラン鉱石が入荷したけどどうでっか?」と誘われたら仕事をおっぽり出して着いていくだろうし、黒鉛チャンネル型原子炉とか粒子加速器など、ぜひとも所有して心ゆくまで弄くり倒したいものだと思っているくらいだ。もちろん、テクノロジーの粋を尽くした兵器にも感情的な嫌悪感はなく、逆に唯の軍事技術を如何にも夢だの平和利用云々と言い包め、言い含められることには反吐がでる。
どのみち世間は世間。世情が何を求めようと成り行きのままにあればよい。
だから、ただひたすら鯉に餌をやり、植木に水遣りをする毎日ですが、どうせならいつの日か、そのテクノロジィの粋を見せて欲しい。SLBMがぼこんぼこんと海面を割り、点火したロケットブースターが未酸化の固体燃料の噴気を尾に引きながら上昇し、MIRVがオレンジ色に輝く夕景に白くたなびく流星群のように雨あられと降り注ぐのを見ながら死にたいものだ。
公式Webもあるようですが、配置といい色合いといい、とどめは“アーティスティック”な固定文字とわけわからんナヴィと表紙見ただけで引き返したくなるタイプ。どうしても資料が必要な場合は、便利セットでスタイル無効化して見ますが、音楽系のWebというものはどうして根本的な論理性が甚だしく欠如しているのだろうか。

apex
8573 89235 2
2001
Messe Chorale/Gounod, Mass Op.4/Saint-Saëns //Michel Corboz
だから戦争と平和などという事象は幸福か不幸かといった観念の遊びに似ている。それはワンセットで存在する相対的な状況であって何か定量的に、あるいは定性的にすら規定された定義があるわけではない。時間、場所を限定すれば、この世のどこかの誰かは常に戦争をしているはずだ。そして、身の回りの空間的、時間的平和に内包されているはずの事実を僅かな思慮でそっと覗き見さえすれば、平和というものは戦争を支えるための経済的手法であり、戦争から得た果実を欲望のままに享受する場に他ならないことに気付くはずだ。逆にいえば、今日一日、しこしこと手を動かした代償としての経済的定常状態の揺らぎは、自らを利すると同時に蓄積されて不公平と搾取を生み出し、今を維持しようとする欲望は、やがて弱いところを綻びさせ、不平等を実現し固定化するための一発の弾丸、一発のミサイル、一発の核弾頭に取って代わるに過ぎない。
オペラ作曲家、シャルル・フランソワ・グノー(Charles François Gounod:1818~1893)は世俗の対極である宗教曲の作曲家でも知られるアンビバレンツなお方であったようだ。「Messe Chorale」は30分弱の通常文グロリア・ミサ曲。情緒的で流麗なメロディが特徴です。サン・サーンス(Camille Saint-Saëns:1835-1921)はロマン派の大家。「Mass Op.4」は40分ほどのこちらも通常文グロリア・ミサ。冒頭キリエが15分と長大。変化に富んだ曲調と類い稀な構成力に裏打ちされた技巧がフランス的な情緒と相まって透明な高みを作り上げている。教会オルガンの音圧とコーラルの清廉な響きは西洋音楽の完成された一つの典型だ。
1988年録音のERATO原盤の再発廉価盤。演奏はパイプオルガン+コーラル。ローザンヌ大聖堂での収録で、演奏はコルボの私兵合唱団だから隅々まで行き届いた丁寧さが感じられる。少なくとも現代においてはあまり玄人受けする人ではないようだが、しっとりとしたロマンティックな情緒の載せ方がとても好みに合う。
自らの繁栄を願うことは他者の窮乏を望むことに等しいし、平和を希求することは他所に戦争を押し付けることと同義でしかない。今までも、これからも、ただそれだけのこと。
鯉の餌すら食えなくて飢えている人、植木に撒く水すら飲めなくて渇く人。その事実を目を閉じることなく純粋に傍観しながら、今日もただ鯉に餌をやり、植木に水を撒く。
それはさながら祈りに似ているかもしれない。

Silence/North Side
NSD 6008
Trä/Hedningarna
スウェーデン+スオミ連合によるドンと来い壮絶激舞呪術民謡。スオミ・おばちゃん隊のポリフォニー歌謡がぶっ飛んでいる三作目。タイトルはスウェーデン語で『森』ないし『木材』の意。暗い彩りに染まった迸るエネルギーと深い森が太古の昔から抱き育んできた精気が独特の風土とアイデンティティを語り尽くす。全11曲、歌詞はフィン語とスウェーデン語が半々ぐらいか、全英訳付き。リュートやハーディ・ガーディ等の弦楽器、フィドル、バグパイプ、ハープ奏者に打楽器を加えた古楽器アンサンブルを基調に打ち込みの上を縦横無尽に駆けるおばちゃん隊の謡いは壮絶だ。フィン語の曲は妙にアジア的な語感が耳に残り、うっかり日本語で意味を考えてしまうところがけったいである。緻密でテクニカルな演奏と原初的で野太い歌のバランスが絶妙で唯一無二。歌詞、楽曲も6割ほどがトラッドのリアレンジだが、この密度の濃さはどういう背景風土から生れるのだろう? 自ら異教徒と名乗る西洋音楽に対するアンチテーゼは理解に易いが。
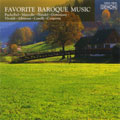
DENON
COCO-70616
パッヘルベルのカノン~バロック名曲集/イタリア合奏団, etc
著作権切れのタダ曲を適当に寄せ集めて、2、3年おきに新装盤でもう一商売という巷に溢れた廉価コンピ盤……と思いきや1974-2000年録音という表記が。DDDと書いてあるが74年だったらどう足掻いてもADDだろう。個別の曲に録音データはクレジットされていないのでなんともいえない。似たような企画物をいくつか聴いていますが音の抜けはこれがいちばん良いようだ。
ざっと挙げてみるだけでパッヘルベル、ヘンデル、ヴィヴァルディ、アルビノーニ、コレッリ、クープランと揃い踏み。その各人の多分いちばん有名な曲の、それも最も印象的な一部を切り出してイージー・リスニング風にモダン楽器で演奏したもので、これだけ聴くとバロックを大きく誤解できるという代物。大まかに1600年から1750年の150年間、J.S.バッハの死とともに終わりを告げるのがバロックの時代。端的にいえばルネサンス声楽ポリフォニーから後の古典派によって完成される和声+器楽演奏の端境期。絶対王政の下で絢爛豪華な文化が花開いた時期でもあり、華麗な親しみ易さが特徴の一つでもある。なぜなら曲名までは憶えていないが、耳に入る音はすべて知っているメロディなのだなぁ。
個人的にはアルビノーニ命(いや、アダージョではなくてね)だが、切りがないから一つだけ。タイトルにもなっている「カノン」は「3つのバイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ ニ長調」という曲の前半なのだが、バロック期ということでリファレンスがないからテンポや解釈も演奏者によって大きく異なる。この盤は中庸なテンポ(5分2秒)で弄繰り回していない素朴で艶やかな演奏で気に入っている。 ちなみに、アフロディーテズ・チャイルドの1968年のヒット曲「雨と涙(Rain and tears)」として世に出たのが認知のきざはしで、翌年のフランス映画で人気を不動のものにしたらしい。
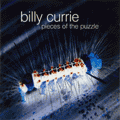
Puzzle PZLCD107
Pieces of the puzzle/Currie, Billy
80年代に一世を風靡したウルトラヴォクスの鍵盤奏者のソロ・コンピ盤。思わず取り落としそうになるスリーブ写真は正直、スキャンするのが嫌だったなぁ。ウルトラヴォクス以後、既に五作ほどのソロと再編ウルトラヴォクス名義で二作がリリースされているようですが、入手性はあまりよくないようだ。
基本は打ち込みリズム。一部を除きほぼインスト曲のみ。ところどころギターのみゲストといったアレンジで思う存分弾きまくる鍵盤の涼しげでクールな感触が夏向き。ウルトラヴォクス時代の曲のリアレンジはカリー自身が歌っているが、上手くはない。2000年風エレポップに走るよりも、作曲センスを生かして『Transportation』時代のアンビエント・ポップを突き詰めて欲しいものだが、それでは食えないのかな。鍵盤以外にもバイオリン、ビオラをこなす技量もあるので、過去に拘らない方が質は上がるはずだ。
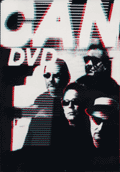
Spoon
0724359411606
CAN DVD/Can
2DVD+CDのアンソロジー。70年代初期のダモ期のライブとTV出演時のフィルム、自前スタジオでの演奏、インタビューなど極めて豊富で多彩な内容。編集の質も高く、映像、操作性、資料性も同業他者に比較すれば抜きん出た内容だろう。おまけに海外版でも日本語字幕選択可という極めてけったいな仕様には驚いた。
フリー・コンサートのダモは真紅のもっこりジャンプスーツ、顔が見えない髪の毛オバケ状態でなんともいえない気味の悪さ。ほとんど即興の演奏に合っているのか合っていないのか、歌っているというよりは、喚いている、喚いているというよりはお祈りしてると。そのすぐ脇や前面の同じステージ上では不明な団体が軽業組体操をしていたり、初老のオジサンが鍋釜やら三色の傘で芸をしている。どれもあまり上手くないから素人の学芸会?なのだろうが、いやはやなんともシュールで斬新だ。
イギリスのTV番組では司会者の“ドイツの田舎もんだぜ、ぷ”といった小馬鹿にした態度丸出しに失笑。ドイツの番組ではしらっとして椅子に座って微動だにしない観客のなかで、唯一人、足をもぞもぞ動かしている男をまるで変態のようにカメラで捉えているのが傑作である。演じるはフェンダー・ジャズベースを腰だめに踊る黒人ベース、ロスコ・ゲー(Rosko Gee)に、チュカイは脇で電話したり機械を弄くったりとすっかりノイズ担当、泣く子も踊るのりのりファンクの変曲「Don't say no」、歌なしバージョン。
もっとも、リーベツァイトのドラムには改めて感銘を受けた。機械のような正確さと即興を引っ張る主導性と周囲に同調させる柔軟さ。ここまで周りを見回しながら叩く太鼓奏者は初見である。「Vernal Equinox」(TVでやるか?)で見ることのできる凄まじいまでの演奏に象徴される、なんとも形容し難いジャズでもロックでもない人間シーケンサ民俗太鼓には恐れ入った。この時代にこういったタイプの奏者はおそらく他にいなかっただろう。
ついでにいくつかの疑問が解決する。
日本語テロップでは“Jaki”はヤキと表示されるが、複数の人の発音を耳で聴く限りはジャキとしか聞こえない。ジャズ出身だからジャッキー(字幕にもあるようにJacky)の略なのではないか? と推測。もっとも本名はまったく別だろう。ジャッキー・リーベツァイトなんてふざけた芸名だな。一方、髭のバス奏者はチュカイとしか聞こえない。ダンツィヒ出身だし、頭文字Cだからポーランド系プロイセン人でしょう。Cz+母音はポーランド語やチェコ語ではそれほど珍しくはない。
NTSC、リージョン0。

Hit Thing
HTDVD013
Impressions/Faust
こちらもDVD+CDという構成だが中身は一転して“す”の入った大根のように味気ない。DVDは過去の映像を様々なギミックやコラージュで編集したもの。映像版『Patchwork』とでも云うべきか。これといったセンスの煌きもなく、BGMというかBGVのようなもの。BGMになっている曲は未発表バージョンだったり、リミックスが施されているのかもしれないが、10年ほど前に作られたようなつまらないCG効果が見るに耐えない。白熊君がドラムセットに座っているシーンとエフェクトが掛けられたライブがほんの少し。廉かろう悪かろうといった按配か。このところ“アート”という領域はすこぶる苦手な範疇に入りつつあり、その手の催しには一切近づかないし、身の回りから遠ざけるよう慎重に排除しているつもりなのだが、今更こういうものが出てくるとは夢にも思わなかった。
CDはファウスト=ディールマイヤー(Zappi Diermaier)の映像作品『I spin』のサントラ・ミニアルバム。こちらは再編ファウストの乗りで冷え冷えとしたノイズ・コンテンポラリ。もちろん好みはアコーディオンが可愛らしいワルツ「Hamburg Walzer」。
最近イルマーの代わりにペロンが復帰したみたいな話もどこかで目にした気がしましたが、もう過去のものと割り切るべきなのだろう。
NTSC リージョン0。
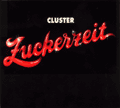
Spalax
CD 14865
Zuckerzeit/Cluster
74年の三作目。ツァッカーは砂糖、ツァイトは時間を意味するから『甘味なひととき』といった意味だろう。内ジャケには白服のローデリウスの膝の上に黒服のメビウスがぺっとりと横座りして微笑み合っている写真が掲載されておりまするが冗談だよねぇ。
調性の復活、数分の短曲、全10曲、角の取れた可愛らしいメロディ、後のエレポップを髣髴とさせるアナログ・シーケンサー、気持ち良く遷移するループと劇的かつ質的な方向転換が図られている。アンサンブルの組み上げかたにはなんとも摩訶不思議な浮遊感が漂い、さながら色とりどりのキャンディ菓子がきらきらと乱反射しながらぶちまけられていくような甘い恍惚感に襲われる。市場のキャンディ屋の木箱に入って並べられていて、シャベルですくって買うあの膨大な種類の飴菓子。う~ん、寒いところだと溶けてくっついたりしないのだろうなぁ。
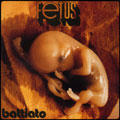
BMG/Ricordi
74321585522
Fetus/Battiato, Franco
イタリアの変人バッティアートの1stソロ。この時期はカンタウトーレというよりは現代音楽。先鋭的で刺激的な音像とコラージュされたような断片の羅列。それでいて耳についてしまうお得意の美フレーズと類い稀なメロディは鮮烈だ。すっぱりと断ち切られたような切断面の鮮やかな色彩が目に浮かぶ。SEの使い方や全体構成も当時としては先進にまったく引けを取らない優れたものだろう。というか今でも十分斬新です。トータル・アルバムの作りで冒頭の心音のSEがなんとも生々しい。
タイトルは妊娠三ヶ月以後の胎児の意。副題は「Ritorno al Mondo Nuovo(新世界への帰還)」。中身はイギリスの作家、オルダス・ハクスリー(Aldous Huxley:1894-1963)による母性否定の管理社会を描いた未来SF小説「Brave New World(すばらしい新世界:1932)」をテクストにしたもの。タイトルの元はシェイクスピアだろうが、ここではもちろん反語的に使われている。
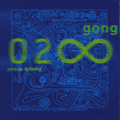
One Eyed
Salmon Records
SMACD824
Zero to infinity/Gong
Radio Gnome Invisible(不可視電波妖精)の5作目に位置付けられるらしい、おそらく最後の正規スタジオ、フル・アルバム。もっとも2005年現在、ご本尊のほうは既に末期症状でしょうか。昨今のデモから発掘音源、ライブに至るまでクォリティの伴わないCD、DVDの乱発、集金ツアーは憐れを誘います。『Flying teapot』の和み系解読と表ジャケに堂々と書かれている通り、焼き直し+αです。それでもZeroの冒険はまだまだ続いているらしい。既に不良老人集団と化した爺さん婆さんによる妖しくてゆるゆるなブレイクビーツ・テクノ風味、宇宙空間浮遊上下左右前後でたらめトリップ・サイケ、回顧メロディに絡むマルールブのサックス、ハウレットのベースは健在にして不滅だが、さすがにスピード感と緊張感には欠ける。
そう、結局のところ、Zeroはオーストラリアの神秘的な環境で死ぬことになるが、物理的肉体を失っても彼は生きている、と物語は結ばれている。
“02∞”で“zero to infinity”と読ませようという魂胆か。ビニール製スリップ・カバー付き。
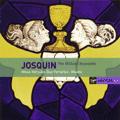
Virgin Classics
7243 5 62346 2 8
1990
2004
Missa Hercules Dux Ferrariae, Motets/Josquin des Prez //The Hilliard Ensemble
ジョスカン・デ・プレ(1440-1521)はルネサンス期、前期フランドル楽派の代表的な作曲家。ギヨーム・デュファイ(Guillaume Dufay:1400?-1474)の功績を受け継いで、通模倣様式なる西洋音楽の一つの基礎を築いた多声ポリフォニー音楽の頂点である。ポリフォニーとは後に主流になる旋律+和音形式ではなくて、独立した旋律(この場合はカウンターテナー、テナー、バリトン、バスの四声)が同時に別の旋律、歌詞を歌うもので、ハーモニーは結果として生れる。一見、無茶苦茶になりそうで信じ難いが、そこはルターが絶賛したプロのなせる技、これが実に儚くも透明で美しい。ちなみに器楽演奏は一切ありません。
2CDの一枚目はモテトゥスとシャンソン。モテト(Motets)は宗教歌、シャンソン(chansons)は世俗歌を指す。後半は『二本の剣をもった(?)ヘラクレスのミサ』と若干の賛美歌、モテト。6部構成、26分越えのミサが白眉だろう。一部の隙もない理知的な響き、天上の美声の完成度には圧倒される。演ずるはイギリスの古楽男声合唱アンサンブルであるヒリアード・アンサンブル。非常に透明度の高いしなやかな発声が特徴で、ある意味とても現代的な合唱団。