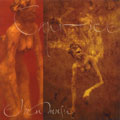
Prikosnovenie
PRIK048
Elven music/Caprice
ロシアのネオ・クラシック、カプリスのデビュー作。歌詞はディズニィ嫌悪で有名なイギリス人作家+言語学者トルーキン(J.R.R.Tolkien:1892-1973;だからトールキンだと思うが)から取られたもの。初作の割には完成度の高さが特徴で、構成、展開、もちろんテクニックも問題なし。英語で歌うソプラノ女性歌手は若干エキセントリックな声だが、プロの発声で声量、音域とも文句なし。優美で典雅なアコースティック・チェンバーはポップ色は皆無というよりも、アンチ・ポップに邁進する。その潔い姿勢は賞賛に値する。
リリースはフランスのプリコスノヴェニから。続編が2003年に出ています。
具体的にトールキンのどの著作をモチーフに据えたのかは、苦手領域なのでまったくわからないし、興味もない。ファンタジーってどうしてもダメなんですねぇ。
適切な例かどうかは心もとないが、北村薫が著作「赤頭巾」で指摘していた通り、森で見つけた赤頭巾を何故その場で食わなかったのか? お婆さんの家に先回りして、お婆さんを排除して、わざわざお婆さんに化ける必然性は何か? そこに引っ掛かってしまうと先に進めなくなってしまうのだ。「お約束だから」でもいいのだが、そこに込められた悪意を曖昧に糊塗するのはつまらない。
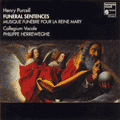
Harmonia Mundi
HMX 2981462
Funeral Sentences/Purcell, Henry //Collegium Vocale, Dir.Philippe Herreweghe
パーセルである。ヨーロッパの辺境ゆえに、あるいはその功利主義的な土壌が作り上げた経済的先進性によって、少なくとも音楽的には自ら生産することなしに純粋に消費することを幸福としてきたイングランドで、バード(William Byrd:1543-1623)と共に、無二といってよい作曲家がヘンリィ・パーセル(1659-1695)である。近年はその功利主義と密接に結びついた産業音楽が世界を席捲しているが、当時は土俗民謡以外の大半は大陸からの輸入品(あるいは帰化人作曲家)であった。
まぁ、興味の端緒はナイマンの『The draughtman's contract』だったのだが、女王メアリ二世の葬儀のために作られた宗教歌を中心に、典礼のための楽曲、アンセム(賛美歌)や世俗歌曲であるオード(叙情詩)が含まれております。先進地であるフランスやイタリアの楽曲を上手く取り入れた内容ですが、最大の特徴はラテン語ではない、英語合唱曲であるということ。ちょうど英国国教会がローマと袂を分かって成立した頃で、揺り戻しはあったにせよ、恵まれた時期ではあった。伊仏に比べれば質素且つ謙虚で清々しい。
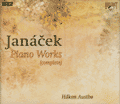
Brilliant Classics
92295
Piano Works/Janác`ek, Leos` //Håkon Austbø
とうとうレオシュ・ヤナチェク(1854-1928)である。cとsにはカロン^を逆さまにした記号がつきます。チェコの民族派といわれるが、ボヘミア人ではなくモラヴィア人で、モラヴィア民謡の採取と保存に貢献し、それら独特のメロディやリズムを自作民族オペラや楽曲に積極的に導入した作曲家として知られる。列強の間で揺れ動きついには分裂に至った国と同じく、ヤナチェクの立場と評価もいろいろと複雑なようだ。時代が新しいせいもあるのだろうが、ピアノ曲集ですが曲調は大胆で熱情的。それでいて神経症的な生真面目さと偏執的な暗さが同居するというなんとも複雑な楽曲の数々。 老境に入って自分の年齢の半分の人妻と不倫、挙句の果ての温泉不倫行で客死するという 今をときめいちゃうような人だったらしい。良寛禅師の40歳年下には負けるかもしれんが。
リリースはオランダの廉価盤BOXセット乱発レーベルから。均すと一枚300~500円ほどという格安CDですが、中身が酷いというわけではなく玉石混淆。新しいものは録音も良く非常に充実しています。録音情報や演者、ライナーもそれなりで十分及第点のレベル。
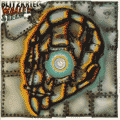
King Record
KICP 2731
Blitzkrieg/Wallenstein
メロトロンといえばヴァレンシュタインというくらい全編に渡りフルート音とストリングズ音のメロトロンが弾き倒されている1stアルバム。ドラーゼ+グロスコプフという主軸に、アメリカ人ギター奏者に2ndリリース前に発狂するオランダ人ベース+ボーカルという混成で、リリカルな長尺曲はこの時点で既に全開であるが、弾き捲くるギターが思ったよりロック色を強めている。フェイズかかった驚異的な手数のドラム、弾き捲くるドラーゼのエレピも強烈な印象を与え、濃密でエキセントリックな非尋常さに一役買っている。
若干の歌入り二曲、歌詞は英語、全四曲。全曲を書くドラーゼはおそらくクラシック出だろう。ドイツロマン派やバロックに通ずる劇的な展開・構成が好みのようだ。
穴の開いた装甲板と占星術の星分儀が何を意味するのか、今一つ困惑を禁じえないが、ブリッツクリーク(電撃戦)というタイトルはWW2初期、いわゆる戦車を機甲師団として初めて単独運用した革新的な用兵戦術を指すのだろう。元々は楽団名だったらしい。
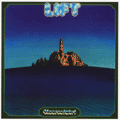
BuschFunk
8026-2
Meeresfahrt/Lift
旧D.D.R.のリフト、2ndアルバム。前作に比べメロトロンの出番は減ったが長曲を中心にした構成とアレンジは一歩抜きん出た感がある。特筆すべきはなんともいえない安定感だろう。D.D.R.ものとしてリリースが許される最低条件は、他人に聴かせられるだけの技能を持ったプロであることだっただろうから当たり前のことなのだろうが、ここまで精緻な安定ぶりを見せ付けられると逆に奇異にすら感じてしまう。
リリカルで明快なメロディは歌謡曲としても十分通ずる質を誇る。アカデミックでクラシカルなアレンジを基調に、静と動、序破急をもった展開、弦楽四重奏まで引き入れたアンサンブルは完成度が極めて高い。船旅をテーマにしたトータル・アルバムの扱いで歌詞はすべてドイツ語。ロマンチックなまでの中音域豊かな骨っぽいバリトンが映える。
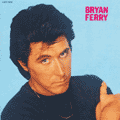
Virgin/EG VJCP-3334
These foolish things/Ferry, Bryan
濃い視線に思わず、たじたじと後ずさってしまうキワモノ風エキセントリックな顔ジャケのおかげで長い間手に取る気にならなかったファースト・ソロ。廃盤セールでやっと購入。おっさんの才気が評価されるのはまだまだ後のことだが、基本的な路線は頑固一徹、この頃から何も変わっていないところが凄いというか、自信の現われというか、それしかできないというか。炭鉱夫(農夫?)の家庭に生まれ育ったという典型的な北部ワーキング・クラスの上昇志向は手法的洗練には欠けるが、有り余る野心が一つの夢を成し遂げたといえるだろう。滲み出ちゃうものをバタ臭いとみるか、味があると評価するかで好みは大きく分かれそうだ。
全曲カバー。選曲はディラン、ビートルズ、ストーンズに60年代ポップとオーソドックスで且つメジャー処。リリースはロクシィの『Stranded』の直前らしいが、頽廃色はほぼ皆無で過去の遺産に対する素直な憧憬が核になっているのだろう。
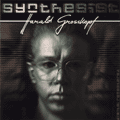
Think Progressive TPCD
1.906.051
1999
Synthesist/Harald Grosskopf
ヴァレンシュタイン→アシュラという経歴のグロスコプフの1stソロ・アルバム。リリースは80年なのでこれは再発盤でしょう。このレーベルはシリアル・コピー・マネージャが掛かっているので有名だが投売り$6だったから許す。まぁ、SCMはプロテクトじゃないから外して焼直せばそれだけの話だし、劣化コピー作る趣味もないので関係はない。
タイトで華麗な全曲インスト。流れるように遷移していくシンセのメロディが美しいアンビエント・テクノ。アシュラの『Correlations』あたりの発展形だろう。最長でも7分ほどの短曲で、こなれたシーケンス・パターンとクールな叙情性が特徴か。怪奇心象アンビエント等を含めて、パーカッションよりはシンセが前面に出た扱い。クレジットがまったくないのでわからないが、『Vienna』のころのウルトラヴォクスに通ずるシャープで現代的な感触はコニー・プランクの存在を髣髴とさせる。

Warner Classics
2564 61924-2
Cantigas de Santa Maria/Alfonso X el Sabio
一部がミニモム・ヴィタルの『Sarabande』でモチーフとして使われている『聖母マリア頌歌集』。編纂はスペイン王、アルフォンソ十世(1221-1284)。大半は当時、所領であったカスティーリャからレオンの世俗歌で、400を越える曲数から構成される中世を代表する歌曲集。歌詞はポルトガル-ガリシア語という古語で歌われる。グレゴリオ聖歌と同様に単旋律の抑揚に富んだ歌謡が特徴。様々な階層の人々が危機や誘惑に陥ったとき,聖母マリアによって救済されるというかなりコミカルなまでの内容がおもしろい。
伴奏はまだ通奏低音の時代ではないので控え目。ア・カペラも多い。
レコンキスタ以前の当時のスペインは南部を支配するイスラム教国との交易で、最新科学や音楽理論、楽器などが流入したヨーロッパの先端地でもあった。そのせいか、楽曲にはアラビア色をほのかに感ずる。
フランスのErato原盤の廉価再発盤。モロッコ録音で全英訳付
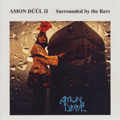
Spalax
14810 MSI
Surrounded by the Bars/Amon Düül II
81年の『Vortex』(2005年めでたく再発)以降、完璧に沈黙していたなかで、突然フランスのSpalaxからリリースされたリミックス・コンピ+新曲集。新曲は次作『Nada Moonshine #』にも使われたもの。別バージョンが含まれている。タイトルは5作目『Wolfcity』の「Surrounded by the Stars」に掛けているのだろう。リミックスされているのは70年代前半のもの。1stから6thまでから万遍なく選ばれている。 「お茶目な天使の雷鳥(Archangel thunderbird)」の最後にくっついている(原盤では組曲「Restless Skylight-Transistor-Child」の一部だと思うが……)「Riding on a Cloud」が秀逸。
「雲に乗って(Riding on a Cloud)」
聞き耳を立てよ
さぁ、聞き逃すな
ハバククはすぐそこに来ている
へつらうな
もう萎縮する意味はない
ジンテルマン氏がドアを叩いている
目を瞑れ
さぁ、目を瞑れ
おまえが見るすべては
まったく同じ楽園でしかない
翼を広げ
墜落するのだ
倒錯した子供達は
町になだれ込む
わたしの向こう
肩越しに見よ
沈んだ都市が
今、海中から隆起する
ハバククは旧約聖書に登場する預言者。ジンテルマンは前曲に登場する不可解な紳士。歌詞も著しく意味不明だが、ジャケットも意味不明だ。頭に花を乗せた帽子を被り、民族衣装を纏った不思議なグルカ兵みたいな男が巨大なクローゼットのような監視廠の覗き窓を塞いでいる。

DHM 82876 601522
Symphoniae/Hildegard von Bingen //Sequentia
ビンゲンは現ドイツ中部、ライン河畔の町、ビンゲンのヒルデガルト(1098-1179)はヨーロッパで最初の女性作曲家といわれる女子修道院長であった。薬草学、医学者であり幻視を伴う神秘主義者(当時も微妙、数世紀遅ければ異端間違いなし)で神学の著作もあり、法王にも預言者として認知されていたらしい。個人的には薬草学の権威なら、精神なり意識に影響を及ぼす薬物の扱いにも長けていたのだろうと思うのだが、そういうことは言ってはいけないのが世の常であろうね。
ヒルデガルトが作曲をはじめたのは幻視による啓示を受けた40代になってからといわれ、1150年代にはそれまでの曲を集めて『天の啓示による調和のシンフィニア』なる本作が成立したらしい。もちろん、中世初期だから単旋律が主調で、器楽はオルガン、フィドル、ハープ、フルートなどによるが基本的には歌曲集でしょう。音数の少ない穏やかな宗教音楽ですが、崇高とか清廉とか敬虔というよりは、官能的な美しさに溢れた華麗なメロディが特徴です。歌詞はラテン語。中身は典礼歌曲ということで、その恍惚神秘主義に基づいた宗教歌です。
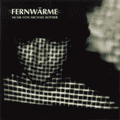
Random Records
398.6583.2
Fernwärme/Michael Rother
ミヒャエル・ローターのソロ四作目。昔、日本盤があったらしい。タイトルは『Fern + Wärme』で『熱の外側』といった意味だろう。地元の公演で聴いた、プロイセンの君主、フリードリッヒ大王(フリードリヒ二世:在位1740-86年)のフルート協奏曲に着想を得たらしいが、どこが? といわれれば?? と答えるしかない。ハンマー・ビートは若干趣を変えて、以前よりも軽やかに洒脱にトランス・アンビエント色が強まった。メランコリックな演歌調からリリカルで流麗なテクノ調まで多少幅はあるが、珍しくモノクロームで湿った温もりを感じさせてくれる。シーケンサーとユニゾンするドラム、シンセとユニゾンするギターと表現手法の二重性が、かえって微妙に焦点の定まらない揺らぎを醸し出しているようでおもしろい。
生ドラムは前作に引き続きカンのドラム・マシン、ジャキ・リーベツァイト。
2000年の再発CDはボーナス3曲入り。
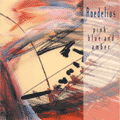
CTCD-040
Pink,blue and amber/Roedelius
クラスターの片割れ、ローデリウスのソロ。
とにかく多作且つ頻作過ぎて全容が掴めない。なんとなく持っていないものを、なんとなく入手して、なんとなく聴く。25年前のものだったり去年のものだったり、いつのものでも良い。そんな聴き方がいちばんしっくりすると思うこの頃。
綴りからして本当は“Rödelius”で“レデリウス”と読むのが正しいのだろうが、昨今は商標か屋号のような意味合いでラストネームだけを使っているのだろうと判断しています。
タイトルの色名はクラスターの公演で訪れた日本の印象を表したものといわれ、邦題は『ジャパン』だそうだが、それはリップサービスに便乗した牽強付会というものだろう。恣意的で稚拙な曲名翻訳はゆとり教育の成果を思わせる。如何にもエキゾチックな曲名が並んではいるが、青は水路、ピンクはドイツ人が住んでいた家の屋根の色でありレンガの色、そして何よりも琥珀といえば東プロイセンの飛び地、ローデリウスがかつて住んでいたケーニッヒスベルク(Königsberg:現ロシア領カリーニングラード)を指すと考えるのが妥当と思われる。
冒頭、松崎裕子(誰?)の歌う「Poetry(ドラゴンの跡)」は唯一の歌曲にして、ドラマチックでエモーショナルに他の楽曲から浮き上がっている。“月夜に恋をしたドラゴン”のお話は、ローデリウスのひんやりしたエレクトロニクスとふわふわとした官能的な歌で極上の透き通った情景が描かれる。一部に『Aquarello』のリミックス? リメイクを含む。
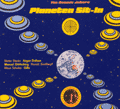
Spalax
14904
Planeten Sit-in/Cosmic Jokers
コズミック・ジョーカーズ名義でおそらく5作が存在すると思われるが、1、2作目以外はそれを音源にしたテープ・コラージュを継ぎ接ぎ、朗読詩やボイスを添加した今風に云えばリミックス集であるらしい。これはそのリミックス版でおそらく5作目にあたるもの。
73年頃を端緒として、Ohr(耳)、Pilz(茸)、Kosmisch(宇宙)という当時ベルリンにあった三つのレーベル(社長はどれもロルフ・ウルリッヒ・カイザー)のプロデューサー、ディーター・ディエルクス(Dieter Dierks)が中心になって、ヴァレンシュタインのユルゲン・ドラーゼ、ハラルド・グロスコプフ、アシュラのグトシンク、クラウス・シュルツェ、レーベルの社長秘書兼“星の淑女”ギーレ・レトマンと、今考えればそうそうたる人員が掻き集められて為された共同作業。
どろどろサイケ時代のアシュ・ラ・テンペルを髣髴とさせる前衛エレクトロニクス・セッション祭という趣だが、個人的に最も印象的なのは、おそらく作曲面での主導的な役割を果たしていると思われるドラーゼの叙情的なピアノとメロトロン。
CD再発は1995年、フランスのSpalaxから。デジパック、ライナー他一切無し。
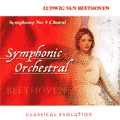
Delta 14 566
Symphony No.9 Choral/Beethoven, Ludwig van //SKD. Dir. Herbert Blomstedt
ベートーヴェン(1770-1827)である。古典派の最高峰と崇め奉られているのかどうかは知らないが、普通知らない人がいない程度に著名であることは間違いないだろう。そのなかでも日本では極め付きの人気を誇る「第九」。4楽章からなる交響曲。同種の曲としては珍しく(というか最初の)合唱付き。そういえば第四楽章の合唱の中間部は、エヴァにも使われていて仰け反った憶えがありますが、歌詞はシラーによる理想主義啓蒙革命詩「自由に寄せて」を元にした世俗歌曲である。
これは再発CDだが、この原盤はその筋ではたいへん著名らしい。正式名称は「Sinfonie Nr.9 d-Moll op.125 mit Schlusschor über Schillers Ode "An die Freude"」。
録音は1985年3月、D.D.R.のドレスデン、1945年の空襲で焼け落ちたゼンパー・オパー(ゴトフリート・ゼンパー設計のザクセン州歌劇場)の再建柿落とし記念コンサートにおけるライブ録音。指揮はヘルベルト・ブロムシュテット、演奏はSKD(シュターツ・カペレ・ドレスデン)による世紀の名演なのだ。それが、まぁ、数百円(新品で$3くらい)で買えちゃうというのもある意味凄いが中身はもっと凄い。それほど比較しているわけではないが、演奏のほうも良い意味でライブの特質が顕著に表れた圧倒的な緊張感と躍動感に頭がくらくらします。主催者側、演奏者側に特殊な思い入れがあるにせよ、日常的に年末にやっているのとはまったく別の曲。終章の余韻が完全に消え失せた後、熱狂的なまでの喝采を送る聴衆がこれほど羨ましく思えたことはない。

Epic Sony EVD 50187
The last supper/Black Sabbath
前後関係はまったく不詳ですが、オズボーンが復帰して結成当初人員構成に戻った実況撮影録音盤。おそらくアメリカでのライブ。一応、この後地元イギリスで同じ内容のツアーをしたそうだが、それがタイトル通り『最後の晩餐』になったのかどうかは不詳である。
かなりアグレッシブな楽曲の割には、アイオミもギーザーもこれといって派手に動くわけでもないし、いたって生真面目、オズボーンも歌うときはほとんど直立不動、スタイルなのだろうがこれはかなり印象的。歌っていないときのオズボーンは動物のようにあっちウロウロ、こっちウロウロ。バケツに水汲んでは観客にぶちまけている。肥えたとはいえ元気だなぁ。かつてのおどろおどろしいサバト風のステージではないものの、それなりに感慨深いものがある。
いちばん脂が乗り切っていたはずの4,5,6thアルバムからの選曲がまったくないのは非常に不満というかガックリ。ライブではやり難いという技術的な問題もあるだろうが、それをやってこそ見る価値があるというものだ。撮影は単調で創意も工夫もありゃしない、と酷評したいがまだましな方か。映像は良好です。
ところどころ観客を捉えたシーンは笑える。白い肉の塊が軋み合って蠢いているのだな。肉饅頭。少し食い物を考えた方が良いだろう。おまけに担ぎ上げるわ、喧嘩はしてるわ、彼氏に肩車の姉ちゃんは裸だわ、と品が無さ過ぎ。
曲間やソロ部分には部分的にインタビューが挟まれるなど編集されている。ブラック・サバスに関しては、集大成たるライノ・リマスターの初期8枚組+DVD BOXセットをもって近々、もう一度真面目に振り返ってみよう。
NTSC、リージョン0。

Lavina Music
LM CD-402
Волшебство/Flëur
ウクライナのアコースティック・チェンバー、フルールの2nd。タイトルはヴォルシェブストゥボ、『魔法』の意。ジャケ違い、タイトル違いで中身は同じ(値段はえらく違うが)『Magic』なる英語タイトルがついたフランス盤が存在します。
リズムに若干バリエーションが加わって、アンサンブルもシンプルなものから凝ったものまで、アレンジに良い意味で洗練が加わった。ただし民族色が濃いものの方がこなれているように感じた。Webの写真にもありますが、YAMAHAのシンセ? をご購入なさったようで、さっそくいくつかの曲でそれらしき音を聴くことが出来るよう。意欲的に模索しているのでしょう。一方、室内楽的な展開とフルート+弦楽器の威力は、前作にも増して美しくも儚い調べを奏でるよう。頭二人が女性というかなり危うい形態だが、末永く続けて欲しいものです。
公式Webに置いてあるビデオも美しい。トップに置かれている「Remont(遡上)」はこの2ndの8曲目、「Ремонт」であるわけですが、朝日、コーヒー、オデッサと思われる港町の光景と黒海の砂浜、花嫁(表情がいいなぁ)、花売りの子供、老人、町、普通の人、洗濯バサミ、公園、風船、電動三輪車の女の子、マネキン、売り子、ほとんど意識的に顔を映さないで長いコート着て歩いているオルガ・プラトーワと文句なし。いやぁ、こんな曲書けるのって本当に素晴らしいし、それを聴ける幸せをしみじみ噛み締めてしまう。語る言葉がないとはこれをいう。
と、思っているうちに新作『Sijanije (An aureole)』が出ていた。英語ページで見ても曲名なんかほとんど英語にならないところが最高じゃないか。英語では絶対に表現できない日本語がある(まぁ、今となっては完全に少数派だが)ように、ロシア語にだって同じ事情があるのだろう。