
Musea
FGBG 4075.AR
La source/Minimum Vital
過渡期四作目。すべての曲が自前、またはゲストによる歌入りになったが、前作までの変拍子フュージョン・コンプレクス(複雑系という意味のほう)と中世世俗歌舞曲への傾倒が巧くミックスされた意欲作。民族色豊かな技巧的な舞踏リズムに載せたしなやかなメロディと作り込まれたアレンジが冴える。自前、ゲストともにいまひとつ頼りない歌声ではあり、次作で登場する専任シャントゥーズ、ソーニャ・ネドゥレには及ばないものの方向性は固まったとみるべきだろう。半分ほどの歌詞がプロバンス語と思われる。
ちなみにタイトルはソースじゃなくてスュルス。DVDではソルスって聞こえるけれどやっぱりスュルス。副題は「光輝なる八歌」とでもいおうか。全8曲、それぞれの曲に副題がついている。
「La source -Final(Prière)(泉-終章(祈祷))」
願わくは
願わくは神よ
この終の棲家で我等に慈悲を与えたまえ
死とともに去るために
生のために
この此岸に
神よ、願わくは
その彼岸にて我等を愛したまえ
死にゆくときの
死の扉を開きたもうな
開きたもうな
今日、もはや我々が再び“泉”、その水で我々を直に潤してくれる“生命の泉”を見出すことはないだろう。我々は自らの失った人間性を“泉”の魔法によって過去の楽しみに置き換えていくことになろう。我々はドラゴンに打ち勝って、古代の蛇を鎖に繋いだ。その結果、我々は踊り、歌い、夏のさなかに幸福な死を迎えることができるのだ。将来、地獄の敷居に直面しても、我々は何ら恐れを抱くことなく、その光輝を見ることが出来る。ただ闇の中で孤独に埋葬されることはないだろう。
裏表紙に綴られているジャン-リュック・ペイッサンによる言辞。馬に乗った中世騎士がとぐろを巻いている大蛇を退治しているスリーブと何らかの関係があるのだろう。説話の類いだろうか。
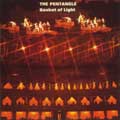
Castle
CMRCD207
Basket of light/Pentangle
イングランド・トラッドとブルーズ、ジャズの混合態としてのアコースティック・ラジカル・トラッドの完成形。三作目にして文句のつけようがない世間的にも名盤扱いされる内容を誇る。ジャズ色とブルーズ色もほどほどで明解なメロディと卓越したアンサンブルが特徴である。冒頭、TVのテーマ曲だが変拍子に乗った絶妙なメロディに唖然とさせられる。この醸し出される雰囲気、創造される音場は深遠にして崇高、厳粛にして精緻、半分弱がトラッドだが、程よい緊張感と余韻の美しい楽曲は感動的ですらある。歌姫の虚空を舞う薄光のような声と、それを支える男四人の演奏技術も的確で熟練した味わいが小気味よくも格好良い。
2001年の再発リマスターCDはオリジナル9曲に別テイク、シングルB面のボーナス4曲入り。

Mercury
838 965-2
Scarlet and other stories/All About Eve
おそらく最も評価が高い2ndアルバム。リーガン(Julianne Regan)の御声もますます磨きがかかって妖しく(撞着語法的にいえば)清廉に美麗で哀切なメロディを謳いあげておりまする。オクターブ狭いし、それほど上手いとは思わないが、その赤バックにも負けない可憐な美貌とともに纏う雰囲気と突き抜ける感覚に虜になるのでしょう。ね。ライブでもズボン(イギリスでパンツといえば下着ですね)じゃなくてロングスカートとかワンピースなのだねぇ。作っているイメージなのかもしれないが、ロセッティやミレイの絵のモデルになったビクトリア朝の女性のよう。1stのゴシック風味が抜けてゆったりとした情感と質感を湛えた楽曲が大部を占めて、歌詞も韻をきちんと踏んだりして気持ちが良い。タイトル通りスカーレットという名の少女を主人公にした物語風トータルアルバム。
「December」
ビクトリア朝のブリキ缶、
わたしの想い出が封印された
それを屋根裏部屋で探し出し
内を覗いて見出した、ずっと隠していた秘め事……
残された葉はヤドリギのキスを免れて
郷愁だけがわたしに残された想い
あなたを失ったという
あのときのことを
憶えている? あの12月を
それはダイアモンドの光彩の傍らの針葉樹のよう
憶えている? あの12月を
降り積もる雪と夕映え
それは息を止めてしまうかのよう
でも、年月が記憶の行く手を塞いだ
憶えている? あの12月を
あの日はあなたの内に宿ったのだろうか?
バレンタインには似つかわしくない、
首飾りが輝いているのを見つけた
ワインなら間違いないと思うけれど
その輝きはすべてが現実だと思わせる
どこにも韻を踏むようなこともなく
埃を被った記念の品に生命の息吹を吹き込んで
そのうえ尚、雪片で鎖を繋ごうとするわたし
あるいは心の痛みを繋いでいるのかもしれない
そんなときがあったことを
憶えている?
この孤独に苛まれて、
電話を取り上げようと思う
あなたに電話して、
ハッピー・クリスマスと祈りたい
深い孤独に打ちのめされて、
電話を取り上げよう
この手にわたしの心を添えて
憶えているか訊ねてみよう
2000年代にアコースティック・ユニットとして再編されておりますが、わけわからんほど同じ内容で別ジャケとかタイトル違い、やっぱり一部別テイクなどリリース状況が滅茶苦茶なのは何とかして欲しいものです。
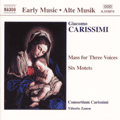
NAXOS 8.555075
Mass for three voices/Six motets/Carissimi, Giacomo/Consortium Carissimi
「三声のミサ」にモテット(時代によって意味は異なるが概ね宗教的な歌詞を用いた無伴奏多声部合唱曲を指す)を六曲加えたもの。初期バロックにおいてオラトリオ(う~む、オペラから演劇的な要素を取り除いたものといったところか)の原型を創りあげたジャコモ・カリッスィミ(Giacomo Carissimi:1605-1674)の小品集のようなもの。モンテヴェルディよりは若干後の人で、三声はテナー、バリトン、バスの男声のみに通奏低音としてオルガンやハープシコード、若干の弦楽器が加わるかたちが基本です。ミサだから、キリエに始まりグロリア、クレド、サンクタス、最後はアニュス・デイに終わる。ポリフォニックでない男声のみというのもなかなか簡潔で清々しいものです。歌詞はラテン語。全英訳付きのナクソス廉価盤。
代表作はオラトリオだろうが、オペラや能と同じく話の筋立てがわからないと(あるいは、物語に興味がもてないと)興味が続かないような気がする。それには個人的に語学力と教養が不足気味で今更梃入れするのもなぁ。

東方魅力
SEM20017-2
Bounce/Bobochan 陳文媛
送料を無料にするため帳尻合わせで買ってみた300円CDだが、海のものとも山のものともつかぬ不安は蓋を開けてびっくり。18cm角のスリップケース入りで美麗写真集、歌詞、ポスター付き。いまどき珍しい美人(一昔前の日本人みたい)でとっても可愛いけれど露出度は極めて低いあたりがお国柄(広東人かな)か。全8曲にビデオ・バージョンが2曲、HDCD仕様とサービスも満点。もちろん全部漢字だが歌詞までついていうことなし。
愛称はBobochanと書いてボボチャンとかボーボーチャンとかいうらしいが、それは日本人的な語感からするとあまり可愛くないと思うぞ。曲調はあまり中華色の強くない中華ポップス。もっとも中華色が強いゆったりと構えた曲のほうが全然良い。あんまり媚びないで自らのアイデンティティを見据えた音作りがやはり良いように思います。透明感の高い凛と響く声は意外に珍しく、尚且つそれなりに上手い。
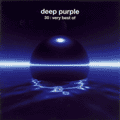
EMI
7243 4 96807 2 2
30:very best of/Deep Purple
かつての青臭い中学生御用達の深紫、唯一所有する音源にして30周年偏ベスト盤。正規盤ではない別テイク、シングル・バージョンで固められた往年の名曲集である。もうすっかりうろ覚えであるが、聴いていたのは『Burn』くらいまでか。以後に関しては皆目見当もつかないが、いや、まぁ、懐かしい楽曲の数々。う~む、聴いてしまうとここに含まれないものも聴きたくなって、『Burn』まで全部集めようか。イアン・ギランとブラックモア、ジョン・ロードだったか。「Child in time」「Smoke on the water」「Highwaystar」に「Burn」と嬉し恥ずかし昭和の懐メロじゃないか。今、改めて今の耳で聴き直してみるとそれほど派手でもハードでもなくて、とってもメロディアスでクラシカルだなぁと考えを新たにしている。

curved light
CU-LT CD001
Lupi sintetici e strumenti a gas/Patrizio Fariselli project
アレアの鍵盤+管楽器奏者+コンポーザ、パトリッツィオ・ファリゼリの近作。オザンナの復活ライブでもあるプログ・イタリアーノ30周年記念フェスタ(おお!、なんと正しい言葉遣いだろう)でもその健在振りを示しておりましたが、単なる回顧に留まらない斬新と意欲に満ちた良作です。民族調の衝撃的なメロディで幕を開ける、精密でハイテンションなジャズ・ロックにしてアレアを継ぐもの。アンジェラ・バッギ(Angela Baggi)なる女性ヴォチェの存在もはまり役で、かつてのデメトリオ・ストラトスのように百変化で歌うのだが、しっとりした曲を聴くとその実力がよくわかる。声質はアルトで湿った穏やかさから突き抜ける雌叫びまで。もちろんころころ入れ替る変拍子と転調をこなすアンサンブル全体の力量も遜色はまったくない。
タイトルは『合成狼と気体楽器』。なんとも妖しく艶めかしい(まぁ、蘭は皆こんなものだが)スリーブも秀逸。
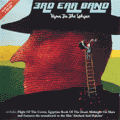
Mooncrest Records
CRESTDCD 067
Hymn to the Sphynx/Third Ear Band
どっこい生きている第三の耳団の新作+70年の未発表作+ライブにして2CD。72:49+67:28という長尺お買い得品。60年代後半にパーカッションのインド系? イギリス人グレン・スウィーニィ(Glen Sweeny)を中心とするアコースティック・チェンバー・ユニットとして出発している。70年初期に三作リリースしてその後の消息はまったく聞かなかったが90年代に入って新作が出だしたようで最初は見間違いだと思ったものだ。
いつのまにかお姉さんが加わって、若干色気のある楽曲を奏でてくれるようになりました。電気も使っておるし、ループするシーケンス・パターンの上でリズムがエスニックで単調な酩酊を刻み、生音がうねりのたうち散華するという迷宮でありながら、かなり強迫的に迫ってくるところなどもあって過去を髣髴とさせる。さすがに今のものは、ここでも聴くことができる70年代ものの偏執狂的なまでの狂気は感じられないという意味では大人になったのだろう。
ライブもうねるようなグルーブまで感じられて期待以上に聴かせます。バイオリンのおっさんはステージに胡座かいて、残る三人は椅子に座って黙々と演奏しているところなども新鮮。かつては視覚的な情報が皆無だった故、わけのわからない不気味なイメージだけが先行していたものです。
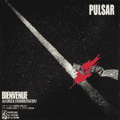
Musea
FGBG 4355.AR
Bienvenue au conseil d'administration/Pulsar
四作目にして第一期の最終作。御他聞に漏れず時代の流れの中で不運にも埋没していく時期でもあった。正規盤ではあるが『ようこそ取締役会へ』なる劇伴音楽ということで、音だけ聴く分には起承転結がわからないこともあって構成がいまひとつ不明解。もっともそれぞれの楽曲の出来はタイトで高質、第一期の集大成に相応しいものになっている。ラストに向かっての盛り上がりもそれなりに劇的で、前作までのうろうろと漂うような静謐感とは若干趣が違うようにすら感ずる。独特の浮遊感と切ないメロディは健在で、冷涼で流麗な展開とフランス語の台詞が深い青の底を思わせる。
オリジナルは劇場でのみ販売された自主制作。ボーナスとして4曲、30分強収録されている86年のジャック・ローマン(Jacques Roman)名義でのソロ・カセットの出来も素晴らしい。89年の最高作『Görlitz』へと継承される完全な布石とみてよいだろう。
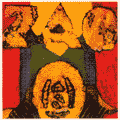
Musea
FGBG 4125.AR
Akhenaton/Zao
カーン+セファーにジャン・ミー・トルーン(Jean- My Truong)が復帰した一時再編ザオの新録アルバム。内容的には『Kawana』の延長線上。曲は概ねコンパクトでタイトな方向性でまとめられているようだ。バイオリン奏者(Patrick Tilleman)とベース(Dominique Bertram)も過去のZAO在籍者でテクニックは申し分ない。クールで押さえ気味のアンサンブルも70年代とは違った意味でコンテンポラリな魅力を上手く引き出しているように思う。総じてエスニック色は強くないが、アラビア風の乾いた彩度の高い色彩感が全編に漂う。ラストのカーン、セファー共作「ネフェルティティ(Akhenatonの妻)への花束」なんぞ、ロマンティックでシャス・スプリーン(Chasse-Spleen)でも飲みながらまったりとした時間を過ごすのに最適。こっちもそうだが、ZAOの皆さんもお歳ですし、セファーはそろそろ娘の方がよいなぁ。
タイトル『Akhenaton』はイクナートンで古代エジプト第18王朝の王、Amenhotep4世(:宗教改革者で最初の一神教信者)を指しているのだろう。
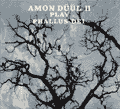
Repertoire
REP 3016
Play Phallus Dei/Amon Düül II
初期の25分ほどの長曲「Phallus Dei」のライブ映像を納めた発掘フィルムのDVD。タイトル「Phallus Dei」はミサの主題「Agnus Dei」をもじったもの。「アニュス・デイ」と読んで「神の子羊」という意のラテン語。月のアモンの方は『神の陰茎』という意なのだろうなぁ。ちなみにギリシャ神話だとウラヌスのちょん切られた陰茎が海に落ちてそこから生れたのが愛と美の女神であるヴィーヌスであるということになっているから、あながち冒涜というだけではないのかもしれない。
ビデオとしてはとにかく古いし、素人撮影のようでアングルもパンもズームも無茶苦茶。途中ちょん切れで関係ない映像が挿入される等1000円台だったから、まぁ、許したろうかといった按配。いちばん印象に残ったのはカーレルがころころバイオリンやらギターやらを持ち替えるところと、何といっても若きレナーテ・クナウプ・クレーテンシュバンツ嬢のびっくりするくらいの美貌でしょう。あまり出番がなくて戸惑い気味でつまらなそうなのだけど極めて普通のお嬢さんといった趣が麗しい。
NTSC、リージョン0
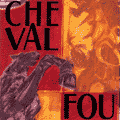
Legend Music
LM 9004
1975
Cheval fou/Cheval Fou
フランスのアモン・デュールIIと云われたかどうかは知らないが、どろどろアングラ・サイケ、シェヴァル・フュー(暴れ馬)の70年代初期のアルバム、その他のデモ音源等をまとめたもののようだ。計75:45のテンコ盛り。ギターのペトー兄弟(Jean-Max Peteau, Michel Peteau)にパーカッション(Stephane Rossini)が加わったトリオ編成。
しかし、内スリーブの写真を何気なく見ていると微妙に記憶の底を刺激するものがある。どこかで見た顔と思ったら、やはりそのまま前回のNILでした。CDを捜し出して確認したら70年代のNILは実質ミシェル・ペトーとロッシーニなのでした。レーベルも同じだし、録音の悪さもそっくりだ。しかし、人間の人間の顔に対するパターン認識というものには微細な差異を見分け、かつての面影から共通項を搾り出してしまうまで機械を越えた空恐ろしいまでの能力が秘められているのだろうなぁ。本当は嬉しいのだけれど平静を保っている顔とか、言いたいことがあるのだけど言えないでいる顔とか。
1stや2ndのころのアモン・デュールIIに酷似したフレーズや音使いもさることながら、エスニックで刺激的な嬌声、でろでろとドライブするリズム、75年作の時間切れで切り詰められたようなラスト曲「La fin de la vie...(臨終)」に至ってはアンビエント・ループ風の酩酊感が浮遊する快楽を醸し出している。
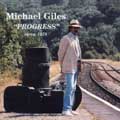
Voiceprint
VP264CD
“Progress” circa 1978/Michael Giles
70年代に録音されていながらリリースされなかった蔵出しソロ・アルバム。クリムゾン以後の事情についてはジャイルズ本人によるライナーにこと細かく書かれている。録音はドーセットの自宅スタジオにキャラバンのジェフリー・リチャードソン、ジョン・G・ペリー、もちろん弟その他を招いて行われたとある。タイトル通り、およそ78年ごろには完成していたらしいが時期が悪いので寝かすことにしたそうだ。その後はTVや映画音楽の作曲、マイケル・ナイマン、ジェイミー・ミュア(Jamie Muir:あのクリムゾンの)、カニンガム(David Cunningham)あたりの現音人脈と仕事をしていたらしい。どうりで陽のあたる表舞台では名前を聞かなかったわけだ。
夏のイングランドの朝日をついてシティを発ち、カントリーサイドを走り、黄昏のコーンウォール(イングランド最南西端の保養地)に到着するまでを綴った列車の旅の叙事詩。凝ったリズムとさり気ないテクニックの応酬、ジャイルズ自身による楽曲の出来も味わいのある洒脱なものでしょう。ラフな格好をしてもジャケットと帽子は必携という典型的な中流階級(庭も広いし)のようですが、汗の臭いを感じさせないさらっとした知的なドラミングは(78年の録音だから当然だけれど)健在です。

CTCD-100/101
Cha Cha 2000 -Live in Tokyo/La! Neu?
ノイ! 後、クラウス・ディンガー主宰のラ・デュッセルドルフ(La Düsseldorf:自らの居所であるドイツの地名にフランス語女性名詞に付ける冠詞を冠したもの)の2nd『Viva(万歳)』に収められていた「Cha cha(チャチャ)2000」の2000年光臨ライブバージョン、2CDで全一曲(57:43+46:39)、96年東京でのライブ音源。仔細はわからないが2CDの一枚目と二枚目は原曲の意図を考えれば順序が逆なのだと思う。逆からたどるような構成は、後にVol.2として同じ東京でのライブの前半がCD化されているから何らかの意図があるのかもしれない。
“ちゃちゃにせん”と日本語で歌うヤケクソなのかサービス精神なのか、これまた不詳であるが、中身はアンビエントテクノ風味太鼓パンク。キーボードは控え目で緩急、お遊び、アンビエント・ピアノソロ、その場で思いつき即興を挟みながら延々と続くハンマービート、あったりずれたりするツインドラム、お経、和太鼓ドンドコ、人の遠吠え等々プロフェッショナルなショウを放棄した内輪のお楽しみ会の乗り。ディンガーはドラムではなくてリズムギターを弾いているようだ。リリースは日本のインディから。おかげで入手が大変だわ。
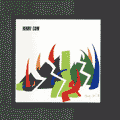
ESD 81652
Western culture (remastered + bonus)/Henry Cow
グリーブスは既におらず、実質的にアート・ベアーズと分裂状態に陥っていた四作目にして最終作。全曲インストの極めてシリアスで息苦しいまでの緊張美と緻密に作曲された構成美が隙間なく充填された室内楽の現代における完璧な完成形。タイトルが自負なのか皮肉なのかは知らないが、どちらにしてもその内容にふさわしい完成度を誇る。というか、この系統でこれを越えたものはないでしょ、という方がわかりやすい。もっとも、ホジキンソンがいうにはカウで最も軟弱なアルバムだそうで。ははぁ。
すべてホジキンソン+クーパーの楽曲のみで構成されている。前半ホジキンソン作には“History & prospects(歴史と展望)”、それに対するように後半クーパー作には“Day by day”なる副題がついている。演繹的展開と帰納的収束。 ホジキンソンは一応鍵盤奏者だが本職はクラリネットやサックスの木管、クーパーはもちろんバスーン(ライブではフルートやオーボエも吹いてるけど)が専門で、楽器としての歴史的成立過程を鑑みてわかりやすく解釈するならば、琴も弾けるけど本職は篳篥(ひちりき)ですというに等しい。
ボーナスは三曲。かなりの間をとって始まるあたり当初リリースの完成度を壊さない配慮がなされています。槌と鎌が山? を突き崩す左翼的ジャケ絵(というか切り絵?)はもちろんカトラー作。
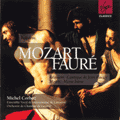
Virgin Classics
7243 5 62325 2 5
Requiem/Mozart/Fauré //Michel Corboz
ヴェルディを含めて三大レイクイエムと称されるうちの二つが収録された2CD。録音はフォーレが1993年、モーツァルトのレクイエムは1995年のライブ。レクイエムは鎮魂歌と訳されて葬式の歌のように思われていることが多いが、実際には今は行われなくなったレクイエムという形式のミサそのものを指し、これら楽曲としてのレクイエムは煉獄に落ちた死者の魂の救済と罰の軽減を祈るためにそのミサで歌ったお祈りの歌を指す。
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(Wolfgang Amadeus Mozart:1756-1791)のレクイエム(K.626)は未完成の絶筆。後年弟子が書き加えて完成させたもの。貧困にあえいで35歳で没し、ウィーンの墓地に埋められたそうだが、誰も葬儀に立ち会わなかったのでどこに埋められたかわからない(無縁仏の穴に放り込まれた?)という、なんというか生前のしょうもない人柄が偲ばれる死に様だったようだ。書いた本人はただの一度も演奏されるところを見聞きできないという、手直しも出来ないしアレンジも変えられないという、考えてみればある意味壮絶な楽曲でもある。モーツァルトが書いた部分と弟子の補填で若干異なるが、その圧倒的なまでの情感は比較の対象をもたないというか、300年以上昔の古典中の古典だとはいえ、今聴いたとしてもそんじょそこらのプログを完全に凌駕する斬新性と革新性には圧倒されてしまう。
基礎もないし感性もないし(ついでに面倒臭くなくなってきたし)音楽に関わりもないので、モーツァルトを語るつもりも語れる素養もないが、経験的に天上の声系の美麗華麗透明感とあり得ない展開、意表をついた構成を主調にした明るい曲が多いように思う。短調の曲は比較的珍しいが、その場合、こめられた哀惜が滴り落ちるほどの圧倒的なまでの情感の演出はこの世に存する音楽のなかでも最上の部類であることは間違いない。硬質な透明感と痛々しいまでに清廉な天上の至福。
フォーレ(Gabriel Urbain Fauré:1845-1924)は近代フランスの繊細で華麗な音楽家。それなりの地位にあった人だが、やはりあまり誉められた人格ではなかったようでそのせいかどうかは不詳だが(レクイエムといいつつも)宗教色も薄い。このレクイエムは母親の死後、ほんの十日で完成させたといわれている。劇的なディエス・イーレ(Dies Irae:怒りの日)を含むモーツァルトに比べれば遥かに優美で静寂、深く染みわたるゆったりとした上品で長い旋律が特徴である。時間も短くて40分弱ですっきりとまとめられている。
ジャケ画はルーアンのミュゼ・デ・ボ・ザール蔵、カラヴァッジョ(Michelangelo Merisi da Caravaggio:1573-1610)の「Flagellation du Christ à la colonne(柱に縛り付けられて鞭打ちされる耶蘇教教祖)」の部分。この画家も本当にどうしようもない人だったようで、現代においては再評価されているとはいえ、敢えて採用するあたり選者なり企画者の意識的な過程が面白いというか、意味深といえば意味深。