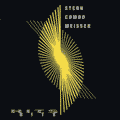
BMG/AMIGA
74321326182
Hits/Stern Combo Meißen
旧D.D.R.のシュテルン・コンボ・マイセン、77年から82年に亘る国営アミーガ・レーベル時代の全10曲、71分越えのシングル・コンピと思われる。頭はムソルグスキーの「禿山の一夜」、ラストはヴィヴァルディの「四季」から「春」他のリアレンジ改作で、中間にオリジナルが並ぶ。
ファンクなベースとタイトでソリッドなドラムによる精緻なリズムもさることながら、あたりを制圧する上品なメロトロン、完璧なコーラスと当時の西側ものにもまったく引けをとらない(むしろ完璧)質はCDにも堂々と記載がある通り、旧東独随一といって間違いないだろう。歌詞はすべてドイツ語。多分、2004年現在も現役、前回のLiftや以下のElectraとの合同ライブ盤などもリリースされている。
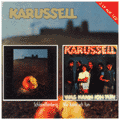
BuschFunk
8024-2
1984
Schlaraffenberg/Was kann ich tun/Karussell
これまた旧D.D.R.のポップ・ロック、カルーセル(回転木馬の意)の2ndと3rdにアウトテイク、ライブ音源をボーナス追加していると思われる計80分のカップリング・リマスター。歌謡曲風の優美でリリカル、親しみ易い歌メロと適確で新鮮なアレンジが特徴です。安定したテクニックとアンサンブルは国営の基準に適うものだし、特にギターの弾きまくるソロは見事としか云いようがない。それでいて媚びることも驕ることもなく、正しい芸道を歩む生真面目さを持ち合わせているという“東”でこそ初めて成立した非常に質の高いポップスであろう。
『Schlaraffenberg(怠けもの天国)』:2nd。何を揶揄しているのかは不詳だが、ジャケは遠くにぼける暗い建物と齧り捨てられた林檎。東欧トラッド調からブルーズまで、ポップな歌もの中心だが中音豊かなボーカルが映える。トータル・アルバム風にラストは再び頭に戻る。
『Was kann ich tun((君の代わりに)わたしに何が出来るというのか)』:3rd。これまた随分意味深なタイトル。キーボードに深みが出て、複雑な展開とアレンジが増えた。曲調もドラマチックに抑揚のついた怒涛のストリング・シンセが大活躍。歌ものからは脱却した聴き応え十分の格好良さ。歌詞はすべてドイツ語。
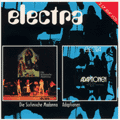
BuschFunk
8021-2
1980
Die Sixtinische Madonna/Adaptionen/Electra
まだ続く旧D.D.R.のエレクトラ、二作目と四作目のカップリング再発CD。前半『Die Sixtinische Madonna』が四作目。タイトルはそのままドレスデン古典巨匠美術館蔵、ラファエロ(Raphaello,Sanzio:1483-1520)の絵画『サン-シスト(システィーナ)の聖母』を指す。このマリアの表情は多分、類似絵画の中でも個人的にベスト。
前半、『サン-シストの聖母』の旧A面タイトル曲は25分超え、女声合唱団入りのライブ。新古典主義的なかっちりとした構成と展開、荘重なまでの高揚感に溢れた秀作。曲の出来、アレンジ、バンド・アンサンブルのバランスは文句のつけようがない完成度です。醸し出される上品さと至高の美、それでいて自由度を失わない適確なリズム、どれをとっても素晴らしい。
後半『Adaptionen(編曲集)』はボロディン、バッハ、ラフマニノフ、グリーク、モーツァルト等の楽曲をアレンジしたクラシック+現音メドレー。六人組の楽団編成ですが、プロフェッショナルでありながら素朴で自然な情感の発露が心に迫る。
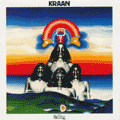
EMI Electora
7243 8 22669 2 1
Wintrup/Kraan
クラーン2nd。タイトルの『Wintrup』はドイツ北西部、ノルトライン・ヴェストファリアとニーダーザクセンの州境付近、ドルトムント近郊のハトラーおばさん(Hellmut Hattler:男)の出身地でもある森の村の名前。公式WebにはCIAが撮影した(本当はKGB)衛星写真が掲載されている。
前作よりも若干コンパクトな曲とアレンジ、エフェクト掛けまくりの中近東サックスソロがエスニックな情感を醸し出す、ラフなのか高質密なのか、的を絞らせないおふざけが決まり過ぎたハイテク・ジャズ・ロック。キーボードやSEも入ってかなり凝った作りになってきましたが、リードを弾きまくるハットラーおばさんのベースは相変わらずの突出ぶり。ギターソロは控えめだけれどお得意のベースソロはびんびん。

Brain
843075-2
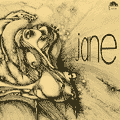
LP
Together/Jane
ジェイン(ヤーネ)の1st。トリミングされてずたずたのジャケ絵はなんだか意味不明のものになっているが、元はキュビズム風多面展開された女体であろうか。縦横無尽に駆け巡るオルガンとギターの怒涛の音圧とブルーズ演歌ぶりぶりの湿ったメロディ、安心して聴ける堅実なリズム・パターン、極めて抒情的かつドラマチックな展開が不細工なほどロマンチックで濃い。
1stのみで聴くことができるベルント・プルスト(Bernd Pulst)なる切なげな嘆き節専任ボーカルは、ノヴァーリスの1stと少し似た雰囲気を感じさせる。全曲英詩で通しているところはエロイと同じ。後のライブの定番となる長曲「Daytime」「Hangman」を含む良曲揃い。もちろん今でも現役しています。エンジニアはお決まりのコニー・プランク。

EMI CDP
564-7 46130 2
Computerwelt/Kraftwerk
テクノポップ・ブーム真っ最中、その中心で途方に暮れる元祖。既に温泉饅頭の元祖争い状態で雨後の筍のように、にょきにょき生えてくるエピゴーネンの勢いに押され気味。思い余った結果が「イチニッサンシ」。ジャケのIBMの原始的なパソコンも今は昔だが、変に衒って迎合しなかった分だけ音楽としては長生きできた。アナログでピコピコするのがファッションだった時代に、デジタル化の先鞭をつけたという意味でも意義深いものは感じる。一方で、スリーブの機械仕掛人形に見られるように、ロボットを人間が演じる、機械が生成する音楽を人間が演奏するような本末転倒路線を余儀なくされて、行き詰まりはもうすぐそこに見えていたのも事実だろう。
英語盤は聴いたことがないので、どこがどのように違うのか具体的に知らないが、これはタイトルの通りドイツ語ヴァージョン。
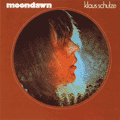
Brain
841353-2
1991
Moondawn/Schulze, Klaus
カセット音源しかなくてCD化されて買い直した一枚。いろいろ調べた限りではシュルツェ自身によるリミックスが施された『91年版Moondawn』とでも云うべきものらしい。全部聴いているわけではないから偉そうなことは言えないが、内容的には初期から中期への橋渡し。中身は聴かなくても概ね想像はつくし、事実その通りのもの。完全無欠な前作『Timewind』に比べれば、自分で作り上げてしまった一つの枠を超えようとするもがきと色気、あるいは繊細さと迷いが感じられる。昇り始めた月に銀色に照らされた沼地からゆらゆら立ち上る瘴気のような幽かな空気のゆらぎ。そんなナイーブな心象風景を丁寧に優しく描写していく。生ドラムはアシュ・ラ・テンペルのハラルド・グロスコプフ(Harald Großkopf)。
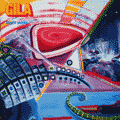
Garden of Delights
CD 035
1999
Night works/Gila
70年代初期に二枚のアルバムを残しているギラの未発表作。72年のラジオ番組「Nachtmusik(夜の音楽)」用のライブ音源で、最後の曲は時間切れでフェイドアウトしている。時期的には1stと2ndの間、1stの編成のアングラ・ブルーズ・サイケでのテイク。コンラート・ファイト(Conrad Veit)の出身地、シュツットガルトが拠点だったようですが、ライナーにはベースはスイス人、キーボードはフランス人と記載されていて、随分国際的だったようだ。“Gila”は毒蜥蜴の一種“Gilatier”からとられたそうで、ちなみに現在、首領のファイトは既に業界から足を洗ってハンブルクで絵描きをしているそうだ。
アシュ・ラ・テンペルやグルグルと同じく初期のピンク・フロイドの影響は多大なものがあるが、ほぼ全インスト曲で延々とのたうつように繰り広げられる即興はクラウトの真骨頂だろう。
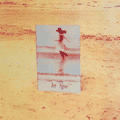
Musea
FGBG 4118.AR
Typewriter concerto in D/(Группа) In Spe
バルト三国最北エストニアのグルッパ・イン・スペー(in spe:おそらく元々はドイツ語の形容詞句、未来の~)、平たくいえば“未来集団”というかなり恥かしげな名前。エストニア語はフィン語と同系統のアジア・アルタイ語系だそうだが、如何せん辞書も資料もありゃしないので、あまりアテにはしないで下さい。これは85年の二作目と思われるアルバム。一応、79年結成の楽団形態だったようですが、1stとは異なって2作目はアロ・マッティーセン(Alo Mattiisen)なる鍵盤奏者が仕切るかたちになっているようだ。
全曲インスト、後半の小品集にはクラシカル基調ながらも華麗かつポップな楽曲が並ぶ。重暗くはないが冷涼で清浄な、フォーカス(Focus)かペッカ(Pekka)のような無国籍な感触が漂う。冒頭のタイトル組曲はクラシカルで上品なジャズ・ロック。木琴とフルートが印象的。ムソルグスキーやチャイコフスキーなどを範にした、スラブ系の現代音楽を音楽的基盤としているのだろう。ラストの長曲は冷たく儚げな、まさにジャケのイメージ通りのネオ・クラシック・アンビエント。イメージ通りの儚げな美しさが心に染みる。
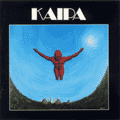
Musea
FGBG 4091.AR
Kaipa/Kaipa
スウェーデンのカイパ、1stアルバム。現フラ・キンのロイネ・ストルト(Roine Stolt)がかつていた楽団というと通りが良いらしいが、今のところフラワーキングズというのは冗談抜きで聴いたことすらない。フラワーキングズという表記が何語なのかは知らないが、キングズでは11件、キングスだと3,100件ヒットするので多分私が何か根本的に誤解しているのだろう。清く正しく品行方正、明るく暖かい北欧ヒューマニズムを基調にした、典型的な抒情シンフォ・プログ。今となっては古さは否めないが、初作は比較的短めの曲が中心で、穏健でかつ透明、謳い上げるボーカルが特徴。フェイド・アウトが多いところは興醒め。良くいえば牧歌的、悪くいえば鈍った包丁のような切れ味の悪さは田舎のわりにはマシな方か。カイパ=ルンディン(Hans Lundin)という認識なので、個人的に好きなのはクラシカルな色彩が色濃い「Ankaret(The anchor)」や「Skogspromenad」。全英訳付きで歌詞はスウェーデン語。原人Mみたいなカバーイラストはストルトによるもの。

WSM/Rhino
R2 60204
Tubular Bells 2003/Oldfield, Mike
音質には定評のあるライノ盤CDDA。30年前の焼き直しで安売りで1500円はちょっと高いが、一応、新録音ということで微妙にアレンジも変わっている。敢えてCCCD回避の向きにはビデオが追加になったDVD-Audio版もあるようであまり値段も変わらないのだが、うちのオーディオ・システムではまだ再生できないので見送った。98年の『III』以降の近年のものにはどうも手を出す気になれないが、これは懐かしいので買ってみました。
一聴して、クリアな粒立ちでありながら周波数帯域の狭まった今風のコンパクトな音は当然として、かなり解釈というか受ける印象が変わった。繊細であることに変わりはないが、原盤のペシミスティックな叙情性はそれなりの経験と熟練に裏付けられた一本芯のある良くいえば洗練、悪く言えば手慣れ過ぎな老獪さに取って代わられた。明るいカリブの海のようなイメージと、初作の北海の寒風吹きすさぶ海辺に焚き火か鳥の死骸が転がっている暗鬱で絶望的なイメージの間にある圧倒的な差。それは多分、恵まれない出自から伸し上がった自信であり、確立したアイデンティティなのだろう。
内スリーブに記載されている「このステレオレコードは、“いまだに”たとえ形が合ったとしても古いブリキの箱では演奏できない。もしあなたがそんなものを持っているなら、さっさと最寄の警察署にでもくれてやれ」というのは、音に対するこだわりを示すジョークなのだろうが、30年前の初作『Tubular Bells』のLPジャケ裏に“いまだに”を除いてそっくりそのまま記載されていたもの。

Cherry Red Records
CD BRED 110
Hystery/Geesin, Ron
「Atom Heart Mother」の実質的な作曲者としてピンク・フロイドふぁんからは徹底的に無視されるイングランド人現音作家、あるいは音楽職人ギーシンの全28曲、76分超えのアンソロジー。何故かバンジョー奏者としても腕は一級。もちろんバイオリンやピアノもそこそここなすマルチ奏者でもあります。1966年から1994年に至る間に20枚以上の音源があるようですが、もちろん殆ど手には入らないようだ。
ルイ・アームストロングやディキシーランド等、黒人の古典ジャズの要素と、エレクトロニクスを使ったノイズ・アンビエントのなんとも軽妙で楽天的な異種結合の奇矯なセンスが楽しくもけったい。極めていかれた独創的でキッチュなセンスは音ばかりでなく、人物としても極めてひょうきんらしい。
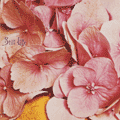
Repertoire Records
REP 4198-WP
Still Life/Still Life
覆面楽団としてそれなりに有名らしいスティル・ライフの唯一作。リリースは70年、イギリスのヴァーティゴから。覆面ゆえにインディアン・サマー(Indian Summer)あたりと取り違えられることもあったらしいが、直接関係はないようです。その前身をPeepsとかRainbowsといったらしく、実体は Martin Cure:vocal、Graham Amos:bass、Terry Howells:keyboards、Alan Savage:drums のギターレス・カルテット。スティル・ライフに改名する前の時点ではギターに後のネクター(Nektar)の親分ロイ・アルブライトン(Roy Albrighton)がいたとか。へ~え。
総じて明るくない、粘っこい曲調と全編に流れるハモンド・オルガン、重くてばたばたしたリズム隊が時代を感じさせる。可愛くてポップな歌とブルーズ色の濃いアンサンブルが特徴か。ジャケット・デザインは一見、美しくも悩ましいセント・ポーリア? で一杯の少女趣味風ですが、ゲイトフォールド・スリーブを広げると、ごらんの通り。哢笑が聞こえてきそうなセンスだ。もっとも、CDでは意図不明なまでに完璧にぶち壊しになっております。

Akarma
AK 182
Cressida/Cressida
当時はヴァーティゴから同じく70年にリリースされていたクレシダの1st。クレシダは“ウスバ蝶”かシェイクスピアの『トロイラスとクレシダ(Troilus and Cressida)』に登場するヒロイン、トロイの神官カルカスの娘のことだろうか。内ジャケの雰囲気は後者を指しているように思える。爽やかで清々しい全12曲。短い曲ばかりですが、展開や抑揚に粋を凝らした質の高さは70年としては出色の出来であろう。コンパクトでアップテンポなものから、アコースティックな儚さを朗々と謳い上げる憂愁を湛えたメロディアスな歌曲が気持ち良い。派手ではないが楽曲の良さと適確でさっぱりとしたアレンジが秀逸。全体を引き締めるオルガン、ピアノ、ハープシコードも地味だが味わい深い。
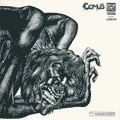
Dawn
22DN-69
First utterrance/Comus
しつこく続く70年もの。まぁ、古過ぎるとリコルクされてしまう葡萄酒と違って、リマスターで甦ることもあるから良いではないか。コーマスは飲酒宴楽を司る有翼のギリシャ神話の若い神で、ギリシャ語で「お祭騒ぎ」を意味するそうですが、ここで描かれる世界は、多くの例に習って微妙にぼかされた当たり障りのない“神話”ではなくて、ヒューマニズム基盤の価値観の隆盛と共に御伽噺風の体裁は持つものの、かなり強烈で直截的な内容になっている。もちろん今なら完全に犯罪。どちらかというと、サテュロス(Satyros)なる男神のほうが合っているような気がする。
「Drip drip(ポタ…ポタ)」
ぶら下がってゆらゆら揺れているおまえ
吊るされて、くるくる廻って、ぶ~らぶら…
柔らかく白い肉体はわたしの前で血まみれになる
おまえの憎悪の目付きは悪魔の呪いよりも呪わしい
おまえの愛しい躰はもうすぐ泥で厚く覆われる
おまえを墓に運んでやろう、わたしの腕が霊柩車だ
おまえはわたしの前で無抵抗だ
おまえの動かない、冷たく、鋭い眼差しはわたしを恋焦がす
おまえの垂れ下がった唇からポタポタと
真っ赤な液体が白い躰に広がって
柔らかな胸、深いへその泉はキラキラと輝き
椅子にかかったおまえの影は、山を越えて飛んでいく飛行機のよう
濃密な森の秘密の間で、陽光が透明に踊る中で
おまえはその蒼ざめた美しさをゆっくりと休めるがよい
馨しき林間にその身を祭るのだ
その亀裂にはわたしの刃が挿入されて
おまえの躰は大地の静寂に満たされる
さぁ、おまえを切り刻もう
そう、これが最後の物理的なコミュニケイションだ
出来るだけ優しく、苦痛は与えない
エキセントリックで叙景的というか演劇的な男女ボーカルとアコースティックなサイケ・フォークのつもりだったのだろうが、やり過ぎて蒐気迫るチェンバーに近い。軋むようなフィドルの暗鬱な音色、フルート、オーボエ、土俗的なパーカッションがとぐろを巻いて精神疾患にどっぷり浸かった病的な美を垣間見せる。

Edsel
medcd 726
Cathedral Ocean i & ii/Foxx, John
その30年後、「巨大な、半分水に浸かった廃墟と化した聖堂のための音楽」と題された97年の『i』と2003年?の『ii』のカップリング2CD。全曲インストのお耽美アンビエント聖歌集です。聞こえてくるものは、サンプリングされたクワイアとひたひたとたゆとう至高の真美。芸術至上主義的なまでのロマンチズムと冷え冷えと凍りつく氷の蒼さを透かし見るような明晰な論理が普く敷衍された黄昏の領域はあまりにも悲観的だ。
昨今はもっぱら欧州各地の廃墟巡りに精をだしているそうですが、「水没する」というのはあくまでイメージ上の幻視と思われる。過去『Systems of rommance』において“大地が海になる”という感覚は既に呈示されている。
脳裏に湧き上がるイメージは“Golden Green”。「金色の緑」である。緑の蔦に覆われた大天使ガブリエル、ミカエル、ラファエル、ユリエル。発光する金色。突き抜けて何も残らない無為と虚構、あらゆるものが透明にそして、不可視に、見えないことの無窮と静謐。 彼岸へ。