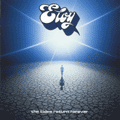
A.C.I CD
084-48202
The tides return forever/Eloy
昔と同じ名前で出ているエロイ、何作目かは既によくわからない。当然、時代なりの味付けが施されて、滑らかでかつ洗練されたメロディを聞かせている。かつてのとろんとしたまだるっこしさは嘘のように消えて、タイトで清涼感溢れるプログ・ハード(でもないか)路線の延長線上。一つのジャンルにドップリ漬かったお約束的予定調和に微妙な郷愁とネオ・クラシック色が加味された。どういう経緯か知らないが一曲、ジャンヌダルク(Jeanne d'Arc;1412-1431)の歌でミリアム・ストックリィが天使のお告げのフレーズを歌っている。
オリジナル・メンバーはギターのボルネマン(Frank Bornemann)のみだが、80年代後期からのキーボードのゲルラッハ(Michael Gerlach)に加え、今作から70年代後期のベース、マッツィオル(Klaus-Peter Matziol)が復帰したようだ。歌詞は全曲英語ですが、何年経っても上手くならないところが良い。
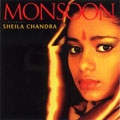
Mercury
314 526 527-2
Monsoon/Chandra, Sheila
顔ジャケ三題その一。そういえば普通CDの表面を飾るのは人間の顔であることが多いことに気付いたのはいつ頃だろう。逆に想えば所有CDの表スリーブはほとんど顔ではなかったりして不思議な思いに駆られるものだ。マイク・オールドフィールド然り、ミヒャエル・ロータ然り、ギター奏者や歌手に顔ジャケが多いのは目立ちたがりと自意識過剰の賜物であり、宣伝広告の常套なのだろうが、音に興味は引かれるが作り手の人と成りは正直どうでもよい。まぁ、手法としてどうやってこの音を出しているのかと云う部分で、ライブや映像に興味がないわけではないし、見映えが良いに越したことはない。でも、画集の表紙が画家の顔でないように、本の表紙が作家の顔写真でないように、個人的には極めて本質を蔑ろにした異質な感覚であると思っている。
顔はインド・アーリア系だが大方インド系イギリス人だろう。スティーブ・カウ(Steve Cow:本名?)なるプロデューサ兼プログラマとつるんでいる現在進行形です。インド音階の多用や努めて民族調なメロディであるにせよ、エスニック色はほどほどで、洗練され過ぎの感がある。この時点では所謂ワールドミュージック風のポップスと捉えた方が正確か。一応、シェイラ・チャンドラのデビュー・アルバムですが、82年のオリジナルのタイトルは『Third eye/Monsoon』。モンスーンというユニットのアルバムに+αしたもの。額の真中にあるのが第三の眼なのだろうなぁ。

Taurus
TACL-2400
淡淡幽情/鄧麗君
典型的な漢民族である鄧麗君(テン・リーチュン)は一般的にはテレサ・テン(Teresa Teng)として知られているらしいが、そちらは逆にほとんど知らない。95年、タイの古都チェンマイで死んでいた(変死、病死諸説あり)という故人。
テレサ・テンは日本では歌謡曲の歌手だったと思ったが、これは香港で録音されて高い評価を得たもの。宋代の不定形自由詞(唐詩に対して宋詞という)をそのまま歌詞にした全12曲。宋は唐の後、五代十国時代を経て、元に至る960-1279年に栄えた北宋、金、南宋の時代を指す。漢詩としては唐代の定型韻律詩の影で一般にマイナーな扱いですが、長さの問題から韻律詞は歌詞にするには不適当だから、あるいは口伝で歌い継がれた宋詞がふさわしいとして選ばれたのだろう。
一つだけ短いものを。
「獨上西樓」
無言獨上西樓,
月如鈎。
寂寞梧桐,深院鎖淸秋。
剪不斷,
理還亂,
是離愁。
別有一番滋味 在心頭。
「一人西楼に上る」
無言で一人西楼に上れば、
月は鈎のごとし(のように暗く細い)。
寂しげな梧桐(アオギリ)が奥庭にあって、薄ら寒い秋を閉じ込めている。
断とうと思っても剪れない、
整理をつけようと思っても、尚まだ乱れる、
それは故郷への郷愁。
なんともいえない一種の味わいが心に生ずるものだ。
本来は「烏夜啼」という詞で、作者の李後主(李煜:りいく;937-978)は五代十国の一つ南唐最後の国主である。国は侵略されて他国に幽閉されていたときに詠んだ詞。その後毒殺される。
曲調も音も特に古典的というわけではなくて83年当時のコンテンポラリーなもの。作曲はすべて中国人だから中華風ではあるけれど、ポップスとして十分通用するレベルでしょう。
ブックレットの駅はシンガポールにあるマレー鉄道の終着駅ですね。似たようなスタイル(いや、見目ではなくてね)で、くそ暑い日差しを浴びながらぬるいビールを飲んだことがある。
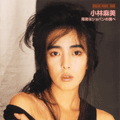
Sony Music House
MHCL10
雨音はショパンの調べ/小林麻美
こんな風に見詰められてしまうと、思わず「こんにちは、ご機嫌如何ですか」とか言って眼底検査でもしてしまいそうです。遥かな昔、休暇のたびに某火山の麓にある高原別荘地に集合離散を繰り返していた折りに盛んに聴かされて耳にタコが出来た音源の復刻ミニアルバムのようなもの。6曲入りCDDAで定価1050円と格安。Sony系列だけどこれはレーベルゲート(もう撤退?)ではなく普通のCD。今聞くとちょっと古臭いドラムマシンによるユーロビート風のアレンジが当時は“新しかった”だけに御愛嬌だが、一つの時代を象徴する音源だろう。
歌詞が聴き取れない舌足らずさが特徴でもあるのだろうが、原曲の良さも相まってバブルな世相と完全に合致した華やかな切なさを表象する。みんなパール入ったピンクの口紅にセーラムとか吸ってたね。
一応、元々はアイドルなのだろうが若い頃はあまり記憶にない。この曲で何年かぶりに再デビューを果たしたと微かに記憶している。同時期にカメラマンとしても写真集を出版していた。そっちも実は結構好きだったり。原曲はイタリアのガゼボ(Gazebo)。日本語歌詞は松任谷由美。

Rama Lama Music
RO 50492
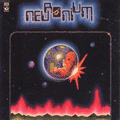
1st (1977)
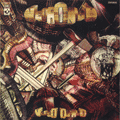
2nd (1978)
Quasar 2C361/Vuelo Químico/Neuronium
スペインのキーボード・アンサンブル、ニューロニウムの77年の1stと78年の2ndのカップリング2CD。既にかなりの枚数のアルバムが出ているのですが、極めて入手性が良くない。この時点では顔役でキーボードのミケル・ウィゲン(Michel Huygen)を中心に、ギメネス(Alberto Giménez)のギター、ギラオ(Calros Guirao)のフルート等もソロをとる鍵盤トリオ編成で、タンジェリン・ドリーム辺りに範があるのは明らかなのだが、フルート、ギター等の生音は節操なくメロディを奏でたり、歌詞付きボーカル入りの曲があったりするあたり方向性はかなり異なるだろう。それでも、最近のものに比べればずっと実験的で、アヴァン・ガルドな方向性であるが、メランコリックに湿った抒情性と甘く艶やかな微かな南国色がとても気持ち良く押し寄せる。
1st 『Quasar 2C361』:クエーサーは準恒星状電波源で、当時は準星と云われていただろう。実際には星ではなくて銀河そのもの。非常に遠くにあって最も明るく輝く天体で実体(というかエネルギー源)は超大質量ブラックホールと考えられている。タイトル曲は電波が飛びかう中をアコギのアルペジオとフルート・ソロが彷徨するような曲ですが、それを含めて抒情的でゆったりとたおやかなメロディが美しい。
2nd 『Vuelo Químico(化学的な飛行)』:前作に比して、更に角がとれたような印象。飛躍的に音が良くなって、深みが増した。楽器生音もあまり目立たなくなってテクニカルな意味でも初期電子音楽の体裁を整えたといったところ。前作がマクロなら今作はミクロを示しているのだろうか。タイトル曲ではポーの詩をニコ(Nico)が詠唱している。
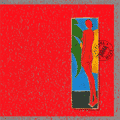
Spalax
14242
Tropical Heat/Ashra
85年頃に録音されたお蔵入り音源の91年リリース。順番から云えば『Belle alliance』の次ということになる。一応、グートシンクにウルブリッヒ+グロスコプフを加えた体制で製作されているようだが、曲によって欠けたリ加わったりといい加減。中身の方はスリーブの色合いといい、その名の通りの“熱帯”もので、曲名まで、1;蚊踊り 2;熱波 3;可愛木瓜(パパイヤ) 4;汗の夜 5;ファンを止めないで 6;季節風 とそのもの。『Belle alliance』路線の継承か、サンバからワルツまで明るくエスニックでミニマルなリズムがとうとうと流れ、ループしている。
ちなみにうちのスリーブは逆折りのようなので、公式サイトに準じました。
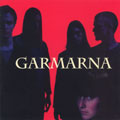
Omnium
OMM 2014D
Gods musicians(Guds spelemän=Fiddlers of God)/Garmarna
北欧民謡ガルマルナのアルバム二作目。GodではなくてGodsであることに注目すべきか。『神々の楽士』たちが仕えるのは北欧土俗多神教の神々であろう。デジタル・ループや電気処理された古楽器と躍動的なリズムのアンサンブルに加え、ヘルデリンの呪術的なまでの神秘的かつ深遠な声色で一気に花開いた感がある。
「狼男(Varulven(Werewolf))」
乙女が一人、森の別荘へ行こうと
:菩提樹の森がざわざわと震え
青の森を抜ける小道を通って
:愛の果実を運んでいた
青の森に着いたとき
そこで乙女は灰色の狼に出会った
あぁ、きれいな狼さん、どうか私を食べないで
あなたに私の銀のガウンをあげましょう
銀のガウンはまったく着れなかった
おまえの若い命と血で贖わねばならない
あぁ、きれいな狼さん、どうか私を食べないで
あなたに私の銀の靴をあげましょう
銀の靴は履けなかった
おまえの若い命と血で贖わねばならない
あぁ、きれいな狼さん、どうか私を食べないで
あなたに私の金の冠をあげましょう
金の冠は頭に載らなかった
おまえの若い命と血で贖わねばならない
乙女は樫の木の高みによじ登って
狼は地面を歩き回り吼えました
狼が樫の根元を掘り返し始めると
乙女は胸を引き裂くような悲鳴を上げました
それを聞いた灰色の馬に跨った従僕は
飛ぶ鳥よりもわずかに早く馬を走らせた
でも彼が森のその場所に着いたとき
そこには血塗れた腕が一つ転がっていた
森の神は慰め、労わった
:菩提樹の森が震えて
乙女は姿を消して、馬はへたばった
:乙女は愛の果実を運んでいた
タイトルを考えると狼は狼男なのだろうが、これは血生臭くないヴァージョンだそうだ。ブックレットの英訳がなんか今一つのような気がして自信がない。

PRWO13
Influências/Marco Antônio Araújo
ブラジル南東部、ミナス・ジェライス(Minas Gerais)州に勃興した所謂ミナス音楽のマルコ・アントニオ・アラウージョ。1stアルバム。ミナス・ジェライスは“あらゆる鉱山”の意で、エメラルドと金、鉄鉱石など豊富な鉱物資源には恵まれているが、かつてはポルトガル、今はアメリカ資本による搾取の象徴のような地域で、植民地支配の遺構と結果としてのキリスト教が最も普及している高原地帯。当人はメスティーソのように見えるが、結果的に教会音楽の影響を強く受けたヨーロッパ色が濃厚だ。
既に故人で、知っている限りで計四作の素晴らしい作品を残しています。経歴はライナーに結構詳しく載っているのだが、如何せんポルトガル語である。スペイン語とは似ても似つかないし、辞書も高いので内容が掴めるようになるのにはまだまだ時間がかかりそう。ヴィオラン(ミナス音楽におけるガットギター)奏者としての腕もさることながら、作曲者、アレンジャーとしての才を如何なく発揮している。自らはバックに徹し、フルートやチェロが美麗なメロディのリードを取って、リズム隊のアンサンブルにも独特かつ透明な感触が漂う、展開とアンサンブルの妙を尽くした室内楽。楽団編成で電気楽器もそこそこ使ってロック色もある。そしてなによりも4枚のアルバムすべて、ただの一曲も歌がない器楽であることに、その矜持に感服しました。
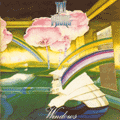
WEA
WPCR-1717
Windows/Taï Phong
毎度お馴染みジャケの鎧兜に今回は桜と苔、池の緑と東洋趣味が全開ですが中身に直接関係はない。若干の東洋趣味と冷涼なメロディが冴えるタイ・フォン二作目。前作に比して完成度は大きく上がっているといえるだろう。彼等の特徴は表面的な美麗ポップとは裏腹に、突き詰められた完成度、意外というかびっくりするほどの上質で適確なテクニック、緻密なアンサンブルあたりにあると思う。一方で、戦略としての英詩や他愛ない歌詞の中身、ポップなメロディ指向など歯がゆい部分をどう捉えるかで評価は変わるだろう。
元々、編成に無理がある(頭が三つ)形態だから長続きはしなかったのだろうが、それが逆に程よい緊張感に繋がっているのだろう。前半のスピーディな展開、後半のシックでアンビエントな音像定位とポリリズム風の展開、そしてタイ・シン(Taï Sinh)の曲作りとアコギ辺りが終局の兆しを孕みながらも切なく迫ってくる。
国産廉価盤はシングル曲のボーナス3曲入り。

Musea
FGBG 4322.AR
Ex tempore/Vital Duo
ミニモム・ヴィタルを率いるペイッサン兄弟によるソロアルバム。タイトルは『世俗を離れて』といった意だろう。本体は専任歌手が二人いるからやり難くなったことはこっちでやろうか、みたいな趣向か。半分ほどが13~15世紀の中世舞曲を自由に解釈したリアレンジで、アコースティックな感触とデジタル・チャーチ・オルガンの荘重で可愛らしいメロディが全編を覆う。ミニモム・ヴィタルの2ndアルバム『Les Saisons Marines(海の季節)』からも二曲がリアレンジで収録されている。非常にこなれた内容で、絢爛豪華なまでの豊穣なリリシズムと丁寧で真摯な歴史参照が確固たるオリジナリティと青と金の美学を奏でている。
このCDを半分ぐらいにして、ミニモム・ヴィタルのスタジオライブを足した100分ほどのDVDで見る限り、ギターのペイッサンはバスドラとハイハットを両足で叩きながら座ってギターやらリュートを弾いていて、まぁ、なんとも忙しそうというかバタ足している金魚みたいで動きが格好悪い。
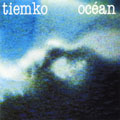
Musea
FGBG 4013.AR
Océan/Tiemko
クールで現代的なティヤンコの二作目。無調で冷たく上品な全曲インストのテクニカル・ジャズ・ロック。パーカッションのデローネ(Eric Delaunay:故人)を中心にしたトリオ編成のようで、畳み掛けるリズムと複雑怪奇、変幻自在な室内楽的展開が言葉では言い表し難い独特な質感を作り出している。
1;Épisode(エピゾド:挿話) 6:02
2;Hypercontraste(イペルコントラスト:強対照) 5:30
3;Bonbon très sucré(ボンボン トレ スュクレ:とっても甘いボンボン) 7:39
4;Vodka frappé(ヴォドカ フラペ:よく冷えたウォッカ) 6:51
5;Océane(オセアン:大洋) 21:55
食いものネタが目を引きますが、「1」の無調なギターと変拍子、「3」のクールで気持ち良いアコギ、「4」の輪廻転生風堂々巡り、等々、密やかに不安感を煽るキーボードと先鋭的に切れ込む冷たい肌触り、微かな予兆と共に挿入される煌びやかなフレーズが新鮮だ。

SKY
CD 870 3055
71/Cluster
クラスターの1stが廃盤になってドイツ、Skyレーベルから再発されるときに改題したもの。中身は『II』の前哨、古典的電子音響。物理学的な環境音響というべきか。既存楽器の生音は皆無といって良いほどの加工と、パルス発信のモジュレーション、エコーや音像定位、位相の操作を徹底して行った記念すべき1stアルバム。既に発音をループ状に繰り返すことによってシーケンサのような効果をあげているし、更に主たるメロディやリズムを捨象しているという意味では古典音楽の規範を逸脱しているだろう。
“K”のクラスターからコンラート・シュニッツラーが抜けて、実質的にコニー・プランクを含めたメビウス+ローデリウスの三人名義のクレジットがなされている。15:33-7:38-21:17という記載は曲を示しているのだろうが、曲名の記載はなく全部で「Cluster 71」ということで良いのでしょうか。

BuschFunk
8025-2
Lift/Lift
旧D.D.R.(Deutsche Demokratische Republik=ドイツ民主共和国)のリフトの1stアルバム。Amigaという国営レーベルから数多くの音源が発売されていましたが、その中でも“マイセン星”と並ぶ質を誇っていたと思う。時代物ですが、フルートと効果的なメロトロン、中音域の豊かなボーカルがなんともいえない郷愁と哀感を醸し出す。リズムは如何にもドイツ風な正確で精緻なもの。テクニックもけっこう変拍子バリバリだったりして、演歌調のメロディと決めのメロトロンのバランスが非常におもしろい。媚びない頑固な謹厳実直さと意外にポップで洗練されたセンスが素直に楽曲に顕れている。
ラストは1972年のシングル曲? がボーナスで追加になっている。近年、ブッシュフンク社からかつての“東独もの”がほんの10ユーロ前後で怒涛のようにリリースされて、大変喜ばしい。
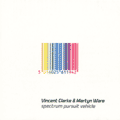
CDSTUMM
194
Spectrum pursuit vehicle/Clarke, Vincent/Martyn Ware
最初期デペッシュ・モードのソングライターだったヴィンセント・クラークのアンビエント作品集。相棒は天国拾七のマーティン・ウェア。といってもちいとも知らないのだけど、二人のコラボレーションとしては第二弾らしい。3Dオーディオ処理された立体音響として録音されているので、ヘッドフォンで聴くことが推奨されている。ハープやキーボードの楽器音と波や鳥の声、心音など自然音の位置関係がそれなりに規定されているようだが、耳が悪いせいか実際聴いてみてもよくわからん。曲名は白を含む色名で「白、黄、赤、青、緑、白」に至る6曲。それぞれ「天国、浜辺、子宮、水中、森、再び天国」を表わしているそうだが、それ自体は何とも安直で工夫がない。音の方は明るめで白っぽい光のイメージが強い。アトロピンで瞳孔散大したような眩しくて、差し込まれても逃れられないような美しい光景が垣間見える。これまた美しいスリーブデザインはバーコードを虹色に着色したもの。普通は短波長から長波長に、すなわち紫と赤が両端にくるように並べるがこれはちょっと珍しい。
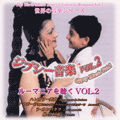
Cielito Lindo
CD-WO-5
ジプシー音楽vol.2/不詳
フィドル(バイオリンの古称)、アコーディオン、ツィンバロム(ピアノの原型)等を用いて、驚異的な奇数拍子と目まぐるしい展開、陽気でありながらも微妙に哀惜を募る音階とメロディラインは老若男女を問わず本邦でもお馴染み。一般的な認知を得ているといえるだろう。この100円CD、第一集が歌曲、この第二集は全曲インストとなっております。全10曲ですが、クラシックのリアレンジも多く、残りがルーマニアのトラッドかどうかはかなり疑問。演奏者、製作者、録音データ等も一切不明とないない尽くし。なんとなく聞いたことのある曲の方がいいだろ? みたいな感覚が透けて見える。
ジプシーは現在主としてヨーロッパ各地に居住する北インド出自のロマ族(かつてはルーマニア、ハンガリー等の非定住民族)を指し、その多くは音楽を専業にする職能集団でもあった。あるいは、タロットやフラメンコはロマが起源であるように“占い”や“踊り”にも長けていた総合芸能集団であったのだろう。もちろん、逆の観点から見れば文字を持たないロマ族が自らの歴史を伝える唯一の手段が芸能であったのだろうし、非定住被差別民としての必然だったのかもしれないが。
文字と所有権という概念を持たなかったおかげで生き易いのか生き難いのか、利子という概念を禁忌(つまり信用経済の根幹を認めない)とするムスリムと共に、定住型農耕社会を基礎にした現代の価値基準に乗り切れないことが差別と迫害を生むのだろう。
日本でも中世以降、猿楽や能楽が職能集団であったように、時代が下れば一部は権力者の庇護の下、芸術として定着するが、残りは旅芸人、祭りのテキヤ、香具師あるいは“ちんどん”等として現在に至る系譜もないわけではない。
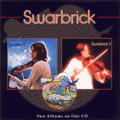
Castle
ESM CD 355
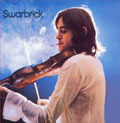
1st (1976)
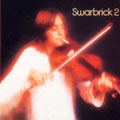
2nd (1977)
Swarbrick/Swarbrick, Dave
最盛期フェアポート・コンベンションのフィドル、マンドリン奏者であり、イングリッシュ・トラッドにおけるフィドルの第一人者、スウォーブリックの1stソロ、2ndソロのカップリングCD。フィドル(Fiddle)は元来、モンゴル帝国によるヨーロッパ占領の置き土産が民俗楽器として発展したもの。後に上流階級向けの音楽でも一般的に使用されるようになりバイオリンと総称されるようになる。フィドルを体制としての西洋(教会)音楽から離れて使用してきた音楽として著名なのは上記ロマとケルトなのだろうが、ヨーロッパ辺境の島国イングランドのトラッドでもそれなりに使用頻度は高いように思える。
演奏されるのは全曲インストで非電化、9割ほどがトラッド。独奏からフェアポートの古参、サイモン・ニコル(Simon Nicol)、デイブ・ペグ(Dave Pegg)あたりが全面的に関わっているアンサンブルまで。咥えタバコで、飄々と、あるいは情熱的に弾きまくるスタイルは上品とは云い難いが、元々はパーティの余興楽団で生計を立てていたらしく、悩ましくも悲哀を感じさせるソロから、ハチャメチャに陽気なフォークダンスものまで多芸多才にして多種多様なフィドルを堪能できます。