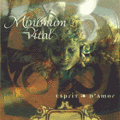
Musea
FGBG 4209.AR
Esprit d'amor/Minimum Vital
ミニモム・ヴィタルの五作目くらい。タイトルは『愛の才気』ないしは『愛の精霊』だろうが、“amor”はポルトガル語またはスペイン語の綴りなわけで、もしかしたらフランス南西部の方言なのだろうか。なにか捻った意味があるのだろうか。男女専任ボーカルが加わって全9曲、うち一曲だけインスト曲。
ソーニャ・ネドゥレ(Sonia Nedelec)なる(ポルトガル系?)中音域のゆったりした女性と、ジャン-バプティスト・フェラッシ(Jean-Baptiste Ferracci)というイタリア系みたいなこれまた中庸な男性が加わったかたち。メインは女性ボーカルで、歌詞はどうもフランス語とポルトガル語のちゃんぽんになっておるよん。曲中間部ラテン語挿入なども相変わらず。フランス語もボルドー方言なのか古語だろうか、標準語とはずいぶん違うものがある。というわけで、グローバルな洗練とは無縁な地方色全開。
元々、中世古楽とトラッドに対する造詣と、複雑なリズムと露骨でない変拍子、凝った展開が真髄であるが、敢えてダンサブルなまでのノリとラテン風味の導入でなんとも風変わりなポップが出来あがった。ミニモム・ヴィタルとしては大きな転進で賭けだっただろうが、とても良い意味で成功しているだろう。
8分越えの2曲を筆頭に、まったりと重厚で芳醇、それでいて切れるセンスと斬新な展開、フレーズが満載。やっぱり王道をいくフルボディのカベルネ・ソヴィニヨンか、ポルト酒の濃厚さか、風土を正確に捉えたゴージャスなまでの豊かさが感慨深い。
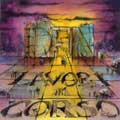
Mellow
MMP 392
Lavori in corso/D.F.A.
デウス・エクス・マキナ(Deus ex machina)と同じくヴェローナ出身ネオ・プログの1stアルバム。D.F.A.でDuty Free Areaなんだろうがそのセンスはわからん。マキナほど野蛮(というかあれは野獣)ではないが、馬鹿テク疾走は引けをとらない。一方で、緩急というか押しと引きが良い具合にバランスして抑揚のある滋味を引き出しているとも云える。静の部分の抒情味は、過去のイタリアーノ譲りであろう。とはいっても今のものだから、こてこてにはならず淡々とさり気ない。7、8分の曲を中心に16分越えの長曲と比較的展開の凝った技巧的な曲が中心で、歌詞はイタリア語。ブックレットには曲ごとに歌詞と綺麗なフルカラー・イラスト付。
『流れのなかでの労働(流れ仕事)』というタイトルは、インダストリーというか非人間的な意味での人智ならぬ機械智礼讃なのだろう。
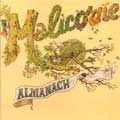
HEXAGONE
GRI191252
Almanach/Malicorne
ユーロ・ラディカル・トラッドの原点、マリコルヌ三作目。暗鬱な冷涼感が若干とれたものの、美しくも素朴な情感に溢れた哀感と、それを成す独特のコード進行と転調は虜になるものを持っている。中身は『アルマナ(暦)』と題された通り12ヶ月に渡る季節を歌ったもの。要するに種まきとか水やりとか嵐など季節の行事と注意を謳う農民歳時記である。
ガブリエル・ヤクー(Gabriel Yacoub)、マリー・ヤクー(Marie Yacoub)の男女ボーカルに加え、クラムホルン、ダルシマーなどの古楽器とフィドルやフルート、電気電子楽器のバランスも優れて新鮮だ。ブックレットにはなかなか意味深な各曲解説に歌詞、イラスト付。
ラスト一曲「ティンパニー奏者のフィアンセ(La fiancée du timbalier)」はビクトル・ユゴー(Victor Hugo;1802-1885)の『オード(抒情短詩)とバラード集(Odes et Ballades;1826)』のパスティーシュ(平たく言えば模倣)だそうだ。

Dare Dare
DDCD005
Troupeau bleu/Cortex
明るい透明感が気持ち良いコルテクスの1stアルバム。タイトルは『一群の青』。これを含めて三作出ているらしいが、再発CDを出していたレーベルは倒産したらしく既にwebがない。よくあるタイプのジャズ・ロック・フランセといちばん趣を異にするのは、やはりミレイユ・ダルブレイ(Mireille Dalbray)のスキャット入りシャンソンだろう。まぁ、フランス人がフランス語で歌えばこうなるというだけのこと。声量はないけれど上品で可愛らしい。
アラン・ミヨン(Alain Mion)なるエレピ主体のジャズ鍵盤奏者がコンポーザでかつ主要人物らしく、この人は今でも現役のようだ。メロトロンの音なども聞こえ、非常に上手いながらも、それなりにバリエイションに富んだ構成と柔らかな質感が清廉で女性的な華やかさを感じさせてくれる。
“Cortex”はラテン語で“外皮”とか“皮膜”という意味だが、今となっては真意はもう何もわからないだろう。環のなかにいる『一群の青』は動物のようだ。しかし、このごろラテン語が多くて困るな。
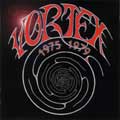
le Triton
TRI-03508
1975-1979/Vortex
コルテクスとくりゃヴォルテクスだ。26ドルもしたが2枚組だから許そう。75年の1st『渦』と79年の2nd『死神の季節(Les cycles de thanatos)』のカップリング2CD。よくあるマグマ風の地鳴りベースがぶいぶい唸る1stアルバムは、前衛劇『M'dame S91』のためのサウンドトラックで、75年の夏、アビニヨンの演劇祭で演奏されたテープから作られたとある。音の分解能が低いのはライブテープを使っているからかもしれない。
どちらが受けたのかはまったく知らないが、緊張感に溢れたジャズ・ロック基調の1stよりは2ndの方が圧倒的にオリジナリティが高く素晴らしい。ZAOの『Osiris』あたりの雰囲気を漂わせる1stに対して、かなり大所帯になった2ndは手数の多いドラムと、バイオリン、そして何よりも室内楽に近い静謐な余韻と研ぎ澄まされた構成・展開が見事だ。70年代末にはアール・ゾワやユニヴェール・ゼロ、ZAO後のヨシコ・セファー等とツアーを組んだこともあるらしい。豪華ブックレット付で野外ライブが多いなぁと思ったら、首領のヴィヴァント(Jean Pierre Vivante)はリヨンの出身らしく、ちょっとこってりした民族風味というか南仏色が感じられる。
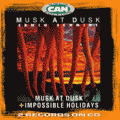
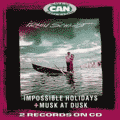
Mute/Spoon
9072-2
1991
Musk at dusk/Impossible holidays/Irmin Schmidt
カンの鍵盤奏者、イルミン・シュミットのソロ二作のカップリングCD。カンにおけるエスノ風味や飄々としたメロディ等、楽曲面では作曲家として予想以上に貢献しているのがよくわかる。その上、渋くてしょぼい、はずしまくった親父声でへろへろ歌う。この時点で既に50歳と、いやぁ、すんごい経歴のインテリ親父が開き直っちゃったというか、この歳だから出来る技とでも云うべきか。
「Le weekend(週末)」
人生はしんどいし
筋肉は痛いし
もうたくさん
休みが欲しい
一緒に来ないか
そして、みんなお出かけさ、ひひひ
愛はしんどいし
感情が疼くし
もうたくさん
休みが欲しい
遠くへ飛ぼう
そして、みんなお出かけさ、ややや
水平線が消えるような
ぼくらは透明な晴れ間にいる
きみの背中を引っ掻いてやろう
ここ、サワラクで
パンテレリア島
イズミール
雄大なサマルカンド
げげ、もう月曜かい?
享楽の日には
ワイキキでお茶でも
サワラクはボルネオ島西岸の州。マレーシア領の熱帯リゾート。
パンテレリア島はイタリア最西端、チュニジア、マルタに近い。文化的にはアラビア。
イズミールはトルコ西岸、エーゲ海に面した海浜リゾートにして宿敵ギリシャとの激戦地。
サマルカンドは中央アジア、ウズベキスタンの青の都。セルリアン・ブルー、ターコイズ・ブルー、コバルト・ブルーの饗宴。
ワイ・キ・キは旧ハワイ王国の海岸だったかな。
いいなぁ、みんな行ったことがあるのだろうか。
こんなどうでもいいようなふざけた歌詞に、仏英混合ちゃんぽんなタイトル、極めつけのヘロヘロ歌唱と言うことなし。
ジャケットは、どこかのリゾートの沖合いで沈みゆく船で抱き合っているのが『Impossible holiday(あり得ない休暇)』、ハイヒール履いた足がキリン柄なのが『Musk at dusk(黄昏の麝香)』。共に再発CD仕様。
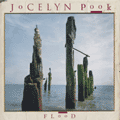
Virgin America
7 2438-48150-2 8
Flood/Jocelyn Pook
イギリスの現代音楽作曲家、ジョスリン・プックの近作。一部の曲がキューブリックの映画に使われた云々で、一瞬、脚光浴びたかもしれない。狙いはポスト-モダンあるいは現代の聖歌とはっきり述べているように、ヒンズー、キリスト、ユダヤ、イスラムを越えた宗教歌の創造にあるようだ。個人的には仏教も入れてよって思うのだが、いや、まぁ、凄いものです。こういう方面は情報が極度に限られているので、聴けたことに感謝。
ご当人は、ボーカル(メインは別だが)に加え、キーボード、バイオリン、ビオラを演奏する才女のよう。打ち込みまで含めて極めて高質な楽曲と素晴らしい音質(サイモン・ヘイワースだな)、美しいスリーブに脱帽した。内スリーブの美麗写真は上述のシュミット曰く「水平線が消える透明な晴れ間」というやつだろう。
竪樋の終端の水溜りに浸かるのは、サグラダ・ファミリアの尖塔とヒンズー寺院だろうか。『洪水』というタイトルそのものが、キリスト教的にはいわば“やり直し”の意味を込めているのだろう。オッペンハイマー(J.R Oppenheimer;1904-1967 マンハッタン計画を主導した理論物理学者。後に反逆で公職追放)の演説を含めて、まともなイギリス人らしい優れて良心的な見識は感じ取れる。
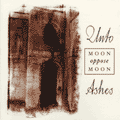
Projekt
106
Moon oppose moon/Unto ashes
出所不明なウント・アッシーズの1st。Projektというアメリカのレーベルのようで、主にダークアンビエント系の通販をやっているところのようです。セールの$6.98は魅力だが、欧米人以外はカードのハードコピーを送れとかって、ふざけているので使ったことはないですが。
デッド・カン・ダンスを継ぐものとしては最右翼だろう。中世の暗黒をこれでもかといわんばかりに体現する魔性。中世楽器の演奏力、打ち込みのセンスも初作とは思えない出来です。極めて暗く救いのない歌詞はすべてが英語というわけではなくドイツ語にラテン語(次作はすべてドイツ語とラテン語)、不詳言語が一曲、アレンジもこなれており何よりメロディがとても美しく可愛らしくそして悲しい。
形態はかなり不定なようですが、男女各二人から6、7人、といったところでしょうか。女性(Natalia Lincoln)はドイツ語とハンガリー語が母語だそうで、最新のマキシ・シングルにはMarikoという人も加わっているようです。公式サイトのビデオ(Palästinalied;パレスチナの歌)はなかなか。ラテン語かな? イデッシュ語かな? 中身はさっぱりわからんが、う~ん、このスタイル、キリスト教原理主義者かユダヤ教かいな?
“Unto Ashes”の由来は当然『ヨブ記』なのだろう。Webにもある"Your remembrances are like unto ashes, your bodies to bodies of clay." -- Job 13:12 というのは『ヨブ記 13章12節』の「あなたの記憶は灰と化し、あなたの身体は粘土と化す」であり、「あなたがたの格言は灰のことわざだ。あなたがたの盾は土の盾だ」という意味なのかな。すいません、興味がないもんで。
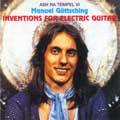
King Record
KICP 2855
Inventions for electric guitar/Ash ra tempel
『E2E4』と並び称されるアンビエント・テクノの古典的リファレンス。どうでも良さげな(というかあまり直視したくない)顔ジャケとは裏腹に、ここまで中身と外身の印象が食い違うスリーブ・デザインも珍しい。所有盤も珍しく民族系音盤会社の日本盤でカタカナ縦書きのタイトルがわかりやすくて良い。できれば『インヴェンションズ・フォー・エレクトリック・ギター』じゃなくて『電気洋琴のための発明』と漢字仮名混じり文にするのが美徳であろう。カタカナは単位字数あたりの情報量が少ないし、この後に及んで発音をなぞる意味はないだろう。
例えば床にCDが1mほどの高さに横積みにされて、そこからある特定のCDを探す場合、圧倒的に楽なのは背の部分に日本語表記のされている日本盤だったりするわけで、圧倒的に視認性が良くて少ない文字数で意味すらとれる仮名漢字こそは優れてありがたきものである。そこには私自身に、外国語は苦手で、辞書がないと意味がわからないし、発音も調べたり訊いたり、ちょっとした問い合わせだって日本語なら30秒の作文が10分もかかったりする始末であるという、能力資質の欠陥に起因する問題が厳然と存在したりするわけだから、なんとも仕方がない。暇をみて努力はしているのだがねぇ。
そして誰もいなくなった、というわけで仕方なく一人でこつこつループを重ね録りしていたら、ミニマルが出来ちゃいましたぁ、というわけかどうかは知らないが、ギター・オンリーで製作されたテンペル六作目。才気が音のつづら織りなって溢れ流れて官能に至ると、弱冠21歳の快挙。
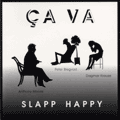
V2CI 0021
Ça va/Slapp happy
スラップ・ハピィ名義としては75年の『絶望一直線』以来23年ぶりの新作。90年代にTV用音源『Camera』で一同に会してはいるものの、これこそが『カサブランカ・ムーン』を継ぐもの。まぁ、スタジオ盤の新録はこれで最後になるのだろうなぁ。全曲新規で書き起こされる予定だったらしいが、結局、時間的な制約でムーアとブレグヴァドの持ち寄りになったらしい。それでも内容的に文句は何もない。ただ、聴ける幸せを甘受しよう。サ、ヴァ。
いきなり冒頭ブレグヴァドの曲ですが「Scarred for life(わたしに傷跡を残して)」の懐かしくも艶かしいクラウゼのアルトでノックアウト。どうとでも取れるが、ブレグヴァドの歌詞だから“わたし”は男だと思いたい。
「Scarred for life(わたしに傷跡を残して)」
君を思い出させる何かを残しておいてくれ
髪の一房とかじゃなくて
傷跡を残して欲しい
君が気に掛けていたことを示すためにも
君ならば思いやりをもってできるだろう
ナイフで身を切るよりも簡単に
僕の前から消えるだけで
一生消えない傷跡を残せるのだから
僕等はいかれてたけど、手に手を取って歩いてきた
ほんの僅かな微風にのせて
秘密の愛を囁いてきた
僕等は病んでいたのだろう
忘れ得ぬ何かを残して欲しい
単なる刻み目や引っ掻き傷ではなくて
僕等が出会ったことを思い起こさせるもの
こんなにも釣り合った君という人を
表面的なものではなくて
人に見せるつもりはない
僕の内側に隠しておける何か
君と僕だけにしかわからないもの
かつて僕は君に同じことをした
だから同じことをして欲しい
僕等が再び会うことが二度とないとしても
僕等が過ごしたすべての時間のために
僕の急所に残して欲しい
永遠の傷跡を

Hypnotic
CLP 9823-2
Other places/Cosmic Couriers 1
宇宙特使シリーズの第一巻。次が出たのかどうかは知らない。こんな養老会もやっているようです。クラスター(Kluster/Cluster)のメビウス(Dieter Möbius)、グルグルのノイマイヤー(Mani Neumeier)、ディー・クルップス(Die Krupps)のユルゲン・エンクラー(Jürgen Engler)の三人による人力テクノ・セッションみたいなもの。エンクラーだけノイエ・ドイッチェ・ヴェッレの世代でメタル・パンク出身。コニー・プランクがいれば、そのままかつての『Zeroset』ということなのだろうなぁ。古くは70年代伯林派のCosmic Joker(コズミック・ジョーカー)に範を見ることができるが、三人寄れば文殊の知恵なのか、ドイツのおじいさん達はこの手の仮説ユニットが好みのようです。すべて9トラックのデジタル・レコーディング一発録りでオーバーダブなしの即興。相変わらず尖っております。
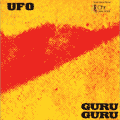
Ohr ZYX
CD 556005-2
UFO/Guru Guru
のたうつ音塊と野放図な重量感が暑苦しい教祖の1stアルバム。一般的に世間で評価されているほどのものとは思わないが、アシッド・スペース・サイケの元祖といわれればそうだろう。次作以降の下品なユーモア路線はまだ聞こえず、一応シリアスに迫ってきます。初期三作はノイマイヤーよりもベースのウリ・トゥレプテ(Uli Trepte)のセンスに依るところが大きかったといわれておりますが、さもありなん。時期によって表層的にはまったく異なった音楽性を惜しげもなく吐露するグルグルですが、その表出される音楽性がことごとく壊れているということが一種のアイデンティティになっているという、逆説的な存在感を誇り、主張し続けているようです。まぁ、年が経つにつれスマートになっていくという傾向は見られるものの、ここではその原初形、壊れて横滑りしていくような不安定で、胡散臭いハード・ロックを演じている。
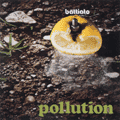
BMG RICORDI
74321585542
Pollution/Franco Battiato
電子音楽からカンタウトーレ、果てはエレクトロ・ポップにオペラまで、多芸多才なバッティアートの二作目。数えたことがないほどのアルバムがリリースされておりますが、おおむね80年代以降、最近の方が評価は高いらしい。当初は5人の楽団編成で、ドラム以外全員がVCS2ないしVCS3シンセを操るという、音響的でコラージュ、SEばりばりの先進性と、そこに重なるエレガントでクラシカル、イタリアの荘重かつ異端宗教的なメロディのつくる抑揚が暗く異質なけったいさが売りだった。
「中央世界磁気研究会」なる組織に献上されたタイトル『汚染』、レモンに打ち込まれたステンレス・ボルトと、なんだかよくわからないが、終末的であまり明るいイメージではない。北イタリア独特の創造性とそれに起因する排他主義的なまでの孤立感が見事に映える。

EMI
7243 8 32599 2 2
Pane e Rose/Angelo Branduardi
『パンと薔薇』なるタイトルも円熟と年季を感じさせる95年作。サンバ、ルンバ、タンゴ、地中海音楽、カンツォーネとありとあらゆる形式を越えて、アンビエントでリズミカルな打ち込みからアコギのカンタウトーレまで、持てる才は縦横無尽に駆け巡り、留まるところを知らない。そして、そういう何でもできてしまう環境にありながら、ほとんどア・カペラで歌われる「L'albero」で幕を開けるところ、その枯れた意気と変わらぬ真摯な姿勢を賞賛しよう。
「L'albero(木)」
わたしは一本の背の高い木に育つ……
太陽が輝き
夏の雨にからだを開く
そして、どの葉も歌いだす
熱く黒い大地を抱きしめる
すると、どの葉も歌いだす
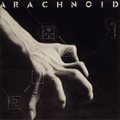
Musea
FGBG 4126.AR
Arachnoïd/Arachnoïd
「arachnéen+oïde」で“蜘蛛状のもの”という意なのだろう。トレマがとれてるから、アラクノワの唯一作。と思ったら、大文字だから省略されているだけのようです。最後の「e」は造語するときに意図的に落としたのだろう。ということで、アラクノイ(ド)と読むのが正しいようです。
蜘蛛のような手が示す通り、中身はシリアスで冷徹な歌入りジャズ・ロック。かなりダークな印象で、パトリック・ワンドリシュ(Patrick Woindrich)というかなりエキセントリックな風貌のギター奏者が親玉のようです。メロトロンを使ったシンフォ色、語り風のテアトラルと後発にありがちな欲張り過ぎの面と、変化があって目まぐるしくおもしろい二面性を持つ。不気味で暗鬱なメロディと非常に凝った転調、展開が堰の役割を果たして、こなれてはいないけれど、きっちりした厳格な楽曲を成している。Museaの復刻CDはボーナス4曲付。

Clearlight Music
C8M-102
Nocturnes Digitales/Cyrille Verdeaux
教祖ブルドー氏、自前のレーベルを立ち上げて好き勝手に気ままな音楽をリリースしておりますが、『ノクターン・ディジタル』ときたか。う~ん、所謂『量子化された夜想曲』でもよいが、フランス語の“Digital”には“指”とか“ジギタリス”という意味もあるわけで、『ジギタリスの夜想曲』というのもなんともえぐくて良いなぁ。盛夏の半陰陽に折り重なるように咲き乱れる淫蕩さには毒があると知りながらもつい惹かれてしまうものだ。タイトルからすると、すべてピアノ曲のつもりで買ったのだが、そういうわけではなくて、それなりにバリエイションに富んだ内容になっています。とらえどころのなさは相変わらずだが、熱帯の夕景を髣髴とさせる叙景的な印象は今の季節にぴったり。
ジャケ写真はもちろんクメールのアンコール・ワット夕景。