
KING RECORD
KICP 2735
Einsjäger & Siebenjäger/Popol Vuh
原画は不詳だが義経の屋島の合戦絵が曼荼羅模様に埋め込まれた、なんとも西洋的な東洋趣味、更に『Salmi di Re Salomone(ソロモン王の詩編)』から採られた歌詞等、要するに当時の“西欧でないもの”を無造作にまとめたエスニック趣味が苦笑を誘う五作目。路線的には『Hosiana Mantra』の発展型。フィッシェルシャー(Daniel Fichelscher)の存在感が大きいエスニックの入った耽美民族路線。リズム入りであるところから、そのなかでもコンパクトで聴き易いものだろう。音楽的には特にフィッシェルシャーの曲に顕著だが、ドラムとナチュラルなギター、美しくもシンプルなメロディはアモン・デュール2を髣髴とさせるものがある。おもしろいところでは、AD2のプロデューサだったキュプラー(Olaf Kübler)がフルートでクレジットされている。
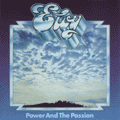
EMI Harvest
7243 5 22760 2 8
Power and the passion/Eloy
2004年の再発EU盤は廉価だがCCCDなので要注意。それ以前のものもリマスターなので、単にCCCDになっただけと思われる。あまりこてこてのクラウトではないエロイの四作目。歌詞はすべて英詩。これを境に以前(2nd、3rd)はオルガン・サイケ、以降はスペース・シンフォとメンバーを含めてかなり変わる。今作は1358年にタイムスリップした男をテーマにしたトータル・アルバムで、ラストの「ノートル・ダムの鐘」の99年のリミックス・ヴァージョンがボーナスとして追加になっている。前作に比べるとスリーブを含めてすっきりと洗練された内容で、オルガン中心だったキーボードに清涼感が感じられるなど巾が出てきた。その分、こてこてしたこねくり回した隠微な雰囲気が薄れてしまったか。重暗く流れるようなメロディが特徴で地味だけど良い味が出ています。
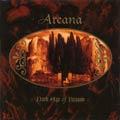
Cold Meat Industry
CMI.43
Dark age of reason/Arcana
アルノルト・ベックリン(Arnold Böcklin;1827-1901)の『死の島(Die Toteninsel)』をスリーブにしてしまうという、かなり安直な手法がなんともあっけんからんというか無頓着なスウェーデンのアルカナ、1stアルバム。『死の島』は(贋作じゃなくて)いろいろなヴァージョンがあって、これは1886年の最終ヴァージョンの(左右逆転してる)ようだ。モデルとなった島は実在でナポリ湾のイスニア島。墓地の島に棺桶を積んだ小船が到着したところを描いたもの。糸杉が死の象徴であることは既に自明だろう。
ペテルソン(Peter Pettersson)とベングツソン(Ida Bengtsson)という男女二人ユニットによる俗称ダーク・ゴシック。もっとも一般的に云われるほど暗くはなくて、中世宗教の耽美的側面と北欧神秘主義をエレクトロニクスというオブラートで半透明に包み上げた極上のアンビエントといったところでしょう。
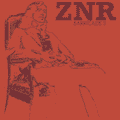
RéR
ZNR1
Barricade 3/ZNR
ZNRとしての初作はARP2600とピアノ、サックスの饗宴。もっとも音のエッセイのような作りで隙間だらけ。多くはリリカルな単音アンサンブルと、それをぶち壊すような相対する概念で成り立っている。それがサックスだったり、ボイスだったり、あるいは意識的にずらされた調子、はぐらかされた内容であったりする。孟郊(唐の詩人;751-814 50歳にして科挙“進士”に及第。)の詩をわざと数カ国語で歌ってみたりもその一環だろう。最長5:35、ほとんどは数十秒から3分ほどの全15曲。サティのエッセンスの引用とアンティークで減色されたハーフトーンを思わせる色彩感。自動書記か自動演奏ピアノ(現代の電子制御ではなくてピアノロールによる機械制御)のように部屋に入ると動き出すからくりのような仕掛、からくりの偽装。偽装と諧謔の虚構、ここに今、彼岸が構築された。
尚、この時点ではクラリネットのポルテラ(Patrick Portella)が正規メンバーとしてのクレジットになっており、トリオ編成です。
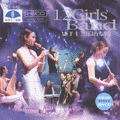
ISRC CN-A63
-02-349-00/A.J6
専輯/女子十二樂坊
中国盤の1stアルバム。専輯は(せんしゅう)でアルバムの意らしい。日本語垂れ流しメディアには接する機会も意志もないので、日本盤が出ているとはまったく知らなかった。アジアものでかねてから探しているものがいくつかあって、信用できそうな中華系サイトを探しているときに引っ掛かったもの。しかし、VCD付だのDVD付だの、本土盤だの台湾盤だの香港盤だのいろんなパッケージがあって、曲は重複してるし、おまけに東夷向けは独自仕様でアレンジまで違うとかで混乱の極みだ。
作曲、アレンジの梁劍鋒というおやじ(中スリーブに写真が出ている人かな)が12人の小姐の首領のようですが、昔よく場末の小屋で掛かっていた中国曲馬団の労使関係みたいで面白そうだ。内容はまだまだ発展途上で未消化な上、方向性が不分明。東夷のショウビジネスを範にする愚行は回避しているようだが、英米もののカバーは不要だ。せっかく古民族楽器を多用しているのだから中華風の伝統に則って、中華(チュンファン)を体現するような、しなやかな力強さを今以上に期待しておこう。
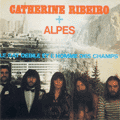
Mantra
642084
Le rat débile et l'homme des champs/Catherine Ribeiro+alpes
カトリーヌ・リベイロ+アルプの5作目と思われる『虚弱な鼠と野の人』。類推するに、都市と在野という意味なのだろう。リベイロ個人については不詳ですが、職業:詩人+歌手で、アルプは「アルプス一万尺」のアルプスで残りの三(四?)人のことを指しているようだ。パワフルで暗い情念を吐露するような、シャンソンとは180度向きが逆の詠唱に近い。内容的にはそうでもないがちょっと雰囲気がニコに似ているかもしれない。素朴だが野趣に富んだ、シンプルなメロディとシンプルなアレンジが暗鬱に幽玄にループする。ただし、完全な歌ものというわけでもなくて、サイケでムーディな長編組曲があったり、朗読があったりとかなり変化に富んだアンサンブルです。神経症的なシンセ? の音が悩ましい。
「石…、…わたしが作り上げた。斧で、包丁で、ナイフで。この愛の骨格を」
チリの詩人パブロ・ネルーダ(Pablo Neruda;1904-1973 コミュニスト、60年代国外追放、イタリアに亡命。アジェンデ政権成立で帰国。71年ノーベル文学賞。73年、快晴のサンチアゴに雨が降るなか死去)の一文。何を示すのだろう。

Garden of Delight
CD 079
Hijack/Amon Düül II
74年だから『Vive la trance』と『Made in Germany』の間だろうか。Brainからマイナー・レーベル(Lollipop)に移籍して音信途絶、当時は存在すら知らなかった七作目(かな?)。2003年にようやくCD化され再発されたもの。一般的には評価が落ち切った時期のようですが、当時はまったく情報がなかったのでいつ誰が言ったのか興味深い。その不評の原因はのたうつアングラ・サイケから、今作ではSFじみた冗長歌ものポップ、次作では似非ネオ・クラシックへの接近にあったのだろう。全9曲中8曲がボーカル・ナンバーというのもある意味凄い。本当にやることが極端なのだよねぇ。 それでも「You're not alone」や「Da Guadeloop」における偏執的で切ない空気感は、AD2たる所以というか、覆いきれない闇が垣間見えてしまう。
しかし、まぁ、レオポルトは明るいドイツ青年みたいだし、レナーテ嬢も健康的だね。ローター・マイトはスタイルまでいつも同じ。なんだか素朴でとても良い。

Random Records
398.6587.2
Radio/Michael Rother
「二人でやる“ぐるぐる攻撃”はぼくとペロリンちゃんのコンビが村ではいちばん上手です」といわれても何やらさっぱりだが、歌謡曲、民族音楽、賛美歌、コーラン、ドラマ、アニメ、ニュース…世界各地の短波放送を切り貼りした「Die ganze Welt(全世界)/World Mix」で始まる、シングル・コンピ全21曲。77年-93年の15曲に6曲の新ヴァージョンを加えてCD化されたようだ。元々、美しいメロディと蕩けるような楽曲だから、決してシングルとして不適切な内容ではないが、一体どういう人が買うのか? と考えるとそれはそれで極めて不思議に思う。媚やコマーシャルとは絶望的なまでに無縁な上に、ノイ!の片割れ、ディンガーのように自前ファミリィ化するわけでもなく、どこまでもひたすら孤独な人だ。
新作『Remember』はCCCDでがっくりだが、WEA系列のメジャーみたいだからそのうち非CCCDで英米盤が出るかもしれんね。気長に待とうか。厭な世の中になってきた。
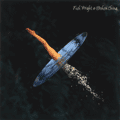
EMI
7243 8 53645 2 5
Broken china/Richard Wright
ライトの18年ぶりのソロ二作目。老いたな。名義はライトだが実質アントニィ・ムーア(Anthony Moore;現音作家、ex.Slapp Happy、Henry Cow)との共作だろう。これまでのライトやフロイドとは異なったアプローチ、アレンジ、明らかに向上した作曲技法と構成、クラシック、現代音楽の基礎的素養に裏打ちされた打ち込みプログラミング等はムーアなしでは得られない成果。おまけに作詞までしているようで、完全に食われてしまっている。
まぁ、食うに困る人じゃないから、いきおい丸まり過ぎた感性と抜けた叙情味がすべてだろうが、そのあたりもプロデューサ稼業にも円熟したムーアにアンビエント風味で気持ち良くすっきりとまとめられている。フロイド風の得意なコード進行や『WYWH』、『アニマルズ』あたりの焼き直しフレーズは頻繁に聞かれるものの、前作の鮮烈でヴィヴィッドなリリシズムを期待するのは酷というものか。ヒプノシス風のスリーブデザインも今更ぱっとしない。タイトルは「壊れた磁器」という意味だろうが「覆水盆に帰らず」と云いたいのなら、それはそうだろう。

NSD
6056
Garmarna/Garmarna
93年にスウェーデンでリリースされたデビューEPで、現在の再発CDは、それに加え6曲のボーナス・トラックで倍増されている。この時点では、ヘルデリン嬢はまだゲストで二曲で歌い祝詞を唱えるにとどまる。初期集ということでトラッド色が非常に強く、陰惨な歌詞に加え、古楽アコースティックの純粋さが潔くも美しい。
インタビューのWebページなどをみるとこれがまたなかなかおもしろい。どこまで真面目に答えているのかもわからないし、質問の下らなさも笑えるのだが、認識を新たにしてしまうところがあるなぁ。
例えば、宗教は? という問いに対し、“俺は仏教徒だ”と公言するものから、ヘルデリンちゃんに至っては「I have no belief in any god.」だそう。おいおい、大丈夫か?
その他、好きなスポーツは? “俺はスポーツを憎む”に始まって、左翼だとか社会主義者だとか無政府主義者だとか、もう言いたい放題で爆笑だな。よく仕事なくならないなぁ。
GarmarnaはGarmの複数形で、北欧神話でヘルガードを守る四つ目の巨大な犬らしい。死の大地のGnipaなる洞窟に棲み、赤いのは血で染まっているからだそうだ。
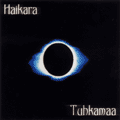
Mellow Records
MMP 414
Tuhkamaa/Haikara
70~80年代に三作、98年に復活四作目をリリースしているフィンランド(Suomi:スオミ)のハイカラ最新作。まぁ、ハイカラは“はいから”ではなくて“コウノトリ”という意味だそうですが、同じアジア系言語として困ってしまうくらい音感はとてもよく似ている。タイトルは『灰塵に帰した土地』らしいが辞書がないのでよくわからん。
ヴェザ・ラットゥネン(Vesa Lattunen)なる初老の首領と同齢に近いサックス奏者が以前と変わらず中心のようで、それに加え女性ボーカル他4名がコアのようです。サックスとチェロが主要なメロディをとって、ラットゥネンによる地味な地声の極めて抒情的で独特なボーカルがうろうろと漂うアンサンブルが特徴です。どちらかといえばオーソドックスでセンスが煌くわけではない、上手くもない、これといって刺激も奇態も演じないが、なんだろう、こののめるように惹かれる魅力は。なんともいえない寂寞と湿度、ゆったりとたゆとう温度が肌に馴染む。一応、トータル・アルバムですが、ラストの女性ボーカルの小曲なんか昔懐かしい唱歌みたいだ。生涯の終わり、走馬灯のように記憶が流れ出すときに聞こえてくるのだろうな。

Mellow Records
MMP 254
Finisterre/Finisterre
90年代ネオ・プログの中でもリリカルな透明感が真骨頂なフィニステッレの1stアルバム。ジェノヴァ風味の清々しさとおしゃれな雰囲気がとても現代的だ。モーツァルトやガーシュウィン等クラシカルな要素の取り入れ方も自然で嫌味がない。専任ボーカルはいないし半分以上はインスト曲ですが、それでいて盛り上がりのメランコリックなメロディはこれまたはっとする鮮烈さを感じさせてくれる。オペラ風のボーカルやアヴァン・ガルドな即興と絡むフルートも絶品です。要素は盛り込み過ぎでごった煮、不分明で不明解だが、曲もアレンジも丁寧で思い入れを込めて作られていると思う。
ギリシャ神話を意識した内容のようですが、前半で奏でられたワルツが後半にも登場したりするあたり、若いながらもかなり凝った作り。
「見渡す限りの荒地、空が大地に注ぎ込まれた」
イメージは空の青。
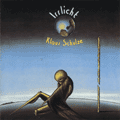
Brain
833 127-2
Irrlicht/Klaus Schulze
タンジェリン・ドリーム、アシュ・ラ・テンペルと渡り歩いたシュルツェの1stソロ・アルバム。タイトルは『鬼火』または『人を惑わせる光』。孤独な片足のサイボーグが固体の海に落した(比重が軽いから浮いていくのだが)水銀の涙。冷たい金属の海を泳いでいるような圧倒的な音圧のオルガン、次第にシーケンスされるようにループするリズム、強靭でフラットな安寧と酸に侵されていくような絶望がせめぎ合う。変調された生オーケストラは薄気味悪く遠くにたなびく。冷たく不透明な、重く粘性の高い流体に包み込まれるような、電子音楽黎明期の完成度の高い秀作。
「Satz Ebene(楽章;平野)」「Satz Gewitter(楽章;雷雨)」「Satz Exil Sils Maria(楽章;流刑地シルス-マリア)」の全三曲、計一時間。ちなみにシルス-マリアはイタリア国境に近いスイス東部の地名で、ニーチェが晩年、発狂する以前、夏に滞在して執筆していた避暑地の村として有名。

The Wild Places
RCD 1011
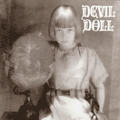 欧州仕様
欧州仕様The sacrilege of fatal arms/Devil doll
前作『Sacrilegium(神聖冒涜)』の進化ヴァージョンにして通算四作目。同タイトルの映画のサントラとして書き直されたものらしい。首領のMr.Doctorはもう音楽はやめて映画に転進しているそうだが、この映画は公開されたのだろうか? 天使、悪魔、子供、狂人の声音を使い分けた一人四役変態ボイスは健在(公称では1000の声を持つ男)で、アレンジ、アンサンブルも派手に荘重に練り上げられた。パイプオルガン入り。棺桶に横たわり人生を振り返る男の物語らしいが、教皇の宗教演説?、ゲッベルス(Joseph Paul Göbbels;1897-1945)やレーニン(Ленин(本名 ウラジミール・イリイチ・ウリャーノフ Владимир Ильич Ульянов);1870-1924)と思われる演説が巧みに挿入されて、大衆の操作と圧迫という最終兵器をもって行われた冒涜の過程が描かれているということなのだろうか。ラストは教会の鐘が響き、烏が鳴くなか、神父が弔辞を読み、棺桶が穴に下ろされて上から土が掛けられる“葬式”を棺桶の中から実況しております。最後は心臓の動悸だけになったりして生きながらの埋葬ということらしい。
限定版から一般売りのCDまで、いろいろな版があるようでジャケットはかなり違うようです。
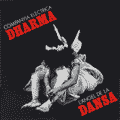
PDI
80.1248
L'angel de la dansa/Companyia Elèctrica Dharma
最初から最後まで、間もへったくれもなく常に叩き続けるドラムとチャルメラみたいな音色のソプラノ・サックス、可愛いというか童謡みたいな民謡みたいなメロディ(カタルーニャの舞曲かな)が極めて爽快だ。スペイン北東部カタルーニャ地方のコンパーニャ・エレクトリーカ・ダールマ、直訳すれば「戒律電気団」あるいは「仁徳電化衆」とでもいうのか。表記はすべてカタルーニャ語(というのはスペイン語表記であって彼等は頑なにカタラン語といい、スペイン統治を拒否しつづける)。タイトルは『踊りの天使』の意だろう。中期四作目(現役だけど)で、チャルメラ民俗音頭としてはこのあたりが最高峰かもしれない。実際、LPの両面ラストの小曲は共に現地民謡。ボーカル入りは2曲ほど、大半がインスト曲ですが楽しいメロディの波状攻撃に息つく間もない。
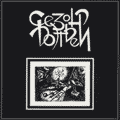
Boheme
CDBMR 010179
Возвращение/СЕЗОН ДОЖДЕЙ(Return/Rainy season)
サンクト・ペテルブルグ(旧レニングラード)で80年代CCCP時代にスタートしたらしい。Maxim Pshenichnyなるマルチ奏者兼コンポーザにパーカッションが加わった二人ユニット。ゲストでフルート、ギター、コーラルボイスが入っているようですが、お決まりのように極めてプロフェッショナルで上手い。リズムセクションも派手過ぎず地味過ぎず。もちろん、ポピュラーというよりは現代音楽+チェンバーといった趣で全曲インスト。
森閑としたタイガの森に分け入って、夏だというのに凍り付きそうになる冷気を浴びて、木芽の芳香と落ち葉の腐臭に囚われるという、鮮烈な森林浴体験アンビエント。森に抱かれ森に同化し森に朽ちて土に帰る。菌、カビ、キノコ。腐敗、分解、有機から無機へ。
「森の香り;7:00」「澄んだ水に向かって;14:19」「赤い夜;20:00」の全3曲、全編にわたって微かに鳴り続けるトライアングルの音が沈痛でありながらもすこぶる狂的だ。