
Cuneiform Records
rune 165
Rhythmix/Univers Zéro
新作『Implosion』の出来もさることながら、復活宇宙零の過去を越えた内容と、高みに昇りつめようとする意志には毎度感服せざるを得ない。ドゥニとベルクモンが中心的な存在とはいえ、既にパーマネントな形態は敢えてとらずに、二年おきぐらいに新作をリリースするかたちが定着しているようです。
タイトル通り非常に複雑なリズムを徹底して追及した楽曲で構成された緻密な迷宮あるいは繰り返される夢。毎晩いつも同じ夢をみたら人は正気を保てないと思うが、回転する物体と同じ速度で回転すれば見かけ上は静止しているように、常に同じ夢を恒常的に見続けることはできるかもしれない。変拍子とポリリズムの饗宴。リズムの崩し方はもはや芸術の域に達している。ただし、徹底的に排されたビート感の向こうにうねり低く静かに浸透する呪術と、あくまで高雅に繊細に奏でる管楽器のアンサンブルによる“何でもない美”が屹立している。その回りをうろうろと漂うものは、電動機の回転子が見る夢であり、磁界と電界に翻弄される双極子モーメントのゆらぎなのだろう。
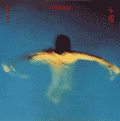
Polydor
813 653-2
China/Vangelis
中期の終りぐらいか。この後は売れて映画音楽作曲家になってしまうのだな。ソロアルバムとしては75年の『Heaven and hell』路線の終端。テーマとして特異な部分はあるものの、楽器の音色や全体の構成は驚くほどその個性に忠実だ。79年というのは所謂西側主要国と中国の国交が回復して中国が国際社会の表舞台に再登場した年だが、テーマの選択としてはなかなかエポック・メイキングだ(った)ね。前半はバラエティに富んだ曲調の短曲中心。ゲストのミシェル・リポッシュ(Michel Ripoche)がバイオリン・ソロを入れて、カンフー・マンに依る李白の詩の朗読、クーパー(J.C.Cooper;作家らしいが不詳)の「Taoism(道教)」からの翻訳以外はすべてバンゲリスに依るもの。でも曲名が「The Tao of love」ってのはまずくないか? 中華風のメロディは可愛らしいが、“道”の概念というか“非概念”は西洋人の認識外だろう。
後半は支那というよりはチベット。まぁ、西洋人には区別がつかんのだろうな。
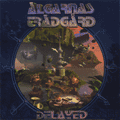
Silence
SRSCD 3626
Delayed/Älgarnas Trädgård
73年から74年にかけて録音された二作目として作られながら日の目を見なかった発掘音源。タイトルは27年遅れたという意味なのだろう。1stに比べリズム・セクションが大きくロック寄りに舵を切って電化され、結果的にはミックスも含めてかなり聴き易いかもしれない。ホルストの『惑星』(火星ですかな)の一部、サード・イアー・バンド(Third Ear Band)の「Water」の一部を一部の曲で抜粋しているとありますが、グルーブ感を感じさせるものから、シタールや笛、タブラの生きたアンビエントな東洋趣味まで結構幅広い。
よくある3Dゲームの世界のようなスリーブは27年前の前作のスリーブのボッシュへのオマージュだろうか。ちなみにエルヤルナス・トレッドゴァールトと呼んで“ヘラジカの庭”という意味だそうだ。
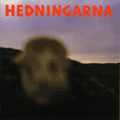
Silence
SRSCD 4717
Kaksi!/Hedningarna
ガルマルナを静(でもないけど)とするならばこちらは動か、エネルギッシュで強烈な躍動感に溢れた北欧急進派民謡の雄、評価を決定的なものにしたヘドニンガルナの2ndアルバム。元々スウェーデン人の歌なしトリオだったようですが、このアルバムからフィン人女性が二人加わって五人組。ボーカルはアジア風の音感が郷愁をかきたてるフィン語。全英訳付。全13曲中12曲がトラッドのリアレンジ。あらゆる北欧古楽器の驚異的なまでの演奏力に加え、打ち込みプログラミング、電気楽器まで文句のつけようのない技能はまさに驚嘆に値する。おばちゃん二人の野太く、自信に満ち溢れた歌謡もどっしりと地面に深く根を下ろし、その土着と安定、頑固と因習が生半可な洗練などまったく寄せ付けない。強靭でしなやかな、あくまで自然な民俗性の発露は感嘆に値する。
“Hedningarna”は“Hedninga”の複数形で“heathens(野蛮人、異教徒)”の意、“Kaksi”は「"Kaksi!" is Finnish for "Two!"」ね。
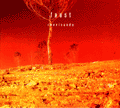
Klangbad
frav 1999
Ravvivando/Faust
ペロン、リタイアにより黄昏が若干冷徹なノイズに置き換わってしまった近作。へろへろな薄っぺらさが意外に重厚で切ない審美と、打ち込みによるアンビエントなビート感に遷移した。
Stille
der Zikadenlärm
dringt ein in die Felsen
An einem Abend im Herbst
ist es nicht leicht,
Mensch zu sein
Mond und Blumen
ach, neunundvierzig jahre umhergegangen
und die Zeit vertan
歌のようなものがあって歌詞があります。女声のドイツ語、ほとんど詠唱。空間に低く木霊するような寂寞とした音響を背景にした詩吟。
インナーにも記載されているこれらの歌詞はそのまま
閑さや岩にしみいる蝉の声 (芭蕉)
なか ~ に人と生れて秋の暮 (一茶)
月花や四十九年のむだ歩き (一茶)
だったりするわけだ。二句目は取り違えているかもしれません。だって日本語なのに意味がよくわからんのだもの。でも、読むのではなくて詠まなくてはいけないよなぁ。なんとなくあちこちを検索していたらこんなWebがありました。“瞬間-撮影”というのだろうか。一茶の同じ句が書かれていますが、うむむ。先回の『You know faust』における「なんで芭蕉なのよ?」という疑問はここに帰着する(ま、勝手な思い入れなんだけど)のであった。美しい写真スリーブ(加工しているけど)は、どこかの産廃処理場の光景のようだ。
俳句なんてもしかしたら日本人が前(前々かぁ)世紀の遺物として既に葬り去ったものなわけで、それをこんなかたちで目の当たりにしてみると、すこぶる居心地が悪いというか、結局明治以降の薩長田舎コンプレックス政治の末路ということか。いつまで続くやら。永遠? 合掌。
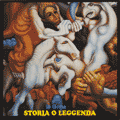
Philips
842 510-2
Storia o leggenda/Le Orme
『Verità nascoste』と『Florian』にはさまれた77年作。傾向的にもほぼ両者の中間をイメージさせるものと、それ以前の揺り戻し風インスト曲があったりしてわかりやすいのかわかりにくいのか。前作の明るめの典雅に比べれば、ジャケ絵から連想される通り少し暗めの味付け。どちらにしても安定した円熟味は文句のつけ所がないだろう。いつものトリオ+セラフィン(G.Serafin)のギターといった構成ですが、セラフィンのアコギがけっこう効いていて、素朴な暖かさがゆったりとしたミディアムテンポの曲と相まって上品な奥行きを作り上げている。歌ものオルメ、中期の頂点といったところかな。
初期の『Uomo di pezza』と同傾向のよく見ると気持ち悪いジャケ絵は現代画家マッツィエリ(Walter Mac Mazzieri;1947-1998)によるもの。

Numero uno
ND 74430
Sognando e risognando/Formula 3
大化けしたというか、これだけ異質な三作目。モゴール+バッティスティ(Mogol+ Battisti)の曲は半分ほどになって、自立へ向けて歩み始めたというところか。長めの組曲が増えましたが、感じる音感は驚くほど地味で、精緻に練り上げられたアレンジを的確なテクニックで演じているところが気持ち良い。元々、歌ものグループなだけにときおり挟まるボーカルパートの表現力には目を見張るものがあるが、インスト部分は少し気負い過ぎか。ただ抑揚のある抽象的な演出力みたいなものは極めて秀逸で、感覚的な天才肌のセンスのぶつかり合いと緊張感は数あるイタリアものの中でも特異な位置を占めている。この時代にイタリアでここまでできたセンスも特筆すべきだろう。ただ、やっぱり次作の歌ものの威力を聴いてしまうと彼等の本質はカンタウトーレなのだと改めて思う。
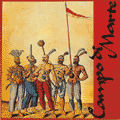
Mellow
MMP 181
Campo di marte/Campo di marte
“練兵場”唯一のスタジオ・アルバム。意味は“戦場”とした方が良いのかな。名前の由来は出身地でもあるフィレンツェの地区名から取られたらしい。メロトロン+ギターのエンリコ・ローザ(Enrico Rosa)のワンマンのようですが、五人なのだがツイン・ドラム(一人は兼フルート)のリズム隊の非常にねちっこい手数の多さとへんてこりんな録音もおもしろい。「Primo tempo(第一幕)」から「Settimo tempo(第七幕)」に至るトータル・アルバムで、構成や展開は一流処と比べても引けをとらないでしょう。ずるずるしがちなイタリアものにしては間の取り方が非常にタイトで乾いているし、静と動の抑揚の妙、イコライザのかかりまくったボーカルもドライな叙情を上手く表現している。
ジャケ絵は自らの強さと勇気を誇示する中世トルコ人傭兵。木靴がいいなぁ。自分の身体に矢とか剣を直接装備している気色の悪さ、愚かさをを、スリーブ裏の反戦詩などを見る限りは愚弄しているのだろう。2003年に復活ライブがあったそうで、72年と2003年のライブを収めた2CDがリリースされております。
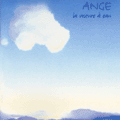
M10
130102
La voiture à eau/Ange
デカン老(Christian Décamps)+四小姓(一人は息子か)によるどっこい生きてるアンジュ、というか新生アンジュ、90年代のラスト。他の同類項に比べればハード・プログに染まらないのは過去の遺産なのだろうな。水力自動車をテーマにした一応トータルな作りのアルバム。新生アンジュはそれなりにコンスタントに、既にけっこうな枚数のアルバムが出ていますが、演歌のどさ回り歌手のようになってきた感があるな。個人的には落ちぶれていく悲哀と老獪な味、それでいて若さに対する憧れと喪ったものへのあがきがそこはかとなく醸し出されて、人の行く末を見るようで興味深い。
「進歩、それは発明の死骸」 Décamps
「われわれの肉体は空の上にあり、その空はわれわれの精神の上にある」 Leonardo da Vinci
「Eurêka(ユーレカ)」 (アルキメデスが王冠の金の純度を測る方法を発見したときに叫んだ言葉)とか故事の造詣に突っ込むのもおもしろいのだが、水蒸気を表していると思われる茫漠とした美しい水色が目にしみる。

Musea
FGBG 4014
Sarabandes/Minimum Vital
フランスものだし歌詞もフランス語なミニモム・ヴィタル90年代最初の三作目。次作を境に以前がインスト系ジャズ・ロック・フランセで以後が男女専任ボーカル入りの変態ポップ・フランセ。どちらも非常に味わい深い、派手ではないが華麗なボルドー出身のユニット。同郷のXII Alfonso(ドゥーズ アルフォンソ)とも人脈的な関係があるようですが、ティエリ(Thierry Payssan)とジャン・ルック(Jean-Luc Payssan)のペイッサン兄弟を中心にした現在進行形です。
タイトル『サラバンド』は三拍子の古舞曲のこと。全部が三拍子というわけではないが、テクニカルで複雑な変拍子とノスタルジックな舞曲が絡み合い、アコーディオンと中世楽曲が咽び泣くコンテンポラリな流麗さが特徴か。非常に上手い上に奇を衒うことは何もしていない音感が実に独特で素晴らしい。この滲み出てくる味はなんだろう。
中間部の「Cantiga de Santa Maria(聖マリアの賛歌)」はカスティーリャの賢王にして吟遊詩人、アルフォンソ・エル・サビオ(Alfonso el Sabio;アルフォンソ十世 在位:1252-1284)への献歌。この王による古楽同名曲は歴史的に見ても極めて著名。珍しく歌入り。「Hymne et danse」はラテン語で歌っておるな。
ジャケ絵は所謂京劇だなぁ。駱駝みたいな龍と鶴の楽器を抱えて向かい合っているのだが、昔のライブでは鼻に角くっつけていたからその辺の名残?
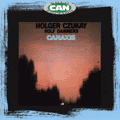
Spoon
CD15
Canaxis/Holger Czukay, Rolf Dammers
1968年録音、CANが始動した直後にリリースされたチュカイのソロアルバム。サンプリングされたアナログ音源をテープの切り貼りという手法によって再構成した最初のアンビエント・ミュージック。「Boat-woman-song(舟歌)」は二人の無名ベトナム人女性の伝統歌謡をサンプリングしたもの。ベトナム戦争最盛期ということもあってそれなりにクローズアップされていたのだろうか。「Canaxis」では経とか祝詞とか琴のサンプリングが使われているあたり、後を髣髴とさせるアイディアはこの時点で既に取り入れられているようだ。どちらかといえば冷たく湿った感触でアンビエント。後のファンキィな諧謔趣味は聞こえません。
ラスト一曲「Mellow out」はCD化に際しての追加音源。なんと1960年にチュカイが初めてプロとして演奏したラジオ音源だそう。ダメルズ(Rolf Dammers)という人物は不詳ですが、共同プロデュース、マネジメントとしてクレジットされております。
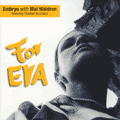
disconforme sl
DISC 1939 CD
For Eva/Embryo with Mal Waldron
一応、エンブリョの1stアルバムと云われているもの。けっこう、昔からやっておるのだねぇ。ほぼすべてミュンヘンでのライブ音源で、エンブリョの原型にマル・ヲルドロンという黒人ジャズピアニストが加わった即興ジャズ。ベース(コントラバスだけど)にローター・マイト(Lothar Meid)の名前が見える。クリスティアン・ブルカルト(Christian Burchard)なる鉄琴奏者が親玉なのですが、息長く現在もけっこうコンスタントに新作が出ております。途中、エスニック重量サイケ路線にぶれたりはあったものの基本はジャズ+中近東アジア民族音楽で最近のものほどワールド色が強まる。
ちなみにこの disconforme sl というレーベル、ピレネー山中の極小国アンドラ(Andorra)公国にあるようで廉い(いや、まぁバスクも廉いよねぇ)。同じユーロ圏でもピレネーを境にずいぶん違う。イギリス人が週末になるとトンネルくぐってフランスのど田舎で食料品を買い漁ったり、ドイツ人がスペインまでBMW買いに行って転がして帰ってくるように、早く朝鮮半島やら樺太経由ロシアやらに手ぶらで買出しに行けるようにならないものかねぇ。

WNMMS 045
Rare birds/Hoelderlin
四作目。この後ライブが一枚出て、80年代はヘビメタか何かに転進するはず。もったいない。といいつつもそれが世の現実なのだね。初期四作の中では内容的に最高作でしょう。こなれて無理と無駄のない楽曲に加え、歌ものの部分とインスト部分のバランスも良く、ふわっと浮遊して拡散していく気持ち良さと美しさがない交ぜになったような刹那感が素晴らしい。整形な庭園と樹木線で区切られた整形な空、花崗岩の幾何学的な石組に湛えられた水、白昼の光と眩惑を象徴する端正で淡白なアンサンブルと、連綿と流れる彩り豊かな情感が見事です。キーボードの作る優しい背景と淡いけれど意外に現代的なリズムもさることながら、やっぱり最大の特徴はノッペナイ(Christoph Noppeney)のロマンティックな電気ビオラにあるか。下手糞な英語ボーカルはご愛嬌だが、ドイツロマン主義の正統な嫡子である。
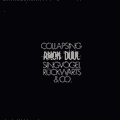
Spalax
14949
Collapsing- Singvögel Rückwärts & Co./Amon Düül
ツヴァイトでない方の二作目。一般的には1stの評価が著しく高いようだが、正規三枚はどれも良いです。『崩壊;背後で(退化していく)鳴く鳥と共同被告』というタイトル通り、鳥の鳴き声が意味不明だが何らかのテーマになっているようだ。前作に比べ、短曲が増えて音像は若干明確になったがポテンシャルは下がり気味。1stと同じく『Disaster』の音源を加工したものですが、コラージュや展開、SEの入れ方等はかなり進歩しているように思う。モワレのようなぐずぐず感と後ろ髪を引かれるような焦燥感に加え、IIででてくるようなフレーズもあって妙に惹かれる妖しさがおもしろい。内スリーブの原色絵は1stの『Psychedelic underground』と同一人物でヨガの行者 J.H.Loffler によるもの。けっこう好きなの。
本家のWebにあったのだけど、Amonはやっぱり古代エジプトのアモン神、Düülはトルコ語で「月」の意だそうだ。
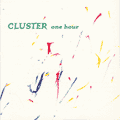
Gyroscope
GYR 6610-2
One hour/Cluster
90年代に入って突如デュオで復活したクラスターのウィーンでのライブ。ソロは別にしても、復活後のクラスター名義は何故かすべてライブ音源のようだ。タイトル通り一時間に渡って全一曲、曲名は「一時間」。う~ん、何も言うことないですな。わざわざ、スリーブには、“一つの連続した曲であって、インデックスはプログラミングのために入っているだけ”と記載されております。
美しいメロディを弾く気持ちの良いシンセ音にリズムがかぶさり何やら室内楽風ですらあるところが(以前を考えると)驚愕です。でもローデリウスのリリカルなピアノソロが終われば、ホニョプヨなかつての世界が甦ります。民族楽器調の音や暗鬱なメロディがアンビエントに、かつクールに絡み合っておりますが音感的にはずいぶんバリエーションが増えたかもしれない。
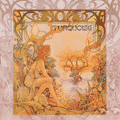
Ars Mundi
AMS027R
Turquoise/Turquoise
キダム(Quidam)かコラージュ(Collage)あたりからというのが定番だろうが、そこはそれ、ターコイズの1st。見映えは可愛い女の子+サル四匹といった按配で笑ってしまう(加工済)のだが、中身は意外や意外、可憐でメロディアスなポーランド歌謡。リズムキープが今一というか決して上手くはないがツボを突かれた。カタルズャーナ・ヤイコ(Katarzyna Jajko)嬢の素人臭いけど蕩けそうなアルトと、微妙に民族調の曲調、東欧風のメランコリックな転調が優雅にかつ涼しげに響きます。使っている楽器は今風だけれど昔の童謡のようなやさしい響きがしっとりと迫り来る。全曲ポーランド語のボーカルも何とも異国情緒たっぷりで新鮮だ。
ポーランド盤だから当然だろうが記載されている文字はすべてポーランド語。Webにゃポーランド語Epwing辞書もあるし、文法講座もあるがこりゃきっついわ。ずいぶん難しいのね。ま、日本語ほどではないが。そのうち曲名ぐらいは調べてみよう。