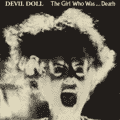
The Wild Place
RCD 1008
The girl who was... death/Devil doll
スロベニアのデビル・ドール、自主製作の1stアルバム。偉大なる男パトリック・マッグーハン(Patrick McGoohan)主演監督の『The Prisoner(邦題;プリズナー No.6)』の製作20周年祝賀にあたり製作されたようです。内スリーブにそのシュールな一場面が載っておりますが、本編トータル65分の35分過ぎから延々と続く無音に呆れ果てていると最後2分程であの有名な台詞が登場します。
「なにが欲しいんだ」
「情報だ」
………
「おまえは誰だ」
「新しいNo.2だ」
「No.1は誰だ」
「おまえの名前はNo.6だ」
そして、あのオレンジ警報の風船ローバーが登場するゴボゴボ音ですね。突如メタルなロックが鳴り響いて終わるのですが、プリズナーと同じくわけわからん。
本国ですらあまりの不可解さに半年で放映を打ち切られたTVシリーズですが、シュールであると同時に、現実と虚構がするりと入れ替わり、入れ子になったり、徹底した欺瞞と化かし合いが錯綜して、人間の認識の本質を揺さぶるような切込みが素晴らしい作品でした。
さて、デビル・ドール主宰は Mr.Doctor なる男のようですが所謂覆面楽士というやつで、そのすべてが不詳です。博士は気持ち悪いボーカル、語り、鍵盤等を担当されているようですが、他には洋琴、グランドピアノ、第一バイオリン、第二バイオリン、チューバ、打楽器、鍵盤、ハープ、ベース等の担当がおるようです。さらにデビル合唱団も加わってなかなかの大所帯のようです。
霧の奥底からハープの音が漂いはじめ、荘重な混声合唱がたなびくイントロ、テーマが繰り返されると、グランドピアノをバックに
「彼を信じてはいけない…たとえ彼が背を向けていようと…」
「彼を信じてはいけない…たとえその目が閉じていても、奴はおまえを見ているのだ…」
などと演技過剰で変調されたような語り風の台詞が入るのね。
突如挿入される妙にリリカルなハードメタルと壮巌なオーケストレイション、合唱団のクワイア、変態語り、バイオリンソロが節操もなく展開されて、渾然一体となって玉砕する変調一大絵巻には唖然とする他ないな。この過剰な劇場趣味は同郷のライバッハにも通づるものがありますが、こちらはワルツから物語まで耽美的ですらあるバロック趣味で固めております。
タイトル『死んだ女の子』は、そのまま『The Prisoner』の一巻でもあるのだが、わけのわからん滑稽さには通づるものがありそうだ。裏スリーブはおそらく映画のスチール写真だろうが美女死体集と、なかなかレトロなつぼを突いた趣味が素晴らしい。以後、似たような路線で数作出ておりますが、どれもなかなかの出来映えで楽しいです。
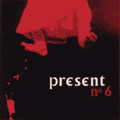
Carbon 7
C7-043
N°6/Présent
ぶら下がり、体液が滴る足元に一言。
「どうしてママの言うことを聞かなかったんだい」
で、図らずもこちらもニュメロシス。おまけにネタまで似通っている。「ぐったりとした幼女」だものね。99年の6作目。ロジェ・トリゴーが作曲・アレンジに専念したせいかどうかは知らないが、恐ろしいほどの密度と緊張感に溢れた、溶鉱炉の銑鉄をぶちまけたような熱く滾る壮絶なアルバムになりました。
「Le cauchemar yo(ウホッ、悪夢)」
望むものすべてをくれてやれ
彼等が望むすべてをくれてやれ
くそ! ちくしょう! 駄目だ!
望むものすべてをくれてやれ
破滅をおまえたちすべてに!
望みをかなえてやれ
食いものにゲームだ、セックスはもうよい
望むすべてをくれてやれ
物語、英雄、TVセット
彼等の望みをかなえてやれ
望むものすべてをくれてやれ
そういや、おまえらの革命の理念はどこだ?
そんなもの、とうの昔にない!
闘う理由はどうした?
それこそお笑いだ! そんなものなどない! ない! ない!
この社会は死ぬ、そう運命づけられた
なにも心配することはない
支配者の夢が悪夢になっただけのことだ
なにも心配することはない
今更焦ったところで変えようはない
なにも慌てふためくことはない
何をするにももう遅過ぎる
なにも心配することはない
今更
目くるめく怒涛のダーク・チェンバーの快感。

Island
IMCD 61
Unhalfbricking/Fairport convention
濃いものが続いたので心機一転、フェアポートの3rd。なんとも上品な老夫婦と教会を望む高級住宅街、これまた管理の行き届いた美しい公園(個人の庭かな? にしては凝り具合が足りない)と中産階級的な日常を余すところなく描写する美しい写真に負けず劣らず中身もノーブルな気品と繊細な感覚に溢れた秀作です。格子の向こうにはフェアポートの面々が見えますが、早春といった感じで少し寒そうだが気持ち良さそうですね。ボブ・ディランのカバーが三曲にトラッドが一曲、あとはオリジナルといった構成ですが、力が入っていながらも決して汗臭くならないというラインは見事にキープされているでしょう。内容的には過渡期ですが、サンディ・デニィの凛と突きぬけたボーカルも曲も益々冴え渡って、イングランドという土壌から確実に新しい芽が開いたことを実感させてくれるようです。
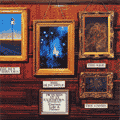
Cotillion
20P2-2049
Pictures at an exhibition/Emerson, Lake & Palmer
ムソルグスキーのピアノ曲をラベルがオーケストレイションした「展覧会の絵」を下敷きにアレンジしたライブアルバム。最初に聞いたELPだったかもしれない。もっともTVで見たそのライブはELPに対する認識を180度転換させるものであったことは間違いない。当時購入したLPが行方不明で、中古CDの安物があったので二十数年ぶりに聴き返してみたのだが、サーカスの猛獣が暴れているような滑稽さが頭に浮かんでしまう。その後の顛末を考慮に入れなければ、この時期のELPはいろいろな要素のごった煮ながらもアレンジメントの斬新性という意味では優れて規範的ですらある。こけおどし的なキーボードやセンチメンタルな弾き語りも猛獣ショウのアトラクションの一種だと考えれば良いのだろう。
それでも「キエフの大門」かな、「They were ~」のくだりはある種の高揚感をもたらしてくれる例だった、かな。

Catsle
CMDDD132
Sweet child/Pentangle
急進ハイブリッド非電化民謡、ペンタングルの2ndアルバムは元々2LPで今は2CD、前半がライブで後半がスタジオ録音。それに加え2001年の再発CDには大量のボーナス入り。元の録音が良かったのだろうが、非常に優れたリマスターで、再生装置を選ぶ一音一音に触感に触れるような繊細な生々しさが感じられる。特筆すべきは以前にも増して切れ味の良いマクシーのボーカル。ほんのワンコーラスのトラッドをア・カペラで歌う(“歌い上げる”ではなくて、この人はあくまで“歌う”)マクシーの声は手が切れそうな透明で張り詰めた無常感をもって迫ってくる。バート・ヤンシュ(Bert Jansch)とジョン・レンボーン(John Renbourn)のボーカル曲ないしはパートの方が暖かみを感じるところが面白い。目立たないけれどダブルベースとドラムのリズム隊も極めて秀逸で、アンサンブルとしても表現力豊かな質感が素晴らしい。
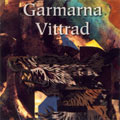
Omnium
OMM 2008D
Vittrad/Garmarna
エンマ・ヘルデリン(Emma Härdelin)嬢の巻き舌ボーカルが冴えるガルマルナの1stフル・アルバム。同郷のヘドニンガルナと共に、所謂90年代北欧急進派民謡の双璧を成す。正直言って北欧ものは言語がまったくお手上げで腰が引けてしまうのだが、マイナーであることは自覚してくれていて、歌詞はスウェーデン語だがどのアルバムも英訳付で親切(というかESD/NorthSide/Omniumは同じ会社なのか)。まぁ、急進派民謡自体は70年代にマリコルヌ(Malicorne;フランス)やコリンダ(Kolinda;ハンガリー)あたりが先鞭をつけているので、何を今更感が拭えないのも事実だが、古典楽器からエレクトロニクスまで何でも有りの奔放さと、北欧ゲルマンの素朴な重厚さというか重暗さ、そしてもちろん直立不動、ないしは着席背筋真っ直ぐ両手は膝に頭を微動だにしないで歌うエンマ嬢の媚のない清楚な透明感が心を打つのでした。ここまで格好良いのは久々だな。フィドルの扱いを含めてアンサンブルもさり気ないけれど的確で斬新、かつ巧い。地道に成果を重ねていけるみたいな環境にも恵まれているのだろうが、元を辿れば自らで作り上げたものなのだろうから羨んでも仕方のないことなのだろう。

WEA
4509-96265-2
Last Flight/Taï Phong
タイトル通り末期症状を呈しているタイ・フォン三作目。首領であったはずのタイ(Taï Ho Tong)は既におらず、カーンもゴルドマンもクレジットされてない曲があるなど実質“名前だけ”の崩壊状態だったのだろう。中身もそれに準じて、1st、2ndの趣と展開を持つ10分弱の2曲と穴埋めみたいなポップソングで構成されて、アルバムとしてはなんとも取り留めがない。ポリリズムやけっこう凝った展開も用意されているし、メロディも冷やっこさも気持ち良いのだが曲によって落差がありすぎるか。スリーブデザインも如何にもどうでも良さげな力の抜けきったものになっていて無残だ。この後、ゴルドマンは目論見通り独立してスターダムにのし上がる。復活組の方は2003年に青い鳥コンサートに出演したとかで、まだ生きているのだね。
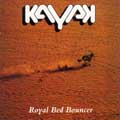
Pseudonym
CDP 1012 DD
Royal bed bouncer/Kayak
一転して、砂漠を駈け抜けるバッファローのジャケ写真が鮮烈なカヤック3rd。ほぼすべてをシェルペンツィール(Ton Scherpenzeel)が作曲した短曲ばかりのポップソング集。ボーナス9曲入り。いきなり冒頭のアップテンポなタイトル曲は、王様のベッド係りのことをコミカルに(かつ死に至る職業としてブラックに)歌っている。ナイフやダイナマイトが隠されていないかピョンピョン飛び跳ねて確認するのかいな。要はベッドの毒見係ということらしい。各曲ともコンパクトですが美麗なメロディにはますます磨きがかかり、後を思い起こさせる片鱗を顕わにしております。
しかし、このジャケにこのタイトルと、どうもオランダ人のセンスは抜けているというか、極めているというかよくわからん。
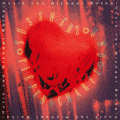
Random Records
398.6585.2
Süssherz und Tiefenschärfe/Michael Rother
TVのメロドラマ?『甘美な心と焦点深度』のサウンドトラックと思われる。CD化に際しての94年の追加音源が二曲あり。文字通り甘美なアコギの透明な音色が冴え、Midiシステムを使ったトランス・エレクトロニカに大きく移行する80年代中期作。オルゴールのような可愛らしくも愛らしいメロディと素朴で綺麗な音階は一度はまると堪えられないものがある。サウンド・トラックという制約はあるにせよ、クラウト直系とは思えない濃さの発露の仕方が根本的に違うところが興味深い。けっこう斬新かつ難しいことをやっていると思うのだが、光の粒を織り込んでいくような繊細さと傍に寄るだけで空気の色が変わるような情感が満ち溢れる。
5月末に新作『Remember』が出るようです。
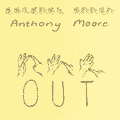
Voiceprint
VP165CD
Out/Anthony Moore
ヘンリィ・カウをお払い箱にされた78年頃に録音された蔵出し音源。スラップ・ハピィの3rdとして(つまり、ボーカルはダグマー・クラウゼ)用意された楽曲だったのだろうが、クラウゼはカウに獲られてしまったし、出してくれるレーベルがなかったことが未発表だった理由なのかもしれない。そういえばカトラーのインタビュウではクラウゼの旦那は不詳な別人(Bob Ward)とあるが、ムーア夫人という話も聞いた憶えがあるしよくわからんな。どうでもよいけど。
さて、ブレグヴァドが一詩提供+演奏してますが、残りは旧ホールワールド人脈の協力で録音されたようだ。エヤーズ(Kevin Ayers)がベース、スパロー(Eddie Sparrow)はドラム、アンディ・サマーズにベドフォードのストリングズ・アレンジが目を引きますが、面白いところでアマンダ・パーソンズとロル・コクスヒルの子供のボーカル等々。ポップでひねくれた楽曲の数々は確かにエヤーズの資質と通づるところもあるのかもしれない。 タイトルは“世に出たときには時代遅れ”みたいな意味だろうが、どうでもよさげなジャケ絵は手話になっておるのね。

RCA
ND 74112
La Bibbia/Rovescio della medaglia, Il
舌噛みそうなイル ロベッショ デッラ メダッリャの1stアルバム。メダルの裏という意味でしょうが、「“Ogni medaglia ha il suo rovescio.”=“どのメダルにも裏がある。”=“何事も良い面と悪い面がある。”」あたりからきてるのでしょうかね。タイトルはいきなり『聖書』ときたもんだ。バカロフと組んだ後年の作品が有名ですが、ここではシンフォの欠片も感じられない重いブルーズ・サイケ。おまけにライブ録音です。G、B、Dsのトリオに音響兼SE兼パーカッション兼フルート?が加わったかたちで、非常にシンプルなのだが展開や即興の混ぜ具合にはなかなか斬新なものがある。手数の多いドラムと唸りを上げるボコボコしたベースによる躍動と初期音響派のような加工ノイズが不明瞭にとぐろを巻いてのたうっておりまする。
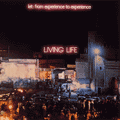
Mellow
MMP 259
Let:from experience to experience/Living life
イスラム系の建物にアラビア語の標識とチュニスかトリポリかモロッコあたりの雰囲気が濃厚なエキゾチックな夜景が美しい、リビング・ライフの1st。2ndよりもアヴァン・ガルドなジャズ色と即興風の音数の少ない展開が特徴で、英詩のボーカル曲が一曲、他はインストです。ゆったりしたアラビア風ジャズ・ロックでイタリア特有の粘っこさというか、カンツォーネなところはまったくない。荒涼とした乾燥と空気が薄いような虚無感がアヴァン・ガルドな展開と相まって独特の空気感を作り出しているように思えます。トリノのCircus 2000のドラマーだったベッティ(Johnny Betti イギリス人かな?)が主要人物だったようですが、アフガニスタンにおったそうだ。なるほどね。

Atlantic/Mesa
92796-2
Odù/King Sunny Ade
西アフリカ唯一の英植民地だったナイジェリアもの。歌詞は現地語(ヨルバ語)だが英訳付。“豆植えたら山羊に全部食われた”とかけっこう面白い。一応このアデという人物はギター+ボーカルだったりするのだが、分厚いバックコーラスとアフリカンで軽やかなリズムによるアンサンブル重視の構成のようだ。総勢18名ほどがクレジットされているようだが、半分ほどがパーカッションと非西洋音楽の典型のよう。アデ本人は所謂、世界進出にはあまり積極的ではないようで、アカペラを多用したゆったりとリズミカルな曲調が陽光の明るさと自然の風を髣髴とさせる。衣装の青紫の刺繍がとても美しい。
“Odù”とは伝統的な薬や薬草を入れる陶器製の壷、重要な文化的なアイテムをしまういれもの、俗語で今流行りの最新の事物という意味のようです。
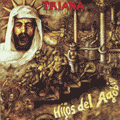
fonomusic
5 050466 176325
Hijos del agobio/Triana
外から見るイメージとしては最もエスパーニャらしいアンダルシア地方(南部8県)の領袖、トリアナ二作目。トリアナ自体が州都セビージャ(セビーリャ)の地名のようだし、「カルメン」の舞台でもあるフラメンコの本場。毎度お馴染みヘスス・デ・ラ・ロッサ(Jesús de la Rosa;本名か? 薔薇のイエス)の哀愁の演歌ぶりぶり中高域ボーカルとフラメンコ・ギターのアンサンブルに加え、ストリングシンセを多用したキーボードがいちばん目立つアルバムか。前作ほどの土着な民族性もなく、次作ほどの展開の妙と抑揚もないのだが、決して光り輝く明るさだけでないアンダルシアの闇の深さが垣間見える。少なくとも初期6作はみな闇のイメージなのだなぁ。そのあたり、ちょっと考えさせるものがあります。

Polydor
523605 2
Socrates drank the conium/Socrates drank the conium
“ソクラテスは毒ニンジンを飲んだ”の1stアルバムと思われる。もちろんソクラテスは古代ギリシャの哲学者(Sokrates;B.C.469-B.C.399)のことを指している。ちなみにソクラテスはタイトル通り、公開裁判で死刑を宣告され毒ニンジンを飲んで刑死した。 クリームみたいなブルーズ・サイケで、もこもこしたリズムと奥の方で我関せずといわんばかりにアンビエント風にでろでろ弾きまくるギターが特徴ですか。ときおり挟まれるリリカルな間と、南欧風のこってりした哀愁ボーカルが隠しきれない風土を表象している。年代物なのでリマスターとはいえ音は良くない。良く言えば情熱的、悪く言えば野卑な如何にもギリシャ風の粘っこさとオリーブ臭さが、英詩とはいえ、名は体を現すといった趣で好ましい。
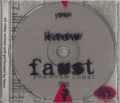
ReR F4
You know Faust/Faust
90年代の復活第一作。透明ケースに透明なロゴシートとどこかで見た仕様。CDの円盤が透明だったら驚いてあげられたんだがそれは物理的に不可能かな。所有音源はCuneiformの売店で購入した(ESD盤?)ものですが、透明なジュエルケースの表は「you know faust」と「you know us」の二枚の透明シートが重なって、裏面にはトラック・リストが印刷された透明シートがパッケージされています。オリジナルの1stと狙いは同じかな。
ディールマイヤー(Zappi Diermaier)、イルマー(Hans Joachim Irmler)、ペロン(Jean-Hervé Peron)の三名による復活ですが、確かにファウストとしか言いようのない音塊で、中欧の黄昏を一身に集めたような崩壊感と憂愁も健在です。壊れていくことの悲しさを、その先にあるグレーのプレーンな地平を冗長でなく明晰にみきれる安寧と無常があくまで荒涼として美しいのです。
「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」
見渡す限りの枯野で浅白い枯色と冷たい風が目にしみて、ふと後に伸ばした指先を温もりが包んでくれなければ、波打つ枯草の海に溺れてしまいそうだ。