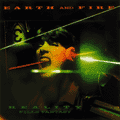
Red Bullet
RB.66.143
Reality fills fantasy/Earth & Fire
けっして一般的な評価は高くないが、個人的には気に入っている6作目。赤弾の再発ものでろくな情報がないのですが、カーフマンはいちばんかわいい。うん、普通にしたほうがずっといいじゃないか。で、そのカーフマン期待のハイトーン・ボーカルはかなり意識的に歌い方を変えていて、曲作りもカチッとまとまったタイトさが前面に押出された。トレードマークの一つだった怒涛のメロトロンが聞こえないことも変化を際立たせているだろう。その路線変更は当然ポップな方向に偏ると思いきや、11分超えの冒頭「People come, people go」で見事に裏切られるのだ。ファンキィ・タッチの軽妙さと生ストリングズのクラシカルな洗練、凝った曲展開とこれまでの垢抜けなさとの差異に面食らいますが、そのあたりはいつのまにか奥座敷に鎮座して曲まで書いているフォーカスのベルト・ルュイター(Bert Ruiter)のせいなのだろうね。その道の人にはおおむね評判の悪いルュイターですが、カーフマンの新たな魅力が引き出されてとてもおもしろい。

Sire
WPCP-4220
Azure d'or/Renaissance
同じく、なんだかあまり話題に上ることもない第2期の実質ラスト。身の丈に合った短かめのシンプルな曲と新機軸のキーボード(要はARPストリングシンセにエレピ、メロトロン)が受けなかった理由なのだろうねぇ。個人的にはあまりアレンジの冴えないオーケストラを仰々しく使うよりは無理がなくて良いと思うがなぁ。
原題は何故かフランス語で、『黄金の青』とでもいうのか、良いタイトルだ。そういえば“Renaissance”をルネサンスと呼ぶのはフランス語だし、元は再生するという動詞“renaître”から来ているのだろうからおかしくはないのか。本場イタリアなら“Rinascimento”だし、英語なら訛ってリネイサンスとでも呼ぶのだろう。元々、ハズラムの声にはトラッド基調の明るめの曲(マイナー調でない)が似合うと思うのだが、今作はその辺りをきちんと狙っているような気がします。まぁ、生き残るための時代の必然だったのだろう。それでも、経験と成熟によって、鮮やかな色彩感が匂うような上品さと相まって安定した情感を作り上げているように思う。

EG Records
EEGCD 2
No pussyfooting/Fripp & Eno
フリップ&イーノ最初のコラボレートもの。全盛期クリムゾンの影で、ギャビン・ブライヤーズなどと共にそれなりに流行っていた記憶もある。全二曲、延々とループしておりますが、後半「Swastika girl」はクリムゾンのライブの冒頭に流れている曲だね。しかし、何が鉤十字なのか逆さ卍なのか不詳だが、鉄血少女なのか女子挺身隊か? 相変わらずガラス? のテーブルにはイーノお気に入りの例のカードが並べられていて、微妙に猥雑な雰囲気が醸し出されているようだ。後々よりもずっと生々しく、官能的にうねるフリップのギターとイーノのシンセによる羊水耽溺コラボレーション。
ちなみにタイトルは、反日和見主義者という意味で猥褻な意図はないのだろうが、狙っている部分はあるのだろうね。
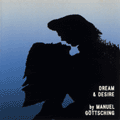
Musique Intemporelle
883 598-907 CD
Dream & desire/Manuel Göttsching
91年リリースの個人名義蔵出し発掘音源。色違いのSpalax盤もあるようです。中身は77年製作のラジオドラマの音源だったようだ。全3曲。「夢」を夢見て「希求」して、挙句は「落胆」乃至は「絶望」するという、日夜陥りやすい情動のパターンを表象しているのか否かは不詳である。何故か曲としては後者になるほど明るく華麗なのが不思議だ。時期的には『New age of Earth』とほぼ同じということで内容の方も似ているかもしれない。20年ほど先取りされたミニマル・アンビエント・テクノ。夢うつつの蕩けそうな快楽に浸りきっていると、胡蝶の夢ならぬ現実こそが限りなくうつつであることにはもはや疑義がない。ましてやインチキを旨とし衆愚盲目に開き直る世に顧みるものなど何一つない。

Marginal Talent
MT-367
Eruption/Kluster
青、赤と来て黒は一応ラスト・アルバムにあたるライブ音源ですが、前後関係はよくわからない。別に拍手や歓声が入るわけでもない至極淡々とした今作は朗読なしのオール・インスト全一曲。31分と25分に分かれてはいるけれど、別に曲名があるわけじゃないみたいだから「Eruption」一曲でよいのでしょう。内スリーブにはただ一言「Elektro Akustische Musik」すなわち「電気音響音楽」と記載されておりまする。タイトルが『Eruption(噴火)』なのだから、どっかでドカンといくのかいなと思いつつも、結局若干の抑揚はあるものの爆発はないな。無調かつリズムレスということでいつの間にか聴いているという行為を忘れてしまう。
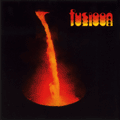
Divucsa
32-516
Fusioon/Fusioon
フシオンの1st。長くても5分ほどの短曲ばかりですが、これがまた目まぐるしい。バルセロナ出身のようで、いわゆるカスティーリャ風のスペイン臭さを感じることはなく、時折挿入される生ストリングズや木管もバロックですね。基本的には民謡をアレンジしたインスト・カバー曲ですが、印象的なフレーズがころころとコラージュされた展開と構成は新鮮です。曲は分かれていますが同じテーマが繰り返し現れて、変奏されていく様、それもジャズだったり、クラシックだったり、ロックだったり、フュージョンだったりとこれまた目まぐるしく変態しております。それを支えるテクニックも手馴れた安定感がある。後のシュールでアヴァン・ガルドな展開と空気感はまだ見られぬものの、変だったのは最初かららしい。

Deram
42284 4769-2
On the threshold of a dream/Moddy blues
コンピュータが(あるいは“に”)見る夢をテーマに据えたトータルもの、4作目。とはいっても今からみればおもちゃのガラクタが動いている音や、如何にも人工音声のようなちゃちなSEが挿入されていて、微笑ましい。一方で、ムーディーズとしてのオリジナリティはほぼ完璧に確立されて、暗い海底で這い回るような、地味で陰鬱な色調と潮に揺らぐ海藻のような穏やかなメロディ、ピッチベンドするストリング音のメロトロンが気持ち良く響いております。中身は特に暗い内容ではないけれど、60年代末期の郷愁と憂いをまざまざと見せ付けられる。
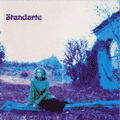
Black Widow
BWR CD 007-2
Standarte/Standarte
70年代のヴァーティゴっぽいというかアトミック・ルースターを崇拝するスタンダルテの1st。スリーブ裏面にはルースターのヴィンセント・クレイン(Vincent Crane)の遺影付。もっともこちらはイタリアもので、いきなり冷やっこいメロトロンが唸りを上げる。何故かクレジットにはないギターもそれなりですが、所々に挿入される語りとクワイアがちょっと冷やっこくて神秘的なイメージをうまく醸し出しているようだ。歌詞は全然上手くない英語だけど、演奏はかなり達者。
でまぁ、個人的にいちばん惹かれたのはスリーブの女の子なのね。一瞬アネクドテンと間違いそうな色使いのスリーブだけど、廃墟の倒木に横座りした指先しか見せないポーズが気に入った。まぁ、馬という動物には特に感慨はないし、こういった(馬を小道具に使うという)センスは本質的には理解不能だが、女の子の可憐さはより一層高まるかもしれない。
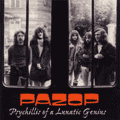
Musea
FGBG 4191.AR
Psychillis of a lunatic genius/Pazop
ベルギーのパゾ(ップかいな?)の唯一作+その他音源の寄せ集め。専任バイオリンにフルート入り、ギターレスのポップよりのジャズ・ロックとでも云おうか。かなりコミカルなコミック楽団すれすれな部分まであってちょっと印象が狂うが、TV用の主題歌やらサウンドトラック等も手掛けていたようだ。そのせいか極めてプロっぽいアンサンブルは諸刃の剣というか、二律背反というかなんとも難しい境地に陥っているような気がする。歌詞が英語なのだがフランダース人だろうか、オランダものに通ずるこなれた感覚が感じられる。非常にテクニカルで時折奏でられるメランコリックなメロディと壮絶なバイオリンには目を見張らせるものがある。コンバットやゴジラのテーマみたいなTVソングは笑っちゃうのだがねぇ。
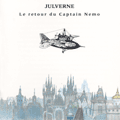
IGLOO
089
Le retour du Captain Nemo/Julverne
1973年ごろにワロン(ベルギー南部のフランス語圏)・フォークとアメリカの“フラワー・パワー”、そしてクラシックの土壌のもとに萌芽したジュルベルヌの初期(3rdは除く)のコンピ+再録盤。ユニヴェール・ゼロと共に所謂ベルギー・チェンバー燭明期の明暗双璧を成す。若干のボーカル曲もありますが、基本は管弦楽器+ピアノによるアコースティック・サロン室内楽で、ひんやりとした典雅と上品な諧謔は上質のビロードを素肌に纏うような感触だ。
スリーブのデッサンはおそらく中心的なメンバーと思われるピエール・クーロン(Pierre Coulon)とジュノー・ジリ(Jeannot Gillis)に依るもの。「t Kofschip」が飛ぶ街は、中欧ゴシックのティーン聖母教会と火薬塔の特異な屋根形状と遠望されるプラハ城? からプラハ旧市街と思われる。
もちろんジュルベルヌはジュール・ベルヌ(Jules Verne;1828-1905)から来ているのだろうが、『海底二万哩(Vingt Mille Lieues sous les mers)』の主人公がネモ船長だったっけ。大昔、ずいぶん興奮して読んだ記憶があるが既に遠い彼方、記憶も薄れた。
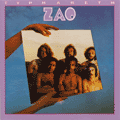
MUSEA
FGBG 4146.AR
Typhareth/Zao
ハンガリー人もベトナム人もいなくなって実質ZAO=太っちょカーン(François "Faton" Cahen)となった5作目。毒気が抜かれて、一般的にはほとんど相手にされていないよう。タイトルは何語か不明だが、“Beauté”の意らしいので“美”、“色香”といった意味なのでしょうが、エキゾチックな先鋭感と緊張感が薄れてまったりと聞き易いものになった。アフリカ系専任エスニック・パーカッションが加わったせいもあるけれど、志向は完全にアフリカ。曲はすべてカーンによるものだが、音の密度が薄くなった分、新加入の木金管隊とジェラール・プレヴォ(Gérard Prevost)のベースは粒立ちがよく明解だ。インプロの掛け合いで決める方向性ではなくて、完璧にアレンジされた楽曲ですが華麗で少し湿った西サハラの夕景といった趣。
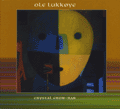
klangbad
06280-2
Crystal crow-bar/Ole Lukkøye
ロシアのアシッド・サイケ・トラッド、のようなもの。歌詞はロシア語。89年ころから活動しているようで、これが4作目にあたるようです。ボリス・バルダッシュ(Boris Bardash)なるマルチ奏者にレイニィ・シーズンとも関わりがあったアンドレイ・ラブリネンコ(Andrej Lavrinenko)、バスーン+女性ボーカルというカルテット。全員ロシア人の名前ですが中央アジアの土俗とトランスというかアンビエントなエレクトロニクスが混沌と入り乱れた奇妙でパーカッシブな音塊がのたうっております。ちょっとイタリアのリビング・ライフあたりに似た広漠でエスニックな叙情が特徴です。
ファウストのイルマー(Hans Joachim Irmer)がプロデュースというあたりで、若干ノイズ臭とアヴァン・ガルドな味が加わっているか。元々、保守的であると同時にアヴァン・ガルドという極端に芸術至上主義なお国柄だから、妙に商業ズレしていない媚のなさが気持ちよい。
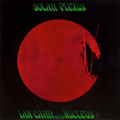
LMCD
9.00743 O
Solar plexus/Nucleus
ニュークリアス71年の三作目。アルバムクレジットはIan Carr with Nucleus+だそうで、全曲カーによるもの。+の部分は大量のゲストを意味しているのだろう。これを最後にジェンキンズ、マーシャルはソフト・マシンへ移籍、スペディング(Chris Spedding)もリタイアする。前二作でも既に頭角を現しているジェンキンズ風のリフやビート感とはほぼ無縁な楽曲の数々ですが、品質は非常に高く如何にも英国風な渋さが横溢したジャズ(・ロックとは云い難いかな)。冒頭の「Elements」を元に変奏された各曲を、各曲ごとに異なる人のソロがフィーチャされるかたちになっておるのですが、なんとも緊張感に溢れた演奏が繰り広げられております。リードを取らずにバックに徹しているスペディングのギターがとても心地良くも奥ゆかしい。

Angel Air
SJPCD111
Affinity/Affinity
サセックスの大学で60年代中期につくられた中産階級ジャズ・ロックというのかな。アフィニティとしての唯一作。男は全員理系、紅一点リンダ・ホイル(Linda Hoyle)は国語教師という変り種。なんだか中身よりもジャケットの方が有名だったりすることはジャケット以上に有名そうだな。特にセンスが良いわけでも斬新なわけでも上手いわけでもないのだが、アフィニティ最大の売りは、この時代の中でその身についた風土とそこから湧き上がるような情感を適切に表現できたことだろう。それは例えばホイルのしっとりとハスキーな声であり、くぐもったエレピやハモンドの音だったりするわけだ。
近年の再発ブームにのっていろいろな蔵出し音源が怒涛のように出回っておりますが、そこまでするほどのものかどうかはかなり疑問です。でも、ま、なんちうか、ね。
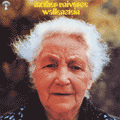
KING
KICP 2732
Mother universe/Wallenstein
いきなり“ど演歌”してしまう二作目。歌詞は中身共々今一つな英語だが、これがまたほんとに“ど演歌”で羞かしい。その下手糞など演歌をのせて、ピアノとメロトロン、躍動感と泣きのメロディで押し捲る洗練もへったくれもないドイツの剛直さが実に麗しい。
「Mother Universe」
わたしがその脳裏に感じた悪夢
昨日の夢はわたしを怯えさせた
無用な木々に巣食う蛆虫のように
生き長らえてきたことを奇異にさえ思う
今日、わたしが検証しようとしたこと
それはわたしが未来の人間でも過去の人間でもないということ
肉体は既に遥か彼方に去り
思念には悲しみと痛みだけが残された
母なる宇宙よ
我に歌を与え
涙を乾かし
そして教え給え
死後の生き様を
雨の後に輝く太陽を想像してごらん
鳥が話かける様を想像してごらん
盲目の画家の絵が悟りを導いた
内なる呼吸こそが真なりと
来世が到来し
闇が辺りを支配する前に
すべてが為されるだろう
慈愛がすべてを
終いの墓標に導く
ドイツ人のわりには英語が下手(母語なのにね)なせいか、難しい言い回しや寓意がなくて訳すのは楽なんだが、なんとも中身が青臭くて羞かしい。謹厳実直一本気なのだねぇ。
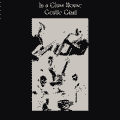
Truck
CD 001
In a glass house/Gentle giant
初めて意識的に聴いたGGはこの5作目だった気がする。移籍+シャルマン三兄弟の長兄の教職復帰等逆境に置かれた中で、GGのレベルからすればやっつけ仕事の部類に入るものかもしれないが、結果的に練り込み過ぎずストレートな内容でとっつき易かったのかもしれない。当時、この無調なメロディと外したリズム、極めてタイトで乾燥しきった音には、最初、どうにも覆せない違和感を感じたものだ。ウェットであることをとことん拒絶する天邪鬼は、やはり以前どこかに書いたようにある日、突然受け入れられるのだった。ほとんど快感に近い。ともあれ、内容的には73年という黄金時代にふさわしい先鋭と斬新だ。
ディテールに凝りまくった不可解な味わいは、ガラスの家なのにカフカの城の如く全容が見えず、行けども行けども事象の狭間に埋没していくような崩壊感覚。