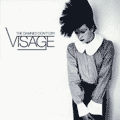
Spectrum
544 381-2
The damned don't cry/Visage
3rdかと思ったらコンピでした。3rdはCD化されておらぬようですね。出来が悪いんだろうか? コンピですが全16曲中、EPか未発表と思われる未聴が4曲に別Mixが3曲、他にもシングル乃至EPヴァージョンが含まれているとみえて、値段(1000円くらいか)の割にはお得だった。フランス語の発音がちょっと明瞭に聞こえるあたりリマスターされているような気もする。ヴィザージュ自体、80年から84年くらいの短い命で当時のコンポーザ達は今でもそれなりのことをしていますが、フロント・マンだったストレンジ氏(Steve Strange)は栄光から滑り落ちると後、美川憲一のようにはなれなかったようで、TVのクイズ番組にゲストで登場し落ちぶれきった姿を晒したとかしないとか。それ以来消息を絶ってしまったようです。世の片隅にひっそりと咲いた花は、一瞬だけ一際美しく華やいで、次の瞬間には人知れず萎れていく。考えてみるまでもなく1000年も前の人間が盛者必衰の理を説いておるのだ。人はいずれ死ぬが、かたちとして残るものは残る。いくら著作権で縛っても残らないものは残らない。それでよいではないか。
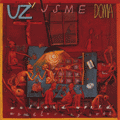
Škoda
SK0010-2
Nemilovany` sve`t/Uz` jsme doma
今年も来るらしいUJD(pronounced ooje-smay-doma(ただしアメリカ人によるもの), 'Now We're at Home' or 'Now I understand. Now I get it' in Czechね)の2nd。CDは英語バージョンとチェコ語バージョンがよくわからない順番で並べられていて困惑しますな。相変わらずの惚けた辛辣さと1stに比べ洗練された感はあるものの疾走感と緻密さはランクアップ。東欧哀歌というか演歌も美しくもアホバカしております。男女二人のSax奏者にボーカル+G,B,Dsという編成ですが、精密で手数の多いリズムセクションと重機関銃の六連射のようなギター・カッティングが聞き物。ジャケ絵を手がけているマルティン・ベリシェク(Martin Velišek)は現代画家、ガラス工芸作家としてもそれなりに有名らしい。一応インタビュー等では、彼らの作品は音楽と絵と詩の三位一体なのだと言及している。
リリースしているレコード会社のシュコダは工業国チェコの戦前からの重機メーカーで、戦車からNC工作機械、原子力発電所まで、硬質でマシナリィなちょっとしたブランドです。

ESD
81522
In praise of learning/Henry cow
スラップ・ハピィと合体したカウ名義三作目。スラップ・ハピィ名義の共同前作『Desperate straight』で歌の持つ力に刺激を受けたカウが合体を持ち掛けたらしい。その試みは後に“Art Bears”という形で結実することになる。もっともこの合体はダグマー・クラウゼ以外は“ヌルイ”と云われて無情にもお払い箱にされてしまい、結果的にスラップ・ハピィは解散に追い込まれてしまうことになる。
残されたカウの四作の中でもボーカル入りということ、ムーア+ブレグヴァドによる曲があることなどの点で最も耳に馴染み易い音だろう。一方、中身の方は極めて過激でポリティック。槌と鎌の赤旗を掲げたライブも有名でこれまた極めて格好良い。
教養が滲み出てしまう完璧に韻を踏んだ「War」の歌詞も然ることながら、「Living in the heart of the beast(獣心譜)」のホジキンソンによるテクニカルでアヴァン・ガルドな作曲技法とそれを歌いこなす透き通るダグマー・クラウゼの声が心に染みる。
「Living in the heart of the beast」
...........
さぁ、今や前進のときだ。絶望を越えて
孤独な人類の暗闇-自らコントロールできない市場という
-自由という名の下に私たちの街に吊るされた棺衣のように
彼らの沈黙の塔を我々は破壊するのだ
さぁ、今や進むべき方向を決めるときだ
運命の理の存在を受け入れることを拒絶せよ
すべての英雄と商人から我々の労働と生活、歴史的慣行を奪取するのだ
それが我々の選択だ
我々がすべきあらゆる真実を明確に規定せよ
外力、すなわち資本の王の権力をもって我々に敵対する言葉を奪取せよ
資本は貨幣制度を征服し、空虚な交換制度で我々をもがき苦しめてきた
それらは苦々しくも長らく続いてきたのだ
それらを権力から一掃するときだ
我々の言葉を回復するのだ
自由のための戦いにおいては、敢えて極端をとれ
共通の利害が我々をより強固に断固たるものにするのだ
矛盾が衝突し、繰り返される戦争をつくりだす階級制度と軍の思想
我々はそんな混乱に向かう世界の中心にいるのだから
ラスト4節の染み入るような説得力はこの時点ですら既に絶望に塗り込められたエレジーにしか聞こえない。それはそれで彼等にとってはジレンマなのだろうなぁ。
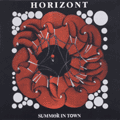
Boheme
CDBMR 008 152
Детний город/Горизонт(Summer in town/Horizont)
旧CCCPのホリゾント85年録音の1st。ゴリゾントと読むのか? おそらく。スリーブに記載されている通りのチェンバー・インストゥルメンタル・アンサンブルです。70年代中期にニジニー・ノヴゴロド市(旧閉鎖都市ゴーリキー)でセルゲイ・コルニロフ(Сергей Корнидов)なる人物を中心に構成された楽団のようだ。写真はコルニロフと思われる初老の大学教授のような人物を中心に15人ほどが写っているのだが、メンバークレジットは6人。極めてテクニカルなリズムセクションが入った変拍子バリバリだったりするのだが、基調が万に一つのポップさの欠片もなくロマン派現音+プロコフィエフ+ストラビンスキィなのでした。そのあたりがらしいといえばその通り。非常にプロフェッショナルな演奏とコーラスでつけ入る隙のない密度は賞賛に値する。醸し出される冷暗な質感とロシア・アヴァン・ガルドがアカデミックに奏でられる。
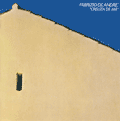
DISCHI RICORDI
CDMRL 6308
Creuza de mä/Fabrizio de Andrè
マウロ・パガーニによるプロデュース(というか共作に近い)によってかどうかは知らないが、大きく民族基調に舵を切るデ・アンドレ中期の代表作。タイトル(歌詞も)はジェノバ方言で『海につづくラバ道』の意と思われる。キーボード、管楽器、弦楽器のパガーニに加え、フランコ・ムシーダ(Franco Mussida)のギター、リズムセクション入り。正にスリーブ写真そのまんまの印象がそれ以上でもそれ以下でもなく、青と土色の透明な世界を紡ぎ出している。穏やかで学究的な視線と押さえに押さえた熱情が描き出した風土は暖かくも厳しい。市場の売り子のおばちゃんの声がいいなぁ。
深く響くジェノヴァ方言による歌と正確で緻密、的確なアレンジは地中海民族音楽をテクストにしながらも、そこに止まらない新しいかたちを呈示しているといえるだろう。パガーニの1stソロの歌もの版というか、甲乙つけ難い一枚。
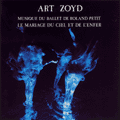
Atonal
ACD 03031
Mariage du ciel et de l'enfer/Art zoyd
ブレイク(William Blake)の「The Marriage of Heaven and Helle(天国と地獄の結婚)」をテクストにしたローラン・プティ(Roland Petit)の創作バレエの音楽。実際84年から85年にかけてのバレエの興行に同行したライブ音源のようで、バレエに関しては完璧に無知ですが、踊っている奥の一段高いステージで演奏しているようです。70年代ものに比較するとパーカッションがかなり高い比重を占め、シーケンサが導入されて今の耳には聴き易くなったとはいえ、グルーブを期待すると外します。緊張感あふれるシリアスさは相変わらずで、凍りつくようなリリシズムが堪能できます。 70年代後半にRIOに参加していたことから、それなりに情報も入って来るようになりましたが、90年代には積極的なデジタル化とともに、フィルム(無声映画)を上映しながら演奏する“映画”を演じているようです。信じ難いことに来日もしているのですが、いわゆる興行ではなくて地方芸術祭への招待参加? らしく情報を得たときには既に遅し、二度とも見逃した。
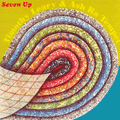
Spalax
14249
Seven up/Asha ra tempel
当時各国政府当局に追われ、スイスにしか住めなくなっていたLSDの研究者兼教祖ティモシィ・リアリィ(Timothy Leary)をスイスに訪ねた一発録り。同行者はベルリン・コズミック軍団の同朋から重役社長まで。7up(美味くもない安っぽい清涼飲料だったな)の瓶に詰めた薬でラリラリになりながら、昨今話題の回転ドアに乗ってるようなもんだなぁ。最近の自動制御大型は野趣に欠けて何が面白いのかさっぱり理解不能だが、回転ドアの楽しみは勢いつけて框に乗ってぐるぐる廻るのだよ。遊具としては目が廻るし、空調効率も良さそうだがこれを重歩行パブリック通路(なのかどうかは知らんがね)に採用する設計者と施主の感覚は極めて面白いというか、目新しさで釣れると思ったんだろうな。どこもたいていは飾りと化していて、みんな避けて通るものだよなぁ。タイミング合わないと中でスキップしなくちゃいけないし、あの自重と角速度がもつ運動量を食らうのはいやんと思うものね。
曲名も「Time」「Space」などと如何にもどうでもよさそう。御一行様誰一人真面目に考えていないのがありありなのだが、中身はそれなり。特に後半「Space」はうるうるした諦観と叙情が押し寄せてくる。

Repertoire
PMS 7060-WP
Tango fango/Guru Guru
あまりの変わり様に唖然とする中期8作目。世評も極めて低くディスコグラフィから外れている例も見受けられる始末である。悪乗り気味ののたうつグログロ感は一掃されてコミカルに明るいトランス・ファンク。かつての変人たちも教祖ノイマイヤ(Mani Neumeier)以外はおらずメンバーの違いが音楽性の違い等と割り切られるのが通例のようです。ボサノバ、タンゴ、カリプソ等の節操のない導入に加え、へろへろでぺらぺらな歌入り、ヨーデル、ゴング風、盆踊り風フォークダンス、ラストはチャック・ベリィ(Chuck Berry)の「Bye,Bye,Johnny」だよ! このアルバムの存在自体が放屁であり灰汁であり毒なのだな。
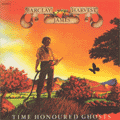
Polydor
831 543-2
Time honoured ghost/Barclay James Harvest
これ見よがしなメロトロンがなくなって大人になった中期の作。背景でしんなりと鳴っている様は上品かつ今風に近いかもしれない。非常にこなれた無駄のなさとメロディの美しい良曲揃い。ビートルズの曲名を散りばめたトラッド曲まであったりして、嗜好の一部が垣間見える。アコースティックなアプローチも増えて田園趣味にも一層拍車がかかった。ムーアのほとんどは国立公園で今は開墾などできないのだろうが、かつては新田開発と同じように農地の開墾に入植したのだろうねぇ。巨大な鎌(Amon Düül IIの『Yeti』と同じ)を持った農夫が蝶を見ながら一日の終わりに佇む、微妙に憧れをくすぐる光景だ。
ちなみに、ジャケ絵はノヴァリスの『Sommerabend』を描いたパリッシュ(Maxfield Parrish)みたいですね。日本ではほとんど無名に近いようですが、なかなか惹かれるものがある。
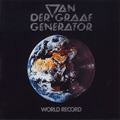
CHARISMA/Virgin
CASCD 1120
World record/Van der Graaf Generator
VdGGの最後のフルアルバム。VdGGの歴史を総括するような「Wondering」をもって幕を閉じる。無駄と隙の感じられない完成度の高さはこれ以上の存続を意味のないものにしたともいえる。実際にはこの後ミニ・アルバムが2枚ほど出るのだがVdGと名前が変わるのだね。前半はのたうつような重く攻撃的なSax、キーボード、ボーカルのバトル。複雑な変拍子を叩き分けるタイトなドラム、ハミルのギターと新機軸もあるのだが、やはり重厚で暗鬱な雲間から光が差し込むように始まる、宗教を超えた賛美歌としか思えないラスト「Wondering」だろう。
この後、キーボードのバントン(Hugh Banton)は事実、教会オルガン奏者に転進する。
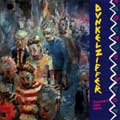
Fünfundvierzig
100
Colours and soul/Dunkelziffer
後にダモ鈴木をボーカリストに迎えることになるドゥンケルツィッファーの1stアルバム。位置付けやジャンルは不詳だが、ノイエ・ドイッチェ・ヴェレの世代による80年代版カンの情動的解釈なのだろう。コラージュされるノイズの気持ち良さが特徴です。ちょっと黒っぽい雰囲気はやっぱり末期カンのリーバップ・クワク・バー(Reebop Kwaku Baah)によるもの。80年代風の強調されたファンクなリズムと混入されるノイズ感はカンの空間的完成度(あるいは荒び)はないが、名前通りの未知数を孕んでいるのだろうな。「はーろ~、開けてくれない?」って聞こえるのは何だろう?
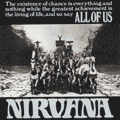
island IMCD
302/980-001-1
All of us/Nirvana
レニ・リーフェンシュタール(Leni Riefenstahl;1902-2003)によるNSDAP(国家社会主義ドイツ労働党)のドキュメンタリィ『Triumph des Willens(意志の勝利)』のワンショット、「死人が横たわる野を巡幸するナポレオンを模した戦争指導者」をジャケ絵に据えたニルヴァーナ2nd。圧倒的な才能を持ちながらも、負け組としての烙印が生涯付き纏った不運は(リーフェンシュタール共々)如何ともし難いが、たとえ歴史を作る人々からは黙殺されても中身の真価が減ずるというわけではことさらない。今回は特にコンセプト・アルバムというわけではないですが前作に勝るとも劣らぬ良作です。前半はストリングズを配した優美な佳曲、後半はキャッチィでコミカルな余裕が楽しい。総天然色のサイケ時代に敢えてモノクロ・ジャケットを上梓する天邪鬼も絶賛しよう。 前作が滑らかな曲線美のミューシャだとするならば、こちらは構成力と直線で魅せるアール・デコのマキントッシュ。ノーブルな美意識が匂い立つようだ。

REP
4943
Rebirth/Birth Control
家族計画だか受胎調節だか知らないが、名前ほどにはいかれていないドイツ産四作目。もっとも歌詞は英語だし、内スリーブにでかでかと書いてあるジャーマン・プログレッシブというよりは初期シカゴやドアーズを思わせる重量級です。間奏のように挟まれるアコースティックやメロトロンの短曲にはキーボード(Zeus B.Held)のセンスを感じるか。10分ほどですが長曲の展開、構成も円熟しているでしょう。60年代末期に結成されているようで、元々はアモン・デュールと同じく、アンチ教会を標榜したヒッピー・ムーブメントから誕生したらしい。最近は聞かないが90年代までは少なくとも生きていた息の長さを誇る。
ちなみに音源は2001年の再発CDですが、リマスターはかつてのグロープシュニットのエロック(Eroc)によるもの。おとぅさん、さすが。

Fünfundvierzig
107
Tournee/Kraan
こちらもかなりタイトで上手いドイツ産ジャズ・ロック。音は極めてまともだが風体はいかれていますな。たとえ顰蹙を買ったとしても何かやらずにはおれないところがクラウトなのか。八頭身のおじさんも考えることは変わらないのか。かなりのアルバム枚数が出ている上に80年代末には復活まで成し遂げておりますが、これは中期のライブ盤。疾走感溢れる芸達者な曲から、リリカルなバラードまで若干のエスニック趣味を加味しつつもほぼ100%インストながら良い曲を聴かせます。ライブでここまで出来れば微妙なユーモアも含めてテクニックも申し分ないでしょう。一時、グルグルあたりと合体していたこともあるようですが、グルグルのマニ・ノイマイヤーが感銘を受けたなどという話もどこかにあったな。

BMG
74321984482
Dedicate à Giovanna G./Hunka Munka
カラフルな便器が日本にお目見えしたのは80年代中頃だったか。便器は接続管の口径が日本の規格に合わないし、タイルは寸法精度がてんでバラバラな上、陶器あるいは磁器として歩止りが悪過ぎて使いものにならなかった“イタもの”が懐かしい。基本的なところは今も何も変わっていないのかもしれないが、EUの標準化は大きな影響を与えているのだろうな。
本名はロベルト・カリオット(Roberto Cariotto)、Dik Dikのキーボードでもあります。ラテン系言語は語頭にHがくることはほとんどない(発音もしない)ので、如何にも胡散臭げな偽名だし、盤面にはこれまた違う名前が記載されているので、契約上の問題でもあったのでしょう。カンタウトーレのイヴァン・グラツィアーニ(Ivan Graziani)との共演というかたちで、イタリアらしい暖かで優美な楽曲が並びます。リマスターとはいえ音の切れはかなり悪く古臭い。輪郭がボケているだけに、よく伸びるハイトーン・ボーカルとオルガンの音はますます春の霞に溶け込んでいくような深い味わいを醸し出す。
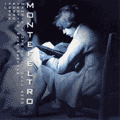
Mellow
MMP 413
Il pesce rosso, vestito alla Werther, mangiò l'uva 1º dell'anno/Montefeltro
モンテフェルトロの二作目。二人ユニットの片割れが消えて、二人加わって結果的にトリオになったらしい。察するに主要人物はアティッリョ・ビルジッリョ(Attilio Virgilio)というマルチ・プレイヤーの中年のおっさんだったようだ。う~む、ふわっと儚げで優しい、かなりへタな歌もこの人が歌っているようで、写真を見ると思いきりイメージが狂います。
イタリアものでは比較的珍しいローマ録音だし、この頭巾のスタイルからしてラッツィオ以南(チュニジアじゃねえだろうな)の出のようです。けったいで創意に富んだ変拍子に乗る極めてリリカルで美麗なメロディが儚くも霞に溶け込んでいくような味わい。もっともその最大の特徴はカチッと締まらない詰めの甘さにあるわけで、それがこの微妙な淡さを醸し出す雅致に至るのであろう。
今回は聞いたこともないいくつかのイタリア・オペラからの引用がネタのようで、冒頭ではジャック・プレヴェール(Jacques Prévert;1900-1977)の詩が朗読されている。長ったらしいタイトルは『金魚、ヴェルターの服、年に一度ブドウを食べた』の意だが、ヴェルターは古臭くいえばヴェルテルで、ゲーテの「若きヴェルテルの悩み」のヴェルテルなのだろうが、お手上げ。この単語の羅列から何も閃かない教養のなさが露呈してしまったな。