
Strange place for snow/E.S.T.
スウェーデンのジャズ・トリオ。わたしはかっぽれの方が好みですが、稀にちょっと品の良い西洋音楽なども聴いてみたりします。昨今は夕暮れ時に雨が降らない限り散歩などと称して近隣の在を逍遥いたしております。ときには停車場の方まで足を伸ばすこともありますが、夕陽のあたる場末の駅頭で傷痍軍人さんのハーモニカを少し離れて聞きながら、おもむろに懐中から時計を取り出して時間を気にしたりするのです。
気がつくといつのまにかハーモニカの音が止んでいて、顔を上げると帽垂れ付きの下士官用略帽を目深に被った軍人さんと正面から目が合ってしまうのです。いや、そんな気がするだけかもしれません。そのときだけは人通りが絶えた凍りつくような静寂のなかで、つばの影になった深くて黒い穴のような双の目に吸い付けられてしまうのです。じりじりと夕陽がつばの影を小さくしていきます。赤く弱い光が目にかかりそうになった直前、わたしは思わず目を逸らしてしまいます。
やがて、なにごとも無かったようにハーモニカの音が再び聞こえ、足元を乾いた風が抜けていきます。硬直している自分の影が針金のように細く長く黒く伸びきって、薄闇に消えていきます。
歌無しだから意味はわからないけれど、タイトルの「雪降る不思議な場所」という単語から瞬間的にイメージが浮かびました。研ぎ澄まされた怜悧な音でありながら、ノスタルジックな淡さを併せ持つ。色の薄い透明さに身を切られそうだ。これはジャンル云々を超えて素直に心に切り込んでくる。
コロンビア系列のレコード会社から出ているのですが、「このCDは究極的な品質基準によって製造されている。もし製造上の瑕疵があると思ったら以下に電話されたし」として電話番号が書いてあったりしておもしろい。確かに音質面では音圧が高いだけといったレベルでなく粒立ちと透明感が凄い。円盤のデザインも美しいし、新品でも安価で手に入る。楽師の才能もさることながら、CDDAでもここまで出来るみたいなエンジニアリングも良い仕事です。売る側の都合にすぎないSACDやDVD-Audioに移行するつもりはないので、CCCD化の波とは無縁なところで生きていける余地も少しづつ狭まっているのでしょう。新しいものに興味は向かないのだけれど、再発でCCCD化という例も散見されるようなので、そろそろ引退も視野に入れておかないと。

Live - Playing the fool/Gentle Giant
正規ライブ盤。芸人ですね、超一流の。ぴ~ひょろ、ぴ~ひょろ、みんなで笛(リコーダー;竪笛だな)を取り出して吹きだす「Octpusからの抜粋」「On reflection」なんて小学校の鼓笛隊のようだぞ。5人のア・カペラ・コーラスワーク、パーカッション・アンサンブルも完璧に再現されています。非常に繊細に決めまくる変拍子に、一音たりとも落とさない職人芸的な緻密さは正に脅威的でしょう。テクニックを超えたところでのエンターテインというか芸人魂がいかんなく発揮されているのですね。かなりフラットで概観的な録音なので、今風のダイナミズムには大きく欠けているのだが、GGはベースがぶんぶん唸っちゃったりしたらやっぱり興醒めだからちょうど良いのかもしれない。

USA/King crimson
少し前にようやくCD化された70年代の正規ライブ盤。録音は『Red』以前だったと思った。新品1000円で叩き売ってたから買ってみた。リマスターに伴って、ボーナスが追加になっているのはどうでも良いのだが、LPに比べ、ベースの音がやたら奥に引っ込んでしまって音質的には非常によろしくないし、冴えない。おまけに「Starless」を歌うウェットン、歌詞が無茶苦茶です。うろ覚えで歌っているのがみえみえ。ライブで歌いながら完成度を高めたみたいな話もあるようですが、詩を書いているのはそれなりの別人だし、一つの節の中で意味が通らなくなっているし、聴いていてちょっと恥ずかしい。個人的に好きなのは「Exiles」かなぁ。展開の妙とリリカルで淡色の寂漠感が堪らない。
当時(の当地で)はヘビメタとして聴かれることが多かったようですが、その辺の教訓が今のクリムゾンに生かされているんでしょう。
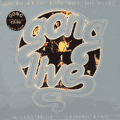
Live etc/Gong
全盛期の3年に渡るライブLP二枚組。もっとも中身はヴァージンが勝手に編集して出したらしく散漫だ。A-C面がデビッド・アレン在籍時の音源と未発表曲で『電気チーズ』から『天使卵』まで。D面がアレン抜き『Shamal』時のメンバーによる『You』の再現。前半はティム・ブレイク(Tim Blake)とミキサー、トリシュ(Christian Tritsch)による音響効果と宙を舞うウィスパー・ボイス、後半はコケティッシュな変態感を省略した畳み掛ける超絶リズム隊が聴きどころでしょう。ヒレッジ(Steve Hillage)のギターと同等以上の存在感があるのがマルールブ(Didier Malherbe)の管楽器で、この人の存在がゴングをゴングたらしめている、と個人的には思う。
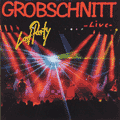
Brain
843 106-2
Last party - Live/Grobschnitt
1989年、出身地である地元ハーゲンでのラスト・ライブ。午前0時スタートで朝の4時過ぎまでのライブだそうで、こちらは是非CD二枚組にしてほしかった。この時点ではかつてのメンバーである、エロック(Eroc)、ミスト(Mist)、フンター(Hunter)等に加え、ローディー兼舞台役者、玉男(Ballermann)まで総出演のようですね。聴いているだけではわけのわからない演出の数々で是非DVDで見てみたいものだ。ほぼかつての名曲ぞろいで、アレンジも音も非常に良い状態で録音されています。音楽的に奇を衒うことはないし、テクニックをひけらかすわけでもないのだが、演じることに対する独特の矜持が強烈なオリジナリティに結びついた稀有な例だろう。ライブは存在した1970年から89年にかけて計1356回にのぼるそうで、これだけの完璧主義でこなすとなると想像を絶して疲弊するでしょう。お疲れさん。
グロープシュニットは第一次大戦時のプロシアの軍楽隊から取ったものと思われる。
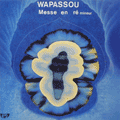
Messe en ré mineur/Wapassou
メジャー・デビューの初作、実質二作目。その名の通りの宗教曲、通しで全一曲です。後の文藝シリーズに比べると、ドラマチックな構成や展開には欠けるし、稚拙さもあちこちに見え隠れする。一方、リズムレスであることを逆手に取ったような奔放さで入れ替わり立ち代わり極めて音響的なソロをとるキーボード、バイオリン、ギターが、これまた音響的に処理されたボーカル・スキャットを加えて構築的でいながら夢見るような儚げな四重奏になっている。ほぼ全編を貫くスキャットは Eurydice(ギリシャ神話;オルフェウスの妻ユーリディス=妖精)ということでぼかされていますが、似たような音色のキーボードとユニゾンして相乗効果を狙っていたりするところなど非常に独創的です。
アンジュと同じストラスブール(ドイツ名;シュトラスブルク)出身ですが、フランス色は薄い。むしろ中世ドイツで勃興したプロテスタント色すら感じさせる部分がある。まぁ、フランスになって高々60年ほどだし、中世以降ドイツとの係争地で文化も人間も入り乱れているのでしょう。
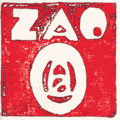
Z=7L/Zao
マグマをリタイアしたカーン(François Cahen)を中心に、管楽器のセファー(Yochk'o Seffer)、バイオリンのジャン-イブ・リゴー(Jean-Yves Rigaud)をフロントマンにしたジャズ・ロック、ザオの1st。最大の特徴はプラトン(Mauricia Platon)という多分モーリタニア系黒人女性ボーカルがいることか。もっとも歌うというよりはほとんどスキャット。比較的よく伸びる声だけど体型も含めてなかなか迫力があります。アレンジされた硬質なアンサンブルで、リード楽器が掛け合いをしたりすることはまったくありませんが、マグマよりは若干即興の余地が残されているので、かっちりとした構成的なアレンジを期待した人の中には肩透かしを食った人もいたようです。方向性としては良いと思う。
わたしたちに調和された円環を踏破する必要がある限り、
わたしたちにあらゆる知識の統合を忘却に導く手法を完遂する必要がある限り、
わたしたちはリズムとパワーという二つの要素からなる。
それは音楽という引き攣った天空を最大限跳ね回る
太陽という巨大な回転円盤のO(オー)なのだ。
水平線のような眉のもとで、三つのフェルマータは
光に沸き立つ無数のダイアモンドの心の奥に浸透する。
それが“ザオ”だ。
内スリーブのプラトンによるフレーズは変てこりんなマークの説明なのだろうな。“ザオ”という名称の由来はベルグモン(Boris Bergman)という詩人?によるものらしいが、響きにはアフリカ的なものを感ずる。

クラシックピアノ名演集Vol.2 「皇帝」「テンペスト」/Ludwig van Beethoven
一区切り。もちろんお目当てはピアノソナタ 第17番 ニ短調 Op31-2「テンペスト」。1802年作曲で「テンペスト」は後世つけられた表題です。まぁ、有名なのは第三楽章なのだろうが、第一、第二があっての第三なのは云うまでもない。もちろん弾く人によっていろいろな解釈があり、まったくクラシック慣れしていないわたしにもずいぶんとメディアによって違って聞こえるのは事実だ。ちなみにこの100円CDは冗談です。音質的に決してお薦めできないので、できれば1000円ぐらいするのを買って下さい。
ろくに聴き比べているわけでもないのだが、結局いちばん好きなバージョンは遥か昔に聴いた、ほんの素人による無名のバージョンなのだ。指先から溢れ出すような感情の奔流と、窓から差しこむ断末魔の夕陽が冷たく少し薄暗い空気の中で燠火のように燃えあがっていた。特に音響が良い部屋でもないし、ピアノもごくごく普通のグランドピアノだったけれど、記憶の底に刻まれた音は溢れるほどの情感をもって甦る。
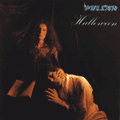
Musea
FGBG 4022.AR
Halloween/Pulsar
後追いで聞いた三作目。巷では最高傑作といわれているらしい。実際、当時のフランスではアンジュの次のレコード・セールスを誇ったそうだ。もっとも、メロトロン買ったりとか、機材への投資額が馬鹿にならず貧乏に喘いでいたらしいのはよくある話。アイルランド民謡で始まる隙のない完成度を誇る文藝路線トータル・アルバム。ビクトル・ボッシュ(Victor Bosch)によって書き起されたスュルレエル(surréel)な物語を下に淡々と繰り広げられてゆく。中身は《少女と最後はボタンになってしまう不定な男「彼」》の物語。歌詞が英語なのが残念だが、よく練られた構成と冷たい霧に霞む流麗なメロディがひたひたと忍び寄る。ジャック・ローマン(Jacques Roman)とローラン・リシャール(Roland Richard)という二人のキーボード(リシャールは兼管楽器)が作り出す、ピュルサ独特の眠いような黄昏たほの暗さが類稀な一つの世界を作り上げているだろう。ボッシュのパーカッションも一定の様式にとらわれない創意と工夫が冴えている。

Primadonna/Sphéroe
スフェローの2ndにしてラスト。パウル・ブンダーリッヒ(Paul Wunderlich)風のアートワークだけれど中身は淡く儚いジャズ・ロック・フランセ。空気の色がほのかにエロティックに染まる。全曲インストで複雑な展開と華麗なメロディは、鮮明な補色が作り出す眩惑感さながらのように新鮮だ。テクニックに関しては文句のつけどころがなく、その優劣で語るレベルを超えて、純粋にセンスで評価できる高みに昇華されている。
フランスというとマグマやゴング、あるいはシャンソンかpleymo(名前知ってるだけだけど)ぐらいしか話題になることはないし、陽のあたる部分は極めて限られているようだ。でも、その背後の日陰にはこういった優れた音楽が石のように転がっている(いた)。肥えた土壌だったのだろう。
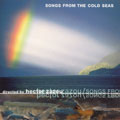
Songs from the cold seas/Zazou,Hector
極海をめぐる企画もの。北極海をめぐる地域の民族音楽(等?)を極めて今風にアレンジするというお得意のシリーズものか。ディープ・フォレストやアディエマスあたりのブームに上手く乗っかろうとした気配が濃厚かもしれない。非常に器用な人のせいかそれなりのものに仕上がっているし、若干アヴァン・ガルドなセンスは品が良いし、世間的には十分通るのだろうね。最大の売りは各地域の著名人を引っ張りだしたことなのかどうか、アイスランドのビヨルク(Björk)、北米のスザンヌ・べガ(Suzanne Vega)+ジョン・ケイル(John Cale)に加え、何故か北海道がTokiko Kato(加藤登紀子?)なのだなぁ。原曲がアイヌの音楽(と思われるもの)には北海道アイヌ・パーカッショニストの太鼓が入っているのだが、こちらは無記名。加藤と北海道やアイヌが何の関係もないように、あるいは、東シベリア、ヤクート族の歌で日本人が箏を弾いていたりするところなど、他のボーカリスト達とその地域の関係性も実に胡散臭い。

Three mantras/Cabaret Voltaire
スロビング・グリッスルあたりとタメを張っていたインダストリアル・ノイズ。当時既に中年のおっさん、ワトソン(Chris Watson)の実験をライブで実現するために組織されたと思われる。LP A、B面各一曲という豪奢なパターンで、「Western Mantra」「Eastern Mantra」全二曲入り。エルサレムのアラブ人市場のテープが使われている方が二曲目で「東」としか考えられないので、CDの曲表記は前後が逆になっていると思われる。「西」は延々とループするリズムにノイズが絡むカッコ良いインダストリアル、「東」はエスニックな民族性の光と影が強調されたアンビエントに近い。梵語のマントラはそのまま真言の意で“仏や菩薩の教えや功徳を秘めた呪文”のこと。高僧が唱える真言はそれなりに迫力があるものです。
もちろん、一般的にはキャバレ・ヴォルテールはスイス、チューリッヒのキャバレの名称で、トリスタン・ツァラ(Tristan Tzara;1896-1963)がダダ宣言をしたチューリッヒ・ダダ発祥の地として名高い。WW1の最中の1916年、ドイツの亡命作家・演出家フーゴー・バル(Hugo Ball)によって開店した。あるいは一号だけ発刊されたダダの機関紙の名前を指す。
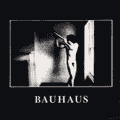
In the flat field/Bauhaus
けっこう評価が高いデビュー・アルバム。色身のない黒基調でポスト・パンクしております。如何にも初期4ADなノイジーな音響と引き攣れたような神経症ボーカルが相まって、暗い影の中にシリアスな耽美が見え隠れします。切れ込んでくる鋭利な刃先が斑に白く輝く。ゴシック云々はもとより、ニューウェイブすら知らず、都落ちして音楽全体に完全に興味を失っていた時期に、ただ、たまたま引いたくじが当たったぐらいの確率で聴いたバウハウス。
CDはtrack2-10がLPと同曲で前後にプラス8曲のシングルが追加になっている。LP収録曲を中間に埋めたことが意図として良いのかどうかは疑問なところだ。その上、記載されているのは全部で17曲なのだが、何故か18曲目が入っているのだなぁ。
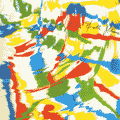
Spalax CD
14591
Belle alliance/Ashra
比較的ロックっぽいリズムでまとめられた『Correlations』の次作にして80年代リリース一作目。『Correlations』の三人体制ですが、アシュラとしての固定的な体制はここで終り、ヴァージンからのリリースも前作で終了して以後はプロジェクト風の流動体制になる。三人分の食い扶ちはとても稼げなかったということでせうか。ひんやり冷たかった前作に比べ、音感はかなりカラフルで鮮烈だが鋭角的に尖った角は意識的に丸められ、しなやかで女性的な印象を持つ。後半にアンビエントな曲調は集中するも、気持ち良く美しく遷移するメロディとループによる、さざなみに揺られる小舟さながらの悦楽。掛け声風の人声や、グロスコプフのパーカッションの効果もあって、アシュラのアルバム中でも非常に親しみ易い一枚かもしれない。
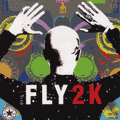
Grammy Grand
G-0543003
2k/Fly
30代後半といった感じの苦労と容色の衰えが滲み出ちゃっているフライ。タイ文字にタイ語ということで、これは極めて手強そうな文字であり言語だ。上っ面を撫でるレベルはおろか、中身はほとんど完全にお手上げです。外観はよくあるロック風ですが、もろ東南アジア歌謡曲というかメロディアスな演歌で微妙にやるせなく湿っぽい。歌を歌っているのがサンプラザ中野のような剃髪のおっさんなのだが、甘めの良い声しています。リズムもけっこう凝ってたりするのだが、いちばん合うのはバラード風の南洋恋歌なのだなぁ。
むっとするような雨上がりの屋台なんぞで、安っぽくて温いビールを傾けながら、焼き鳥と鳥の代わりに豚肉が差さっている串に、適当に調味料をぶっかけて甘過ぎたり、辛過ぎたりオタオタしながら、締めはカオ・パット(炒飯ね)みたいな、なかなか沈まない夕陽を眺めつつも、ふと仰いだ天空が思いのほか蒼かったりして、まぁ、明日のことは明日、朝飯食いながら考えようかと思ったり思わなかったりと、極めて杜撰な心境なのだ。
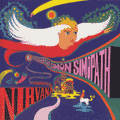
island IMCD
301/980 001-0
The story of Simon Simopath/Nirvana
相変わらずニルヴァーナ違いの方のニルヴァーナ。年代物の1stアルバムです。非常に安価な再発CDはステレオ盤とモノラル盤のカップリングの上に、シングルのBサイド4曲入りとてんこ盛り。SFパントマイムを元にした世界初のトータルアルバムとライナーには書かれています。67年7月のリリースのようですが、ムーディーズよりも早かったんでしょうか。
この時点でのニルヴァーナはアテネ生まれのスピロプロス(George Alex Spyropoulos)とアイルランドはウォーターフォード生まれのキャンベル-ライオンズ(Patrick Campbell-Lyons)の二人ユニットに加えて、4人加わったかたちになっています。スピロプロスがキーボード、キャンベル-ライオンズがリズム・ギターで、シンガー(Ray Singer)がギター、ヘンダーソン(Brian Henderson)がベース、紅一点、シュスター(Sylvia A. Schuster)がチェロ、さらにビオラ、フレンチホルン、オーケストラアレンジのクー(Michael Coe)といった陣容です。写真がなんというか時代を感じさせる良い出来です。ちなみに左から二人目がスピロプロス、右端がキャンベル-ライオンズ。
中身はうっとりするほどメロディアスなポップ。アール・ヌボーからアール・デコあたりを思わせる微妙にクラシカルな雰囲気と、無国籍なメロディが絡み合って不思議な魅力を放ちます。甘い樹液に誘われる甲虫か、花の蜜に囚われた蝶になった心境だ。音はさすがに年代物だけれどそれを補って余りある優雅で品の良い楽曲の数々。至福のティータイムに。