
In search of the lost chord/Moody Blues
ジョージ・ハリスンあたりに影響を受けたと言明しているが、当時のトレンドだった東洋(っていうかインド)思想へのカブレぶりが色濃い。人の「生」をテーマにした、生命を司る神視点の歌詞が思い上がっていると批判された三作目。思い上がりというよりは若気の至りだろう。前作の空前のヒットを受けて、一気にオーバーグラウンドに浮上したはずだが、派手なオーケストレイションはあっさり捨てて、ポップな歌ものアンサンブルと流れるようなトータルな展開に拘泥しているようだ。シタールなんぞも使っていたりするのは御愛嬌だが、やはり派手過ぎず地味過ぎず、オーケストラの単なる代用を超えたメロトロンとレイ・トーマス(Ray Thomas)によるフルートが画期的ともいえる効果を与えている。
元々、メロトロンの製作会社で調整と出荷前テストをしていたピンダー(Mike Pinder)によって、ほぼこれ以上はないというぐらい斬新に、かつ全面的に限界まで弾き倒されているメロトロン(Mellotron Mark II)の威力は正に目を見張る。
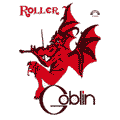
Roller/Goblin
一枚目のオリジナル・アルバム。サントラを含めると三作目。全曲インスト、シャープでクリア、緊張感と抒情性が高いレベルで結合した逸品です。壮大ともいえる構築美を誇りながらも根底に漂う民族性を忘れない。優れて、非常にアグレッシブなのだが気品すら感じさせるセンスと楽曲は、総じてレベルの高いイタリアものの中でも一際異彩を放つ。何だか極もの風の扱いを受けることも多いのだが、教会オルガンの崇高さはピカ一。
クラウディオ・シモネッティ(Claudio Simonetti)による繊細で大胆なキーボードもさることながら、アゴスティーノ・マランゴーロ(Agostino Marangolo)の卓越したバテッリャももの凄い。アルティのフリオ・キリコとはタイプが違うが、この静謐ともいえるクールな躍動感は筆舌に尽くし難い。

Burn the bridges/Spirogyra
1st以前のデモテープと未発表曲、シングルをまとめた編集盤といったところでしょう。ケント大学の学生だったコッカーラムとガスキンを中心に1969年頃にはその体を成していたようです。デモは1970年と1971年にケント大学の音楽室で録音されたそうですが、非常に優れたリマスターが施されて恐ろしくクリアな音質に仕上がっています。ガスキンのボーカルの硬質な透明感も申し分のない出来です。ドラムレスが基本ですが、フェアポートのマタックス(Dave Mattacks)が叩いている曲もあります。アレンジは正規盤に比べ稚拙だし洗練されていないのだが、素朴ながらも如何にもミドルクラスといった落ち着いた丁寧さが麗しくも暖かい。

Liege & Lief/Fairport Convention
フェアポートの評価を名実共に不動のものにした四作目。8曲中、独自解釈のトラッドが5曲、残りはオリジナル曲で、サンディ・デニィ(Sandy Denny)の凛としたボーカルと、バイオリン、ギターを前面に出した力強いアンサンブルが冴え渡る。電気も通っているし、リズムもかなりロック風のビートを強調したものになっている。それでいて、枯れた味わいのイングランド滋味と乾いた抒情が滲み出るように湧き上がる。ボーカルが女性ボーカルのデニィだけ、いわゆるフィドル奏者といわれるバイオリン、ビオラのスウォーブリック(Dave Swarbrick)が正式加入したことで中途半端な饒舌感がなくなって、コンパクトにかつ自然体にまとまったように思える。冷たい風が吹き抜ける灰色の街路でも眺めながら、冷えたラガーとヒラメのマリネ、熱々のチップス(ポテチじゃないよ)に塩胡椒で文句なし。
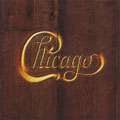
V/Chicago
初めてのシングルLPだった5thアルバム。初期の融通のきかない武骨な固さがとれて洗練されてきた。逆にいえば若干軽やかにポップになったともいう。アヴァン風の展開をみせるファンクなリズムを背景にした即興と、アレンジされた爽やかなポップソングが交互に並ぶ。ほぼ全曲をロバート・ラム(Robert Lamm)が書いていて、メロディ・メイカーとしての才覚も十二分に発揮されているだろう。著名なのは「Saturday in the park」か、ノンポリとセクトの掛け合い漫才みたいな「Dialogue」あたりだろうが、意欲的だが吹っ切れた感もあるなぁ。
「Saturday in the park」
土曜日の公園、それは7月4日だったと思う
土曜日の公園、あれは7月4日だったと思う
踊る人、笑う人
アイスクリーム売りのおっさんもイタリアの歌を歌っている
「Eicay varee, eisee nardee(注;テキトーな伊語のフレーズらしい)」
わかるかい? もちろん
ずっと長い間待ち望んでいた
そんな土曜日
土曜日の公園、それは7月4日だったと思う
土曜日の公園、あれは7月4日だったと思う
話す人、本当の笑い声
ギターを弾く人、歌う人
みんなに歌を聞かせてくれる
さぁ、一緒に世界を変えていこう
わかるかい? もちろん
ずっと長い間待ち望んでいた
今日まで
騎馬警官がゆっくりとした動きで国旗を掲揚する
銅像になる男はいまだに嘘をつき続けている
でも聞いてくれ、すべてが失われたわけじゃないだろう
すべてが失われたわけじゃないだろう
その公園での40日間、毎日が7月4日だ
その公園での40日間、毎日がお祭りだ
手を差し伸べる人、それを受ける人
みんな歌を待ち望んでいる
本当の祝賀のための歌を
わかるかい? もちろん
ずっと長い間待ち望んでいた
今日の日まで
公園はNYCのセントラル・パーク。7月4日は独立記念日。一歩身を引いて廻りを見回したとき、世の中捨てたもんじゃないな、という前向きな感覚に浸れることは人間に固有の感覚なのだろう。市井の幸福に(東洋人なら自然でもよいが)慰藉を求めるとき、平凡で平和な光景が何の上に立脚しているかは言わずもがななのか、捨象されているのかはよくわからない。シカゴの歌詞は二つめだが、内容が直截的だし単純でわかり易いからであって他意はありません。
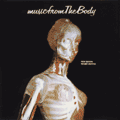
Music from the Body/Ron Geesin,Roger Waters
ドイツのドキュメンタリィ医学映画のサウンドトラック。映画もTVで見た記憶があるが、非常に科学的かつドラスティックで余り気持ちの良いものではなかった。残念ながら民生用ビデオがこの世になかった頃の放映のはずなんで、あまり記憶もさだかではないのだが、サウンドトラックとしてはとてもよく出来ていた印象は残っている。ロン・ギーシンはバレエ音楽等を手がけていた現代音楽系のコンポーザ。ギーシン自身が演奏しているバイオリンやピアノは奇矯でかなり変態的な印象が強い。初聴時はかなり面食らったものだ。
ピンク・フロイドとの最初の関わりは『Atom Heart Mother』だったのか、バレエ音楽だったのか、あるいはこの『Body』だったのかは不詳です。リアレンジが施されているとは云え、ウォーターズの曲「Sea shell and stone」、「Chain of life」そして「Breathe」はそのまま後の『Dark side of the moon』の「Breathe」、「Give birth to a smile」はそのまま「Eclipse」の原曲と思われる。『DSotM』の毛色の異質さ、黒人女性バックコーラスの導入や、SE(Sound Effect)の多用、滑らかに展開されていく曲間の繋ぎなどはすべてこの『Body』に範があると思われる。

EMI/Harvest
07243 538406 2 4
Once again/Barclay James Harvest
二作目。後々に渡ってライブでも取り上げられる「She said」、ゴドフリィによるオーケストラ・アレンジ、コンダクトが冴える「Galadriel」「Mocking bird」等を含み、BJHらしさの確立に向かう最初の転換点だろう。ビート感はほとんど失せているのだが、メロトロンをバックにした憂愁で儚さいっぱいの田園BJH節と、ロック風のダイナミズムと粗野さも捨て難いみたいなバタバタした中途半端さ加減を堪能できます。長曲が増えて、一曲の展開もかなり凝ったものになってきた。
ジャケットは蝶を模式化したもの。1stもそうなのだが蝶がトレードマークになっているらしい。分解能があまり上がっていないリマスターはオリジナル8曲に5曲のボーナス入り。公式Webは非常に丁寧で誠実な作りで好感が持てる。

Love over gold/Dire Straits
キーボードが加わって音に広がりが出たスタジオ盤四作目。14分15秒の「Telegraph road」を始め、6分から8分に近い長めの曲が並びます。サウンドトラックを思わせる叙景的な曲と起承転結のある展開が特徴的です。前作は『Making movies』ってそのままのタイトルだったし、副業で始めた映画音楽の作曲の成果がすんなり出ています。節度のある端正な楽曲と、これまた得意の叙事的な歌詞で中高年向け、大人の滋味を謳い上げておりまする。一本調子になりがちなタイプなだけに、抑揚と展開の妙を尽くしたようなダイナミックな動静が、タイトなリズムと相まってとても気持ちが良い。
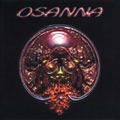
AFRAKA
SIAE CDEL 2004
Taka Boom/Osanna
チャカ・カーンの妹がタカ・ブームというらしいが初めて聞いた。チャカ・カーンはけっこう昔の黒人R&B歌手だった、気がする。で、その名前とタイトルはどう関係するのだろうかは(歌詞探してもないし)知らない。いきなりトンでもないダンサブルなビートで、目が点になりますがすぐに聴き憶えのあるメロディに移行するという仕掛け。基本的にはセルフ・カバーのリミックスといったところ。それでも「Oro caldo(鮮やかな金色)」や「There will be time」等々には記憶の底を刺激され、沸々と湧き上がるものを押さえられないものがある。かつての狂おしいまでの無常感と刹那感は、安定したリズムと今風の節度ある音に置き換えられてしまったが、こっちも歳を食ったから丁度良いのかもしれない。
オザンナとはいえ、かつてのメンバーはダニーロ・ルスティッチ(Danilo Rustici)とリノ・ヴァイレッティ(Lino Vairetti)しか残っていない。おまけにナポリのインディ・レーベルみたいなところから出ているようだし、次は期待できそうもないな。
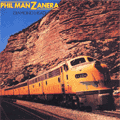
Diamond head/Phil Manzanera
ロクシィ休止期のソロアルバム。マンザネラは確かベネズエラ人だと思ったのだが、いきなりワイアット(Robert Wyatt)がスペイン語で歌い始める「Frontera(国境)」で幕開け。まぁ、なんというか人望があるのだろうね。マッケイ(Andy Mackay)、トンプソン(Paul Thompson)、イーノのロクシィ組に加えて、ウェットン(John Wetton)が出ずっぱりで歌にメロトロンまで弾いて、マクドナルド(Ian MacDonald)にエディ・ジョブソン、クワイエット・サン(Quiet Sun)からヘイワード(Charles Hayward)、マコーミック(Bill MacCormick)、ジャレット(Dave Jarret)に、更にラテン系と思われる人達まで目が廻りそうなゲストです。元々、弾きまくるギター弾きじゃないし、出力をイーノのトリートメントを通して加工しているので、今聞いても新鮮な感触が味わえる。関わっているメンバーのわりには特に奇矯を狙うこともなく、エキセントリックでもなく、非常に質の高いひどく落ち着いた大人の渋みを淡々と演じている様が気持ち良い。これがこのまま“801”に直結しているのだろう。
ダイアモンド・ヘッドというのは旧ハワイ王国にある火山の名前だと思うのだが、タイトル曲はインスト曲だし意図はよくわからん。
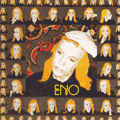
EG Records
0777 7 87020 2 3
Talking Tiger Mountain(by strategy)/Eno, Brian
ソロ二作目で基本は前作の延長線上。フィル・マンザネラ(Phil Manzanera)の全面的な協力で作られた模様。地味だけれど音響処理されて、ツボを押さえた巧みなギターサウンドが特徴的です。その他ロバート・ワイアットのバック・コーラス入り。暗中模索な前作に比して、コンパクトでポップな方向性は固まったように思える。
タイトルは革命現代京劇「智取威虎山(チ チュ ウェイ フ シャン)」からとっており、「智恵で威虎山を奪取する」と云う意味。京劇のシーンをもとにした絵葉書と切手からイメージを膨らましたようだ。中身は雪の威虎山に立て篭もった山賊を智恵と策略で奪取する人民解放軍の物語であるのだな。まぁ、イーノ自身は典型的なアングロサクソンの常として毛沢東主義者ではないし、むしろアンチだと語っているそうです。ジャケットは1500枚製作されたリトグラフの何枚かを並べたもの。
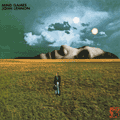
EMI
7243 5 42425 2 6
Mind games/John Lennon
ちょうど30年前の秋、発売されたばかりの新品のLPを聴いたときの印象を今でも鮮烈に思い出すことができる。冒頭「Mind games」の力強さと刹那さがない混ぜになったような情感に呑まれたものだ。単純な曲なのだけれど突き上げるような高揚感に包まれる。全体的に前作までの過激な政治性は薄れて、リリカルでポップな楽曲が並ぶ。当時、ビートルズの4人の中ではその思想と行動がいちばん日本の社会には歓迎されておらず、『Imagine』だって話題にならないよう配慮されていたものなぁ。
豪華ブックレットの最後には小野洋子が“Only people can change the world”などと書いているのだが、「Only people」からとった1973年当時のはなしだよなぁ? 古いアナログ・カセットしか持っていなかったのと単純に安かったので、リマスターを機にボーナス3曲入りのEMIのUK盤を買ってみましたが、普通のCDDAだった。
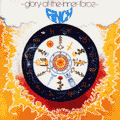
Glory of the inner force/Finch
オランダものを二つほど。フォーカスからエキセントリックなヨーデルとクラシック趣味を取り除いたような淡白で叙情的なジャズ・ロック、フィンチの1stアルバム。全曲インストなところも潔い。全曲をニムヴェーゲン(Joop van Nimwegen)なるギター弾きが書いているワンマンタイプの楽団だったようだ。ナチュラルなトーンで弾きまくるタイプで、洗練というよりは情熱的に押し捲る。長曲4曲も構成と展開の妙で聞かせるというよりは、勢いと情感に訴える。テクはそれなりで跳ねまわる。リズム隊はフォーカスより良いな。ときおり聴かせるマイナーでド演歌調の人懐っこいメロディ、背景のメロトロンが心に響く。
ボーナス二曲(「Colosus part1,2」)は同名映画のサウンドトラックだったらしいが、これはシングルで出たものらしい。インスト曲なのだが。
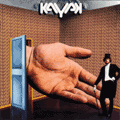
2nd/Kayak
メロディ・メイカーとしての面目躍進著しい2ndアルバム。全員オランダ人ですが、環北海文化圏とでも云おうか、イングランド、ノルウェイを含めた三王国ものは、内容的に非常に近しいものを感ずる。田舎臭い非洗練は上述のフィンチと同じだが、こちらは短曲の歌ものが中心。歌詞はすべて英詩で、かつとてもわかりやすい。9分超えの長曲もあるが無理やりフェイドアウトで縮めたような中途半端な感は否めない。もちろん最大の魅力はピアノとメロトロン(キーボードが二人でメロトロン専任がいる)の上を駆け巡るこしゃまっくれた癖のある美麗メロディにあるのだろうから、そういう方向は望むべきではないのだろうね。95年のオランダ盤リマスターはシングル曲一曲ボーナス入り。
しかし、まぁ、当時のオランダもの全般にいえることだが、直截的で趣味の悪いジャケットだねぇ。

Vielleicht bist du ein Clown?/Novalis
絵画シリーズを止めてデザインはヒプノシスになったけれど面白味には欠けるな。同時にノヴァーリスの詩の引用も止めて、一つの転機になった六作目。ラストの「Die Welt wird alt und wieder jung(世界は老い、また再び若返る)」の歌詞がシラー(Johann Christoph Friedrich von Schiller 1759-1805)の引用と記述されている。それなりに当時のドイツで流行っていたようで、2曲目「Zingaresca」はTVシリーズのサントラとして使われていたそうだ。フレート・ミュルペク(Fred Mühlböck)の才能全開で大活躍。曲の出来もコンパクトでタイトで高質です。かつてのなよなよした夢見心地は失われましたが、リリカルでメランコリックな湿度は変わらない。「Der Geigenspieler(バイオリン奏者)」、「City-Nord(北の町)」なども平凡だが心に響く味わい深いものがある。
シラーといえばその詩「歓喜に寄す」にベートーベンが曲をつけて「第九」になったのだが、ヤーパンでは知られているのかどうか、元はドイツ啓蒙主義の理想主義的革命詩です。この度はとうとうEUの“国歌”にまでなるそうでめでたいことです。もう一つおまけ。有名な話しだが、太宰治の「走れメロス」はシラーの詩「Die Bürgschaft(担保)」を翻訳したもの。
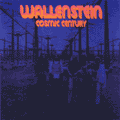
OHR 70032-2
Cosmic century/Wallenstein
シラー繋がりでもう一つ。ヴァレンシュタインの三作目。ヴァレンシュタインはそのままシラーの戯曲「Wallenstein, Ein dramatisches Gedicht」からとったものだろう。中身は30年戦争の実在の武将アルブレヒト・フォン・ヴァレンシュタイン(1583-1634)の悲劇を描いたもの。シラーは評価も高いが、こちらのヴァレンシュタインは今一つ玄人受けしない。
ユルゲン・ドラーゼ(Jürgen Dollase)というキーボードのおっさんのワンマンに近いユニットのようです。初期四作以降はメンバー総入れ替えで80年代最初くらいまでポップしていたそうです。ドラムが後のアシュラのハラルド・グロスコプフ(Harald Großkopf)だったり、今作から加わった専任バイオリン、ヨアヒム・ライザー(Joachim Reiser)が、ドラーゼのピアノ、圧倒的な音圧のメロトロン、ソリーナと相まってリリカルでメランコリックな世界を紡いでおります。それなりの疾走感などもあったりするのだが、個人的にはヘロヘロした締まりのなさがとても好みだったりする。バックにいるディルクス(Dieter Dierks)+カイザー(Rolf-Ulrich Kaiser)はベルリンのオール、ピルツ、コズミック・レーベル辺りの立役者。しょうもないジャケットはどっかの無線基地。張り巡らされたアンテナ線の支柱の下で羊がへろへろ草を食っておる。