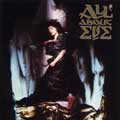
All About Eve/All About Eve
そういえば『イヴの総て(All about eve 1950年)』などいう映画もあったが、関係があるのかどうかは知らない。ミッションの『God own medicine』『Children』あたりでバックコーラスしていたのが紅一点のジュリアンヌ・リーガン(Julianne Regan)。イングランド北部、ヨークシャーのリーズ出ということで、シスターズやミッションと同郷。ウェイン・ハッセイ(Wayne Hussey)の名前もちらほら見える。プロデュースとストリングズやリコーダー入れてるポール・サムウェル-スミス(Paul Samwell-Smith)というのはあのヤードバーズの人なのだろうな。
儚く沈みがちのゴシック調トラッドとでもいえばよいか。メロディアスだが類型的なロック風の曲よりも持ち味はアコースティックなトラッドに顕著だろう。声質も歌謡曲風のゆったりとした曲の方が合う。ウェイン・ハッセイが女だったらこうなるのだろうねぇ。ほぼ全編リーガンのエレガントな魅力を全面に押し出して、ほの暗い耽美と寂寥感を情感豊かに謳い上げる。

French kiss/Bob Welch
中身はおもしろかったが、売れ行きはさっぱりだったパリ(Paris)を畳んで、新規巻き直しのソロ一作目。ようやく世間に認知された。二匹目のドジョウを狙ってもう一枚同じ路線で出ていたようだけれど、続かなかったねぇ。その後どうしたのかは全く知りませんが、かつてのマック(Fleetwood Mac)の正式メンバーとして認めてくれないとか、いろいろ物議を醸し出す人だな。旧スペイン領ロス・アンヘルス生まれのアメリカ人らしいですが、60年代にリビエラあたりで修行したそうで、そのあたりがこの(本人はいかしてると思っている)外面に繋がっているんでしょう。舌をレロレロするのを、なんでフレンチキスというのかは知りませんが、まぁ、当たらずとも遠からずなタイトルにはなっているんでしょう。コケティッシュでカラフルなポップスに仕上っております。
冒頭、「Sentimental Lady」のアレンジ違いはマックの『Bare tree』のアコースティックな素朴感の方が良いかな。
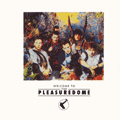
Welcome to the pleasure dome/Frankie Goes To Hollywood
今は無きバブルの徒花、ZTTの看板。飛ぶ鳥を落とした「しゃっちょう~」って感じの社長トレバー・ホーンについては何も知らないが、2ndよりもずっと生きが良くて明るい当時は2LPだった1stアルバム。熱帯植物園の大ドームでの実況のような雰囲気からそろりそろりと始まる極楽総天然色エンターテイン、カリギュラの園ってところですか。個人的には乱歩の大暗室のような雰囲気の方が好み(似たようなもんか)ですが、彩度の高い色が感覚をくすぐる。バブル前夜という浮つき始めた世情のなかで、ちっとも流行った記憶はないがファンキィでアンビエントで妖しい。意味不明な公案が一つ。
導師に厳粛に問うた
「仏とはなにか」
導師は草履を脱いで、頭に載せ、歩み去った
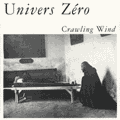
Cuneiform
Rune 155
Crawling wind/Univers Zéro
1983年に日本のレコメンレーベルでのみ発売された12吋EPに、ライブ3曲を加えてCDで再発された未発表音源。ライブはベルギーとドイツで収録されたもののようですが、是非一度見てみたいものだ。冒頭「Toujours plus à l'est」は『Uzed』ばりの畳みかける変拍子リズムと、主導するクラリネット、幽玄を思わせるバイオリン、ピアノの間奏が美しくも鋭利に決まる。歓喜を思わせる長調が珍しい。既に研ぎ澄まされたセンスとそれを支える精確無比なアンサンブルは真似ができない領域に達している。工場で寸分の狂いもなく穿孔し続ける機械のような黒光りする冷徹。豊潤なまでの完成度の高さには言葉がない。
後半ライブもドラム・ベース入りの室内楽といった趣で、静謐さと狂おしいまでの強迫感が混然と襲いかかるようだ。演奏が終わって入る拍手はクラシックのコンサートみたいだねぇ。
スリーブ写真はケルテス(André Kertész;1894-1985)の「修道院にて」。

See see the sun/Kayak
知名度のわりに意外にデビューの遅いカヤック、1stアルバム。コンパクトでポップなものから複雑な構成とクラシカルな抒情性までいろいろだが、共通点はメロディの良さだろう。同じオランダのアース&ファイアと同じく冷湿だが、ボーカルが男でそれほど特徴的でないから余計地味に聞こえるかもしれない。屋台骨は後にキャメルのキーボードに抜擢(別にキャメルの方が上だとは全く思わないが)されるトン・シェルペンズィール(Ton Scherpenzeel)なのだが、ピアノ、ハープシコードからメロトロンまでクラシックに裏打ちされた華麗で上品なセンスが特徴です。長曲でも8分ほどですが構成、展開と転調が既にカヤック節を形作っている。
ジャケットは73年6月の皆既日蝕の金環蝕の瞬間らしい。黒い下敷き?フィルム? を透かして見るのは世の東西を問わず同じなのか。
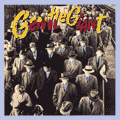
Civilian/Gentle Giant
12枚目の正規スタジオ盤最終作。変拍子と転調を減らしてよりメロディアスに、よりポップにファンクに転換を計ったが見事に失敗した。決して内容が悪いわけではないのだが、まぁ、本人たちも一生懸命、簡単に、普通に弾こうとしたんだろうが苦労しただろうなぁ。どうも妙な雰囲気になってしまうのだな。本シシャモにカペリンって名前付けて売っているみたいな居心地の悪さ。中身もほとんど皮肉と反語で、嫌気がさして辞めてしまうのもよくわかる。
ラスト(のボーナストラックの前)には「That's... All... There... Is....」というほんの数秒?の曲?が入っている。これはこのアルバムの3曲とボーナスの「Heroes no more」の歌詞から単語を抜き出して繋ぎ合せたものらしい。「どうってことないさ、ただそれだけのことだ」といって、消えていくなんて最初から最後まで楽しませてくれるじゃないか。
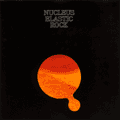
LINAM RECORDS
LMCD 9.00688 O
Elastic rock/Nucleus
トランペットのイアン・カー(Ian Carr)を中心とするジャズ寄りのジャズロック。ジャズがわかるほど耳が肥えていない田舎の粗忽者としてはありがちな、後にソフト・マシンを禅譲されるカール・ジェンキンズ(Karl Jenkins)、ジョン・マーシャル(John Marshall)あたりの繋がりで聴いてみたというわけ。ソフト・マシンがロック側からのジャズに接近したのに対してちょうど逆方向ですね。そういや、ギターのクリス・スペディング(Chris Spedding)もそれなりに有名だね。ここでも精密に冴えたフレーズが冷たい輝きを放っております。総じて、ジャズの人間のロック寄りのアプローチだからトーンは抑制気味でかつクールです。1stアルバムにして、冷えた緊張感とよく練られた端正な構成がジャズロックの完成形の一つを作り上げています。半分以上の曲を書いているジェンキンズの曲では既に後期マシンでのキーボード反復リフの原型が聞けたりします。まぁ、こっちが元祖だったのだろうが。
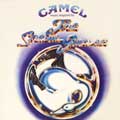
The snow goose/Camel
デビッド・ベッドフォード(David Bedford)指揮のオーケストラ付のトータル・アルバム。ポール・ギャリコ(アメリカ人;1897-1976)の短編小説『白雁』がテクストになっている。一般的には『ポセイドン・アドヴェンチャー』が有名なんだろうけど、得意? の動物ものよりは『幽霊が多すぎる』みたいな方がおもしろいかな。キャメルの方も製作時期を考えれば内容的な新味はまったくない。すんなりと入ってくる気持ちの良い穏やかさと、グレートマーシュ(The Great Marsh;モデルは北米マサチューセッツ北東の沼沢地帯と思われ...)のくすんだ心象風景が最大の特徴です。元々、歌が上手くないから全曲インストというのは良い選択だし、キーボードもギターも煩過ぎず地味過ぎず程良く中庸にまとまった。曲の構成、展開、アレンジ面での進歩はベッドフォードに依るものだろう。

Il concerto 1979/various
病床に臥していたアレアのデメトリオ・ストラトス(Demetrio Stratos)の支援のためにマウロ・パガーニ、クラウディオ・ロッキ(Claudio Rocchi)等によって企画プロデュースされた'79年6月14日のミラノでのライブ。前日にストラトスが死亡したため支援は追悼に切り替えられた。LP2枚組でかなり編集されていると思われるが、16組くらいが各一曲(Areaだけ2曲)づつ収録されています。カンタウトーレから現音まで、知っているのも知らないのもありますが、ブランデュアルディの「Il funerale(葬式)」、バンコの「E mi viene da pensare(湧きあがる思考)」、そしてもちろんラストのストラトス抜きの「L'internazionale(インターナショナル)」あたりが心迫るものがありますな。もっとも演者も聴者も湿っぽい雰囲気はまったくないところがプロフェッショナルで良いな。
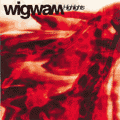
Highlights/Wigwam
フィンランドのウィグワムの69~77年のコンピ盤。70年代前半にはペッカ・ポホヨラ(Pekka Pohjola)にユッカ・グスタフソン(Jukka Gustavson)と、現代のフィン人ではリーヌス・トーバルズ(Linus Torvalds)の次くらいによく聞く名前が在籍していた。瞬間的ではあるが、Virginあたりから世界デビューも果たしたはずだ。日本でもポホヨラのソロも含めてLPは出ていたと記憶している。2000年代に再編、新盤が出ています。このコンピは7枚のアルバムとシングルからほぼ平均的に抜き出された全19曲。74年くらいを境に音楽性が大きく変わります。前期はウィットに富んだ緻密なジャズ・ロック(というとカンタベリィみたいだが)、後期はボーカル主体のポップ・シンフォ。少し北欧色が強まるかもしれない。どちらもテクニカルなアンサンブルが身上だが、糞真面目に突っ走ったりせずに、抜きどころを心得ているようなユーモラスなかわし方が見事だ。
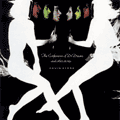
The confessions of Dr.Dream and other stories/Kevin Ayers
ソロになって5枚目のアルバム。前後で作風が変わる(豁然大悟したんだろう)転換点でもある。以後パートナーになるオリー・ハルソール(Ollie Halsall)がゲストで参加。他にも有名処だと、毎度お馴染みラトリッジにオールドフィールド、ニコになんとマイケル・ジャイルズまで豪華絢爛、雨あられ。
前半はコーラス入りの脳天気でふわふわ、でのりのり。後半はラトリッジのオルガンとニコのボイスが宙を舞う暗鬱な組曲。ジャイルズの精緻なドラミングが冴えております。ラストはライブでも定番の「Two goes into four」で締め括り。なんとも単純な曲なのだが、風に乗って流れればいいじゃないかという突き抜けた悟入感が気持ち良い。
「Two goes into four(2が4になる)」
2が4になる
2倍以上にはならない
2が4をつくる
青も緑になる
ほとんど見たことはないけれど
梅毒だって緑になる
夢見たことでこんなに遠くまでやってきた
人生は輝く星のようだ
罠にはまった瓶詰めだけど
さあ、いこう
風にのって
心を解放して
スタートしよう
ちったぁ、ましになるために
所有音源はBGOのリマスターですがこれがまた凄い。プラケースに貼りつけられたシールには「オリジナル・マスターからリマスター」、「スリーブノートを追加」、「完全再現アートワーク」と書かれておるのだが、実態は「カセットテープと違わない痩せたリマスター」、「曲名以外すべての情報が完璧に捨象されたスリーブ」、「表ジャケ以外すべてのアートワークを割愛したデザイン」とすべてにおいて大嘘です。ここまで徹底的なのも珍しい。あっぱれ、あっぱれ。

Caves/Ollie Halsall
パトゥ、ラトルズを経てテンペストの二代目(初代はアラホ;Allan Holdworth)ギタリストというよりは、ケヴィン・エヤーズの楽団での黒子(でありながら右腕兼屋台骨)ぶりが印象的なオリー・ハルソール唯一の個人名義音源。1992年薬物死の既に故人であります。おそらくデモ程度に録り溜めた編集盤といった内容で、作曲に加え一人ですべての楽器をこなして1979年に録音、1999年にリリースされています。味わい深いというか、スルメのように噛めば噛むほど味が出る人で、堅実な職人芸も然ることながら安定感のある渋みが良いのぅ。
あらゆる意味で業界では恵まれなかった人ですが、ラトルズでのひょうきんぶりも忘れがたい。この人が亡くなってからエヤーズもすっかり新作出さ(せ)なくなってしまった。
ジャケ絵(エッチング?)は「マジョルカの洞窟」なるハルソール自身によるもの。

K'cou chat vol.1/架空舎
さて架空舎である。「K'cou chat」は架空舎をフランス語読みにしたそうである。ちょっと辛いな。また、vol.1とあるがvol.2があるらしいという情報はない。本多るみなと岡根谷薫という女性デュオ。弛緩した覇気のない(これは重要)透明な声とピアノを中心にした演奏で学芸会路線を突っ走ります。おまけに「フニクリ フニクラ」をフランス語で歌ったりしています。本多によるモノクロ写真と手作り風のアートワークを見ていると、日常の狭間にすっぽりと落ちこみながらも、その日常に同化できない瞬間を感じてしまうやるせなさみたいなものが伝わってくるか。その表現の方向性が社会の病理に迎合せざるを得ないのは仕方ないとしても、名前が日本語なのは今となっては探し易くて便利。
ヘタウマというセンスが受け入れられる場合、高度な趣味性の極致としての手遊びという側面と、単なる同類愛的卑近感という側面があると思われる。昨今のあらゆる場面に進出し氾濫するマスコットやキャラクター類はもちろん後者としての戦略で使用されているのだろう。いい歳こいた大人が「ちゃん」づけで呼び合ったりする社会は世界的にも稀だと思われるが、そんな関係性が大人相手の商売に「かわいさ」が有効な土壌を醸成しているのだろう。
ヘタウマというか社会全体に広く敷衍している一種の幼稚感覚、あるいは一歩進んで子供社会化は、結局ずいぶん頑張って壊すものは壊しちゃったけれど、実は大人になってもそれに代わる何の文化も生み出せなかったということに起因しているのだろう。強いていえば、毎朝、命が危ないわけでもなし、好んでいるわけでもない(と思う)のに、自ら進んで粛々と一糸乱れなく遂行されている“通勤”という参加者数千万人の壮大なマスゲームなどを傍観していると、これはもう実利を越えた文化としか云いようがないな、と思うこの頃。
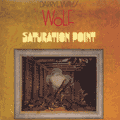
Saturation point/Wolf
世評は高いウルフの2nd。曲の出来は1stに譲るが歌入り曲が減ってアンサンブルの展開と構成はすっきりしたかもしれない。ウェイ(Darryl Way)のクラシック志向とエサリッジのジャズ志向は相変わらずで、どたばたしたロックっぽいリズムと相まってわけのわからない中途半端さ(一応、褒めている)は他に類をみない。ウェイのバイオリン、ビオラの響きと裏打ちされた素養は他の同業者と比較して抜きん出ているとは思うが、逆にいえばクラシックの域を抜けられていない。エサリッジのギターが勝手に指が動いてしまうようなフレーズを連発するのに対し、ウェイは譜面見ながら弾いているようだ。ソロを交互に取るような展開でも妙な温度差が生じているように思える。コンパクトな曲が増えたがウェイの特質を生かすには後半のようなある程度長尺曲が必要だろう。
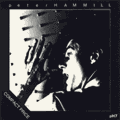
pH7/Peter Hammill
何枚目なのか数が多過ぎてよくわからない70年代ラストのソロアルバム。既にVdGGはなく以後は完全にソロ作品のみとなる。3~5分程度の小曲による構成で、アコーステックで敬虔なものから冷笑的なパンクに近いものまで趣向はいろいろ。一部の管楽器とバイオリンを除き、おそらく楽器類ほぼ総てを自前で処理している自家録音の模様。ドラムもリズムマシンが多いかな。ハミルにしては意外に外向的(社会的ともいう)な内容なのだけれど、それとpH7の関係はわからん。次作『Black box』でけっこう方向性が明らかになる、暗めのかなりえぐいシンセの音が特徴的でおどろおどろしい。
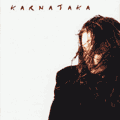
Karnataka/Karnataka
ウェールズのジャンル横断トラッド・ポップ。微妙に変拍子だったり、コード進行の特異さとか音響的な味付けがおもしろい。もちろん売りはレイチェル・ジョーンズ(Rachel Jones)のけっこう珍しいタイプの謳い上げる情感なのはいうまでもない。洗練とは程遠い素朴さが潔い。この1stアルバムは、8トラックの自前録音だそうでミックスのバランスが悪いうえ、音場の広がりもない。内容に対して設備が貧弱過ぎるのだが、中身がないのに過剰装飾でこてこてに塗りたくったものよりは遥かに聴き応えがあるというものだ。
80年代;コクトー・ツインズ(スコットランド)>80年代後半;アイオナ(アイルランド+イングランド)>90年代;オール・アバウト・イブ(北イングランド)>90年代後半;カルナタカ(ウェールズ)
などとたいして意味もなく並べてみると、このマイナーな系譜はみんな田舎者であるところがおもしろい。
ウェールズ(Wales)はスコットランドと同じく、連合王国(U.K.)の一部を構成する形骸化してるけど独立国です。カルナタカというのは地名(インド南西部の州)なのか、アメリカ先住民のカルナタカ族? のことなのだろうが、えらく今風の公式Webには何も情報がないのね。