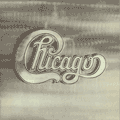
Chicago/Chicago
そう、爺の拙い記憶によればじゃ、昔は憧れてたのじゃよ。やっぱり。何を今更シカゴかよ、と思う向きもあるかもしれぬがの、「懐古」じゃからね。懐かしければ何でもOK! なんて何でもござれのコンセプトじゃない。ほっほ。せっかくだからノスタルジィに浸れそうなものをかき集めてみた。最初に買ったのは74年で当時発売されたばかりの『VII』。ロゴのデザインが気にいったというか、ずっと気になっていたから。その時点からの逆方向後追いですが、結局『VIII』以降は今でも聞いたことすらないというへそ曲がりな聴き方。元々、ほとんどがLP二枚組で、中にはBOX4枚組とかいうふざけたものまであって子供には非常に負担が厳しかった。レコード屋で「おぅ~」とかいって触るだけで済ましていたなぁ。
実質2ndアルバムですが、1stの時点では“Chicago Transit Authority”と名乗っていたため、1stアルバムみたいなタイトルになっております。たぶん25年ぶりくらいに聞き返して(これはCDだけど)みると、かつてはけっこうキツイなぁと違和感を抱いていたはずのブラス部分もへいちゃらだ。可愛いものじゃないか。今じゃ袋叩きに会いそうな、かなり濃い目の政治色とアヴァンギャルド・ジャズに走っている部分すら“うむうむそかそか”と包含できてしまうぞ。1stの直情径行が洗練されて音にも歌詞にも広がりが出てきた。組曲、長曲と新しい試みに対する意欲もおもしろい。
ライノ・レーベルのリマスタの解説では、有名な「25 or 6 to 4」の解釈に関して、オリジナルアルバムの解説や「革命」献辞と絡めたけっこう意地悪な質疑が加えられていておもしろい。作者のラム(Robert Lamm)は“それは一日のとある時間を示しているのであって、ソングライティングに関する歌詞だから深読みしないでね”とはぐらかしているのだが、確かにどうとでもとれる歌詞である。
「25 or 6 to 4(午前4時25、6分前;邦題「長い夜」)」
夜明けを待っている
言うべき言葉を探している
(反対側の)空には光が踊っている
目を閉じることは諦めて
床に足を組んで座りこむ
4時まであと25、6分
空中をやみくもに星(曳光弾)が飛ぶ
顔にはねがかかりそうに近づいてくる
目覚めた(生きた)ままでいたい
自分にできることなどどれだけあるだろう
もっと努力すべきなのか
4時まであと25、6分
眠ってしまえばよかった
回転する部屋(輸送ヘリ)は深く沈んでいく
言うべき言葉を探している
夜明けを待っている
4時まであと25、6分
薬物系サイケ・バージョンでもいいんだろうが、個人的にはベトナム・バージョンがいちばんしっくり来るな。もっとも、土足で踏み躙られたべトナム人からみれば、これだってお為ごかしに過ぎないけれど。と、今ならば振り返ることもできる。当時はもっぱら、好きな女の子が偶然シカゴ(というよりはロバート・ラムかな?)のファンで、彼女とシカゴの話ができるのが日々の唯一の楽しみだった。う~ん、健全だ。

EMI/Harvest
07243 538405 2 5
Barclay James Harvest/Barclay James Harvest
オリジナル盤全7曲はアシッド・サイケ風ビートポップとオーケストラ入りの田園クラシックが半々といったところ。二曲のオーケストラ・アレンジとコンダクトは後のイーニドのゴドフリィ(Robert John Godfrey)。ビートポップの方は R&B とビートルズあたりの影響が顕著だが、田園クラシックでは既に後のBJHを彷彿とさせる、穏やかなメロディと流れるような展開の原型を聴くことができる。既に当時から「ムーア(moor)で曲を書く四人のポップ・ボーイ」と称されていたようで、イングランド田舎趣味にあふれたトラッドとポップのニッチ狙いだったのかなぁ。もっとも本国ではあまり受けなかったようですが。
マスターテープの状態のせいかあまり優れたリマスターではないが、2002年の再発廉価盤CDは上記以外に初期のシングルにアウトテイクと全13曲のボーナス入り。EMIだからやばいかなと思っていたら(アングロ・サクソン向けに生産されたものだったらしく)普通のCD-DAでしたね。ブックレットもけっこう廉価盤にしちゃ豪華で、中にLP時のジャケット(写真はそれ)の表裏が縮刷されています。
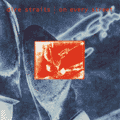
On every street/Dire Straits
おそらくスタジオ盤のラスト。ギター奏者:マーク・ノップラー(Mark Knopfler)のワンマン楽団だったが、おそらく映画音楽の作曲兼プロデューサ業が当たってしまって楽団どころじゃないよ、というかたちで自然消滅したと思われる。元々、つけた名前が“ダイア・ストレイツ=どつぼ”というぐらい苦労したらしいが、空前のヒットを飛ばした前作『Brother in arms』からインターバルが6年と業界の大御所みたいなかたちにまで登り詰めた。1stの「Sultans of swing」(注;別にイスラムの王の話じゃなくて、スウィングのサルタンというジャズ楽団がオーデションに落ちまくる話だと思う)が同業者の共感を呼んだだろうし、玄人受けもしたし、苦労人としての人の良さが認められたのだろう。渋いけれど良い味が出ていた。音楽的には前作の延長線上で、タイトだった前作に比べると若干メロウかな? 年輪を感じさせる。意外に長い曲が多いので、暮れ方にゆったりと七輪で鳥でも焼きながら聴くのがいいなぁ。
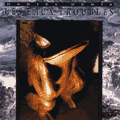
Les eaux troubles/Daniel Denis
内容的には90年代版ユニヴェール・ゼロといってよいソロ二作目。アンディ・カーク(Andy Kirk)からガイ・セガーズ(Guy Segers)、デェシェメカー(Dirk Descheemaeker)まで、ゲスト扱いだけれど顔ぶれもかつてのゼロを思い起させる強力な布陣となっている。奇数拍子の変拍子にもますます磨きがかかって、複雑怪奇でいながら微妙にツボに嵌まった「格好良さ」は既に芸術の域に達しております。非類型的で精緻で研ぎ澄まされた美しさは狂おしくも完璧。そのマイナーさ加減も超絶だが、本来なら歴史に名前が残ってもおかしくないだろうと思う。
ちょっとおもしろいところでは、「ブルガリアの空飛ぶ精霊の踊り」なるアクサク・リズム全開の民族色豊かな曲があったり、暗鬱なチェロがたなびく「ベルギーの歴史」、これまた全然楽しく踊れないアコーディオン民族舞踏「エレクトロニカ・マンボ・ミュゼット」までバラエティに富みながらも、硬質で明晰な芯はまったくずれることがない。
スリーブは黄金色に輝く蛙。ロダンの考える人のごとく方杖ついて何を考えているのだろうか。河童みたいだな。意味はよくわからないのだがタイトルは『濁った水』。
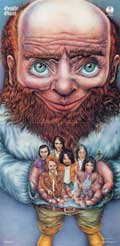
Vertigo
842 624-2
Gentle giant/Gentle Giant
イギリスの超絶滑稽熟練職人、ジェントル・ジャイアント(以下GG)の栄えあるデビュー作。GGの不遇はこのスリーブデザインにあったと思う。『Octopus』以前のいたずらにキッチュなデザインはどうにも感覚的に手を出したいと思わせない。まぁ、中身とのギャップも意図するところではあったのだろうが、この軽妙なウィットとユーモアとエンターテインがフィルターのように作用して、かえって素性をわかり難いものにしてしまっている気がしないでもない。
荒いけれど既にGGとしてのオリジナリティが確立されている1st。GGとしてのオリジナリティという表現はそのまま一つのジャンルを意味してもよいと思う。聞き込めばそれなりにリリカルだったり、ユーモラスだったりと伏線が張り巡らされた複雑な展開が楽しめる。10年ほどの間に出した10枚ほどのスタジオ盤の中では最もアヴァン・ガルドな風味に溢れたものかもしれない。質のよいミステリィを読むような、最後にピタっと嵌まる感覚は中期以降に譲るが真似の出来ない変態ぶりは最初から変わらない。
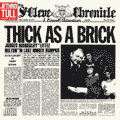
Thick as a brick/Jethro Tull
アコギに始まりアコギに終わるLP A、B面通しで44分全一曲。ただしどういうわけか全米 No.1 ヒットです。今じゃ考えられない時代だったのだな。小さなミルトン、弱冠8歳のジェラルド・ボストックの文学賞受賞作が詩『Thick as a brick(煉瓦のように分厚い=愚鈍とか“とんま”、バカ、アホ)』でその受賞を報せる新聞記事がジャケットになっている。LPは本当に大判の新聞紙を折り畳んだような変形ジャケで作られていた。もっともこのジェラルドは架空の人物で、新聞自体も記事から裏面の求人広告、犬猫求むに至るまで巧妙かつシニカルにでっち上げられた偽造というのがコンセプトの要。
脅威的な展開とこれまた決めの連続するテクニックに息つく暇もない、それでいてゆったりとまったりと歓喜に震え苦悩に打ちひしがれるクラシカルなブルーズ・トラッド。フルートと生ピアノ、ハモンドの織成す英国趣味の音のモザイク。いわゆる「超名盤」だから敢えて説明することもないと思うが、隙というか無駄のない完璧さと美しくもリリカルなメロディが素晴らしい。想いは遥かに遠く、高校受験の頃の定番で、耳がちぎれそうな寒気のなかで頭の中をぐるぐると「Do you believe in the day …」のフレーズが駆け巡っていたっけ。

Verve 8829522
Caravan/Caravan
カンタベリィのWilde Flowersを母体として、片方がソフトマシン、もう一方がキャラバンとしてデビューしたこれが1stアルバム。リマスタCDは前半にモノラル・バージョン、後半がステレオ・バージョン、ボーナス一曲入り。ステレオとはいっても単にリバーブがかかっているようにしか聞こえないものもあって、さすがに年代を感じさせるな。中身は意外に真っ当というかありがちなサイケ・ポップ。メロディアスでおとなしめ。後のライブの定番も多い良曲ぞろい。単なる歌ものでない心意気は認めるが、R & Bやトラッドあたりの影響もあるか。コーラス・グループみたいなヘイスティングス+R.シンクレアのボーカルもゆったりとたおやかで憂愁ですね。絶対にリードをとらないヘイスティングスのカッティング・ギターとソロを弾きまくるD.シンクレアのぶりぶりのオルガンが当時の(今もか)時代の主流との差異だったのだろう。
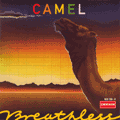
Breathless/Camel
その十年後、一曲目いきなり頭からキャラバンかよ! と思わせるキャメルですが、ラストの曲が「Rainbow's end」だって。たった今気がついた。もっとも内容は「君が虹の根っこを見つけ出せることを祈っているよ」という訣別の歌で、そのままバーデンズ(Peter Bardens)の脱退を意味するのだろう。それはそのまま、元気がないキーボードと元気いっぱいのギター・ソロが延々と続く曲があったりしてちょっとなぁ、というバランスが悪いことを意味し、内容的には前作に劣ると考える。シンクレアの曲と彼が歌えばまぁ、ほとんどキャラバンもどきになってしまうところが救いか。
また、メル・コリンズがゲストから正式メンバーになって管楽器の質が上がって出番も増えた。結果的に『アイランド』あたりのクリムゾンか、バッハ風の宮廷バロック趣味が増してそれはそれでおもしろい。総じて小品風の短曲のセンスは煌いているのだが、長い曲は普通の典型的なポップ・ロックになっちゃっているな。既に思惑や方向性がバラバラで、これをもって実質的にキャメルは瓦解した。
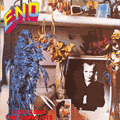
EG Records
0777 7 87019 2 7
Here come the warm jets/Eno, Brian
ロクシィを辞めた(正確には解雇)後のソロ一作目。今じゃ現代音楽の大家、繊細でセンシブルでスマートなアンビエントの始祖というのが一般的な評価なのかどうかは知らないが、昔はこういうことやっていたんですねぇ。70年代後半にドイツでクラスターとコラボレイトして来るまでは、ちょっと異様に陽気、微妙に安っぽくてキッチュなエロ・ポップ路線が3作ほど続く。元々、楽器が弾けない作曲家だったようで、サポートはロクシィからクリムゾンまでびっくりするような超一流どころが目白押し。
What does that title mean ?
『ほうら、温かい流れだよ』と、ネタ振りしてみたところで考えるまでもない。スリーブ写真を目を皿のようにしてよく見れば、トランプの中に答えは提示されている。どっかのWebでもわけわからん歌詞の解釈で揉めていたが、「nowhere to be」を「nowhere to pee」と聞けば意味は明解だとの解釈に諸手を打って賛成する。

Deram 844 767-2
Days of future passed/Moody Blues
それなりに有名な2ndアルバム。65年の1stは実質別ものということで未聴。この2ndは、うろ覚えだけれど、初のオーケストラ全面導入に初のコンセプト・アルバムというポップ音楽領域では前例のない偉業だったはず。当時「アルバム」というのは、それまでに出したシングルを量が溜まると寄せ集めて売り捌く時期遅れのお買得品でしかなかったわけだ。ということで、曲間無しでオケの間奏が入ったり、語りが挿入されて、トータル1枚で全7曲、夜明けから再び夜に至る一日というテーマに基づいた一つの作品というかたちが提示されている。また、オケとのバランスや、楽曲の出来、アルバムとしての全体的なアレンジも非常に水準高くまとまっていると思う。
ほぼ全面的に使用されているピンダーの弾くストリング系のメロトロンの使い方や、ギターソロじゃなくてフルートのソロが入っちゃったりするところなど、個人的にはかなり画期的だと思っております。ラストの「Nights in white satin(サテンの夜(?だったかな))」はシングルカットされて全英No.1だったと思ったけれど、今聞いても良い曲だ。ロックじゃないけどね。CDはかなりリマスターの状態が良くて音の分解能やクリアさは、とても67年の録音とは思えないレベルになっている。

Random Records
398.6580.2
Flammende Herzen/Michael Rother
『燃え立つ心』と題された77年のソロ。一応、2000年バージョンと称するようで、リマスターされて最近のリミックスが二曲追加になっている。ノイ、ハルモニア以降かなりの枚数のソロアルバムが出ているが、弱小レーベルのせいか入手性は非常によくない。よくある例ですがTVや映画音楽の仕事で食いながら、ぽつんぽつんと新作をリリースしている模様。これはソロの1stにあたり同名タイトルの映画(邦題;燃えつきた夢:非商業公開)のサントラ。表面的には穏やかで寡黙、その風貌通りの音なのだが窺い知れない底に秘められた凍りつきそうな意志が空恐ろしい。極度に抑制されたシンプルかつミニマルなギターとシンセ、ちっとも熱くならない精緻なビートを刻むドラムスによって構成された楽曲は極めて優しく美しく平滑だ。磨き上げられた氷のように透明に、ファイニンガー(Lyonel Feininger;バウハウスの画家、1871-1956)の「ゲルメローダ IX」のように空間の光が固着された静定力学。

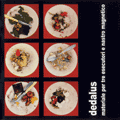
TRIDENT 1001
1975
Dedalus, Materiale per tre esecutori e nastro magnetico/Dedalus
イタリアのアヴァンギャルド・ジャズ・ロック、デダルズの1stと2ndのカップリングCD。世に出たのはこの二作のみと思われる。1stは華麗でクール、少しだけウェットなジャズ・ロック。ロングトーン・ギターとサックスが絡みあい、エレピとミステリアスな電子音が右往左往しておりまする。トーンが非常に抑制されていて寒々しい。
2ndのほうは「あぁ~、やっちゃいましたねぇ」という表現がぴったりの、最初から最後まで徹頭徹尾アヴァンガルド・インプロビゼイション。もごもご朗読しているのはベケット(Samuel Beckett;1906-1989)だそうだ。今風にいえば完全にアンビエント。突然貫入してくる童謡のようなメロディと背景の落差がゾクゾクするほどシュールだ。ちなみに皿に乗っているものは極一部を除き食いものではありません。 どちらも歌もの系のイタリア臭さは皆無の、あるいはジャッポーネでいう“イタリアン” とはほぼ180度正反対の、グルッポ7を端緒とするイタリア合理主義の嫡子なのだろう。

ESD 81342
Leg end/Henry Cow
これだけ書いていてヘンリー・カウが出てこないのはやはり不自然か。でもこちら側の闇は深く、見通しが利かない。俗に云う元祖レコメン。レコメン=Recommended という独立系レーベルなわけだが、太鼓奏者であるクリス・カトラー(Chris Cutler)がRIO(Rock In Opposition;後のレコメンディド・レーベル)を立ち上げるのは75年に変節した独立レーベル:ヴァージンに切られた後のこと。ケンブリッジの超ぼんぼん超エリートであるティム・ホジキンソン(Tim Hodgkinson)とフレッド・フリス(Fred Frith)によって組織されたのがその歴史の始まりとされる。そこに何故か一人だけロウアーだった闘士カトラーが加わったことにより、彼等は戦闘的ともいえる行動力を得たような気がする。当然のごとく左翼思想に極度に傾倒して炭坑ストの支援ギグなど政治活動に邁進したらしい。
ベースのジョン・グリーブズ(John Greaves)が76年の脱退後にNational Healthに参加していたが、カウ自体はいわゆるカンタベリィとはちょっと趣が違う。カトラーとデイブ・スチュワートが知合いだとか、所属レーベルが同じ新興ヴァージンだった復帰後の党員ワイアット(Robert Wyatt)やクーパー(Lindsay Cooper)あたりが被るのかな? 3rdくらいまでのソフトマシンの影響はあるだろうが、ラトリッジ(Mike Ratledge)はオクスフォードだから水と油。カンタベリィの穏やかなウィットとイングランド風洗練というよりは、研ぎ澄まされた怜悧、アンチ・イングランドとして積極的に外へ出ていった前衛、息苦しいまでのシリアスさが特徴で現音系チェンバーの始祖ともいえる。インプロとアレンジを通して、破壊と再構築の論理的実践といういわば音楽上の革命を目指したと考えて良いんでしょうか(かなり逃げ腰)ね? 1stということで荒削りな部分や構成に甘さや混沌もあるような気もするが、既にアンチ・ロックとしての完成度は極めて高い。いわゆるポップ系音楽の観点での評価を嫌うので普通の物差しで測っちゃいけないんだろう。カトラーの公式Webもあるんでちょと勉強しないと。
LPだった頃は『Legend』で邦題も『伝説』だったが、最近は『足の先っちょ』なのかぁ。

Polydor
835 230-2
ジャケ裏
Fairport convention/Fairport Convention
これ以下の三枚は読む前から自明であろうが、《あぁ、ジュディ・ダイブル(Judy Dyble)か》という観点が共通項になる。著しく詳細が不明で彗星のように現れて、きれいさっぱり足跡すら消して去っていった才女であるダイブルは、極めて上品な美人であったのだが何故か極めて徹底的に何らかの意志を持って抹消したとしか思えないほど写真がない。特に若い頃のまともな写真はまったくないといってよいのではないか? いいとこのお嬢さんだったのだろうか。
1stのフェアポートは後の電化トラッドというよりはR & Bやボブ・ディラン風アメリカン・フォークロックの影響が大きい。実際カバー曲も多いのだが若干サイケ風だったりするところに当時の流行りがみてとれる。男女のボーカルを立てているのだが、しっとりとした透明感があってよく伸びるダイブルの声はあまりロック向きではないなぁ。同じくボーカルでクレジットされているイアン・マクドナルドはイアン・マシューズ(Ian Matthews)のことでクリムゾンの人とは別人。紛らわしい。
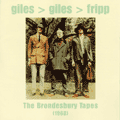
MISTER E
MRE01
The Brondesbury tapes(1968)/Giles,Giles & Fripp
不遇な男、ピーター・ジャイルズによる発掘? もの。フェアポートを辞めたダイブルが出した《ベース、ギター求む》という求人広告を見て、ジャイルズがコンタクトをとったことがクリムゾンの始まりというのはよく知られた話。おっとり刀でダイブルにくっついて来たぼんぼんイアン・マクドナルド(Ian MaCdonald)こそがアイディアと作曲、アレンジ、ついでに資金面での初期クリムゾンの立役者になるわけで、当時は誰一人考えていなかっただろう、このGG&Fとの合体が大袈裟に云えば歴史を変えたわけだ。個人的にはそのままクリムゾンのボーカリスト兼ピアノ、オートハープとしてのダイブルを見てみたかったなぁ。当時の広告や写真を見るとGG&Fは演劇トラッドみたいな(かなり恥ずかしい)ノリで売り出していたらしいが、その路線からは脱却したかったのだろう。
中身は基本的にデモテープレベルのもので音も割れてたり、ワカメになっていたりとリマスタでは救えない部分も多々ある。クリムゾンという名前がなければ誰一人振り向かない内容だろうが、全21曲中ダイブルが7曲、マクドナルドが残りの大半を歌っている。ちょっとキイが低いような気がするが、1stの「I talk to the wind」を歌うダイブルが渋い。
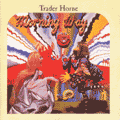
Catsle
CMRCD074
Morning way/Trader Horne
結局、マクドナルドとの破局がクリムゾンからの離脱につながって、ようやく自分の居場所を確保したというか、やりたいことができたのがこのトレイダー・ホーンなのだろうか? そしてこれをもって航跡はぷっつりと途絶える。引退したのだろう。マッコリィ(Jakie MaCauley)なる北アイルランド人とのデュオであるトレイダー・ホーンも、結局これ一枚ぽっきり。フェアポートの2002年の同窓会で歌ったらしいのが最近の唯一の消息。
ボーカリストとしてのダイブルは癖のない素直な発声、正統的できれいな発音、控え目で透明で柔らかい。マッコリィのマルチぶりも凄いが、曲間をつなぐダイブルのピアノやオートハープのセンスも素晴らしい。いわゆるトラッド・フォークのアルバムながら、テーマ、楽曲共にトータルな仕上りでイングランド滋味にあふれた優れた抒情性と空気感、そして何にも増してそのプログレッシブな先取性を称賛したい。