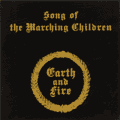
Song of the marching children/Earth & Fire
脱アイドル・ポップ化を図った二作目。18分強のタイトル曲を含めてバタバタした安っぽさが無くなって、前作とは打って変わった音の質感を堪能できます。怒涛のメロトロン。
「Song of the marching children(行進する子供たちの歌)」
壊れた封印の隙間から覗いて
わたしは人生の木、永遠をみた
枝は緑に茂り
人間の果実がたわわに実る
おまえは知らないふりを続けている
自分がなにになるのか
おまえは一旦縫いつけられて収穫されるのだ
それがおまえの行く末だ
壊れた封印の隙間から覗いて
わたしは行進する子供たちを見た
教会のすぐ隣りの門で
牧師は説教を読み上げる
おまえは知らないふりをする
どこの地獄に行くことになるのか
世界がどうなろうとも神はおまえを祝福する
(中略)
最後の審判はいつだ?
明日か?
明日なのか?
行進する子供たちの未来の墓に月桂冠を
行進する子供たちの未来の墓に月桂冠を
内スリーブの如何にも薬物依存系の原色SF絵そのもののぱっとしない歌詞の内容はどうでもよいのだが、個人的に理解不能なのは「アムステルダムの少年兵」という言葉がどこから湧いて出たのかということ。30年以上前の国内盤シングルの段階で既にこの邦題タイトルが存在したようですが、フラワームーブメント云々と関係があるのでしょうか。月桂冠(酒じゃなくてね)はわかるのだけど。手元にあるドイツ盤の再発CDを見る限りは不詳です。オランダやスイスはその手の薬物を法律で縛っていないせいか発祥地(ダダとか)にはなるけれど、そこ止まり。禁忌がないと人間頑張れないんだよなぁ。
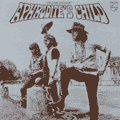
It's five o'clock/Aphrodite's Child
スリーブを見ればわかる通りのど田舎のポップという感じが濃厚な『666』の前作。彼等の基本的な路線はあくまでこの田舎ポップ(民族系ポップでもいいや、歌詞は英語だけど)であったわけて『666』が異質というか突然変異というか狂い咲きの徒花だったということ。パパタナシュゥ(Evangelos O.Papathanassiou=Vangelis)のキーボードアレンジとデミス・ルソス(Demis Roussos)のギリシアど演歌、ちょっとエスニックでズンドコなシデラス(Lucus Sideras)の太鼓が聴きどころですが年代物だからそれなりの内容です。当時、お国の状況が芳しくなくて既にフランスで活動していたようですが、汎ヨーロッパ風の如何にもなムードの曲を謳い上げるルソスの極甘ボーカルが売りです。よくあるキーボード・トリオといった形態ですが曲作りはさすがにセンスに溢れて気持ちが良い。
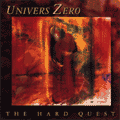
The hard quest/Univers Zéro
目がいっちゃってるドゥニ尊師、何を思ったのか零名義10年ぶりくらいの新作です。ドラマー主導型の楽団形態ですが、相変わらずポップともロックとも無縁なハイテンション・チェンバー。というのは一般解で実は逆説的にここまでポップなロックもないだろうと思わせる細密と極彩。形式としてのロック(あるいはロックといわれているもの)には最早何の感慨も興味も持てないし、単に懐メロとしか感じないが、Cuneiformという発行媒体を含めた表現行為に対する一種の楔は敬服に値する。馬鹿の一念岩をも通すじゃないけれど、アレンジの極みに登りつめている。畳み掛ける強迫グルーブ感というよりは研ぎ澄まされた余韻、法悦。昔は暗黒だったけれどランクアップして闇になった。
珍しく歌詞のある曲がある。歌うというよりは詠唱ですが。
「News from outside」
世界は不可解な遺跡になってしまったようにみえる
なぜあなた方の精神はそこまで病んでいるのだ
なにがわたしたちの心に勢いよく流れ込んで、
混沌に突き落とすのか
世界は混乱の遺跡になってしまったようにみえる
歪んだ魂は疑いを差し挟むこともなく、
他に道はなく、回避もできない
その深みだけがこの窮地からわれわれを解放することができる
始まりもなければ終わりもない
この業火、万物の唯一の源、がわれわれが不純物から本質を、
闇から光をを分離するのを助けてくれるだろう
われわれを底無しの穴から引っ張り上げてくれるのは誰だろう
世界は抑圧の遺跡になってしまったようにみえる
自分の尻尾を咥えている蛇「ウロボロス」とそれをつつむ炎。スリーブも炎につつまれる僧なのか。好きか嫌いかの感情論だけで物事が決まっていく思考停止社会には今更未来などないから関係ないけどなぁ。
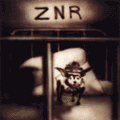
Traité de mécanique populaire/ZNR
エクトル・ザズー(Hector Zazou)+ジョゼフ・ラカイユ(Joseph Racaille)でザズー アンド ラカイユと。元はクリアライトのシリーユ・ブルドー(Cyrille Verdeaux)とのトリオでバリカード2(Barricade 2)と名乗っていたらしい。ちなみにZNRとしての1stアルバムが『バリカード3(Barricade 3)』。バリカードはバリケイドでそのまま5月革命以後、占拠、立て篭もりのときの防衛線のことだろう。椅子とか机とか積み上げることかな? 解釈が日本的過ぎるか。タイトルは『(人民)大衆力学概論』とした方が意味的にすっきりすると思いますがどうなんでせうか。しょぼいフランス盤なもんでたいしたことは書いてないし、その手の運動を経験したこともないもので詳しくは知りませんが。ぺらぺらと読んだ限りでは1977年の夏から12月にかけて音とイメージが練られ、マダム・ルイーズ・アルカザール議長の下に置かれたG.I.R.A(反駁芸術の国際団)の最初の公衆示威行動を成したとのことです。
などと書いてあると何じゃぁ? と思うけど、中身はとてもロマンテック(としか思えない)な、ほんの数十秒から数分の全19曲、ラカイユの象牙(アコーステック・ピアノ;昔は白鍵が象牙、黒鍵が黒檀)とザズーのエレピ、ベースによる美しくも虚ろに侘しいサロン・チェンバーです。派手さも奇を衒うこともないけれど絶妙な愛着を感じさせるセンスが素晴らしい。2ndである本作はほとんど生音で、表面的にはサティ(Erik Alfred leslie Satie 1866-1925)を継ぐものであったのかもしれない。中ジャケのアートワーク(これはCDのインナー)がいみじくもその音楽をよく表していると思う。

Picchio dal pozzo/Picchio dal Pozzo
カンタベリィだのジャズ・ロックの範疇で語られることが多いPdPですが、個人的には(あまり似てないけど、まだ)ZNRやサムラ辺りにより近い民族系アヴァン・ガルドと考えたほうがすっきりすると思っている。英米ものの○○に近いという表現は、単に英米ものに近似なら無条件で受け入れる土壌の特質を突いた販促だろう。一方、4人全員がパーカッションもこなす(ただし正規メンバーにドラムはいない)という意味や、PdP=井戸の中の啄木鳥、洞穴で叩くという名前からも彼等自身の狙いどころは一般的な認識からはかなりずれたところにありそうだ。リリカルだとしても感覚はカンタベリィのリリカルさとはまったく別物です。特にアルド・デ・スカルツィ(Aldo de Scalzi)の多彩なキーボード群が作り出す音場は斬新でいながら上品というPdPの屋台骨を支えている。多彩なジェノバ人脈のゲストも特徴的で、チェレステのペリーノ、ラゴリオに加え、アルドの実兄ニュー・トロルスのビットリオ・デ・スカルツィまで、聴かなくたってわかるほどの質は保証されているも同然だ。
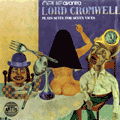
Lord Cromwell plays suite for seven vices/Opus Avantra
立て続けに4枚組BOXものがリリースされる昨今ですが、バラも出して欲しいのよねぇ。再評価の機運が高まっているのか、金に困っているのかは知らないが取敢えず入手は楽になったのは歓迎できることだ。クラシック系アヴァン・ガルドであるオプス・アヴァントラ二作目。Seven Vices(七つの悪徳[大罪? キリスト教徒じゃないもんで不詳])というのはGiotto di Bondone(1267-1337)のフレスコ画を観る限り絶望、嫉妬、背信、不正、復讐、浮気、愚鈍を表すものらしい。Lord Cromwellはクロムウェル護国卿(Oliver Cromwell 1599-1658)でイングランドに瞬間的ながらも共和制を実現した下院議員兼軍人兼清教徒のことだろう。でもってそのクロムウェルが「七つの悪徳」組曲を演じるという創作オペラをオプス・アヴァントラが作ったという解釈でよいんでしょうかね。ふぅ。で、このクロムウェルが誰をもじっているのか、とかになるとそれはもう理解の範疇外ということで日本盤?(あるの?) の解説でも読んでください。前作に比べればクラシックのフレーズが引用されたり、コンパクトにまとまった曲構成で聴き易くなったともいえる。歌の部分は意外に少ないのだが、ボーナストラックを含めて突き抜ける透明感とダイナミックな抑揚のソプラノと艶やかな弦楽器が演じる至高の美。
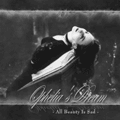
All besuty is sad/Ophelia's Dream
これまたクラシック系のユニットであるオフィーリアズ・ドリーム。もちろんオフィーリアはシェイクスピアの『ハムレット』の登場人物であり、ラファエル前派がこぞって描いた水死する美女のことを指しているのだろうな。ディトマー・グロイリッヒ(Dietmar Greulich)なるコンポーザ兼ピアニスト兼プログラマ兼デザイナの一人ユニットのようですが、完全に現代音楽系の作りでポップ系を期待すると思いっきり外します。ジュリア・ティージュ(Julia Tiedje)というソプラノオペラ歌手が歌っていますが、これまた完全に声楽です。ドイツやルーマニア、ロシア辺りのゴシック系のwebで紹介されていることが多いようですが、スリーブのイメージ通り暗い暗黒お耽美で一杯のネオ・クラシック。『All Beauty is Sad』、『Stabat Mater』という二作のカップリングCDのようで、デジパック豪華お耽美写真ブックレット(おまけ)付、ボーナストラック満載で75分ということなし。

Alla fiera dell'est/Angelo Branduardi
一気にカンタウトーレの頂点に登りつめてしまった三作目。カンタウトーレ(Cantautore=シンガーソングライター=自作自演歌手;日本語だけ微妙に意味が違いそうで笑)といっても数えきれないほどいるのだし、もちろん極めて一部しか知らないのでエラそうなことは云えないが、これは凄い。いきなり一曲目「Alla fiera dell'est(東の市で;素晴らしい邦訳がイタリアの歌のコーナーにあります)」、クラシックギターの静かな弾き語りがワンフレーズごとにありとあらゆる楽器が加わって怒涛のシンフォニック・アンサンブルになってしまう。それを5分の曲でやってのけるところ、鳥肌が立つほど格好良い。比較的ロックっぽいリズムとバロック風の気品ある管楽器アレンジが目立ちますが、恐ろしく生々しい音の良さと相まって風格まで感じさせる新鮮さが見事。マイナー調の曲は少ないのだがしっとりとした情感を表すのは本当巧いなぁ、何が違うのだろう。
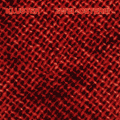
Zwei-Osterei/Kluster
天下のクラスター、堂々のセカンド。などというとお笑いですね。1stと同日に録音されたやっつけ仕事というと語弊がありますが、得意の即興パフォーマンス。前半はやっぱり説教朗読。前作の女性声に対し今度はおっさん声。前作よりほんの少しだけ張りがあって構築的で22分36秒。後半はインスト曲22分16秒でボーナスは80年のCluster+Farnbauer名義のライブ音源15分10秒と。晴れた朝、心地良い風を浴びながら、青と緑の景色を眺めながら今日も元気にクラスター。抑揚と高揚感のある宗教朗読とループの波状攻撃。メロディもリズムも無くひたすら無調ですが妙に抑揚があって意外にダレないところが摩訶不思議。勝手にループさせておくとすっかり生活の中に溶け込んでしまいます。笛の音が微妙に東洋的なのねぇ。

Novalis/Novalis
打って変わってドイツ浪漫派の中でもわかりやすさでは群を抜くノヴァリス二作目。アコーステックでムーディな1stに対してポップなロックに転換したともいえる。全体を包むトラッド風味の淡い青の色彩感が儚くも美しい。Novalis(本名はKarl Friedrich von Hardenberg 1772-1801)の歌詞が採用されたのもここから。その辺りのアイディアはこのアルバムだけに名前がクレジットされているカルゲス(Carlo Karges)という人に依ると思われるが、今となっては不明だ。再発CDのドイツ人の解説にはこの後、日本で大成功して五万枚以上を売ったと書いてある。おまけにヴェンツェル(Jürgen Wenzel)に代わったヨブ(Detlef Job)は日本人のファンと結婚したと書いてあるわ。はぁ~。そんなに売れていたとか流行っていた印象はないけれど、微妙なマッタリ感と親近感が当時の状況の中では受けていたのかもしれない。インストの部分は今聴くと古臭いし下手なのだけど、歌ものの部分の節回しは演歌に通づるものがある。
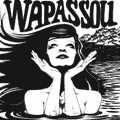
Wapassou/Wapassou
ついでにもう一つ、こっちはフランス浪漫派。リズムレス・トリオになる以前の自主制作2000枚プレスの1stだそうです。97年にMuseaから発掘されてCD化されてます。アマチュアっぽさがワパスーの売りだけど、さすがに契約には漕ぎつけられなかったようだ。ようやく二作目以降は当時モナ・リザと同じCryptoレーベルから出てましたが結局日本では出なかったので知名度の低さは如何ともしがたいな。頭の2曲はシングルとして出たボーナスでドラム入り。3曲目以降は如何にもワパスーといった感じのうろうろと漂うようなそこはかとなくリリカルな曲です。次作以降の構成的な大曲志向というよりは小品で歌入り、ドラム入りもあってこそっと可愛らしい。ギターの女の子も可愛らしい。基本はゴシックの荘重さではなくてロマネスクの武骨な温もりと湿り気です。
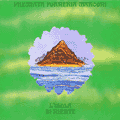
L'isola di Niente/Premiata Forneria Marconi
BMG/RCAの24bitディジタル・リマスタ、デジパック、両面きんきら金のCDでなんと7.99ユーロ(=1080円)というお買得。もっとも円盤一枚ぽっきり、30年も前の音源だから当然といえば当然のお値段ですね。『World became the world』のイタリア語盤ですが、「The world became the world」にあたる曲は入っていないし、歌詞の差し換え(「Just look away」→「Dolcissima Maria」)、曲順変更とけっこう違っていたりする。そのせいかアレンジは大枠同じ気がするが印象はかなり違います。タイトルはジャケ絵の通り『何もない島』。昔のLPには台風で一切合財押し流されたようなどこかの実在の島の写真が載っていたけれど、意味はよくわからん。一応、代表作だし質的にも文句の付けどころは無いでしょう。
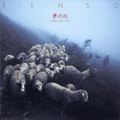
夢の丘/KENSO
J-POP(ROCK)を“街に溢れる残飯”と言って憚らない清水博士率いるケンソー、スタジオ盤5作目くらいです。そういうことが言えるのも業界に依存しない基盤があるからだろうが、筋の通らないことに対する忌憚のなさが小気味良いというか笑えます。公式WebにCDが一万枚くらい売れてくれないと……と書かれていたけれど、日本の現実っていうのはそういうもんなのか。ほいほいと。私が知っているくらい有名だからもっと売れてるのかと思ったらそうでもないの? あちこち噛みつくもんだからレコード会社も表だって販促しにくい面はあるかもなぁ。あるいは噛みつかれても下手糞!とか馬鹿!!とか言い返せないから確かに困るのかもしれない。どのみちマイナスイオン(?非液相大気イオン?クラスター?)と酸素で日夜健康と疲労回復に勤しんでいる無知蒙昧社会(というか宗教洗脳の行き渡った未開文明のレベルか)につける薬はないだろう。らしくなさが売りになってしまうということ自体が既に本末転倒。
清楚で精緻、熟練した江戸の簪(かんざし)職人か櫛職人の手捌きのような繊細な変拍子とテンション、もちろん格好良い。歴史や文化はこうして使えという良い見本だろう。キーボードが華やか過ぎとか生音の録音がフラットなのは金がないから? でも本当に(かつての)凝り性の日本人の作り出す音なのだなぁ。

Gila/Gila
初期ポポル・ヴフをフロリアン・フリッケと共に背負って立っていたコニー・ファイト(Conrad Veidt)がライブ・パフォーマンスを主体にしようとしていたらしいユニット。当人以外誰一人残らなかった2ndは中身も外面も実質ポポル・ヴフ化しているので目論見は外れたようです。この1stはアングラ・サイケ・ロック、2ndは宗教サイケ・フォーク+女性ボーカルといった感触で、どちらが良いかそれぞれのファン層が互いに他を貶し合う様は面白い。もっとやれぇ。『神秘』や『ウマグマ』の頃のピンク・フロイドから受けた影響は他の同時期のクラウトものと同じくかなり大きい方だろう。電子的なギミックとエスニックなリズムがもたらす陶酔感は、意外に直線的で構築的な迷宮を作り上げている。
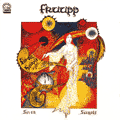
Seven secrets/Fruupp
30年ものですがそれなりに凝った作りで、バロック室内楽とフォークダンスとアイルランド民謡がごったになったような田舎臭い郷愁で一杯なフループの二作目。四作中ではもっともアコーステックで生音の響きが美しく、歌ものの比重が低いかもしれない。凝った部分はキーボードのハウストン(Stephen Houston)の曲に顕著ですがこの人のオーボエは良い味をだしている。食えるならば民族系クラシックをやりたかったのだろうなと思わせる思い入れと意気込みが感じられまする。音のバランスが良くないのだが、バックで茫漠と広がるチャーチ・オルガンの響きなども鳴っているだけじゃない情感を湛えているだろう。1st、2ndは生音の自前アレンジの室内楽ストリングズをかなり縦横無尽に入れているので今聴いている分には豪華な気がするけれど、当時はおそらくストリング・シンセとか使いたかったんだろうね。と、久々に引っ張り出して聴いてみて認識を新たにしてみた。
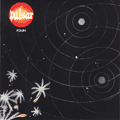
Pollen/Pulsar
デビュー作。キーボードの音が今一広がりに欠けるのだけれど技術的(金銭的)な制約があったのだろう。『Görlitz』あたりに比べれば音場の奥行きは雲泥の差ですが、それなりにその後の15年を予想させる内容になっていると思う。当時はこの1stと2ndだけ聞いていて、時期が悪かった3rd以降は完全に後追いです。とろんとした圧倒的な暗さは病みつきになるものがあるが、漆黒の闇というよりは朧夜の底。表面的にはまったく異なるが、カルプ・ディアンの1stとその内包するセンスが近いように思える。色があることはわかっているのに光量が足りなくて明暗しか判別できないようなもどかしさと曖昧さ。ぬめるような夜の海に漬かって流されているような安寧。
「Aspaisement(沈静)」
太陽の日差しが落ちた葉を温める
(隣りに座っている)暖かいきみの手が私の凍りついた心を慰めてくれる
まだ私の唇は味気なく宙をさまよっている
(寝転んで)沈んでいくからだの上を躊躇うように風が抜けていく
(見上げた)空を引き裂くような木の梢を忘れることはないだろう
熱い血のように流れる小川の水
苦い感情を忘れたこころの血のように
不安の縁で鳥が喚きたてる
霧のなかから聞こえてきた寒そうなフルートの音色を忘れることはないだろう
恐ろしくも鋭いピアノの調べ
(その音に)魅了されて夜の淵に私を引き摺り込む
陰気な百合が悲嘆にくれている大理石の道を(通って)
せっかくだからちょいと苦労してみたら意外に想像通りに近い線じゃないか。妙に散文的で文語的で淡々とした内容と間を補ってやらないと意味が通らない空隙。叙景的な描写と良くも悪くもないような心象が虚ろに響く。