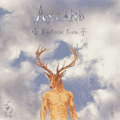
Esoteric poem/Asgard
ちょっとユーラシア・コンチネンタルにシフトしたからか、自虐趣味が反発を食らったのかあっという間にアクセス落ちますねぇ。どっちも何も真面目に考えているわけではないのだが、だって至極つまらないんですもの。逆立ちしても筋金なんか入っていないのだが、つまらなくて醜いものはとことん嫌いだ。ピックアップしているものは真っ当なルートで流通している正規リリース盤ばかりだし、値段も産業音楽の3割から8割くらいでコスト的には嬉しいし、決してマニアックという程のものではないと認識しております。
イタリア人のようだがドイツからレコードが出ているアスガルドのおそらくニ作目。アスガルドという名前は同名のものがいくつかあるんで混乱の元だ。一聴して、ドイツを通り越して北欧ものでも通るかもしれない。前半と後半で著しく曲調が異なるところが面白いというか、妙というか。北欧神話がテーマなのかどうか(基本的にそういうの苦手)よくわかりませんが、リズムレスのシンフォ風の雄大なキーボードとちょっとオペラ風の男性ボーカルで始まって、変拍子アンサンブル、ラストはマリリオンみたいなキャッチーなポンプに変異する。今風の音の良さを除くと英詩だしオリジナリティには欠けるが、涼しげでとろんとした広がりと奥行きが気持ち良い。
ちなみにジャケ裏には次作(『Arkana』)の予告が書かれておるという、一風変わった人達です。
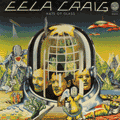
Hats of glass/Eela Craig
三作目。一曲目、「A spaceman came travelling(宇宙飛行士の帰還)」の怒涛の拡散感に綺麗に足元をすくわれて気持ちがよい。この迫ってこないで、ただもう広がっていくだけというトリプル・キーボードの作り出す空間が最大の持ち味です。専任ボーカルが入ってそれなりにポップになったとは思うけれど、もともと重暗いというわけではなかった。リズム廻りのしょぼさ加減も洗練とは程遠いが田舎だからしょうがないよなって云うレベルでしょう。個人的にはデロデロ弾きまくるギターがねちっこくて野趣に富んでいて好みだぞ。聞きながら読もうと 魚喃 キリコ『短編集』と川原泉『ブレーメンII』を準備していたのだが、ここはやっぱり宇宙ものということで『ブレーメンII』ですか。しかし川原センセ、この異様に場違いなアシさん誰ですか?

Pyragony X/Amon Düül II
75年くらいで一旦消滅したと思っていたら、そういえばこんなのがあったか。これはCDだけど原盤はいつ出たのかまったく記憶にないが、その名の通りIIとしての十作目ということなわけだ。いつのまにかすっかりベテランになってしまった。大手のUAレーベルを離れて(切られたのか)からは今一つ情報が不正確だったしプレス枚数も少なかったと思われ、よくわからないというのが正直なところ。『Made in Germany』が2枚組だっただなんてつい最近知ったわ。(←それはただの怠慢) 既にレナーテ嬢もおらずカーレル(Chris Karrer)+バァインツィエル(Johannes Weinzierl)にレオポルト(Peter Leopold)のおじさんトリオに若っぽい人二人という組み合わせ。オリエンタル風味の曲もあるけれど微妙にふやけたストレートなポップで面食らってしまう。
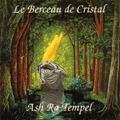
Le berceau de cristal/Ash Ra Tempel
ニコの映画を撮りつづけたフィリップ・ガレによる映画『水晶の揺りかご』のサウンドトラック。映画は未見だがもちろんニコに加え、ドミニク・サンダ、マルガレーテ・クレメンティとどっかで聞いたことのあるそうそうたる顔ぶれだな、こりゃ。75年の8月に南フランスのアルルとカンヌのコンサートでCanとニコに出会い、その縁で「夢を見るための」音楽を探していたガレと知り合ったと書かれております。
中身は元アジテーション・フリーのルツ・ウルブリッヒと二人で初期のギターシンセ大会をしておると。古いファルフィーサ(ファーファイサかね)オルガン以外はすべて「ノーマルでない」ギターのみで作られています。もっとも、毎度の官能丸出しというよりはずっと地味でアンビエントでミニマル風味だったりして求められたものをわきまえるところがさすがドイツ職人。
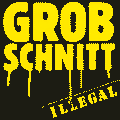
Illegal/Grobschnitt
一般的には初期以外は評価の対象外みたいな感があるグロープシュニットですが、80年代もけっこういけるのではないかと個人的には思っております。余裕綽々のエンターテインというか、わけのわからんノリ具合とブリブリのSE、笑えるリズムと短いながらも凝った曲作りが実に楽しい。こけおどしでなくアコースティックに決める大人の余裕もアレンジの円熟と相まって爽快で質の良い楽曲を作り上げている。年季が入ってるせいか英詩とはいえ、野豚くんのボーカルの表現力というか説得力の向上も目を見張るものがある。ふわっと浮き上がるような高揚感というの? 結局この人達(含浪漫派ドイツもの)が演じているのは、いろいろな要素がごた混ぜだがシラーの戯曲やワグナーの歌劇(あるいは楽劇というべきか)の現代版なのだろう。そういった歴史参照が許されるというか、優れたものを受け継いで、また次の世代に受け継いでいけるみたいな文化があるのだろう。なんだかちょっと羨ましくなってしまう。

Anyone's daughter/Anyone's Daughter
こってり気味で貫禄のグロープシュニットに対し、若いせいもあるけれど清々しい2ndアルバム。本質的な部分はけっこう似ている気がするのだが、こちらは癖の無いファンタジックな甘さとリリカルで端正なアンサンブルが特徴です。如何にも80年代風なのだが薄っぺらさは感じられず、むしろそこはかとなくドイツ浪漫主義丸出しの芯が匂うというか透けて見える。短い曲ばかり(最長8分)だが、それなりにバリエーション豊かな曲が統一された色彩感の下で緩急自在に繰り出されていくところなど老練だし、派手でもなく地味でもなく淡々と中庸をいくところが刺激には欠けるが玄人受けする由縁だろう。個人的には三作目以降のドイツ語になってからの方が(だって英語下手なんだもの)ローカル色が濃くて好みだが、80年代初頭にしては上出来の質と心意気。
しかし、このエニワンズ・ドーター、英語だと決して良い意味はないと思うのだが、どういう謂れなのだろう。
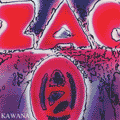
Musea
FGBG 4039.AR
Kawana/Zao
ザオ四作目は『カワナ』でござる。「ケイウォナ」とか言わないでネ。「純粋な意志」とか「明晰な概念」とかいう意味らしいですが、呼びやすくて大変けっこうでござる。ヨシコ・セファ(Yochc'o Seffer)なる管楽器奏者と巨漢のエレピ、フランソワ・カーン(François Cahen)が昔マグマにおったという意味で最も著名であるが、ベトナム混血みたいなドラム(Jean-My Truong)とか、こそっと地味なベース(Joël Dugrenot)もやたらと上手い。脅威的なテンションと上品で目くるめくリズムはザオの最高傑作との評価も高い。テクニカルな上品さがサロン風の貴族趣味に陥らないのはハンガリー人であるヨシコ・セファのソプラノ・サックスに依るのだろう。ハンガリー=フンの国なわけで、端的に云えば中央アジア騎馬民族のフン族の末裔なのだから、ジャズを下敷きにしているとはいえ、滲み出るエッセンスは意外に近しいものを感ずるのだ。ゲストのディディエ・ロックウッド(Didier Lockwood ;やっぱり元マグマだったりするのだが)のバイオリンとの掛け合いもスリリングで惚れ惚れするような出来映えなのだが、結果的に乗っ取られるようなかたちでヨシコ・セファは脱退の憂き目に遭い、ありゃりゃ。まぁ、世の中そういうもんだて。
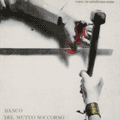
Come in un'ultima cena/Banco del Mutuo Soccorso
バンコ中期の代表作、というか前後は映画のサウンドトラックだったり、オーケストレイションだったり、世界進出盤だったりして中期の唯一作といったほうがよいかも。総じてコンパクトな内容で破綻もなく巧くまとまっている。熱く迸るエネルギーは洗練された展開にとって代わられて、大人しくなった印象はありますが全体の密度は上がった。歌ものと地中海民族調からスリリングなアヴァン・ガルドまでフルカラーの万華鏡。アルバムタイトルは『最後の審判のように』という意味でしょうが、当時の政治状況を引っ掛けたものでしょう。70年代初期に勃興したユーロ・コミュニズムは出る釘はこてんぱんに打たれる弾圧のもとで退潮期を迎え、その芽が育って再び日の目を見るのは80年代中期だったかな(あやふや)。

Senza orario, senza bandiera/New Trolls
言わずと知れた1st。1968年に出ているのですねェ。フォルムラ・トレと同じくビート楽団でしたがこちらのほうが歌もの風か。歌っている人(Nico di Palo)は変わらないからすぐわかる。全10曲の小品集ですがLPの両面各5曲は曲間が重ねられていて、実に自然に移り変わっていく仕掛けになっている。プロデュースはファブリツィオ・デ・アンドレ(Fabrizio de André)とジャンピエーロ・レヴェルベリ(Gianpiero Reverberi)。前者はカンタウトーレの重鎮にして隠者。後者は全盛期オルメのプロデューサであり実質4人目のメンバーだった敏腕プロデューサ。アレンジの斬新さと洗練はこのレヴェルベリに依るものと思われる。
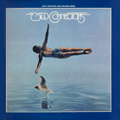
Wild connections/Jack Lancaster・Rick van der Linden
カヤックのプロデュースをしていた(ぐらいしか知らない)ランカスター(名前はアングロ・サクソンだな)とリンデン老(そんなに老けているわけではない、多分)のコラボレーション。生ドラムとコーラス以外は、ランカスターの操るLyriconなるフルセット管楽器シンセとリンデン老のYAMAHA GX-1シンセのみで製作されたと記載がある。と、たった今裏ジャケを読んでみた。歌無しの短曲ばかりで聴き易いといえばその通りだが、上手い人にありがちなテクに流れてしまう傾向は相変わらずですなぁ。ジャケのような濃密な夏の雰囲気はよく出ていると思いますが。ジャズからクラシックまでより取りみ取りですが、生ドラムがロックっぽくて浮いているかもしれない。

En regardant passer le temps/Carpe Diem
朧夜の底。あるいは水底のような月夜。霞んでいたり透き通っていたり。タイトルは『移ろう時を眺めながら』の意。とはいっても中身の諧謔というかシニカルさ加減は日本の文化とはほぼ正反対でリリカルとは云い難い。奏でられる音はほぼ全編墨色に統一されたトータルな作りといって良いでしょう。ちょっと形容しがたい摩訶不思議な、包み込むようなキーボードと絡み合うサックスが儚い。疾走感とリズムのテンションで聞かせるタイプだと思うが、冒頭にも書いたとおり何とも云えない抒情感がひたひたと漂う。初聴は76、7年頃ですがそのとき以来ずっと、今でも変わらず気に入っている。もうすっかりDNAの塩基配列に組み込まれてしまったようだ。
「Réincarnation(転生)」
私は生まれながらのロボット
とある研究所で
ある未来の朝、生まれ
すべての人間
大天使
夜の労働者にすら
服従するよう調整された
私は偶然に受け継いだ
合成された肉体を
そこにとある別の100年間を溶かし出す
幸福だが、貧しい音楽家としての一生を
プログラムされた事物の生成物を
破損した人間である主人に載って治療する
洗面ボウルに座り込んでの
酷く疲れる労働サービス
私は未来を予言できる
こいつの死の埋葬のとき、生の祝福のときを
数学の公式を用いて
酷く無気力に
私はカタログを描く
この自動式奴隷の
私の職務は指揮者
私は服従することができない
私の周囲に広がる
考えようとしない人間の身体
私は虚像を見る
不思議で美しい夢を
私は清廉な大天使の恍惚など
演じようとは努めない
私は少しばかり気の狂った
人間ロボットではないのだ
私は成長する必要がない
私は子供の経験をもたない
私は笑うことすら知らない
私の唯一のビジョンは復讐だ
「Jeux du siècle(100年の遊戯)」
共同体の
広場で
時間領域が
照射された
一日で
100年をつくる
時間が
逆さまに流れた
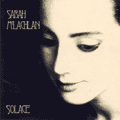
Solace/Sarah McLachlan
裏声になるところがめちゃめちゃ色っぽいマクラクラン。一応、二作目だと思いますが、このあとはお決まりのようにポップ化していくのだろう、深くは知らない。曲が良いのだからもう少し長い曲にして、フェードアウトでお終いってのは止めた方がずっと良いと思うのだが、いろいろ制約があるんでしょうか。ゆったりとした上品な情感が持ち味なのだけど、ボーカルだけに寄り掛からない姿勢が好感です。ただ前作はネオクラシックで綺麗にまとまっていたのに対して、今回は曲調がトラッド風、ジャズ風から今風までいろいろあって取留めがない。バグパイプ風の音やアコギと絡むトラッド風の曲の路線が声質にいちばん合っていると思うのだがなぁ。
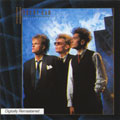
Goldene Zeiten/Hubert Kah
アイドル・ポップのようなダサいジャケ。中身はそうでもないので損してると思うのだけどなぁ。中身を知っていて初めて買えるジャケです。三作目らしいですがこれ以前はギター・ロック。次作『Tensongs』から英詩になりますが、ここではまだドイツ語。要は微妙な狭間にあるのだ。次作にも同じ英語テイクの曲もあったりするのだがアレンジ含めてこちらの方がメカニカルで良い。プロデュースとキーボードは後のエニグマのミヒャエル・クルトゥ。3曲目の「Engel 07(天使七番)」が出世作のようですが、ダンサブルでありがちなエレ・ポップ。世間的には「Angel 07」というらしいが英語テイクは持ってないよん。変にリズムを強調した曲よりもゆったりした黄昏た曲調の方が圧倒的に良いのだが。
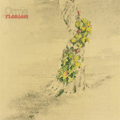
Florian/Le Orme
電気無し、完全アコースティックで耳を疑うオルメ。反骨だったんでしょうか。だったんでしょうね。バイオリン、マリンバ、アコギ、マンドリン、ピアノに木琴、ビブラフォン、そしてもちろん歌。最初と最後はチェンバーというかほとんどバロックの室内楽になっています。素朴でナチュラルだけど上品で技巧的。一つ一つの音の粒が丁寧に磨かれて、透明な流れに透けて見える川底の丸くて小さな光る石のようだ。流れは濁ったり澄んだり、澱んだり激流になったりするのだろうが底の石は変わらない。流されていくものもあるだろうが、その分は流れがまた運んでくるのだろう。本来、電気もコンピュータも無しで音楽を作るなんて当たり前のことなのだが、こう正攻法で真正面から迫られると困ってしまうところはあるかもしれない。生醤油だけで漬けたイクラみたいで化学調味料と添加剤に慣れきった舌が戸惑ってしまうのに似ている。
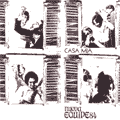
Casa Mia/Nuova Equipe 84
BMG/リコルディの廉価盤がうれしい60年代ビートものの突然変異。イ・ディク・ディクと同じく時代のなせる技か。前作『ID』とここらあたりが所謂プログ風の展開になっておるらしいが基本は歌ものポップスです。それでも妙に斬新なアレンジとそこはかとなく暖かく抜けた感覚の歌がほっとするように気持ち良い。リマスターされているのだろうが、切れのあるリズムと如何にもイタリア風なグランド・ピアノ、メロトロンの響きが郷愁を誘う。ビートルズがストロベリー・フィールズで使ったフルートのメロトロンもあったりして微笑ましかったりする。う~ん、この辺りもう少し追っかけてみようかなと思わせるこの頃でした。
一般的にエキペ84で通っているんですが、これだけNuova(=新)がつくのだな、なんでだろ。

Ceux du dehors/Univers Zéro
宇宙零第三作は緻密かつ高質なものになった。元々、レコメン一派として手抜きはないのだが、この張り詰めた緊張感とダイナミズムは筆舌に尽くしがたい。おどろおどろしさは若干緩和されたものの、強迫グルーブ感と変則拍子の奏でる暗く美しい暗黒チェンバーは唯一無二だ。黄昏色に染まる「魔女の石」のスリーブが正にふさわしい。実は日本でもけっこうファンは多いらしいし、フォロワーもいたりするそうだが、日常耳にする音楽からはある意味一番遠いところに位置しているよなぁ。めらめらと燃えあがる極北です。
たまには少し資料的な価値なんかも考慮したりすると構成はこんな感じ。
ミシェル・ベルクモン(Michel Berckmans);バスーン、オーボエ、ホルン
ダニエル・ドゥニ(Daniel Denis);ドラムス・パーカッション
パトリーク・アナピエ(Patrick Hanappier);ビオラ、バイオリン
アンディ・カーク(キール)(Andy kirk);ハーモニウム、オルガン、ピアノ、メロトロン
ガイ・セガーズ(ギュイ・セジュール)(Guy Segers);ベース
アルバムタイトルは『外なるもの』。曲目はこんな感じ。歌は無し。
1;濃密 2;首吊りの木の先端 3;おはよう、みなさん 4;戦闘 5;エリッヒ・ツァンの音楽 6;大がらすの頭 7;蝿の特技
5はラブクラフトの短編にインスパイアされたインプロ、6はD.Neukens(不詳)を偲ぶ葬送行進曲、7はCDのみのボーナストラックだそう。気分さわやかな朝礼や始業の合図に、ベイエリアを一望しながらの楽しいディナーの友に、特別養護老人ホームの機械浴のBGMに、おひとついかがでしょ。