
2/Neu!
昔はポリ塩化ビニルの無駄使いと言われておったが、今はポリカ(ビスフェノールAと塩化カルボニルの重縮合体:美味くのい)の無駄使いなのだろうか。半分録音した時点でスタジオを借りる金が無くなり、残りは以前出したシングルを回転数を変えてつっこんで埋めたというのは有名な話し。さすがにロータさん、そんなやり方はいくのい! とユニットは崩壊の危機に直面したそうです。今風に云えばremixという手法ですがね。「新しい」ことや「進歩的」なことに何ら価値を見出せなくなった今(それはつまり、ラベルを見てもそそられなくなったということ)になって、ようやく素直に内に響いてくる良い音じゃないか。
チャカッポッコ チャカッポッコ チャカッポッコ チャカッポッコ
チャカッポッコ チャカッポッコ チャカッポッコ チャカッポッコ
ぶちっ……CDなのに針が飛んだ
チコタコチコタコ チコタコチコタコ チコタコチコタコ チコタコチコタコ
チコタコブッ(また飛んだ)コ チコタコチコタコ チコタコチコタコ チコタコチコタコ
ズッタットット ズッタットット ズッタットット ズッタットット
ズッタットット ズッタットット ズッタットット ズッタットット
良い!無い!御意!如意! NEW!NÉO!NEU!のい!

Cœur de verre/Popol Vuh
ヘルツォークの映画『Herz aus Glas(ガラスの心)』のサウンド・トラック。なんでか知らんがアルバムタイトルはフランス語になっておる。映画は未見なのでなんともいえないが催眠誘導されたキャストが演じたらしい。映画なんだけどこの人の映画は社会構造上近年ますます映画館では“まず”見れないというのがおつですな。ちなみにかつてのクラウト系がテクノとかノイズとして市民権を得た今となって、ポポル・ブーの飽くなき神秘主義的恍惚感は暗黒チェンバー系と共に微妙に引かれてしまう(友達がいなくなるの意)ものの代名詞だな。車で聞いたりすると奇異感が極度に煽られて尚楽しい。中期の作ですが、一応電気も使っておるし、ドラム入りの曲もあったりして歌無しだが聴きやすい部類に入るだろう。ふわふわと漂うような奥行き感とあたりかまわず反響しまくる残響がきらきらと美しい。
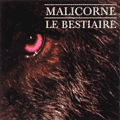
Le bestiaire/Malicorne
何作目かは知らないがどちらかといえば後期の作。トラッドと自作が半分ほどの割合ですが、いきなりファンクな数え歌のリズムにゃ目が点になってのけぞります。初期の野暮ったさはずいぶん洗練されてクールになった。電気を使ったリズムはかなりタイトで工夫されたノリが楽しめるし、うねるような重いベースとシンセ+古楽器の絡みが新鮮だ。一方、ほとんどア・カペラのトラッドでは、しっとりと濡れた冷たい情感がうろうろと漂うさまが美しい。非常に独特な(これを独特と形容せざるを得ないこと自体が異様なのだが)情緒性は健在です。人数が少し増えて7人になっていますが、グリフォンのクラムホルンの人が加入していたりする。おやまぁ。
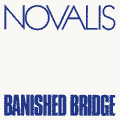
Banished bridge/Novalis
以降とは少し印象の違う1st。ギターのデトレフ・ヨブ(Detlef Job)はまだいなくてユルゲン・ヴェンツェル(Jürgen Wenzel)なる人がボーカル+アコギをこなしております。タイトル見りゃわかるように歌詞も英詩ですが、結果的にはキーボードの比重が高くてムーディでたゆとう感じがゲルマンの森を思わせる雰囲気。最初に聞いたのは3rdの後でしょう。今じゃ鼻で笑ってしまいかねないこの手のロマンティズムも子供心には真摯に響いたものだ。この懐かしくも切ない夏のイメージはとっくの昔に喪失した未知なるものへの憧憬であり、かつて経験したはずの、今となっては身体の細胞だけが微かに憶えている記憶のようだ。
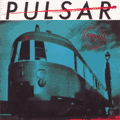
Görlitz/Pulsar
実は大好きなピュルサー、通算5枚目のフルアルバム。基本的な部分はまったく変わらないが、再編後の方が個人的には気に入っている。休止している間に、関連する技術の進歩が上手い具合にピュルサが紡ぎ出す音に追いついたというところか。正に水を得た魚のように、淡い、儚いまでの色につつまれた空気感は誰にも真似が出来ない境地に達している。洗練と円熟が音の良さと相まって、深い海の底のような、どこまでも青い沈静感が見事だ。個人的にこの手のフランスもののしっとりとしたちょっと可憐で冷たい甘さに弱いのだ。
「Görlitz(地名)」
その晩もまだ
望みは眠りについている
星々の望み
ある種のうわべだけの美しさ
眠れない夜に
闇は恐怖をつくり
心はあまりに壊れやすく
どこか遠い他の場所を探す
灰と黒のあいだ
いまだ海に雪が降りつもる
あまりにも短い夢の時間
橋を通過
ばかげた警戒もなく
悲痛とともに
きみは過去へと歩む
冬の月に向けた目の奥底の乾き
灰と黒のあいだ、
絶え間なく海に雪が降りつもる
青の中のすこしばかりの赤
それはきみのための新しい光
ただ火をつけられた9本のろうそく
それでも太陽のように魅惑する
最後の旅で、きみはひとり救いをさがす
きみの沈黙に忘却を歌う雨
雨に打たれる手、雨に打たれる手
今や、時は止まり
きみはゆっくりと解き放つ
こもった物音が頭に響く
本当に変わるものはなにもない
忘却を切望する
列車はおそらく明日には出発するだろう
とても短い記憶の熱情に
香りは失われ
きみの行く道に残される足跡
ゲルリッツを探す足跡
忘却を切望す
列車はおそらく明日には出発するのだろう
「夢の国へ発つ列車はいつでも準備できている」というA.Vialatte(仏現代文学)からの引用が元にあるようだが、これ以上は歯が立たぬな。ここでいう“きみ”とはジャケにもあるかなりレトロな列車なのだろうか。ピュルサの歌詞では二人称に近親者を示す“te”が多用されることもけっこう特徴的か。ゲルリッツは中世から栄えたドイツ東部の都市。WW2の結果、ポーランドが1/3ほど西に移動したので、かつては市街地を二分して流れていたナイセ川が国境になったそうです。可視不可視を問わず境界による区分は認識の根源的な要素というかそのものなのだろう。
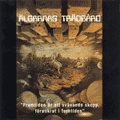
Framtiden är ett svävande skepp förankrat i forntiden/Älgarnas Trädgård
スウェーデンのアコースティック・トラッドもの。弦楽四重奏のピアノの代わりにシンセサイザにして、パーカッション(タブラとか)と管楽器を加えたような編成で、あっさり目のチェンバーみたいだな。当時2ndまで製作されたもののお蔵入りだったそうですが、さもありなん。電気もけっこう使ってますが印象がどうしようもなく生っぽく虚ろに暗い。最近のは詳しく知らないけれど北欧系でこの薄ら暗さはかなり珍しい部類。どろんと流したトラッドの部分と、VCS3が縦横無尽に跳ね回ったりしてかなりサイケでアヴァン・ガルドなところが特徴でもある。そういえばこのところ、スウェーデンのトラッド(というかコンテンポラリ・トラッド)はずいぶん日が当たっているようですが根っこは同じ気がする。
タイトルは“未来とは過去に錨を下した帆走する船である”の意。エルヤルナス・トレッドゴァールトと呼ぶのが発音上は近そうだ。
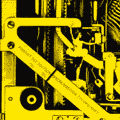
Produkt der Deutsch-Amerikanische Freundschaft/D.A.F
DAFの1stは2nd以降とかなり趣が異なる。メンバーも違ったかもしれない。汗と吐息の筋肉マン、ガビ・デルガド(Gabi Delgado-Lopez)はまだおらず、後にデア・プランになるシンセの人(Kurt "Pyrolator" Dahlke)が居たらしい。当時はほとんど自主制作みたいなかたちでリリースされたらしく、長らく入手不能でしたが今は普通にCD売ってます。ずいぶんと簡素なデジパックですが。中身の方は一曲としてタイトルがないのだが、22曲の切れ味の鋭い断片。歌無しの抉り込まれるようなノイズ。エアコンのびんびんに効いた暗~い茶店とかで周囲を圧倒する大音響でよくかかっていましたね。顔見合わせて目と唇のかたちだけで会話するのには良かったかも。
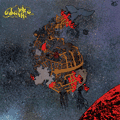
Landscape of life/Osanna
『Palepoli』の成功(いや、まぁ、売れたかどうかは知らないが)を受けて、国際進出を念頭に入れた4作目。既にイギリスでNovaを作っていた「おれたちゃヤルぜ組」と「ナポリに帰ってまったり組」であるチッタ・フロンターレに実質分裂状態。もっとも、夢破れて戻ってきた組とすぐに再編されて77年に『Suddance』、2001年にセルフ・カバーというかRimix風の『Taka boom』が出ています。一応全盛期のラストなのに評価が低いのは、英語タイトルに英詩まであるところか。暗黒どろどろ粘着していた前作に比べ、あまりに軽いというか媚びているロックンロール・バラードは確かに戴けない。一方、半分以上はかつての泣きのメロディに怒涛のメロトロンで粘着していてその落差が笑える。比較的歌もの要素が濃いのだが、鬱憤晴らしのようなボコボコしたリズム隊とヤケクソ気味のアンサンブルが疾走しております。しかしこの歌メロはやっぱりイタリア語だよなぁ。
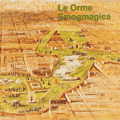
Smogmagica/Orme, Le
一般的にはポップ化を遂げた駄作と貶められてきた中期の始まり。専任ギターが加わって趣がちょいと変わってしまった部分もあるのだが、ターリャピエトラが一曲、地声で歌っていたりしてひどくたまげた。一見、明るめのエスニック(中華風か)なところとか、タイトにさらっと流してるところとかロックっぽいアンサンブルなどがポップに聞こえる一因なのだが、実は構成とか展開とか今までにない新境地を開こうと意欲的ににさりげなく凝っている。努力がみえてしまうのね。オルメって妙に良心的で真摯な姿勢が昔教育TVでやっていた「♪口笛吹いて空き地へ行った~♪」という主題歌の道徳番組を見ているようで懐かしい。空き地なんぞいまどきもうないけどなぁ。
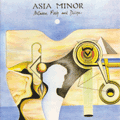
Between flesh and divine/Asia Minor
ソリーナと変拍子によるちょっと恥ずかしいくらい“ど演歌”。一応、フランスでレコードが出ていたようですが、その名の通りトルコ人のグループなのだな。出ずっぱりだったフルートの出番が少し減ってキーボードの音圧が上がったこれは2作目。微妙にオリエンタルなメロディにはいっそう泣きが入るようになった。表面的には美麗なポップということでありがちな80年代ものなのだが、どうも彼等の音楽にはいろいろな意味で微妙に近しいものを感ずるのだ。
「北方の光(Northern Lights)」
北の光
それは黄昏に流された涙
光の波
それは夜の闇から落ちてきた
輝く瞳
それは苦悩する人類が喪ったもの
砂漠に落ちる雨滴
そこでおまえは孤独に戦うのだ
おまえの誕生と存在は北の光の上昇
おまえの死と不在は北の光の固着
北の光
それは黄昏に流された涙
鳥の群れ
それは空にダイアモンドのように穏やかに舞う
不思議な音
それは時の回廊を通ってこだまする
天国の秘密
それは暗闇の深い霧を透した
詩人の破れた心に北の光が燃えあがり
沈黙の知識は夜を越えて横たわる
中学生並みの英詩で「あはは」といいたいところだが、こういう臭さというか湿っぽい雰囲気には同じアジア人として妙な親近感を抱いてしまう。「北」に対する意識も意外に似ていたりするのかな。何か辛いことがあったりすると「北」を目指すでしょう。別離を悲しんでリビエラで豪遊したり、失恋を癒しにトンガに相撲をとりにいったとかって聞かないもんね。歴史上もトルコはオスマン朝以来独立を保ってきたわけだが、かつて欧米の植民地にならなかった国として日本(人)をとても尊敬して親近感を抱いていたそうです。かつての話しだから今はどうだかねぇ。要因は単純ではないとは言え、EUに混ぜてもらいたいがための卑屈ぶり(一応独仏を選ぶ才覚はあるようだが)と、作り出された危機に作った当事者の責任を問うばかりか逆に庇護を求めてしまうポチぶりと、どっちもそれなりに涙を誘う憐れさじゃないか。八方塞の原因がグローバリズムにあることを見て見ぬふりまでして、自前の文化すら放擲しちゃったんだから後は腐るしかないよな。腐敗の過程はそれなりに美しい(美味しいとも云う)ので生きてるうちに是非とも末世を目の当たりにしたいものだ。トルコはそこまで落ちているのかどうか不詳だが、取敢えず御多幸をお祈りしときます。
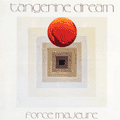
Force majeure/Tangerine Dream
『Cyclone』の延長線上でありながらも、ずいぶんこなれたというか円熟味が堪能できる一枚。歌入りの曲はなくなりました。前作同様にクリーガーのドライでタイトなドラム入り。起承転結のある構成と美麗なメロディ、多用されるギターと、初期ドイツ時代に比べると耳を疑うような変わりようだな。18分オーバーのタイトル曲はシーケンサ等の使いこなしが非常に自然で音の広がりも隅々まで染み渡るように美しい。シンセのみで奏でられるメインのテーマが終わると、シーケンサとドラムが加わってエンディングに突入していく。その辺り、敢えて崩していると云えないこともないか。
これが一応最後のタンジェリン・ドリーム。見返してみるとけっこうあるものだ。80年代以降は70年代のエッセンスを希釈した一種の現状追認型セルフ・コピーBGM。あと70年代ものとしてはライブとサントラと『Green desert』というのがあるらしいが、一種のアウトテイクだろうことなので300円くらいで売っていたら買ってみようか。

Light in the dark/Hector Zazou
70年代初期にソルボンヌでサロンをしていたZNRの片割れ、エクトル・ザズーによるアイルランド・トラッド乃至は聖歌。68年の五月革命の影響は無視できない、というのはCANのイルミン・シュミットも言っておったらしい話しだが、Magmaやチェンバーものも含めてザズーもその影響下にあることは間違いない。もっとも、かなりごった煮で筝曲からアフリカンまで節操には欠けるかもしれない。かつての室内楽的な緻密さは精緻なエレクトロニクスとアコースティックな生音の絶妙な対比に巧く生かされているように思う。ゲール語と思われる3人の女性ボーカルもゆったりとした哀感が透き通るように美しい。でも宗教的なバックグラウンドが違うから子守り歌みたいに聞こえてしまう。
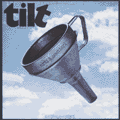
Tilt (immagini per un orecchio)/Arti e Mestieri
その名の通り「芸と職」がいかんなく発揮された1st。「職(腕前)」として当然の自負もあるでしょう。脅威的に上手い。おのれは千手観音か! と思わせるフリオ・キリコ(Furio Chirico)の高速で滅多やたらと手数の多いドラムはあまりにも著名だが、キリコ以外も皆負けず劣らず上手い。一方、それが決して見せびらかしになっていない全体構成と地中海情緒にあふれたリリカルな曲調は正に「芸」にふさわしい。メロディをとるのがほとんどバイオリンかサックスというあたりも正統的だろう。クールなテクばかりが強調されることが多いのだが、それにも増して(歌は少ないのだが)精緻な歌ものとしての側面が本当は正面なのだと思う。暖かみのある爽快感が気持ち良い。
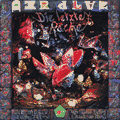
Die letzte Rache/Plan, Der
映画のサウンド・トラックらしいが不詳でござる。さらさらと流し読みした感じでは、“話す賢知”に“支配者”、“機械魚”と音楽以上にイカレタ感じであることに間違いはなさそうだ。デル・プランとしては3枚目の正規盤。ノイエ・ドイッチェ・ヴェレ(Neue Deutsch Welle=New German wave)というのだっけ。西武あたりがそれなりにかぶれておりましたが、それなりの時代の盛り上がりの中でもピカ一の幼児退行性というかへろへろ具合がキッチュに決まる、うつけ具合が最高というかサイテーなデル・プラン。エレクトロニクスとノイズ、風刺とキッチュが混沌として、蓋を開ければアヴァン・ガルドな童謡というのが良い線か。
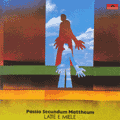
Passio secundum Mattheum/Latte e Miele
なんだか評価の高い一枚目は混声合唱入り『マタイの受難劇』。全一曲というありがちなパターンですが、一分を切るような短い曲の断片があれよあれよと変奏されて長さを感じさせない緊張感が持続する。けっこう厳粛かつ大仰なのだが中間のジャズっぽいインプロを除くとリリカルの極みの美メロということで、形式的に固くならず可憐なところがいかにもイタリアもの。逆に、曲間や唐突にぶち切ったりとか作為的な編集がイタリアものではかなり珍しいかもしれない。若くて未整理な印象は否めないが、これまたきらきら耀くような、あくまで可憐な熱っぽさが儚くも切ない。
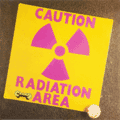
Caution radiation area/Area
混迷の度合いを深めるアレア2ndでござる。ギリシャ語で歌う東地中海民族音楽とノイズ風前衛電子音楽のるつぼ。アレアの凄さは一種の徹底した方向性にある。なんと「赤い彗星」(赤はコミュニズムの表象)だもの。ライブで「インターナショナル」を演じたりするのは、少なくとも私の存する(あるいはしてきた)環境では想像できないことなのである。ベースがPFMに引き抜かれたのだが新加入のタボラッツィ(Ares Tavolazzi)なる人はダブルベースまで弾いてしまうこれまた凄い人だわ。シンセでピヨピヨしていないアンサンブルはこれまた驚異的に格好良い。ベースを支えるアコースティック・ピアノの活きの良さも特筆すべきか。
ちなみにジャケの右下の小さな白い丸はマリリン・モンローのバッジみたいだな。はは、意味深。