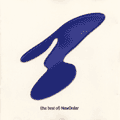
(the best of)NewOrder/New order
80年代におそらくEPなりシングルとしてヒットした代表的な曲の94年バージョンのリミックスがいくつかと、聴いたことがないものも含まれているから単純にベスト盤とは言えないかもしれない。一応翌年出る(the rest of)と対になっているのだろうが、深い意味があるとは思えないし、当人達がどこまで関っているかはもっと疑問だ。ディジタル・レコーディングによって手法としてのリミックスは隆盛を極めるのだが、それは同時に歌曲の商品化を究極的に押し進めることにも繋がった。表向きがどう人の目に映っているのかは知らないが、一つの産業としての意思が非常に明確になったのも90年代の特徴か。そんな背景の中でいきなり「True Faith」などといわれてしまうと、一体どこに目を向ければよいのか戸惑ってしまいますが、見たいものだけを見ることが取り敢えずは幸せ。

Dies irae/Formula tre
フォルムラ・トレの1stアルバムであるが、いきなり「最後の審判」だそうな。時節柄、想像通りの重量サイケ・カンツォーネです。プロデュースに加え、大半の曲はBattisti & Mogolという黄金のコンビによるもの。イタリアものにおけるこの二人の影響力は、置屋のやり手婆ぁじゃなくてほとんど神に等しいのは周知の事実であるが、フォルムラ・トレは忠実かつ優秀な弟子であったのだろう。アレンジの荒っぽさや詰めの甘さを差し引いても、単なるコピーの域を出た心意気は評価に値するだろう。ラディウス(Alberto Radius)、ロレンツィ(Gabriele Lorenzi)、チッコ(Tony Cicco)と後のイタものを代表する三人のデビュー作でもある。
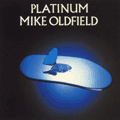
Virgin
CDV 2141
Platinum/Mike Oldfield
2000年以降は未入手(なんだかまったく食指が動かん)だが、これがいちばん好み。世評は最悪みたいですが、初期の民族風のリリカルさとタイトなポップさの混ざり具合が丁度良いのではないか。曲が短くなってそれなりに物議を醸していたが、長くて当たり前みたいな、今考えてみりゃかなり変な時代だった。個人的になかなか微妙な端境期にあった時節で、解放と鬱屈がない交ぜになったような二律背反が懐かしい。ここから少し路線変更なのだが、何年も同じことやってたら演る方も聴く方も飽きるからそれはとても良いことだ。特に前半の組曲(グラスのカバー)の民芸調のリリカルなメロディにかぶさる躍動感のあるリズムはファンキィでミニマルで炒った銀杏のように好みである。
手元にあるのは84年製VirginのCD。初期のLPとは曲が差し替えられているとか、初心者向けとかいろいろあるそうですが、特に意識的でもなくてプログレからも縁遠いわたしにとってはかけがいのない一枚でした。
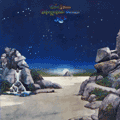
Tales from topographic oceans/Yes
敢えてLP2枚組にする必然性は感じられなかった6作目。特に後半は冗長だと思います。ドラムがアラン・ホワイトに代わったことや主導権がアンダーソンとハウに集中したこと等も含めて転機になったアルバムか。LP A、B面の緻密な構築に比べて後半はどうもまとまりがないというか流れてしまっている。キーボードも『Close to the edge』の冴えが感じられない。曲調も緊張感で畳み掛けるというよりはゆったりとした明るめのメロディが特徴だ。個人的には一曲め(A面)の高揚感と奥行き感がうっとりするほど気持ち良い。
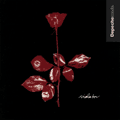
Violator/Depeche Mode
前作で開き直って、少し明るくなったかなと思ったら、また暗いわ。ウルトラヴォクス(Ultravox)のようなマイナー調の美学ってわけではないのだが、生まれてから死ぬまで日陰者みたいな宿命的な暗さだ。はまってしまうと日常的になってしまってむしろ気持ち良いのだが。
「Waiting For The Night」
夜の訪れを待っている
夜がすべてを包み込んでくれるだろう
闇の帳が
明晰な現実を覆い隠してくれる
夜の訪れを待っている
何が起きても耐えられそうな
その静寂の中で
感ずるすべては平穏におちていく
夜空の星が
その光で導く
輝く月は
解放がもう近いことを示している
夜の訪れを待っている
夜がすべてを包み込んでくれるだろう
闇の帳が
明晰な現実を覆い隠してくれる
夜の訪れを待っている
何が起きても耐えられそうな
その静寂の中で
感ずるすべては平穏におちていく
静寂のなかに響く音
人によっては害になる
耳を手で塞いでしまえば
夜の帳の中で恐怖を忘れることなど簡単だ
目を細めたら
世界は薔薇色に見え
天使が降臨した
驚いたことに
半分目を閉じたほうが
目を開けているよりも
物事は上手くいくようだった
夜が満ちるのを待っていた
夜がすべてを包み込んでくれるはずだ
いまや闇の帳が
明晰な現実を覆い隠していた
夜が満ちるのを待っていた
いまや堪えがたきことはない
この静寂のなかで
感じるすべてが平穏におちていく
一見似たような繰り返しかと思うと、最後の3節は時制が過去と過去完了だったりして救いがないなぁ。訳は久々だけど、本来訳す(真似事だけど)ことは個人的にはあまり良いことだとは思っていません。聞くなり原文を見るなりして、英語なら英語のまま理解したほうが直感的に正確です、間違いなく。五言絶句をレ点つけて読めば意味は通るかもしれないけど、たぶん原文の持つ韻とか歌(耳に入る音)としての面は完全に捨象されてしまうのに似ていると思うのです。とはいっても英語マンセーではないので念のため。「a」を「エイ」、「i」を「アイ」などと発音する言語は世界的にみてもとても稀な辺境方言みたいなものです。「a」は「ア」、「i」は「イ」というのが人類の90%の共通認識です。だから子供の頃から無理やり教え込んだりするとロクなことにならないと思いますが、ボスに忠実な子犬の躾だと思えば良いのかの。最近久しぶりに里に下りてきたら、世の中の変わりようにびっくりでした。異人さんのお国に迷い込んだようでした。くわばらくわばら。日本で暗い歌は売れないというのはほとんど定説らしいですが、確かに人気は無い。

Waterloo lily/Caravan
デイブ・シンクレア(Dave Sinclair)がマッチング・モールに引っ張られて、スティーブ・ミラー(Steve Miller;Phil Millerの兄者?弟者?)に交代した4作目。ゲストにロル・コクスヒル(Lol Coxhill)等カンタベリ・ジャズの面子が加わって、内容的にもかなりジャズに流れたところはあるかもしれない。前作の『灰桃地』のポップな明るさとは打って変わった灰色の落ちついた雰囲気。音感としてデイブ・シンクレアのオルガンがミラーのエレピに変わったのがいちばん大きいか。
そういえば昔『Lol Coxhill & Steve Miller』(1973)というHatfields+Coxhillみたいな、これまた途方も無く美しいLPが出ておりましたが、CDになっていないようです。どうでも良いような量産品の紙ジャケ化やリマスターなんぞしている暇があるならば、聴き過ぎてテープ切れちゃったので何とかして欲しいものです。
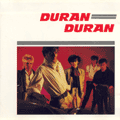
Duran Duran/Duran Duran
うぉ、ダサいスリーブだけど、中身は思いの他良いDuran x2の1stでござる。二、三作目のときめいちゃう感覚はまだだけど、さすがメロディ・メイカー、曲はなかなかの出来です。久々に聴いていたら気に入っちゃって、このところ作業のお供ってところです。まぁ、Duran x2というと元祖ビジュアル云々ばかり、中身はまともに評価すらされないのが現実。フォロワーも多いし。フォロワーといえば皆フォロワーなんだが、似たような格好して、似たような歌を歌って、似たような楽器を弾いたりして、同じ枠の中で色が違うくらいを個性とかオリジナリティって呼ぶのはかなり空しい。ちんどん屋のほうが同じ歴史参照にしてもずっと個性があるのじゃないか? まぁ、音が格好良くてきちんと聴ける中身があれば見てくれは関係無いのだけど。
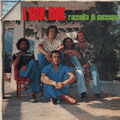
Raccolta di successi/I dik dik
いきなりプロコル・ハルムの「青い影」のイタリア語バージョンでぶっ飛ぶベスト盤かカバー集。あるいは60年代のシングル・ヒット集であろう。リコルディの再発廉価盤LPですが第二集もあります。ほとんどの曲は(彼の有名な)Battisti & Mogolのクレジットが入ってます。まぁ、彼等にとってはこの路線がメインなわけで、『女組曲』とか『Volando』は実はウンカ・ムンカ(Hunka Munka)なのかいな。有名なこの2作はなぜか、まるでそんなものはこの世に存在しなかったかのように本家のWebには載っていないのだ。権利関係なのか実際に違うのか(そりゃまた凄いことだが)は知りませんが、どういうこっちゃ。
本質的には都市国家の集合体であって、イタリアなどと一括りにすると北部同盟に睨まれそうなんで、この場合はミラノのディク・ディクと言うべきですか。しかし、なんでこうイタものは嵌まるのでしょうか。ちょっと前まで一緒に枢軸してた仲だからでしょうか。もっとも足手まといになりこそすれ、役に立つことは無かったようですが。
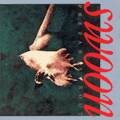
Swoon/Prefab Sprout
素朴なのだけど可愛くて少しクールな1st。意外に複雑で弄くりまわした曲をさらっと自然に演じるのが、顔でもあるパディ・マクルーン(Paddy McAloon)の特徴である。曲調はフォークっぽいのからボサノバタッチ、変てこりんな変拍子に、ストリングシンセに透明な女性ボーカルまで非常にバリエーションに富んでいるのだが、独特の節回しがプリファブ・スプラウトなのだ。ニ作目の冷やっこい洗練感(あれはプロデューサの趣味だとか)は薄くて非常に地味なネオ・アコースティックです。

1978
Out of the mist,Illusion/Illusion
不運と不幸を背負子に満載して背負ったかのようなオリジナル・ルネサンス。これはイルュージョン(Illusion)に改名して再出発した1stと2ndのカップリングCD。今は知らないが当時はまったく人気が無くて、1stはいつまでも埃をかぶって売れ残っていた。若輩ながらジェイン・レルフ(Jane Relf)のジャケを見かけるたびに心を痛めておったのです。『Out of the mist』が1stで『Illusion』が2nd。知名度無さ過ぎで1stが売れなかった場合なんかによくあるタイトルのつけ方です。実際、3rdはデモくらいまでは録音したようですが結局出ることは無かった(90年代前半に発掘されてますが)です。キース・レルフの事故死が大きなブランクの原因だろうが、時代はすでにパンクなわけで誰も相手にしてくれなかったのだろう。兄者の代わりに妹ジェイン・レルフを表に出して再起を図ったのだろうが、もともとトラッド基調のアコースティックな音(特にピアノ)だからインパクトや話題性には欠けた。ルネサンスのアニー・ハズラムのクリア・ソプラノに対してパン屋の店員さんだったジェイン・レルフはどっちかというとアルトな情感が持ち味ってところでもひたすら地味だ。マカーティの曲も学校の教科書に出てきそうだという意味では刺激が必要な商業主義ポップでがっぽり路線からは大きく外れてしまった。
と、悪いこと尽くめなのだが、まぁ、良いじゃないか。ヤードバーズのドラマーだったマカーティのコンポーザとしてのセンスと、ホウクンのピアノ、シェナモのベースと派手じゃないけど完成度の高い、祟高などという単語は使いたくないが、情念を揺り動かす音だ。それなりの歳になったら聴いてみてくださいな。なんで秋に芹があるのか知らんが(旬は10月から4月だそうで、昔田んぼに採りにいったのは水が冷たい早春だった)、おひたしにして食いながら聴いてたら、もうめろめろ。
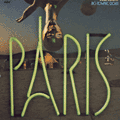
Big towne,2061/Paris
2ndにしてラスト。まったく売れなかったみたいでかなり方向転換してます。ミステリアスな未来志向とときどき顔を覗かせるラテン風の軽やかさの組み合わせが異質というかかなり変。おかげで今でも風化を免れていると言えなくもないが、当時はとんでもなく異質(一作目のファンにも見離され)で結果的には1stよりも売れなかっただろう。爆笑。つくづく Bob Welch という人は不運な人だなと心底同情を禁じえません。今回はカリカリギターにかぶさる中途半端にエスニックなシンセが売りなんですが、おかげで妙に無国籍でクールな未来派サウンドになっちゃってやんの。形骸化した残骸のような音楽ばかりの中で、しがらみのない軽やかなセンスが光っておったのぅ。
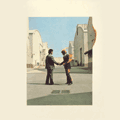
Wish you were here/Pink Floyd
発売日(日本盤のね)に買った最初でたぶん最後のレコード。まだ青かった頃、ちょうど今ぐらいの時期でしたか。友人と二人で学校帰りに買いに出て店を出たらすっかり日が落ちていたことを憶えています。前作から異例の2年半というインターバルに期待が高まり過ぎたという点を差し引いても、初めて落胆したレコードでもあった。もっとも、それは逆に考えればとても“らしい”アルバムだということでもあるわけか。1968年の2作目から前作までを相対的に汎progressiveな時代と考えるならば、その間には二つのブレイクスルーがあって、一つは70年の『Atom Heart Mother』、もう一つは73年の『Dark side of the moon』なわけだ。今更ながらちゃんと俯瞰して眺めてみれば、共通項は結局ロン・ギーシン(Ron Geesin)の存在なのだ。『Atom Heart Mother』に関してはアレンジャーとしてクレジットがあったかもしれない。『DSotM』に関してはギーシンとロジャー・ウォーターズの共作サウンドトラック『Body』がネタなのは自明である。アルバム全体の構成はもとより、黒人コーラスの導入から直截的でわかりやすいSE(もろ、そのものか)に至るまで、テーマは別としてもポップなアレンジや手法はまさしく『Body』の完成型。一方、この『WYWH』は個々の曲の出来は悪くはないけど(特にタイトル曲は良い)、あまりにも保守的なブルーズ楽団に戻ったというか、戻り過ぎてしまった。シド・バレットへのオマージュ第二弾というのも前作より直截的で洗練に欠ける。
そんなわけで、『DSotM』の次作じゃなくて、『神秘』『Ummagmma』『Meddle』を基盤にしたポップでムーディなブルーズ演歌としての発展型であり完成型と捉えるのがすっきりすると思う。
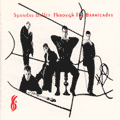
Through the barricades/Spandau Ballet
ブームも終わりってことで、ちょっとリズムがファンキィになったりして末期症状。売れなくなる>新機軸>ブラックでも入れてみっか って良くあるパターンだ。ミディアムテンポのバラードは相変わらず高質で良い。朗々と響くハドリー(Tony Hadley)のボーカルと流れるように華麗な曲調は健在なのだ。この人の声を聴いているとどうも敬愛する東海林太郎(1898~1972)を思い出してしまうな。トータルアルバムのような作りになっているけれど、最初と最後をアコースティックに締めているとこなんか憎いよなぁ。
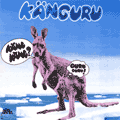
Känguru/Guru Guru
流氷に乗ったカンガルーのお母さんが「カンカン?」と問うと、袋から手と頭を出した子供が「グルグル」って答えるのです。それでもってカングルーって3作目くらいですか。なんだかずいぶん曲っぽくなってきてめでたいことです。重いリズムがドスドス、てろてろなギターがびゃんびゃん、ふざけた変態声がほにょほにょと全4曲。「撞着語法」「いつでもひょうきん」「Baby cake walk(ステップダンスの一種)」「うーが・ぶーが(なんじゃ?)」と、まぁ、マニ・ノイマイヤ尊師シリアスにおふざけが決まっております。うえ~ん。たった今まで撞着語法なんて知らなかったよ~~ プロデュースはグルグル+コニー・プランク。
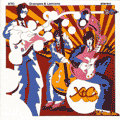
Oranges & lemons/XTC
類稀なけったいさで驀進するXTC。はずしまくるポップなメロディは後のマスク(スウェーデンの Masque ね)に影響を与えてそうだし、コンポーザ、アレンジャーとしてのパートリッジ(Andy Partridge)の影響力にも目を見張るものがある。方法論は異なるにしても70年代のジェントル・ジャイアント(Gentle Giant)と同質の根っこから派生していると思われる。楽理の専門的なことはちっともわかりませんが、期待させる展開を逆撫でするような緻密なおちゃらけ加減はパートリッジにしか出来ない技だ。メロディもサビも和音も、コード進行もリズムも微妙にずれていて、複数の曲を同時に鳴らしているような常道の反し方は尋常ではない。曲調がポップであればあるほど違和感が募るという妙な仕掛け。GGとは全く逆にライブをしないことでも有名ですが、スタジオでとはいえよく間違えないで演じれるよなと感服しております。

Still life/Van der Graaf Genarator
重くくぐもったダークさが遺憾なく発揮された中期(後期?)の最高作か。あるいは人によって好みはかなり割れそうだが、個人的には通しでも最高と認識している。タメの利いた格好良さと静謐なパワーが全開で円熟した孤高と崇高の境地に達している。いわゆる歌物ではなくVDGGという一つの楽曲なのだが、ハミル節も絶好調で、ここまで変幻自在に、かつ圧倒的な説得力を誇る『歌』もないだろう。マジョリティのつもりが初めてマイノリティに転落して、肩身が狭いというか、旗色の悪い時期だったりもして「Pilgrims」なんぞには随分と勇気づけられたものでした。まぁ、結果的には○○信仰などという欺瞞に訣別できて良かったのだがねぇ。