
Touch/Sarah McLachlan
ふんわりした品の良さが身上のマクラクランの1st。若いし一枚目なのに意外に稚拙さが無いというか素人臭くないんだなぁ。しっとりと滑らか(かつ上手い)なボーカルとこれまた非常に品の良い曲作りが特徴ですか。カナダ人みたいですがどちらかというとヨーロッパ風というか、クラシック寄りの素質を感じさせてくれます。最近じゃすっかり有名人みたいですが、歌上手いし曲も良いし、才能有りそうだからそれはそれで当然のことだろう。今聞くと生っぽいシンプルさが非常に新鮮だったりするのだが、育ちの良さを思わせる擦れていない生硬さが微笑ましい。スリーブデザインも当人のようですが、この手のネオ・クラシックに対する憧憬みたいなものは次のデレリウムも同じで面白い。アジアにありながら太平洋の彼方を見つめる人もいれば、北米にありながら大西洋の向うに浸りたい人もいるわけだ。
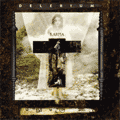
Karma/Delerium
打って変わった。初期と同じとは思えない。「カルマ」なんちゅう語句を西洋人が持ち出すときは要注意なんだが、やっぱりなぁ。エニグマかディープ・フォレスト並みのサンプリングにダンサブルなビート。一瞬、耳を疑いましたが、出てくる女性ボーカルは何とサラ・マクラクランを含めて美しく冷やっこい透明感と宗教的な陶酔感に包まれた天上の声です。味付けは少々違っても狙いは同じか。大西洋を渡るのに5年かかったのかどうかは知らないが、まぁそんなところでしょ。やる側ではなくて受け入れる側の問題なのだが、決して太平洋を渡ってこないところはそれなりに味噌です。総じて圧倒的に聴き易く、耳に馴染む音になっているんで、このところセコセコ仕事しながら聞いていますが、「Silence」? だっけ、なんともせつないサビを謳いあげるマクラクランも同一人とは思えないほど麗しく、びっくりするくらい色っぽい。ちょっと参ってしまう。
ドイツ盤の2000年エクストラ版CDとかで、2CDのリミックスてんこ盛りで1500円とかいうお買い得だったもんで買ってみました。結構長続きしてるユニットみたいです。昔のはおどろおどろしくて売れそうには思えなかったからとっくにぽしゃってたかと思うたわい。
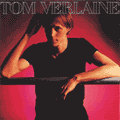
Tom Verlaine/Tom Verlaine
おそらくアメリカ人でありながら多分アメリカ人は誰も知らないヴェルレーヌの1st。テレヴィジョンも一部の評論家に絶賛されただけで売れていたのはイギリスだけだったらしい。本名は何ていうのか知らないし知りたくもないけれど、やっぱりこのひとも海の向うを見ているのだろうか。良くも悪くもTV時代の半死人のような壮絶な禍禍しさは薄れて血色も良くなって来ました。神経症的なキリキリするギターとちょっと浮かれたような甲高い声は相変わらずですがそれでも懐が深くなりました。いい年こいてパンクしたりロックしてるわけにもいかないだろうし、それなりのものを創ってしまった人は周りの期待も大きくて大変だろう。本質はとてもオーソドックスな音なのだろうが、微妙に心をくすぐるような色気がそこはかとない趣を醸し出すのであった。
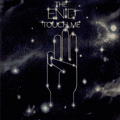
Touch me/The Enid
テーマが明解で聴き易い3作目。すっかりポップだとも言われていた。そんなこともないと思うのだが。LP、A面(Charade)、B面(Albion fair)各一曲という構成ですが、緩急自在な編曲とリズミカルな展開、彩りの豊かな多様な音色を楽しめます。中身は完全に中途半端じゃなくロマン派シンフォニィ。100人編成のオーケストラ向けの曲を7人で演じ切っていると言うことです。「Charade」に関してはちょっと文句のつけようがない完璧さ。優美さでいうならばEnidの中でもこれが一番でしょう。
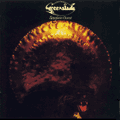
Spyglass guest/Greenslade
転機を迎えた(かもしれない)3作目。個人的には最高作だと思う。冗長な浪花節が消えてコンパクトで微妙にポップになった。短い曲に詰め込んだゆったりとした優美さとめまぐるしい展開はカンタベリものを思わせるところもある。意外に手数の多いリズムセクションもダイナミックというよりは軽やかに変拍子を刻むし、ベースも表情豊か。もともと女性的なイメージの繊細な楽曲が多かったけれど、可愛らしいメロディがとても印象的でそのあたりにも益々拍車がかかったように思える。要所を締めるメロトロンの使い方が非常に効果的で、熟練したアレンジの妙を聴かせてくれます。
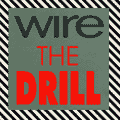
The drill/Wire
ドリル変奏曲集ですかい。リミックスってわけじゃないんである意味良心的ですが、突っ込んでいます。「Drill」ばっかり全9曲です。時期的には『Manscape』以前に録音されたみたいですが、打ち込みの抉るようなインパクトと迷宮のようなループ、皮相なノイズが強烈です。「ドリル」だから穿孔するんですが“教練”という意味も引っ掛けているんでしょう。覚醒的で四角四面なぺらぺらの剛直さが潔い。非常に丁寧に破壊されたシステムというか、神経シナプスを一本一本切り離していくような緻密な解体作業だ。生物としての家畜が屠殺、解体されることによって初めて食材として完成されるように、ワイアの呈示する音楽は逆説的に完璧だ。
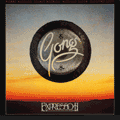
Expresso II/Gong
とうとう正規メンバーはリズム隊だけになってしまったゴング。でも打楽器3人+ベースでここまでできるみたいな心意気がうれしいのぅ。ホルズワースにストーンズのミック・テイラ、バイオリンはダリル・ウェイまでメロディ楽器のゲストはいるのだが刺し身の具のように感じてしまうところがゴングの真骨頂。マリンバの女の子の少し東洋的で可愛い曲が増えて個人的には嬉しいが、総体的にはなんだか逆に繊細さが薄れタイトで骨太な感が強まった。いきなり一曲目ブルーズで始まってびっくりですが、それ以外は如何にもゴングらしい英仏混合フュージョン。ホルズワースのねちっこいギターに絡まれながら全曲歌無し、代りにマリンバが疾走しておりまする。

Last/Agitation free
その名の通り70年代のラストになったアルバム。2枚目の音楽的な多様さを越えて、再び戻っていったのは1stで聞こえたフレーズだ。初めから3部作を狙ったとは思っていないが、通して聴いていると目くるめく輪廻、転生と再生を思い起こしてしまうぞ。モノクロフィルムに着色したような隠微と頽廃、黄昏た曖昧さ。主体としての音というよりは音場。今でいうアンビエントで不明瞭な浮遊感が漂う。曲はすべてスタジオでライブレコードされたインプロヴィゼイションのようですが、同時期のアシュラやタンジェリン・ドリームと同様の方法論を採るところなど根っこの同質性を感じさせます。スリーブの着色陰画は廃墟と化したベルリンと思われます。

Rubycon/Tangerine Dream
ユリウス・カエサルはルビコン川のたもとで「骰子は投げられた」とのたまってローマへ進軍したんだっけ? はて、タンジェリン・ドリームは何を渡ったのか。アンチ・メロディとシーケンサによるループの波状攻撃は、中身としては『フェードラ』路線の完成形ですが、次作以降は確かに趣が変わるかもしれない。完成形にしがみついていないのは個人的に良いなと思うのだが、転進先がちょいと迎合していた。ミルク?が落ちる瞬間を捉えた表スリーブは、裏スリーブではミルク・クラウンに成りかけている。と思ったら逆なのか。時系列が逆で落ちた一滴が最初にミルククラウンをつくるらしい。ルビコン一曲全35分程ですが、スリーブの一瞬に何を表象したのだろう。
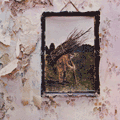
No titled/Led Zeppelin
おや、懐かしい。一応、特定するときは『4 symbols』と称しておりますが、ジャケットの外側(って内側もか)にはいっさい文字を書かないというのが当時のゼペリンの「やり方」だったそうです。そんなに大物だったとは思わなかったけれど、流通業者は困ったでしょう。「薪背負った爺の絵」の奴とか「裸の餓鬼」の奴とか呼んだんでしょうか。中身に関してはあまり言うことは無い。重量感と明解さにあふれた完成型です。「天国への階段」ばかりが取り上げられたものですが他の曲も十分高質でしょう。トラッドの曲でデュエットしてるのはあの民謡界の重鎮サンディ・デニィ(Sandy Denny)です。世間が狭いのか、懐が深いのかは知りませんが頼むほうも受けるほうも刺激があって羨ましい。
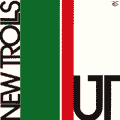
UT/New trolls
泥臭いがちょっと洗練された透明感や繊細さも感じたりして掴みどころがない。イタリア臭さを生かした明るく硬質なセンスが冴え渡る初期の代表作でもある。元々60年代ビート・グループの出身だからヘビィなリフもお手のもの。クラシックからフォークあり、カンツォーネありと一歩間違えれば破綻しそうな展開を圧倒的な構成力で捩じ伏せてまとめちゃいましたって感じだ。曲を作る人によって明らかに方向性の違いが感じられるところは直後の分裂の伏線になっているのだが、緊張感に結びついてそれはそれで良いのかの。個人的にはのほほんとしたタッチの方が好みなので、左右のスピーカで交互に繰り広げられる「パオロとフランチェスカ」のギターの痴話喧嘩か睦みごとがほんのりと空気を染めあげる様が気に入っております。もとネタはダンテ(Dante Alighieri 1265-1321)の「神曲(地獄編)」ですがイタリアっぽくて良い。
「Paolo e Francesca(パオロとフランチェスカ)」
きみはずっとパオロをさがしている
フランチェスカはきみをさがしている
雲ひとつない空のしたで
誰一人いない道で
どんなに手を尽くしても 彼女は堂々巡り
永遠にめぐりあえない罪の下で
どんなに手を尽くしても 彼女は堂々巡り
そんな私達の生き様の物語
きみはずっとパオロをさがしている
フランチェスカはきみをさがしている
二つの魂の物語
一つの因果の物語
どんなに手を尽くしても 彼女は堂々巡り
永遠にめぐりあえない罪の下で
どんなに手を尽くしても 彼女は堂々巡り
そんな私達の生き様の物語
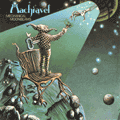
Mechanical moonbeams/Machiavel
密度の濃い3rd。スリリングな展開とリリカルな穏やかさが絶妙のバランスで同居しておりまする。緻密なアレンジと拍子を変えまくるリズム、それをこなすテクも文句の付けようがないか。それにも増して、マキャベル独自のスタイルというかオリジナリティが色濃く出たアルバム全体の完成度を賞賛しよう。非常にメロディが綺麗だし聞きやすいのだけれど中身は恐ろしく高度なことをしてます。8分程の曲にもきちんと起承転結があったりしてアイディア詰め込み過ぎというか、もったいないような嬉しいような。全体を通してふわっと包み込むようなキーボードが冷やっこい夜のしじまの透明感を彷彿とさせるところなども非常にツボに嵌まる。この辺はアンジュもそうだけれど大陸系はベースの雰囲気作りがとても上手い。しかし、このCD(UGUM)古いせいか音がこもっちゃってどうしようもない。最近のジャケ違い(オリジナルだそうで)の奴はもっとマシなのだろうか。
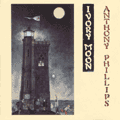
Private parts and pieces VI "Ivory moon"/Anthony Phillips
おっと、ピアノ・リサイタルもあるのか。最近借りてきたもんで知りませんでした。71年から85年にかけて作った曲をまとめて録音したもののようです。曲によって趣はそれなりに異なりますが、ピアノしか使っていない本当の個人選集です。まぁ、いわゆるピアノのプロではないんで、拙い部分がないとは思わないし、曲もピアノ曲というよりはギター向きかもしれない。左手の使い方がピアニストではないようだ。もちろん御多聞に漏れず繊細でリリカルで上品な曲調はこの人の特質です。おっとりとして非常に地味なので、ショパンのノクターンでも聞きながらまったりしてる気分に近いかもしれない。
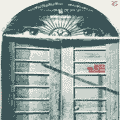
Io sono nato libero/Banco del mutuo soccorso
「私は自由の子である」という直訳タイトルは「人は生まれつき自由である」と言いたいのであろう。当時の政治状況を思い起こさせるタイトルですが、勿論日本では「自由への扉」とかってきっちりぼかしてありました。いきなり「政治反逆者の歌」で始まるのだが、初期の中でも美しくも優美な完成度を誇る。音がとても整理されていてアレンジの妙を尽くしたと言えるだろう。結果的にも聴きやすい。ジャコモおじさんのボーカルもバランス重視で少しおとなしい。内容からするととても闘争的な雰囲気なのだが、むしろ敗北感を抱えた物悲しさを感じるかも。ラストの少しだけ力強いテーマが救いかもしれない。

The first of the Microbe hunters/Stereolab
典型的な今風のリズム、品良くまとまった明るめの女性ボーカルに加えノイズっぽいエレクトロニクスの味付け。綺麗で軽くあっさりディジタル味ってとこですが新鮮味には欠けるなぁ。売れ線外したくないという思惑はわかるが、若いんだし筋も良さそうだからもう少し冒険しても良いのでないかの。Clusterとモワルランの頃のゴングを掛け合せて、饒舌にダンサブルにしただけって見切っちゃいけないか。Clusterの突き抜けようという意思の方がずっと爺さんだけどずっと潔いぞ。所謂音響系だそうですが非常にコマーシャルでポップでぬるい。これを前衛とするならばClusterはもう音楽以下のただの異音、Klusterに至っては月面宙返りのドグラ・マグラってとこですか。ポストロックだの21世紀の音楽だのいう商売筋の宣伝文句に釣られたほうが阿呆と言われりゃその通り。もちろんお車でのおデートのお供等にはぴったりだろうから、さういう立場にあれる人には良いかも。

Prism/Prism
昔何度か観たプリズム。正統なテクニックと端正なセンスに憧れた。「Dancing Moon」を踊った君はどうしたことか。圧倒的なまでにテクニカルなフュージョンの部分も凄いのだが、やっぱりメロウでうっとりするようなリリカルさが特質か。中心人物である和田アキラは当時20才そこそこだろう。しかし若さと国籍をここまで感じさせないというのはかなり珍しい。それなりに変遷はあったにせよ、サラッと乾いた取り敢えず新しい時代の幕開け的な新鮮さを感じたものだ。冒頭のギターの音だけで「うわっ!」って思った人は多かったに違いない。ヘトヘトの一週間を終えて目覚めた日曜の朝は快晴ってとこですか。まだリゾート云々の時代じゃなかったはずだが、プリズムに関しては「青と白」のイメージが離れない。