
Lemmingmania/Amon Düül II
入手不可能な70年代前半のEPやらシングルをかき集めたコンピ盤。CDにはボーナストラックとして「Phallus Dei」のリミックスがオマケ。変な組み合わせ。まったくセンスを疑う。それは置いておいて、音源としては実はとても貴重だし良い曲が多い。今聞いても相変らず異形ですが、この時代ではそれ程違和感は無かったねぇ。ちゃんと聞けるし、メロディも恰好良いし。アルバムの滾るような暗黒感というか、どうしようもない原初性みたいなものはかなりソフティスケイト(なんちゅう単語じゃ)されてますが、諦観したサイケデリックなどろどろ感が素晴らしいの。アモンと言えば古代エジプト、カルナックのアモン大神殿(アモン神を奉っておるのか?)か、ソロモン王が召喚した72悪魔の一つで過去と未来の調停者かのどちらかを示すと思われるが、勿論知らない(後注:後者のような気はするが、実は前者)。CDではわからんがLPはシルバーの美しいジャケだった。

Treasure/Cocteau Twins
大化けした3作目。裏声率50%ぐらいですか。ここと4AD以前以後で傾向が変化するように思う。スリーブ通り、暗がりの中でレースのカーテンを通して垣間見る光景のような音。深い残響の中を黄泉の国の気まぐれな美神のように呪いと祝福が交錯する。フレイザの歌はとても情動的だし、著しく女性性を発露するようでエキセントリックにすら感ずる。至福と明るめの耽美感が増すのはもう少し後になってから。CTの場合、当時4ADがどういう売り方をするつもりだったのかは知らないが、シングルやミニアルバムに力が入っていてフルアルバムはどうも重視されていなかったような気がするのだ。同時期のものとしては明らかにコンピの『Pink Opaque』やカップリングの『Tiny Dynamine~』の方が質は高いものなぁ。
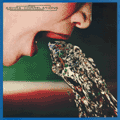
Correlations/Ashra
アジテイション・フリーのルツ・ウルブリッヒ(Lutz Ulbrich)とヴァレンシュタインのハラルド・グロスコプフ(Harald Grosskopf)を加えて3人体制になったアシュラの3作目のスタジオアルバム。専任パーカッションが加わったとはいえ、人間シーケンサみたいなもんだから派手になった印象は無い。むしろライブを意識した音作りをしているのかパートが明確に分離できるような構成のように思える。現在のテクノないしはハウスの原型(というか人力かコンピュータかの差だけでたいして違わない)としての一つの完成形を完璧な形で提示したもの。二人のシンセサイズド・ギターの音色は所謂ギターの音じゃないというか、華麗というかカラフルというか、創意と官能とセンスに溢れている。本質的にギターものはまったく琴線に触れないのだが、こういうやり方には心底愛着を感じるな。最近もそれなりに活動してるようですが昔に比べて人気があるらしい。80年代後半から90年代のテクノ勃興期におけるパクリ元。

Hawkwind/Hawkwind
長寿を誇る現代の仙人、デイブ・ブロックいきなりハーモニカなんぞ吹いたりしてスタートはなんだかブルーズしているのだ。勿論、スペイシィなサイケ感もあるし、リズムが前面に出てくる曲もあるけれど、どよんとした虚ろな暗さが結構幅を利かせている。長めの曲に後を髣髴とさせる特徴が出ていますが、いかんせん機材が追付いていない。イブ・タンギーの海底絵のよう(一緒にしちゃ失礼か)な変な生物がのさばるジャケに負けない変てこりんなわけのわからなさが悠久の時を刻んでおるようだ。最近のEMIのリマスタにはピンク・フロイドの「Cymbaline」のカバーが入っているそうだが、勿論私のには入っていない。
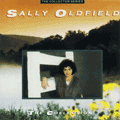
The collection/Sally Oldfield
余計なお世話だろうが全然似てないマイク・オールドフィールド(Mike Oldfield)のお姉さん。トラッド寄りのものからポピュラーものまで一色汰で雑多な内容ですがキャリアは長そうです。曲に関するデータがまったく無いもので何とも云えないのだが、昔は(子供の頃から)一緒にやっていたせいもあるのだろうが弟に通ずるものは確かにある。姉の方は高音の透明なソプラノばかりが有名ですが、ここではそれなりに抑揚もあるし、テレビの歌のお姉さん風のかわいいものまで結構バラエティに富んでおるの。弟が鉄琴、木琴を多用するのはおそらくここが原点なのだなぁ。くすんだ哀歓はアイリッシュ・トラッドそのもの。うっかりしてるとクラナドあたりと見分け(聞分けか)がつかぬのぅ。

Rotters' club/Hatfield & the North
まぁ、あまり真面目にとられても困るのだが、いわゆるカンタベリィ系の特異性はイングランド(イギリスじゃなくてね)の社会構造の表出そのものであると考えればわかりやすいのだと思う。
カンタベリィはイングランド南東部のイギリス国教会の総本山があるケント州の州都。当然、伝統的かつ保守的な土地柄で貴族やお金持ちが多い。有名な庭園やら館などもゴロゴロしている。デイブ・スチュアートあたりがよく解説を書いていたりしますが、彼等が使う英語を見れば明らかに語彙というか単語そのものが労働者階級(Working Class)が使う英語とは違う。内容がいくら良くともイングランドでは決して売れ筋じゃないってのは、そのウィットや皮肉なジョークにまみれた内容が一部の教育のある中流(日本の中流とは逆に全人口の10%以下か)以上にしか理解できないからだ。
あるいは、階級を越えて音楽を聞くこと自体がスノッブとして社会的な嫌悪の対象になっているからだ。
パンクが台頭した70年代後半から80年代いっぱい無視され続けたのも、その以前だって質は良いのに売れなかったのは対象の人口が少ないからなのだろう。音楽産業としてはどうせ搾取するなら数が圧倒的に多くて煽動しやすい労働者階級を相手にした方がお手軽に儲かるってことなのだろう。労働者階級に受けるためにはビートルズがそうであったように、やはり労働者階級にも理解できる労働者階級の(なまった)言葉で歌う人が必要なわけだ。
だから勿論、中流階級の音楽としてのカンタベリィ系(ヘンリー・カウは少し違うのだが)には体制を辛辣に皮肉るユーモアはあっても、壊す蓋然性はない。これまた勿論、(思い上がって)世の中を変えようなんて考えて音楽を作る時代じゃない(そんな時代があったわけじゃないけれど)だろうから、労働者階級向けの発情歌や受けの良さげな言葉を取っ替え引っ換え並べてるだけの欲求不満解消歌よりは少なくとも中身の有意性としては圧倒的にマシであろうという結論になるだろう。
ジェネシスがゲイブリエルからフィル・コリンズに歌い手が変って、人気が出たのもそんなところに理由があるのでしょう。私には今一つよくわからないが、発音やイントネーション、使う単語まで含めた言葉使いや物腰、服装、立ち居振るまいがまったく違うとの指摘は適切なのだろう。
端的に言えば「Rotters' club=嫌われ者倶楽部」ってことですが、自分達のことを茶化してるのかいな? この「Rotters' club」というのが実在する固有名詞なのかは知りませんが、イングランドのクラブというのは単なる同好会ではない。同好の志なら誰でも加入できるというわけではないのです。近年、王子がフットボールのワールドカップを見たいと表明したりして騒ぎになったりするように、部分的に曖昧な部分が出てきているとはいえ、クラブに関しては女性は勿論、サー(Sir;卿)が付かなきゃ入れないなんてのは極当り前のこと。
例えばゴルフの同好会をカントリィ・クラブと称したりしますが、ゴルフは中流以上のスポーツなので、いわゆるプロ・ゴルファーという職業の人はクラブハウスに入れなかったりする。それは、スポーツはアマチュアが行うものという前提がまずあって、プロ・ゴルファーという職業は労働者階級の肉体労働者という扱いだからなわけです。
また、町にはパブという社交場があるわけだけど、実はパブにすら入り口が2ヶ所あって内部は中流のサルーンバーと下流のパブリックバーに分かれていたりするのです。さすがに現代では誰でもどちらにも自由に入れるそうですが、サルーンバーで一気コールなんかした日にゃ、間違いなく叩き出されますね。
そんなわけで経営者や管理職等として普通に働いてるアッパーミドルの人ならば、午後3時くらいになると仕事を切り上げて、馴染みの会員制クラブに顔を出してジントニックでもやりながらサンドウィッチを摘まむなり、お茶とスコーンで新聞(勿論"The Times")のクロスワードをしたり、同業者(同階級)同士で今日の天気の話とか、昨夜のハムレット役の出来の良し悪しを語るわけ。優雅に至福のティータイムというわけです。その後は観劇してサパー。一芸に秀ていたら入れてくれそうなフランスでいうサロンとは少し違うそうだ。
必要なものはまず出自。当然それに付随する教養、そしてお金。子供の時から交わることなく(行く学校も違う)そうやって育てられるわけです。注意しなければいけないのは、異なる階級を蔑視したり差別するといった感覚は本質的にありません。階級間の移動はあり得ないことなのです。
そんな背景から想像されるように均質な社会向けの音楽ではないし、元々労働者階級向けの音楽である「ろっく」とかいう範疇で語ることはおそらくお笑いなのかもしれない。演じている方にだってそんなつもりは全く無いような気がする。と、とてつもなく長い前置きでした。
少し華やかに、より洗練された2作目にして一つの完成形。裏カンタベリ(表とはソフト・マシン、キャラバンを指しているつもり)の代表作でもあるが、全く売れずにこの後あっさり解散。スチュワートの理論と作曲技法を具現化した完成度の高さと、それを楽しくこなす演奏力は見事としか云いようがないし、わざと崩す洒落っ気も捻りが効いている。個人(特にリチャード・シンクレア)に対する思い入れはまったく無いけれど相変わらずのテノールは冴えています。ゲストは名前も腕も超豪華。カウのティム・ホジキンソンにリンゼイ・クーパーの管楽器、モント・キャンベルのフレンチ・ホルン、ジミー・ヘイスティングスのフルート、サックス。勿論コーラス隊のノーセッツが路傍の水仙のような清々しさを添えている。
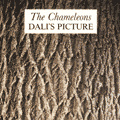
Dali's picture/Chameleons
デビュー前に録り溜めたレコード会社向けのプロモーション音源だそうです。粗削りだけど云々…とは勿論言わないし思わない。聞く人が聞けばアレンジの変遷がわかって面白いのだろうが、わたしゃ耳が肥えてるわけじゃないんで、単純に正規盤の方が洗練されてて良いなぁとしか思わないか、やっぱり。転調が非凡というか独特で、かつ粘っこくないところが清々しくて好みなのだが、これはキーボードが無いせいか音が拡がらない。書きもの中はブラウザを立上げて、あちゃこちゃ適当に思い付くまま検索しながら書いてることが多いんですが、今日はオペラがよく落ちる。一概にオペラ自身に問題があるとも言えないのだが、タコなスクリプトやら、くそhtmlに当たったくらいで落ちてんじゃ使えねぇゾ。おかげでちっとも進まないじゃないか。

Faust IV/Faust
ヴァージン・レーベルでの2作目にしてラスト。この後はドイツに戻って崩壊したものと思われていた。78年くらいまでライブはしていたそうですが、ステージで振り回したチェンソーで誰かが怪我してそのまま人知れず消えていったと風の噂に聞いた憶えがあります。90年代後半に一部のメンバーで復活しますが、70年代Faustの奇矯さは最早ないかもしれない。ポップになった駄作等とも言われておる通算4作目ですが、確かに曲っぽくはなってきた。チープで空虚な音と残響が壊れているというよりは著しく胡乱に、唐突に鳴ったり鳴らなかったり。大昔、日本盤が出ていた頃、誰がつけたのかは知らないが『青空と廃墟』って言い得て妙な邦題がついていたことを憶えている。
クラウト系というのはこのアルバムの一曲目「Krautrock」から採られたものだ。キャベツの酢漬けの樽をひたすらグニョグニョ掻き混ぜてるような性懲りも無さが発酵してデロデロに美しい。本来はキャベツとか“かぶら”の漬物を指す言葉ですが、一般的には、イギリス人やフランス人がドイツ人を蔑むときの蔑称です。

Peace at last/The Blue Nile
またまた毛色違い。アイリッシュ(スコットランドか)風味の歌物です。非常に地味ですが生音の生きの良さが命。露骨なまでのキリスト教的世界観には思わず後ずさりしてしまいますが、歌い方も少しソウルフルで明るくなった。英語なんてどうせわからないんだから、音だけ聞いてる分には気にもならんということで良しとしよう。エンジニアもとても優秀で恐ろしく音が良いわけだし。などと開き直って良いのかどうかは知らない。ちなみにナイル(川のこと)はスーダンのハルツームで青ナイルと白ナイルに分岐します。白ナイルはウガンダのビクトリア湖が水源、青ナイルはエチオピアの高原が水源のようですね。なんで青と白かってちゃんとした理由があったような気がするんだが思い出せない。で? と言われてうろたえる。

Waves/Jade Warrior
エスニック・アンビエントか? ジャズだかなんだかごちゃまぜの相変わらず形容のし難い音楽を作っておる(おった)。ヴァーティゴ時代のポコポコした感じは薄れて今風に言えばワールド・ミュージックに限りなく近づいた。この波は多分広重あたりからぱくってきたんでしょうが、東洋風な雰囲気はまったく無いといって良いでしょう。Waves全一曲だけれどクラシックにみられる構築主義的な構成がとられているわけではないので、ひたすら淡々と変転していくのみです。テーマを繰返すことによって印象づけたり、ドラマチックに萌えることもなく、敢えて音楽の常道に反するような趣向は正に寄せては返す波をひたすら描くように叙景的だわい。

Cyclone/Tangerine Dream
とうとう歌入りになってしまった。いや、今なら、実はとても良いのではないか等と思っていたりもする。ついでに生ドラムまで入ってコンテンポラリな普遍性は放棄したが、趣味性の強い部分で個人的には聞き易いし、シーケンサのグルーブ感もとても気持良い。ボコーダを通した凍り付くように冷たい声と、虚ろに響く単調なリズム。当時としては口ずさめそうなメロディに落ちるとこまで落ちたな等と恰好をつけた憶えがあるな。(あぁ、恥ずかしい) まぁ、確かに後半の歌無し20分の大曲「Madrigal meridian(絶頂恋歌)」が一番良い出来だとは思うけれど。多くの人が抱いているシンセサイザの陳腐なイメージ(特にTVのBGM)とは裏腹に、完璧な方法論と構成で組上げられた壮大な楼閣なのだ。クラウス・クリーガ(Klaus Krieger)という人がドラム叩いてるみたいですが、抑制の効いたモノトーンな感覚が良い。もっとも何故か名前すらクレジットされてないのねぇ。
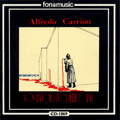
Los andares del alquimista/Alfredo Carrión
詳しいことは知りませんが、カナリオスの「シクロス(Ciclos)」でオーケストラ・アレンジを担当していた人のようです。その筋ではひどく評価の高い人みたいですが、勿論これ以外に関してはまったく情報も無いです。前半はマリア・アラゴン(María Aragón)なる女性歌手をフィーチャした小品。中音域の豊かなボーカルが半陰陽でくすんだメロディに映える。転調バリバリの非常に難しそうなメロディをすいすいと歌いこなしてしまうとこなんか、かなり圧倒されます。曲を書いているカリオンという人はポップ系の音楽とは無縁な人みたいで、アレンジや曲の展開が予想もつかないというか、尋常でなくて面白い。民族風の哀愁でゴリゴリ押してこないところも特筆すべきか。とても上品です。後半は真骨頂の長編大作。意外にジャズっぽいアンサンブルと修道院風の混成合唱の絡みがスリリングに美しい。ここでも典型的な西洋音楽であることを敢えて外すようなアレンジが非常に個性的です。非常に先進的な楽理とアレンジがスペイン特有の民族性に絶妙にマッチして独特な味わい。

Sun/Taï Phong
なんとタイ・フォンの新作です。ベトナム人とポーランド人のタッグマッチで70年代後半に2枚(3枚?)のアルバムを出してました。一応フランス(ベトナムの宗主国だし)で活動してたせいもあって、もちろんぱっとした話しはないし、売れた憶えもないが、透明な冷やっこさと超メランコリックな楽曲は群を抜いていたと思う。復活タイ・フォンも歌謡曲を越える美麗メロディで泣きまくっております。ベトナム人の片割れ(弟)の姿が見えないのが寂しいぞ。アンサンブルは比較的タイトで緩急自在だけどおそろしく繊細。練りに練られた品質の高さを誇っておるなぁ。 水の波紋のようなヒタヒタ感が見事です。
いきなり1曲目、「サイゴンの雨の夜 part1&2」で参りました、降参状態です。中国琴の悩ましい音色。しかし、なんで大魔神が出てくるのだろう? おまけにダサイ絵じゃのぅ。次作はまだかよ? と強く期待しております。

Bells,boots and shambles/Spirogyra
スパイロジャイラのラスト。正式メンバーは既にコッカラムとガスキンの二人だけ。コッカラムはこの後(やっぱり)宗教に走り、(たぶん)傷心のガスキンはハットフィールズ解散後の不遇の時代、極東の京都女子大で英語の先生をしていたらしい。このおそろしく硬質で透明なピューリタン的な清爽感はコッカラムの宗教観が成せるもの(って思い付いただけだけどさ)だったのだなぁ。長くて複雑な曲構成が増えて、フォーク調の軽快なアンサンブルというよりは重厚で凝ったアレンジとリズミカルでアコースティックな躍動感の対比で聞かせるような巧さが出てきた。ゲストになってしまったクザック(Julian Cusack)もバイオリンよりもピアノの出番が多くて、電気トラッド風の趣は少し薄れたかもしれない。一方で、ブレイク(ロマン主義の神秘思想家、詩人、画家 William Blake 1757~1827)の引用にみられるようにクラシカルで神秘的な陶酔感が包みこむように全体を支配している。
ブレイクの「The Auguries of Innocence(無心の前触れ)」の一節
一粒の砂にこの世をみる
一本の野の花に天をみる
その掌に無限をつかみとり
その一瞬に永遠を封じ込めるのだ
がすべてをあまねく言い表しておりまする。
スパイロジャイラって植物プランクトンの一種、アオミドロのことですが、その池に沈没しちゃったようなスリーブ写真です。

Ibtaba/Wire
タイトルはそのまま「It's beginning to and back again」の略という相変わらずあまりやる気の無いワイア。ライブです、一応。ミキシングでかなり手は入れているのだろうが、消すものは消し去って捨象された音になっておりやす。スリーブの方も、う~む、ここまで情報の少ないCDも珍しい。記載されているすべての文字数を合計しても400字はないな。半分ぐらい打ち込みの音という雰囲気ですが、妙な気怠さと軽くすこ~んと抜けきったような諦観が見事じゃないか。スタジオテイクとはアレンジがまったく違うんでなかなか異質で面白い。おまけにスタジオテイクよりぶっ飛んでるというか、ポップさが薄くて虚構性の骨組みが透けてみえるようなところが一層ワイアらしいといえよう。とても涼しげに聞こえてしまって実は夏向きだと思うておるのじゃ。

Milano calibro 9/Osanna
「ミラノ カリブロ ノーヴェ(ミラノ口径9m/m)」なる不明な映画のサントラとして作られたオザンナ2作目にして出世作か。ニュウ・トロルス(New Trolls)のコンチェルト・グロッソの二番煎じと言えばその通りでしょう。プロデュースも同じ人だ。勿論、ジェノバのトロルスに比べ、ナポリのオザンナは明らかに田舎ものです。どんなに粧し込んでも(これ英詩だし)染み付いた野卑さ加減は抜けるものではないし、そこが逆に尋常でない最大の魅力でもある。
公式Webにラストの曲「Canzona(There will be time)」他数曲は置いてあるようです。もっともモノラルの128kbpsのmp3で尻切れでやんの、意味無いじゃん。CDは全部でも30分程の短さなのだが混沌と清廉の対比が最大の売りかもしれない。頭とラストのあくまでも美しく華麗なストリングズと野蛮でグツグツと滾るようなアンサンブル。ストリングズの部分が単なるバロックに終っていないで、コンテンポラリ調なのがより洗練された印象に繋がっていると思う。抑制の効かないエリオ・ダンナ(Elio D'anna)のフルートが決り過ぎ。
昔出ていたレコードとはジャケが違いますが、勿論昔の方が質的に全然良かった。最近再結成されて新盤が出ていますが、そんな余地があるってことは、結局のところ所謂ポップ・ミュージックというものがすっかり形骸化して何ら進歩していないということなんでしょう。手を変え品を変え外面だけ時代の気分に合わせた色を塗る。娯楽と割り切れば進歩の必要性だって無いし、むしろ邪魔だけどねぇ。私自身は「アーティスト」による「アート」はわからんし、今のライブだって生のビートルズは知らないけれど、25年前に見たフォーカスや四人囃子と比べてどこが如何に違うのか実はよくわからんわい。形式に浸れるシアワセみたいなものか。別に「新しいもの」を追い求めているわけじゃないから、これくらいが丁度良いなぁ。へへ。