
The geese and the ghost/Anthony Phillips
ジェネシス離脱後の1stソロ。PP&Pシリーズとは異なってボーカル入りだし、ギターのみというわけでもない。古巣のジェネシスのマイケル・ラザフォードにフィル・コリンズもクレジットされていたりする。中身はトラッド基調の非常に上品な中世趣味の夢物語。人柄(家柄か)が出ているというか、流行りとはまったく無縁な独自の世界だ。ここまで完璧に現実を無視できるのも良いなぁ。派手さもドラマチックさにも極度に欠けてはいるが、うるうると心に染み入る美しさ。フィリップス自身と思われる頼りないボーカルも良いのだが、オーボエ、フルート等の管楽器に弦楽器を加えた室内楽風のアレンジがつまらないシンフォにならないところが素性の良さを物語っているのでしょう。
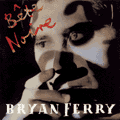
Bête noire/Bryan Ferry
前作『Boys & girls』の絶妙な緊張感は緩和されて少しかったるくなった。タイトル通り暗くてぬめっとした精悍さというか、フランス風のゆったりしたエレガンスにかぶれたのか、夜の音。闇に蠢く獣(って感じじゃないけどなぁ)に明るさは似合わない。基本的には前作の延長線上で目新しい感じは無いのだが、強いて言えば少しエスニック風味のリズムだったりするようだ。この頃結構少女マンガやTVとかでもくねくねしてました。中身は完全なポップだけど相変わらず音は良い。ギルモアにスミスのマーあたりがクレジットされていて、このギターがそうかなぁとそれなりに想像してみたり。個人的にはタイトル曲のジプシー風のアコーディオンとバイオリンをバックに例のふにゃふにゃ声でくねくねと歌っておるのが痺れて良いです。
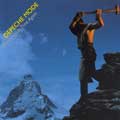
Construction time again/Depeche Mode
鎌ときて槌とくればさもありなん。露骨と言えば露骨だな。これが「People are people」に繋がるのか。お山は大方マッターホルンでしょうか、意味がわからないですが。金属打音に接近していた3作目。もっとも、それほど目だってがんがん響くわけではありません。音の方は到って大人しいというかダークでうち沈んだ趣。ほんわりした柔らかさは時々出てくる可愛い笛(もちろんシンセだろうが)の音ぐらいですか。メタル・パーカッションの金属音がそれほどシャープに響くわけでもなく、なんとも捉え所の無い曖昧糢糊とした音が最大の特徴のようです。虚ろに響くお経のようなボーカルも鬱な気分にはぴったりでしょう。アンビエントではまったくないですが、すぐ隣にあっても気にならない親和性の高さと地味で不思議なメロディが妙に調和しています。

Bedside manners are extra/Greenslade
キーボード浪花節。一応世評では4作中の最高作だそうですが、わたしには3作目の方が馴染めるというか性に合うようです。この2作目は二人のキーボードの絡み合いで聞かせるかなりテクニカルな内容だと思う。内容的には硬派なのだが当たりはとても柔らかいというか女性的。地味だけど撓み方がしなやかで艶やかなわけです。メロトロンとピアノの掛け合いはさすがに美しいと思うし、歌無しが多いとはいえ、あまり上手くないボーカルも味があって線が細くて、とても曲調に合っているでしょう。逆に言えば枠組みというか構成が甘いところ(73年にもなってドラムソロ入りだよ)が玉に傷というかB級の証し。いかにも的な展開がどうしようもなく浪花節なところでもあるのだが、浪花節は浪花節なりに聞いてる分には楽しいもの。

In the wake of Poseidon/King Crimson
一般的には1作目の評価が異常に高くてほとんど二番煎じ扱いの2作目です。この時点で楽器を弾けるのはフリップ一人だし実質的には崩壊してたのだろう。結局残りはすべて外注で処理、アレンジは前作の(つまりイアン・マクドナルドの)パクリとせざるを得なかったということか。もっとも外注がジャイルズ兄弟だったり、キース・ティペット等ジャズの職人だから質的には遜色は無いと思うし、マクドナルドの女性的な感覚が無くなって硬質な固さが表に出てきたのが救いになっている部分は確かにあるだろう。シンフィールドの創り上げる世界観も前作の単調さを越えるものになっていると思う。タイトル曲はこの世の摂理を天秤のバランスを表象として、切々と訴えておったわけですが、子供騙しのダブルスタンダードを盲目的に肯定し、一方的な優位性を膠着させようとする流れはいっこうに改まる気配が感じられない。中庸が肝要って学校で習わないのかねぇ。
「In the wake of~」をどうとるかで昔は結構話題になったこともあったが、結局今でもそのままらしく、なんでエラー訂正が機能しないのかは知らない。間違いは間違いとしてきちんと対応していかないと、何も変わらないぞ、と気付いてみれば早30年。間違いを認めたり謝ったりってプライドに触れちゃうんでしょうか。しかとしてればそのうち忘れるだろうってのは身内では通用するんだろうが、外の世界には通用しないと思うが、やっぱり。
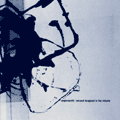
Second toughest in the infants/Underworld
所謂テクノですが少しアンビエント風にすら聞こえる冷やっこいビート感が気持ち良い。意味のありそうな文字は何もないんでタイトルすら意味不明ですが、まぁ、文字に意味はないって解釈して聞けばいいんでしょうか。スペインのアンダルシアの光景? が歌われてるようだが、青とか赤とか黄色とかオレンジ色が飛び交って鮮烈に美しい。UWに関しては人が言うほどダンサブルっていう意識はそれほど持っていないのだが、「ボークー・フィッシュ」の原型はこの時点で既に完成されてると思う。こっちの方が全体的にダークで黄昏た感じがするけれど、一定のトーンというか色彩感が安定した良い感じ。もう少し頻繁に出してくれると良いのだが。
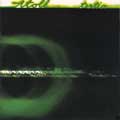
Tertio/Atoll
バイオリン弾きがいなくなった文字通り3作目。どこまで本当か知らないが、昔の映画『パリは燃えているか?(Paris brûle-t-il?)』と引っ掛けていると思われる「Paris, c'est fini」で始まる。
「パリ、崩壊」
失う
どこかで
カルチェ・ラタンか
オステルリッツ駅でか
ただ
歩道のアスファルトを
よじ登る
女が一人駆けずり回る
自己を探す人波の視線の中を
畜生!地下鉄!プラスチック!
パリ
十分に一人前の女
コカイン漬けの
パリ
闇の中
お終いだ
サクレ・クール寺院で
屋根を打つ雨音を聞く
喜びもつかの間か
酸っぱくて、どす黒い窪地に穴を掘る
膠の脂肪に完全に包まれて
炭酸の雲は崩れ落ちる
お終いだ、私は宿に戻る
パリ
まさに売春婦、とんでもなく売女
パリ!
「禁じられた遊び」
調子が良かったのも、もうお終いだ
お前の運命は自滅だ
ニューヨークのように、ロンドンのように
東京、バンコク、モスクワと同じように
ドルの王者を操る
この模造品の幸福のように
ドルの王者を操る
この模造された幸福のように
ニューヨークのように、バンコクのように
東京、サンフランシスコ、デリーと同じ
メッツ、サンフランシスコ…
映画『パリは燃えているか?』はフランス人監督(ルネ・クレマン)にフランス人キャストなのだが、パラマウント映画っちゅうわけでフランス人キャストはどヘタな英語のセリフを喋るわけだ。アメリカ資本に屈したフランス風映画ってとこですか。ついでにもう一つ奥があって、この映画の内容はWW2におけるパリ解放を描くわけなのだが、結局のところフランスのレジスタンスは貧弱だったので、アメリカ軍を引き入れる事によってドイツ占領下のパリ解放を成し遂げるわけ。最後の方に出てくる『禁じられた遊び』もルネ・クレマンによる映画。こっちは誰もが知っている名作? として名高い。アンドレ・バルザァという人は非常にシニカルな人のようで、意外になかなか(歴史的に)自虐的なところには共感します。しかしまぁ、引っ掛け過ぎで何が何だかわからんよ。まだ奥があるのかいな? 何故か2作目が好きな人には評判が悪いみたいだが、洗練されたメロディと卓越したテクが見事に開花した硬質な外観と、とってもシニカルでシャイな内容の落差が気持ち良い。女性コーラスはマグマのステラ・ヴァンデールとリサ・ドゥリュスみたいで(写真があるのだ)すが、マグマ風ではなくて極普通にコーラスしていて、なんだか美しくてびっくり。
ちなみにメッツ(Metz)はインディ・レーベル、ミュゼア(Musea)のあるフランス北東部ロレーヌ地方のルクセンブルク国境に近いモーゼル県県庁所在地。

Canis lupus/Wolf
Canis Lupusはオオカミの学名で、西洋では家畜を襲う害獣>悪魔の化身ですが、草食日本では大神と書いて猪や鹿の食害を防ぐ益獣で信仰対象にもなったりしてました。近年はもっぱら「送り狼」だの「男はオオカミ」だの絶滅している動物にしては酷い言われよう。そんな名前を敢えてつける感覚はよくわからんが、派手さは無いが落ちつきのある円熟味とそこはかとない叙情性が見事な雰囲気を醸し出しています。カーブド・エアのダリル・ウェイがジョン・エサリッジと組んだユニットですが、3作ほどアルバムを残していてこれが1st。プロデュースがイアン・マクドナルドだったり、ドラムがイアン・モズレィだったりして、そこはかとなく興趣をそそられる向きもあるかもしれないが、関係無いでしょ、多分。「マクドナルドの嘆き」なんちゅう曲まであったりしますが、おそらくビオラと思われるウェイの演奏は絶品です。しかし、相変わらずここまでPOP系の音が似合わないのも珍しいが、総じて優雅を絵に描いたような極上の味わい。エサリッジは後の超早弾きまくりではないですがミュートの効いた固めの一風変わったスタイルです。
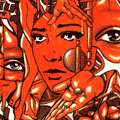
Il tempo della gioia/Quella Vecchia Locanda
バイオリンものと云えば知らぬ人はいない(嘘)2作目にしてラスト。ライブが一枚あるみたいだが、高くて買えない。あくまで典雅な室内楽風の曲調と少しジャズっぽいアバンギャルドな展開が極めて高い次元で融合した逸品です。アコースティック・ピアノやハープシコードに至っては完全にバロックと言っていいでしょう。弦楽器の音の艶やかさも完全にクラシックのノリです。緩急と強弱のレンジも極めて広いので、それなりの再生環境を選ぶという意味では著しく一般性には欠けるかもしれない。敢えて期待されるだろう予定調和を崩すようなところが単なるメロディアス・シンフォにならなかった理由でもあるのだが、それ故にその心意気は個人的にとても好みだ。ボーカルも意外に正統派な熱情溢れるカンツォーネタイプだったりするところも面白い。

Deep/Peter Murphy
キャラの立った音とでもいいませうか。明解で粒立ちが良いです。とても生に近い録り方をしているようにも感じます。さりげないけれど自信に満ち溢れた堂々たる音でもあります。ゴシックな雰囲気も無いとは言わないし、一筋縄で括れる人ではないが、総じて気持ち良いし肯定的に元気だ。曲もバラエティに富んでいてソロ4作中では内容的にも最高ではないでしょうか。アコースティック・ギターからビオラまで登場する新境地には少しびっくりした。音がもの凄い勢いで拡散していくようなサビの部分でのキーボードの使い方も、とてもロマンティックでうっかりするとプログみたいだ。何故か前作にもあったアラビア風のエスニックなリズムとメロディも一段と冴えていて、昔のアジテーション・フリー(Agitation Free)を思い出してしまう。
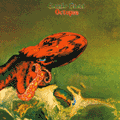
Octopus/Gentle Giant
これは歴史に残る(と思ってるのはわたしだけか)変態さ加減が秀逸な中期の作。どこをベストとするかは大変難しいのだが。内容は完成度高過ぎで何も言うことはないのだが、一応言ってみたりすると、テク万全緻密、リズム超絶、アレンジ完璧、展開びっくり、ハーモニー絶品、歌唱、歌詞共にレベル高過ぎと、まぁ、足らないのはリリカルさと人気だけだ。少しコミカルな部分まで出てきて余裕と貫禄もみえるか。う~ん、結局のところ音楽の形態の独自性が強過ぎて、曲が頭に入らなくて憶えられないってのはあるよなぁ。一曲だけラブソング風の甘い曲があって、Gentle Giant自身による解説によると「個人的な曲。特に親密な雰囲気を大事にするためにシンプルにした」などとわざわざ書いてあるのだ。(冗談か皮肉なのだろう)ところがどっこい! メロディ綺麗だし、そのフレーズは憶えられるのだけど、曲全体の構成となると一体どこがシンプルなのよと問い詰めたいの。小一時間といわず三時間ほどな。はぁはぁ。

Technique/New Order
スリーブのどうしょうもないダサダサ加減とは対照的に中身はとても良い。ハウスっぽいのもあるけれどそれは二義的なことだし1曲目の頭だけじゃないか。当時ハウス云々は世間的にも流行っていたはずだけど、何それェ? みたいな顔をされて凹んだ憶えがありますな、爺には。しかし、まぁ、アコースティックな香りとメロトロンみたいに聞こえるストリングシンセに下手なピアノが郷愁を誘うじゃないか。円熟と熟練(ヘタウマだけどなぁ)の上に成り立つ貫禄すら感じさせるのじゃ。お爺さんは後半もうメロメロですがのぅ。ボーカルも相変わらずヘタクソなんじゃが、メロディラインが微妙に難しい、歌いにくそうな曲ばっかり作るところがまた良いのじゃ、ほぉうほぅほぉほぉほぉ。

Attahk/Magma
短い曲が増えて少し明るくなったマグマ。跳ねるようなリズムと相変わらずのエネルギッシュな太鼓が炸裂しています。変態混成合唱オペラにもファンキィな味わいが加わり、益々磨きがかかってご健勝なによりだし恰好良いぞ。基本的にパーカッション+合唱隊+ベース+ピアノという構成でブラスが加わることもあるという感じだもんで、世の主流にはちと程遠い。それにも増して、クラウス・ブラスキーズの壊れたボーカルというか人間を越えた発声も、100人中99人は眉を顰めそうで尚更素晴らしい。まぁ、マグマの場合マグマ以外にxxに似ているという表現ができないので形容のしようがないのだが、新興宗教だと思えば大きな間違いはない。当然、儀式というかライブが肝心で本質的にライブで聞くものでしょう。96年に再編されてライブを再開していますが近々新作! が出るらしいと言われております。結構隠れ人気あるみたいだから新作出たらきっとまた来るのだろう。
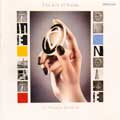
In visible silence/The Art of Noise
MTVとかプロモビデオ全盛時代の申し子的な視覚的なイメージが強烈に残っているユニット。「Legs」か?、男女長短細太黒白いろいろな足だけがうにょうにょ動き廻るのは。サンプラーに依る合成音とディジタル・ビートを積極的に取り入れたコンピュータ・テクノ・ポップってとこですか。当時としては自然界に存在しない音のオンパレードでおそろしく斬新でしたが、あっという間に耳に馴染んでしまった。手法のみの斬新さなんて長続きしないもの。それでも2年くらいは持ったか。80年代のこの手のテクノは結局のところ、同じ機械を使うとどれも同じに聞こえてしまうという致命的な欠陥があって、オリジナリティを出すためには結局古典楽器を導入する方向に動かざるを得なかったという、世紀末の徒花に終わった感がある。結果的に、70年代アナログ・テクノは今でも個性バリバリだし、徹底的にコピーされているけれど飽きがこないのは不思議なものだ。
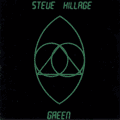
Green/Steve Hillage
意外に世評も高いソロ4作目。この人は一見、出ずっぱり風のイメージなのだが、実はそうでもないところが不思議なところ。全盛期ゴングでの印象が強すぎるのが原因なのだろうが、元はカンタベリィだから(いや、ゴングだってカンタベリィだろうけど)本質的には地味で上品で皮肉屋の南東イングランド中産階級のはずだ。テクニックには定評がありますが、ここではデュレイにギター・シンセもバリバリで類型的でない音づくりをしています。所謂一般的にギターの音と言われる音とは気持ちが良いほどまったく異なります。確かにコズミック・サイケをやらせれば第一人者だろう。空間的な広がりと深みに突っ込んで行くような浮遊感に囚われてしまう。ラストはゴングの「You」の「Master builder」だ。プロデュースがピンク・フロイドのニック・メイスンというのもはまり役。

True/Spandau Ballet
おぉ!懐かしの『True』だ。『True』以降は鳴かず飛ばずでいつの間にか人の噂にのぼることもなくなり、塵が積もり埃に埋もれていったのかどうかは知らない。ニュー・ロマンティックものの中では比較的子供ゝしてないところが特徴で、おかげで日本では流行らなかったねぇ。顔がまずかったのかな、知らないけれど。「True」だってNo.1ヒットだったのに。ゆったりとしたバラードっぽい曲調が得意で基本的な部分の質はとても高かったと懐古的に思ってみたりもする。Duran2のネチャッとしたきらきら感は無いけれど、タイトで乾いた優雅さが比較的高めの朗々としたボーカルと相まって、味わい深いポップであった。たまぁに車で聞いてみたりすると気持ちが10年ほど若返ってしまって、それに気付いたりすることが少し悲しかったりする。