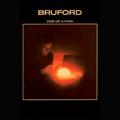
One of a kind/Bruford
イエス、クリムゾンと渡り歩いてヘルスに一時的にせよ加わっていたことがここに繋がったのはまちがいない。内容的にはヘルスの延長線上だし、ソフト・マシンだのUKをぶち壊して来たばかりのアラン・ホールズワースまでいたりして、うわぁ、こりゃ長持ちせんわ、と初っ端から末期的な感慨を抱いたものです。デイブ・スチュワートを含めて、時代に乗れないあぶれ浪人みたいで腕はたつけど、有名過ぎちゃって引き取り手がないってところですか。決めの変拍子が格好良いのになぁ。19/8拍子とか全編変態しまくってますが、流れるような展開で全然気になりません。スコーンと抜ける硬めで端正なドラムセットとカンタベリィでウィットなキーボードとが絶妙に絡み合う緊張感が真似のできない典雅。ホルズワースのべっとり粘着ギターもおとなしいから許そう。個人的にはポップで聴き易いと思うのだが、でもまぁ、今気がついたけど(ただの一曲も)歌無しだからどうだか。
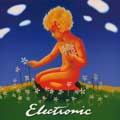
Raise the pressure/Electronic
忘れた頃にぽろっと出てくる2作目はええなぁ。一段とこれ以上はまずいだろというとこまで大ポップ大会。そうかぁ、やっぱりわたしはポップ好きなんだぁ、と5月の蒼穹にぐぐっと伸びをしつつ、さわやかに再確認した1枚。自然で優美とすら言えるエレガンス。サムナーのお声はやっぱり贔屓目にみても「おへた」だけど、上手けりゃいいってもんじゃないし。ギターのマーが前に出てくる曲は少しロックっぽくて、サムナーのはやっぱり明るい(ァ軽いともいう)ニュー・オーダー。カール・バルトス(Kraftwerkのマンマシン)がクレジットされているけれど、だからといってどうというわけではい。でも実は、まじめな人向けの歌だと思うんだが、内容は結構真摯というか、むしろ深刻なのだろうと思う。なんだか凄い文章も書いてあるし。これ日本語だったら引いてしまって誰も買わないような気がする。しかしセンスとか扇子とか何も言いたくないジャケのおデザインもお見事。買うのが恥ずかしかった。

"Fede,speranza,carita"/J.E.T
昔は面白いって思わなかったのだが、ようやくツボがわかったというか、米寿を目前にして私も大人になったということでしょうか。JETがわかれば君も大人の仲間入り。パチパチ、そぉら、皆のもの、お祝いじゃ!。これ1枚出して数年後にはマティア・バザールに化けるわけでして、やはり素性は歌もの系のポップスです。するっとジャズになったりテクもアンサンブルも味はあるけど引き際は心得てるって感じです。ポップスというと悪い印象を持つ人がいるみたいなので誤解の無いように願いたいのですが、“美空ひばり”とか“くうる五”みたいで格好良いと言っておるわけです。今年の日本放送教会御主催の紅白歌合戦に出ていても全く違和感はないはずです。第2部の3番目くらいがしっくりきそうです。「Gloria,gloria」とか。ちょっとベースが響き過ぎて審査員の場違いヘタレ爺っちゃんにはきついかもしれないが。
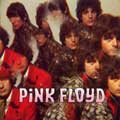
The piper at the gates of dawn/Pink Floyd
言わずと知れた1stアルバム。いやぁ、時代物です。これが一番好きなどと逆説的な方もおられるとは思いますが、そりゃ只のビートマニアか追っかけおばさんだかロックおじさんだ。そういうのは相手にしないで、さすがに数ある60年代サイケビートの中でも、この特異さはピカ一です。シド・バレットの覚醒才能全開、陰鬱情念全閉もさることながら、ニック・メイスンのへんてこりんな太鼓も鬱な気分にゃぴったり。長くはないが、よくもまぁ、こんな変な曲ばかり創ったなと率直に感心します。エッグ(Egg)を聴いているとケっ躓きそうなリズムに針が飛んだかエラーでスキップしたかって思いますが、これはいきなりボリュームが上下しちゃったりしてアンプが壊れたかと思いますです。輝くダイアモンドなバレットの尋常ではないカキコキギターとあか抜けないセンスの対比がシュール・レアルな美しさを醸し出している。
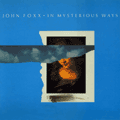
In mysterious way/John Foxx
クールで一歩引いている感があるせいか相変わらずの無機的なまでの人気無さ。4枚目のソロですが突き抜けてるなぁ。以前の鋭角的な先鋭感は無いです、まったく。むしろどこまでも透明で明るくて輝くばかりに無機的な夏です。覚悟(かくごせい! じゃなくて悟りを覚える方ね)したんでしょうか。孤独な美意識だけで創り上げた理想郷なのかもしれないが、住めるんだろうか? 人間に。完璧な庭。夏の庭を伴にするお相手は形而上学的天使なのだろうが、湿度が低そうでいいなぁ。「夏への扉」の向こうは光と花が乱舞する明晰な光の帝国か。マグリットの絵のようなジャケの青は夏を表わしているのだろう。これで隠居かと思ったら最近また出てます。うぬぬ。
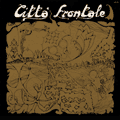
El tor/Città Frontale
分解したオザンナの片割れでナポリ残留組の唯一のアルバム。もう片割れは世界制覇を目指しインギルテッラ進出を果たしたが、あえなくNovaとして砕け散ってしもうた。地元組はさすがにごはんの苦労はしなかったせいか、とても暖か味のある高質なアルバムを残しました。ごはんが食べれないとやっぱり刺々してしまうのは人間の性ってやつですか。El tormentoで拷問とか苦悩とかって意味みたいですが、El torは人名? 雷じゃないのは確かだな。ナポリ風の歌ものの側面と毒は薄れたが暗重いアンサンブルが、表裏一体のように苦悩を謳いあげる。リリカルにドラマチックに盛り上げるというよりはテクで流す方向性で、ある意味社会的だし大人になったのだろう。
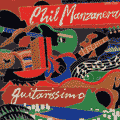
Guitarissimo 75-82/Phil Manzanera
75~82年にかけてリリースされた数枚のソロアルバムからピックアップした編集ベスト盤。ロクシィのギタリストとしてが一番有名なのだろう。生真面目そうな人だけど、妙な虹色のトンボの眼のようなサングラス姿が蠅みたいで印象に残っています。およそギタリストとしてはまったく目立たない人ですが、ひどく理知的な弾き方をするからか? ギター弾きのソロアルバムだというのに、たいそう控えめです。大抵は用もないのにしゃしゃり出てくるのばっかりなんだが。Quiet Sunも801も確かにこの人が立役者なんだろうが、立場的にはU2のエッジのよう。カンタベリィ系のお友達もたくさん参加してるし、テクニックは申し分ないしセンスも覚醒的に冴えてて気持ち良かですたい。

Dice/Dice
明るい透明感を除けば、あまり北欧っぽくないところが特徴でしょうか。重くはないが、変拍子を多用したキレの良いリズムと醒めた中音域のボーカルはジェントル・ジャイアントみたいだし、叙情的なメロディはフォーカスみたいにも思えるがの。ただし根っこはジャズというよりは完全にクラシックです。バロックないしもっと遡ってバッハあたりまで行くのか。構築力が素晴らしい。面白いのは「フロンによるオゾン層の破壊が癌を増やす」とか「精神分裂症は病気じゃない。それはどっちの世界を信じるのかという小さな問題だ。内側か、外側か」などと言い切ってるところです。あわわ、スウェーデン版「虚無への供物」かと思っちゃいました。78年っていうと私なんかチョンマゲ結って「ギブミー チューインガム!」とか言ってた頃じゃないですか。勿論、今じゃ“気違いはふん縛ってとっとと処刑”ってのがみんなで決めた(らしい)この世の習わし。

Merlin/Kayak
75年くらいまではプログ風のノリをしてたけれど、最高作との評価が高いこりゃ完璧なダッチ・ポップ。一応、LPの旧A面は5世紀ブリタニアの主任建築家で魔術師で??(CDじゃ字が小さくて読めんちゅうに)なマーリンをテーマにした組曲風なんだが(たぶん)、いや、まぁ、美しくて格好良いな見事なアレンジで御座ります。個人的にロック音楽とか苦手なもんで、こういう素直に綺麗で優しいのは心に響きます。ストリングシンセの少し冷湿な音はEarth & Fireにも通ずるところがあって、やっぱり国民性なんだろうか。一応ラストアルバムだったのだが、2000年に復活したらしい。まだ未入手ですが。

Missa universalis/Eela craig
宗教は苦手なのだが、うぐぐ。ミサというカトリックなる異教の礼拝の儀式ですね。日常的な宗教基盤がないもんで、まぁ、宅配ピザ食ってるようなもんです。個人的にはドミノがお薦めよ、って関係無いっす。一瞬、でろでろのシンフォかと身構えるがそうでもないじゃん。田舎臭い(オーストリア? ザッハトルテは美味しいけどな)感はあるがけっこう骨太な感じが武骨でよろしい。“キリエ・エレイゾン”って野太く歌うごついボーカルが渋い。琴のようなへんてこりんなギター(泣きもあるけど)も興趣に富んでますが、やっぱり鍵盤三人の重厚なようでいて、意外にすっきりしたタイトなアンサンブルでしょう。前作も次作も確かとってもポップだった記憶があるのだが、基本的には変わってないと思います。シンフォとかって言っておけば、存在そのものが既に勘違いしてるプログレおやじが引っかかりそうで、それもまた一興。
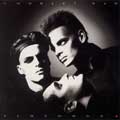
Tensongs/Hubert Kah
ドイツものですがこれはただのエレ・ポップ。ぴこぴこ感は全く無いし格好良いですが。タイトルも曲もすべて英語だし、お人形さんみたいな見映えにもこだわっていたのでしょう。男のツラなんかどうにもこうにも興味が持てないもんで、目の前で殺人があってもモンタージュもできやしない。どこに売り込もうとしたのかは知らないが、次作のぱぁぁぁあっとした明るさはまだ控えめでほの暗い。暗いものは自動的に好きになっちゃうのでこれも好きです、はい。君、性格暗いねという言葉は四半世紀前に聞き飽きたので今更ですが。デジタル系の処理とプロデュースは後のエニグマのクルトゥさんだから、音響的には美しくも冷やっこくて気持ち良い。人工的だけど広漠とした空気感が、いみじくもみみっちい社会で生きていく上での一服の清涼剤、にまではならんと思う。
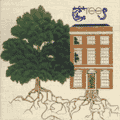
The garden of Jane Delawney/Trees
トラッド。正確には電気トラッドか。本当にトラッドなものと自前の曲が半々といったところですか。アンサンブルはロックぽかったり、アコースティックだったりいろいろ。響きの良い女性トラッド・ボーカルと電気の入ったアンサンブルのギャップがかなり新鮮だったりする。ご多聞に漏れず、かなり暗くて重い芯があるような曲調が、聡明で優雅って感じのスパイロジャイラとは正反対か。ギターがサイケでブルーズっぽいフレーズを弾きまくる音が曇り空に虚ろに響くようで、少しやり切れない雰囲気もあるのだが、総じて丁寧で味わい深い。
「The garden of Jane Delawney(ジェイン デロウニィの庭)」
彼の言葉は宙空で首つり
あなたが歩く地面は
そこではないのかもしれない
もう、そこにはないの
あなたを私の夢に案内しましょう
朝のもっとも暗いうちに
小川が血で染まったなら
ジェイン デロウニィの庭へ
さぁ、その庭へ
たとえ薔薇が美しくとも
通りすがりに摘み取らないで
そこの柳の木陰で
炎があなたを呑み尽くすのだから
そして、あなたの目はガラス玉になる
ガラス玉になるの
汝、深い眠りにつきたもうな
黄金と翡翠の涙が
眠りにつくその時、目に溢れるの
あなたの目に溢れるの
ジェイン デロウニィは夢をみた
その小川をつくる流れが
愛する人の命の血
愛した人の血の流れ
そんなものはなにも見てないわ
清浄な陽の光なんて
ここでは二度と輝くことはない
その夢の精霊が
庭に生き続けるかぎり
永遠に
女の人の声は可愛いぃって感じですが、とても寂しげです。同じ年にもう1枚『On the shore』(こっちはもっと有名みたい)を出しています。

Run/Jerney Kaagman
アース・アンド・ファイア(Earth & Fire)のボーカルしていたお姉さん。もっともこの数年後、Earth & Fire自体が復活して彼女も元の鞘に納まります。フォーカスのべルト・ルュイター(後期Earth & Fireでもしっかりベース弾いてますが)によるプロデュースですが中身はダッチ・ポップ。“長い名前のKayakのキーボードの人”とかもおりますが、小さくまとまり過ぎか。声量でメロトロンに拮抗する伸びまくるハイトーン・ボーカルが聞けるわけじゃないのが残念といえば残念。大人っぽく、女っぽく(おばさんか?)年を重ねたようです。しかし、まぁ、センスのへったくれもありゃしないダサイジャケです。もうちょっと可愛く撮ってやればいいのに。

Trace/Trace
リンデン兄弟+ヤープ・ファン・アイクというトリオ。持ってる鍵盤は全部弾かなきゃ気がすまない怒涛のキーボード博覧会。しかしリンデン弟のドラムがうっさいヨー。こやつの下品な猿以下シンバル連打が無ければ……という声が巷に渦巻いたことでしょう。さすがに兄ちゃんも庇いきれなくて、次作ではあっさり首になっています。さて、兄であるリンデン老はバルトークだろうがバッハだろうが、多分本人よりも巧く弾ける人ですね。この人の目が廻りそうなキーボードを聴いていると、中国芸のクラゲ美女が人間にはできない格好で指の先から水出したり、足の先に立てた棒の上で皿を廻すのを思い出してしまって忙しい。どこ見てりゃいいのかわからなくなるじゃないか。テクに溺れるタイプじゃないとは言わないけれど、構成は端正でねちっこくないし、変化に富んだそれなりにツボも心得た演奏です。全編歌無しのクラシカル・キーボード・疾走メドレー。

Boheme/Deep Forest
エリク・ムケとミシェル・ソンシェなるフランス人二人のユニット。2作目は東欧からロシアがテーマなようだ。ボヘミア(チェコだな)とかルーマニアとかブルガリアとか果てはモンゴルまで。おっと台湾も? あたりの民族音楽をモチーフに、おジャポン風に言えば癒しなおメロディのおヒーリングよ。って巫山戯てるわけじゃなくて、アディエマスほどではないけれど、エニグマよりは真摯な姿勢が感じられるのではないでせうか。サンプリングされた美しいメロディと今風のリズムの上にブルガリアンな女性ボイスとよくあるツボを突いた構成ですね。西の住人から見れば東方のエキゾチズムといった按配なんでしょうが、私は日本人なもんで別にエキゾチックだとは思いません。何故か大好きなアコーディオンの音がフランスっぽくていいなぁとか思ったりして。
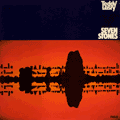
RCA RVP-6400
Seven stones/Teddy Lasry
マグマでキーボードを弾いていた人ですが、一人でやれば勿論マグマじゃないです。オルゴールのように可愛らしいシンセものと、管楽器を駆使した少しチェンバー風の暗黒ものが入り交じっておりまする。きらきらした煌めきが少しおフレンチなフレーズを一層際だたせていて、独特の触感。全編歌無しなので、一般的にはBGMっていう(信じられないけれどそうらしい)のかもしれませんが、これじゃ魚は売れないな。魚が売れなきゃBGMとしての価値もないわけで、勿論「おさかなの歌」に比べたら勝ち目はありません。だいたい石(綺麗系の鉱物だけどさ)が趣味じゃ偏屈爺さんくらいしか乗ってこないだろう。そういや前作だか後作は『E=mc²』というタイトルだった。一般相対論で売るのか? ますます鬱。