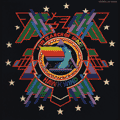
In search of space/Hawkwind
暗く胡乱な前作を経て辿りついた地平はワンコードが延々と繰り返される無空であったか。人声シーケンサと人間リズムマシンがアナログオシレータと絡み合って宇宙の「Null」を体現するのだ。(きっと) アナログフェイズのかかったリフが格好良いのは当たり前として、曲全体にフェイズをかけて位相をずらすのは普通はしないと思うが、お馬鹿っぽくて楽しい。初期のホークウィンドには基本的に所謂リード楽器が無くてサックスとオシレータが音響として扱われ、あとはボーカルもギターもリズムなのだ。後のクラウト系における「アパッチ(ノイやクラスタのひたすら8ビートを叩き続ける人間リズムマシン。ハンマービートともいう)」の元祖はここにあるのかもしれない。
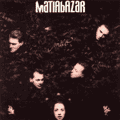
Meló/Matia Bazar
アントネラ・ルッジェーロ時代末期のマティア・バザール。カラフルなきゃぴきゃぴ感は消え失せてダークなモノトーンが支配する淫蕩な温もり。アップテンポな曲も結構あるのだけれど全体を支配するこのほの暗さとタイトで締まった洗練は不思議な取り合わせ。ルッジェーロの声は突き抜けるハイトーンが減って地味で柔らかい。諭すような歌い方。キーボードのコッスがかなり前に出たしなやかな華麗さが目立つけれど、ノリノリのポップから脱皮した新境地の完成度はかなり高い。もともとバックを固めるオジサン達がムゼオのジャンカルロ・ゴルツィだったり、JETのカルロ・マラーレだったりするわけで、良くないわけがないだろうみたいな部分はある。(よなぁ) ちなみにどうせ行くなら、こういうのが聞こえてくるような料理屋で酒の肴にフォークだけでパスタを食いたいものだ。
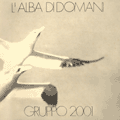
King Record
KICP 2835
L'alba di domani/Gruppo 2001
今回はイタリアものがやたら多くなってしまったが、まぁ、いいか。付けた名前をすっかり追い越した時間が流れてしまったけれど、中身は時間を越えて耳が憶えているものだ。偶然引っ張り出した グルッポ 2001 だが、この前聴いたのは多分15年くらい前だろう。見開きは同じ写真のカラー版なのだが、真っ青な空を背景に真っ白な鴎が飛んでいる。フォルムラ・トレの『Grande casa』と同じコンセプト。これ一枚こっきりであとは一切合財消息不明という数ある無名な一枚ですが、どっちかというと暖かみのある歌ものと云ってよいかも。親爺臭い声で切々と謳い上げるという表現がぴったり。
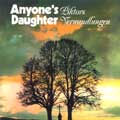
Piktors Verwandlungen/Anyone's Daughter
曲が終ると歓声が入ってライブだったのかとわかる不思議なトータル・アルバム。ヘルマン・ヘッセの短編「ピクトルの変身」を朗読する文芸劇である。ヘッセは「車輪の下」ばかり有名で道徳的な妙なイメージが出来上がってしまっていますが、実はとってもロマンティックな人です(だと思う)。同じく朗読と交互に繰り返される音はとても達者だけれど、出しゃばらない素直でシンプルな演奏。地味だけど実直で完璧なアンサンブルが心地良い。蛇の甘言に乗せられて老木に成ったピクトルの孤独と煩悩と絶望は、若い女の涙を得て一対の男女の木(ジャケのような?)と成ることにより完全と成就を得るという童話みたいだが、ラストの一節だけオリジナルの歌詞を謳いあげます。大意は
「今、そこに座って、聞き入っている君たちにはわかるだろう。君等はピクトルと同じ道を歩む。彼は暗がりにおける道標だ。その手に水晶をもった老木と言われても、自分を変えていくことが、我々の命なのだ」
といったところでしょうか。
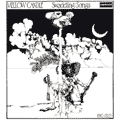
Swaddling songs/Mellow Candle
巷ではスパイロジャイラ、チュダーロッジと並んで「プログレ親爺」のトラッド三種の神器と言われるそうだ。スパイロジャイラやチュダーロッジとの違いはやはり両手に花というか、左右のスピーカから違う女の人の声が聞こえるところ。あるいはスパイロジャイラの新鮮だが荒削りな部分や、チュダーロッジの初々しい若さとは対極的な完成度の高さだろう。ピアノからチェロまでクラシカルなアプローチは多用されるものの、基本はトラッドというかフォークに忠実です。メロトロンまで引っ張り出してくるこだわりと、かなりロックっぽいリズムセクションが詩情溢れる二人の女性ボーカルと相まってトラッド独特の香しい雰囲気を作っています。
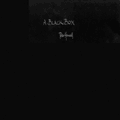
A black box/Peter Hammill
テクニカルな音に急接近するハミルの何枚目だかもうわからん80年代最初のソロアルバム。この人の表現意欲と質の高さをキープし続けられる能力は本当に敬服に値する。かなり実験的なものからポストパンクばりのカッコ良いものまで千差万別ですが、音質、音響面ではデビッド・ロードなるミキシング・エンジニアの腕が光っている。本質的に世の流行りとはまったく無関係なところで成立している音楽ですが、シンセサイザのかなりノイズっぽいエグイ使い方が神経を掻き毟るような焦燥感を煽りたてます。圧巻はLPならB面を占める「Flight」ですが、暗く冴えたボーカルと静から動へと変幻自在なメロディとリズムが結晶しています。

Uomo di pezza/Le Orme
いきなりバッハの教会オルガンみたいなイントロで始まる、かなり密度の高い2作目。トータル・アルバムじゃないけれど『Felona e Sorona』の原型は既に出来あがっています。上手くはないなりに、聞かせどころは心得ているというところでしょう。アルド・ターリャピエトラの歌とアコースティック・ギターの弾き語りみたいな、いかにもイタリアの歌ものという雰囲気の陽が当たっている部分と、手数の多いパーカッションと怒濤のキーボードアンサンブルでずんどこ押してくる部分の影のある湿っぽい部分の対比がのけ反るほど美しい。人に言わせれば確かにB級なのだろうが、どうも私はすっかり囚われてしまったようだ。

Modern masquerades/Fruupp
一般的にフループの代表作と言われる四作目にして実質的なラスト。全体的な構成や曲のつなぎ、間奏、展開がびっくりするほど繊細でドラマチックだが、これはプロデュースがイアン・マクドナルド(Ian MaCdonald)だからであるか。あまり目立たないけれどサックスを入れているような気がする。完成度の高いトータルアルバムですが、いかにもアイリッシュなあか抜けない朴訥な鈍臭さが薄くて、品良く決まり過ぎじゃないかとも思う。それでも、湿った泣きのメロディとダイナミックなアンサンブルの波状攻撃は実に日本人好みだろう。個人的には、ところどころに出てくるあんまり上手くはないちょっとジャズっぽいインプロ風の部分とがっちりアレンジされた部分の対比とか、弾きたがりのベースとかも面白いと思う。

Sono io il Signore delle Terre a Nord/Il Castello di Atlante
結構ベテランみたいですがこれが1stアルバム。この後にあと2枚ほどは新しいのが出ている模様。いきなりクエラ・ベッキア・ロカンダの再来を思わせるバイオリンを全編で弾きまくっておりますが、クラシックに流れるというよりは民族風(ちょっとロマ風)か。ミラノあたりの出みたいで音も歌もねちっこくはならず、クラシカルなピアノもあくまで端正です。スリーブの写真を見る限り、堂々と中年のオジサン5人組といったところ。楽曲に躍動感や疾走感はないけれど、しっとりとした大人の情感で結構盛り上げてくるところは見事に決まっている。
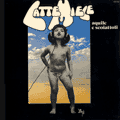
Aquile e scoiattoli/Latte e Miele
一般的には1,2枚目の評価が圧倒的に高いみたいですが、メンバーがほとんど違う3枚目もなかなか良いと思われる。別に捻くれているわけではなくて方向性の違いだろう。ツイン・キーボードにリズム隊という編成ですが、長い曲はちょっと緊張感に欠けるし、クラシック趣味が鼻につくところはあるのだけれど、独特の線の細い上品さがふわっと柔らかく心をくすぐる。個人的には歌ものの方がずっと出来が良いと思う。特に前半の小品のうろうろと流れるようなロマンティックな展開は絶品です。ほぼ全編のバックを流れるソリーナ? の音が春の霞みのような雰囲気を醸し出していて、少し寒いが季節的にはぴったり。

Movement/New Order
言ってしまえばジョイ・ディヴィジョン(Joy Division)の残滓というか、残骸としての1stアルバム。個人的にはそれほど悪くはないと思うのだが、ニュー・オーダーを期待すると大外れだろう。歌える人を失って暗中模索の真っ最中、ボーカルは変わりばんこでとっているようですが、上手くないねぇ。音が薄っぺらくなるのを見かねたのか、シンセを使ってエレクトロニックでノイジィな味付けをしているが、この辺はプロデューサの貢献だろう。全編を覆うあまりダンサブルじゃないリズムと暗くて陰鬱なメロディは、この時期のインディ特有の時代認識なのだろうか。不毛な80年代の始まりだ。まぁ、人それぞれだが、意外にするっと同化していけるところは怖いかもしれない。

To the world of the future/Earth & Fire
同じ頃、Earth Wind & Fireという集団もおった。あれはソウル(というか、たわけた踊りか)、こちらはダッチ・ポップ。もちろん比較にならぬほど有名なのはWindが入ってる方です。もっともこちらのこの4作目、一曲目の頭が少しソウルフルでありゃ、間違えたか? と一瞬だけ思いました。あとはもちろん別世界。冷湿な大陸風の泣きのメロディとジャーニー・カーフマンのかなりパワフルなハイトーン・ボーカルが映える。きつめのストリングシンセと鋼のようなメロトロンの洪水があまりにも有名ですが、展開とか、リズムとか、なかなか細かいとこまで手の入った力作でしょう。カーフマンの声は表現力豊かな、所謂、旨いボーカルですが、曲に上手く溶け込んだ良い味が出ていると思うし、メロトロンに負けない声量もある。変に仰々しくならないところも好感度が高い。
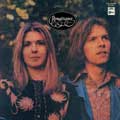
Ashes are burning/Renaissance
サイケ風のシンセサイザが無くなって、少しトラッド寄りになった第2期の2作目。メンバーのクレジットにマイケル・ダンフォード(Michael Dunford)の名前はないが5曲を書いて、アコースティックギターを弾いてるようだ。残り1曲は第1期のマッカーティ、作詞はすべてベティ・サッチャー(Betty Thatcher:第1期のJane Relfの友達)が書いているという、よく考えると不思議なアルバム。アニー・ハズラムのソプラノボイスが全曲で全面的に聴けるようになって評判もとても良いらしい。上品でポップなセンスとバロック風のクラシカルなアレンジが既に確立されています。タイトル曲は曲に対して演奏力が不足しているように思えますが、もともとシンフォ系が苦手な私としてはこの2作目位がいちばん性に合うかもしれない。ちなみにジャケの写真は可愛いのと全然可愛く無い2種類があるみたいです。(これは可愛い方かな)
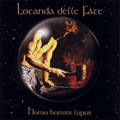
Homo homini lupus/Locanda delle Fate
何だか妙なタイトル(“妖精の帰還”というらしい)の日本盤が出ていますが、知らなかった。まぁ、相変わらずです。このところイタリアは随分活気があるようで、いろいろなものがとてもじゃないが追っつかないほどリリースされていますが、中身はもちろんのこと、どれもCDの作りがとても良くて(ブックレットも円盤のデザインも美しい)好感です。一昔前のMade in Japanのようだ。タイトルはラテン語みたいでよくわからんですが「人>類人>狼」という彼等なりのどんどんダメになって行く人類の進化の過程を嘆いているのでしょう。22年ぶりの新作は基本的には歌物ですが、良い味が出てます。内容は結構シリアスですが、音の方は密度は濃いし暖かめ。「広島の庭」という曲があって、「原爆なんてもはやすっかり忘れ去ってしまった」と歌っていますが、イタリア人にイタリア語で謳われるとかなり複雑な心境です。一応、いつも前向きな日本人にとっては興味の無い過去の話だろうが、言及しておこう。
「I giardini di Hiroshima(広島の公園で)」
広島の公園で
子供たちが遊んでいる
女の子は白い花のドレスを着て
白い帽子を載せている
そしてもちろん
核爆弾のことなど誰も憶えていない
突然、目の前が暗くなり
木々も花々も視界から消える
子供たちの笑い声も
喧騒も聞こえない
手を取り合っていたカップルは
どこへいったのだろう
残された死の灰だけが
雪のように風に吹かれて舞いあがる
そして、核兵器は頼りになる友人だと云うのだろう
でもわれわれのためにではない
西側の子分であるわれわれ
いつも恐怖に満ちたわれわれ
暴虐親分の息子であるわれわれ
いつも怯えているわれわれ
ツバメたちはどこへ飛び去ったのだろう
巣を空っぽにして
季節の失われたこの世界から
鳴くこともなく消え去った
論理的だなどと考えてはいけない
もし火薬が発明されていなかったのなら
大砲が爆風をもたらすことはなかっただろうと?
偶然のこと、悪意など欠けらもなかったと
そして、火薬は信頼に足る友人だと云いたいのだろう
でもわれわれのためにではない
西側の子分であるわれわれ
いつも恐怖に満ちたわれわれ
暴虐親分の息子であるわれわれ
いつも怯えているわれわれ
西側の子分であるわれわれ
いつも恐怖に満ちたわれわれ
核兵器の従僕であるわれわれ
いつも怯えているわれわれ
子供たちが遊んでいる
女の子は白い花のドレスを着て
白い帽子を載せている
そしてもちろん
核爆弾のことなど誰も憶えていない

Trespass/Genesis
この後の全盛期の奇妙なジャケを描いたポール・ホワイトヘッド初登場です。部分的にビアズリ(Aubley Vincent Beardsley 1872-1898)の絵を使っていると思われます。音楽的にもジェネシスとしてのオリジナリティが確立された2作目。意外に世評は低いみたいですが、そういうものか。アントニィ・フィリップスのギターもアントニィ・バンクスのキーボードも控えめで派手さの欠けらもないけれど、正統派英国趣味に溢れた滋味で一杯だ。ゲイブリエルもまだ役を演じるという歌い方ではないけれど独特の節回しは既に見て取れる。今改めて俯瞰してみると、複雑な展開も違和感無くこなせるだけのテクニックとビジョンは他にひけを取らないどころか、時代としては抜きんでていたかもしれない。少し曇った冷やっこさが美しい曲調と相まってとても気持ち良い。霧に霞む朝の大気のようだ。

Cover/Tom Verlaine
ロンドンのパンクがレコード会社や興行プロモータの作り上げた瞬間的で消費的なムーブメントだったのに対し、ニューヨーク・パンクはヴェルヴェットの流れから派生したずっとアンダーグラウンドな、長続きのする形だった。ウォーホールやヴェルヴェットの遺産を素直に引き継げば、既成の体制に寄り掛からずに済んだだけかもしれないが、実はとても賢かったのだろう。このレコードは数年に渡る録音の寄せ集めだそうで、あまりまとまりは無いのだけれど、やはりテレビジョン以後の暗中模索の時代なのか。北の海辺の小さな町で半隠居してるのかどうか知りませんが、なんだか突き抜けた感触。相変わらず格好良い音ですが、少し悲しい。ジャケは車が左側通行なんでよく見ると四角いマンホールの蓋にはロンドンって書いてありました。