
Il fiume/Le Orme
復活オルメの第一作、通算すると一体何作目でしょうか? 話しの種になれば良いかと全然期待してなかったのですが、思いっきり裏切られました。こりゃ、昔のも全部揃えてきちんと聞き直さなくちゃと再認識しましたです。かつては、ちっとも上手くなくて味だけで勝負といった趣が、一聴して、聞き違えたかと思うほど田舎臭さがなくなって正直びっくりです。特にリズムセクションは引き摺るようなもったり感がなくなって、すっきりした上に変拍子までシャープにさりげなくこなしています。大河をテーマにしたトータル・アルバムですが全編、とても丁寧だし、隅々まで工夫された、良く練られた素晴らしい出来です。そして、何にもまして、あの線は細いが懐かしくて暖かいアルド・ターリャピエトラの歌に、もう何も言うことはない。こういうかたちで大成することもあるのだな、と感慨深い。

Essere o non essere,essere,essere!/Il Volo
タイトルは「To be or not to be」の意。シェイクスピアの「生きるべきか、死ぬべきか…云々」から来ているのでしょう。中身は、まぁ、完璧です。幽かに泣くラディウスのギターを皮切りに繰り広げられる繊細と躍動、密度の濃さは天下逸品。所謂とても楽団っぽい演奏ですが、ほとんど現代のバロックといってもいいくらいの緻密でいびつで、コンパクトな室内楽。オルメとは正反対のテクに裏打ちされた非情なまでのリリシズムと情熱を秘めたクールさは文句のつけどころがないでしょう。時代背景からみて多少左がかった雰囲気は見て取れるものの、内実は芸術至上主義的な美に対する飽くなき執念ばかりが目立つように思います。

Introspezione/Donella del Monaco:Opus Avantra
これもまた極度に耽美的なオプス・アヴァントラの1stです。日本でもとても有名みたい。モナコのドネッラというソプラノ・オペラ歌手と作曲・編曲のアルフレッド・ティソッコ、アートディレクションのジョルジオ・ビソットを中心にしたプロジェクトのようです。テクがあるとかないとかじゃなくて、プロなんだから上手くて当り前、素養と滲み出るセンスだけで十分といったところですか。フルート、バイオリン、チェロ、ピアノ、ドラムの刻む前衛と伝統が混然と、あるいは整然と縒り合わされた稀に見る美。所謂ジャンルを完全に超越してしまっているので、ピエロ・ルネーレと同じく形容に窮してしまいます。カオスの中に垣間見える極度に粒立ちの良い音、ドネッラの歌、かつて経験したことのない世界です。初めて聞いたときは心底ぞくぞくしました。

Hölderlins Traum/Hölderlins Traum
ドイツ・ロマン派のヘルダーリン(Johann Christian Friedrich Hölderlin:1770-1848)と関係あるのかどうかは知りませんが、とても評価の高い1stアルバム。トラッドっぽい展開と雰囲気、柔らかい女性ボーカル、バイオリンとメロトロンの叙情的なコラボレーションがとても美しい。こんなに柔らかく聞こえるドイツ語(オランダ人らしいけど)も稀でしょう。同じピルツ・レーベルのエムティディ(Emtidi)と少し似た線の細さを感じますが、エムティディには無い伝統的な暗鬱が特徴です。音が薄くて向こう側が透けて見えそうな透明感が見事。

Gammapolis/Omega
まだ壁のあった時代の東欧ハンガリーのオメガです。衛星国家などという名前をつけて同じ穴の狢のくせして公式に蔑んでいましたが、今じゃ私達が地球上で最後の衛星国家(いやはや、時代は変わるもんだ)の住人になってしまいました。東欧ものと言えば総じて芋臭いのが相場ですが、これがまた意外に抑制の効いたSF風なシャープな音で多少困惑したりもする。メロディも泣きが入ってるしなぁ。パーカッションがワンパターンなところが玉に瑕だけど、暖かめのナツメロみたいな雰囲気で良いのでないでしょうか。久々に引っ張り出して聴いてみたら、昔聴いてた頃と随分イメージが違ってしまって少し慌ててしまいました。

Living in the material world/George Harrison
つい先日、病気でお亡くなりになりました。一般紙にもけっこう大きな扱いで載るくらいやっぱりビッグネームのようです。ちょっと関心してしまいました。西洋人なりの物質文明に対する批判と東洋思想への憧憬といったところでしょうが、結局のところ、自分達が一番だと思ってる以上は何も変わらないことに気付けないことが永遠の誤謬であろう。楽曲という面に限ってみれば、特有の暖か味というか慈悲に溢れた素晴らしい曲の数々。メロディ・メイカーとしての遅咲きの才能が開花してます。線が細くて儚げな冬の陽だまりのよう。

Travelling ways/Caravan
2CD、全24曲で1300円を切るお買い得。新曲? が7曲、ライブが4曲であとは旧作の96~99年バージョンです。なんだかベンチャーズみたいになってきました。勝手に想像するに、基本的にキャラバンというのはパイ・ヘイスティングス(Pye Hastings)とリチャード・コフラン(Richard Coughlan)の楽団です。そこにシンクレア兄弟がどう関るかで右に行ったり、左に行ったりはあるけれど基本は変わらない。いつも真ん中でどーんと構えているのは保安官みたいなヘイスティングスです。若い頃はけっこう線が細かったのだけど、今や貫禄でっせ。古いのから今のまで、通して聴いていると紛れもない職能芸人の音。対象を限定しながらも、芸道を突き詰めた、すなわちカンタベリィの音楽です。

Volume 1/Soft Machine
最近いろいろな音源が出回って、どれがなんだかよくわからん状態のソフト・マシンですが、これが一応正規の1stです。このCDは『1』と『2』のカップリングですが、『2』は単独で別に持ってたりもするし、メンバーも若干異なるので次回以降にきちんと書きます。さて、この時点で既にオーストラリア人デビッド・アレン(Daevid Allen)はフランスにツアーに行った帰りイギリスに入国できなかったそうでマシンを離れています。エヤーズ(Kevin Ayers)はこれを作った後、「ツアーは疲れるからいや」と言ってマジョルカに逃亡したそうです。エヤーズは歌をワイアット(Robert Wyatt)に任せきりにしてベースを弾いているようです。ほんのちょこっとだけバックでコーラスを入れている程度。キーボードのラトリッジ(Mike Ratledge)を含めてトリオ編成ですが、ワイアットのジャンルを越えたドラマーとしての才能には目を見張るものがある。歌を歌いながら変拍子をびしばし叩いてます。当時、ちっとも人気がなかったそうですが、ここまで類型的でないことをするとさもありなん。サイケデリック・ポップ・ジャズ・ロック? なのか、なんだかジャンルで区分できない今もって不思議な音楽です。

Recycled/Nektar
年末にドイツ・ベラフォンからリマスタがどっと出た元祖ハード・プログ、ネクターの最高作と云われる中期の作。しばらく大丈夫だろうとめぼしいとこしか購入していませんが、音はリマスターされてけっこう良い。当時、ドイツに居着いたイギリス人の楽団といわれておりましたが、英詩ですが雰囲気に大陸色がみてとれるところが売りでした。一風変わったリズムが気持ちよくて、P.F.M.の最盛期にちょっと似たような不思議な“ノリ”の良さが感じられる。ストリング・シンセの雄大なアンサンブルと叙情的なボーカルの対比、かなり斬新で強力なリズムに圧倒されます。クラウト系の前衛的な暗さはまったくなくて、清く明るいタイプの気持ち良い響き。ボーカルのバックのフニャフニャしたシンセの音がとってもかわいいのだ。

Music for the masses/Depeche Mode
開き直ったのか、以前とは異なる力強さと肯定的な価値観が表に出た。男っぽくて音がストレートに、生音も増えて重厚味が増した気がします。ゆったりとしたうねりに身を任せていられる安心感と安静感。前作から引き継ぐダークで壮重な暗さとミニマル風に削ぎ落とした少し実験的な単音シンセに二極分化してきた感もある。ガーンの歌も一段と上手くなったし、いろいろな意味で熟成した内容ですが、なかなか一つ所に留まらないのは時代の要請かもしれんし、やってる方も飽きちゃうというのはあるだろう。難しい時期にさしかかる予感。
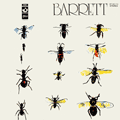
Barrett/Syd Barrett
言わずと知れた初期ピンク・フロイドの中心というか立役者というか一人飛び抜けていたシド・バレットの2作目のソロですが、結構きてます。様々な逸話が残されたようですが、途中で歌うの止めちゃったりとか、調子がどんどん外れていく壊れてしまったようなものが多いわけではない。が、ギルモアの献身でほとんどスタジオワークで処理したみたいな話しもあるから、本当のところはよくわからん。まぁ、典型的なサイケ・ポップですが転調が非常に独特で奇妙。中身を見れば徹底した疎外と孤独に苦しむ、どうしようもなく淋しそうな歌ばかりだ。最近また掘り出し物的なアウトテイク集が出てます。ジャケが恐くて買えません。

Join inn/Ash Ra Tempel
アシュ・ラ・テンペルとクラウス・シュルツェのコラボレーションというかセッションです。全2曲、1曲目はシュルツェが意外に手数の多いドラム叩いてます。グートシンクは相変わらずの感性オンリーですが、時々ギターシンセみたいに音がボワーと広がって、返って来ないぐらい発散しっぱなしが面白い。2曲目はうって変ってうねり系のシンセサイザとロジの囁きボイスでいっぱい。暗めのトーンとゆらゆらと揺すられるような優しい感触が気持ち良い。個人的には屋台骨を支えている献身的とも云えるハルトムート・エンケのベースに一票。昔、まったく手に入らなかった音源がその辺に転がるようになって、実際聴いてみると持っていたイメージが間違っていて新鮮なのだが、個人的にアシュ・ラ・テンペルはその典型で、もっと密教秘儀淫猥凄愴地獄絵巻みたいなおどろおどろしいものを想像していましたです。

Sogno di una notte d'estate/Mauro Pagani
パガーニ先生の一応ソロ2作目です。シェイクスピアの戯曲「真夏の夜の夢」を愚弄したミュージカルのサントラのようです。音楽監督といった立場なんでしょうか、作曲と製作がメインで、あとはバイオリンとブズーキ、ピッコロあたりを演奏してるようです。いきなりファンキィな乗りのバイオリンにたまげてしまいますが、中身は踊れるものからブルガリア民族風のゆるりとした感じまでいろいろ。セッション系のテクのある人を掻き集めてるようで、かなりタイトでかちっとまとまってます。LPをCD-Rにしたときに、たまたま80分の枠にぴったり嵌まったNicoの『Desert shore』を後半に入れちゃったもんで、『真夏の夜の夢』を聞き終えるといきなり寒風が吹きすさんじゃって、もう、二度びっくり。

Ragnarök/Ragnarök
スウェーデンのラグナレクの唯一作と思われる。北欧系特有の明るいさわやかな暖か味はあまり感じられず、白夜のような(見たことないので、あくまでイメージですが)モノトーンでシンプルで端正なギター・ポップ。まぁ、渋いの一言です。劇的とは云わないまでも、少しは盛り上がるみたいな部分にすら極度に欠けるため、うっかりすると耳に馴染み過ぎて楽曲として認識できなくなりそうだ。だからといってアンビエントを目指していたわけでもないようで、なかなか職人的なタメの効いた大人の演奏を淡々とこなしております。全編歌無し、インスト曲ですが重過ぎもせず軽過ぎることもなく、まさにこの世の中庸をいく。

The dreaming/Kate Bush
一つの曲でいったい何トラックのボーカルがあるのかよくわからない凝りようで、ほとんどパラノイア寸前。技巧に走り過ぎて奔放な躍動感が消えてしまった以上に、内側に崩れていくような崩壊感覚すら感じさせる才女の四作目。なかなかシリアスな内容ですが、何かに憑かれたような歌い方とエキセントリックな情念でいっぱいです。タイトル曲など異質というか異形過ぎちゃって3回くらい聞き返さないと、どれがメロディなのかさっぱりわかりません。今までには無かった民族音楽? へのアプローチが新機軸でしょうが、それが唯一ホッとできる部分だったりします。

Quella Vecchia Locanda/Quella Vecchia Locanda
正規盤が2枚、ライブが1枚あるみたいですがこれは1st。デリリウムかジェスロ・タルばりのフルートが特徴なロック・イタリアーノ、クェッラ・ヴェッキア・ロカンダ(例の昔ながらの宿屋)1st。タルの背景にあるのがトラッドならQ.V.L.の場合はもろにバロックです。その辺はあまりにも有名な2ndで顕著ですが、ここではまだロックっぽいアンサンブルが占めている割合が大きいようです。フルートとバイオリン、ピアノによる静的でクラシカルな部分とギター、ベースとドラムの動的で音圧の高い部分の対比で聞かせようということでしょうが、何故だか、今聞くと後者は古臭く聞こえてしまう。