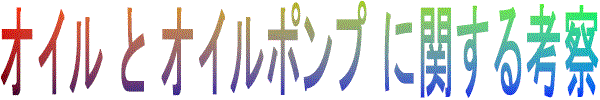
■ 添加剤について考察する ■ |
←←Return to HOME(ホームにもどる) ←オイルとオイルポンプ INDEX にもどる
レガシィのドレスアップ・改造 / ユーザー車検ガイド / 8ナンバー登録の全貌 / 技術的Q&A集
評価損( 格落ち )を請求しよう
/ オイル と オイルポンプ
に関する考察 / オフ会開催記録
/ 掲示板・過去ログ集
スバル掲示板
/ 8ナンバー掲示板
/ リンク集 / スバルグッズ / あとがき /
自己紹介 / ヴィヴィオ&プレオ
◆掲示板はこちら
・・・ KAZのスバル掲示板
、 KAZの8ナンバー掲示板
◆もくじ(いわゆるサイトマップ)は、こちら → サイト案内(構成ページ一覧表)
このページは、添加剤についての考察です。
※以下の記事を予定しています。 ※予定は予告無く変更する場合があります。
●1999-04-16:新製 ●1999-04-20:更新
内容 1. 添加剤の歴史
2. 添加剤の種類と役割
3. 添加剤の成分と特徴
4. 添加剤に寿命が来たらどうなる?
5. その他、添加剤に関する事項
■ 添加剤の歴史 ■ |
ここではまず、添加剤(と呼べるもの)がどれくらい前から使用されだしたのか、主な成功例
を挙げてみます。
添加剤の歴史は1800年ころから本格的となり、綿紡産業や船舶産業、
その後は航空機産業、そして近年の自動車産業といった具合に、産業発展の歴史と重なっ
ています。それぞれの時代の要求に応じて開発・改良されてきた、と言っても良いでしょう。
大げさに言うと、添加剤は産業の発展をカゲで支えてきた黒子、と言えるかも知れません。
| ・1850年頃 鉱油に石けん(脂肪酸石けん)が配合され始める |
| ・1917年頃 酸化防止剤として、鉱油にリン(赤リン)が添加され始める |
| ・1920年頃 摩擦低減材としてオレイン酸の添加が研究され、特許となる |
| ・1930年頃 芳香族が酸化防止剤、こはく酸が錆止め剤として使用される |
| ・ 同
ジチオリン酸亜鉛類が酸化防止剤、スルホン酸Ca塩が清浄 分散剤として使用され始める |
| ・1943年頃 シリコンが消泡剤として使用される |
| ・1950年頃 焼き付き性能向上としてPb−S系ギヤ油が使用される |
| ・1954年頃 無灰の清浄分散剤が開発される |
| ・1965年頃 環境面を考慮したS−P系ギヤ油が使用される |
| ・1980年頃 有機モリブデン系やグラファイト系の添加剤が使用される |
| ・ 現代
MoDTC+ZnDTPなど、FM剤の効果持続性などの研究や 燃費・排気ガス低減への寄与(環境指向)に関する研究が盛ん |
添加剤も用途に応じて色々なものが開発されてきました。しかし、極論すればそのどれもが
消耗品です。
したがって、添加剤に関する研究形態も、当初の目的である
「基油にはない
性能を付加し、欠点を克服する」 といったものから、次第に
「いかにして添加剤の効果を持
続させるか」
といった耐久的な研究、あるいは燃費や排気ガスといった環境志向型の研究
に比重が変わってきたように思われます。
それでは次に、添加剤としてどのような種類があるのかについて、説明します。
■ 添加剤の種類と役割 ■ |
ひとくちに
「添加剤」
といっても、その用途や種類は千差万別です。ここでは、エンジン
オイルやギヤオイルなどパワーユニット用のオイルに用いられる添加剤について、その
種類と役割、代表的な成分について順番に挙げてみます。
| 種 類 | 役 割 | 具 体 例 |
| 1.酸化防止剤 | オイルの酸化による劣化を防止します。 具体的には、ラジカル基の不活性化などにより酸化反応を抑制します。 |
ZnDTP(=ジチオリン酸亜鉛)、フェノール類、アミン類、硫化物など |
| 2.粘度指数向上剤 | 温度による粘度変化を小さくします。 具体的には、高温状態でポリマーの溶媒和が進んで比粘度が大きくなるようにします。 |
ポリメタクリレート、エチレン−プロピレン重合物、スチレン−ブタジエン重合物、ポリオレフィン系など |
| 3.摩擦調整剤 | (=FM、Friction
Modifier) 摺動面のフリクションを低減します。 具体的には、金属表面に吸着したり、あるいは反応するなどして、摩擦係数の小さな皮膜を形成するものです。 |
脂肪酸、脂肪酸エステル、リン酸エステル、二硫化モリブデン、モリブデンのジチオリン酸塩など |
| 4.清浄分散剤 | 不溶解分のスラッジ化を防ぎます。 具体的には、燃焼ガスによる酸化生成物を中和したり、高分子重合体を可溶化させたりして、スラッジの抑制と分散をはかります。 |
清浄剤・・・Ca、Mgなど金属系化合物(スルホネート類など) 分散剤・・・こはく酸イミド、こはく酸エステル、アミン類など |
| 5.流動点降下剤 | 低温時のワックス分の凝固を防ぎます。 具体的には、ワックスの表面に吸着し、結晶構造を変え、その成長(=析出化)を防ぎます。 |
ポリメタクリレート、アルキルナフタレン、フェノール類など |
| 6.極圧剤 | 接触荷重の高い摺動部の摩耗を防ぎます。 具体的には、金属の表面に高荷重に耐える摩擦係数の小さな皮膜を作り、メタルコンタクトを防ぎます。 |
ジチオリン酸亜鉛、リン酸エステル、硫黄化合物 |
| 7.消泡剤 | オイルの表面張力を下げて、泡を壊れやすくします。具体的には、泡の膜の表面張力を下げたり、あるいは泡の中に取り込まれることによって泡膜を破断させます。 | アルコール、シリコン(ジメチルシロキサン) |
| 8.防錆剤 | 金属がサビてしまうのを防ぎます。具体的には、酸を中和したり金属表面に吸着皮膜を作ったりして、酸素や水分との接触を断ちます。 | アルカリ土類金属の塩、スルホン酸類(アルカリ)、アルコール、アミン類 |
| 9.腐食防止剤 | 金属の表面に保護膜を形成して、腐食を防ぎます。具体的には、金属の酸化触媒反応を防ぐことによる腐食防止もあります。 | ジチオリン酸亜鉛、亜鉛、S−P化合物など |
| 10.油性剤 | 金属表面に潤滑皮膜を作ります。具体的には、金属の摩擦面に吸着されて油膜をつくります。 | エステル、アルコール、油脂、有機酸など |
| 11.着色剤 | 場合によっては、オイルに着色することもあります。 | 芳香族化合物を用いる |
以上より添加剤を性質上から分類すると、
「もともと基油の持つ性質を高めるもの(→例:粘度指数向上剤)」
「もともとの基油には無かった性質を付加するもの(→例:極圧剤)」
「精製過程で失われた性質を復活させるもの(→例:酸化防止剤)」
の3種類に大別することができると言われています。
しかし、これらの添加剤は単独でその効果を発揮するというよりも、ブレンドされることによって
お互いが相乗的に効果を発揮する ということが多く、いわば
「総合力」 としての効果を考える
べきであるから、上記のような便宜上の分類はあまり意味の無いものかも知れません。
ところでこれらの添加剤ですが、その添加率は、多いもので30%程度(清浄分散剤)にも及び
ますが、少ないものだと0.01%とか0.1以下
(消泡剤など) というわずかなものになります。
そのわずかな配合比率によって、オイルの性質は大きく変わることが予想されますから、オイ
ル開発者にとって 「新油開発」
とは、多大な開発費と長期的な試験の必要な一大イベントだと
想像されます。
以上のように、鉱油も化学合成油も、様々な添加剤によって支えられながら製品化されている
と言えるでしょう。それでは次に、これらの添加剤の成分と特徴について、詳しく述べてみます。
■ 添加剤の成分と特徴 ■ |
【1.酸化防止剤】
ジアルキルジチオリン酸亜鉛
OR OR
| |
S=P-S-Zn-S-P=S
| |
OR OR
ここで、Rはアルキル基を示す。
パワーユニット用のオイルは比較的高温にさらされるので、添加剤も高温用のものが
用い
られます。その一例として、ジアルキルジチオリン酸亜鉛の化学式を挙げると上記のように
なります。
例えばエンジンオイルでは、金属の存在下で高温状態のとき、空気(酸素)に触れることに
よって酸化反応が起こります。この場合の酸化反応は、オイルがアルコールやケトンを経て
高分子状の不溶解分へと成長する反応なので、反応体である過酸化物
を分解する作用を
持ったジアルキルジチオリン酸亜鉛が用いられるということなのです。
ちなみに、自動車のパワーユニット用オイルよりもさらに高温にさらされるジェットエンジン
用オイルの酸化防止剤には、フェノチアジン系の添加剤が古くから用いられています。
さらに付け加えると、自動車用よりも低温域である工業用オイル(タービン油など)の酸化
防止剤としては、連鎖反応型の酸化を防ぐ
という目的で、フェノール類やアミン類の添加
剤が用いられるとされています。
(↓'99-04-16 加筆)
参考文献に
「三菱石油 技術資料 No.83」
「SAE Paper No.982506/妙録/TOYOTA自動車
(5W-20低摩擦ガソリンエンジン油の燃費効果)」
を追加。
【2.粘度指数向上剤】
| ポリアルキルメタクリレート | ポリイソブチレン |
| CH3 | −(CH2-C-)n− | COOR |
CH3 | −(CH2-C-)n− | CH3 |
| Rは炭素数1〜18程度 分子量は2万〜150万 |
イソブチレンのポリマー 分子量は5千〜30万程度 |
粘度指数向上剤として用いられるものに、ポリアルキルメタクリレートやポリイソブチレン
があります。他にもスチレンもの(エチレンのHが、直鎖基-CnH2n+1を持ったベンゼン環
に置き換わった構造、ポリアルキルスチレン)やエチレン・プロピレン共重合体などがあり
ますが、ここでは代表例として前2者の化学式を挙げておきます。
これらの添加剤が粘度指数を向上させるメカニズムは、ズバリ、以下の仕組みです。
・添加剤は、低温状態では基油へあまり溶解しない。
したがって、オイルの粘度≒基油の粘度、となる。
・油温が上昇すると、基油の粘度は次第に下がる。
・一方、油温が上昇すると、添加剤(ポリマー)が基油に溶解し始めるので、
溶解した分子の径は次第に大きく成長し、その分の粘度が上がり始める。
・温度上昇により基油の粘度が下がるが、溶解した添加剤による粘度は上がる
ので、添加油トータルとしては温度上昇による粘度低下幅を小さく抑えられる。
そうです、粘度指数向上剤のマジックは、「低温時にあまり溶解しない」点と、「高温時
に溶解するので、それ自身の粘度が上がる」点にあったのです!
これをもう少し化学
的な根拠で補足説明すると、温度と運動エネルギーの関係になります。
・低温時 添加剤(ポリマー)自身の凝集エネルギー > 基油への溶媒和
・高温時 添加剤(ポリマー)自身の凝集エネルギー < 基油への溶媒和
・理由
温度上昇により、添加剤の持つ運動エネルギーが増加するので、
そのぶん凝集力が低下し、溶解力のほうが強くなる。
ナゾが解けました。温度上昇で基油の粘度が下がるなら、温度上昇で(凝集により)粘度
が上がる性質をもった物質を加えれば良かったのです。
ただ、低温時に基油にあまり溶
解しない状態であっても、悪さをしない(デメリットが無い)ことが必須です。その性質を決
定付けるのが、上の分子構造式中のアルキル基(R)です。
アルキル基の構造がノルマル(直鎖状)かイソ(分岐状)か、あるいはその炭素数はどれ
くらいかによって、最大効果の得られる温度域が異なってきます。例えば炭素数が小さい
(=アルキル基が短い)場合は粘度指数向上効果は高まりますが、あまり小さくしすぎる
と、低温であっても基油への溶解性が良くなりすぎてしまう恐れがあります。 つまりは、
どこでバランス点を取るかが重要になってきます。
その点で、安定したチューニングを取りやすいポリアルキルメタクリレートやポリイソブチ
レンが用いられるのでしょう。ただ、今後の方向性としては、基油そのもののポテンシャ
ルで高い粘度指数特性が得られるもの、の研究も進んでいくように思われます。
【3.摩擦低減剤(=FM、Friction Modifier) 】
摩擦低減剤は、現在もっとも注目・研究されている添加剤成分の一つです。
MoDTC(ジアルキルジチオカルバミン酸モリブデン)
R S O S O S R
\ / \ ‖ / \ ‖ / \ /
N-C Mo Mo C-N
/ \ / \ / \ / \
R S S S R
ここで、Rはアルキル基を示す。
摩擦低減剤は摩擦調整剤(Friction
Modifier)とも呼ばれ、2つの部品の摺動面が直接
触れ合うような 「境界潤滑領域」 あるいは 「混合潤滑領域」
における摺動摩擦を低減
させる添加剤です。その代表例として、MoDTCの構造式を上記に挙げてみました。
一般に摩擦低減剤は、その機能発揮形態から、次の3種類に大別されます。
| 機能発揮形態 | 添加剤の具体例 | |
| 1 | 分子レベルで物理的・化学的に金属表面に吸着し、効果を発揮するもの | アルコール類、アミン類、脂肪酸エステルなど |
| 2 | 摺動面に層状の被膜を形成することによって、摩擦低減効果を成すもの | 二硫化モリブデン、グラファイト、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)など |
| 3 | 摺動面で分解し、反応被膜を形成することで効果を発揮するもの | MoDTP、MoDTCなど |
表中のタイプ1は、分子吸着タイプと呼ばれるものです。直鎖状のアルキル基の末端に
-OH基、-COOH基、その他アミン類などの官能基を備えたものや、脂肪酸のエステル
などは、極性を持つため金属表面に吸着します。
物理的な吸着よりも化学的な吸着の
方が吸着力が強いと言われますが、必ずしも吸着力の大小と(金属表面を覆う)被覆率
とは比例関係とはならないので、効果の現れ方も添加剤によって差が出るようです。
表中のタイプ2は、容易に剪断される層状の分子構造(骨格)を持ったものが、摺動面
に皮膜を形成するタイプのものです。グラファイトを考えるとイメージがわいてきます。
二硫化モリブデン(MoS2)もこのタイプであり、固体潤滑剤とも言われます。高温状態
でも熱安定性に優れるという長所がありますが、実はオイルには不溶性である
という
大きな欠点を持っているのが一般的です。
したがって、通常は微粒子化(1μm以下)した上で、他の分散剤と併用して用いられ
ます。
そうしなければ、油中に安定して拡散せず、また最悪時は固体として析出する
恐れがあるからです。つまり、摺動面の摩擦係数低減効果自体は優れているものの、
その使用方法には注意の必要な点が 「やや難あり」
といったところでしょうか。
そこで、そのような二硫化モリブデンの欠点を改善したものが、表中のタイプ3の添加
剤です。つまり、分子構造を変えることによってオイルへの可溶性を持たせているので
す。
MoDTP(ジアルキルジチオリン酸モリブデン)、MoDTC(ジアルキルジチオカル
バミン酸モリブデン)が、その代表例です。これらの添加剤は、摺動面で分解して二硫
化モリブデン類の化合物を含む被膜を形成し、摩擦低減効果を発揮するようです。
当初はMoDTPが盛んに用いられていましたが、分子中のリン(P)が触媒の浄化作用
や耐久性を悪化させるという弊害が指摘されてからは、MoDTCが主役になりました。
摺動面で皮膜を形成しないものが油中に残っても、可溶性をもっているため析出・沈殿
するなどの心配は不要です。同じ理由で、使用に際しては分散剤を併用させる必要は
なく、また有効に皮膜が形成するので、基油への添加量も少なくて済む長所があります。
(↓'99-04-20〜21 加筆)
これらのMoDTPやMoDTC、一部のモリブデンのアミン塩は
「有機モリブデン」 と呼ば
れています。アフターマーケット( カー用品店
)で販売されている添加剤にも、「有機モリ
ブデン配合」 をうたっているものも多いと思います。
これらの有機モリブデンは、一般に
それ単独で用いるよりも、前述の酸化防止剤の章で出てきた
「ZnDTP(=ジチオリン酸
亜鉛)」
と組み合わせて用いた方が摩擦低減効果が高い、といった報告例があります。
その理由は、いったんZnDTPが(金属表面と有機モリブデンとの間に)皮膜を作って、
有機モリブデンの吸着の仲立ちをするからだそうです。
また、有機モリブデンは通常の
精製鉱油に添加するよりも、高精度の精製油(
高VI油、高粘度指数鉱油 )に添加した
方が効果を発揮しやすい、とも言われています。よって、ユーザーが自分で市販のモリ
ブデン添加剤を購入する場合の注意点としては、次のようになるでしょう。
<固体潤滑剤(二硫化モリブデン)を選ぶ場合>
・成分表示ラベルに分散剤の併用が表示されているかどうか
・オイルに溶解しないので、微粒子処理されているかどうか
・濃度は高い方が良いが、あまり高いと沈殿となって析出する恐れあり
<有機モリブデンを選ぶ場合>
・添加剤を入れたいオイルが、化学合成油や高VI鉱油であるかどうか
・成分表示ラベルにZnDTPなどの併用が表示されているかどうか
(実際には、添加される方のオイルにすでに調合済みである場合が
多いので、あまり気にしなくても良いと思われます)
<その他>
・動弁系がローラーロッカーアーム方式であるなど、すでに低フリクション
型のエンジンの場合は、(混合潤滑状態や境界潤滑状態が少ない
ので)もともと添加剤による改善効果は現れにくい場合がある。
【4.清浄分散剤】
| スルフォネート |
/\_R R_/\ |
ここでRは炭素数8〜30のアルキル基を、Mは金属元素(Mg、Ca)を示す
| こはく酸イミド (Nテトラエチレンペンタミンポリイソブテニルこはく酸イミド) |
| R−CH=CH−CH2−CH−CH2 | | OC CO \/ N−(C2H4NH)3−C2H4−NH2 |
改行くずれ ご容赦!
一般に、金属系の清浄剤(detergent)と無灰系の分散剤(dispersant)の両者を合わ
せて 「清浄分散剤」
と呼びます。もともとの基油には備わっていないものです。清浄
分散剤はその名の通り、パワーユニット中の劣化成分や摩耗粉、その他の異物を油
中に分散させたり可溶化させたりすることによって凝集・沈殿を防ぎ、スラッジの形成
を防止する添加剤です。
どちらもパワーユニット用の添加剤としては主要なものであり、特に金属系清浄剤に
ついては、1940年代ころまでには、現在の添加剤とほぼ同様なものが開発されて
いたと言われています。研究歴史の長い添加剤ですね。清浄分散剤の基油への添
加割合については、他の添加剤に較べるとかなりの量になります。一説によると、そ
の添加量は30%ほどにも達する製品もあると言われています。
続きは準備中です。完成まで、まだ少々ありますが、
気長に待ってやって下さいませ・・・。
(書き始めて結構大変なことが分かったKAZより)
参考文献 :
「JISハンドブック・石油/日本規格協会」
「TOYOTA Technical Review/Vol.47 No.1」
「三菱石油 技術資料 No.83」
「出光技報 41巻4号/1998」
「SAE Paper
No.982506/妙録/TOYOTA自動車
(5W-20低摩擦ガソリンエンジン油の燃費効果)」
「月刊出光」 他
■オイルとオイルポンプに関する考察 INDEX■
(目次を確認する)
↑
![]() BACK ← 添加剤について考察する →
BACK ← 添加剤について考察する → ![]()
(「オイルの成分と機能」に戻る) (このページ:2/6ページ) (次のページは準備中)
レガシィのドレスアップ・改造 / ユーザー車検ガイド / 8ナンバー登録の全貌 / 技術的Q&A集
評価損( 格落ち )を請求しよう
/ オイル と オイルポンプ
に関する考察 / オフ会開催記録
/ 掲示板・過去ログ集
スバル掲示板
/ 8ナンバー掲示板
/ リンク集 / スバルグッズ / あとがき /
自己紹介 / ヴィヴィオ&プレオ
◆もくじ(いわゆるサイトマップ)は、こちら → サイト案内(構成ページ一覧表)