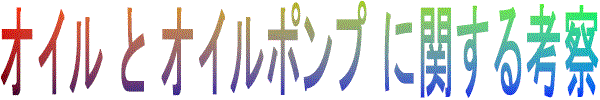
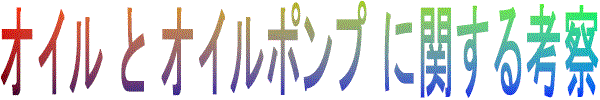
■ オイルの成分と機能などについて ■ |
←←Return to HOME(ホームにもどる) ←オイルとオイルポンプ INDEX にもどる
このページは、オイルの成分・特徴・機能・
劣化原因など、総論についてです。
●1999-03-29:新製 ●1999-04-15:更新
1999-04-15 の更新点 :
「オイルに求められる機能や特性について」
と、それ以下の文章を加筆。
1999-04-14 の更新点は、ページ後半の 「オイルが果たす役割」
以下の文章を加筆したことです。
内容 ■ オイルはどうやって作られる?
■ 化学合成油の成分と特徴
■ オイルが果たす役割について
■ オイルに求められる機能・特性について
■ オイルの寿命を決める指標
■ オイルはどうやって作られる? ■ |
以下、鉱油と化学合成油のそれぞれの場合について述べます。
【鉱油の場合】
1.原油を沈殿・濾過させる
2.原油を常圧蒸留する
3.残留分を減圧蒸留する
4.不純物を除去する
鉱油の場合、大雑把に言うと上記の行程によりベースオイルが作られます。各行程について、
もう少し詳しく述べましょう。まず「1.原油を沈殿・濾過させる」
についてです。油田から採掘
したばかりの原油には、砂・泥・水分など、様々な不純物が混ざっています。まずは、この不純
物を除去する作業から始められます。その手法は、沈殿や濾過といった地道なものとなります。
砂・泥・水分などの不純物が除去されたあとは、「2.原油を常圧蒸留する」
工程へ進みます。
原油は真っ黒い色をしており、ガスからアスファルトといった様々なものが混ざった、どろどろな
状態です。これを常圧状態で蒸留します。通常は常圧蒸留棟などと呼ばれる設備の中に入れら
れて、およそ350℃前後に加熱されるようです。この工程では、原油を構成している
それぞれ
の成分の沸点差・比重差を利用して蒸留されます。
常圧蒸留により、原油は留出する成分と炉に残る成分とに大別されます。このうち、炉に残った
方をさらに 「3.減圧状態にして蒸留」 します。言葉で表すとこの一言になりますが、実際には
不純物の各成分(
主に分子量や分子間の結合エネルギーの違いですね
)ごとに沸点が異なり
ますので、留出させたい成分の沸点に応じて、
何段階かに行程を分けて、減圧蒸留されること
になります。
その後、減圧蒸留では除去仕切れない成分(例えば芳香族化合物や硫黄化合物などです)を、
それ専用の溶剤を用いて化学的に除去します。あるいは水素を添加して精製(分解)させます。
それでもまだ
ベースオイルとしては不要な(あるいは不都合な)成分が含まれているので、それ
を冷却分離させます。これが 「4.不純物の除去」
行程になります。
ここで言う冷却分離とは、つまり
「脱ろう」 をすることです。温度を徐々に下げていくと、次第に
溶液に濁りが生じ始め、さらに冷却を続けていくと、今度はワックス分が
ゲル状 となって析出
(沈殿)してくるのです。これを除去する操作を言います。
こうして残った成分がベースオイルと
しての出発点になります。
【化学合成油の場合】
1.石油を分解してエタノール、ベンゼンなどの「原料」を得る
2.「原料」に油脂を化学反応させてゆき、所望の合成油を得る
化学合成油も、元をただせば原油から作られることにはなりますが、鉱油が
「原油から不要な
成分を次第に分離除去していく」
作業により得られるのに対し、化学合成油は 「材料を意図的
な化学組成に組み替えて合成」
することにより得られる点が異なります。 つまり、分解反応で
はなく化学反応により(文字通り) 「合成」
して得る点が異なります。
具体的には、エタノール、エチレン、プロピレン、ベンゼン、トルエンといった原料からいくつかの
行程(中間生成物)を経て、ポリオールエステルやポリオレフィン、シリコンといった
ベースオイル
を合成します。中間生成物としては、アルデヒド(例 :
エチレン→アセトアルデヒド、プロピレン→
ノルマルブチルアルデヒド、メタノール→ホルムアルデヒド)、フェノール、アジピン酸などです。
これらの中間生成物の名前はご覧になったことがあるでしょうか? 私は高校の授業で習いま
した。今から15年以上も前のことですが、当時は化学の教科書にも
「アジピン酸」 などが、ごく
普通に出てきました。 ちなみにアジピン酸はHOOC(CH2)4COOHで、ナイロンの原料です。
余談ですが、化学の世界では
「1・2・3・4・5・6・7・8・9・10」
の数字を示す言葉は、それぞれ
順に、「モノ・ジ・トリ・テトラ・ペンタ・ヘキサ・ヘプタ・オクタ・ノナ・デカ」
といいます。 今の教科書
にも載っているかどうかは分かりませんが、化学物質の命名法には規則性
があるので、これら
の数字名や、ノルマル=直鎖状とか、「形状+炭素数+官能基」
の順で命名されているなどの
意味さえつかめれば、簡単な物質なら構成が想像できるようになっています。シャンプーの成分
や風邪薬の成分を見ても、使用されている物質の命名法もほぼ同等です。
このようにして得られた化学合成油(のベースオイル)は、分子量が300〜700であると言わ
れています。化学合成油はその名の通り、合成(化学反応)によって作られることから、原料の
入手単価や合成手順の難易度が、最終的な製品としての価格を左右することになります。
■ 化学合成油の成分と特徴 ■ |
ここでは、化学合成油の特徴について化学的な分類をもとに述べていきます。
【ポリαオレフィン(PAO)】
αオレフィン
ポリαオレフィン
CH3(CH2)7CH=CH2 → R1-(R2)n-H
ここで、R1はC10H21、R2は(-CHC8H17CH2-)を表す。
αオレフィンを重合させたものが、ポリαオレフィンです。省略してPAOと表記されることも
あります。これは化学合成油の基油として古くから用いられてきました。αオレフィン(炭素
数10のもの)は鉱油を分解しても得られますが、エチレンを重合して得る方が安価に効率
よく得られるので、後者の製造法が一般的なようです。炭素数10の
αオレフィンが用いら
れる理由は、ズバリ、粘度指数と流動点に優れているからです。当初は航空機用のオイル
として開発されました。
ポリαオレフィン(PAO)の重合度を変える(=上式中のn値を変える)ことによって、粘度が
変わります。ここでポリαオレフィン(PAO)の構造は、上式に示すように、重合部R2がイソ
型(=分岐構造、単純直鎖状のノルマル型ではない)で、いわば
「くし形状」 となっているの
が特徴です。そのため、鉱油に較べて次のような長所があります。
・粘度指数が高く、流動点が低い
・引火点が高い(粘度の割に蒸発しにくい)
ただし世の常で、長所だけではなく短所もあります。それはポリαオレフィン自体は-OH基
や-COOH基を含まない無極性油であるため、エンジンのシール材として幅広く用いられて
いるゴム(アクリロニトリル)
との相性がイマイチなのです。つまり、シール材を収縮させてし
まうという性質があるのです。化学合成油が初めて世に出た当初は、この収縮性が問題に
なった時期が確かにありました。しかし、逆の性質、すなわちシール材を膨潤させる性質を
持つ エステル を付加させて、いわば 「中和」
させるという研究が進んでからは、実用上は
まったく問題にならなくなりました。
【ジ・エステル】
アルコール 二塩基酸 ジエステル 水
2R1-OH + HOOC(R2)COOH → R1-OOC(R2)COO-R1
+ 2H2O
ここで、R1、R2は(CmHn)を表す。
エステルとは、アルコールと塩基酸との化合物、です。前述のように、「ジ」
は 「2」 という
意味ですから、分子内に 「2個のエステル結合を持つ」
ということになります。ものの本に
よると、エステル(グリセリンと脂肪酸のエステル)は、古代エジプトの太古から利用され続
けてきた、といいます。その真偽のほどは分かりませんが、近年では戦争(
World War II )
を境にドイツやアメリカで研究が進み、やはり航空機(
ジェットエンジン油)として実用化が
進んだと言われています。
原料であるアルコールには、2エチルヘキサノール、イソデカノール、トリデカノールが用い
られます。ここで復習すると、2エチルヘキサノールは、「直鎖基の2番目にエチル基がつ
いたヘキサノール=直鎖炭素数6のアルコール」
という意味ですから、トータルでは炭素
数がエチル(2)+ヘキサ(6)=C8になります。
イソデカノールは 「分岐状の炭素数デカ
=10のアルコール」、 トリデカノールは 「
トリ(炭素数3)がついた炭素数デカ(=10)の
アルコール」
で合計炭素数はC13、になります。
もう一方の原料である二塩基酸には、上式のR2の部分に炭素数4のもの(アジピン酸)、
炭素数10のもの(ドデカン二酸)、その他C=7、8が少量使われるようです。
ジエステルも粘度指数が高く、低粘度であり、引火点の高いものが多いことが特徴です。
ただし、単独のままでは熱に弱いので、酸化が進むと重合反応が起こってポリエステル
化するため、添加剤とともに用いられるのが普通です。
【ポリオールエステル】
R1
|
HOCH2−C−CH2OH
|
R2
R1、R2、がともにメチル基(CH3)のとき → ネオペンチルグリコール
R1、R2、がともに(CH2OH)のとき → ペンタエリスリトール
R1、R2、が(CH2OH)と(C2H5)のとき
→ トリメチロールプロパン
「多価のアルコール」と「一塩基性の脂肪酸」が反応してできるエステルのことを、
通常は
「ポリオールエステル」と呼びます。つまり、「ポリオールエステル」とは特定
の物質を指す
のではなく、そのような反応によって得られる物質の総称を表して
いることになります。
その中で代表的なものを挙げると、上式にある通りです。ポリオールエステルは、
同じエ
ステル類でありながら前述のジエステルと区別されることが多いのですが、
その理由は
耐熱性・耐酸化性・摩擦低減効果など有用性に差があるためです。
その一例として、摩擦低減効果について触れてみましょう。エステルには、金属の表面に
吸着してある種の皮膜を形成するという効果が確認されています。
その理由は、分子間
中に極性基を持つためです。この皮膜により、金属表面の摩擦係数
が下げられるので、
例えばエンジンオイルに用いると摩擦(フリクションロス)を低減できると言われていますし、
実際にそのような研究も各方面で盛んにされたようです。
ここでその効果について考えてみると、ジエステルは分子間にエステル基を2ヶ所持って
いるため、2点吸着になると考えられるのですが、ポリオールエステルではこれが3〜4個
になるため 吸着力がより大きい、すなわち摩擦
(フリクションロス) 低減効果がより大きく
現れる、とされているのです。
【リン酸エステル】
エステルには、この他にも「リン酸エステル」があるのですが、これについては別途、添加
剤のページで述べることにします。というのも、リン酸エステルは、耐摩耗性を向上させる
ための添加材として古くから使用されているからです。
【シリコン】
R
R
| |
R-(-Si-O-)n-Si-R
| |
R R
分子間中に「Si-C」結合と「Si-O-Si」結合を持ったものを、シリコンと呼びます。
シリコン
の特徴は、何と言っても低温時の流動性に優れていることです。これは、分子間中に原子
半径の大きなSi
があるため、屈曲性が良好なためです。重合度(上式のnの値)を変える
ことで粘度調節されますが、粘度指数自体は200〜500と非常に高いことが特徴です。
そのほかの特徴としては、表面張力が低いこと、熱や酸化に対して強い(安定している)
ので使用温度範囲が広いこと、などです。エンジンオイルなどでは、1943年から消泡材
として添加使用されているのが一般的です。
【クロロフルオロカーボン】
クロロ・トリフルオロエチレン クロロフルオロカーボンポリマー
CF2=CFCl → -(CF2-CFCl)n-
フッ素(元素記号F)の登場です。上式のように、エチレン(CH2=CH2)の水素原子を
1個の塩素(Cl)と3個のフッ素(F)で置き換えたもの(クロロ・トリフルオロエチレン)
を、
ポリマー化(重合)して得られるのがクロロフルオロカーボン(総称)です。ポリマーです
から、重合度を変えることで粘度の大きなものから小さなものまでの合成が可能です。
フッ素は原子半径が(水素より)大きく、自然着火性がないので、C、H、Oだけから成る
他の合成油とは異なった性質を示します。難燃性のため高温での安定性に非常に優れ、
絶縁性や薬品に対する耐力も高いのです。
ただ、やはり欠点というのも存在します。温度に対する粘度の変化度合いが大きい(粘
度指数が低い)ために、なかなか利用されないのです。代わりに今日では、合成油中に
存在する 「C-H結合」 を部分的にのみ、 「C-F結合」
に置換させることで、元々のオイ
ルの特性を保ちつつ高温安定性に優れる合成油を作り出す研究が進められています。
(↓'99-04-14加筆↓)
(注): 「オイルに求められる機能とは?」
というタイトルを、
「オイルが果たす役割について」 と
「オイルに求められる機能や特性について」
に分割・変更しました。
■ オイルが果たす役割について ■ |
前節までは、オイルに関する化学的な知識を中心に話しを進めてきました。教科書的な
内容であったため、読んでもあまり楽しくなかったかも知れません。
ここから先は、少し
ずつですが、具体的な話しに焦点を移していこうと思います。
まずは、オイルがパワー
ユニット(=エンジン+ミッション+駆動系)の中で果たしている役割から、延べます。
私たちが日常使うクルマには、エンジンオイル、ミッションオイル(
ATF、CVTオイル、
ギヤオイル)、パワステオイル、ブレーキフルードなど、さまざまなオイルが使用されて
います。
厳密には、オイルは適用されるべき部位や用途によって、少しずつ果たして
いる役割が異
なってきますが、以下に挙げる基本的な役割についてはほとんど共通
項であるため、ここでは特に区別はしないで述べてみます。
・フリクション低減効果
・焼き付き防止効果
・冷却効果
・シール(密封)効果
・ダンピング(緩衝)効果
・清浄効果
・防錆効果
それでは各効果について、順に述べます。
【フリクション低減効果】
フリクションとは摩擦力ですから、減摩効果とも呼ばれます。パワーユニットには、お互い
に摺動しあう2つ以上の金属部品が数多く存在します。
あるいは、摺動部分は金属とは
限らないかもしれません。
いずれにせよ、オイルはこれらの摺動面に入り込んで 油膜を
形成することによって、摺動部品が直接的に接触してしまうことを避け、摩擦係数を低減
してくれるという重要な効果を発揮します。
【焼き付き防止効果】
これはフリクション低減効果と基本的には同一のものです。ただパワーユニットにおいて
は、摺動部品の 「フリクション低減」 と言うと
主に常用域における、より安定した運動状
態を示すことが多いです。これに対し、限界時での運動状態に目を向ける場合には、「フ
リクション」 という言葉よりも 「焼き付き」 という端的な現象
の発生有無で 安定性を見る
ことが多いです。
したがってオイルが果たす役割としては、パワーユニットの限界時でも
安定したフリクション低減効果=耐焼き付き性の高さを持つことが、重要になってきます。
【冷却効果】
オイルはパワーユニット各部を循環することにより、発熱部から受け取った熱を、より低温
部へと伝熱します。オイルには、冷却効果あるいは温度均一化効果を示す媒体作用があ
ることになります。実際、オイルクーラーはオイルそのものを作用媒体とする熱交換器です。
【シール(密封)効果】
具体例を挙げると、エンジンのシリンダー内では、ピストンリングとシリンダー壁との間に
油膜が形成されることにより、高圧な混合気の 「圧縮漏れ」
や燃焼ガスの 「吹き抜け」
を防ぐ効果があります。このように気密を保つ効果がシール(密封)作用です。
【ダンピング(緩衝)効果】
油膜が衝撃力を緩和する効果です。
具体的には、エンジンのクランクメタルやコンロッド
メタルに入り込んだ油膜は、シリンダー内で発生する強大な爆発力に打ち勝って、回転
部品のメタルコンタクト(金属接触)を避けて支えるようなダンピング効果を持つということ
です。また、この作用は、パワーユニット各部の摺動部品の摩耗を防ぐという重要な効果
でもあります。
【清浄効果】
エンジンやミッションなどパワーユニット内部を循環するオイルは、コンタミ
(使用中に発生
していく金属摩耗粉や樹脂摩耗粉、繊維、外部から混入するゴミなど)や炭化生成物など
を運搬したり、あるいは分子中に取り込んだりして、常にパワーユニット内部を清浄すると
いう効果も持っています。
【防錆効果】
防錆効果とは、金属が「サビる」ことを防ぐ効果です。一般に金属は空気中にさらされる
と、酸素や水分と反応してサビてきます。
オイルは、金属表面に皮膜を形成するので、
これらサビの原因となる物質を遮断し、その結果、サビによる腐食進行をくい止めます。
以上のように、サッと挙げただけでも、オイルの果たす役割は非常に重要です。オイルなしでは
パワーユニットは成り立たないとも言えます。
これまでオイルはパワーユニット側の要求に対応
する形で開発され、進化をとげてきましたが、今後はオイル自身が、これらの効果を高めるよう
自ら進化して提案性を持つことで、逆にパワーユニットの発展を支えていくかも知れません。
■オイルに求められる機能や特性について■ |
前述の各章を読み直すと、おぼろげながら理想のオイル像、というものが見えてきます。
もちろん、オイルは適用されるべき部位や用途によって、少しずつ求められる機能・特性
が異なってきますが、基本的には次のようなものが求められていると言って良いでしょう。
・粘度が適切であること
・粘度指数が高いこと
・熱安定性に優れること
・酸化安定性に優れること
・清浄分散性に優れること
・省燃費効果に優れること
・ドレンインターバルが長いこと
・排気ガス浄化特性に優れること
【粘度が適切であること】
まず、何よりも重要で真っ先に挙げるべき項目がこの「適切な粘度」です。先にも説明した通り、
摺動部分に適切な油膜(薄くても厚くても不適)を形成し、焼き付かずダンピング効果を発揮し、
フリクションも低減させるためには、適用部位に応じた最適な粘度を持つことが不可欠です。
例えばエンジンに高粘度油を用いると低温始動性は損なわれ、燃費も悪化し、MTに低粘度油
を用いると高温・高回転・高負荷状態では(
十分な皮膜が形成されないので )ギヤの摩耗や
ベアリングの焼き付きを誘発する恐れがあります。金属ベルトを用いたCVTでも同様に、粘度
が不適だと低温時の車両特性や振動・騒音、はたまた動力伝達特性にも懸念点が出てきます。
【粘度指数が高いこと】
ここでは先に、用語の確認から行いましょう。オイルは、その温度が変化すると粘度も変化
します。低温ではドロドロのオイルが、高温ではサラサラになるといった具合です。「粘度指
数」とは、温度変化に対する粘度の変化具合(変化のしにくさ)を示す指標です。数字が大き
いほど、温度が変わっても粘度がしにくい、つまり安定した特性を保つ、ということを表します。
ちなみに、粘度指数は「VI
= Viscosity Index」とも表記されます。元々はアメリカで導入され
た指標で、鉱油中で最も温度による粘度変化の大きなオイル(ナフテン系のオイル)をVI=0
とし、最も粘度変化の小さなオイル(パラフィン系のオイル)をVI=100
としたときの計算値
です。市場で販売されているオイルの中には、宣伝文句で「高VI油」とうたっているものがあ
りますが、その意味するところは、さしずめ「温度変化による粘度変化を最小に抑え、安定し
た性状を示します。」といったところでしょうか。
パワーユニットに用いられるオイルとしては、この
粘度指数 が高いことが要求されます。
なぜか? 理由は、低温から高温まで、(航空機ほどではないにしろ)実に広い温度範囲
で使用されるからです。地域にもよりますが、下は−30℃くらいから上は140℃(エンジン)、
160℃(ミッション)などとも言われています。
(↓'99-04-15加筆↓)
(注): 「オイルに求められる機能や特性について」
の中の最後の項目に、
「排気ガス浄化特性に優れること」
を追加の上、以下の記事を追記しました。
【熱安定性に優れること】
オイルは高温にさらされると、それ自身が熱により分解され、粘度変化を起こす場合があり
ます。特に金属が存在する状態で空気に触れると、分子の一部がケトンや酸となってスラッ
ジ (不溶性の高分子化合物) を生成してしまう恐れもあります。
したがって、パワーユニットに用いられるオイルには、高温・高負荷が連続する状態であって
も、熱分解を受けることなく安定した性能を発揮することが求められます。
具体的には、たと
えばエンジンオイルではターボ車で高過給圧状態が続く場合、ミッションオイルやギヤオイル
では
トレーラーや車両を牽引しながら勾配の急な坂道を登坂する場合、などでの安定性、と
いうことになります。
【酸化安定性に優れること】
オイルは高温状態でも酸化しますが、燃焼ガスにさらされることによっても酸化します。
例えばエンジンオイルでは、燃焼ガス中に含まれる高濃度のNOx(窒素酸化物)に触れる
ことで、ラジカル反応(遊離基による連鎖反応)が起こり、酸化劣化が進行すると言われて
います。
したがって、オイルは酸化に対する耐力も持ち合わせていなければなりません。
【清浄分散性に優れること】
エンジンオイルの場合、窒素酸化物や硫黄酸化物などスラッジの原因となる物質を包み
込み、油中に分散させて沈殿体積させないように保つ性能が要求されます。 ミッション
オイルでは、コンタミをオイルフィルターに補足させるよう運搬する性能も、(広義の清浄
性として)要求されることでしょう。
【省燃費効果に優れること】
ズバリ、これからの時代に要求される性能だと言えます。パワーユニットの機械効率を考え
てみると、損失は出力の2〜3割にも及ぶ、とする説があります。オイルの改良により、この
損失を減らそうとする試みが盛んに研究されているようです。添加剤の助けを借りるだけで
なく、オイル(基油)そのものの低粘度化により、省燃費効果を得よう
とする動きが 今後は
ますます大きくなっていくことでしょう。トヨタのエンジンオイルの5W-20化も、こうした流れ
に乗ったものです。
【ドレンインターバルが長いこと】
極論すると、オイルは使用することによる劣化が避けられません。しかし、その劣化の進行
を抑えることができれば、ドレンインターバルを延長することができます。オイルの劣化を抑
えるとは、すなわち(結果的に前述と同様になりますが)酸化安定性を向上させることです。
その他としては、摺動部品間の摩耗を防ぐ作用に優れることです。これは、例えば摺動部品
のスキマに入り込んで皮膜を作るという作用に劣っていると、メタルコンタクトによる摩耗粉が
発生するので、たとえオイル自身は劣化していなくても、オイル中に浮遊している摩耗粉を除
去する目的でオイル交換を余儀なくされる、という恐れもあるということです。特にギヤオイル
の場合、オイルはまだきれいなのに、油中の鉄粉が多いので交換してしまった、というような
時がこれに相当します。ロングドレン化のためには、耐摩耗性も重要な要素となってきます。
【排気ガス浄化特性に優れること】
例えばエンジンオイルでは、オイル消費を減らすことができれば、排気ガスの浄化につながる
ことから、蒸発特性に優れたオイルを開発することが、触媒(貴金属を用いています)の保護
や排気ガスのクリーン化に貢献することになります。
以上に挙げた機能や特性は、残念ながらベースオイル単独ではなかなか達成し得ないのが実状です。
鉱油に較べ、化学合成油の場合は性状が安定している(構成物質の化学的組成が均一である)ぶん
有利ですが、それでもなお、ベースオイルですべての要求を高次元で満たすことは非常に困難です。
そこで登場するのが、添加剤やブレンドといった概念です。
添加剤は、もともとのベースオイルには
無い性質を付加させたり、あるいはその欠点を補い合うために混合されたりします。どんな添加剤を
どれだけ付加するかについては、そのオイルの適用部位や目的によって異なってきます。
また、添加剤にもベールオイルとの 「相性」 があるようです。
これらについては、別途、「添加剤に
ついて考察する」
というページにて解説する予定ですので、そちらもご覧下さい。
■ オイルの寿命を決める指標 ■ |
「オイルは使用していくうちに徐々に劣化していく」
ことは先にも述べました。具体的には、オイル
そのものの変質により劣化する場合、添加剤が消耗することによる劣化、外部からコンタミ(使用
中に発生していく金属摩耗粉や樹脂摩耗粉、繊維、外部から混入するゴミなど)が混入することに
よる劣化、等が挙げられます。ここではそれを原因別に分類して、もう少し詳しく追ってみましょう。
・オイル(基油)そのものの劣化
・添加剤成分の消耗による劣化
・燃料成分の混入(希釈)による劣化
・燃焼ガス成分の混入による劣化
・コンタミ混入による劣化
【オイル(基油)そのものの劣化】
オイルは高温・高負荷にさらされると、酸化反応により基油の一部が-CHO基や-COOH基など
の官能基へと変化します。さらに酸化が進むと、官能基を複数個持った化合物へと成長し、それ
らが次第に重合していきます。重合が進むと分子量が増えるので、ついには溶けきれずに不溶
解分となって析出し始め、粘度は上昇してしまいます。
つまり基油が劣化すると粘度は上昇し、不溶解分によるスラッジ(高分子化合物による堆積物)
の発生や、メタル(軸受け)の腐食・摩耗、その他摺動部の摩耗促進の原因となってしまうので
す。このような劣化に対しては、「全酸価(単位は mgKOH/g)」
という指標を用いた化学分析を
行うことで、使用中のオイルが使用可能範囲内にあるか、限界を越えているかの判定を行いま
す。これはJIS規格で試験方法が定められており、例えばSAE30相当では「JISK2502-65」
という試験方法にて 「新油からの増加量が2〜3以下のこと」
となっています。この値を超えた
劣化油は、限界なので使用しないこと、という意味です。
【添加剤成分の消耗による劣化】
パワーユニットに適用されるオイルには、鉱油にも化学合成油にも、基本性能をアップさせるた
めの各種添加剤が加えられています。清浄分散剤や消泡剤、酸化防止剤、摩擦調整剤(FM)
などです。これらの添加剤は、使用していくとともに消耗し、その機能が低下していくことが知ら
れています。例えば
省燃費効果を狙った摩擦調整剤(FM)としてMoDTC(モリブデン・ジチオ
カーバメイト)
がよく用いられていますが、運転時間(≒走行距離)の増加に応じて摩擦損失も
次第に増加してしまいます。添加剤の機能が消失したオイルは劣化したオイルということです。
【燃料成分の混入(希釈)による劣化】
エンジンオイルでは、燃料の希釈により粘度が低下することがあります。これは、燃焼室内で
壁面とピストンリング、あるいはピストンリングとピストンとのスキマを通って
油中に燃料(ガソ
リン)が混入するためです。特に低温始動時など、燃料の気化が不完全で液体状のまま燃焼
室内に導入される場合に起こりやすいと考えられます。
希釈による粘度低下が進行すると、
油膜保持効果が低下するので、摩耗や焼き付きといった懸念点がでてきます。
【燃焼ガス成分の混入による劣化】
同じくエンジンオイルにおいては、排気ガス中に含まれるNOx(やニトロ硝酸エステル類)が
ブローバイガスとともに油中に混入します。ブローバイガスは高負荷になるほど増大します。
油中に混入したこれらの物質はスラッジの原因となり、オイルを変質・劣化させます。スラッジ
が成長するとピストンスカートやロッカーカバーに付着するだけでなく、油圧経路を閉塞する
恐れもあると言われていますので、燃焼ガスによるオイルの酸化程度も、劣化具合を判断す
る一つのパラメーターになります。
【コンタミ混入による劣化】
オイルは、使用していくうちに、その内部に様々な異物を取り込みます。例えばミッション
オイルやギヤオイルにおいては、ハイポイドギヤの金属摩耗粉やクラッチフェーシングの
摩耗粉、その他繊維質、外部から混入するゴミなどが挙げられます。これらのコンタミは、
それ自身が摺動部の摩耗を促進させる場合もありますが、油中で不溶解分のコアとなっ
てオイルを劣化させることもあります。
これらの原因により、オイルの劣化は避けられませんが、その劣化度合いを判定する指標としては、
一例として次のような項目があります。
・動粘度(Cst)の測定
・全酸価(mgKOH/g)の測定
・全アルカリ価(mgKOH/g)の測定
・引火点(℃)の測定
・ペンタン不溶解分(Wt%)の測定
・ベンゼン不溶解分(Wt%)の測定
これらの項目にはJISで定められた試験方法があり、参考としてそれぞれのパラメーターごとに使用
可能範囲が示されています。ただ実際には、パワーユニット用オイルの交換時期については、クルマ
(機構)ごと、ドライバーごと(運転条件)、あるいは季節によっても異なってくるので一概に横並びで画
一的に決めることは困難であり、その時点でのオイルの状態(色、粘度、におい、コンタミ有無、前回
交換時からのインターバル、交換後に想定される車両の使用条件、など)を総合的に考慮したうえで
決定されます。現実には、ドライバーの嗜好や感覚により交換される場合もあります。
そこで、オイルメーカーが推奨する交換インターバルや自動車メーカーが整備手帳に記載している
交換インターバルを元に、自分なりの車両使用状況を考慮して決めるのが現実的で良いでしょう。
ただ、ガソリンスタンドのサジェスト(お勧め作戦)やカーショップが独自に定める交換インターバル
については、実際のオイルの実力よりもはるかに短い期間に設定されている場合がほとんどです。
宣伝に踊らされないように注意することが必要です。
というのも、GSやカーショップではオイル交換による売り上げ利益増を狙って、必要以上に短い交換
サイクルを設定しているのではないか、と思われてならないのです。
ごく一般的な走りのごく一般的
なユーザーであれば、例えば今どきのクルマではATFの交換は(10万km程度までは)不要です。
あらかじめ不要となるように、劣化状態を見越してATのソフト&ハードの設計・仕様決めを行って
いるからです(旧車はこの限りではありません)。やはり、自動車メーカーが整備手帳に記載してい
る交換インターバルが基本です。 もっとも、その記載値自体が短い交換サイクルなら、それに従う
べきですが。
このページでは、
「オイルの成分と機能などについて」
と題して説明をしてきました。
次ページでは 「各種添加剤について」
の説明をする予定です。こちらもご覧下さい。
参考文献 :
「JISハンドブック・石油/日本規格協会」
「TOYOTA Technical Review/Vol.47 No.1」
「出光技報 41巻4号/1998」
「月刊出光」 他
■オイルとオイルポンプに関する考察 INDEX■
(目次を確認する)
↑
![]() ← オイルの分類と機能について → NEXT
← オイルの分類と機能について → NEXT![]()
(前のページはありません) (このページ:1/6ページ) (「添加剤について」に進む)