「炎症疾患における各種薬剤の話」 第一部へ戻る
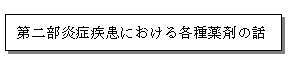
8. 「炎症」においても各種の細胞が分子を介して相互作用します。
(炎症=発赤、膨張、発熱、疼痛)
「目で見るクスリの作用学」第二部
「炎症疾患における各種薬剤の話」
第一部へ戻る![]()
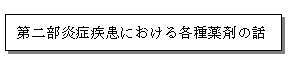
8. 「炎症」においても各種の細胞が分子を介して相互作用します。
(炎症=発赤、膨張、発熱、疼痛)
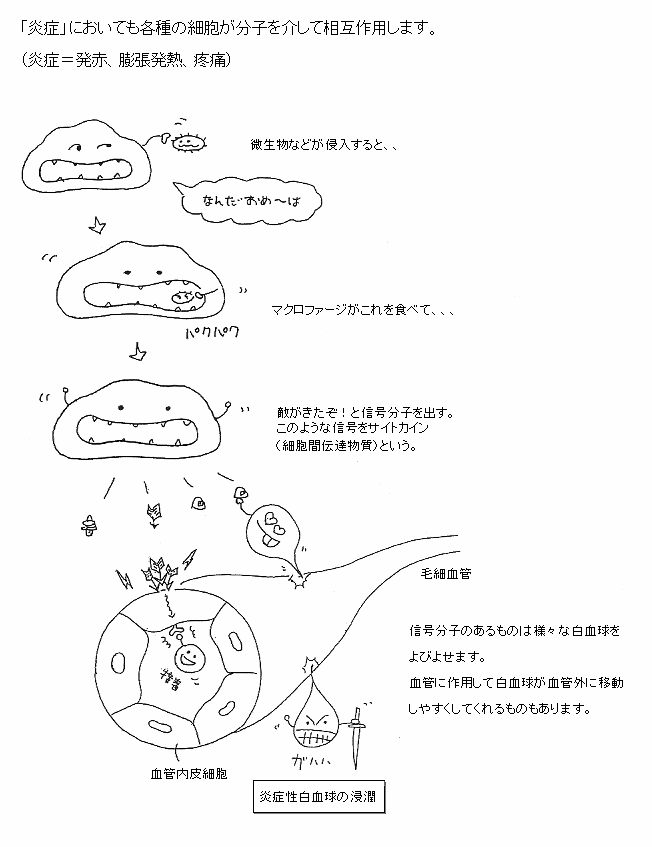
9. 微生物がやってきて炎症の急性期を越すと、今度はより高度な細胞間の相互作用が働きます。
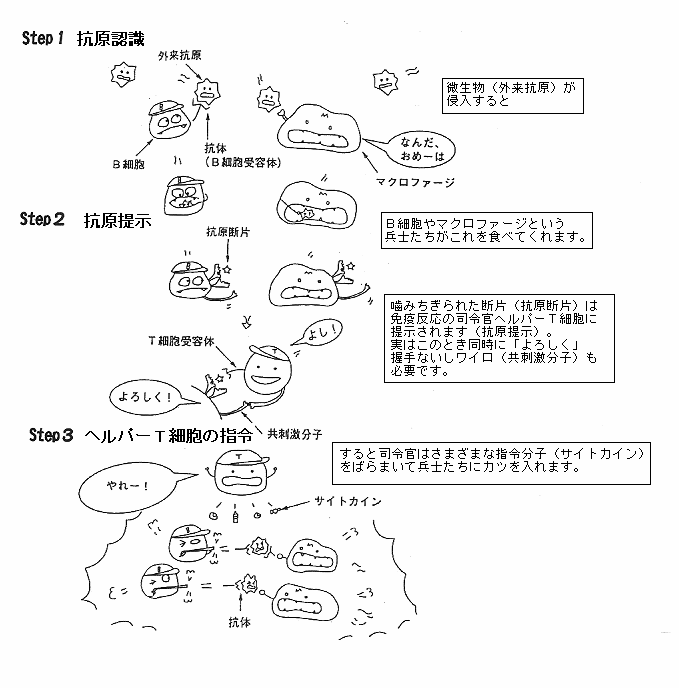
これが免疫反応のアウトラインですが、度を超せば「アレルギー」
自分の成分に対して生じれば「自己免疫」となります。「慢性炎症」「アレルギー」「自己免疫反応」を抑える薬についてみていきましょう。
10. 非ステロイド性抗炎症薬
(いわゆるNSAIDs = non steroidal
anti inflammatory drug)
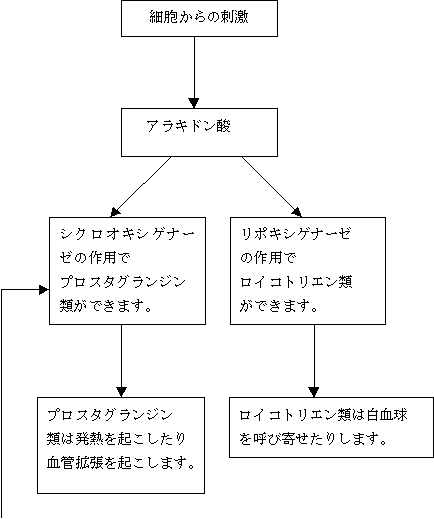
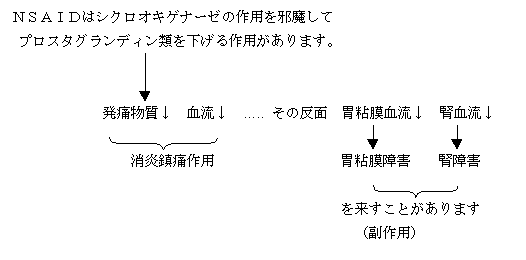
<参考1>
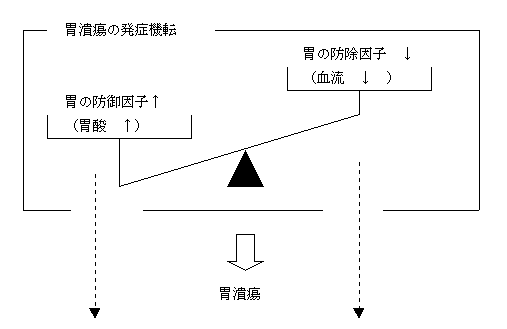
<対策> 制酸剤を使う
胃粘膜保護剤を使う
(胃酸
↓) 胃の血流低下を来しにくい
NSAIDを使う(→参考2)
<参考2>
シクロオキシゲナーゼ2のみを邪魔すれば、胃や腎の血流を下げることなく消炎鎮痛効果が発揮できるかも知れない…..消炎鎮痛効果が発揮出きるかもしれない….. との期待のもとで開発がすすめられています。
(製品名:ハイペン、オステラックなど)
「COX-2のみを抑制する治療法は、副作用のない方法として開発当初は期待されていましたが、からだはそれほど単純ではなく、このような単純な図式では割り切れないことのほうが多いということを常に念頭におかなければなりません。日本で現在使用されているCOX-2阻害剤は副作用は少ないながらも作用、つまり鎮痛作用も弱いことが多いのが現状で、まだまだ開発の余地があるようです。」
11. ステロイドの作用機序と処方量
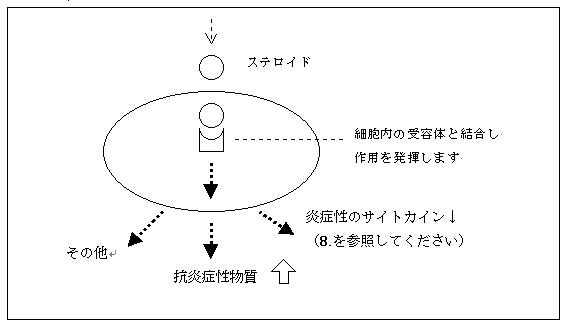
※ステロイドは目的に応じて処方量が異なります。
① パルス療法 プレドニゾロン 1g 3日点滴
大量 プレドニゾロン 60mg 前後
② 中等量 プレドニゾロン 30mg 前後
③ 少量 プレドニゾロン 5~10mg
過剰な免疫応答が 肺や腎臓などをおかし、生命の危機がある時には
① のような量を使います。状態が落ち着けば、②→③と減らします。
また、慢性関節リウマチだけで、①、②の量を処方することは、まずありません。使うとしても、③の量です。
12. 免疫抑制剤
(メソトレキセート、ミゾリビン、シクロスポリン、アザチオプリン等)
対象とする疾患ごとに意味合いは異なります。例えばステロイドが効かない難治性の膠原病に対して免疫抑制剤を加える場合は、ある意味で「いたしかたなく」処方するのですが、慢性関節リウマチに対するメソトレキセート少量パルス療法は、今やごく一般的な処方法なのです。
13. 抗リウマチ薬
(今やメソトレキセートもここに含まれます。シオゾール、アザルフィジン=サラゾピリン、リマチル、メタルカプターゼ)
慢性関節リウマチの患者さんに薬を処方する時、私はこの氷山の絵をかいて説明させていただいています。
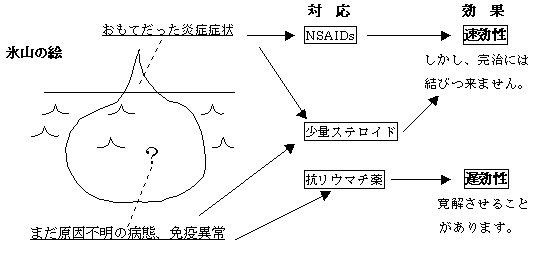
14. これは私の印象ですが、同じ病名でも氷山の形は、個々で全く異なりそれぞれの患者さんが受ける治療方法もそれによって異なって当然と思います。
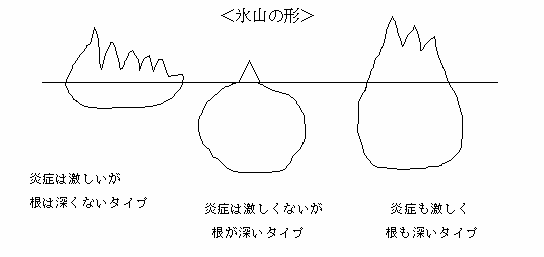
これまで不明の病態が、だんだんと明らかになるにつれて、個々の固有の病態に応じた治療がなされる時代が必ずくることでしょう。
|血清反応陰性脊椎関節炎 | 強直性脊椎炎とは | 強直性脊椎炎とHLA | AS及び血清反応陰性脊椎関節炎の治療 |
|強直性脊椎炎とぶどう膜炎 | 強直性脊椎炎の急性ぶどう膜炎とHLA-B27サブタイプおよびDR8 |
|腸炎合併性脊椎関節炎 | クローン病・潰瘍性大腸炎について| サラゾピリン(SASP)、ペンタサ(5-ASA)の薬効と作用機序 |
|「AS治療の最前線」 外科的治療|「目で見るクスリの作用学」|