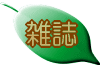第五章 サイト開設
インターネットを利用するようになってからというもの、ずっと願っていることがあった。海老沢作品の完全目録サイトの登場である。この広い世界にはファンは大勢いるだろうから、いつか適任者がそういうサイトを立ち上げるだろうと漠然と期待していた。いまのところ、ぼくがあちこちから得た情報を書き記した一冊のノートより詳しいサイトはなかった。ノートはいつもバッグの中に入れておいた。図書館や書店で何か情報を見つけたとき、それがすでに入手済みの情報なのか、または新しい情報なのかをすぐに確認できるように。そして新しい情報だったら書き足した。
そういうある日、ふと、このノート以上に詳しい目録は存在しないのではないだろうかと思った。ファンは大勢いるだろうが、ぼくほど詳細に調べ、大宅文庫にまで通ったりしている人間がいるだろうかと疑問が湧いたのだ。
証拠はないが、答はノーだと思った。
「それじゃあ、適任者はぼくということになるじゃないか」
と思った。何しろ情報はすでに揃っている。あとはサイトの制作方法を勉強するだけなのだ。
最初は冗談じゃないぞと否定的だった。ノートは時間と金をかけて集めた結晶なのだ。それを無料で公開するなんてできない相談だった。そのころ友人に、
「そのノートのコピーを取らせてくれと頼まれたらどうする?」
と聞かれ、
「十万円積まれても応じるつもりはない。五十万円積まれたら少しは考える」
と答えたことがある。何て狭量なのかと恥ずかしくなるが、それぐらいぼくにとっては大切なノートだった。
そういうケチな考えはしばらくすると朝霧のように消え失せた。ファンの人たちの参考になるなら、それでいいじゃないかと思うようになった。情報を公開したところでぼくの体験が色褪せるわけではないのだ。
海老沢作品を求める過程において、ぼくは様々なことを知った。出版社に対する認識がまちがっていたこともそうだし、ISBNという、本の裏表紙に記されたコードナンバーは世界に一つのナンバーだということもそうだし、共同通信のこともそうだ。
テレビのニュース番組で、「共同通信によりますと」という言葉をよく耳にしてきたが、何のことか知らなかった。だがネット検索で共同通信の取材に応じた海老沢泰久のコメントがいくつかヒットしたので調べてみると、共同通信という通信社が取材した情報を、契約している新聞社や放送局に配信していることが分った。つまり「共同通信によりますと」という言葉が使われるときは、そのニュース番組や新聞社の独自取材ではなく、共同通信から配信された情報を伝えているに過ぎないということだ。そして配信された情報を使うかどうかは各社の判断だった。そのために、海老沢泰久のコメントがどの新聞に載っているのかは地道に調べなければならなかった。
直木賞における短編集の扱い方も、知ったことの一つだ。
『帰郷』が受賞したとき、ぼくは表題作の短編『帰郷』が一作で受賞したのかと勘違いした。しかし調べてみるとそうではなく、短編集全体を一つの作品と見なしての受賞だった。
ぼくはそれらのことを知ったり、図書館や大宅文庫に行ったり、書店で目次チェックをしたり、パソコンを買ったりしたことのすべてを愛した。それで充分だった。
しかしそれでもサイト制作に向けてなかなか行動に移せなかった。踏み切れない最大の理由は「著作権の侵害」だった。
サイトに海老沢作品を丸々載せてしまったら「著作権の侵害」になることぐらいは分る。だが、転載と引用の違いなど、細かいことはまったく分らなかった。目録だけのサイトなら構わないのではないかとは思ったものの自信はなく、もし法に抵触してしまったらどうしようと怖気づいていた。
それがあるとき、知り合いの図書館員の男と話しているとき、彼が言った。彼には専門的知識があった。
「どの雑誌に何という記事が載ったかという一般的事実を並べるだけなら、著作権の侵害にはならない。それどころが、それを体系的にまとめたら、それ自体が君の著作物になる」
サイト制作はその日からはじまった。
書店のパソコン関連コーナーにはサイト制作のための手引書は何種類もあった。技術的なことは何とかなりそうだった。問題は内容だった。
法に抵触しないものにすることはいうまでもない。だが抵触しなければ何をやってもいいとは思わなかった。ファンサイトの中には、目撃情報を載せているものもあった。デパートで買い物をしていたとか新幹線のなかで見かけたという情報である。そういう、プライベートに立ち入ることのないように心がけた。また、ぼくはエッセイを通して海老沢泰久の生い立ちをある程度知っていた。どこで生まれ、どういう少年時代を過ごし、どういう本を読み、イギリスでどんなふうに暮らしたかを。それらを集めれば面白い年表のようなものが作れそうだった。だがそれもプライベートに立ち入ったことなので控えた。あくまでも作品目録にとどめることにした。それがファンとしての領分をわきまえることになると考えたからだ。
基本的な構成はすでに決めていた。すべての情報を「書籍」、「雑誌」、「新聞」、「その他」の四項目に分類し、年代順に並べるのだ。「その他」に載せるのは、ネット上にだけ発表されたエッセイや文学賞の選考委員情報や講演情報である。「書籍」にはもちろん、ISBNも載せる。
確証が得られない情報は載せないことにした。ネット検索で新聞記事や雑誌記事がヒットしても、ぼくがその記事を実際に目にするまでは載せないということだ。ただし講演情報は、ぼくがその講演に参加していなくても、新聞記事になっていれば本当に開催されたものと見なした。
自分なりの解説や評価は書かないつもりだった。そんなことは簡単にできることではないからだ。ぼく宛てのメールアドレスは記したが、掲示板を作るつもりもなかった。著作権を侵害しないように配慮していても、掲示板に作品を丸々書いてくる人間が現れないとも限らない。発言内容を削除すればいいのだろうが、削除するまでのあいだは著作権を侵害していることになる。そうかといって四六時中監視しているわけにもいかない。だからこちらが一方的に情報を提供するだけにとどめた。
トップページのデザインは公園をイメージした。春のおだやかな日、木漏れ日を浴びながらベンチで読書を楽しんでいる風景を思い浮かべた。そんなふうにして海老沢作品を読んだら楽しいだろうなと想像しながら。
サイト制作を誰かに手伝ってもらおうとは思わなかった。反対に、誰にも手を出してほしくなかった。図書館通いや目次チェックといった一連の行為に関し、ぼくはすべてを一人でこなしてきた。友人の中にぼくほどの海老沢ファンはいなかったし、いくら友人だからといって、ファンでもない人間に大宅文庫や古書店街につき合ってもらうわけにはいかなかったからだ。ここまで一人でやってきたのだ。最後まで自分の意思を完全に反映させたかった。
そういうサイトを二カ月かけて作った。
完成したのはある土曜日の夜だった。情報はたくさんあるしパソコンの操作にも不慣れなので、ぼくは気長に、時間のあるときに少しずつ進めていた。急ぐ必要はない。締め切りなんかないのだ。その夜もノートを見ながらキーボードを叩いていた。それがあるとき、ページをめくると白紙が出てきた。
「あ、終わったんだ」
と思った。実に呆気なかった。
一九九八年八月十三日、海老沢泰久ファン以外にはまったく意味のないサイトが、インターネットにひっそりとデビューした。