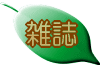第四章 パソコン
ぼくは大宅文庫でのコピー一枚百七十円を筆頭に、海老沢作品のためにけっこう金を使ってきた。こんなに好きになれるものなど生涯を通してもそう出会えるものではない。海老沢作品と出会わなかったらと思うと、ゾッとするほどである。だから金のことは問題にしないようにしてきた。
それでもパソコンのときは大いに迷った。「特報首都圏」を見た翌日、さっそく近所の家電量販店に行ったら、三十万円もしたからだ。デスクトップが、である。今なら六万円ぐらいで買えるものが当時はこれぐらい高価なものだったのだ。それはぼくにとってはポンと出せる額ではなかった。もっと安く買えないものかと秋葉原にも出向いたのだが、安くても二十七万円だった。店員にマニュアルだけ売ってくれないか交渉してみたが、断られた。
さすが秋葉原というべきか、マニュアルだけを扱っている専門店もあったが、そこにも『これならわかる パソコンが動く』はなかった。新商品のマニュアルは入荷までしばらく時間がかかるということだった。
どうしようかとため息が出た。車以外にそんな高価な買い物をしたことはない。大きな買い物だった。しかし一方、きっと買うことになるのだろうなと思っていた。他のことならともかく、海老沢作品がからんできたとき、ぼくは精神的な抵抗力を失ってしまうのだ。結局、一カ月ほど迷っていたのだが、それは買うかどうかを決めるためというよりも、二十七万円を使う覚悟ができるまでの期間だった。
アパートにパソコンが配送されたのは一九九七年二月だった。直後にNECはユーザーからの「あのマニュアルを販売してほしい」という要望に応えて出版した。書店に並んだわけだ。皮肉なことではあったが、覚悟を決めた上での購入だったので、特に悔しくもなかった。
二年前のウィンドウズ95の登場以来、パソコンが急激に売れはじめていることは知っていた。しかし友人の中で、ぼくより先にパソコンを買っていた人間は二人しかいなかった。流行ものにはまったく疎いぼくが三番目の早さなのは非常にめずらしいことだった(ただし携帯電話に関しては本来のぼくが発揮され、今も持っていない)。
インターネットが使えるようになって一番頼りになった機能はサーチエンジンだった。「海老沢泰久」をキーワードにして検索すれば四百件も五百件もヒットした。
ぼくは雑誌記事に関してはかなり把握できているつもりだったが、新聞記事は弱点だった。地方紙まで含めると何十紙あるのかさえも分らず、雑誌とちがって目次もないので手をつけることもできずにいた。そんなことは砂漠で落としたコンタクトレンズを探すようなものだと思っていた。それが検索でヒットした。北海道新聞や日刊スポーツの記事を発見できたし、スポーツ報知における報知ドキュメント大賞の選者を海老沢泰久が務めていることも知った。大賞が発表されるときには選評があり、それももちろん海老沢作品だった。
今度こそ、もう書店での目次チェックは必要ないだろうと思った。そのころになると、目次チェックはかなり早くできるようになっていた。「海老沢泰久」という文字を目を凝らして探すというより、目次をパッと見て、そこに「海老沢泰久」の文字があれば、意識しなくてもそこに焦点が合うようになっていたからだ。そういう境地に達したのだ。目次チェックをはじめて五年が経過していた。ちっとも苦ではないが、やらずに済むならそれに越したことはない。三十誌ばかりをチェックしていたが、これからはもっとたくさんの目次をアパートに居ながらにしてチェックできる。そう思っていた。何しろ世界とつながっているのだから。
甘かった。いくら世界中から情報を集められても、情報の提供側がちゃんと「海老沢泰久」という文字を入れて目次を公開してくれなかったらヒットしようがないのだ。そして完全な目次が公開されている雑誌は驚くほど少なかった。三十誌どころか、二十誌にも満たなかった。ぼくはまた出版社に対する自分の認識がまちがっていたことを思い知らされた。出版社というのは、雑誌を売ることに力を注いでいて、そのためには完全な目次を公開することなど基本中の基本と考えているところだと思っていた。そうではなかったのだ。
また、検索結果がすべて正しいとも限らなかった。
あるとき、健康雑誌の目次に海老沢泰久を発見した。それはエッセイで、本文の一部が紹介されていた。それがどうしても海老沢泰久の文章とは思えなかった。いつもの、心にピタッと収まる文体ではなかったのだ。「ですます調」なのも腑に落ちなかった。『これならわかる パソコンが動く』は「ですます調」だが、それはマニュアルであるための配慮であって、それ以外の作品はすべて「である調」だった。
その健康雑誌を買う前に情報提供者にメールで問い合わせることにした。
「それは本当に海老沢泰久氏が執筆したエッセイなのでしょうか?」
翌日、返信がきた。
「すいません、まちがいでした」
返信はそのあと、意図的ではなく、本当に単なるまちがいだったと続いていた。
ぼくは悟った。インターネットもツールのひとつに過ぎないのだ。とても便利ではあるが、検索してヒットしないからといってこの世に存在しないとは限らないし、ヒットした情報を盲信するわけにもいかない。何かを調べるとき、インターネット一つを頼るのはとても危険なことなのだ。
オーケイ、目次チェックを続けようじゃないか。
ツールの一つに過ぎないとは言うものの、インターネットが貴重な情報源であることはまぎれもない事実である。
『F2グランプリ』は一九八四年に映画化されていたが、まだ見ていなかった。封切り当時はまだファンではなかったし、評判になった記憶もない。ファンとしては見ておきたかったが、どこのレンタルビデオ屋にも置いていなかった。
それがインターネットによる中古ビデオの売買によって、あっけなく入手できた。
『プロ野球グラフィティー 西武ライオンズ』と『プロ野球グラフィティー 1984西武ライオンズ』という絶版本も簡単に入手できた。
その二冊は、新潮文庫という書物のかたちをとってはいたが、一種のムックだった。だから重版されることはなく、入手するには古書店を当たるしかなかった。書物の体裁を整えていたので図書館で所蔵しており、借りて読んではいた。だがやはり手元に置いておきたく、週末の会社帰りによく神保町の古書店街を歩き回っていた。五年に渡って、二十回ぐらいは行ったと思う。しかし見つけたことはなかった。
それが、九州にある文庫専門の古書店のサイトにその二冊をリクエストしておいたら、一カ月も経たないうちに入荷のお知らせメールが届き、料金を振込むことで送られてきた。なんて便利なんだろうと感心した。
『F1500戦/40周年 地上最速のドラマと歴史』を入手したときはあまりの便利さに感心を通り越してあきれてしまった。
検索によりそこに海老沢泰久のエッセイがあることが分った。しかしこれもムックだった。重版されることはない。そしてまずいことに、今度は図書館どころか大宅文庫にもなかった。大宅文庫でもムックは弱点だったのだ。
浦安の図書館が所蔵していなかったときは、特に危機感もなく、いつものように大宅文庫を頼ればいいやと楽観していた。しかし次の土曜日に訪ねてみると、そこでも所蔵していなかった。ショックだった。絶望感でいっぱいになり、目の前がまっくらになった。打ちひしがれ、その日は何の収穫もないままアパートに帰った。
残された方法は、情報提供者にメールで入手方法を相談してみることだった。ぼくはそうした。すると翌日、神保町あたりの古書店にあるのではないかという返信がきた。そして、親切にもモーター・スポーツ関連本が充実している店まで教えてくれた。それに従い、ぼくは店に電話をかけ、有無を問い合わせた。
「ちょっとこのままお待ちください」
と若い声の男の店員が受話器を置いて探しに行った。ドキドキしながら待った。どうかありますようにと願いながら。ここになければ、もうおそらく入手できないだろう。最後の頼みの綱だった。やがて帰ってきた店員が言った。
「ありました」
ぼくは飛び上がりたい気分だった。興奮を抑えて言った。
「今日の昼に伺いますので、取り置きしてもらえますか?」
それは平日十一時ごろの、会社近くの公衆電話からの電話だった。
「分りました。お待ちしております」
と店員が言った。
電話を切り、会社に帰ったぼくは店員から聞いた店の住所をこっそりと地図で確認した。そして昼休みに、まっしぐらにその店に行って買った。ほしい本を求めて何度も古書店街を歩き回っていたときとは正反対の、まったく無駄のない入手方法だった。これがインターネットの真骨頂なのだろうが、あまりの効率のよさに、開いた口がふさがらなかった。