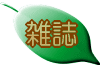第三章 「直木賞」
今でこそ芥川賞や直木賞は候補に選出された時点で新聞記事にもなり、受賞でもすればテレビでも報道されるが、一九九四年当時はそういうことはなかった。受賞作が決定したときだけ新聞に載る程度だった。ぼくもそのニュースを新聞記事ではなく、友人から知らされた。候補になっていたことすら知らなかったので実感が湧かなかった。呆然としてしまい、友人の「おめでとう」という言葉に、ぼくが受賞したわけでもないのに「ありがとう」と答えていた。
喜びは時間の経過とともにじわじわとやってきた。
何よりうれしかったのは、これで海老沢泰久も売れっ子作家の仲間入りが約束されたことだった。ファンになってから七年が経っていたが、そのあいだに、ぼくに『監督』をプレゼントしてくれた友人を除いて、海老沢作品を読んだことがある人間に会ったことはなかった。誰かと小説や作家の話をするたびに苦汁をなめていた。
そういう状況が一変するに違いなかった。書店では「海老沢泰久フェア」が開催され、本の売れ行きは飛躍的に伸び、その名を知らない人はいなくなる。今後は小さなエッセイでも何でも、書いたものはすべて本になり、過去の、まだ本になっていない作品が続々と出版されるだろう。必然的に書店での目次チェックも必要なくなる。目次チェックは進んでやってきたことなので苦になったことはないが、やらずに済むならそれに越したことはない。そのようにして海老沢泰久は、本人が望まなくても売れてしまう。直木賞を受賞するというのはそういうことなのだ。ぼくにはそれは、コーラを飲んだらゲップが出るのと同じぐらい当然のことに思えた。栄光の扉は開かれたのだ。
甘かった。ぼくの職場は大手町で、近かったせいもあって、受賞後すぐに八重洲ブックセンターや日本橋の丸善に行ってみたが、「海老沢泰久フェア」は開催されていなかった。一週間後に再度行ってみても同じだった。店員も客も海老沢泰久のことを気にしている様子はなく、何事もなかったようにそれぞれの事情に従って黙々と行動していた。暇そうな店員に、
「他にやるべきことがあるんじゃないのか」
と詰め寄りたいぐらいだった。
結局、八重洲ブックセンターの「今週のベストセラー」コーナーの十位に『帰郷』が二回だけランクインしたこと以外に目立った動きはなかった。とてもじゃないが、売れっ子になったとは思えなかった。
ぼくは拍子抜けしてしまい、荒野にぽつんと取り残されてしまったような孤独感におそわれた。霞んだ頭で、
「売れるって何だろう、直木賞を取るって何だろう」
と思った。
ぼくは出版社というのは、直木賞のような大きな賞を取った作家の作品はどんなに短いエッセイであれ、すべてを本にして世に送り出すところだと思っていた。売れる売れないは関係ない。採算度外視。そうすることは活字文化に身を置いている者の責務だと考えているのかと思っていた。しかし調べてみると、受賞者のすべての作品どころか、受賞作でさえ、売れなくなれば絶版にするところだった。受賞は実力が認められたに過ぎず、そのことと売れることはまったく別の話だった。ぼくが無知だったのだ。
その後も図書館通いと目次チェックは続くことになった。新作が期待できる目次チェックはともかく、図書館通いも尽きることがなかった。新聞・雑誌記事目録に載っていない情報を知ることもあるからだ。
デビューから直木賞受賞にいたるまでのエッセイにこういう件があった。
「『夏子』という二十枚の小説を書いて(小説新潮新人賞に)応募したが、吉行さん(吉行淳之介)の選評によれば『これはたわいもないことをたわいもなく書いているが、そのたわいのなさ加減におもしろいところがある』というので、入選作になってしまった。(中略)入選するなどとは思ってもいなかったので発表誌を買うのも忘れていたほどだった」
ぼくは海老沢泰久が『乱』で小説新潮新人賞を受賞したことは知っていたが、このエッセイによって、『乱』の前に『夏子』という作品が雑誌に掲載されていたことを知った。それを探すためには図書館に足を運ばなければならなかった。
直木賞受賞から二年ばかり経ったある日、八重洲ブックセンターで新刊『愚か者の舟』を発見した。
うれしかったが、なんだか様子がおかしかった。通常、新刊が発売されるときというのは、新刊コーナーで平積みされているものだが、棚に一冊だけ背表紙を向けて入っていただけだったのだ。店員に聞いてみると、全国の書店に並ぶ一週間ぐらい前に、ほんの一冊か二冊入荷することがあるということだった。
それは大型書店だけの事情なのだろうが、そのわずかな期間に、あるかないかの一冊に巡り会えた。ぼくはそのことに運命を感じた。
運命は続いた。
ある土曜日の夕方、テレビでNHKのニュースを見ているときだった。翌日放送の「特報首都圏」という番組の予告が流れた。ナレーションが、
「今、パソコンメーカー各社は、マニュアルが分りにくいというユーザーの声に対応するため、分りやすいマニュアル作りに取り組んでいます」
と言った。何気なく見ていると、ほんの一瞬、海老沢泰久らしき人物の横顔が映ったような気がした。
ドキンとした。本や雑誌で顔写真を見たことはあるが、動いたりしゃべったりしているところを見たことはなかった。そしてほんの一瞬の映像だったので、本当に本人なのか確信はなかった。翌日の放送は必見だった。
やはり海老沢泰久だった。NECの分りやすいパソコンマニュアルを書いたのが海老沢泰久だったのだ。
番組内でパソコンマニュアルに関する報道は五分ほどで、海老沢泰久の発言は一回だけだった。
「パソコンを電源コンセントにつなぐとき、従来のマニュアルだと、『ACコンセントにつなぐ』と書いてある。ACコンセントが何のことかわからない人にはストレスがたまる表現だと思う。そしてそういうことが何度もあると、最後にはストレスが爆発して、もうやめたということになる。そこでぼくは『部屋のコンセントにつなぐ』と書いた」
それは、ぼくがはじめて聞く海老沢泰久の肉声だった。想像していたよりかん高い声をしていた。
興奮して画面に釘付けになりながら、明日にでもそのマニュアルを買いに行こうと思った。『これならわかる パソコンが動く』というのがマニュアルのタイトルだった。パソコンは持っていないからマニュアルだけ買っても意味はないのかも知れない。しかし海老沢作品を全部読まなきゃ気がすまないぼくにはそんなことは関係なかった。
ところが大きな問題が立ちはだかった。
そのマニュアルはNECのバリュースターという機種に無料で添付される非売品だったのだ。