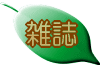第二章 「美味礼讃」
「五月のある日曜日、日高三郎は前夜から一睡もできぬまま朝を迎えた」
『美味礼讃』の冒頭の文章である。
一九九二年二月、飯田橋駅近くの書店。ぼくは新刊コーナーで平積みされた『美味礼讃』を発見した。
「あ、新刊が出たんだ!」
と胸が高鳴った。夢中で手にとってページを開いた。そしてこの文章にぶつかったのである。
この書き出しが一体どうしたのかと思われるだろうか。何のへんてつもない簡単な文章じゃないかと。たしかにそうかも知れない。でも海老沢作品を熱心に五年も読み続けてきたぼくにとってはそうではなかった。この書き出しだけで、こう直感した。
「とてつもなく素敵なことが起こる」
直感は正しかった。これは辻調理師専門学校の創設者辻静雄の半生を描いた伝記小説なのだが、さっそく買ったこの本を、ぼくは例によってダイヤモンドを一つ一つ確認するように、五日ほどかけて味わった。その五日間はこの本のことが頭から離れなかった。そのときぼくは就職して会社員になっていたのだが、昼間、表面的には仕事をしていたが、頭の中は本のことでいっぱいだった。物語の続きが気になっていたのではない。言葉が心にピタッと収まる快感を味わっていたのである。
「誰かを食事に招くということは、その人が自分の家にいる間じゅうその幸福を引き受けるということである」
これはブリア・サヴァランという一九世紀のフランスの美食家による『味覚の生理学』の一節である。『美味礼讃』にそう書かれていた。その『美味礼讃』はぼくが読んでいる間じゅうの幸福を引き受けてくれた。残りページが少なくなってきたときには、
「ああ、もうすぐこの物語が終わってしまうのか」
とさびしい気持にもなった。
そして物語が終わった。
本を閉じたぼくは、静かに、そして深い感動に包まれた。とても満ち足りた気分で、しばらく目をつぶってその余韻に浸った。
やがて目を開けたとき、ぼくは決心していた。
「この人の作品をすべて読む」
それまでは著書を再読できれば満たされていたが、もうそれだけでは我慢できなくなった。新聞や雑誌に掲載されただけで本になっていないエッセイや小説があるはずだ。それらを一つ残らず読むのだ。そうしなければ、誇張ではなく、死んでも死に切れないと思った。
ぼくの図書館通いと書店での雑誌の目次チェックがはじまった。
すべてを読むためには、すでに発表された過去の作品と新作を探さなければならない。過去については図書館で調べ、新作については書店で雑誌の目次をチャックすることにした。
雑誌の目次を隅々まで見て「海老沢泰久」の文字をさがすのは簡単ではなかった。目を凝らさないと見過ごしてしまいそうなぐらい小さい表示のときもあるからだ。「文藝春秋」や「小説現代」といった文芸誌を中心に、「ナンバー」などのスポーツ誌や「青春と読書」などのPR誌まで含めて、三十誌ばかりを最新号が出るたびにチェックした。そしてたとえ数行のコメントでも、掲載されていれば入手した。
隈なくチェックしていたからだろう、半年もすると、「海老名」とか「海老蔵」という似た字面にも目が行くようになり、さらに時間がたつと「海音寺」、「養老」、「貴久」といった、一文字しか符合していないものにまで反応するようになった。
図書館のほうでもっとも有効だったのは大宅文庫だった。
ぼくはそのころ浦安に住んでいた。地元の図書館で新聞・雑誌記事目録で七十作ばかりの記事を見つけ、そこで閲覧できる作品はコピーを取っていた。しかし図書館で購読していなかったり、購読していてもバックナンバーの保存期間が短いために閲覧できない作品がほとんどだった。雑誌によっては県立図書館から取り寄せてもらうこともできたが、すべてを入手するにはほど遠かった。
大宅文庫はそれをやすやすと解決した。
大宅文庫は評論家大宅壮一が遺した雑誌専門の図書館で、京王線の八幡山駅から徒歩八分、閑静な住宅街の一角にある。外見は図書館には見えないほど大きくない。しかしここには公共図書館では所蔵していないような大衆誌まで揃っている。海老沢泰久が長編デビュー作『監督』を書く前にルポルタージュを連載していた「GORO」もそういう大衆誌の一つだった。
ただしここは公共図書館ではないとはいえ、ずいぶん金のかかるところだった。現在では料金体系は変わっているようだが、当時は入館料五百円で閲覧できるのは十冊だけ。もっと閲覧したければ十冊ごとに五百円かかった。公共図書館のように見たい資料を自由に棚から取り出せるシステムではなかった。用紙に記入し、カウンターで申請しなければならない。どの人間がどの資料を閲覧しているかを完全に把握するシステムである。申請すると五分ほどで届く。名前を呼ばれたらカウンターで受け取り、空いている席で広げる。
ぼくは浦安の図書館で調べた新聞・雑誌記事目録の情報が完全かどうか疑っていたので、ルポルタージュが連載されていたころの「GORO」を片っぱしから調べたかった。また、「GORO」に限らず、広岡達朗の関連記事も調べたかった。ぼく自身がファンだったこともあるが、例えばインタビュー記事において、聞き手が海老沢泰久である場合も考えられたからだ。そちらも調べるとなると、もう年会員になるしか道はなかった。一万二千円を払って年間員になると、一日につき百冊閲覧できたからだ。そして実際、目録は完全ではなかった。
金がかかるのはそれだけではない。コピーが一枚につき百七十円だった。十枚コピーしたら単行本一冊買うより高くついてしまう。それでできるだけコピーは大宅文庫を頼らないことにした。そのためにもっとも利用したのは広尾にある都立中央図書館だった。そこでは一枚三十五円だった。大宅文庫で情報を得てもすぐにはコピーせず、その足で広尾に向かう。そこで所蔵していればコピーを取り、所蔵していなければ翌週改めて大宅文庫でコピーを取るというやり方だった。効率的とは言えないが、極力安く済ませたかった。しかし大宅文庫でしか入手できない資料は少なくなく、一回行くとコピーに三千円もかかってしまうことはめずらしくなかった。だが、海老沢作品があるかも知れないと期待に胸をふくらませて山積みされた雑誌を一冊ずつ手に取る行為は鉱脈を採掘するような興奮があった。開館時間の十時に合わせて行き、気がついたら午後二時を過ぎていたなんてこともあった。
そんなに血まなこにならなくても、いつかは本になるかもしれなかった。そうなればぼくがやっていることは、時間と金をかけて人よりほんの少しだけ早く読んだだけということになる。そんなことは分っていた。でも待てなかった。そうせずにはいられないほど、未読作品を渇望していた。
そんなことを二年ばかり続けたころ、ビッグ・ニュースが飛び込んできた。海老沢泰久が短編集『帰郷』で直木賞を受賞したのだ。