| ●データ、△引用、*私見。シェイクスピアの映画化だけでなく、関係する映画もとりあげる。
△道化に関して以下に喜志哲雄の論評を付記しておこう。 あらゆる劇は"世界の究極の意味を探る試みであると言える。その場合に、一つのやり方は、人間を超えた絶対的な目、つまり神の目を想定し、その目で見れば世界は隅々まで見えるのだと考えることである"。 "もう一つのやり方は、絶対的な目の存在を認め、しかもそれを人間のものと考えることである"。"我々は歴史の流れの中にある法則性ないし秩序を認め、歴史の目で見れば世界の意味が分るだろうと考えるのである。つまり、人間は歴史に究極の意味の認識を委ねるのであって、いわば歴史が神の代りをするのだと言える"。 "道化の精神はこれら二つのやり方のどちらもとらない"。人間を超えた絶対的な目も、歴史の法則性も否定する。"世界の究極の意味を現在この場で見てしまおうというのだ。道化の立場から見れば、過去と現在と未来との間には何の相違もないことになる。誰が王になろうと、誰が権力闘争から脱落しようと、同じことだというわけだ。人間とは要するに、自らの意志とは無関係にこの世に生まれ、欲望に動かされて生き、何の理由もなくやがて死ぬものなのだ"。 "道化とは完全な認識を得ようとする人間のことだ"。神にもっとも近づいた時のあり方だが、"しかし、人間は神ではない。賢明な道化はそのことを知っている。だから道化にできるのは、あたかも自らが神であるかのように、あたかも自らが世界の究極の意味を知っているかのように振舞うことだけである。あらゆる道化につきまとう演技性はこうして生まれてくるのではないか。フェステやタッチストーンは、あるいはハムレットやフォールスタフは、愚者ないし狂人を演じているにちがいないが、彼等はまた神をも演じているのである"。(喜志哲雄「シェイクスピアの道化」) 映画『マクベス』 池田博明 (1) ポランスキー監督の『マクベス』(1971年) ▼この映画は、登場人物を限定した心理劇だった。寒々しい風景が多く、荒涼とした感覚が漂う。この作品については狩野良規の本が詳しい。 ポランスキー監督の作品はよく見てきたし、『反撥』『吸血鬼』『ローズマリーの赤ちゃん』『チャイナタウン』や『テス』などは好きな作品だが、 この『マクベス』は登場人物が少なく、残酷描写が話題になったが、映像は物語をなぞっているだけに思えて、私は好きではない。もっとも、 最初に見たレンタル・ビデオはビスタサイズで収録してあったが、元のサイズはワイドである。BS2で放映したときはワイドサイズであった。 録画した本編を見直すまでは判断を留保せざるを得ないかも。 (2)黒澤明監督『蜘蛛巣城』(1957年) ▼大胆な翻案である。撮影は中井朝一(白黒)、音楽は佐藤勝(音を切りつめた効果)。冒頭、濃霧の中、荒野に蜘蛛巣城址の標が立っている。「いまは昔」の声明が響く。 戦国時代、蜘蛛巣城は敵の戌亥(いぬい)の軍勢に押されている。しかし、二番使者、三番使者によると鷲津の働きで形勢を盛り返したことが分かる。 合戦の帰途、蜘蛛手(くもで)の森で道に迷ったマクベス(鷲津:三船敏郎)とバンクオー(三木:千秋実)は糸繰りの老爺の予言を聞く。老爺が消えると辺りには屍の山。 予言の通り、北の館(たち)の主君となったマクベスの妻・浅茅(山田五十鈴)は夫に予言通りの謀略をそそのかす。折も良く敵を討つべくお忍びで城主が北の館にやって来る。 好機到来、血糊に汚れた開かずの間に寝たマクベスは夫人に後押されて、城主を暗殺する。 評定で城主に推薦されたマクベスはバンクオーの息子に跡目を譲る催しを計画するが、夫人は自分が身ごもったことを告げ、二人を途中で暗殺することをそそのかす。 宴の席に現われたのはバンクオーの亡霊だった。息子は討ちもらしたと告げる刺客をマクベスは刺殺する。 夫人の胎児は胎内で死亡し、毒がまわって夫人も危険な状態になったと聞いて、自分を嘲笑し、高笑いをするマクベス。 マクダフ(志村喬)らは戌亥方につき、攻めてくる。森の亡霊に会うマクベスは、亡霊から「森が動かぬ限り、いくさに負けることはありません」と聞く。 亡霊は「悪逆非道の限りを尽くせ」「さらに屍の山を築け」と薦める。亡霊は、どうやら戦いで死んだ悪霊の総意の化身のようだ。 戌亥は二百騎ほどの軍勢(遠景に見事に並ぶ)。マクベスは味方に対してこれまで予言が実現していることを、さらに森が動かぬ限り負けないと言われたことを明かす。 奥方は発狂している。自分の手についた見えない血を必死で洗い流そうとしている。そこへ敵方の森が動いたとの連絡が入る。城の上から見ると確かに森が動いて接近してきている。 うろたえる味方を鼓舞しようとするマクベス。ところが矢が放たれた!味方が射掛けてきたのだ。 「わかったぞ、俺の首を手土産に戌亥に付こうというのだな」。味方は「主君を討ったのはお前だ」と矢を射掛ける。遂に一本の矢が首を貫き、マクベスは倒れる。 ラストの味方が城主を殺すシーンは黒澤脚本の創意。原作の台詞をほとんど省略して、大胆に順序を変え、骨格だけを残して静と動で見事に物語が展開する。 欲にとりつかれて滅亡する人間の悲劇を突き放して描いた傑作である。 △佐藤忠男『黒沢明の世界』(1969,三一書房)214頁より。 『蜘蛛巣城』は美学的には非常に興味深いものであるが、黒沢明に思想的なメッセージを期待していた観客の多くは、 黒沢明が現代の日本の状況とは無縁な古典の世界へ逃避したものとして、失望した。しかし、いうまでもないことであるが、芸術作品においては、 その思想的な価値と,美学的価値とを、まったく別のものとして切りはなして問題にすることはできない。 『蜘蛛巣城』で観客が失望したのは、そこに思想的なメッセージがなかったからではなく、そのメッセージに共感できなかったからである。 マクベスの鷲津武時は、シェークスピアの戯曲にもとづく人物であるが、破滅的な運命のなかへ盲目的にとびこんでゆくという点では、 黒沢明がこれまで描いてきた人物たちと非常によく似ているのである。すなわち『酔ひどれ天使』のギャングの松永がそうであり、 『羅生門』の盗賊多襄丸がそうである。ただ、松永や多襄丸にとっては、その無分別な行動は、社会の最下層の人間が、無秩序な混乱した社会状態に乗じて、 自己の欲望をぞんぶんに解放することであった。観客はそこに、戦後の混乱した社会に生きる自分自身の欲望と嘆きとを発見して共感したのである。 しかし、『蜘蛛巣城』の鷲津武時にたいしては、そのような共感をよせる要素は乏しかった。鷲津武時は、欲望よりもむしろ、 自分が殺されるという恐怖のために破滅的な行動をするように見える。戯曲では、マクベスの心のなかの葛藤を告白する多くの華麗なセリフによって、 彼の心の中のできごとをスリリングな冒険的な興味をもって追体験しえるが、セリフが少なくて映像が強烈な映画『蜘蛛巣城』では、鷲津武時の内面の欲望の激しさの印象は薄れ、ただ彼に破滅的な行動をうながす物の怪や亡霊やうす気味の悪い風景などの外 面的なj恐怖感が強調されることになる。黒沢明のこれまでの作品は、登場人物の傍若無人な自我の主張の激しさによってこそ共感されたのである。 ところが『蜘蛛巣城』では、自我の主張の激しさ以上に、それを破滅させる、外側の状況の重苦しさのほうが圧倒的な力をもっている。 (3) イアン・マッケランがマクベスを演じ、ジュディ・デンチが夫人を演じ、トレヴァー・ナンが演出したテレビ用作品がある(アメリカからビデオで購入できた)。  ▼現代的な心理劇として演出されている。台詞中心であって、映像で見せ場を作る作品ではなかった。イギリスの演劇TV版の特徴かもしれない。 (4)ヴェルディの歌劇『マクベス』のレーザーディスクとビデオがある。 クロード・ダンナ監督、リッカルド・シャイー指揮、ボローニャ市立歌劇場管弦楽団・合唱団。1983年制作、133分。ロンドンD、LD仕様。 小畑恒夫の評をレコード芸術1993年1月号より抜粋。 △ダンナが視覚化したこの『マクベス』は非常にリアルだ。映画仕立てということもあるのだろうが、舞台のように抽象的な処理はほとんどない。 中世の古城、戦場と屍、魔女、現実も幻想も、すべてがカメラの前にさらされる。とりわけ魔女は衝撃的だ。腐敗し始めた死体を背景にそれが現れたとき、 「何だこれは?」と思わず目をみはった。腰布一枚の裸形。群れをなして猿のような姿勢で地を這い、目には魔性の光がある・・・。 あまりびっくりして、途中でビデオを静止画面にしてとくと眺めたほどだ。シェイクスピアの原作ではバンクォーがこう口走る。 「何だあれは。ひねこびた姿形、気違いじみたなりふり、どう見ても、この世のものとは思われぬ、が、確かに大地の上に? おい、生きているのか?・・・・うむ、女らしいな、それにしても、そのひげ、女とも言いかねるが」(福田恒存訳)。 この映画の魔女にひげはない。しかし魔女を見たバンクォーとマクベスの驚きは、ひょっとすると正確にこの映像に現れているのかもしれない。 それにしても、この異様な生き物に、本当に未来を予言する力があるのか。地下から涌き出し、荒れ果てた城内をネズミとともに彷徨する彼女たちに? 非現実的なものをリアルに映像化するのはなんとも難しいものだ。 魔女にはひっかかるが、この映画は物語を非常によく説明している。視点を自由に変えられるカメラは、暗く陰湿な城内を歩き回るレディを追い、 マクベスのこわばった表情を克明に写し出す(バリトンのレオ・ヌッチ。ヌッチの目はすごい。それは不安と恐怖に苛まれ、自分の意思を持たない男の目だ)。 バンクォ暗殺の場を処刑場に設定して不吉な感覚を強調するとか、終幕の「虐げられた祖国」の合唱の間にマクダフの子供たちの遺骸が運ばれるとか、優れたアイデアには事欠かない。 とにかく映像のインパクトの強いオペラ映画だが、ヌッチやヴァーレットの密度の濃い歌唱とともに、指揮者シャイーの陰影と起伏に富んだ素晴らしい仕事を忘れないようにしたいものだ。 (バンクォーとマクダフを歌うレイミーとルケッティーは映像では別の役者が担当している。それがどんな理由によるのか、ぼくには分からない)。 ヴェルディがこのオペラで描きたかったものは、マクベスとレディの野心や不安や恐怖であって、決して超自然現象ではないのに、 映像にするとどうしても興味がそちらにいってしまうのが辛いところだ。(小畑恒夫、レコード芸術1993年1月号) △写真の説明文:恐るべき姿をした魔女たち。大地から涌き出して獣のように地を這い、兵士の屍を食らう。目の鋭さは悪そのものかと思えるほど凄まじい。 西洋の悪魔や魔女は両性具有の驚くべき姿をしているというが、これは人間が演じられる限りの奇怪な生き物ではないだろうか。この生き物の神出鬼没ぶりも見どころのひとつ。 △国王を殺して放心状態になったレディ。意志をなくし、まるで操り人形のようにぎこちないマクベスに対してレディは冷静だ。ヴァーレットの目の色やときおり口許に浮かぶ微笑は、 レディが倫理感のまったく異なる世界にいることを納得させられる。 △第四幕第一場。悲しみに閉ざされたスコットランド人の難民キャンプ。水に浮かぶ筏や霧にかすむ民衆の映像は、 北国の寒さばかりか、祖国を失ったスコットランド人の悲しみや諦めの感情も映し出す。マクダフの妻や息子たちの遺体を見守る人々の表情は疲れている。 ▼オペラにしたときに、『マクベス』は見せ場の多い作品となる。魔女との出会いの場面、王殺しに躊躇するマクベスを鼓舞するマクベス夫人の場面、 バンクォー暗殺の場面、宴会に亡霊が現れる場面、魔女の二度目の予言の場面、マクベス夫人夢遊の場面、家族を惨殺されたマクダフの哀しみの場面、終幕などなど。 ヴェルディが33歳の時に作曲された第10作目のオペラである(1846年)。後の1865年に一部を改訂している。 『椿姫』や『リゴレット』などの傑作群は、この『マクベス』以後に生まれる。台本はフランチェスコ・マリア・ピアーヴェによってまとめられた。 大筋は生かされているが、かなり大胆に省略・脚色されている。ただ歌手の声を聞かせるオペラではなく、ヴェルディとしては劇的効果や精神性の高さを追求した最初の作品となった。 オペラでは、前述した主人公たちのそれぞれのアリアのほかに、合唱が効果を挙げる。6人ずつ3グループに分かれて登場する魔女たちの合唱、 家来たちの合唱、国民たちの合唱などは,戯曲上演では絶対に見られない場面である。フランスのダンナ監督の演出はこういった群集シーンに、きちんと見せ場を作っていた(池田記)。 (5)歌劇『マクベス』チューリッヒ歌劇場2001年7月公演、NHK共同制作。衛星2放映2002年7月27日。 演出ディヴィッド・パウントニー、舞台ステファノス・ラザリディス、衣装マリー・ジャンヌ・レッグ、振付ヴィヴィエンネ・ニューポート、 照明ユルゲン・ホフマン、指揮フランツ・ウェルザーメスト。2時間20分。 ▼魔女たちは現代的な衣装でサーカスのクラウンか、パンクな若者集団のように派手ないでたち。思い思いに切り紙細工をしたり、ハサミやフープで遊んだりしながら歌っている。 そこへ鎧を着たマクベス(トーマス・ハンプソン)とバンクォー(ロベルト・スカンヴィウッツィ)が登場し、予言を聞く。 ヴェルディの音楽の持つ劇的な効果がよく伝わる演出であった。第1幕第2場、マクベス夫人(パォレッタ・マッローク)は城の岩壁の上で歌い、 マクベスは下で歌うという、装置を立体的に使った効果や、暗殺をほのめかす場面で舞台前に降りるのが時計の針と文字盤をデザインした半透明なスクリーンであるのも面白い。 暗殺されたダンカン王は金の装束に飾られて、最後はマクベスの腕に抱かれ、マクベスは少しよろめく。歌手の目線や仕草まで演劇として演出され、 映像はそれらをよく捉えていた。 第2幕はマクベスがバンクォーの亡霊を見る場や二度目の予言を聞く場、マクダフが妻子を殺されて嘆く場、マクベス夫人の夢遊の場、 失意のマクベスの場など、見せ場が多い。コントラストの強い照明と抽象的な舞台で印象的であった。バーナムの森が動くというマクベスの周囲に、 持った枝を壁にうちつける沢山の子供(緑の目隠しをしている)を配するなど、斬新な演出であった。主役ふたり、マクベスとマクベス夫人の歌唱力が大きい。 特にマクベス夫人のパオレッタは大喝采を浴びていた。 マクダフ(ルイス・リマ)、マルコム(ミロスラフ・クリストフ)、夫人の侍女(リューバ・チュチュローワ)、医者(ペーテル・カールマン)。チューリッヒ歌劇場管弦楽団・合唱団。 マクベスは自分の運命を知ってしまった者のあがき、運命に抵抗しようとして悪行を積極的に実行してしまう男の悲劇である。 マクベス夫人の運命は魔女の予言に全く現れない。夫人の発狂は魔女の予定に入っていたのだろうか。 △喜志哲雄『劇場のシェイクスピア』(1991年、早川書房)はシェイクスピア演劇を論じて興趣つきない本だが、この中に「ルネサンス劇団のシェイクスピア」を論じた一文があった。 ルネサンス・シアター・カンパニーを率いるブラナーは、1990年に日本で『夏の夜の夢』『リア王』の両方を演出した。この劇団のシェイクスピアについて、 “必ず指摘できるのは、分りやすくて楽しいことである。作品のリズムが何よりも俳優の演技のリズムとして捉えられている。あるところでなぜ声を張上げるのか、別のところでなぜおさえた芝居をするのかといったことが、一々納得がいくのである。だから、舞台を見ていると実に快い。観客は俳優の声と身体とによる表現に自らをらを委ねていればいいのだ。めりはりがきちんとしているから、台詞がよくわかる。もちろんこれは、芝居が深みを欠いていてくさいということでもあって、差当ってブラナーの演技がその例である。しかし、くさい芝居ができるということはその俳優がかなりの技術を持っているということであり、下手であるよりはずっといいことなのだ。第一、若い時から枯れた演技をする俳優などというものは、かりにいたら相当胡散臭い存在であるに違いない”。 “ブラナーという俳優が名声をきわめる頃には私はもうこの世にいないであろうが”、“イギリスで芝居を観る楽しみが確実にひとつふえた”。 この時の舞台では、エマ・トンプソンが『リア王』の道化を演じており、肉体的存在感が排除されて道化が抽象的な表現になっていると感じられたという。 また、喜志氏はボトム役とリア王役を演じたリチャード・ブライヤーズを高く評価していた。資料によれば、ブラナー自身は悪役エドガーを演じていた(ちくま文庫『リア王』)。 ブライヤーズは映画『空騒ぎ』では知事レオナートを演じている。 (6) BBCシェイクスピア全集『マクベス』Macbeth[11] 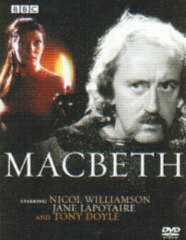 第6シーズン、製作はショーン・サットン
Shaun Sutton, producer。演出 Jack Gold、収録日June
22-28, 1982,英国初放送 October 17, 1983,
アメリカ初放送 November 5, 1983 第6シーズン、製作はショーン・サットン
Shaun Sutton, producer。演出 Jack Gold、収録日June
22-28, 1982,英国初放送 October 17, 1983,
アメリカ初放送 November 5, 1983■ブレンダ・ブルース Brenda Bruce as First Witch, アイリーン・ウェイ Eyleen Way as Second Witch, アン・ダイソンAnne Dyson as Third Witch, マーク・ディグナム Mark Dignam as Duncan,ジャイムズ・ヘイゼルディン James Hazeldine as Malcolm, ジョン・ロウ John Rowe as Lennox, ゴーン・グレインジャー Gawn Grainger as Ross, ニコル・ウィリアムソンNicol Williamson as Macbeth,イアン・ホッグ Ian Hogg as Banquo, ディヴィッド・ライオン David Lyon as Angus, ジェイン・ラポテイアJane Lapotaire as Lady Macbeth, アリステア・ヘンダーソンAlistair Henderson as Fleance, トニー・ドイルTony Doyle as Macduff, トム・ボウルズTom Bowles as Donalbain, イーモン・ボーランド Eamon Boland as Seyton, ジル・ベイカーJill Baker as Lady Macduff, クリスピン・メイアCrispin Mair as Young Macduff,マシュー・ロング Matthew Long as Menteith, ピーター・ポーテウスPeter Porteous as Caithness, ウィリアム・アブニーWilliam Abney as Old Siward, ニコラス・コッピンNicholas Coppin as Young Siward (7)ビクター「シェイクスピア全集」(9作品)のVHS第18-20巻『マクベス』 演出アーサー・アラン・シーデルマン、製作ジャック・ナカノ。BARD PRODUCTION。  ■マクベス(ジェレミー・ブレット)、夫人(パイパー・ローリー)、マクダフ(サイモン・マッコルキンデル)、マルコム(リチャード・アルフィエリ)、バンコー(バリー・プライムス)、マクダフ夫人(ミリー・パーキンス)、ダンカン(アラン・オッペンハイマー)、レノックス(フランクリン・シールズ)、ポーター(ジェイ・ロビンソン)、ロス(ブラッド・デヴィッド・ストックトン)、セイトン(ジョニー・クロフォード)、サイウォード(スタンリー・ワックスマン)、医師(アラン・マンデル)、メンティース(フィリップ・パーソンズ)、若いときのサイウォード(ロバート・アバデイーン)、ケースネス(フレデリク・クック)、血まみれの召使(ティム・プレイジャー)、アンガス(ジョン・パペイス)、フリーアンス(ダグラス・ケイバック)、ドナルベイン(マイケル・オーゲンシュタイン)、マクダフの息子(エリオット・ジャッフェ)、幽霊(ジェイムズ・ボジアン、ディヴィッド・ヒロカネ、ショーン・リーバー) ▼このバード・プロダクションの作品群は舞台劇を収録したという作りで、映画的な演出はほとんどないシリーズなのだが、この『マクベス』は三人の魔女の場面などは、スモークや照明で雰囲気作りに工夫がされていた。三人の魔女だけでなく、常に這い回るだけの地獄の従者三人も引き連れている。魔女たちはマクベスとマクダフの決闘場面にも目撃者として登場してくるし、最後のスコットランド王万歳という場面でも人々の間を不気味に動き回る。まるで新しい王にも自分たちの呪いがふりかかることを予言しているかのように。 (8)オーソン・ウェルズの映画『マクベス』 COSMIC PICTURESのシェクスピア名作映画のDVD廉価発売の一本。これまで日本ではほとんど話題になったことがない作品。映像の質は悪くない。IMDbの評価は7.3。 製作・脚本・監督がオーソン・ウェルズ。撮影ジョン・L・ラッセル、音楽ジャック・イベール。マクベスをウェルズ、マクベス夫人をジャネット・ノーラン。マクダフ役をダン・オハーリヒー、マルコム役がロディ・マクドウォール、バンクォー役がエドガー・バリア。1948年の英国・米国製作映画、ヴェニス映画祭で初公開され、日本での公開は1952年。白黒103分。  他の役者と(役)はAlan Napier (A Holy Father)、Erskine Sanford(Duncan)、John Dierkes(Ross)、Keene Curtis(Lennox)、Peggy Webber(Lady Macduff)、Lionel Braham(Siward)、Archie Heugly(Young Siward)、Jerry Farber(Fleance)、Christopher Welles(Macduff Child)、Morgan Farley(Doctor)、Peggy Webber,Lurene Tuttle and Brainerd Duffield (The Three)。   (9)NINAGAWAマクベス 蜷川幸雄演出 再演 2015年 渋谷Bunkamura 台詞はそのままに舞台を安土桃山時代に置き変えた作品。 |
『リア王』 池田博明 ピーター・ブルック監督の演出映像(1969年,主演ポール・スコフィールド)があるというが、未見。他にローレンス・オリヴィエのテレビ作品(1983年)、 イエーツ監督『ドレッサー』(1983年)のビデオがあったが、廃盤。傑作という評価の高いソ連の『リア王』(コージンツエフ監督、1970年、主演ユーリ・ヤルヴェト)は 2003年11月にDVDで発売された。内容が多くなったので別ページとして独立させた。 『リア王』参照。 ラム姉弟はシェイクスピア劇は上演するよりも読むにふさわしいものと考えて、物語化したそうだが、特に『リア王』は上演不可能とみなしていたという。 ラム姉弟の『シェイクスピア物語』は、史劇以外のほとんどを物語化している。ラムの物語は、よく出来ていて、梗概を把握するにはうってつけである。 喜志哲雄はシェイクスピア劇の演出について、こう書く。 1960年代から70年代にかけて《現代的》と呼ばれて来たピーター・ブルックなどの《クール》な演出とは、 人間に現実感を与えようとはせず、暴力や性を強調し、性格を捨てて、状況を重視する傾向である。 これは、"リアリズムの演劇観を支えている「芝居は人生だ」という考え方を否定して、「芝居は芝居であること」、 舞台上の出来事は虚構であることをわざと強調するやり方につながっている"。 しかし、1968年にロイヤル・シェイクスピア劇団の総監督に就任したトレヴァー・ナンは"人物の個人としてのあり方に焦点をすえると言っても、 それは、人物に心理や情熱による肉づけを施し、現実らしいものにして登場させることを意味するのではない。 ナンはシェイクスピア劇をアレゴリー風に演出することに意を用いている。"そして、"状況そのものを虚構とみる 《演劇の再演劇化》の方向へ"、更には、"「人生は芝居だ」とする視点が現代においては失われているのを承知のうえで、 敢えてそういう視点の可能性を探ろうとしているのではないか。つまり彼は、まがいものをほんものであるかのように扱うという逆説の上に立って、 シェイクスピアを理解しようとしている。これは要するに、シェイクスピアの作品をバロック演劇として理解することである"。(喜志哲雄「シェイクスピアと現代」) △ ロイアル・シェイクスピア劇団が発足したのは1960年、若い演出家ピーター・ホ−ルがシェイクスピア記念劇場の責任者に指名されたのである。 ホールはロンドンのオールドウィッチ劇場も獲得し、これらの劇場はロイアル・シェイクスピア劇団と改称された。 1963年にはオールド・ヴィックを仮の本拠地としてナショナル・シアターが仕事を始めた。この二つがイギリスのシェイクスピア上演の二大劇場である。 ロイアル・シェイクスピア劇団の舞台では演出家のコンセプトが前面に出て、台詞の空洞化が目立つようになっていった。ブルックの『夏の夜の夢』 (1970年)のように成功した舞台もある。"三方から壁に囲まれ、装置は無く、現実のイリュージョンを作り出すための照明も用いないというのは、 シェイクスピア時代の舞台のあり方に他ならない。言いかえれば、ブルックの演出は、近代リアリズムの演劇観を斥けるという意味では確かに前衛的だったが、 他方ではそれはおそろしく伝統的なものだったのである"。(喜志哲雄「ロイアル・シェイクスピア劇団は何をしたのか」) △水田宗子の『リア王』論=老人の人間的成長(『活字マニアのための500冊』朝日文庫,2001年より) 老いを扱った古典的な作品は、なんといってもシェイクスピアの『リア王』だろう。『リア王』はまず老害を描いた作品である。 そして、その老いという障害を通して、老人の人間的成長と成熟と救済を主題とした作品である。『リア王』では、老いは、社会や政治、 家族や絆、愛や忠誠、善や悪など、自然、社会、法、人間を考えるキーワードとして作品の中心にすえられている。テーマとしても、 中心人物像としても、物語の展開要素としても、このように老いを作品構成の中心に組み入れて書かれた作品は、ほかにあまり例を見ない。 老いたリア王は、なかなか権力を若い世代に譲ろうとしなかった。すでに一家をなしている姉娘たちは自分の国を持ち、統治するという 自立への願望を抱きながら、長い間、その成就を引き延ばされてきたのである。父のリア王から国を分けてもらうために、娘たちは頑迷で 我がままな父に逆らえず、我慢してご機嫌をとってきた。娘たちはいつまでも王座に居座り、財産分与を引き延ばす父親に、怨みと憎悪を内に含んできたのである。 リア王の老害はそれだけではない。いざ引退を決意し、国を娘たちに分与しようとするときに、娘たちが自分を愛する度合いによってそれを分配しようとする。 父親は自分への憎しみをさえ抱いている娘たちの心に気がつかず、親への情愛の大きさを彼女たちの言葉で測ろうとしている。愛は言葉で表現され、 言葉は心の真実を表現するものと思い込んでいる。姉たちの偽りの愛の言葉に腹を立てたコーディリアは、そのような言葉が愛を意味するなら、 自分は父を愛してはいないと言って、父を怒らせ、財産の分与に与れないばかりか、父から勘当されてしまう。 リアの愚かさは、性格によるものでもあるが、長い間権力の座にいた者の傲慢さから来るものでもあり、それは彼の老いを表してもいるのである。 年をとって耳が痛いことは聞きたくなくて、人にへつらわれることだけを欲する老人。財産と権力に固執する老人。すぐに感情的になり、 物ごとの客観的な判断や理解ができない老人。真実を見分ける目も洞察力も失って、見かけだけを信じ、物ごとの表層だけにしか反応できない老人。 そのような愚かさでむざんな老いのありようが、国や財産と引き換えに娘たちから甘い言葉を期待し、末娘の本物の愛をみすみす失ってしまう、老いた王の姿なのである。 『リア王』は、リアの老害ばかりでなく、姉娘たちの甘い嘘の言葉で国土も権力も財産も失って、怒りに取り乱す老醜の姿もあますところなく 描いている。しかし、リアはその老醜をさらけ出すことによって、ますます深まる孤独を経験し、しだいに自らの愚かさと間違いに気がついていき、 世の中の不条理と自然の理の認識を得ていく。『リア王』は、ドラマとしては悲劇だが、老いの愚かさと醜さが成熟をもたらす契機であること、 人生では成熟こそ達成すべきものであり、それは老いてなお可能なのだという人間認識が描かれていて、老いに深い意味を見出しているのである。ここでは、老いとは人間が成熟に達するための嵐であり、人間の生をまっとうするための通過儀礼なのである。 |
映画『オセロ』と歌劇『オテロ』 池田博明 シェイクスピア劇は、これまで例外なく、その一つ一つが、時代によってその上演が易しかったり難しかったりの連続であった(大井邦雄『シェイクスピア この豊かな影法師』)。 △世界史の鼓動と連動しているのではないかとさえ思えるときがある。六十年代、ベトナム戦争の泥沼化とキューバ事件の十年は、シェイクスピアの歴史劇が深みのある柔構造で舞台にのった時代だった。七十年代には、出口なしのジャコビアン演劇(ターナー、ウェブスター、ミドルトン)が妖しい発光体となって点滅した。八十年代には、シェイクスピア劇の隠花植物として久しくいじめの対象になってきた『タイタス・アンドロニカス』が、顕花植物として陽光を浴び、花と実と種を残した時節だった。そして九十年代は、これまでさほど神経質にならずとも上演できた二つの劇、『ヴェニスの商人』と『オセロ』が、取り扱い厳重注意の演目になってきた。特に『オセロ』の場合はそうで、オリエンタリズム(東洋蔑視)、宗教問題(非キリスト教徒は野蛮か?)、色意識(黒は汚い)、性差の問題(女は口出しするな!)、更には、中央(ヴェニス)と周辺(キプロス)、中世(オセロ)と近代(イアーゴ)、都市型(デズデモナ、キャッシオ)と田舎型(オセロ、イアーゴ)、市民(プラバンショー、ロダリーゴ)と軍人(オセロ、イアーゴ)といった対立項目を果てしなくかかえこんでいて、これが、冷戦構造崩壊後の世界の諸問題と共鳴しないわけがないのである。(大井邦雄『シェイクスピア この豊かな影法師』260頁) △ブラッドレーは、オセローが高貴であり、他人を容易に信用するといって賞賛する。イアーゴーの毒が回って初めてオセローは「人が変わった」とするのがブラッドレーだ。逆にリーヴィスは、オセローを「鈍感かつ野蛮な利己主義者」とする。開幕の場で自ら理想化してみせるが、試練にあったあとは正反対の姿をさらけ出す男、それがオセローだと考える。ブラッドレーもリ−ヴィスも劇中に二人のオセロー、本物のオセローともう一人のオセローを認めている点では同様ではないか。ただ開幕と共に現れるオセローは本物であるとするのがブラッドレーであり、本当のオセローは第三幕になって突如現れるとするのがリーヴィスと言える。はたしてどちらに軍配が上がるのであろうか。オセローの役割演技、つまり「自己理想化」を強く表面に出しているのはリーヴィスの論であるが、それももっともであり、彼は現代社会学を大いに利用できたのである。リーヴィスの方があらゆる点で有利な立場にいたし、彼が我々のオセロー理解に一役買ってくれたことは間違いない。しかし、高貴なムーア人か残忍な利己主義者かという、二つのオセローのどちらが「本物」なのか、答えはまだ出ていない。ひょっとしてどちらのオセローにも「役割演技」の要素が見出せるのではないか。(ホニッグマン『シェイクスピアの七つの悲劇』27頁)。 (1) 『オーソン・ウェルズのオセロ』(1952年、モロッコ映画)は映像に凝った作品である。 ▼ まるでエイゼンシュテイン監督の『アレクサンドル・ネフスキー』のような冒頭、オセローとデズデモーナの葬儀の場面から始まる。鎖につながれたイアーゴが引き出され、檻に入れられて吊るし上げられる。狩野良規は“映像的な処理が恣意的で、どこまでも遊びに留まっている。原作の精神を反映していない”。“切れ切れの断片を寄せ集めたような、この目くるめくような映画は、不思議なほど各場面の情景も人物も記憶に残っていない。映像ドラマは人間のドラマを破壊し、さらにはそのスピード感が映像ドラマ自体をも散漫なものにしてしまっている”失敗作と評価している。  ●監督・脚色・主演オーソン・ウェルズ、撮影アンチーゼ・ブリッツイ、G.R.アルド、ジョージ・ファント。衣装マリア・ド・マッティーズ、美術アレクサンドル・トローネル、音楽フランチェスコ・ラヴァニーノとアルベルト・バルベリス。イアーゴ役マイケル・マクラィアマー、デズデモーナ役シュザンヌ・クローティエ、キャッシオ役マイケル・ローレンス、ロデリーゴ役ロバート・クート、エミリア役フェイ・コンプトン、ブラヴァンショー役ヒルトン・エドワーズ。 (2)オリヴァー・パーカー脚色・監督『オセロ』(1996年)  ▼ケネス・ブラナーがイアーゴ役。イアーゴのする対話(話し相手はロデリーゴやカッシオ、オセロ)は、バスト・ショットからアップ中心の画面作りで、密告や内密の話にふさわしく、かつ観客に話しかけるのもイアーゴだけと、イアーゴ中心に演出されていたが、オセローも気品ある姿勢で一貫していた。オセローがイアーゴに「妻の不実の証拠を」と迫る場面はウェルズ作品と同様、海岸である。 ▼ケネス・ブラナーがイアーゴ役。イアーゴのする対話(話し相手はロデリーゴやカッシオ、オセロ)は、バスト・ショットからアップ中心の画面作りで、密告や内密の話にふさわしく、かつ観客に話しかけるのもイアーゴだけと、イアーゴ中心に演出されていたが、オセローも気品ある姿勢で一貫していた。オセローがイアーゴに「妻の不実の証拠を」と迫る場面はウェルズ作品と同様、海岸である。●撮影デヴィッド・ジョンソン。オセロ役ローレンス・フィッシュバーン、デズデモーナ役イレーネ・ジャコブ、その父プラバンシオ役ピエール・ヴァネック、副官カッシオ役ナサニエル・パーカー、イアーゴの妻エミリア役アンナ・パトリック、ロデリーゴ役マイケル・マロニー、キプロス島の仮総督モンターノ役ニコラス・ファレル、カッシオの情婦ビアンカ役インドラ・オヴ。 (3)歌劇『オテロ』。ショルティ指揮コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団/合唱団。パイオニアLD仕様。 國土潤一評、レコード芸術1993年9月号より抜粋。 ●オテロ役プラシド・ドミンゴ、デズデモーナ役キリ・テ・カナワ、イアーゴ役セルゲイ・レイフェルクス、カッシオ役ロビン・ラゲージ、ロデリーゴ役ラモン・レメディオス、ロドヴィーコ役マーク・ビーズリー、モンターノ役ロデリック・アール、エミーリア役クレア・ポーウェル、伝令役クリストファー・ラックナー。演出エリシャ・モシンスキー、映像監督ブライアン・ラージ。(1992年10月27日収録) △ ショルティの八十歳を祝しての『オテロ』でも、彼の指揮は、ヴェルディの円熟した音楽の深みを凄まじいまでのエネルギーで描き上げている。(中略)何よりも素晴らしいのは、オテロ役のドミンゴである。ゲネラルプローベの時には風邪気味であったと伝えられたドミンゴだが、ここでの演唱は、そんな気配など微塵も感じさせぬ充実しきった声の密度と、その声を駆使したドラマ性、美しいカンタービレを聞かせてくれる。初演時のタマーニョ以来、ライモン・ヴィナイやマリオ・デル・モナコらによるオテロは、あまりにも剛直なスタイルで歌われすぎてはいなかったろうか。ドミンゴはヴェルディの作った音楽が、いかに美しいカンタービレに溢れていたのかを、われわれに再認識させてくれる。第一幕終りのデズデモナとの愛の二重唱を、ドミンゴ以上の気品と甘美さをもって感動的に歌った歌手を、私は知らない。その音楽的充実美に加え、ドミンゴのオテロには、かの名優のローレンス・オリビエがそうであったように、見事な演劇的必然性がある。 オテロは、なぜデズデモナを殺したのだろうか。理由(殺人衝動の心理的背景)は、二つ考えられる。ヴェネツイアの将軍でもあり、ムーア人でもあるオテロの自尊心と、コンプレックス(これらはいずれも自己愛の変形したものとも考えられる)が主たる動機である場合と、デズデモナに対するひたすらな愛を動機とする場合である。前者は、デル・モナコを代表とするスタイルであり、後者はドミンゴのそれではなかろうか。 シェイクスピアは、デズデモナを殺したオテロに、「愛することを知らずして愛しすぎた男」と語らせている。デズデモナへの狂おしいまでの愛が、オテロをデズデモナ殺しという凶行に走らせたのだとすれば、ドミンゴの演ずるオテロは、まさにシェイクスピアが望んだオテロではなかったろうか。デル・モナコもタマーニョも、ヴィナイも、つまり今世紀を代表するどんなオテロ歌いも、こんなオテロ像を作ってはくれなかった。デル・モナコのオテロを誹謗する気はさらさらないが、ドミンゴのオテロ像を知ってしまった後には、あまりにも十九世紀的なナルシズムが生んだ、テノール歌手の独善のように見えてしまう。 デル・モナコの場合には、このドラマが、まるでデズデモナの悲劇のように思われはしないだろうか。理不尽な殺され方をするデズデモナ以上に、彼女を愛しすぎたゆえに、しかも愛し方を誤ったゆえに殺し、みじめ極まりない男に、英雄から転落していったオテロの悲劇であることを、ドミンゴは改めてわれわれに認識させてくれる。自殺をするオテロは、もはや英雄であってはならないのだ。とすれば、デル・モナコは、最後の瞬間まで、あまりにヒロイックであり続けようとし過ぎているとは言えまいか。第四幕のドミンゴを見てみよう。デズデモナの寝室に入ってきたオテロの、愛惜と悲嘆に満ちた顔は、デズデモナの目覚めと同時に、プライドを堪えた怒りの表情へと変化する。そして、デズデモナを殺すオテロの苦しみの表情、真相を知った後のオテロの表情の変化・・・・。何という深い心理的洞察と、内部共感に裏打ちされた演技であろうか。これはもはや、演技という領域を(少なくともオペラの演技という領域を)超越している。この、ドミンゴの入神の演唱によって、初めてヴェルディの音楽とシェイクスピアの世界は、完璧にひとつのものになったのである。 ドミンゴの相手役であるキリ・テ・カナワのデズデモナ、セルゲイ・レイフェルクスのイアーゴも素晴らしい。キリの凝縮性の強い、恰幅の良い演唱は予想とおりだが、彼女以上に印象深いのは、レイフェルクスである。キーロフ・オペラの名バリトンであるレイフェルクスは、本来はよりリリックな役柄が適しているが、このイアーゴも、何よりその狡猾さが不必要に肥大化しない役作りが好ましい。ミルンズやディアスのように、まるで安手の映画の悪役のようなイアーゴは、何かしら興ざめさせられるが、彼のインテリジェンスに満ちた役作りは、オテロがイアーゴという人物を信じ込んでしまうことの必然性を、充分に納得させてくれるものである。 これらの万全のキャストを配した舞台を演出するモシンスキーも、オーソドックスな中に、美しく細かな配慮を行う舞台を作り上げている。ショルティのダイナミックかつ繊細極まりない音楽作りの姿勢と、完璧に合致したモシンスキーの舞台作りを、映像監督のブライアン・ラージの大胆なカメラ・ワークは、見事に映像へと転換していく。各歌手のアップのカットが多いのも、この映像の特色だが、これはラージの演出であろうし、ドミンゴやレイフェルクスらの演技が、それに耐えるだけの密度をもっているからにほかあるまい。 劇場での体験とはまた別の楽しみを、このレーザー・ディスクは堪能させてくれる。コヴェント・ガーデンの映像権を掌握した。コヴェント・ガーデン・パイオニア・FSP・リミテッドの、設立第一作として国内に紹介されるこの『オテロ』は、映像で見るオペラの新たな楽しみを、われわれに教えてくれる。 (4)演出をゼフィレッリ、オテロ役をプラシド・ドミンゴが演じたヴェルディの歌劇の映像版がある。ビデオ。 映画としてダイナミックに面白く見ることができる。  DVDではプラシド・ドミンゴがオテロを歌った2001年12月ミラノ・スカラ座公演を収録した版も出ている。イヤーゴをレオ・ヌッチ,デズデモーナをバーバラ・フリットリ。演出はグレアム・ヴィック、指揮リッカルド・ムーティ。石原俊が『クラシック・ジャ−ナル』004に書いた評を引用する。 “抽象と具象の中間点をつくヴィックの解釈が素晴らしい。抽象化された舞台には余計なものが何ひとつなく、それでいて装置・衣裳は重層かつ象徴的で、ストーリーと密接な関係をもつ。人物の動かし方はシンプルで無駄がないのだが、細部をよく見ると非常なこだわりが感じられる。 (中略) ムーティが満を持して振っただけのことはあるな、というのが正直な感想である。(中略) 現在望みうる最高の「オテロ」である。” ●映画ではローレンス・オリヴィエ作品(1966年)があるが廃盤のため未見。 BBC放映、トレヴァ・ナン演出、イアーゴをイアン・マッケランが演じた『オセロ』のビデオ版があるそうだが、未見。オセロ役ウイラード・ホワイト、デズデモナ役イモジェン・スタッブス、エミリア役ズー・ワナメーカー。大井邦雄によればイアーゴの悪が、天地をひっくり返すような大激震ではなくて、ごくありふれた日常的なものとして私たちの日々の生活にくいこんでいく性質のものである、という見事な舞台になっているという。 (5)アメリカ映画『O[オー]』(2001年)  ▼高校を舞台に『オセロ』を下敷きにしたティム・ブレイク・ネルソン監督の映画である。イアーゴ役の主人公を演ずるのは『パール・ハーバー』『シャンプー台のむこうに』『フォルテ』にも主演しているジョシュ・ハートネット。撮影監督はラッセル・リー・ファイン。 ▼高校を舞台に『オセロ』を下敷きにしたティム・ブレイク・ネルソン監督の映画である。イアーゴ役の主人公を演ずるのは『パール・ハーバー』『シャンプー台のむこうに』『フォルテ』にも主演しているジョシュ・ハートネット。撮影監督はラッセル・リー・ファイン。冒頭、主人公ヒューゴー(ジョシュ・ハートネット)のナレーションが入る。「僕は空を飛びたかった。鷹のように」。しかし、背景に映っているのは白い鳩である。バスケットの試合の場面で、接戦を制したチーム・ホークス(鷹)のMVPは、唯一の黒人選手オーディーン(マーカイ・ファイファー)であった。鬼コーチ(マーティン・シーン)の息子ヒューゴーもオーディーンを助けていい動きをしているが、コーチは自分の息子には(多分意図してだろうが)辛く当る。学校での表彰式でMVPの盾を受け取ったオーディーンは、自分のプレーをサポートしてくれた殊勲選手として、ヒューゴーではなく、マイケル(アンドリュー・キーガン)を挙げる。また、鬼コーチはオー(オーディーンの愛称)を「わが息子 My own son」と呼んで絶賛する。ヒューゴは嫉妬する。 オーは校長の娘デジー(デズデモーナ役である。ジュリア・スタイルズ)と交際し始めている。 オー、マイク、ヒューゴーはバスケットのチーム・ホークスのメンバーである。デジーはエミリー(レイン・フェニックス)と同室である。ヒューゴーは鬼コーチの実の息子という設定が活かされている。  ヒューゴはオーに覚醒剤も与えて、正気を失わせていく。ヒューゴー自身は筋肉増強のために、売人からステロイド剤を注射してもらっていた。オーがデジーにあげたスカーフを、エミリーはヒューゴーに渡す。エミリーはヒューゴーに好かれようとして、その利用法を知らずに持参したのだ。そのスカーフはヒューゴーの手からマイクへ、マイクの手から愛人の手に渡って、オーの疑惑のもととなる。 ヒューゴはオーに覚醒剤も与えて、正気を失わせていく。ヒューゴー自身は筋肉増強のために、売人からステロイド剤を注射してもらっていた。オーがデジーにあげたスカーフを、エミリーはヒューゴーに渡す。エミリーはヒューゴーに好かれようとして、その利用法を知らずに持参したのだ。そのスカーフはヒューゴーの手からマイクへ、マイクの手から愛人の手に渡って、オーの疑惑のもととなる。 ヒューゴーの計略は、オーがデジーを射殺し、その罪をマイクにきせた後で、ロジャーがマイクを射殺して自殺に偽装するというもの。 ところが、ロジャーはマイクと取っ組み合いになり、怒りに任せてマイクの足を撃ってしまう。自殺に偽装できなくなったヒューゴーはロジャーを撃ち殺し、デジーの部屋に駈け付けると、そこでは既にオーがデジーを絞殺してしまっていた。デジーが試合を観戦に来ていないのを不審に思ったエミリーがちょうど戻って来て、スカーフの真相をオーに話す。ヒューゴーはエミリーを撃つ。絶望したオーは警官に取り巻かれたなかで、「白人に罠にはめられた自分の人生」を呪い、自分を撃つ。 オーは、白人の高校にたった一人、バスケットの才能を認められて入学してきた過去に犯罪歴のある黒人青年という設定で、陰では「ニガー(黒人を意味する差別語)」と言われて蔑まれているという状況がある。彼は讒言に、簡単にはめられてしまいやすいのだ。このような状況設定は説得力のあるものだった。 『オセロ』を意識しなくとも、青春映画として見ることができる作品であった。ジョシュ・ハートネットは父親に認められない孤独な陰謀家という屈折した青年を好演している。セリフも現代的であった(脚本はブラッド・カーヤ)。 (6) BBCのシェイクスピア全集の『オセロ』Othello 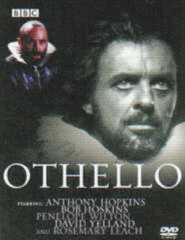 演出ジョナサン・ミラー Jonathan Miller,収録日March
9-17, 1981,英国初放送 October 4, 1981、アメリカ初放送
October 12, 1981 演出ジョナサン・ミラー Jonathan Miller,収録日March
9-17, 1981,英国初放送 October 4, 1981、アメリカ初放送
October 12, 1981 アンソニー・ペドリー Anthony Pedley as Roderigo,ボブ・ホスキンスBob Hoskins as Iago, ジョフリー・チャッターGeoffrey Chater as Brabantio,アレクサンダー・ディヴィアン Alexander Davion as Gratiano アンソニー・ホプキンス as Othello, ディヴィッド・イーランドDavid Yelland as Lodovico, ジョン・バロンJohn Barron as Duke of Venice, ペネロープ・ウィルトンPenelope Wilton as Desdemona, ローズマリー・リーチ Rosemary Leach as Emilia,トニー・スティードマン Tony Steedman as Montano、ウエンディ・モーガン Wendy Morgan as Bianca 《舞台裏で》英国俳優労働組合は労働許可の発行を拒否した。制作期間中にジョナサン・ミラーはエル・グレコの視覚デザインを基本にした。 (7)ビクター「シェイクスピア全集」(9作品)のVHS第12-14巻『オセロ』 演出フランクリン・メルトン、制作ジャック・ナカノ  オセロー(ウィリアム・マーシャル)、イアーゴー(ロン・ムーディ)、デズデモーナ(ジェニー・アガター)、キャッシオ(デヴェレン・ブックワルター)、ブラバンショー(ピーター・マックリーン)、ヴェニス公爵(ジェイ・ロビンソン)、エミリア(レスリー・パクストン)、ロデリーゴー(ジョエル・アッシャー)、ビアンカ(ユージナ・ライト)、コーテシャン(アンナ・ドレスドン)、ルドヴィーコー(フィル・パーソンズ)、モンターノ(マイク・ヘイワード)、グラシアーノ(アーノルド・マークウッセン)、使者(ダン・シュタイニンガー)、兵士(ウィル・ナイ)、議員(ラニー・ブロィルズ、ジョン・ブリス) オセロー(ウィリアム・マーシャル)、イアーゴー(ロン・ムーディ)、デズデモーナ(ジェニー・アガター)、キャッシオ(デヴェレン・ブックワルター)、ブラバンショー(ピーター・マックリーン)、ヴェニス公爵(ジェイ・ロビンソン)、エミリア(レスリー・パクストン)、ロデリーゴー(ジョエル・アッシャー)、ビアンカ(ユージナ・ライト)、コーテシャン(アンナ・ドレスドン)、ルドヴィーコー(フィル・パーソンズ)、モンターノ(マイク・ヘイワード)、グラシアーノ(アーノルド・マークウッセン)、使者(ダン・シュタイニンガー)、兵士(ウィル・ナイ)、議員(ラニー・ブロィルズ、ジョン・ブリス) |
| 『トロイラスとクレシダ』 松岡和子訳 彩の国さいたま劇場 蜷川幸雄演出 オール・メール・シリーズ(女性役を男性が演じる)。2012年9月1日公演収録。舞台いっぱいのヒマワリ。 【略筋】 トロイ戦争の最中、トロイの王子トロイラス(山本裕典)は、トロイの美女クレシダ(月岡悠貴)に惚れている。クレシダの伯父パンダロス(小野武彦)はトロイラスを高く評価しているが、クレシダはヘクトルやアキレウスの方を高く評価しているように話す。彼女はわざとトロイラスに対しては、つれない素振りをしているのだ。トロイの城はなかなか落ちない。ギリシアの総大将アガメムノンに、ユリシーズは、その原因はトロイの強さにあるのではない。ギリシア軍の弱さにあると批判する。アキレウスの働きは不十分なものだと陰口を告げる。トロイ軍は白の衣装、ギリシア軍は青の衣装で分けられている。 膠着状態のなか、トロイの使者がトロイの王子ヘクトルと勇者の決闘を申し込む。ヘクトルとの決闘の相手はくじ引きで決める予定だが、くじに仕掛けをしておき、血の気の多いアイアス(通常はエイジャックスとの役名だが)に引かせるのがユリシーズのたくらみ。 ギリシアからパリスが奪ったスパルタの王女ヘレネを返せば休戦するという提案がされ、トロイの王子たち、パリス、ヘクトル、トロイラスが議論する。狂女カサンドラは災いのもと、ヘレネを返せと叫ぶ。結局、男たちの名誉のためヘレネ返還は拒否される。一方、ギリシア軍はアイアスをおだてて、戦おうとしないアキレウスに代わらせようとする。パリスとヘレネは愛の営みに夢中だ。 トロイラスとクレシダは伯父の手引きで会う。ふたりは真実の愛を誓う。 ギリシア陣営、クレシダの父カルカスは娘をトロイの将軍アンティーナとの交換を提案して、アガメムノンに受け入れられる。アキレウスとパトロクラスはユリシーズに戦意をたきつけられる。クレシダとトロイラスの二人のもとへ交換の指令が告げられる。「心変わりしない限り」会いに行くというトロイラスに対して、クレシダは疑いをもたれることを怒る。使者ディオメディスはクレシダの美しさにふさわしい扱いをすると云う。 ヘクトルとアイアスの決闘が行われる。二人は従弟同志だった。剣をおさめ、ヘクトルはギリシア陣を訪れる。 御守り役のディオメディスはクレシダを誘惑しようとしている。トロイラスとユリシーズは盗み聞きする。クレシダはトロイラスがくれた袖を示す。袖をひったくったディオメデスは誰にもらったかを問い詰めるが、クレシダは答を拒否する。トロイラスは「あれはクレシダであって、クレシダではない」と叫ぶ。月岡悠貴演ずるクレシダは女性の弱みを感じさせず、強い意志を持って行動する女性と見える。オール・メールの効果だろう。不実なクレシダとは思えないのであった。 トロイの陣営。カサンドラはヘクトルの死を予言する。ヘクトルとトライロスは出陣する。 戦場。獅子奮迅の働きをするトロイラスとヘクトル。パトロクラスをヘクトルに殺されたアキレウスはヘクトルのすきを狙う。戦い終えたヘクトルが武装を解いたところをアキレウスたちが襲う。ギリシア軍は歓呼の声を揚げる。トロイラスはトロイ軍を復讐で立て直そうと宣言する。 【コメント】 『ハムレット』とほぼ同時期に書かれた作品。喜劇とみなされたり、悲劇とみなされたりの問題劇である。戦争に対する批判的な台詞が多い。さいたま劇場での上演では、始めの方で、若い役者の長い台詞が何を言っているのか、聞き取れない箇所があった。 【坪内逍遥の解説】 書かれた年代及び此作の特質 <旧字を一部新字にしている> 書きおろしの年月は確定しがたい。前に言ったデッカーとチェッテルの合作は一五九九年だと傳へられてをり、又、一六〇二ー三年の二月には、時の内大臣の抱への劇団(即ち沙翁の一座)が「トロイラスとクレシダ」と外題された劇を演じたといふ記録があるところから、一部の論者は、恐らく、右の劇は、沙翁の此作ではなかったらうと推定しようとしてゐる。併し昨今の學説は、寧ろ沙翁自身の作に二種あって、第一作は一六〇二年ごろに書かれて一六〇三年に上演され、更に一六〇六年以後同九年以前に改修されて遂に現存の物となったのだといふ見解に落ち着かうとしてゐる。といふのは、此作の或部分は「ハムレット」以後の筆致かとも思はれるが、辛辣な皮肉味が全曲に通徹して、「幻滅の悲喜劇」とも見るべき一種の特質を具えてゐる点から言ふと、むしろ頗る「アセンズのタイモン」に近似してゐるからである。 とはいへ、此作は、あらゆる関係上から見て、問題の団塊ともいふべき作だから、容易に何れとも断言は出来ない。先づ、今もいった通り、それが史劇だか、喜劇だか、悲劇だかさへも解らないで、沙翁は、一体、何の為に、こんな変な作を書いたのかといふ疑問は、十八世紀このかた、イギリスはもとより、他国の沙翁学者までも悩ました。トロイラスとクレシダといへば、ルネサンス以来は,取りわけ、人口に膾炙した不幸な恋愛の古伝説であり、さうしてそれをイギリスの名作家のチョーサーが、あの通り、美妙な筆で哀れな面白い詩編に書き綴って、既に広く世に行はれてゐたのであるのに、何の必要があって、恰もそれを嘲笑するかの如くに、劇中人物の白に擬して、さんざんに皮肉な批評を浴びせ翔けつつ、特に引歪めたやうにして沙翁が書いたか?『イリヤッド゙』即ちトロイ落城物語といへば、わが『平家物語』の屋島及び壇の浦の悲劇的戦争などにも比すべきもので、其中に現はれる英雄や美人や勇士や智者は、いぢれも、中古時代迄は、欧州列国民の讃美の的とも理想ともなってゐたのであるのに、此作では、それらが皆、殆ど萬遍なく漫画化されてゐるといっていい。通例なら、哀れな恋愛物語であり、悲壮な英雄譚であるべきものが、寧ろ恋愛や政治や戦争を風刺し談笑する為に取扱われた一種の「謎の劇」の如くなってゐる。常に作中の人物に深厚な同情を寄せるのが恒例のやうに見えてゐた沙翁が、不思議にも、本篇では、人物の全部を嘲笑してゐるとも見える。或評者は此作を當時の劇場関係者間の内幕を---即ち所謂劇場間の戦争を--劇化したものと解して、作中の野猪武者エーヂャックスはベン・ジョンソン、毒舌漢サーサイチーズはデッカーだの、マーストンだのと解した結果、トロイの英雄ヘクターは沙翁が自分自身に擬して書いたものだと憶測した。又、或評者(WG)は、---グリース方の智将ユーリッシーズに屡々賢明らしい名白が言はせてあるのをっ理由として---これこそは兎角に韜晦して其正体を見せたことのない此作者の一生の本音である、ユーリッシーズは即ちシェークスピヤだとまで断言した。それにも拘らず、此人物とても、よく調べて見ると、さほど讃めた性格ではない。況んや其他に至っては、作者がサーサイチーズをして罵倒せしめてゐる通り、概して愚物か好色漢かである。大立物のアキリーズからが高慢病に罹った馬鹿者である上に、色好みでもあり。卑怯者でもある。一応は主人公らしくも見えるトロイラスも、要するに、物知らず、世間知らずの只の恋愛病患者であり、美人ヘレンも、クレシダも、明らかに娼婦型の蓮葉女で、貴女らしい淑かさは少しもない。トロイラスとクレシダとの初対面の場及び其交会の後朝の場謎を読むと、自然に「ロミオとヂュリエット」の同一場面が想起されるし、また其恋の媒介をする叔父パンダラスの白にはヂューリエットの乳母の口吻が歴々として辿られるが、而も作者の其人物に対する態度に至っては全く異ふ。「ロミオとヂュリエット」では、作者が人物と同化してゐるが、この作では初めから超然と立ち離れて、冷やかに、むしろ残酷な程に恋愛の幻滅を暗示してゐる。 すなはち、作者は恋にも功名にも忠義にも何等の同感を有せないで、苦笑し嘲笑して、見おろして書いてゐるとしか思はれない。これはまたどうした譯だらう? そればかりでない。生の観察の深刻さや修辞の洗練に於ては、之を最晩年の筆としても、強ち不當でないとさへ思はれる割合には、劇としての脚色、結構は甚だ不手際である。此作者の名を冠ってゐる劇としては、彼のフレッチャーとの合作だとされてゐる「ヘンリー八世」を例外とすると、これほど不取締りな、だらしの無い作は外にはない。筋が幾条にもなってゐるのは、例の手法であるのだが、それが時としてはまるで離ればなれになり、さうしてどれが本筋だかも分からない。感興の焦点が常に移動して定まらないのである。一等同情を呼ぶべき人物のヘクターが五幕目で戦死するのは悲劇らしくもあるが、肝腎のクレシダ対トロイラスの関係は、結局が著かないままで大詰めとなってゐる。どう考へて見ても、作者の主意が解らない。 それこれ、此作は何か特に為にする所があって、---即ち劇としての目的以外の目的があって---わざと破格的に書かれたものではないかといふ種々の仮定説や臆断論が諸評家によって陸続と提出された。例へば、是れは、シェークスピヤが、例のルネサンス以来、ギリシャ文明の崇拝が余りに甚だしきに達したので、それを風刺するために書いたのであらう。すなはち、最高文化の照準から見ると、所謂ヘレニズムにも種々の欠陥がある、しかるを現在の如く頭から盲崇してゐた時分には将来の文化に不測の禍因を遺すことになるぞよ、と大詩人が其予言者的眼光で、早くも後の十八世紀の偽古典文明を予察して風刺的誡告を下したのだ、云々。これはウルリーチーの評の大意である。或ひは又、是れは、彼れの競争者であった作者チャプマン譯の『イリヤッド』が恰も公にされた際であったから、暗に其鼻先を挫かうといふ下心あってのいたづらだらうとか、或ひは又、前に言った劇場関係者の内輪喧嘩を匂はせたパロデーに外ならぬとか、議論紛々として、今尚ほ一決したとはいへない有様である。併し、大勇士のアキリーズを卑怯者に仕立てたり、奴隷のサーサイチーズに「アセンズのタイモン」に出てくるアベマンタスよろしくの毒口を叩かせたりするのは、若し此劇を風刺本位の作だとすると、特に作者が其創意を凝らした点だとも解すべきだが、其実、アキリーズを卑怯者とした作には先例があり、又、サーサイチーズの性格も、大体はチャプマンの『イリヤッド』から借りたものであると推断されるから、以上の風刺本位説は軽々しく信ぜられない。 要するに、本劇は沙翁作中の最も特異な一篇であって、娯楽的に走読するには余りに深刻過ぎ、又、余りに皮肉過ぎた人生観察や性格批判が仮託されてある。で、言外の余意を余程よく含味せないと、或ひは全く理解されず、又は甚しく浅解され、又は全く誤解されさうな箇所が幾らもある。例によって、所々に註脚を加へ、トガキをやや煩細ほどに書き添へておいたのは、主として之が為である。(昭和元年 昭和九年再校 新修シェークスピヤ全集 第23巻 中央公論社) 【人生のルポルタージュ】 『トロイラスとクレシダ』(次回配本) 花園兼定 <旧字を一部新字にしている> (昭和九年 1934年9月 新修シェークスピヤ全集 第12回配本 月報p.22-27 中央公論社) 『トロイラスとクレシダ』は沙翁の作物の中(うち)でも、一つの特別のものである。普通の「沙翁物語」の中にも、この作品は見當らない。テーヌの英文学史の中でも、可成り精細な彼の沙翁論の中にさへ、此の作品は留守をしてゐる。例外の一つはラフカヂオ・ハーンの英文学史にこの作品について幾多の行数が費やされてゐることだ。ハーンの英文学史は非常に個性のある英文学史である所以でもある。大体において、この作は坪内博士が『沙翁研究の栞』のうちに云はれてゐるやうに、謎の作であり「最後の研究に遺す」べきものといふべきほど、二三年の沙翁研究の演習には出て来ない作品である。それだけ、また一層深い興味がもてるわけである。有名なものには、屡々名前だけが残ってゐる。われわれは屡々退屈をさへ感ずる。歌舞伎の舞台を見て、われわれは、常にさういった不満な感情をもたなければならない。歌舞伎が生きてゐない大きな理由だ。 この『トロイラスとクレシダ』の物語は、物語としてはあまりにも有名である。(それは却て残念なことだ)英国文学の祖先といはれるチョーサーの作品の中にも、この物語を取り扱ったチョーサー最長の詩がある。チョーサーがイタリー文学の影響を受けた時代の作品である。チョーサーの詩はイタリーのボッカチオのフィロストラトの上に基礎づけられてゐる。ハーンの英文学史によれば、十五世紀から十六世紀にまたがった英国の詩人ヘンリソンこそは、最も注目すべき詩人であったのである。伝説に従えば、彼は一五〇六年頃に死んだ学校の教師である。彼の作品としては、“The Teastament of Cressida”“The Ballad of Roben and Makyne”“Fables”の三つが挙げられるが、この最初のものが、沙翁の『トロイラスとクレシダ』と同じ物語を取扱ったものである。「若し沙翁のドラマを読んだならば、クレシードは移り気な女のタイプ--つまり他の人を喜ばせやうとしてゐる気の弱い美しい女、一人の男に忠実であるだけに強い性格をもたない女であったことを思ひ起こす。彼女はトロイラスを実際に愛してゐる。彼に信実であらんことを欲する。然し戦(いくさ)のならはしで仕方なく別れた後に、ギリシヤの大将ダイオミーデイーヅに身をまかす。ヘンリソンは此の物語の結末をかう書いてゐる。---ダイオミーディーツは、クレシードにあきて了ふ。そして彼女をすてる。クレシードは怒つて神々をののしる。神々は彼女を罰するために彼女にライ病を与へる。中世紀のライ病患者の如く、彼女は鈴を振って物乞いに出る。途上トロイラスに行き遭ふ。トロイラスには彼女が分からない。何故ならば、彼女の顔は病気で破壊されてゐるからだ。やがて、リングによって彼女であることが分つた時、彼の悲しみはいたましい。悲しみの極み、彼は死ぬ。」(ハーン---英文学史)---これが、ヘンリソンの「トロイラスとクレシダ」物語である。四五十年ほど前までは、トロイ物語は単純な伝説としか信ぜられなかった。四十年ばかり前(一八九三年)考古学的発掘(W.Dorpfeld)によって、トロイの位置と歴史が確定されたのである。 『トロイラスとクレシダ』の場面については此の作の「開場詞」がこれを語ってゐる。 ---トロイが舞台面であります。グリースの島々から、身分の高い、気位ゐの高い君主たちが怒り猛つて、残酷なる兵争の戦員や銃器を満載して軍艦をアセンスの港へ集め、小王冠を戴く六十有九人が、そこからフリヂヤへ向けて進発し、トロイの劫掠を誓ひました。其トロイの城内には、例の誘拐された、メネレーヤス王の妃ヘレンが姦夫のパリスと眠つてゐるのです。さうしてそれが此戦争の原因なのです。」 そして、沙翁の此の作は、「すべて戦争の発端を飛ばしまして真中から始め、演劇に仕組みまするに都合のよい部分だけを御覧に入れまする事をお知らせに罷り出ましたに過ぎません」(『トロイラスとクレシダ』開場詞)---すなはち、トロイ戦争の中途、七年目に初まつてゐる。ホーマーの「イリアッド」においては、トロイ攻囲十年間の戦争の最後の事件アキリーズとアガメムノンとの間の悶着から物語が始まり、ヴァジル晩年の作「イーニエッド」の物語では、トロイの滅亡と、トロイの避難民が、イーニアスに導かれて航海することが描かれてゐる。それと比べて、此の沙翁の作はイリアッドにあらはれてトロイ物語のCyclic史詩の一つではあるが、直接トロイの運命には関係しない。其処には全体の作を通じて、一つの陣中における人生の批評が展開されてゐるのを見るのである。其処には花々しい史劇的の部分はない。併しそれだけ、われわれがクオヴァディスを見たり、シーザーを見たりして退屈するやうなところはなく、沙翁の鋭い人生批評が、ひしひしと、現在の世界を批評してゐるやうに思はれて、さうした沙翁の言葉一つ一つに刃でもつけて、これを思ふあたりに投げ込んでやりたくさへ思ふのである。たとへば、 エージャックス「威張る奴の気が知れない。人間が増長するてのは、どういうわけだか? 我輩には高慢てことが解らん・・・我輩は高慢なやつは大嫌いだ、蟾蜍の群卵ほどに嫌ひだ。」 沙翁は「威張る奴」といふものが、心から嫌ひだつた。此の作品には沙翁のこれに関する訓言が随所にある。そしてまた「コセコセしたハヤシ肉のやうな男」が嫌ひだった。 何故「七年目の攻囲の後に、トロイがなお陥落しないか」? トロイ「強いからではなく」、ギリシア軍にありては、「全軍を統率すべき主権が等閑に附せられてあるからで正邪善悪が其名を失ひ、其無終の争闘を取り捌くべき正義其物が亡びてしまひ、一切が力に帰入されたからである。 この作の物語はあまりにも有名である。有名な物語に基礎を置いたことは今日のわれわれには退屈なことである。併し此の作は「筋」を追つて読むべき作品ではない。むしろ「言葉」を読む作品である。(これはほんとうに有難いことだ)「言葉」は社会的のものである。此の作品は、沙翁の時代を一層われわれに親しましめてくれる。「筋」を好むものならば、川上音次郎所演のオセロの筋書でも読むがいい。一六〇二年から一六〇九年頃へかけてのロンドンの人生と言葉とを見たい人には、この「トロイラスとクレシダ」は一つの発見だ。ヘクターが死んで了はうがどうしやうが、そんなことはどうでもいい。ヘクターの死骸の足を二輪車の後ろに結びつけてトロイの町をあちこちと曳きずつたといふことを知っても、われわれは可愛さうだとも何とも思はない。併し全篇を通じての沙翁の賢明な言葉には頭が下がる。ドラマの形をした語録であり、人生記録であり、一大史劇が実は恋愛によりて動く英雄生活を裏から見たreportageである。「筋」ならば、幕明きと、終幕を見ればいいであらう。此の作の興味は中途にある。「シキ臼の石を落す」といふ當時の言葉一つにさへ一六〇〇年代に呼吸したイギリスがほんとうの影を落してゐる。一夜思ひつきで、町の図書館で「娯楽的に走り読みすべき」ものではなく、ひとり静かに日を重ね。出来得べくんば、原作と共に読むべきものである。さうすれば、空虚な「筋」の中にでなく、一つ一つの言葉の中に、沙翁は今も生きていることを知るのである。普通の「沙翁物語」には入ってゐないかうした作品に向き合ふと、昔ながらに名は知れてゐて人の行かない山間海辺を逍遥する気持ちがする。一体トロイとは何処か? トロイの町の位置についてはいろいろの学説があつたが、小アジアの西北部の海岸であつたものと今日では定められてゐる。 今ここに坪内先生名譯の一として、地方方言までを含めた豊富な語彙をもつて、「どれが本筋か分からない」此の特殊な作品が、完全に日本のものになつたことを心から喜ぶものである。 ---一九三四年八月--- BBCシェイクスピア全集の『トロイラスとクレシダ』 演出ジョナサン・ミラー 放映日 1981年11月7日 190分 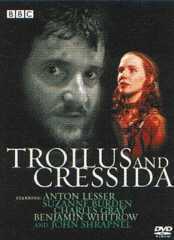 アントン・レッサー Anton Lesser as Troilus, スザンヌ・バーデン Suzanne Burden as Cressida, チャールズ・グレイ Charles Gray, ベンジャミン・ホイットロー Benjamin Whitrow, ジョン・シュラプネル John Shrapnel |