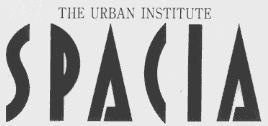まちづくりの参考になる図書
まちづくりブック まちづくり教科書 まちづくり入門・指南
まちおこし・まちづくり物語 人
都市計画 国土計画
保存・再生 景観・路地 みどり・みず ゴミ・エコロジー
産業・経済 商店街 公共空間 交通
市街地整備 地域コミュニティ 住民参加・住民主体 NPO 自治体
住宅地 住まい 建築
地図 まちづくりをテーマとした小説 その他
|
まちづくり極意 くわな流 「くわな」まちづくりブック編集委員会 蛤倶楽部 編著 中日出版社 2003.3 桑名のまちが大好きな市民が参加して作った本。事務局として参加した私もすっかり桑名ファンに。ここで取り上げているのは「桑名」という限定されたまちだが、この本で示したまちの見方やまちづくり市民力は、どんなまちにでも役にたつはず。 |
|
| まちづくりがわかる本−浦安のまちを読む 編著者:浦安まちブックをつくる会 彰国社 1999.11 わかりにくい都市計画をわかりやすく説明するために実際のまちを取り上げ解説。浦安がディズニーランドだけではないことも知ることができる。1999年度の日本都市計画学会石川奨励賞を受賞。 |
|
|
ぼくたちのまちづくり 福川裕一 文/青山邦彦 絵 岩波書店 1999.9 小学校の先生と子供が主人公。まちづくりの楽しさを教えてくれる絵本。児童書といってあなどれない。全4巻。1999年度の日本都市計画学会石川賞を受賞。 |
|
| まちづくり教科書7 安全・安心のまちづくり 日本建築学会 編 丸善 2005.4 地震災害や火災に対する「防災」、災害からの「復興」、犯罪に対する「防犯」、交通事故に対する「交通安全」のまちづくりを取り上げ、その推進方策を事例とともに論考。 |
|
| まちづくり教科書6 まちづくり学習 日本建築学会 編 丸善 2004.9 「まち学習」から「まちづくり学習」、そして「まちづくり」の実践につながる多様な場面をとりあげる。実践編では「まち学習」と「まちづくり学習」の事例を料理のレシピになぞらえる形で整理。 |
|
| まちづくり教科書2 町並み保全型まちづくり 日本建築学会 編 丸善 2004.3 まちづくり運動のひとつの典型ともいえる町並み保全をめぐるまちづくりをとりあげている。 |
|
| まちづくり教科書1 まちづくりの方法 日本建築学会 編 丸善 2004.3 まちづくり教科書と名づけられたシリーズの第1巻として「まちづくりの方法」の基本的な事項が記述され、事例編では、まちづくりの学び方として14の典型的な成功事例がとりあげられている。 |
| まちづくり道場へようこそ 片寄俊秀 著 学芸出版社 2005.12 大阪府技師から大学へ転身した筆者の35年におよぶ研究・教育職の「卒業論文」(筆者の表現)。「志を持った凡人」が良き「まちづくり人」として成長するには何が必要か。まちづくり道場十訓(案)には様々なノウハウがこめられている。まちづくりに真剣に取り組みたいと考えている人にやる気をおこさせてくれるだろう。 |
|
| 現代のまちづくりと地域社会の変革 白石克孝・富野暉一郎・広原盛明 共著 学芸出版社 2002.9 全く異なる経歴をもつ3人による著作。 |
|
| ローマ法王に米を食べさせた男 高野 誠鮮 著 講談社 2012.4 「スーパー公務員」との異名持つ石川県羽咋市の高野誠鮮氏。その活躍についてはテレビ等でも紹介され知っている人も多いと思うが、こうしてまとめられた本として読むとその背景にある思いが伝わってくる。 |
|
| まち歩きが観光を変える 長崎さるく博プロデューサー・ノート 茶谷 幸治 著 学芸出版社 2008.2 「まち歩き」だけにこだわった博覧会が何故うまくいったのか。自分のまちを好きになり、まちを自慢したくなる。そんな市民を多数生み出したことが、長崎さくる博の最大の成果だ。愛知万博との対比で語られる取り組みは、まちづくりのあり方にも通じる。 |
|
| 証言・町並み保存 西村幸夫・埒正浩 編著 学芸出版社 2007.9 わが国の町並み保存を主導してきたリーダー8人のインタビュー。固有名詞で語られる話からその熱き思いが伝わる。 |
|
| そうだ、葉っぱを売ろう! 過疎の町、どん底からの再生 横石 知二著 ソフトバンククリエイティブ 2007.8 朝から晩まで誰かの悪口をずっと話している女たち、朝から酒を飲んでくだを巻いている男たち。そんなまち(徳島県上勝町)が、悪口を言っている暇がないほど忙しくなり、いきいきと働く、みんなが働けるまちに。 |
|
| よみがえれ城下町 犬山城下町再生への取組み 愛知県犬山市都市整備部 監修 風媒社 2006.10 第1回「まち交大賞」計画大賞を受賞した犬山城下町のまちづくりを紹介。まちづくりのキーパーソンが多数登場する。城下町での都市計画道路廃止が何故できたか。住民はどう考えていたのか。 |
|
| こんなに楽しい! 妖怪の町 五十嵐 佳子 著 実業之日本社 2006.4 境港市にある水木しげるロードを取り上げた、ガイドブックであり、水木しげるの本であ り、町おこしの本。 |
|
| 清流の街がよみがえった 地域力を結集−グラウンドワーク三島の挑戦 渡辺 豊博 著 中央法規 2005.11 わが国はじめてのグラウンドワークの取り組みの実践記録。「趣味は事務局長」という渡辺氏の熱き思いが伝わってくる。 |
|
| 黒川温泉のドン後藤哲也の「再生」の法則 後藤哲也 著 朝日新聞社 2005.2 黒川温泉を人気NO1の温泉に作り変えた後藤哲也氏が語る。これまでに訪れた温泉で今一つ満足できなかった人は、そのわけがわかるだろう。7つの癒しの技術、12の再生の法則はまちづくりにも通じる。 |
|
| 町屋と人形さまの町おこし−地域活性化成功の秘訣 吉川美貴 著 学芸出版社 2004.7 1人がはじめたまちづくりが一大ムーブメントとなった新潟県の城下町村上のまちづくり。観光カリスマ吉川真嗣氏の取り組みの一部始終を最も身近に見てきた著者が語る感動の物語。金、労力、責任の3つのリスクを引き受ける。必要なのは「カリスマ性、年齢、頭のよさ」ではなく、「信念」と「実行」だ。 |
|
| 人間都市クリチバ −環境・交通・福祉・土地利用を統合したまちづくり 服部圭郎 著 学芸出版社 2004.4 都市計画の奇跡とも呼ばれる成果をあげたクリチバ。30年間で2.7倍の159万人と急成長し たクリチバの「自動車ではなく人間を中心とした都市づくり」「地下鉄ではなくバスでも工夫によって同等の交通サービスを提供できる」「公園の芝刈りを羊にやらせる」「スラム住民にリサイクルを協力させるインセンティブ」など創造性に富む都市戦略をわかりやすく解説。 |
|
| まちづくりは面白い―地域から人間の生き方・暮らし方を考える 森まゆみ・畠山重篤・内山節・中谷健太郎・福留脩文・太田政男 著 ふきのとう書房 2003.6 地域づくり・まちづくりに関わる5人の人々へのインタビュー。 |
|
| セーラが町にやってきた 清野由美 著 プレジデント社 2002.12 小布施のまちづくりの魅力をさらに高めたアメリカ生まれの女性の感動の物語。小布施に行って蔵部で食事がしたくなる。 |
|
| まちづくりロマン 亀地宏 著 学芸出版社 2002.6 全国10のまちのロマンというにふさわしい物語。まちづくりの発端を見極め、逆境にあえぐ中で、どのように最初の一歩を踏み出し、先進地への道を開いたかを示す。読み物としても興味深いが、まちづくりに取り組むものにとっての視点を与えてくれるという意味でも興味深い本。 |
|
| 日本大正村奮戦記 じいさん・ばあさんが町をおこした 上田昌弘 著 近代文芸社 2000.11 当事者とは違い、第3者の目で大正村の取り組みに対する評価が行われている。それは「青春広場づくりという高齢者対策」という言葉に表されている。高齢者の力をいかし、高齢者がいきいきとするまちづくりを進めているという点で大きなヒントを与えてくれる取り組みといえるのではないか。 | |
| 街が動いた ベンチャー市民の闘い 脇本裕一 著 学芸出版社 2000.7 「まちづくり誕生」で始まる第1章は名古屋で起こった歴史的なまちづくり運動である「名古屋・栄東」をとりあげている。このほかに、大阪・天神橋、高松・丸亀町、長野県飯田市、大阪府豊中市という先進的なまちづくりの取り組みをとりあげている。 |
|
| まちづくりの極意−生涯学習まちづくり二十年とこれから 榛村純一 編著 ぎょうせい 1998.8 掛川市の市長として様々な先進的まちづくりに取り組んできた榛村氏の23冊目の本。榛村氏のまちづくりのノウハウが盛りだくさん語られるとともに、国から出向してきた歴代助役6名の論評が展開されている。 |
|
| 都市の鍼治療 −元クリチバ市長の都市再生術 Jaime Lerner 著 中村ひとし・服部圭郎 共訳 丸善 2005.8 33才の若さでクリチバ市長に任命され、1971〜75、79〜83、89〜92年(3期12年)の任期 の中でクリチバを人間都市、環境都市に変貌させたジャイメ・レルネル氏の知恵が凝縮し たエッセイ。 |
|
| 都市と住まい−西山夘三 建築運動の軌跡 西山夘三 著・新建築家技術家集団 編 東方出版 1997.5 戦後、一貫して住宅問題、都市問題に取り組むとともに、優秀な弟子を育てあげた偉大な学者であり、運動家である著者が新建築家技術家集団の機関誌「建築とまちづくり」に掲載した論文や新建学校等の講演をもとにとりまとめられたもの。 |
|
| 日本版コンパクトシティ 地域循環型都市の構築 鈴木 浩 著 学陽書房 2007.2 コンパクトシティの議論が急速に広まっている。欧米では、環境問題を背景に生まれてきた概念であるが、わが国では中心市街地空洞化をきっかけにコンパクトシティに対する関心が高まってきた。本書では、このような日本特有のコンパクトシティをめぐる動きの背景についてわかりやすく解説している。 |
|
| 自治体都市計画の最前線 柳沢厚+野口和雄+日置雅晴 著 学芸出版社 2007.2 都市計画分野での地方自治体による新しい取り組みを紹介。 |
|
| まちづくりの新潮流―コンパクトシティ/ニューアーバニズム/アーバンビレッジ 松永安光 著 彰国社 2005.9 大学時代に学んだ近代都市計画理論は失敗だった。高層化や標準化が問題であることは実感として感じていたが、理想的な歩車分離の方策として学んだクルドサックが犯罪が多発する現代では不適合だとは・・・。20世紀の失敗を踏まえて生まれた欧米の新しい潮流をみると、未だに20世紀型のまちづくりをすすめている日本の現状が心配だ。 |
|
|
日本型魅惑都市をつくる 青木仁 著 日本経済新聞社 2004.3 2002年刊行の「なぜ日本の街はちくはぐなのか」に続く第2弾。前著で十分論ずることのできなかった3点 |
|
| 区画整理・再開発の破綻 NPO法人 区画整理・再開発対策全国連絡会議 編 自治体研究社 2001.10 区画整理や再開発が本来のまちづくりとしての目的を逸脱し、不動産経営的な側面を前面に押し出した事業が破綻した実態を生々しく伝えている。 |
|
|
国土計画の思想 本間義人 著 日本評論社 1999.7 国土計画の歩みを振り返り、これまでの全総計画が何故うまくいかなかったのかを知ることができる。 |
|
都市の記憶を失う前に 文化庁在籍時に登録有形文化財の創設に深く関わった後藤治氏が歴史的建築物をめぐる日本の現状をわかりやすく解説 |
|
| 求道学舎再生 集合住宅に甦った武田五一の大正建築 近角よう子 著 学芸出版 2008.4 スタートは文化財として保存された求道会館の維持管理費の捻出。敷地や道路の条件が問題なければ分譲住宅になっていた!!。 |
|
| 「地域遺産」みんなと奮戦記-プライド・オブ・ジャパンを求めて- 米山淳一 著 学芸出版社 2007.5 日本ナショナルトラストの事務局として日本各地で歴史資源、鉄道文化財、鳴き砂、茅葺きなど様々な保存活動に関わってきた著者の実践の物語。まちづくりのドラマがここにもある。 |
|
| 東京遺産 −保存から再生へ− 森まゆみ 著 岩波新書 2003.10 東京における様々な保存運動がとりあげられている。その中には、有名な東京駅や上野奏楽堂のような成功事例もあれば、丸ビルや同潤会アパートのような失敗事例もある。それぞれの取り組みが様々なドラマを持っており、読み物としても興味深い。何故、安田邸は保存に成功したのにサトーハチロー邸は保存に失敗してしまったのか。全国各地で進められている近代建築物の保存・活用の取り組みに示唆を与えてくれるだろう。 |
|
|
新・町並み時代―まちづくりへの提案
全国町並み保存連盟 著 学芸出版社 1999.10 全国町並みゼミ東京大会(1998年)において、企画運営にあたった町並み運動に関心を有する若手メンバーを中心に論議されてきた10を越す分科会の主題をもとに執筆者が新たに原稿を書き起こしたもの。 |
|
| 歴史ある建物の活かし方―全国各地119の活用事例ガイド 清水真一・三船康道・蓑田ひろ子・大和智 編 学芸出版社 1999.7 わが国における歴史ある建物の活用の好例について、そこに至る経緯、方法などを解説。活用タイプ別に整理されており、全国で様々な活用がされている実態が浮かび上がってくる。 |
|
| 建物が残った 近代建築の保存と転生 磯崎新 編著 岩波書店 1998.3 磯崎新の初期代表作「大分県立大分図書館」の保存と再生をめぐる顛末記。 |
|
| 歴史的遺産の保存・活用とまちづくり 大河直躬 編 学芸出版社 1997.6 前著「都市の歴史とまちづくり」に続く第2弾。歴史的遺産の保存・活用について体系的な整理がされており、理解しやすい。 |
|
| 景観にかける 国立マンション訴訟を闘って 石井一子 著 新評論 2007.10 景観利益を認め、景観法制定のきっかっけとなった国立マンション訴訟の顛末を市民団体代表の石井氏が語る。明和地所の近隣説明書の内容に唖然とし、行政職員の及び腰の姿、裁判所の理不尽な判決にいらだちを覚える。市民の奮闘が伝わってくる好著であり、「読みだしたら途中でやめられなくなるほど面白い」と絶賛する辻井喬氏の言葉に納得だ。 |
|
| 風景再生論 船瀬俊介 著 彩流社 2007.8 「日本の風景を殺したのはだれだ?」に続く第2弾。 |
|
| 路地からのまちづくり 西村幸夫 編著 学芸出版社 2006.12 路地からまちづくりを考えることで20世紀のまちづくりを見直す。全国路地のまち連絡協議会のメンバーが多数執筆。私も碧南市大浜地区の取り組みを執筆した。 |
|
| 美しい都市・醜い都市―現代景観論 五十嵐太郎 著 中央公論新社 2006.10 「高速道路がない日本橋が美しい」「電柱は地中化すべき」という一律的な景観論を批判。一部納得できない論理の部分もあるが、景観を考える視点としては重要だ。同じ高速道路撤去でも日本橋とソウルのチョンゲチョンでは全く違うのだ。 |
|
| まちづくりと景観 田村明 著 岩波新書 2005.12 横浜でアーバンデザインを実践してきた著者のまちづくり論。「まちづくりの発想」「まちづくりの実践」に続く3冊目。豊富な事例でわかりやすく景観について語っている。 |
|
| 失われた景観 戦後日本が築いたもの 松原隆一郎 著 PHP新書 2002.11 生活圏で生じた4つの景観問題の事例をとりあげながら、わが国における日常景観がなぜこれほど奇妙で見にくいものになっているかを考察。 | |
| 美の条例―いきづく町をつくる 五十嵐敬喜・池上修一・野口和雄 著 学芸出版社 1996.4 1995年度の都市計画学会賞、まちづくり学会賞を受賞した真鶴町の取り組みについて、その中心となった法律家、都市プランナー、建築家の3人が詳細に語る。日本の景観問題に対する画期的取り組みが人口1万人弱の小さな町で何故実現したのか、物語としても興味深い。 |
|
|
みどりのコミュニティデザイン 中瀬勲・林まゆみ 編 学芸出版社 2002.11 「ガレキに花を咲かせましょう」の取り組みが草の根活動のゆるやかな連携から阪神グリーンネットの立ち上げへ。さらにトンボ市民サミットから農都の交流へ。様々な組織やグループによる活動が展開され、みどりのコミュニティデザインが大きなうねりになっていることをいきいきと描かれている。 |
|
| 自転車とまちづくり−駐輪対策・エコロジー・商店街活性化 渡辺千賀恵 著 学芸出版社 1999.3 これからのまちづくりの課題に対して自転車利用が解決の糸口となる期待は大きい。気候や地形など自然条件が異なることもあり、日本全体がオランダのような自転車先進国になることは難しいとは思われるが、地域によっては自転車が主役となるところも生まれてこよう。これからのまちづくりのキーワードとしておさえておきたい。 |
|
|
サステイナブルコミュニティ 川村健一・小門裕幸 著 学芸出版社 1995.11 アメリカで展開されている人間性に根ざした半永久的に存続しうるまちづくり運動を紹介。3組の建築家による3つの事例を紹介し、サスティナブル・コミュニティの2つの理念と7つの要素を整理している。 |
|
|
循環都市のこころみ ソ−ラーシステム研究グループ 著 NHKブックス 1994.10 「都市の水循環」「都市のゴミ循環」に続く著作。都市の悪循環を繰り返して地球を使い捨ててしまうのか、それとも物質循環を取り戻し、未来人に地球を残していけるのかという転換期にあるとし、「環境容量」「環境時間」「環境通貨ルド」という新しい発想を提案。 |
|
|
地域経済は再生できるか 中山徹 著 新日本出版社 1999.3 公共事業に対する批判本の1つといえるが、自治体政策という点で4つの政策的争点をあげ、それを丁寧に解説。論理展開が明確でわかりやすい。 |
|
| 都市はよみがえるか−地域商業とまちづくり 矢作弘 著 岩波書店 1997.12 大型店の進出が地域にとってどんな影響を与えるかを丁寧に検証。米国の例もだしながら、日本の大店法の問題について、都市のマスタープランの実現に即したものであるべきとする。多くの事例が紹介されている。商店街再生を考える上で必読の書。 |
|
| 早稲田発 ゴミが商店街を元気にした! 藤村望洋 著 商業界 2001.8 環境のまちとして有名になった早稲田商店会の話しが大阪弁で読める。早稲田のまちの取り組みが全国に広がっていくあたりの話しがよくわかる。全国の商店街の人に読んでほしい1冊。 |
|
|
スーパーおやじの痛快まちづくり 安井潤一郎 著 講談社 1998.8 商店街の活力がなくなり、どこのまちでも中心市街地の活性化が大きくとりあげられている時だけに、この早稲田商店会のまちづくりと一体となった取り組みは新鮮で、これからの地域と商店街のあり方に大きな示唆を与えてくれる。 |
|
| 公共空間の活用と賑わいまちづくり (財)都市づくりパブリックセンター編著 篠原修・北原理雄・加藤源 他著 学芸出版会 2007.5 欧米を旅するとオープンカフェが魅力的だ。わが国でもそんなオシャレな店が増えてきた。しかし、それはあくまでも民地内でのこと。道路上の利用には多くの制約が設けられ、実現は難しかった。 |
|
| オープンスペースを魅力的にする 親しまれる公共空間のためのハンドブック
プロジェクト・フォー・パブリックスペース 著 学芸出版社 2006.11 ニューヨークで最も大勢の人々を惹きつけ、かつ魅力的といわれる公園、ブライアントパーク。そのしかけをわかりやすく解説してくれるのが本書である。成功している空間の特徴としてあげられている5点は納得できる事項だ。 |
|
| モビリティ・マネジメント入門―「人と社会」を中心に据えた新しい交通戦略 藤井聡・谷口綾子 著 学芸出版 2008.3 2000年前半以降、我が国においても様々な施策展開が行われるようになったモビリティ・マネンジメントの事例を、まず海外での先進的な事例を紹介した上で、我が国における様々なタイプの取組みの代表的事例を紹介。特徴のある代表的事例をとりあげ、わかりやすく解説しているので、交通計画に詳しくないものでも理解しやすい。 |
|
| 住環境整備 街直しの理論と実践 佐藤圭二 著 鹿島出版会 2005.12 住環境整備研究の第一人者であり、名古屋を中心に様々なまちづくりの現場にも直接かかわってこられた佐藤先生の渾身の著。これまで様々な場所で先生の話を伺ってきたが、この本の中で体系的に整理され、解説していただいたおかげで、ようやく先生がいわんとされていたことがわかってきたような気がする。 |
|
| 住み続けるための新まちづくり手法 佐藤滋・新まちづくり研究会 著 鹿島出版会 1995.11 京島や豊中市庄内、神戸市真野のまちづくりを「改善型まちづくりの第1世代」と呼び、基盤整備には成果があったものの住まいの問題にまで到達しなかったと総括し、まちづくりの第2世代として、住み続けられるまちづくりを実現した埼玉県上尾市をとりあげている。 |
|
|
「地域暮らし」宣言 学校はコミュニティ・アート 岸祐司 著 太郎次郎社エディタス 2003.12 著者は秋津の実践を知った人から「秋津だからできたんですね」という質問をよくうけるという。それに対する答えが本書といえよう。ここには、そのための発想法とシステムづくりの方法が丁寧に記載されている。 |
|
| 学校を基地にお父さんのまちづくり−元気コミュニティ!秋津 岸祐司 著 太郎次郎社 1999.3 会議を土曜日に開催したり、父親をひっぱりこむような仕掛けとして飼育小屋づくりや教室を改造した図書館「ごろごろとしょしつ」づくりなどが行われることで、父親が積極的にPTAに参加している。気軽に参加できる舞台と、踊りやすい脚本を用意すればお父さんも出てくるはず。 |
|
| コミュニティデザイン 〜人がつながるしくみをつくる〜 山崎 亮 著 学芸出版社 2011.5 読むと元気が出る、やる気にさせられる本。著者が実際に関わったコミュニティデザインの手法・事例を数多く紹介。 |
|
| ワークショップ 住民主体のまちづくりの方法論 木下 勇 著 学芸出版社 2007.1 ワークショップの広がりとともに、本来のものと異なるものになったり、それが逆にワークショップそのものを否定することになりかねない危機的状況もあるとし、その状況を乗り越えるための注意点を示す。 |
|
| まちづくり協議会とまちづくり提案 久保光弘 著 学芸出版社 2005.8 阪神・淡路大震災の復興まちづくりの現場でのコンサルタントとしての体験を踏まえて書かれた本。 |
|
| 参加の「場」をデザインする 石塚雅明 著 学芸出版社 2004.11 まちづくりプランナーとして各地で参加の住民参加のまちづくりを実践してきた筆者が参加のあり方を問う。どこもかしこもワークショップという状況の中で「参加のアリバイづくり」とならないようにするにはどうすべきか。ワークショップ初心者ばかりでなく、ワークショップの作業に追われて、その本質を忘れがちなコンサルタントも改めて考えてみたい本だ。 |
|
| まちづくり協議会読本 大戸徹・烏山千尋・吉川仁 著 学芸出版社 1999.11 昭和50年代の初期の段階からまちづくり協議会の取り組みに係わってきた行政マンとコンサルタントによって書かれたもの。 |
|
| 市民参加のまちづくり−マスタープランづくりの現場から 渡辺俊一 編著 学芸出版社 1999.2 ニフティの都市計画フォーラムから生まれた本。都市計画マスタープランづくりに関して、先進的な取り組みを行った事例をその当事者に話してもらうとともに、プランナーと弁護士という立場から市民参加のプランづくりについて話してもらっている。まちづくりにおけるインターネットの可能性を知る上でもおすすめ。 |
|
|
多摩ニュータウン発 市民ベンチャー NPO「ぽんぽこ」 富永一夫 著 NHK出版 2000.4 人生の最も重要な晩年を幸せに生きるためには、地域にこころ豊かな人間関係があることが重要であると気づいた富永氏が身近なコミュニティ活動から、暮らしの支援事業を行うNPO法人フュージュン長池を設立するまでの顛末期。 |
|
|
破綻と再生−自治体財政をどうするか 五十嵐敬喜・立法学ゼミ 著 日本評論社 1999.12 財政再建団体になった2つの自治体の例をだしながら、再生の原則の1は「危機の共有」だと指摘。自治体財政を健全にするため、独自の工夫を積み上げてきたという真鶴町「街づくり条例、宗像市「民間委託」、藤沢市「都市経営」などの成功体験も興味深い。 |
|
| 自立する地域−自助・互助・公助のまちづくり 荒田英知 著 PHP研究所 1999.2 中央集権型のまちづくりの終わりから、地方分権、広域まちづくりの必要性を解き明かし、市町村合併を含む広域まちづくりのシナリオをわかりやすく解説。 |
|
| 小舟木エコ村ものがたり 〜つながる暮らし、はぐくむ未来〜 NPO法人エコ村ネットワーキング 編 サンライズ出版 2011.5 「とりあえず、菜園をやるような人にそんなに悪い人はいない」。「エコ村」というネーミングが、いろいろな約束事があり、敷地が広いために価格も高いとまちに一定の意識の高い人々を集めたのだ。 |
|
| ニュータウン再生 住環境マネジメントの課題と展望 山本茂 著 学芸出版社 2009.5 日本最初のニュータウン「千里」の45年の歴史の中から、様々な主体による住環境マネジメントや再生に向けた取組みの軌跡を探り、今後の展望が語られている。 |
|
| これから価値が上がる住宅地 八つの発想の転換 齊藤広子 著 学芸出版社 2005.2 魅力的な住宅地をわかりやすく解説するとともに、8つの発想の転換として、常識として思われていたことに対し、再考をうながし、全国の魅力的な住宅地の事例を紹介することでそれを証明。文章が読みやすく、全体のボリュームも多くないので、本を読み慣れていない人でも気軽に読める。 |
|
| 郊外の20世紀 テーマを追い求めた住宅地 角野幸博 著 学芸出版社 2000.3 関西を中心に明治末期以降の郊外住宅地開発の歴史を紹介。 |
|
| ニュータウンは今−40年目の夢と現実 福原正弘 著 東京新聞出版局 1998.8 千里、高蔵寺、多摩、港北、千葉の5つのニュータウンを比較しながら、その現状と課題を浮き彫りにしている。 | |
| 亡国マンション 平松朝彦 著 光文社 2006.1 日本の住宅政策は「国家詐欺」。現状の住宅政策が続く限り、マンションを購入することは自殺行為だと説く。 |
|
| 建てどき 藤原和博 著 情報センター出版局 2001.4 「家づくりは「生きざま」をも問うてくる」という指摘は考えさせられる。元気なうちに家づくりを体験したいと思わせる本。 |
|
|
インターネットで家が建った 大戸浩+来馬輝順+篠原啓史 著 光芒社 2000.3 インターネットを通じた3つの家づくりの実例紹介。インターネットがこれまで接点のなかったクライアントと建築家の出会いを生みだしている。
|
|
| 骨董市で家を買う 服部真澄 著 中央公論社 1998.11 小説。ある作家が骨董市で古い民家を購入し、それを再生するまでの顛末が書かれているのだが、実体験をベースにしながらも夫という別の目で書くという手法をとっている。実現にむけて突き進む熱気をはらみながら、それを冷静に分析しており、家づくり、それも昔ながらのよさを生かした手作りの課程を教えてくれる。 |
|
| マンションの管理革命−良いマンション・悪いマンション 中島猷一 著 講談社 1998.3 管理会社経営の経験から書かれたマンション管理に関する本。 |
|
|
共に住むかたち 小矢部育子・岩村和夫・卯月盛夫・延藤安弘・中林由行 著 建築資料研究社 1997.12 OM研究所が主催する土曜建築学校の講義録をもとにまとめられたもの。建築を志す若い人たちのために開かれたものであり、わかりやすい。5人の講師が最も得意とする分野について解説してくれており、講師の人となりを知る入門書ともいえる。 |
|
| 新・集合住宅の時代 小林秀樹 著 NHK出版 1997.11 つくば方式についての実際の事例の紹介もあり、仕組みをわかりやすく解説。 |
|
| 誤解だらけのマンション選び 稲葉なおと 著 講談社 1997.9 マンションは、内装や設備や間取りといったこと以前に、コンクリートで囲まれた1つの箱として、その住み心地を検討されるべきものだとして3つのポイントを示す |
|
| これからの集合住宅づくり 延藤安弘 著 晶文社 1995.4 著者が係わった事例を中心に<共に生きる>集合住宅づくり、住民参加の集合住宅づくりの事例12を取り上げ。 |
|
|
自然な建築 隈 研吾 著 岩波新書 2008.11 「コンクリートという素材が、20世紀の都市を作った」という話は大いに納得。何故コンクリートがこれほど普及したのか、そのことによってどんな結果が生まれたか。コンクリートの本質はその中身が見えないことにあった。偽装者がコンクリートの暗黒をターゲットにしたのは必然だったと・・・。 |
|
|
伝統建築と日本人の知恵 安井 清 著 草思社 2007.4 国宝の茶室・如庵の移築、桂離宮の昭和の大修理、ボストン子ども博物館へ京の町家の移築、ニューヨークのメトロポリタン美術館日本ギャラーの書院の建築など、伝統建築に数多くかかわり、志のある大工や職人たちに数奇屋の高度な技術を伝えようと「清塾」を起こした安井氏がその思いを語る。 |
|
|
超合法建築図鑑 吉村靖孝 著 彰国社 2006.5 建築法規がまちのデザインをつくる。街なかにある変わった形の建物が建築基準法の規制ゆえであり、そういうものを時折見つけては納得していたが、その典型事例がこんなにもあるとは・・・。さすが、地価が高く、とにかく基準一杯まで使いきろうという意思が働く東京ゆえというところもあろうが、非常に興味深い。これで学べば建築法規も楽しくなるかも。 |
|
|
奇想遺産 世界のふしぎ建築物語 鈴木博之・藤森照信・隈研吾・松葉一清・山盛英司 著 新潮社 2007.9.20 ぜひ実物を見てみたいと思う。こんな建物があるなんて・・・。 |
|
| 絵地図師・美江さんの東京下町散歩 高橋美江著 新宿書房 2007.6 もともとはグラフィックデザイナーで、新聞に町の絵地図を連載したことがきっかけで、下町歩きの達人に。 |
|
| 京都地図物語 植村義博・上野裕 編 古今書院 1999.4 京都の過去・現在・未来を47のテーマで地図にまとめ、語られている。 |
|
| ロズウェルなんか知らない 篠田節子 著 講談社 2005.7 舞台は過疎に悩む地方のまち。2030年には人口がゼロになると予測されているようなまちで元若者たちが村おこしに取り組む話。悲惨な地方の状況の中で悪戦苦闘する姿をエンターテイメントとして面白おかしく読ませる。 |
|
| エキスペリエンツ7 団塊の7人 堺屋太一 著 日本経済新聞社 2005.7 舞台は東京のとある商店街。シャッター通りと化したまちを現役を退職した7人のエキスペリエンツ(知識や経験をもった熟達者)が再生する話。団塊の世代の定年はまちづくりが大きく進展するきっかけになることを予感させる小説。 |
|
| メリーゴーランド 荻原浩 著 新潮社 2004.2 破綻したテーマパークの再生に取り組む公務員の話。再建のために設置されたプロジェクトチームの最初の仕事が研修視察と称するTDLとUSJの観光旅行の企画を検討するための会議とは・・・。 |
|