| |
石川タニシ先輩の、ネパールでの記録です。
このページの下に「ネパール編-1」、「ネパール編-2」、「ネパール編-臨時増刊」、
「ネパール編-3」、 「ネパール編-4」、「ネパール編-5」、「ネパール編-6」、があります。
ほかに、チベット・カイラス山への「チベット奮闘記」もあります。
タニシの『奮闘記』ネパール編その7平成22(2010)年10月7日〜11月2日 | |
|
「ムスタン王国の都ローマンタン」。なんとロマンの香り高い響きでしょう。
ネパール最後に残された王国です(2008年まで)。地理的にはチベット圏で
ヒマラヤの向こう側です。 今年はここを目指すことにしたのですが、入域許可がなかなか下りません。 とうとう私も政府のブラックリストに載ってしまったのでしょうか。 | |
 ムスタンへの道(2002年撮影)
ムスタンへの道(2002年撮影)
|
ムスタン地域への入域料は10日間までひとり500ドルかかります。これを
政府が徴収してムスタンへの還元がごくわずかなのだそうです。
これに腹を立てたムスタンと政府のゴタゴタが続いており、政府は入域を
拒んでいるらしいのです。 ネパールではもう半年以上も首相が決まっておらず、行政が各所で滞っているよう です。結局ムスタン行きはあきらめざるをえませんでした。 |
|
これはやはり本業の日本語教師に集中せよとのお告げかもしれません。
うれしいことに私の教え子2人が去年と今年、相次いで来日したのです。
それぞれネパール代表6名ほどの1人に選ばれて語学研修のための来日でした。
この2人がさらに上級を目指して勉強中です。ところがいざ授業を始めて
みると2人とも落ち着きがない様子で、なかなか集中できません。 | |
 凧揚げ
凧揚げ
|
この時期ネパールはダサインの祭りの真っ最中でした。 ダサインはお祭り好きのネパールでも最大のお祭りです。 何しろお祭りが2週間も続くのです。この間大人たちは賭けトランプに 興じ、子供たちは凧揚げや花火に熱中します。 街の広場では踊りや音楽のイベントです。夜は親戚や友人を招いての 宴会です。おかげで私もいろいろな家でご相伴にあずかりました。 |
|
祭りの8日目、9日目は神に生贄をささげる日です。
街のあちこちで生贄の鶏やあひる、やぎなどを売る露天商が見られます。
生贄をお寺に持っていって首を刎ねて家内安全と秋のみのりを祈ります。 生贄を売る店→ |

|

|
昔の王宮広場では何頭もの水牛の首が刎ねられます。 神にささげた鶏や あひるが夜のご馳走となるわけです。ネパール最大の祭りダサインは満月 の夜終了します。 ← 首を刎ねられた水牛 |
|
ダサインが終わって2週間もするとティハールのお祭りです。
秋の収穫の祭りとネワール族の新年の祭りです。 ダサインからティハールにかけての1ヶ月、田舎のある人はふるさとに 帰ってしまいます。海外に出ている人はネパールに帰ってきます。 いうなれば盆と正月とゴールデンウイークがいっしょになったような ものです。こんなときに勉強しろというほうが無理なのかもしれません。 |
 カトマンズの満月
カトマンズの満月
|
 ティハール(ネワール族の新年)のつどい
ティハール(ネワール族の新年)のつどい
|
祭りの最中に知人のお子さんが誕生日を迎えました。
神への祈りの儀式があってそのあとダサインとあわせての宴会です。 誕生日の男の子に「おめでとう!いくつになったの?」とお祝いの気持ち をこめて尋ねました。すると父親が即座に「誕生日には年齢を聞いては いけないのです。明日聞いてください」と言うのです。 ネパールではそういうことなのでみなさんもご注意を…。 |
|
友人の山岳ガイドがカトマンズ近郊のシバプリ山を案内してくれました。
標高2732mもある山ですが街の友人たちはほとんど知りません。 鬱蒼としたジャングルに覆われた山でトラも住んでいるとか。 昨年ふもとの村に出てきて射殺されたということです。日本にあれば 百名山に選ばれること間違いないと思うのですが…。 | |
 シバプリ山からマナスル(8163m)を望む
シバプリ山からマナスル(8163m)を望む
|
 タイワンオナガ(シバプリ山にて)
タイワンオナガ(シバプリ山にて)
|
|
新聞に鳥の写真を見つけました。
チメドリ(Babbler)の仲間かと思われますが、もう1種とあわせて2種の
野鳥がネパール初記録として認められたという記事です。 ネパールで記録された野鳥は867種になったと述べています。日本の野鳥 が約600種とすれば、日本の半分にも満たない、なおかつ海のないところ で867種を記録したネパールはきわめて野鳥の多い国といえるでしょう。 右:ネパール初記録の野鳥を報じる新聞(10/14付け) |

| <
タニシの『奮闘記』ネパール編その6平成21(2009)年11月1日〜12月1日 | |
| 初めてのネパール遠征(『ネパール編その1』参照)から40周年を迎えました。 当時ネパールの山の中の小さな村で、はだしで駆け回っている娘たちに我々隊員は心惹かれたものでした。 | |

|
3人姉妹の末っ子の娘は40年後の今、ご主人と一緒に日本でネパール料理店を経営しているのです。私たち当時の隊員は40周年記念のつどいをこの店で開きました。昔にもどった隊員一同大いに盛り上がったのは言うまでもありません。ネパール40年の縁(えにし)です。 ←40年前の3人姉妹 右が末っ子 |
|
このページの管理人宛に国立科学博物館からメールが届きました。 収蔵標本の中に「1969 ネパール 早大生物」のラベルのついたネズミなど小動物のビン入り標本が多数あるそうです。採集時の様子が知りたくて、パソコンで検索した結果『タニシの奮闘記』に行き着いたということです。 当時の標本作成者津田隊員を伴い、高野管理人と私の3人はさっそく研究室を訪ねました。『奮闘記』がきっかけで博物館のお役に立てるならば、小欄としても喜びに耐えません。 さて、今年のネパールには、50年来の鳥仲間であり世界の動物にも詳しい小高先輩が来てくれました。さっそく野生動物の宝庫チトワン国立公園に同行しました。 | |

|
チトワンは東西80km、南北23kmの広大な地域に広がり、世界遺産にも登録されています。 ゾウの背中に乗って動物を見るサファリが売り物です。ここで私たちは野生のインドサイや大きなワニ (クロコダイルとインドガビアル)に興奮し、野鳥は2日間で70種を超える記録を残しました。 ←ワニ(クロコダイル)11/04 |
 インドサイ11/04 |
 ベンガルハゲワシ White-rumped Vulture 11/05 |
|
チトワンの近くに「ハゲワシレストラン」ができたことは「バードライフアジア・ニュースレター」で知りました。編集長を務める上野先輩を通じてネパール鳥類保護協会の会長に、日本から私たちが見学にうかがう旨連絡しました。会長は私たちを現地で出迎えてくれました。 「ハゲワシレストラン」とは、絶滅寸前のハゲワシを救うために牛の死骸を運んできて、餌として供するプロジェクトです。 | |
 ハゲワシレストラン11/05 |
ネパールでは牛を食べません。殺すことも法律で厳しく禁じられています。その牛の死をハゲワシのために
生かそうとするものですが、牛の死骸を得るには自然死を待つしかありません。 そして今日は牛の死骸を入手できないと言うのです。これがなければハゲワシレストランは開店休業です。 会長が解決策を提案しました。水牛なら1頭4,500ルピー(約5,400円)で手に入るというのです。水牛は牛 ではなく彼らの毎日の食料です。 |

|
翌11/6朝、宿の庭先で会長が私たちに話しかけました。「あれがお二人の買った水牛ですよ」。
見ると向こうから村人がまだ子供の水牛を引いてくるのです。何も知らない子牛はあどけない顔でのどかに
とことこついて来ます。 私たちは見なくてよいものを見てしまいました。1,2時間後にはあの子牛にハゲワシが群がるのでしょうか。 |
|
水牛のむくろを前に、私たちは観察舎の中でジーッとハゲワシを待ったのです。ところが1時間待っても2時間待ってもハゲワシは来ないのです。餌がいつもと違うのか、それとも今日は満腹なのか…。 とうとう帰り時間の限界が来てしまいました。カトマンズまで車で6時間かかるのです。後ろ髪を引かれる思いで「ハゲワシレストラン」を後にしました。(帰国後会長から、あの水牛は翌日ハゲワシが平らげたとの連絡がありました。) | |
 エベレスト11/07 |
翌日私たちはカトマンズからブータンに飛びました。ヒマラヤの山沿いに飛ぶジェット機の窓からひときわ気高く大きなエベレスト(8,848m)を見ることができました。 1時間のフライトでブータン唯一の空港パロに到着です。ブータンは「GNPよりGNH(国民総幸福量)」を国の指針として掲げています。経済発展よりも自然や伝統文化を守ろうとする心が伝わってきます。 |
 ターキン11/08 |
パロで1泊し翌日は車で首都ティンプーに移動します。首都といってもここには信号機がありません。珍しい首都といえましょう。 市街地の西に珍獣ターキンの放牧場があります。ターキンは山岳地帯に住む牛の仲間で、ブータンの「国の動物」です。 ここでターキンの保護増殖が図られています。春先には毎年かわいい子供が見られるということです。 |
| 3日目、車はいくつもの峠を越え高度を上げて夕方近くポブジカに到着しました。キリッとした冷気が身を包みます。ポブジカはオグロヅル(Black-necked Crane)の越冬地として知られるところです。 | |
 ↓ツルの里、↑オグロヅル親子11/10
↓ツルの里、↑オグロヅル親子11/10
|
チベットで繁殖するオグロヅルは秋になるとヒマラヤを越えて、この地で冬を越します。緩やかに広がる谷間の湿地帯に昨年は322羽が越冬したそうです。今年は11/08現在104羽が確認されていると観察センターのガイドは言います。 併せて道路以外に立ち入らないことが徹底されます。ブータンの国鳥で絶滅危惧種でもあるオグロヅルもここでは安心して冬が越せそうです。 |

| |
|
11月12日、6日間のブータン旅行を終えて私たちはカトマンズに帰りました。今日からはまた、いつものように日本語学校です。 住み慣れたパタンの街を先輩と歩き、昔の王宮やお寺などを案内しているとき「せんせ〜ぃ!」と黄色い声で呼び止められたりします。 こんな時にはちょっといい気分で鼻をうごめかしているタニシ先生でした。 |
 パタンの旧王宮 11/02
パタンの旧王宮 11/02
|
タニシの『奮闘記』ネパール編その5平成20(2008)年10月12日〜11月13日 | |
|
去年のカラパタール(5,545m)登頂成功に味をしめ、今年はゴーキョピーク(5,360m)を目指すことにしました。 去年と同じサガルマタ(エベレスト)国立公園内の山です。去年は一人での出発でしたが、今年は相棒のAさんと一緒です。私と同じ「前期高齢グループ」ですが、チベットやナムチェバザールにも同行したベテランです。 | |

|
[10月14日] 数日前、霧深いルクラ空港で飛行機が着陸に失敗し、乗客乗員18名が死亡するという事故があったばかりでしたが、私たちは普段の行いのせいか、快晴のルクラ空港(2,804m)に降りたちました。 (写真:ルクラ空港 20人乗りプロペラ機) |
| ナムチェバザールまでは勝手知ったる道のりです。ガイドはそこで探す予定で空港を出たのですが、そこでばったり去年のガイドと出会ってしまいました。これでは彼を雇わないわけにはいきません。これも何かの縁でしょうか。ガイド料1日1,000ルピー(1,300円)で手を打ちました。今年は円高で助かります。 | |
 キャンズマからアマダブラム6,856mを望む
キャンズマからアマダブラム6,856mを望む
|
[10月15日] チェックポストで入山料1,000ルピー(1,300円)を支払いナムチェバザール(3,440m)に向かいます。ほとんどのトレッカーはここで高度順化のために2泊するのですが、私たちは高度順化の心配なしと判断してナムチェバザールを通過してしまいました。 ナムチェからエベレストの見える尾根道に出て、次の村キャンズマまでがんばってしまったのです。去年は3日目の宿でしたが今年は2日目となりました。 |
|
[10月16日] 前日まではまことに順調な旅でしたが、この日はルンルン気分が一挙に吹っ飛んでしまいました。いきなりのモン・ラ(ラ=峠 4,150m)越えが待っていたのです。標高4,000mを超えるとさすがに空気の薄さを実感します。標高差500mをやっとのことで登りきると今度はまた500mの急な下りです。さらにそこから400mあまりを登り返してドーレ(4,084m)までがこの日の行程です。4,000mを挟んでのアップダウンの連続には泣き言の一つも言わずにいられませんでした。 |
 モン・ラ峠4,150m 向こうの山はアマダブラム6,856m
モン・ラ峠4,150m 向こうの山はアマダブラム6,856m
|
|
[10月17日] 毎日朝は6時に起床です。天気は連日快晴ですが、吐く息も白く寒い朝です。 この日はマッチェルモ(4,410m)まで標高差300mあまりの比較的緩やかな登りです。3時間ほどで着いてしまいましたが、先を急いではいけません。高山病の恐れがあるからです。 つい先日も日本のトレッカーが高山病にかかり、ヘリコプターで運ばれたということです。ヘリコプターを呼ぶのに5,000ドル(500,000円)かかるというのがガイドの関心事です。 |
 ゴーキョへの道 マッチェルモの村(左)を見下ろす峠でヤクに出会う 正面の山はチョーオユー8,201m
ゴーキョへの道 マッチェルモの村(左)を見下ろす峠でヤクに出会う 正面の山はチョーオユー8,201m
|
|
[10月18日] 今日も前日同様300mあまりの高度差をゴーキョ(4,750m)まで進みます。30分ほど行くとパンガの村です。1995年11月、ここで大きな雪崩が発生しました。日本人の登山隊および関係者25名と地元の人たちが巻き込まれて命を落としたということです。慰霊碑に黙祷し、先に進みました。 やがて湖が現れます。3つ目に一番大きな氷河湖が現れると、そのほとりがゴーキョです。湖の向こうにゴーキョピークに続く登山道が見えます。 | |
 パンガ村の慰霊碑:1995年11月、大雪崩で日本人登山隊および関係者25名が遭難 |
 ドゥードゥ・ポカリ(ポカリ=湖)とゴーキョ村 左の山がゴーキョピーク5,360m |
|
[10月19日] ルクラの空港を出発して6日目、いよいよゴーキョピーク(5,360m)登頂の日です。5時起床、暗い中ヘッドランプをつけての出発です。すぐに標高差600mの胸突き八丁です。 やがてヒマラヤの山々が朝日に輝きます。希薄な空気にあえぎながらも、2時間ほどで私たちは頂上に立ちました。 右写真:頂上にて うしろの山チョーオユー8,201mとギャチュンカン7,922m(右) |
 |
|
振り返ると氷河湖ドゥードゥポカリ(ポカリ=湖)が青く光っています。そのほとりがゴーキョの村、その向こうにンゴズンバ氷河がせり出しています。 目を転じると北にチョーオユー8,201m、ギャチュンカン7,922m、東にエベレスト8,842m、ローツェ8,516m、マカルー8,463mと8,000m級の山々が聳え立ち、思わず息を呑んでしまいます。 | |
 ドゥードゥ・ポカリのほとりにゴーキョ村 その向こうがンゴズンバ氷河 正面の山はチョラツェ6,440m |
 頂上からのエベレスト8,848m 右の山はヌプツェ7,879mとローツェ8516m |
| 頂上直下で10羽ほどのユキバトSnow Pigeon の群れや、チベットセッケイTibetan Snowcock を見ました。夏は5,000mを越えるところまで生息しますが、冬は低地に下りるとのことです。まもなく旅立ちの時期かもしれません。 | |
 ユキバト Snow Pigeon |
 チベットセッケイ Tibetan Snowcock |
|
[10月20日] 帰りは高度にもなれ息苦しさも和らいで、行きに泣き言を言ったモン・ラ峠(4,150m)をぶじに越えることができました。回り道をしてエベレストビューホテル(宮原氏経営の高級ホテル)に立ち寄り、カレーライス(350ルピー=450円)を食べる余裕さえありました。 [10月21日] ナムチェバザール3,440mに到着すると、そこはもう富士山より低い所です。ここまでくればもう安心という訳で、私たちは祝賀の宴を開きました。去年は翌日のルクラまで我慢したのですが……。 |
 エベレストビューホテルのテラス |
|
[カトマンズで] カトマンズでは日本語学校の教え子たちが待っていました。ここで日本語を教えて8年目を迎えますが、今年は頼もしい後継者が生まれました。千葉県の公立小学校で教員生活37年、多年にわたり校長をも努めたベテラン教師のSさんです。 | |
|
ネパールのアンナプルナ方面へのトレッキングにも同行したことのある山仲間、飲み仲間です。今年の3月までパリパリの現役でした。私がゴーキョピークに出かけている間に、すでに「日本語能力試験」受験生への講座を始めていました。 私がフィールドにしている近郊の田園では、インドコキンメフクロウ君も待っていました。去年と同じねぐらです。 写真:インドコキンメフクロウ Spotted Owlet |
 |
 |
フクロウ君の近くに友人のシタール奏者サテンドラ君の家があります。探鳥の帰りに時々寄ってマンドリンの親分のような楽器を聞かせてもらっています。今年8月には日本にも演奏旅行に来た、目下売り出し中のミュージシャンです。「荒城の月」や「島歌」が好きだというので、去年CDをプレゼントしましたが、今年は早速それらの曲を聞かせてくれました。 写真:シタールを弾くサテンドラ氏 |
 |
もう一人の友人は、画家のロクさんです。タンカ(仏画)の第一人者で、「地球の歩き方」にも紹介されました。彼は良家の子女が通う私立学校(幼稚園から中学校までの一貫校)で、絵を教えながらネパールのよき伝統や仏の心を教えています。この学校の校長先生は仏教徒で頭を丸めた尼僧です。なかなかの教育理念と信念をもった方とお見受けしました。 写真:画家のロクさん(右) |
|
ロクさんとこの学校の校長先生は私と後任のS先生に「この学校で子供たちにあいさつ程度の日本語を教え、合わせて日本の文化、伝統を紹介し、子供たちが立派な大人に育つよう手伝ってもらえないか」と言うのです。難しいけれども大変魅力的な話です。私はすでに帰国の日が迫っているので、後事は後任のS先生に託しましたが、これって“まる投げ”だったのでしょうか。 Sさんよろしくお願いいたします。私はお先に帰ります。 | |
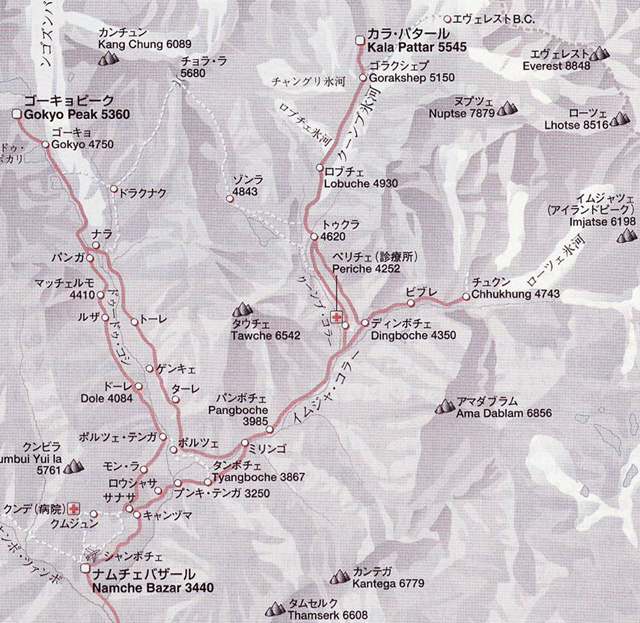 地図は■ダイヤモンド・ビッグ社発行 「地球の歩き方28 ネパール」から借用 |

タニシの『奮闘記』ネパール編その4平成19(2007)年10月15日〜11月27日 | |
|
今年は飛行機の切符を取るのに苦労しました。ベストシーズンのネパールで
ネパールの飛行機が欠航中というのが主たる原因と思われます。 故障が相次いだためと言われています。見かねた当局は飛行機の前に羊を一頭 ひっぱり出し、その首を刎ねて神に祈りましたがご利益がなかったということです。これは人づての話で、真偽のほどは分かりませんが…。 | |
 頭の後ろの黒い三角形の頂がカラパタール5,545m 白い山はプモリ7,145m
頭の後ろの黒い三角形の頂がカラパタール5,545m 白い山はプモリ7,145m
|
10月17日から日本語学校を2週間ほど休ませてもらい、トレッキングに出かけました。
目指すはエベレストのベースキャンプを眼下に見下ろすカラパタール(黒い岩の意、
標高5,545m)です。 カトマンズからプロペラ機で40分、旅はルクラの空港(2,804m)から始まります。空港は山の斜面にあり、着陸の際は斜面を駆け上って止まります。 |
 ナムチェバザール
ナムチェバザール
|
シェルパと二人でルクラを出て、翌日にはナムチェバザール(3,440m)に到着です。ここはエベレスト登山の基地としても知られるシェルパ族の村です。ガイドブックはここで高度順応のため2泊するよう勧めています。今回の旅で最大の心配は高山病です。4年前のチベット行きのときには低酸素室でのトレーニングや、富士山での合宿などの準備を行い何事もなく5,630mまで登ることができました(チベット編参照)。でも今回は怠慢にも何もしていないのです。不安が広がります。 |
|
慎重を期さねばなりませんが、同じところに2泊は退屈です。そこで考えたのが次の日はすこし先の小さな村まで行こうということでした。 ナムチェバザールからひと登りで尾根道に出ると正面にエベレストが現れます。はやる気持ちを抑えてキャンズマという村に泊まることにしました。泊まり客も少なく静かな宿でした。 |
 エベレスト8,848m(左)とローツェ8,501m
エベレスト8,848m(左)とローツェ8,501m
|
| 小刻みに前進しようとの方針は、すばらしい結果をもたらしました。翌日早朝ロッジのすぐ裏の畑でネパールの国鳥 ニジキジを見たのです。一面真っ白に霜が降りて寒い朝でした。その日の行程はかなり厳しいもので、谷底まで下って橋を渡り、こんどは600mの高度差を登り返してタンボチェ3,867mまでというものでしたが、ニジキジのおかげで足どり軽くこなすことができました。 |
 ニジキジ Himalayan Monal
ニジキジ Himalayan Monal
|

|
タンボチェ3,867mは見晴らしのよい尾根の上にあり、大きな僧院のあるシェルパ族の村です。ここか次のディンボチェ4,350mで、やはり2泊するようにと本にあります。前日ニジキジで味を占めた私としては同じように次の日は途中の村に泊まることにしました。4,000mを越えた所です。 ここでも幸運なことに野生のカモシカ、ヒマラヤタール Himalaya Tahrの群れを見ることができました。 |
 キバシガラス Yellow-billed Chough
キバシガラス Yellow-billed Chough
|
 ベニハシガラス Red-billed Chough
ベニハシガラス Red-billed Chough
|
| 少しずつの前進がよかったのでしょうか、高山病も何とか免れています。この先のペリチェ4,252mの村に診療所があり連日救急用のヘリコプターが往復しています。多いときには1日7,8回も見られました。ポーターの背中に担がれて下ってくるトレッカーもいます。シャッターを押す瞬間ちょっと息を止めただけで、動悸と息切れがなかなか治まりません。こんな中での探鳥でしたが、キバシガラス、ベニハシガラス、ルリビタイジョウビタキなどが観察できました。 |
 ルリビタイジョウビタキ Blue-fronted Redstart
ルリビタイジョウビタキ Blue-fronted Redstart
|

| ディンボチェ4,350mからクンブ氷河のほとりに出ると、まもなくロブチェ4,940mです。高山病の心配も少し遠のいたように思われます。トレッキング8日目の明日はいよいよカラパタール5,545mを往復するクライマックスを迎えます。ヌプツェ峰7,896m(写真)が夕日に染まっています。明日も天気はよさそうです。この日はシロボシマシコやムネアカイワヒバリを観察しました。 |
 シロボシマシコ Great Rosefinch
シロボシマシコ Great Rosefinch
|
 ムネアカイワヒバリ Robin Accentor
ムネアカイワヒバリ Robin Accentor
|
| 10月24日、まだ真っ暗な午前5時に起床、6時出発。大岩のごろごろした氷河の ほとりを進みます。やがてエベレスト街道の最後の宿泊地ゴラクシェプ5,288m に到着。前方にプモリ峰がますます大きく迫っています。 その頂上の真下に見える黒い三角形のてっぺんがカラパタールです。高度差に して300m足らずですが、勾配が増し息が切れてなかなか前に進めません。 「もうすぐだよサーブ、ビスターリ ビスターリ(ゆっくりゆっくり)」。 シェルパに励まされながらやっとの思いで進みます。 |
 ゴラクシェプ5,288m
ゴラクシェプ5,288m
|

| 「ローストチキンを食べようかサーブ。うまそうなチキンがいるよ!」。 シェルパの指差す方に目をやるとなるほどうまそうなチキン、いやチベット セッケイ Tibetan Snowcockがこちらを見ていました。 すぐそこにじっとしているのですが写真を撮るのには苦労しました。 動悸と息切れで手振れが激しいのです。 |

|
午前11時30分、這うようにして頂上に達しました。あらためて目を上げる
とヒマラヤの山々がものすごい迫力で襲ってくるようです。 雪のヒマラヤに紺碧の空、このときの感動はなかなか説明できるものでは ありません。 ←カラパタールからのエベレスト8,848m |
|
8日目に頂上に立ちましたが、帰りは4日でルクラに戻って来ました。 ルクラでは熱いシャワーと冷たいビールが待っていました。トレッキング中の12日間は、この私がお酒を一滴も口にしなかったのです。 この強い気持ちがヒマラヤの神様を動かしたのでしょうか。全日程ほぼ快晴、ネパールの国鳥 ニジキジも見られ、高山病にもならず、無事登頂を終えて帰って来られました。羊の首を刎ねるよりもずっとご利益があったと思うのですが…。 | |
| カトマンズではいつものように「日本語能力試験」の試験勉強です。 試験まで1ヶ月という短期間でしたがみんな毎日よくがんばりました。 そして第二部の授業(飲み会)にもよく付き合ってくれました。 | |
|
ネパール鳥類保護協会(BCN)の会員でもある私は、やはり毎日のように
近くの川や田んぼに探鳥に出かけました。BCNの幹事や近所の人たちもよく
付き合ってくれました。 もう一人(1羽)いつも屋根裏の隙間からあいさつをしてくれたインドコキンメフクロウ君、みんなみんなありがとう!! |
 インドコキンメフクロウ Spotted Owlet
インドコキンメフクロウ Spotted Owlet
|

タニシの『奮闘記』ネパール編その3平成18(2006)年10月26日〜12月7日 | |
 ソウゲンワシSteppe Eagle 11/22
ソウゲンワシSteppe Eagle 11/22
|
 カベバシリWallcreeper 11/22
カベバシリWallcreeper 11/22
|
|
今年もまた、「日本語能力試験」受験者の特別講座を開講しました。 教え子の一人が、昨年国際交流基金の招きで来日しました(ネパール編その2参照)。もう一人の教え子が昨年、能力試験3級に合格しました。彼女はその後、日本語弁論大会に出場して優秀な成績を収め、2週間の日本旅行を手にしました。 私の手伝っているちっぽけな日本語学校から、年間二人もの生徒を日本に送り出したのは画期的なことと言えましょう。これひとえにタニシ大奮闘のおかげとは言いませんが…。 | |
 | |
|
ネパールで最初にできた日本語学校の創立41周年記念式典に招待されました。ネパール国の文部大臣をはじめ、日本語教育関係者、卒業生、日本からの協力団体など四百余名の来賓を迎え、カトマンズの一流ホテルで開催されました。 式典の締めの挨拶は、この学校の元校長が格調高い日本語でみごとに決めました。実はこの挨拶、事前に原稿を手直しし、テープによるリハーサルまで指導したのは、かくいうタニシ大先生だったのです。 開校して2、3年の新興日本語学校のネパール人教師から、一度授業を見に来てほしいと頼まれました。行ってみると、その学校の教師全員が迎えてくれました。 授業のあと、お茶を飲みながら校長先生が言います。「先生がこの学校に来てくれれば、どこよりも高給で迎えます。宿も用意します。明日からでも来て下さい」。 これに対して私は悠然とこう答えます。「日本人にはお金よりも大事なものがござんす。私の学校の校長とは10年来の友人でござんす。義理が廃ればこの世は闇でござんすよ」。私は颯爽と席を立ったのであります。 | |
 探鳥会風景 11/04
探鳥会風景 11/04
|
 自然公園の遊歩道 10/28
自然公園の遊歩道 10/28
|
|
ネパール鳥類保護協会Bird Conservation Nepal(BCN)の事務局長が探鳥会に誘ってくれました。カトマンズ郊外の丘の上でした。眼下に田園風景が広がっています。12名のバードウォッチャーが集まりました。このときBCNのパンフレットをもらい、メンバーにならないかと誘われました。年会費は250ルピー(430円)と書いてあるので、その場で加入を申し出ました。ところがよく聞いてみると外国人は10ドル(1170円)だということです。でも、とにかく私は今、栄えあるネパール鳥類保護協会の会員でもあるのです。 | |
 シキチョウMagpie Robin 11/01
シキチョウMagpie Robin 11/01
|
 シリアカヒヨドリRed-vented Bulbul 11/9
シリアカヒヨドリRed-vented Bulbul 11/9 |
| カトマンズを流れる聖なるバグマティ川(どう見てもどぶ川ですが)にBCNは現在自然公園を建設中です(前回報告)。昨年は塀ができただけでしたが、今年は河川敷の藪の中に石畳の遊歩道ができました。ここは私の宿から徒歩15分程度で行けるため、フィールドとして何度も通いました。 日本語学校の生徒には昼間会社や学校に通っている者、仕事をしている者などが多いため授業は早朝7時と夕方5時から行われます。したがって昼間はいつも暇なのです。 | |
 シロボウシカワビタキ
シロボウシカワビタキWhite-capped Water Redstart 11/22 |
 オウチュウBlack Drongo 11/01
オウチュウBlack Drongo 11/01 |
| このフィールドでは日本でもお馴染みのノゴマやシロハラクイナ、ヤツガシラなどが見られます。アオショウビンやオウチュウも常連です。ムシクイの仲間もたくさんいるのですが、図鑑を見ても同じ顔がずらりと並んでおり、識別はお手上げ状態です。もう少し勉強しなくては…。 |
 セボシエンビシキチョウSpotted Forktail 11/22
セボシエンビシキチョウSpotted Forktail 11/22
|

タニシの奮闘記ネパール編 臨時増刊号今回ご紹介するのは、某女子大学教授を務める同期のケロリンタン氏が、平成15(2003)年12月15日発行の同校学園誌第15号に寄せた"巻頭言"です。 | |
昔の日本、今のネパール図書館長 K.K.20世紀初頭、アジアの国々が近代化を学び取ろうと一様に西側諸国へ学生を送り込んでいるとき、ネパールはその進んだ技術を学ばせようと日本に若者を送ったのだ。 |
 村の小学校(撮影 新見亜弥子) |
|
時の国王が、梵語仏典収集のためネパールを訪れた禅僧河口慧海(ネパールを最初に訪れた日本人)に「日本をこれほどまでに強くしたのは、何なのか」と質問した。河口は即座に「教育、そして愛国心だ」と答えたそうだ。今、「日本をこれほどまでに発展させたのは、何なのか」と聞かれたら、「科学技術と……」何と答えるのだろう。 年に数ヶ月はネパールに行き、現地の人々と山にのぼり、彼らの家に泊まり、若者には日本語を教え、現地で働く日本人とともに日本とネパールの交流に力を尽くしている友人がいる。今年も現地の日本語研修生のために日本語の参考書を集め、重たい荷物を背負って旅立っていった。その中には本校の付属小、中、高から戴いた国語の教科書や問題集なども多数含まれていた。私も本箱の片隅に忘れられていた数冊の児童書を彼に託した。 2年前、国民に人望の厚かった国王ビレンドラが暗殺され、共産ゲリラのテロが活発化するなど政情ははなはだ不安定だが、それでも日本語熱は相変わらず盛んで、2000年から日本政府による日本語能力試験も行われるようになったそうだ。日本からの本は貴重な教材として役立ったと大変喜ばれた。もっとも、時間がゆっくり流れているネパールでは、試験が近づいたといって、とくに猛勉強する事もなく、受験生の手伝いに張り切って日本から出かけた彼は、たいそう歯がゆい思いをしたようだが……。 数ヶ月ぶりに帰ってきた彼を囲んで、ネパールの話を聞いた。 ネパールには多くの民族や文化が見られるとの事だが、彼が滞在したシーカ村の人々は驚くほど日本人に似ているそうだ。顔つきや体つきばかりか、その気質、はにかんだ控えめな人づき合い、素朴で飾らない、そして、他人に誠実な人柄。昔の日本の田舎にいるような安らぎをおぼえる、と彼は言う。温かい人情に接したエピソードを聞いていると、彼のネパール土産は棚の片隅に忘れられている日本の心のような気もする。 (Webmaster注:ご本人の希望で出典などをボカしてありますが、支障があればお知らせ下さい) | |
 実りの秋 |
 ヒマラヤの農村 |

タニシの『奮闘記』ネパール編その2平成17(2005)年11月2日〜12月12日 | |
 夜明けのヒマラヤ 左アンナプルナ(8091m) 右マチャプチャレ(6997m) | |

| |
|
ネパールの日本語学校で、「日本語能力試験」受験者のために講座を開きました。その生徒の中で特にまじめに勉強していたA青年が2級の試験に合格し、さらに交換留学生としてネパールで3人のうちの1人に選ばれ、今年(’05年)9月に来日しました。 私としてはこの上ない喜びで、豚もおだてりゃ何とやら……。今年もまたいそいそとネパールに向かったのでした。 今年も早速講座を開き勉強開始となりましたが、この時期のネパールは毎日のようにお祭があります。今日は男の兄弟をたたえる日、明日はネワール族の新年といった具合です。その度に欠席者続出、結局最後まで頑張ったのは3名だけでした。この中から次の留学生が生まれるといいのですが…。 一方、前回も述べたプレムさん。日本語学習歴40年の総決算として挑む最高クラスの1級です。昨年のネパールでの合格者はたった4名という難関。前述したように、試験当日の発熱や夫の入院などアクシデント続きで、4回目の挑戦です。こちらはお祭であろうと新年であろうと休むことなく一日3時間、私が家庭教師を務めました。持病の糖尿病のため注射を打ちながらの勉強です。 | |
 |
「日本語能力試験」は毎年12月第一日曜日に行われます。以前は受験のためにはインドや日本に行かなければなりませんでした。2,000年からネパールでも試験が実施されるようになると、受験生は毎年増加し、今年は1,400名を超えるに至りました。
そんな訳で今年は私までもが試験監督を仰せつかりました。 ←試験中の受験生(12/04) |
 |
そこで分かったのですが、受験生にとって気の毒なのは“聴解”の試験です。教壇の小さなラジカセからテープの声が流れます。音を大きくするためどうしても声が割れてしまいます。加えて窓の外を車が通り、トラクターが通り、時には飛行機の爆音です。こんな中で彼らは試験を受けています。一人でも多くの合格者が生まれる事を祈らずにはいられません。 ←試験監督と聴解試験用ラジカセ |
 | 受験勉強の合間を縫って「ネパール鳥類保護協会」を訪ねました。事務局長が迎えてくれ、バーディングにも誘ってくれました。場所はカトマンズを流れるバグマティ川の川沿いでした。首都カトマンズは人口の流入が激しく、バグマティ川(左写真:11/22)はゴミ捨て場と化し、悪臭が漂っています。それでも1時間半ほどの探鳥で32種もの鳥が見られました。 |
|
ここには現在国連の協力を得て、自然公園を建設中です。川をきれいにし河川敷に緑を増やし、市民の憩いの場とする計画です。 しかしながら、なかなか理解を得られないのが現状のようです。生きるのが精一杯というネパールの人々に、根気よく自然保護を説く鳥類保護協会の人たちに、エールを送らずにはいられません。 | |
 川原にいた2羽のイソシギとオオハクセキレイ(右端) 11/28 オオハクセキレイはインド方面に生息するハクセキレイ の亜種で、日本特産のセグロセキレイによく似ている。 | |
 |
 |
|
| |

タニシの『奮闘記』ネパール編−12003.2.7.受領 |
|
☆ネパールとの長〜いかかわり 「昨年は3ヶ月ネパールで過ごした」と言いましたら、「何をしてたの?」とみ んなに聞かれましたが、これを説明するには遥か34年の昔にさかのぼらなければなり ません。 昭和44年(1969)、私は会社を4ヶ月休んでネパールヘ行ったのです。 早稲田の生物同好会とアジア学会にドクターやカメラマンを加え9名のパーティーで、アンナプルナ方面を目指しました。 今ではトレッキングのゴールデンコースですが、当時はガイドブックも地図もなく、それなりに大変な所でした。何せドクターが肝炎にかかってしまい、軍のヘリコプターを頼んだほどですから… |

「白き神々の座」 ダウラギリ 8,162m(左) と アンナプルナ 8,091m
|
☆4ヶ月の休暇大作戦 4ヶ月も会社を休むと言ったら馘になるだろうなあ、と思いましたが当たって砕け てみることにしました。その計画書に曰く、 ■早稲田大学ネパール西北部民族生物調査隊 ■早稲田大学が総力を結集して送りだす初めての本格的ネパール調査隊 ■隊長は日本歴史学協会委員長文学部教授松田寿男 ■毎日新聞後援、川喜田二郎氏、今泉吉典氏等の推薦 ■翌年に予定されている日本山岳会のエベレスト登山隊、エベレストを滑る三浦雄一 郎隊に先がけて、ネパールとの交流を図る。 上記計画書に加え、松田教授から私の勤務先に対し、現地隊長として石川タニシを ぜひ派遣していただきたい旨、依頼書を書いてもらいました。 そんな訳でやっと馘にならずに行けたネパールで、私はすばらしいものを見たので す。昭和44年10月のことでした。 ☆ヒマラヤを越える鶴 正確に言うと、「ヒマラヤを越えようとしたけれど越えられなかった鶴の群」で しょうか。 ダウラギリ(8,162m)とアンナプルナ(8,091m)の間を縫って流れるカリガンダキ 川。河原から飛び立った鶴の群はダウラギリの稜線を越えようとするのですが、稜線 まで昇っていくとインド方面からの強烈な風に押し戻されて、どうしても稜線を越え ることができないのです。感動の場面でした。 テレビ局のクルーが「ヒマラヤを越える鶴」の撮影に成功し、大変な話題となった のはこの数年も後のことなのです。 ☆もう一つの出会い カトマンズに日本語を勉強している女子学生がいる、と聞いていた私は喜んで彼女 の家を訪ねました。後で分かったのですが、彼女はネパールの日本語学校に入学した 初めての女性だったそうです。名をプレムさんといいます。 今映画館で日本の映画を上映しているというので、2人で見に行ったこともありまし た。その映画は今でも忘れることができません。黒沢明監督の「姿三四郎」でした。 |
|
☆そして今度は 一昨年(2001)の秋、彼女と私は実に32年ぶりの感激の再会を果たしたのです。お互いに32年も年をとっていましたが… そして昨年、彼女は「日本語能力検定試験1級」に挑戦すると言うのです。1級と いえば最上級、日本に何年も留学した人でもかなり厳しいという難関です。試験日は 12月1日。こう聞いては私も黙って傍観している訳にはいきません。試験日直前の 2ヶ月間、私は彼女の家庭教師を引き受けることになったのです。 最初のうちは週3回などと言っていましたが、調子が乗ってくるにつれとうとう毎 日通うようになってしまいました。高校の校長先生であるご主人も、娘さんたち(3 人いますが1人は日本に留学中)も、家族全員が協力し家事を手伝い、本人は文字ど おり頭に鉢巻を巻いて勉強に没頭しました。授業料は娘さんの作ってくれるお昼ご飯 と、ご主人と飲むロキシー(焼酎)ですが、私はマラソンの小出監督のような気分 で、プレムさんと共に試験を目指していました。 しかし物事はそうそう順調にはいかないものです。試験の3日前に彼女は39度の 熱を出してダウンしてしまったのです。 試験は何とか受けたのですが、聴解試験の最中に天井がぐるぐる回って机にしがみ ついてしまったとか。 現在結果を待っているところですが、さて… (続きは「チベット奮闘記」で) |

プレムさんとの再会(左) カリガンタキの河原からのヒマラヤ
北海道天売島でのガイドの記録「タニシの奮島記」へ。
脇野沢編「北限のサル」へ。
チベット・カイラス山への「チベット奮闘記」へ。
「OB近況」頁へ。
![[No-MENU表示]](http://www.asahi-net.or.jp/~xc9t-tkn/image/common/nomenu_b.gif)
この頁をプリントしたり、SVGA以下の画面サイズの場合、
このボタンを押すと左側メニュー部分を消して表示されます。
もとにもどすにはブラウザの「戻る」機能を使ってください。