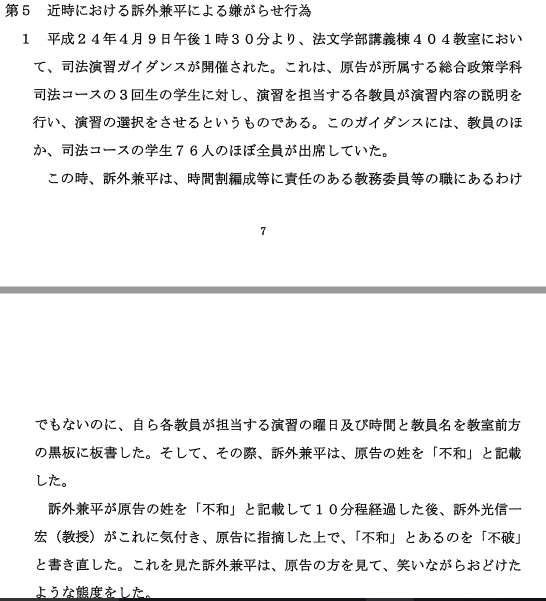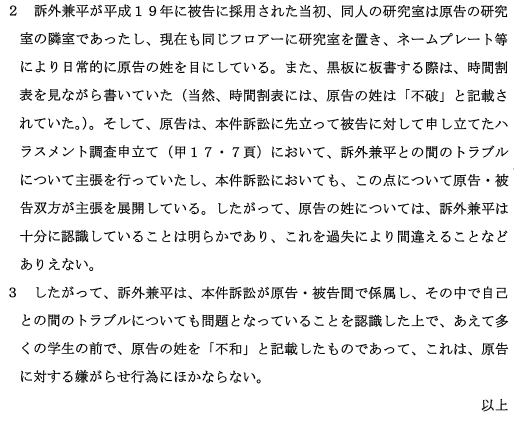裁判のレトリックと真相
大学
原告が弁護士を通じて大学に調査を申し立てた(平成22年3月2付け調査)
申立てたのは、平成2年の就職以来継続していた教員や事務職員らによる集団的組織的ハラスメントであった。以下、人権調査と呼ぶが、ハラスメント被害を受けた教職員・学生が大学に調査を依頼し、人権侵害に対する救済のための何らかの対策を採ってもらう手続であり、学則に規程がある。
人権調査に関わる委員会が複数設けられているが、ここで問題となるのは、対策委員会と調査委員会及び人権委員会である。対策委員会は担当副学長を委員長とし、学長より委嘱される全学の委員会であり、人権侵害の相談があったときに、調査ないし調停の必要があるかどうかを決定する。そして、調査の必要があると判断された事案について、学長の委嘱した全学の調査委員会が調査に当たる。調査委員会には人権問題に理解のある学外の者を含むこととされている。
この調査委員会が対策委員会に対して調査報告を行うこととされており、調査結果の事実関係や被害者救済の方針、処分の必要、予防方策の提案を行う。
原告の調査申立てに対応した対策委員会の決定が、調査委員会による調査不要というものだったのである。学外の者の含まれる委員会に事案を預けることをしていない。
これが最終的に学長を委員長とする人権委員会に報告され、人権委員会は、対策委員会の上記審議結果を妥当であると判断し承認している(平成22年6月22日付け、人権委員会委員長=学長名(柳澤康信)の文書で回答)。

ハラスメント調査なんかするべきではない
ハラスメント救済のための手続が愛媛大学において整備されたのは、そう古いことでは無く、かつて原告が極端なハラスメントを被っていたころにはこのような手続すら無かった。もっとも後に述べるような事情で、講座ないし学科ぐるみの組織的ハラスメントである場合、形式的に手続きを踏むのだが、お手盛りの調査によって既に決まっていた結末を迎える茶番に過ぎない。実態は噴飯物なのである。
学部で秘匿するべき事案であると、あるいは救済を求める者が明白な証拠を欠くとみると、結局そうなる。通常、臭いものには蓋のやり方を踏襲する。
学生対教職員のハラスメント事案と異なり、こと教職員同士の問題であると、被害救済を目的として慎重で公平な調査が行われるなどということはあり得ないのである。
このことは大学に限らず、日本の組織体一般の傾向なのかもしれない。元裁判官で職場におけるハラスメントの原告側代理人として著名な弁護士によると、調査などするものではないのだそうである。お手盛りで調査結果を出されてしまうと、後で裁判にしようとしても、却って、大学という機関によって調査済みであり、ハラスメントを否定する結果が出ているということが証拠として用いられてしまう。調査の不当を訴えても、機関の裁量に属すると言われてしまうのである。

集団的組織的な大人のいじめ=ハラスメント
学部内で繰り返される陰湿な組織的ハラスメントというのは、はた目には軽微なものであっても、長期間の蓄積によって、重大な精神的苦痛を来すものである。加えて、原告の事件では、大学がどうしても表向きにしたくないスキャンダルの隠匿という側面を有していた。
小中学校にある集団的ないじめの存在が、現代日本社会の大きな問題である。いじめられる特質というものがあるわけではなく、いじめる方もいじめられる方も普通の子である、互換性が言われる。大人の職場といった組織内のハラスメントも良く似たものではないかと思われる。ハラスメントを被る側がそのような特質があるとも言えまい。全く偶然的に標的が定まり、集団性を生じると、「ハラスメントを受ける側に問題がある」と周囲に説明され、むしろハラスメントが正当化されることすら有り得る。いじめっ子がいじめを受けている子を指して、あいつが悪いからだという。このあたりもよく似ている。これが、大学という高等教育機関の教員同士にも生じるのである。原告を取り巻く組織というのが、国立大学の、しかもいわば法学部のような法律の研究者集団であってみれば、笑止千万ではなかろうか。
しかし、大人の場合、子供と異なり、「いじめ」を受ける側も自分で防御することができる場合がある。声を上げることができるのである。そこで一見「けんか」のように見える側面を有する。暴力行為が許されないことは当然の前提である。これが刑事犯罪に該当し、警察沙汰になる。刑事告訴されるおそれがある。一定の人格を備えた人間であれば、こんなことぐらいは理解できる・・・はずだ。そこで最初は口げんかから始まるのかもしれない。原告はこの口げんかがめっぽう強い。罵詈雑言の類いを浴びせるというのではない。論理的で知的な、言論による攻撃となる。これに対するに、周囲が物理力を行使する。これが研究室周りでの意図的な騒音であり、聞こえよがしの暴言等である。

衆人環視の下の集団リンチと隠蔽
知人の弁護士によると、研究者集団はお公家さんの集団だそうである。「斬った張ったの世界」(弁護士らは自分らの法廷内外での闘争をこのように表現する)に住む弁護士と違って、実に、嫋やかに、しかし陰湿な方法をとる。口げんかで負けて口惜しいと憤慨すれば、嫋やかな方法でこれでもかこれでもかと嫌がらせを繰り出してくる。それでも相手が尻尾を巻かないとすると、もうそれ以上の卑しい行為を地域社会からは名士として扱われる教授が自分自身ではできない。それではどうするか。自分のコントロールの及ぶ学生や院生を使う。
原告の場合、事務系職員や技術職員(技官)が教員らの悪口に接し、直接これに呼応する形で、あるいは忖度して、更に問題のある行為に及んだのである。特に、特定の技術職員らが原告に対して極端な人権侵害、身体の危険を感じさせる程の行為に及んだ。
特定の技術職員ら無法者を使って、溜飲を下げる、他人の行為によって自らの意趣返しをするという下劣な行為を一部の法学科教員らが行ったのである。その結果、法文学部として、ひいて大学として、犯罪に匹敵する行為を放認してしまった。重大な責任が共謀者である法学科教員らのみならず、大学としても存在するのであり、その後の放置と相まって、この雰囲気が今日まで継続している。
当時は衆人環視の下での集団リンチの様相を呈しており、原告の肉体的精神的苦痛は絶大で、憔悴の極にあった。仮に原告自身の回避行為があったとしても、それ自体、法学科教員の一部により誘導されたのであって、原告を非難することは、到底適わない。
この事実を隠蔽し続け、あるいは公然の秘密として、原告がこれを主張すると、却って原告を非難するのである。証拠があれば出してみろ、証拠が無いなら泣き寝入りするのが当然だというのである。当初の犯罪を含む重大な違法行為に対する何の反省もなく、今日まで、漫然と違法行為、違法状態を放置している。この状況こそ、原告の精神的苦痛が極限に達していることの理由である。

地裁判決の問題
大学人権調査が手続適正を欠くとする特段の事情がない?
原告の調査申立書は、具体名を挙げながら、原告自身のメモに基づき、記憶のある限り詳細に、具体的な行為を逐一記述する内容であった。
これに対して判決は次の様に述べて、一蹴している。「加害者とされる教員や嫌がらせの内容が多岐にわたる」。「原告が嫌がらせであると指摘する他の教員らによる音立て行為は、いずれも日常生活で生じる雑音を、原告が全て自分に差し向けられたものと思い込み、過剰に反応したものではないかと疑われる」。「この他に原告が嫌がらせとして主張するものも、その内容から、被害妄想的な思考様式に基づくものではないかと疑われるものである」。
そして、大学における人権調査の決定は一にかかって大学側の裁量的判断に委ねられるとし、この人権調査が不十分・不適切であると原告が申し立てるためには、「殊更に原告を不利益に扱うものであるなどの特段の事情があることを[原告が]主張立証する必要がある」として、この特段の事情の存在を否定した。
この特段の事情はいかにして立証可能なのであろうか。ハラスメントがあったか無かったかは、正に、言った言わないの世界である。組織的日常的ハラスメントというのは、原告自身の記述や証言以外には証拠の存在し得ないものなのである。
あるいは暴言を浴びた証拠としての録音や暴行の証としての身体の傷害、遺書を残した自殺、耐えきれなくなって辞職することがその証拠となり得るのかもしれない。
実際、和解交渉の際に、担当裁判官が原告に対して、このような訴えは、「辞めてからするものだと考えますよ」と言われたのである。どうやら原告自身の述べる程度のことは、日常的なハラスメントとして「受忍限度」内であるとするようである。「この程度のことでガタガタいうな。そんなぐらいどんな職場にでもあるだろう。裁判で救済を受けることができるとするなら、日本中の裁判所が忙しくなって困る」というのが裁判所の本音だろう。しかし、裁判所は重要な事実を見落としているか、あるいは意図的に見ないふりをしている。
大学の人権調査を全く大学の裁量事項であるとすると、お手盛りの調査手続によって、大学の思い通りの調査結果を得て、ただそれが肯定されるのみである。調査で実際に用いられた証拠、それも当事者双方のそれを精査するとともに、手続過程を、その審議内容に踏み込んで、実際にどの委員がどのような発言をしたかなど、慎重に審査するべきなのである。
この大学側調査において、原告からの詳細な調査申立書があったものの、救済を求める当事者である原告自身への聴取がなされたことがなく、加害当事者から対策委員会にする説明に対して、原告からの反論の機会も与えられていない。裁判において、大学自身がこのことを認めている。
当事者双方からの事情聴取を、何度か繰り返してゆく内に、各々の証言を付き合わせるなどしながら事実が浮かび上がるというものではないか。それほど深刻な原告の訴えに対して、お座なりに、加害側に一回聴いてみただけで本当の調査と言えようか。ハラスメント加害者に対して、穏便に「あなたはハラスメントをしましたか」と尋ねて、やりましたと正直に答える者はどこにもいない。
具体的詳細であって極めて深刻な内容である原告の申立てに対して、外部者が入る調査委員会による調査を不要とする門前払いなのである。

対策委員会は理由を決定することにはなっていないので、理由を伝えることができない?
原告の事件では、調査結果の伝達として、本部の米沢慎二人事課長及び秋谷恵子副課長が原告研究室を訪れ、上記6月22日付け人権委員会回答文書を手渡した際に、原告がいくら求めても、「手続的なことのみお答えします」として、実質的な理由の説明を一切拒絶された。また、調査結果に対する異議の申立てについては、ハラスメントがあったとされた場合に加害側がすることを予定しているので、ハラスメントがないとされた場合の被害側からの異議申立ての手続そのものがないと説明された。
その後、弁護士を通じて、大学に対して、正式に文書で釈明を求めたのに(同年8月18日付け、求釈明書)、学長名文書によって理由説明を拒絶された(同年10月4日け、回答)。実は原告の所属部局から仰々しい相当大部の資料が提出されていたことが、裁判を通じて判明したのだが、このような資料の開示もなされなかったのである。大学は、人権調査に関わる「対策委員会の役割は、判断した理由そのものを決定することとはなっていませんので、これをお知らせすることはできません」という(上記回答)。これは学則上、管掌事項として「理由決定」という明示の文言がないということを意味すると思われる。一体、どのような決定に理由のない決定などあろうか。その理由説明を幾ら求めても、してもらえないのである。
適正手続に悖る。これに対して、裁判所が特段の事情がないというである。

対策委員長の陳述書
裁判において、対策委員会委員長である曲田氏の陳述書が提出されている。労務・環境担当の副学長として、人権委員会の一員でもある。そして、同氏が対策委員会による調査結果を学長を委員長とする人権委員会に報告した。
この陳述書によると、原告が各種嫌がらせを受けたとの主張に対して、「「嫌がらせ」であるとされる各行為の存在を認めることは困難であ[る]」と判断した。その理由が、まず、原告の所属学部の学部長より「提供された資料を確認した結果、原告の行動に問題があると考えられ」ることである。
そして、曲田氏の陳述書によると、「聞き取りに応じたある教員からは危害を受けるおそれがあるので、自分が事情聴取に応じたこと、応答した内容については必ず秘密厳守に願いたいことを懇願されました」とされている。
また、「申立の内容自体の信憑性、15年以上前の出来事についてハラスメントを主張し始めていること」が判断の理由である。
この陳述書に対応する作成者の証人尋問はなされていない。
以下に、反論する。
第一に、学部より提供された資料というのが、大学本部より提供された大量の資料を含むのである。対策委員会が大学本部の一部であるという感覚が当たっているとすれば、最初から調査の中立性が疑われるものであった。
第二に、仮に「原告の行動に問題がある」として、そのことがその他の者のハラスメントが無いと判断することの理由にならない。「原告に問題行動がある」とその部局の者が言っているから、これに対する仕返しは構わないとでもするのであろうか。
危害を受けるおそれがあるので、秘密厳守を願い出ている教員というのが、原告に全く見当が付かない。これが平成22年4月19日に行われた第2回対策委員会の審議において言及されたとある。後掲の兼平氏のことだとすると、宮崎氏の陳述書に対応する。後述する「板書の事件」が平成24年4月のことであり、やはり後述する宮崎氏の陳述書では、秘密厳守であるはずの兼平氏の名前入りで、同氏が原告からの威圧的な言動に恐怖を感じており証言等を一切拒否しているとされたのが、24年9月である。この曲田氏の陳述書の書かれたのが、平成25年6月6日である。「板書の事件」を、危害をおそれ、恐怖で証言等を一切拒否している人がしたのである。
原告のしたという威圧的な言動や危害について、大学において、原告に対する調査や何らかの注意や相談がなされたことがないし、従って、処分などもなされたことがない。危害のおそれがあるほどの言動であれば、なぜこれがなされないのか大いに疑問である。この聴取において、原告が同氏に「だまれ」と怒鳴ったことになっているが、これはあり得ない。同氏が大声で院生と雑談しているので、「あなたは指導者としての立場をわきまえなければならない」と、詰問調であったかもしれないが、そう言ったのである。このことが対策委員会の判断の根拠の一つであるにも関わらず、原告への聴取がなく、反論の機会も与えられない。
第三に、15年以上前の出来事についてハラスメントを主張し始めているというのが、事実誤認である。15年以上前から、学部長にはハラスメントへの対策を願い出ていたのであり、原告の調査申立書はその当時より始めて現在に至るまでの状況を記述し、当該学部において組織的ハラスメントが継続しているという継続性を主張するものであった。また、15年以上前の出来事であっても、事実であるならハラスメントの一つの事例として申し立てても何の不思議もないのであり、ハラスメントが無いとする根拠とはならない。
これに対して、判決が、対策委員会が調査委員会の調査の要否を判断することは、対策委員会の裁量に委ねられるとし、「内容について具体的な調査は不要と判断し、調査委員会に調査を要請しないこととした対策委員会の判断が不合理でその裁量を逸脱・濫用するもものであるということはできない」としたのである。

素行が異常で精神不安定の証拠?
他方、判決は、大学側が、平成5年12月から平成6年1月にかけて、原告の素行が異常で精神的に不安定な状態であった旨主張していることについて、大学側がその事実が存するものと考えたことを相当とし、昇任審査は全人格的判断であるから、教員の執務外における素行等、大学関係者が多く居住する宿舎内での言動は考慮されても仕方ない、というのである。
この内容が、原告がした平成22年における大学への調査申立において、所属より対策委員会に提出された資料に含まれていたのである。
上述のように、これをその調査過程において、原告が見せられたということがない。反論の機会が無かったのである。原告の「異常な素行」や「精神的に不安定な状態」というのが、一にかかってこの大学側文書の中の、事務職員の作成したメモを根拠にしている。裁判において、これを原告が逐一否定しているのは言うまでもない。
そのメモにある原告の発言とされるもののスピーチレベルや内容について、原告自身のものとは到底思えないようなものなのである。殊更に、原告の精神的な異常性を強調するような表現となっている。例えば、大学側文書によると、原告が「宗教団体に命をねらわれている」と発言したとされている。実際、原告にはこのような発言をした覚えがない。
その当時、大学内、官舎内での状況が、生命身体の危険を感じさせるほどであると言ったのである。その根拠は、一例を挙げると、深夜熟睡中に鍵を掛けた自室に侵入され、身体の直ぐ側まで来て、写真を撮影された。また、留守中にも侵入の痕跡があって、しかも当時はその経路が分からなかったというような事情である。その加害主体は宗教団体ではなく、大学職員であった。
裁判所は、被告大学側主張として、その体のメモの記述を繰り返しつつ、専らこれを根拠に、当時の原告の素行や精神不安定の事実を、15年以上も隔てた後の調査時点において、原告からの聴取をすることなく、従って反論の余地もないままに、大学側が存在すると考えたことを、「相当」としている。

大学本部事務部の作成したメモを、所属学部より提出させ、対策委員会が根拠としたこと
このメモは大学本部である事務部の作成したものであった。学長お膝元の経営陣・事務組織を大学本部と呼ぶとすると、ここが大学全体の運営に関わる。所属部局というのは原告の所属する学部である。大学本部と各部局は独立した組織体として、前者が後者を統括している。
上記メモの保管者であるべきは、作成部署の存在する大学本部であるはずである。そうすると、所属学部から提出された資料の中に、このメモが含まれている理由が分からない。原告による人権調査は、原告と所属部局との関係における、ハラスメントの存在と昇任拒絶の正当性を問題にしている。その判断者が本来中立的であるべき全学組織としての人権委員会や対策委員会である。実際には、このメモ類が本部より、所属部局を経由して、対策委員会に提出された。かつ、対策委員会がそのメモ類に依拠して判断した。最初からこれら委員会の中立性など期待してはならなかったのである。(メモ作成者は大学本部事務局であり、その15年以上も前のメモを、法文学部事務部が保管しており、これを調査に際して学部側が対策委員会に提出した。括弧内2022年1月3日追加)
むしろ大学ぐるみで、スキャンダルの隠蔽工作が行われたのである。原告による調査申立を封殺して原告の口封じを狙い、それ以上の問題化を防ごうとしたのである。

アカデミックハラスメントの良い一例が兼平裕子教授による次の事件である。女性教授による壮年期男性講師へのいわゆる逆ハラスメントであり、女性代議士による男性秘書へのハラスメントが近時相当話題にはなっているが、全国的にも珍しいであろう。原告の裁判において、平成24年7月12日付け原告準備書面(5)で主張した事実関係である。若干読みづらくなるが、改変がないように、次に、その準備書面をスキャンしたものを貼り付ける。
ゼミ選択のために説明会に訪れている多人数の学生らの面前で、公然と原告に恥をかかせる行為である。また、ゼミ選択への妨害行為でもある。この時点で、誰一人、問題行動を注意する者もなかった。名前というのは、人の人格権を象徴するものであり、これへの悪戯というは、極めて悪質な他人の人格を傷つける行為である。
この動機としては、次のようなことが考えられる。この数年前、原告の研究室前の廊下で、兼平氏が同人の指導する院生と大声で立ち話をしていたのを、原告が注意したことがあり、自己の院生の前で恥をかかされたと感じた兼平氏がこのことを根に持ち、原告に腹いせをしたものである。また、裁判における原告陳述書に描写したように、平成22年に兼平氏が教授に昇任した際に、その人事教授会において、研究業績の不備について鋭く追求したことがあった。その後も、氏による原告への些細なハラスメントは継続していた。

ハラスメントの集団性及び人権調査の不当の証拠
一見、たわいもないことのように見える。 しかし、次の諸点を証明する事実であると考えられる。
第一に、このようなことが許されて当然であるという、法学系教員ら全体の雰囲気が存在するということである。
次に、一層重要であるのは、大学によるハラスメント調査が恣意的で公平を欠くということを立証できるからである。重要なことは、前訴控訴審口頭弁論終結後に、原告が以上の事実関係について、大学の人権相談窓口を通じて大学に調査申立をしたことである。このときの大学側調査の不公正が明白である。

調査結果の伝達
対策委員会による調査結果を伝達した事務部とのやり取りを全て録音している。以下は、その内容を正確に伝えるものである。
平成26年10月2日に原告より人権問題相談員連絡協議会という大学内組織に対して相談を開始した。
1回目回答
これに対して、同年12月18日午前10時大学本部3階会議室において、人権問題対策委員会より決定が伝達された。伝達者はハラスメント防止対策室長のA氏と人事課副課長B氏(いずれも事務部)である。
A氏が「対策委員会委員長(担当理事副学長・曲田清維)の命を受けて、同委員会の決定を伝えます。文書ではなく、口頭で伝えるように指示されている」と述べ、結論的に、「原告の訴えるような事実関係があったことを確認するが、ハラスメントには当たらない」とした決定内容を伝えた。
これに対して、原告(前訴の)より、次の諸点の質疑を行ったが、A氏より、自分は権限がないので、持ち帰り、委員長の見解を質すとされた。
すなわち次の諸点である。
兼平氏の行為は名前を汚すような行為であり、重大な人格権の侵害である。ゼミ選択のためのガイダンスにおいて、セミ選択のための投票直前に、70名ほどの学生の面前で行われた点も重大な権利侵害に当たる。不破を「不和」と故意に書いたもので、特定の意味内容を有し、原告のした裁判提起に対するものとしてそれぐらいされて当たり前との兼平氏の発言も聞かれた。以上について、少なくとも謝罪に値すると考えるが、この点の見解を伺う。
調査の、対象・範囲、内容がどのようなものであったかを伺う。
本決定及び以上の質疑について、責任を有する者の名前で、文書により回答願いたい。
以上である。
2回目回答
これに対して、翌27年1月22日第2回目回答において(時間、場所、伝達者は同じ)、対策委員長代理(A氏)として次の回答が伝えられた。文書での回答は行わない。決定理由についての原告の問い合わせに対しては、「対策委員会はいかなる意味においても理由を決定するものではない」。
兼平氏の行為が意図的であったかについては判断しない。
少なくとも謝罪が相当の不適切な行為であったのではないかとの指摘に対しては、「ハラスメントには当たらないと判断したのだから、対応しない」。
調査対象及び方法について、「回答しない」とされた。
以上の回答に対して、原告(前訴)としては、70名を超える学生がゼミ選考のために集まる前で、コース所属教員全員がいるところで、兼平氏がこのような所為に及んだことで、大勢の前で恥をかかされたのあり、大変ショックを受けた。重大な問題であるとの考えを伝えている。そして、上記の態様でなされた兼平氏の行為は極めて不自然なもので、意図的行為に間違いない。そこで、意図について判断せず、しかもハラスメントに当たらないと決定された、判断のプロセスが知りたいとして、再度質問したところ、A氏より、これを委員長に持ち帰るとの回答を得た。
3回目回答
同年2月23日第3回目回答(時間、場所、伝達者は同じ)があった。A氏が委員長代理として次の様に述べた。
「ハラスメントに当たらないという結論は、総合的に判断したものである。これ以上の回答は行わない」。
原告からは、事実関係を認めた上で、そのような結論に至った理由が分からない。 調査対象及び内容と判断の根拠が分からないので、今後、情報開示請求の手続きによらざるを得ない、と伝えた。

情報開示請求
同年3月2日に次の法人文書開示請求を大学に対して行った。次の内容である。
「開示請求者が平成26年9月に人権問題相談員に申告し、同年10月2日に面談が実施された、法文学部総合政策学科における兼平裕子教授のアカデミック・ハラスメントに関し、同年12月18日に、事実関係の存在を認めながら、ハラスメントに該当しないとする人権問題対策委員会の決定が通知された。このことに関する人権問題対策委員会における審議の具体的内容が分かる資料及び当該人権問題対策委員会に提出された相談員等による調査に係る関係人らに対する聴取内容などの調査資料の一式」
これに対しては、同年3月26日、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第五条1号に該当する個人情報が含まれるとの理由で不開示決定が通知された。要するに、個人情報が含まれているので開示しないという。ハラスメント加害者として名指しされている兼平氏を巡る内容がここでいう個人情報ということである。
同年4月3日、同様の内容で、原告の個人情報の開示請求を行った。
これに対しては、一部開示が認められた。
一つが、人権問題相談員らが行った原告からの聴取内容についての報告書である。上記内容と同一の内容が報告書として纏められている。
本当は、対策委員会において考慮したはずの、加害側関係人らに対する聴取内容等の資料一式の開示請求を行ったのである。加害側である兼平氏らに対する事情聴取が有ったかどうか分からないが、有ったとするとその内容から、対策委員会の判断の妥当性が検証できると考えられる。被害側及び加害側の聴取内容がどの点で一致し、どの点で対立しているのか、そして対立点をどのように判断したかが重要である。兼平氏が原告の名前を異なる漢字で板書した基本的事実関係を認めているのである。判断の基礎となったこれらの資料は開示されない。
なお、全部開示となっているが、原告への聴取内容のみであり、その全部と言うようである。
他が、上記決定を行った平成26年11月25日付け人権問題対策委員会議事録要旨の一部開示である。但し、審議のプロセス、過程及び内容に関する部分については一切不開示とされている。結論部分のみあり、その他がほぼ真っ黒に塗られているもののみが送付された。「この案件をハラスメントとは認められない」とするが、事実を否定する結論ではない。事実関係を前提として、ハラスメントとはならないとする趣旨である。
以上より、大学におけるハラスメント調査というものがいかに片手落ちであり、不公平なものであるかが分かる。

前の裁判との関係
直近の訴訟の前提となった調査の担当副学長である曲田氏がこの調査の担当ともなった(外部者の入らない対策委員会の委員長)。
兼平氏の板書の問題は、前の訴訟において、最初の調査申立書に含まれない最近のハラスメント事例として、詳細に主張されていた。全く同一内容で(原告準備書面をコピー・アンド・ペーストして)、新たな人権調査申立てを大学に行ったものである。
裁判では何故か認定に至らなかった事実が、少なくとも基本的には大学によって認められたのである。曲田氏からすれば、「こんなことを再び蒸し返して煩く言う」と腹立たしく感じたのであろう。裁判ではこのようにいう。事実があったか、無かったか、それが重要である。両当事者が事実の存否に関して対立するなら、証拠のない限り立証責任のある方が負ける。しかし、基本的事実自体が自白されたなら、その事実があったのである。兼平氏が原告の名を「不和」と表記したのである。
人権調査が不当であることの特段の事情が、立証されたと考える。

大学が前の裁判でいかに嘘をついたか
次に、視点を変えて、この兼平氏の一件と裁判との関係について述べたい。これにより、大学が裁判でいかに嘘をついたかが明らかになる。
原告が、板書の件を裁判において主張していたのに、判決では認定されていない。原告側主張の整理にすら出て来ない。
裁判時における所属学部学部長(宮崎幹朗)の陳述書が重要な証拠として提出されていた。同氏は、原告採用手続における大学側担当者であり、以降、原告からの苦情対応に当たっていた者で、しかも問題の写真回覧等のあった当時、同一の宿舎に住居を有していた。大学に対する裁判であるが、個人として、裁判に最も関係の深い正に当事者的な存在である。この陳述書に次の様な件がある。
「私(宮崎)は直接にこの間の事情を了知しているわけではありませんが、原告が主張するようないやがらせの事実は認められず、むしろ、兼平教員は原告からの威圧的な言動に恐怖を感じて、研究室を移転したほか、原告と接触することを避けているものと聞いています。また、原告からの今回の訴えについても、原告への恐怖から関わるのが怖いとして、証言等を一切拒否しています」。
この陳述書の日付が平成24年9月6日である。
板書の事件が、同年4月9日である。現在まで、同氏は他と談笑しながら会議等(少人数の会議であっても)に平気で、原告と同席している。板書の事件から、五カ月ほど後に、突然、恐怖に襲われ、自分にされたとする「言動」を証言することすら一切拒否するほどになったのであろうか。
再度、日付を整理しておくと、前訴提訴以前の第1回目人権調査において女性教員の「恐怖」に言及されたのが平成22年4月19日、兼平教員の「板書の事件」が平成24年4月のことであり、宮崎氏陳述書で同教員の「恐怖」と表現されたのが、24年9月である。前訴における曲田氏陳述書の日付が、平成25年6月6日である。
宮崎氏の陳述書には、同氏と原告との関わりから言って、他にも極めて重要な事実関係についての証言が含まれていた。愛媛大学における原告採用時の、採用担当者であったので、准教授までの昇任がほぼ確実であるとの説明、その他採用時の状況や当時の噂、講座及び学科の勧告文書(弁護士の頁参照)の内容等、全て、原告の主張を否定していた。事件を決定づけるべきものであった。
この明確な嘘が含まれている陳述書が信用できるであろうか。当然、控訴審終結後に原告からした兼平人権相談については、判決に反映されていない。新たなハラスメント調査の結果が、仮に、地裁判決前に出ており、原告主張に組み込まれていたなら、どのような結論になっていたのであろう。
しかも宮崎氏は、当初、証人として証言予定であるとして、裁判所及び原告に連絡していたにも関わらず、突然取りやめたのである。通常、陳述書とそれを書いた証人の証言を合わせて、信頼性のある証拠となる。人証を欠く陳述書というは、実は、とても危ない代物であり、裁判所によって、正反対に解釈されても仕方が無いのだそうである(知人の弁護士)。実際に、交代前の裁判官が、「人証のない陳述書ばかり出して、その意味が分かっているのですか」と叱りつけるように大学側に言っていた。しかし、交代した裁判官は、この宮崎陳述書も前提して判決を書いている。
最後に、兼平人権相談に関して、次のことを再度強調しておきたい。原告の裁判において、適正手続を欠く不適切な(第1回目)調査手続を行ったとされた対策委員会の委員長が、この新たなハラスメント調査を行った対策委員会委員長である曲田氏その人なのである。曲田氏自身が、前裁判において、大学が行った対策委員会の手続に問題が無かった旨の陳述書を提出している。

事務部の忖度事例
大学によるハラスメント調査というものが、いかに一方的で恣意的であって、権力側(教授等の上位者)に有利な結論先取のお手盛りであるか。よく分かるエピソードであろう。同時に、臭いものには蓋の隠蔽体質が鮮明である。
この新たな調査の一件が済んだ後に、別件で本部人事課に問い合わせたことがある。その返信メールが調査結果を伝達した二人の事務職員の一人である本部人事課・B副課長(前出)からのものである。
その本文で、原告の名前を「不和」と表記していた。
これに対して原告が、強く抗議している。添付したPDFファイルは、原告からの抗議と別件問い合わせをしたメールであり、二頁目、B副課長より原告宛メールの冒頭に「不和」先生とある。
B副課長は、結果通知の際には、A氏(前出)の横に座り、黙々とメモをとっていただけで、一言も発していない。原告名の表記の誤りがこのように奇妙に連続するのは、官僚の忖度文化の一例である。
大学内パワハラ、アカハラ事件、例えば、ある教室・講座における教授と准教授との対立に伴うハラスメントの事件では、事務部は中立であるから、その提出する証拠(文書や証言)は通常裁判所に信頼される。原告の事件では、原告に不利な証拠として、大量の文書類が事務部から提出された。全大学組織を挙げて、原告1人に対してこの裁判を争っている。大学ぐるみであるとすると、事務部の証拠であっても中立性が疑われる。このメールの件は、このことを良く示すであろう。

大学はハラスメントの巣窟-集団的組織的ハラスメントの場合の調査の無意味
大学という組織はハラスメントの巣窟である。集団的組織的ハラスメントを生じる背景及びその場合の調査が無意味となる理由をまとめる。
大学によって、名称や人的組織の大きさが異なるが、一般に、文系においては「講座」、理系においては「教室」という単位が、大学組織内において最も緊密な人的関係のまとまりを示す。例えば法学系学部であれば、私法講座、公法講座、基礎法・政治学講座等となり、それぞれの専門分野の教員が所属する。
医学部であれば、診療科毎のまとまりがある。山崎豊子の有名な小説『白い巨塔』では国立大学医学部の「第一外科」の教授争いを巡る権謀術数が描かれていた。各診療科が、ただ一人の教授に対して、准教授、講師、助教・助手のヒエラルキー型組織を構成している。大学病院の教授回診では、教授を先頭に、准教授以下多人数の医師を引き連れて狭い廊下を歩いて行く有様を見たことがあるかもしれない。よく知られているように、所属医師の人事権や、人脈という意味における系列病院への就職斡旋の事実上の権限集約により、教授の権力が絶大である。
他の理系教室や文系講座では、このような意味での絶対的な教授の権力というものはない。しかし、中講座や大講座と呼ばれる文系講座では、一般には、少数の教授に対して、相対的に多数の准教授以下が所属し、研究業績が優れている又は性格が強い、政治力のある教授に、実質的な権力が集中しやすい。助教、講師、准教授、教授の位階を昇任していくことで、権威及び給料が昂進する。そして学部長等の管理職になるためには教授であることが前提とされる。早くから教授に昇任して準備できるもののみが管理職になれる。
この人事権を実質的に握るのが講座のボスたる教授なのである。
講座の構成員はこのボス教授を中心として人的なまとまり(派閥)を作り、そのほぼ言いなりとなる。このような講座が束ねられて学部を構成する。各講座のボス教授達は仲が良く、その結果、学部運営の実権を掌握する。もっともボス教授間で仲が悪いと、その所属講座に所属する教員の全てが互いに険悪な関係となる。その場合は、講座間の合従連衡による駆け引きが通常の決定方法となる。
最近の法制上、国立大学の各学部運営についても形式的には学長が行うものであるが、実質的には従来通り教授会ないし学部執行部に委ねられることが多い。国立大学では、教授会決定は構成員による多数決による。人事については、構成員である教員らの関心も高く、もめる場合もあるが、他講座の「内政」不干渉が通常である。講座のボスら及びこれらと親しい有力教授らには根回しが済んでいる。斯くて学部の重要事項はこれら教授らが話し合いで決めることになる。その他の教員らは余程のことがない限り、上層部の決定したことに、異論を唱えることがない。これが文系学部の組織的統制のあり方なのである。
講座のボス教授に睨まれることで、やがて学部全体に及ぶ集団的ハラスメントに発展する場合があるわけである。。
更に、各学部の学部長及び管理職は相互に人的関係を築き「親しい間柄」となる。そしてこれら各学部の学部長その他管理職の中から、学長、及び大学の理事や副学長などの役付きが専任されるのが通常である。
各学部の問題について、他学部が干渉しない、内政不干渉が基本的態度である。そして、大学全体の問題にせよ、日本的な、「あの人がいうのだから間違いない」・「あの人の言うことは聞いて挙げよう」型の人的関係に基づく決定方法が採られる。最高の学問の府たる大学なのだから、合理的にものを考えているだろうなどというのは、お門違いも甚だしい。
調査申立て当時の原告所属学部には、学部長を一年間、その後労務担当副学長を努めた要職経験者(湯浅氏)がいた。この人物を中心として、学部長や関係する有力教授らが、学長や大学内部組織の一つである対策委員会(その委員長が理事兼副学長である)に働きかけて、自らにとって好都合な結論のために根回ししていたとしても不思議はない。
「調査申立てなど完膚なきまでに葬り去れば良い。被害側はそれで意欲を消失するだろうから、それでことを納める。後は任せておいてくれ」、と言われればそれまでなのである。よほど明白な証拠がなければならない。あるいは、被害者が外部の市民団体を引き込み、マスコミが騒ぎ出す必要がある。
愛媛大学においては、対策委員会の役割が巧妙に仕組まれている。ここで、加害側、被害側の、証拠その他の力関係を図りつつ、醜聞を外部に出さないで済むなら出さないという処理が可能なのである。もうどうにも仕方が無いという案件は、加害教員の処分含みで調査委員会に送れば良い。ここがいわばバッファの役割を担う。
憲法上保障された大学の自治がある。 結局、大学の自治は、教授会の自治であり、教授会の自治は、実は講座の自治だったのである。
一旦、何かの偶然であっても、講座のボス教授や学部有力教授層の反感を買うと、講座所属教員の全て、学部所属教員の全てを敵に回すことになりかねない。教員ら相互の人間関係と学内政治により、ハラスメントの全体性と継続生が生じる。
大学教員となる者は学者である。偏固者、偏屈、あるいはコミュニケーションが苦手でも、研究能力があればやっていける。一般の公務員や会社員なら、平机の並んだ「島」の並列する執務室で大勢が顔を合わせながら仕事をしている。互いの協力が必須な職場であろう。以前、原告が勤務していた市役所でも、誰かが困っていると、優しく声を掛けて、手助けしてくれる人が必ず現れた。大学では、文系は特に、教育、研究の業務は自己完結的に行うことができる。その限りでは互いの協力は不要なのである。個別の研究室を与えられ、各人が一国一城の主となる。各々の独立心と自尊心のみが研究を進める上での支えとなる。
教員組織と事務部は、互いに協力し合うと同時に、対立する利益集団でもある。事務部は、各係毎、各課毎に独立した縦割り行政を行う官僚組織である。教員組織と事務部の間も、基本的に相互に内政不干渉であって、それぞれの決定事項につき不可侵と言っても良い。学部においては、形式的には学部長が教員組織と事務部を統括するが、実質的には事務長が事務部を統括し、この間の協力が行われる。事務職員は有力な教員の言うことを聞く傾向がある。
教員は、講座のようなグループを形成して、その一員として行動することで、組織全体の中で、かろうじて自己保全を図ることができる。仲良くなるのも、喧嘩するのも、講座単位で行動するのである。
原告は、採用時の噂によって、当初より疎外され、講座の一員として迎えられたことがない。そうすると、群れと対峙する一匹狼のようなものである。一旦、「潰し」の対象となると、どうにも救われない。もともと党派的な行動様式がどうにも苦手であってみれば、致し方ないのかもしれない。
今一度、まとめてみると、第一に、有力教授らの、人事に対する影響力を通じた、学部教員に対する支配的権力が存在し、第二に、集団心理によって惹起される自分も対象にならないかという恐れや、下位の者が上位者の顔色を伺い、乗り遅れることで有力者に睨まれる心配が惹起される。
確かに、人それぞれ温度差が有り得る。しかし、本来ならそのような卑劣な行為を行う人格ではない者であっても、日本的人間関係の中で、巻き込まれてしまう場合がある。郷に入れば郷に従えである。ハラスメントが集団の全体に及び、また長期間に渉って、構成員が入れ替わっても受け継がれていく。

大学の自治は治外法権?
この事件では、大学の自治が治外法権を意味してしまった。 判決の頁参照。
判決の頁参照。
憲法上保障される大学の自治により、警察が犯罪事実を関知しても、大学への通知及びその同意がないと、大学構内には立ち入ることができない。平成二三年頃、既に時効を迎えていたが、この事件に関して相談した警察官によると、例の写真事件の態様から、所轄の警察がその当時、事件に気づいていた。そうだとしても、大学の自治の故に、面倒を避けてしまった初動の誤りがあったとされた。
「こういう事件(わいせつ物陳列)の類いは現行犯逮捕が基本だ。情報提供があったら現場に踏み込む。そこで証拠を押収する必要がある。大学に通知している間に、逃げられたら終わりだ。裸の写真といっても、所詮、被害者は男だし、むしろ騒がない方が良いかもしれない。こういう事件は、被害者が気づいていなければ、それで良いし、構わないだろう」と思われたのだった。
原告に対するそれは、要するに、前半は嫉妬とやっかみから始まり、所属学科教員らが特定の技術職員や宗教団体の一部の信徒らをその目的に使った結果、後半では、そのことが理由で彼らに使われることとなった。職員らを「使う」というのは、動機を与えた上で、その行動を利用する意図を有する場合を含む。無提携の提携と言えようか。多くの場合に、沈黙という方法が採られる。これが、それほど非常識なこと、通常では理解不能なことが行われた理由である。
緊急避難というのは、殺人など重大な犯罪を被る急迫の危険のある場合に、その被害者を救うために、犯人でも被害者でもない第三者が違法な行為を行うことをいう。それ自体、犯罪を構成する行為でも、違法性を免れる=犯罪とならないのである。筆者に対して、大阪の実家に居住するように誘導した、当時の教授が自分の行為を「緊急避難」と呼んだ。筆者に対する睡眠妨害や写真等の展示が犯罪であるとすると、犯人である教職員の犯罪行為から、被害者である筆者を逃避させる自らの行為が、被害者に就業規則の違反をさせるという本来は違法の行為であっても、違法を免れるというほどの意味であろう。
犯罪行為を目撃したとすれば、一般市民であっても通報義務が存在する。まして、大学で法を教育、研究する大学教員である。一層重い義務があったというべきである。少なくとも、被害者が通報できるように、そして刑事事件化させるべく被害者本人に事情を伝えるべきである。これをしないで、すなわち犯人らを庇い、被害者の不利益において退避させ、刑事事件にならないように穏便に事を収めるという方法は、大学教員ないし大学として、幼稚極まりない。
原告は、熟睡中の写真撮影について、十分の認識を有していたとは言えない。まして、その写真を不特定多数に閲覧させていたことについてほとんど事実関係を知らなかった。睡眠妨害が継続しており、肉体的苦痛を伴い、精神的にも憔悴していた。しかし、加害グループを全く特定できていなかったのである。
本人に事情を通知するどころか、住居侵入や睡眠妨害について警察相談を重ねていた原告に対して、大学側が精神異常として非難した。その妄想とでもいうことが、ハラスメントを覆い隠すための、最も一般的で巧妙な口実である。この原告に対しては、大学側が一体となってスキャンダルを隠した。
要するに、この原告(サイトの筆者)に、判決のいう「出勤」が無かったとされる点について、大学に大きな責任があると言わざるを得ない。当時の大学構内および大学宿舎内において、筆者に身体上の危険を感じさせるような状況があり、大学側がその状況を知りつつ放置し、加害者らの行為を放任したことが、原告が適切に勤務を遂行することを不可能とした原因だからである。大学の方に、使用者が労働を提供することのできる環境を整えるべき、安全配慮義務違反があったのである。
その後もその状況を放置したまま、大学の方が原告の「出勤」を問題にはできないはずである。
大学の有力者間の馴れ合いと、官僚の事なかれ主義が、大学内の無法者によるある種政治的な弾圧に伴う人権侵害を、大学の自治の名の下で許容したのである。