
法政大学社会学部メディア社会学科 津田研究室
 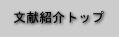    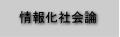 
メディア論
オング・ウォルター、桜井直文ほか訳(1982=1991)『声の文化と文字の文化』
藤原書店
我々は書くことによってもたらされた精神的な変化を所与のものとしてしまっているがために、声の文化(「書くこと」が人々に内面化していない文化)について理解することが出来ないのではないか。本書はこうした問題意識から、声の文化の特徴、文字の文化の特徴について論じ、さらには、文字の文化の特徴をさらに推し進めた印刷について、電子メディアなどを通した二次的な声の文化について考察してゆきます。一次的な声の文化にあっては、伝承などは何度も反復されることによって記憶されてゆき、それを書き換えることは困難であるがゆえに、声の文化における精神は保守的になるが、文字の文化にあっては、記憶という役割を文字が引き受けてくれるがゆえに、精神は新たな思索に向かうことが可能になる、という指摘などはなるほど、と思いました。こうしたオングの指摘に対しては技術決定論だ、という批判がありますが(『ノイマンの夢・近代の欲望』など)、それだけでは片づけられない説得力があるように思いました。なお、非常にわかりやすくて、いい訳です。(1998年)
小林修一(1997)『メディア人間のトポロジー』 北樹出版
サブタイトルが「身体・メディア・空間の社会史」ということなのですが、非常に哲学的なメディア論です。フーコーはともかく、ハイデガーやデリダなど、そちらに疎い私にはつらいものがあったりするわけですが、全く理解不能ということはなく、なんとなくですが、読むことが出来ました。しかも、けっこう面白かったりします。特に最初の部分で挫折しそうになったのですが、それを乗り切ると、後はそんなにつらくありませんでした。というより、楽しめました。内容は、前近代と近代における身体・メディア・空間のあり方の違いについてです。うーん、こう書くと実につまらなさそうな本なのですが、決してそんなことはありません。特に、ポスト・モダン的なメディア論に興味がある人は必読でしょう。 (1998年)
佐藤卓巳(1992)『大衆宣伝の神話』 弘文堂
本書は、「19世紀ドイツの最大のアジテーター」と言われたフェルディナント・ラサールに始まるドイツ社会民主党(SPD)の歴史を追いながら、SPDのメディア政策がいかに大衆の支持を獲得し、そしてナチスの宣伝によってそれを奪われてゆくのかを分析しています。つまりは、SPDが大衆を啓蒙しようとするインテリ集団になってゆき、大衆から遊離してゆくのに対し、ナチスが大衆を大衆として、そのまま受け止めたことに原因の一端があるということでしょうか。なんとなく、小説のように読めてしまう、とても面白い本です。ドイツやSPDについてほとんど何も知らない私にも興味深く読めました。ナショナリズムやファシズムを生み出すのに、何が必要であるかを考えるのに参考となるのではないでしょうか。当時の雑誌・新聞のイラストも数多く紹介されています。 (1997年)
佐藤卓己(1998)『現代メディア史』 岩波書店
最近盛んに論じられている国民化と総力戦という観点から、近現代におけるメディアの役割について考察したテキスト。また、アメリカ、日本、イギリス、ドイツのそれぞれの国でのメディア状況も比較されており、メディア史の教科書としては非常に良く出来た本だと思います。著者の佐藤さんが専門としているのがドイツであることから、国によって分析のレベルに違いがあるようにも思えるのですが、こうした包括的な試みをするということ自体を私としては評価したいと思います。また、インターネットに代表される近年のメディア状況についても批判的な考察が展開されており、そちらも興味深く読むことが出来ました。また、巻末のブック・ガイドも親切で、これからメディアについて学びたいと考えている人にオススメ出来る一冊です。 (1999年)
佐藤卓己(2004)『言論統制』 中公新書
本書は、戦中の言論統制において作家や編集者に「弾圧」を加えたとして、戦後、多くの人びとに糾弾されるに至った鈴木庫三という人物を、全く新たな角度から描きだしています。言論統制に加担した無学で粗野な人物というイメージとは異なり、鈴木は苦学して日大を主席で卒業、帝大でもかなりの業績を上げたというインテリで、その真面目さゆえに、周囲から煙たがられることになったということが論じられています。また、戦後において、鈴木の悪辣なイメージが作り上げられる過程で、文化人たちがいかに嘘をついていたかも明らかにされています。
全体的に見れば、これまでのイメージを覆すという意図から、鈴木に対しては好意的な角度から描かれており、他方、鈴木と対立した出版社や海軍の人びとには厳しい評価が加えられているように思います。もちろん、佐藤さんがこれによって戦前の言論統制を正当化しようとしたり、通俗的「戦後民主主義批判」に加担したりといったことは全くありません。この著作に何らかの批判的意図があるとすれば、おそらくそれは鈴木という人物を生み出した時代的背景(貧富の格差)を全く無視して、それを<加害者としての軍>と<被害者としての作家や編集者>という安易な構図に安住していたマスコミ史、言論史に向けられているということになるでしょう。
ただ、全体を読み終えて思ったことは、たとえ鈴木が貧困のなかから苦学して身を立てた人物で、清廉かつ実直であったとしても、僕はやはりこの鈴木庫三という人物を好きにはなれないだろうな、ということです。橋川文三の『昭和ナショナリズムの諸相』などでも明らかにされているように、「超国家主義」が台頭する背景には、多くの不遇な人びとの国家体制に対する不満があり、現在からすれば意外なほどにそこには社会主義的発想との重なりがあったようです。鈴木庫三の思想にも、社会主義的発想が色濃く反映されており、その最大の敵意はむしろ自由主義的な文化人に向けられていると言ってよいでしょう。
戦前の日本における貧富の差はきわめて大きく、貧困層の人びとがどのような生活環境に置かれていたのかは、やや時期は遡りますが紀田順一郎『東京の下層社会』で垣間見ることができます。そうした社会状況のなか、貧困に苦しむ人びとを尻目に享楽に耽っていた自由主義的文化人に対し、鈴木が大きな憤りを覚えていたことは理解できます。鈴木が行った「言論統制」は、鈴木が「平等」を追求していく上での副産物として生じてきたものであり、仮に僕が彼と同時代に生きていたなら、むしろ鈴木に共感する立場にあった可能性は高いように思います。
しかし、後知恵的発想で、また鈴木が言論統制を始めた張本人でもないことを承知しつつ言えば、やはり鈴木的な「言論統制」が社会にある種の息苦しさを与え、山本七平の言葉で言えば「空気の支配」を後押しすることに貢献してしまったのことは否定できないように思います。そして、それが最終的には、政府や軍の方針に人びとが疑問をもちつつも、それを言い出せない状況を生み出し、より早い段階での敗戦を不可能にしてしまったのではないでしょうか。
さらに言えば、この鈴木庫三という人物はとても勤勉で立派な人でした。だから、酒宴で鈴木の機嫌を取ろうとする「退廃した」自由主義的文化人を嫌悪したというのも理解できます。けれども、人がみな鈴木的モラルに忠実に生きることができるわけではありません。そうした厳格なモラルに沿って社会を営もうとするとき、そのモラルによって表面的に抑圧された欲望や退廃は急速に社会を蝕んでいくことになります。戦前派によって語られる美化された過去とは異なり、実際には戦中の体制は「モラルの焦土」とも言うべき状況にあったことは、小熊英二さんの『民主と愛国』によって語られています。
最後に、『言論統制』そのものから話を大きく逸脱させてしまいますが、戦前的な「言論統制」にはそうした不可避の限界が存在し、また、貧者を放置する弱肉強食的自由主義にも問題があったとすれば、言論の自由をかなりの程度まで保証し、また、貧富の格差を縮小させることに成功した戦後民主主義体制というのは、それなりに評価されてしかるべきではないか、などとも思ったりするわけです。(2004年10月)
佐藤卓己(2005)『八月十五日の神話』ちくま新書
日本政府がポツダム宣言を受託した8月14日でも、戦艦ミズーリ号上で正式に降伏文書に調印した9月2日でもなく、なぜ日本の終戦記念日は8月15日なのか。本書はこうした問題意識から、メディアによって「終戦」にまつわる集合的記憶がいかに形作られてきたのかを分析しています。集合的記憶とは、個々人ではなく、集団によって共有される記憶のことを指しますが、当然、それは自然に出来上がってくるものでも、「ありのままの歴史」を記録していくわけでもありません。そこには様々な取捨選択があり、記憶の中身自体も変化していきます。たとえば、9月2日の降伏については、以下のような指摘が行われています(pp.117-118)。
「今や、『日本国民反省の日』(9月2日のこと:引用者)は消えて、『八・一五終戦』の記憶が前面開花を遂げた。つまり、『戦争の記憶』の重心は『反省』から『平和』へと移動した。それは『敗戦=占領』の記憶を『終戦=平和』に置き換えようとする心性において進められたといえよう。」
すなわち、集合的記憶とは、複雑な力学のなかで形成・再生産されていくものなのであり、その過程なかでもメディアは決定的に重要な役割を果たすことになります。このような集合的記憶についての研究がメディア論の領域では盛んに行われるようになっていますが、本書はそれを代表する一冊と言えるでしょう。(2007年11月)
シルバーストーン・ロジャー、吉見俊哉ほか訳(1999=2003)『なぜメディア研究か』
せりか書房
イギリスを代表するメディア研究者であるロジャー・シルバーストーンの手による、メディア研究の概説書。ただ、シルバーストーンの書く英語はなかなかにトリッキーで、本書でも訳者の苦労の跡がうかがえます。そんなわけで、一からメディア研究をはじめようという人には、本書はお勧めできません(と、あえて断言してみる)。が、ある程度の知識がある方であれば、メディア研究がいかに幅広い領域に関連しており、いかに豊かな可能性を有しているのかを本書を通じて理解できるのではないでしょうか。逆にいえば、すぐにタコツボ化して全体像を見失いがちな研究活動のなかで、よい刺激となる一冊であるように思います。(2004年2月)
中野収(1997)『メディア人間』 勁草書房
まさに、ポスト・モダン的メディア論。エッセイ的な内容で、厳密に学術的な論考とは言い難いのですが、現代を考えるためのエッセンスが詰まっている本です。メディア社会、インターネット、グローバリゼーションと、最もタイムリーなテーマが並びます。特に、あらゆるものをメディアとし、自我とメディアの融合を図る「メディア人間」の登場という本書のメイン・テーマは、新たな人間類型のパラダイムとして注目しうるでしょう。しかし、私個人としては、ポスト・モダン的な論考に特徴的な、権力関係への視点の欠如、技術決定論的理論展開が気になりました。しかし、全体として、読みやすく、かつ、面白い本だと言えるでしょう。 (1997年)
ピカート・マックス、佐野利勝訳(1946=1965)『われわれ自身のなかのヒトラー』
みすず書房
ヒトラーの登場を可能にしたものは何か?ピカートは、ラジオが生み出す断片化された連続性なき世界(ラジオでは何の連続性もなく次々と違う番組が流れる)においてのみヒトラーは登場可能だったのだと論じ、現代世界における連続性の喪失について警鐘を鳴らしています。ヒトラーや反ユダヤ主義の本質を鋭く突き、ナチズムが決してドイツ固有の問題ではないことを改めて痛感させる書と言えるでしょう。が、それはちょっと言い過ぎだろうと思える箇所も多く、ドイツ人が読むとちょっと怒るかも、という気がしないでもないです。なお、最近、復刻されたので大きな書店に行けば手に入るでしょう。 (1999年)
ブーアスティン・ダニエル、星野郁美ほか訳(1962=1964)『幻影の時代』 東京創元社
メディア論の名著中の名著と言える本です。我々がニュースに対する過剰な期待(刺激に満ちた報道)を求めるようになったことから生じた「擬似イベント」を手がかりに、現代社会の本質を突き詰めてゆきます。この本がアメリカで出版されたのは、「黄金の50年代」が終わり、激動の時代へと突入してゆく前夜、1962年のことです。大衆消費社会がまさに現実のものとして立ち上がってくるなか、ブーアスティンは、その時代がまさしく幻影であって、やがては崩壊してゆくものであることを見抜いていたのかもしれません。その意味で、ちょっと(かなり?)説教臭い部分があったりもするわけですが、出版から30年以上たった今でもこの本はまったく斬新さを失っていないと言えるでしょう。 (1997年)
吉田直哉(2003)『映像とは何だろうか』 岩波新書
テレビの草創期から番組制作に携わってきた元NHKのディレクターの著者が、様々なエピソードをもとに映像のもつ特質について論じた好著。あまり学術的だとは言いがたいのですが、紹介されているエピソードが極めて面白いのが印象的です。今日のようにテレビ番組の制作技術が発達していく過程のなかで、どのような工夫や失敗があったのかが興味深く語られています。今年はマスコミで良く言われるように<テレビ50年>であるわけですが、同時に視聴率操作など様々な問題が浮上した年でもあります。ここでひとつ、本書を読み、草創期のテレビを振り返ることで、今後のテレビのあるべき姿を考えるというのも悪くないのではないか、と思います。(2003年12月)
吉見俊哉(1994)『メディア時代の文化社会学』 新曜社
『都市のドラマトゥルギー』、『声の資本主義』、『リアリティ・トランジット』などカッコイイ名前の著書が多い吉見さんにしては普通の名前の著書です。その内容はと言えば、電子メディアや活字メディアなどの歴史的考察やメディア・イベント、リアリティの変遷など現在のメディア論を語る際に重要となるトピックスが満載されています。様々な学説が紹介されているので、メディア学の現在を知るには丁度良いのではないでしょうか。ただ、私個人の感想を言えば、章ごとのつながりがあまり良くないと思いました。一貫性を持たせてあることが序章でも強調されているのですが、章ごとの議論があまりつながっていないと思ったのは、私の読み込みが足りないからでしょうか…? (1997年)
吉見俊哉(1995)『「声」の資本主義』 講談社選書メチエ
電子メディアの先駆けであるラジオや電話が、どのようにして生まれ、どのようにして社会に受容されていったのかを社会史的に本書は考察しています。実は、ラジオも電話も現在使われているような形で初めから使われていたわけではありませんでした。ラジオには相互にコミュニケーションを図るためのメディアとして、電話には演劇や音楽を聞くためのメディアとして、発達する可能性もあったのです。このようにして考えると、結局、メディアをどう使うかを決めるのは社会の側であって、メディアはそこから社会に影響を及ぼしてゆくという構図が見えてくる気がしますね。 (1997年)
吉見俊哉(1996)『リアリティ・トランジット』 紀伊国屋書店
情報消費社会とは何か?本書では、天皇制、ディズニーランド、オウム事件などの分析を通じて、情報化によって我々を取り巻くリアリティがどのように変化しつつあるのかを論じています。私個人としては、ディズニーランドの分析が非常に興味深く、ディズニーランドに行くのに新たな楽しみ(?)が増えたような気がします。ただ、印象論的な分析が多く、実証的なデータに欠ける側面があるのは否めないところです。ちなみに、この本で一番理解しづらいのがなぜか序章で、序章より先に後の部分を全部読んでから序章を読むと、良く分かります。良い意味でも悪い意味でも、最もトレンディ(死語)なメディア論と言えるのが本書ではないでしょうか。 (1997年)
|
