
法政大学社会学部メディア社会学科 津田研究室
 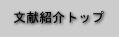    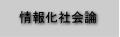 
インターネット論
梅田望夫(2006)『ウェブ進化論』ちくま新書
「Web2.0」、「ロングテール」、「総表現社会」といったキーワードによって、急速に変貌を遂げつつあるインターネットの相貌を捉えた著作。かなりヒットした本なので、今更こんなところで紹介するまでもないわけですが、なかなかに面白い好著だと言えます。グーグルによる「知の再編成」や、アマゾンによる「ロングテール」マーケットの開拓、ブログ等による一方向的なコミュニケーションから双方向的コミュニケーションへの転換などが紹介されています。
そして、本書全体を貫いているのは、インターネットに対する「オプティミズム」であり、インターネットを支える若い層に対する期待感だと言えるでしょう。そうした著者の姿勢は、以下の文章に集約されています(本書、p.206-207)。
「ネットが悪や汚濁や危険に満ちた世界だからという理由でネットを忌避し、不特定多数の参加イコール衆愚だと考えて思考停止に陥ると、これから起きる新しい事象を眺める目が曇り、本質を見失うことになる。…不特定多数無限大の良質な部分にテクノロジーを組み合わせることで、その混沌をいい方向に変えていけるはずという思想を、この「力の芽」は内包する。そしてその思想は、特に若い世代の共感をグローバルに集めている。思想の精神的支柱になっているのは、オプティミズムと果敢な行動主義である。」
このような著者の姿勢には、なんとなく1960年代の学生運動的な雰囲気を感じてしまいますね。僕はまあ、もうそれほど若くもないし、インターネットの技術に詳しいわけでもないので、お祭りに乗れない寂しさを味わいつつ、遠くからそれをちらちら眺めるというスタンスしか取れないのですが…。(2006年6月)
荻上チキ(2007)『ウェブ炎上』 ちくま新書
本書はインターネット上でしばしば生じる炎上現象を中心に、インターネットでのコミュニケーションの問題点やその解決策などについて簡潔に論じている著作です。インターネットに関する知識量の多さはさすがで、ネット上でのさまざまな「事件」に関する記述は楽しく読むことができます。
本書の中心的なテーマとなっているのが、「カスケード」という問題です。要するに、人は自分にとって好ましい意見を聞きたがる性質を有しており、そのために類似した意見を持つ人たち同士で固まりがちになる。そのため、その同質的な集団の内部で意見がどんどんと過激化し、他の集団との妥協や合意が難しくなる、ということです。とりわけ注目されるのは、そうしたカスケードを考えるさいに、AかBかという立ち位置のカスケードだけではなく、問題設定の次元においてすでにカスケードが生じているのではないか、という指摘です。
この指摘自体は面白いのですが、ただ惜しむらくは、この著作全体で「カスケード」という言葉をやや濫用しすぎているような感が否めません。たとえば、特定の問題が人びとによってあまり取り上げられないことを著者は「潜在的カスケード」と呼び、大きな注目を集める「顕在的カスケード」と対比させていますが、「潜在的カスケード」は「カスケード」(滝、連鎖的反応、活性化、etc.)という語義から離れすぎてしまっているのではないでしょうか。その結果、この「カスケード」という言葉が頻出する第三章はややすっきりしない内容になっているように思われます。
あと、重箱の隅をつつくようなのですが、マス・コミュニケーション研究者からすると、pp.133-134の記述はいただけません。マスコミは人びとの政治的意見に直接影響を与えるのではなく、なにが政治的争点であるのかを認識させるという点において影響力を発揮するという指摘のあとに、これは「コミュニケーションの二段の流れ」と呼ばれている理論について触れたものだとされています。
しかし、政治的争点に注目するのはマス・コミュニケーションの効果研究で言えば「アジェンダ(議題)設定」と呼ばれるモデルであり、「コミュニケーションの二段階の流れ」とは別の理論的系譜(限定効果モデル)に属する発想です。限定効果モデルとは、マス・コミュニケーションの影響力はさまざまな要因(選択的接触・知覚・記憶、オピニオン・リーダーetc.)によって抑制されるため、マス・コミュニケーションの影響力は小さいとする1940年代から1960年代ぐらいまでポピュラーだったモデルです。それに対し、1960年代以降に注目を集めるようになったアジェンダ設定モデルでは、マス・メディアは政治的争点が決定されるさいに大きな影響力を行使しうるとされ、マス・コミュニケーションの影響力はそれなりに大きいと考えられています。要するに、本書では限定効果モデルとアジェンダ設定モデルとが混同して語られてしまっているのです。
…というような、ややペダンチックな指摘はさておき、本書はネットでのさまざまな現象を既存の社会理論のなかに位置づけようと試みている点に好感がもてますし、ネットに関する過度の楽観論・悲観論を乗り越えようとする点において評価できます。事例も豊富で、読んでいてなかなか楽しい一冊ではないでしょうか。(2007年10月)
喜多千草(2003)『インターネットの思想史』青土社
インターネット開発史において注目を集めているJ.C.R.リックライダーの思想を詳細に検討している著作です。「インターネットはもともと、対核ミサイル用の軍事ネットワークが発展して生まれた」との通説を批判し、インターネットの起源には複数の思想的な流れが存在しており、とりわけ人間の思考をネットワーク化されたコンピュータによって支援するという発想が強く作用していたことを論じています。関係者の思想のかなり細かい部分にまで言及しているため、正直、それほど刺激的な著作というわけではありませんでしたが、それでもインターネットの歴史の複数性を示してくれている点で重要な著作だと言えるでしょう。
佐々木敏尚(2006)『グーグル Google』文春新書
『ウェブ進化論』からやや遅れて出版されたグーグル本第2弾といったところでしょうか。『ウェブ進化論』がインターネット・オプティミズムを前面に出した著作だとすれば、こちらはもうちょっと後ろに構えてインターネットを論じた著作だと言えるかもしれません。グーグルがどのように新聞や雑誌のビジネスモデルを破壊しつつあるのか、ソフトウェア産業の脅威となりつつあるのかといった話から、グーグルのビジネスモデルの解説、さらにはグーグル的なサービスが生じさせかねない管理社会化の危険性などが論じられています。著者が元新聞記者ということで、話の運び方は『ウェブ進化論』よりも上だという気もします。僕はかなり楽しく読むことができました。
「グーグル八分」など、インターネットの進化がもたらしかねない「負」の側面にも言及している点で、バランスの取れた著作だと言うことができるでしょう。(2006年6月)
野村一夫(2003)『インフォアーツ論』 洋泉社新書
日本でインターネットが本格的に普及し始めた1990年代後半、社会学系サイトとして圧倒的な存在感を放っていたのがソキウスです。そのソキウスの運営者である野村一夫さんがインターネットの現状やこれからのあり方を「インフォテック」や「インフォアーツ」という用語で論じているのが本書です。第1〜2章では自発的な情報提供や討議といった市民主義的なモラルによって支えられていたコンピュータ・ネットワークの世界が、インターネットの大衆化に伴ってどのように変化していったのかが論じられています。そして、第3〜6章では現在のコンピュータ教育の問題点が分析され、たとえば次のような指摘が行われています(p.91)。
「インターネットはたしかに情報技術であるが、そこには初期の開発場面から市民主義的な文化が付随しており、むしろインターネットが実現するオープンな市民的コミュニティこそが画期的だったはずなのに、(政府が主導する『IT革命』においては:引用者)いつのまにか手段が『情報』しかも『技術』にすり替えられている。ここには一方でインターネット的な文化世界の魅力を喧伝しながら、内実においてはその文化的側面に立ち入らず、『コミュニケーションの生々しさ』を脱色しておこうという意図が感じられる。」
こうした問題意識から筆者は、今後のインターネット教育には技術的な知識である「インフォテック」の伝達ばかりでなく、市民主義的な「インフォアーツ」の養成こそが必要なのだと主張しています。
この本が出版されたのは3年以上前なので、インターネットの状況もそれなりに変化していますが、野村さんが指摘したようなネット上での流言の拡大沈や黙の螺旋現象の発生などといった問題は依然として大きな影を落としているように思います。正直、僕は社会の変革を個々人のモラルに委ねる話はあまり好きではないのですが、教育をする側の人間としてはなかなか教えられることが多かった一冊でした。(2006年7月)
松岡美樹(2005)『ニッポンの挑戦 インターネットの夜明け』RBB PRESS
日本のインターネット黎明期における村井純氏らの活躍を描いたドキュメンタリー。インターネット版「プロジェクトX」といったところでしょうか。実際、この本の映像版がインターネットのストリーミングで公開されていました(現在はDVDで販売中)。郵政省の規制やインターネットの潜在力に無理解な周囲との軋轢のなかで、彼らがいかに工夫を重ねて難関を乗り越えてきたのかが描き出されています。
なお、この本の「プロローグ」では、「web2.0」や「ロングテール」といった発想が一歩引いた観点から論じられており、、「インターネットが全てを変える」という発想とは一線を画している点が興味深いですね。(2006年6月)
|

