
法政大学社会学部メディア社会学科 津田研究室
 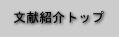    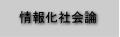 
マス・コミュニケーション論
阿部潔(1998)『公共圏とコミュニケーション』 ミネルヴァ書房
批判的なコミュニケーション研究の二大潮流であるフランクフルト学派とカルチュラル・スタディーズ学派。本書はこの二大潮流の統合における「公共圏」概念の有効性を論じています。フランクフルト学派とカルチュラル・スタディーズ学派がどのように生まれ、発展してきたのかが簡潔にまとめられており、非常に勉強になりました。また、ハーバーマスの「公共圏」概念にも詳細な分析と問題点のあぶり出しが行われており、ハーバーマスをほとんど知らない私にも参考になりました。これまで、伝え聞くところのハーバーマスの議論にはなんとなく胡散臭さを感じてしまっていたのですが、その胡散臭さの原因がわかったような気がしました。阿部さんはそうしたハーバーマスの問題点を踏まえた上で議論を展開しており、その建設的な姿勢には好感が持てます。ただ、少々、引用が多すぎて議論がくどくなってしまっている点が気になりました。(1998年)
大石裕(1998)『コミュニケーション研究』
慶應義塾大学出版会
副題の「社会のなかのメディア」という言葉が示すとおり、本書は社会の中にあってメディアがいかなる役割を果たしてきたのかをさまざまな角度から分析している本です。基本的には教科書なので、これまでのマス・メディア研究の流れを辿ることも出来ます。けれども、本書の主眼は、既存のマス・メディア研究の大半がマス・メディアの社会への効果に関する研究に限定されてきたのに対して、社会全体からコミュニケーション過程を捉え直そうというところにあると言えます。従来のマス・メディア研究の行き詰まり(言い換えればつまらなさ)を打破し、新たな研究領域を開拓しようとする野心的な著作と言えるでしょう。(1998年)
(追記)2006年4月に本書の第二版が出版されました。第二版では、第一版での理論モデルの解説が加筆・修正されているほか、情報化に関する記述が大幅に増えています。本書を紐解いて改めて感じたことは、この本の記述スタイルは、様々な理論やモデルのエッセンスを抽出し、それらを精緻につなぎ合わせていくというものです。もちろん、教科書の場合、多かれ少なかれそうしたスタイルをとるわけですが、本書の場合、その極限とも言いうるスタイルで、余分な贅肉が見事に削ぎ落とされています。そのため、人によっては読みにくいという感想を抱くかもしれませんが、何冊かこの分野の本を読み、頭のなかがごちゃごちゃになっている人が、頭のなかを整理するうえではうってつけの著作であると言えるでしょう。(2006年8月)
大石裕(1998)『政治コミュニケーション』
勁草書房
政治現象の分析において、マス・メディアに代表されるコミュニケーションはいかなる役割を果しうるのか。この古くから研究されてきた問いに、本書はいわゆるマス・メディアの効果研究とは大きく異なる視点からぶつかっています。ダールやバクラック/バラッツ、ルークスなどの権力論を足掛かりに、これまでのマス・メディアの効果研究を整理し直すと共に、「文化としてのコミュニケーション」という観点から人々の政治認識が形作られてゆく過程を実証分析を交えながら明らかにしてゆきます。また、最近のカルチュラル・スタディーズの影響をうけたマス・メディア研究は、大体にしてフランスやイギリスにおける研究を土台としているのですが、本書は近年では珍しくアメリカ政治学をその土台としており、その意味でも新鮮だと言えるのではないでしょうか。(1998年)
大石裕・岩田温・藤田真文(2000)『現代ニュース論』
有斐閣アルマ
体験談や理念に基づくジャーナリズム論が溢れるなか、日本では学術的なニュース研究があまり行なわれていないのが現状です。その意味で、本書は、日本におけるニュース研究の本格的な始動を告げる一冊と言うことができるかもしれません(ちょっとオーバーかな…)。ともあれ、欧米のニュース研究の流れを理解し、学術的なニュース研究がどのようなものでありうるのかを知るのには、格好のテキストと言うことができるでしょう。もちろん、ニュースがどのように生み出されるのかを知ることは、現代の社会を知る上でも不可欠なのであり、それゆえにニュース研究を志す人のみならず、多くの人に読まれるべき本だと思います。(2001年9月)
大石裕(2005)『ジャーナリズムとメディア言説』 勁草書房
ジャーナリストの回顧や倫理的な観点から論じられることの多い「ジャーナリズム論」と、社会学的な「マス・コミュニケーション論」とを架橋するべく、社会理論や政治理論の観点からジャーナリズムを論じているのがこの著作です。そうした著者の姿勢は、たとえば「ジャーナリズム活動の所産としてのニュースをテクストないしは言説ととらえ、それを分析することによって、社会システムのイデオロギーとジャーナリストやジャーナリズム組織の活動との関連の解明をめざす」(p.94)という視点に典型的に示されています。
このような視点から本書では、「客観報道」といったジャーナリズム論での重要な論点に加えて、アジェンダ設定やメディア・イベントといったマス・コミュニケーション論ではおなじみの視座からジャーナリズムを捉え直しています。さらに、集合的記憶や物語などの近年において注目されている概念もふんだんに活用されています。
とはいえ、この著作の最も重要な特徴は、その議論の堅実さにあるのではないかと思います。まるで匍匐前進のようにゆっくりと、しかし着実に論を前に進めていく著者の姿勢には、頭が下がるばかりです。派手さはないぶん勉強になる箇所が多く、今後のジャーナリズム/マス・コミュニケーション研究の基礎をなす重要な一冊になるのではないかと思います。(2006年8月)
金原克範(2001)『<子>のつく名前の女の子は頭がいい』 洋泉社新書
統計学的に見ると、名前の最後に<子>という文字の入る女の子は学校の成績が良い場合が、それ以外の女の子よりも多い―――これはもちろん、<子>という名前を付けたから頭が良くなったわけではありません。著者によれば、<子>という名前を付ける親は、相対的に保守的であり、そのような家庭環境が子供の成績を押し上げる傾向にある、というわけです。そして、そうした良好な家庭環境を作るためには、家庭へのマス・メディアの侵入をできるだけ避ける必要がある、と著者は主張します。言い換えれば、家庭へのマス・メディアの浸透が人々のコミュニケーション・スタイルを変化させてしまい、そのことが情報をうまく入手することができない子供たちを生み出している、というわけです。
子供の名前という新鮮な切り口や、世代間という長期にわたるメディアの影響など、読んでいてかなり楽しい本です。が、問題がないわけではありません。著者は現代の母親を情報に対して受身な「シンデレラ」型と呼びこれを非難する一方、伝統的な日本の母親を情報の発信に力点を置く「ヤマトナデシコ」型と呼び、これを高く評価しています。しかし、どうもこの「ヤマトナデシコ」という類型は過去の分析から導き出されたものというよりは、「シンデレラ」型から逆照射された形で抽出されてきたのではないか、と思われるのです。また、これ以外にも、<子>という名前と成績とは疑似相関なのではないかといった批判がなされていますが、なかなかに面白い本ではあります。(2002年1月)
カラン・ジェームスほか編、児島和人ほか監訳(1991=1995)『マス・メディアと社会』勁草書房
本書は、80年代に大きくパラダイムの転換を遂げたマス・コミュニケーション論の流れを概観しています。とりあえず、教科書的な本なのですが、全くマス・コミュニケーション論に触れたことのない方は手を出さないほうが無難でしょう。ジョン・フィスクのポスト・モダンに関する議論は、私もあまり理解できていません。あと、ジェンダーとメディアに関する章があるのですが、ジェンダー問題に興味がないからといって読み飛ばすには少々、もったいない章です。こういう教科書的な本って、面倒臭がらずに読むと、結構、収穫があったりする気がしますね。私個人に関して言えば、文化帝国主義に興味があるので、それに関する第6章が、議論がよく整理されていて役立ちました。(1997年)
なお、現在の英語版では第3版まで出版されています。(2002年6月)
クラッパー・ジョゼフ、NHK放送学研究室訳(1960=1965)『マス・コミュニケーションの効果』 日本放送出版協会
マス・コミュニケーションの効果研究において、限定効果論が支配的だった時代を代表する一冊。通例、教科書などでは「マス・コミュニケーションの効果は態度を変化させるのではなく補強させる傾向が強い」ということを論じた本として紹介されるわけですが、それだけではなく、それまでのマス・コミュニケーション研究の展開を知る上で大いに参考になる本だということができるでしょう。しかも、現在の研究の萌芽となるような知見がところどころに散見され、研究の発展というものは何もないところから生じるのではなく、やはり積み重ねなのだということを痛感させられます。意外にも、メディア論やカルチュラル・スタディーズの展開につながるような知見も紹介されているようにも思われます。(2000年4月)
サイード・エドワード、浅井信雄・佐藤成文訳(1981=1996)『イスラム報道』みすずライブラリ
マス・メディアに登場する「イスラム」とは、果たしてどれだけ現実のイスラムを表象しているのでしょうか?本書は、フィクションとしての「イスラム」像がどのように生み出され、流布しているのかを分析しています。権力と知が結びついた結果、複雑な現象の原因は全てイスラムへと還元されてしまう、という指摘は、欧米のみならず、日本のマス・メディア(イスラムに関する情報はアメリカを経由して日本へ伝えられる場合が多い)にも当てはまると考えられます。また、こうした異文化に対するメディアの偏向はイスラムに対してのみ見られる訳ではなく、あらゆる異文化に対する報道に見ることが出来ます。その意味で、国際化が叫ばれる今日において、きわめて重要な文献だと言えるでしょう。(1998年)
佐藤毅(1990)『マスコミの受容理論』
法政大学出版局
本書では、マス・コミュニケーションの理論がいかなる展開を経て、今日の研究へと至っているのかが論じられています。特に、日本における研究の展開なども論じられており、これから本格的にマス・コミュニケーション論を勉強しようと思っている人にはとても便利な本だと言えるでしょう。また、近年のカルチュラル・スタディーズの展開へと至る過程もちゃんとおさえられていて、マス・コミュニケーション論の観点からカルチュラル・スタディーズに接近しようと考えている人にはちょうどよい道標になるのではないでしょうか。最新の研究を追いかけることももちろん必要なのですが、そこに至る道筋を知っているのは大切なことです。(1999年)
シーバート・フレッドほか、内川芳美訳(1956=1959)『マス・コミの自由に関する四理論』
マスコミにおける「自由」のあり方を、権威主義理論、自由主義理論、社会的責任理論、ソヴェト共産主義理論の4つの観点から分類し、それぞれについてその特質を抽出した著作です。マスコミ研究における古典の一つであり、言論の自由などに興味がある人ならば必読文献だといえるでしょう。僕としては、なぜかソヴェト共産主義理論の箇所が最も興味深く読めました。たとえば、ソヴェトの新聞があらゆる体制に関する批判を禁じられていたわけではなく、むしろ政府の末端部分に関しては、さかんに批判を行なっていたという点などが面白いと思いましたね。もちろん、社会体制そのものを批判することはできなかったわけですが、ソヴェトの新聞=体制の批判は一切禁止、などというイメージが単純化されたものだったことがわかります(だからといって、ソヴェトの新聞が素晴らしかったなどというつもりは毛頭ないのですが)。
そこから、著者のひとりであるシュラムは「人間が生きている社会の基本的な仮説をも問題にする自由をもっていなければ、いかなる人間も真に自由であるはずはない」(p.237)と述べています。僕も同意見なのですが、実際にはこれは極めて難しい課題であるといえるでしょう。2001年9月のアメリカでのテロは、著者たちが「自由」が存在していると想定しているアメリカですら、社会の根幹を問題にすることが困難になりうるのだということを示してはいないでしょうか。このように現代的なテーマを考えるうえでも参考になると思います。(2002年4月)
桜井哲夫(1994)『TV 魔法のメディア』
ちくま新書
史上最強のメディアと呼ばれるテレビ。本書はテレビとは一体何なのかを、テレビが誕生・普及していくプロセスを追いながら考察しています。同時に、筒井康隆、マクルーハン、ボードリヤール、など様々な人々がいかにテレビを論じてきたを紹介しており、思想界でのテレビの位置づけについて概観することが出来ます。特に面白かったのが、テレビの黎明期から発展期にかけてのテレビ・バッシングに関する議論で、人びとがいかにテレビを恐れてきたかが論じられています。マルチメディアの登場が叫ばれて久しいのですが、まだまだマスコミの中心はテレビであり、現代社会を語る上でもテレビについて知ることは重要だと思われます。(1997年)
高木徹(2002)『戦争広告代理店』講談社
大宅賞、講談社ノンフィクション賞、新潮ドキュメント賞を受賞した、きわめて刺激的なノンフィクション。ボスニア紛争の影でアメリカのPR会社がどのように動き、「セルビア=悪」「モスレム人、クロアチア人=被害者」という単純化された構図が出来あがったのかを小説風にうまく描き出しています。本書を読んで、改めて戦争報道の難しさを実感しました。確かに、筆者が言うように、過度に単純化された完全懲悪的な報道は、人びとの認識を歪め、重大な帰結をもたらします。
しかし、このサイトで紹介している『仁義なき戦争』で語られているように、戦争報道には「愛想づかしの誘惑」もまたつきまといます。つまり、あらゆる戦争当事者(ボスニア紛争の場合であれば、セルビア人、モスレム人、クロアチア人)の悪を暴くことで、「連中にはもう好きなだけ殺し合いをさせておけ」という感情がマス・メディアに接する人びとに生まれる危険性があります(近年のマスコミ論では、こうした現象を「同情疲労(compassion
fatigue)」と呼んでいます)。そうなると、どのような残虐行為が行われようとも、もう放っておけという話にもなりかねないわけです。そこまで考えると、他国の世論を喚起し、戦争に介入するためには、「相対的に」悪い側を決定する必要性があるというマーティン・ショーの見解も説得力があるように思われます。
が、そこにも問題はあって、戦争に介入する側の利害に関係なく、「客観的に」に善悪を決定することがそもそも可能なのか、などといった疑念が生じてくるわけです…。と、まぁ、だらだら書いてしまいましたが、とにかくこの本は面白いので一読をお奨めします。(2002年12月)
竹内成明(1994)『顔のない権力』
れんが書房新社
親子関係や学校、消費社会などに関する考察から、コミュニケーションに内在するミクロな権力を分析してゆきます。コミュニケーションとはあくまで相互行為であり、子どもの観察を怠る親が、子どもの変化に気づかず、「勉強しなさい」としか言わなくなったとき、親は子どもにとって権力として現れるという作者の指摘は、ミクロな領域にとどまるものではないでしょう。つまり、マスコミが一般の人々の声に耳を傾けなくなったとき、マスコミは権力として出現するのであり、それは今日においてしばしば見られる現象なのです。しかし、本書に少々苦言を呈するとすれば、議論が少々混乱しており、理解が難しいところがあるのではないでしょうか。(1997年)
田崎篤郎、児島和人編(1996)『マス・コミュニケーション
効果研究の展開(新版)』北樹出版
マス・コミュニケーションの効果研究は主に三つの時期区分が出来ます。それは、「弾丸モデル」「限定効果モデル」「中程度/強力効果モデル」(論者によって名称は多少異なります)の三つなのですが、要するに、マスコミの効果は最初、極めて大きいものだと捉えられていたのが、限定的なものに過ぎないということになり、そして最近になって、またその大きく捉えられるようになったということです。その流れを簡略にまとめ、最近の主要な理論まで紹介しているのが本書です。非常に読みやすいので、マスコミ理論の教科書としてはなかなか良いのではないでしょうか。(1997年)
タックマン・ゲイ、鶴木眞ほか訳(1978=1991)『ニュース社会学』 三嶺書房
報道する側がいかにニュースを生み出していくのか。「送り手」論として知られる著作のなかでも、本書は最も有名なひとつだと言えるでしょう。著者は実際にニュースの制作現場に入り込み、そこでどのようにニュースが収集され、編集されるのかを社会学的な観点から分析していきます。そのため、社会学の理論的な話も出てきたりして、その手の話に馴染んでいない人にはちょっと厳しいかもしれません。とはいえ、本書を読めば、我々が普段何気なく見ているニュースも、実は複雑な人間関係や選択基準を経て生み出されてくるものだということがわかり、ニュースの見方も変わってくるかもしれません。(2002年3月)
玉木明(1996)『ニュース報道の言語論』 洋泉社
日本のジャーナリズムの脆弱性は一体何に起因するのか?こうした問いに対して、既存の(ありがちな)ジャーナリズム論は記者クラブやリーク情報への依存などを批判してきました。そのような平凡なジャーナリズム論に対して、本書は言語論という観点から、日本のジャーナリズムの問題点を抉り出しています。筆者はいわゆる「客観報道」とそれを支える無署名性言語(署名なき記事)こそが、日本のジャーナリストが自らの見解を打ち出せないまま、紋切り型の記事を生み出してゆく原因となっていると主張し、そこから松本サリン事件報道などの問題点を検証してゆきます。厳密には学術書とは言いづらい記述の仕方なのですが、それでもこの分野を学ぶ者にとっては必読の文献だと言うことが出来るでしょう。(1999年)
玉木明(2001)『ゴシップと醜聞』 洋泉社新書
民衆から犯罪者に発せられる憎悪の声。「人殺し」。「人でなし」。そうした<人が人を裁くこと>の歴史的な背景を三面記事の研究を通して、論じているのがこの著作です。著者によれば、人々がかつて罪人に向ける視線には、どこかに「共感」あるいは「赦し」といった要素が含まれれていました。ところが、それが近代に入ると、罪人は「我々」の「敵」として、憎悪すべき対象として見なされるようになる。著者は、そのような変化の過程を、新聞が犯罪を「面白い話(ゴシップ)」としてではなく、「スキャンダル」として断罪するようになっていく過程と重ね合わせています。そして、そうした報道のあり方が戦後のジャーナリズムにも大きな影響を及ぼし、「サッチー批判」などへと繋がってきたと分析するわけです。本書の一番最初の「人が人を裁くことの無根拠性」という箇所がちょっと納得しかねるのですが、面白い本だと思います。(2002年2月)
ダヤーン・ダニエル、カッツ・エリユ、浅見克彦訳(1992=1996)『メディア・イベント』青弓社
オリンピックやワールドカップ、あるいはチャールズ皇太子とダイアナ妃のロイヤル・ウェディングといった今日のイベントはメディアを通すことによって、いかなる影響力を持ちうるのか。マス・メディア研究の代表者とも言える筆者による、そうしたメディア・イベントに関する研究です。M.ウェーバーによる権力の類型との対比など、非常に刺激的な分析がなされています。マス・コミュニケーション論を学ぶ上で、必読の書と言えるでしょう。また、補録では今日のマス・メディア研究に対する考察がなされ、これからのマス・コミュニケーション論の目指すべき方向性が示されており、そうした点でも参考になるでしょう。(1997年)
デビス・デニスほか、山中正剛ほか監訳(1980=1994)『マス・コミュニケーションの空間』 松籟社
われわれの日常生活にマス・コミュニケーションはいかなる影響を及ぼしているのか、そして、その影響を批判的に受けとめるためにはどのようにすればよいのか。本書は、このような観点から、フレームやコードなど、様々な分析手法を用いて、現代におけるマス・コミュニケーションの役割について考察しています。最近のカルチュラル・スタディーズなどとはかなり色合いを異にした研究なので、そうした興味から読むと失望するかもしれませんが、マス・メディアと社会化など結構面白いテーマを扱っています。とてもわかりやすい本で、翻訳も悪くないのですが、なんとなく締りが無いような、そんな印象を受けました(はっきりしない感想で申し訳ありません)。(2000年4月)
ノエル=ノイマン・エリザベート、池田謙一ほか訳(1993=1997)『沈黙の螺旋理論改訂版』
ブレーン出版
マス・メディアの効果研究は大きくわけて、弾丸効果モデル、限定効果モデル、強力効果モデルの三つに時期区分されるわけですが、その中の強力効果モデルの一角をなしているのが本書で紹介されている「沈黙の螺旋理論」です。本書では、「世論」が人々の意見の表明に影響を及ぼすことで、少数者の発言の機会が減少し、多数者の意見がより強力なものになってゆく過程があきらかにされています。そして、人が自らの意見を多数意見と考えるか、あるいは少数意見と考えるかに、マス・メディアは大きな影響を及ぼすというわけです。訳者解説でも論じられているとおり、この「沈黙の螺旋理論」には様々な批判も寄せられているわけですが、マス・メディアの効果研究を語る上では、欠かせない一冊と言えるでしょう。私としては、もうちょっと内容をコンパクトにまとめられるだろうという気もするのですが。(1999年)
パイ・ルシアン編、NHK放送学研究室訳(1963=1967)『マス・メディアと国家の近代化』
日本放送出版協会
1950年代から1960年代まで、欧米の社会科学を席巻した近代化論。その中で、マス・メディアがいかにして国家の近代化に貢献しうるのかという議論も盛んに展開されました。本書は、そうした「コミュニケーションと発展」論の代表的な研究者たちによる論集です。はっきり言って、極めて楽観主義的な議論が多く、批判をするのはとても簡単です。実際、激しい批判がなされて、「コミュニケーションと発展」論は触れられることすら稀な研究になってしまっています。が、それでも興味深い議論がところどころでなされていて、最新の研究に通じるところがあるのではないか、と僕は考えています。まぁ、批判するにせよ、それを発展させるにせよ、昔の考え方を知る上では便利な本だと言えるのではないでしょうか。(2000年5月)
藤竹暁(1975)『事件の社会学』 中公新書
「擬似環境の環境化」ということをキーワードに、現代の発達したマス・メディアが提供する社会像がいかに人々に影響を及ぼし、危機をもたらしているのかを、様々な事例を紹介しながら論じています。残念ながら絶版だと思うのですが、とても良い本なので古本屋で見かけたら買いましょう。やや古い本なので、引き出されてくる事例もそれだけ古くなるのですが、逆に「そんな事件があったのか」と新鮮な気持ちで読むことが出来ました。石油ショック後の時代風潮を知る上でも参考になるかもしれません。残念ながら絶版になっていると思うのですが、古本屋で探せば買えるかもしれません。(1999年)
マイルズ・ヒュー、河野純司訳(2005=2005)『アルジャジーラ』光文社
アラブの小国カタールに突如として出現した衛星テレビ局アルジャジーラ。「一つの意見があれば、また別の意見がある」というモットーのもと、アルジャジーラはそれまでのアラブ系放送局では考えられなかったイスラエル政府の声を伝え始めたほか、アメリカ政府やパレスチナ人、果てはアルカイダの声明まで放送し、その結果として様々な圧力にさらされることになりました。本書は、そうした中東では特異とも言える放送スタイルを貫くアルジャジーラが誕生した政治的・社会的背景とともに、激動の国際政治のなかで同局がどのような役割を果たし、また圧力にさらされてきたのかを論じています。非常に興味深いエピソードが満載されており、楽しく読むことができます。無論、アルジャジーラの肩を持ちすぎではないかとの気もするわけですが、それを差し引いてもお勧めできる一冊です。
この本を読んで改めて思ったことは、放送局が「公平中立」であるということはやっぱり非常に困難だ、ということです。アルジャジーラは様々な声を放送した結果、欧米のメディアからは「ビン・ラディンのお気に入りニュース専門局」と呼ばれ、アラブ諸国諸国からは「シオニストのテレビ局」だと批判されることになりました。が、一つのテレビ局が同時にアルカイダとイスラエルのプロパガンダ機関になることは不可能です。結局のところ、自分の支持しない意見が放送されただけで、人はその放送局が「偏向している」との感想を抱いてしまうのであり、仮にいくら放送時間を対立する意見ごとに均等に割ったとしても「公平」であるとは認識されにくいのではないでしょうか。(2006年6月)
マコームズ・マックスウェルほか、大石裕訳(1991=1994)『ニュース・メディアと世論』関西大学出版部
近年のマスコミ効果研究における主要な理論の一つであるアジェンダ・セッティングモデルを用いて、マスコミが世論にいかなる影響を及ぼしているのかを分析したのが本書です。アジェンダ・セッティングとは、マスコミが人々に、いかに考えるかということではなく、いかなる問題について考えるのかということ関して影響を及ぼしていることに着目した理論です。本書では、ニュースがいかに作られ、伝えられるかを分析し、世論に対してマスコミが影響を及ぼしていくプロセスを明らかにしてゆきます。テレビと政治との関わりについて考えるには良い文献だと思います。(1997年)
水谷三公(1995)『イギリス王室とメディア』 筑摩書房
戦間期イギリスにおける王室最大のスキャンダルであったエドワード8世とシンプソン夫人との恋。最後にはエドワード8世の退位へと到る「王冠を賭けた恋」を、イギリスのメディアはどう伝えたのか。戦間期の政治、社会状況を踏まえながら、エドワード8世やシンプソン夫人、ボールドウィン首相などの人物の言動を詳細に追っていきます。学術書というよりは、ルポルタージュという色彩が強い著作ですが、それだけに読みやすく、飽きさせません。(2001年1月)
村上直之(1995)『近代ジャーナリズムの誕生』 岩波書店
イギリスにおける言論抑圧に対するジャーナリズムの勝利として知られる、「知識への課税」廃止。その裏にはいかなる社会の変容が隠されていたのか。本書は、「知識への課税」廃止を主張した人々の主張と、当時の社会の状況という二つの観点から、近代ジャーナリズムの誕生の陰にある近代的な知=権力のあり方を解き明かしてゆきます。M・フーコーの権力論を批判的に継承しながら、統計や国家警察とジャーナリズムとがいかに結びついてきたかを論じる本書は、ジャーナリズム史における新たなパースペクティブを提供しているという点で評価出来るのではないでしょうか。(1997年)
ラザースフェルド・ポールほか、有吉広介監訳(1968=1987)『ピープルズ・チョイス』
芦書房
「二段階の流れ」や「オピニオン・リーダー」など、マス・コミュニケーション効果研究における限定効果モデルを代表する概念を提出した記念すべき著作。アメリカの大統領選挙において、人々がどのように投票の意思を決定するのかを綿密な調査を通じて明らかにしています。要するに、人々はマス・メディアよりもむしろ、家族などの身近な人々の影響を受けやすいということが論じられているわけです。が、最近では、そうした集団による規定力が弱体化し、限定効果モデルの仮説が成立しづらくなっているということも指摘されています。人によっては弾丸効果モデルの時代に戻ったなんて言う人もいますが(某宮台真司さんなど)、それはちょっと(というか、かなり)暴論であって、やはり限定効果モデルをきちんと勉強しておくことは重要だと思います。(2000年7月)
リップマン・ウォルター、掛川トミ子訳(1922=1987)『世論』 岩波文庫
マスコミ研究の古典中の古典である本書。にもかかわらず、最近ようやく読み終わったのですが、非常に大きな示唆を受けました。原書の出版は1922年と70年以上前なので、確かに理解しづらい事例などもあげられていたりするのですが、その指摘の多くは今日においても全く古さを感じさせません。本書の前半においてリップマンはまず、ステレオタイプについて議論を行い、我々のものの見方がいかにステレオ・タイプによって支配されているかを指摘します。そして、後半ではそうしたステレオタイプによって歪められる民主主義のあり方について警句が発せられるのですが、このようなリップマンの指摘はまさしく今日的な問題として受けとめられるべきでしょう。マスコミ研究のみならず、政治学や社会学の研究にとっても是非一読すべき文献と言えると思います。(1998年)
|

